�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@���Θb�`�����@�@�@
�@�@�@�@���Θb�`�����@�@�@
�@
�@ �P�X�X�X�N�P�P���^�@�É�����O��^�@�쐼��U�O�������D�D�D�D�D�@�@�@�@
�@
���̑����m��ŁA���E�ő勉�̐[�C�@�탊�O
�g�l.�f. �q���[��
�i��.�h���@����
���J�n���܂����B����ɂ��A�ʎY�Ȃɂ��{�i�I�ȃn�C�h���[�g�w�̒������n�܂�
�܂����B���Ȃ̒n���������A�������Z�p�����������Ȃǂ����̃v���W�F�N�g�Ɏ�
��g��ł��܂��B
�@
�����{���ӊC��̎����D�D�D��
�u���āA�܂��A���̃v���W�F�N�g�̊T�v����������邩�ˁD�D�D��x���́A�̂�L���A��
�ɗ����u�����B
�u���́A�[�C�@�탊�O�g�l.�f.�q���[��
�i��.�h�ƌ����̂́A���{�̂��̂ł͂Ȃ��̂���
��H�v�Ĕ����A�{�[���y���Ńf�B�X�v���C���w�����B
�u���O���炷��A�����炵���ȁD�D�D����́A�C��̍�������V�T���[�g���A��r��
�ʂQ���S�O�O�O�g���̍\�������B�v����ɁA���̋���ȊC�ɕ����ԃ��O������A�[�C��
�̒n�����{�[�����O����킯���B���ꂻ�̂��̂̓��������ƕs���肾���A�p�C�v���C
��ɓ˂��h����A���Ȃ�̈��肪������D�D�D
�@
����ɂ͂܂��A��[�Ɋ���ӂ����Ȑn�������|�ǂ��A���[��P�O�O�O���̊C��
�܂ʼn��낷�B���ꂩ��A�C�ꉺ���Q�O�O�O���[�g���܂Ō@�킷��D�D�D
�@ ���Ȃ݂ɁA���̕ӂ���C��^�����˖��͂R�O�O���قǂ̂悤���B�܂�A���̂�����
���n�C�h���[�g�w���B�����āA���̒��������^���K�X�w�����A���̍X�ɂ����Ɖ��̕���
�Œ�������悤���B�܁A���̒����͎����T���Ɠ����ɁA���Ȃ�w�p�I�Ȓ����̐F��
��������悤���B������A�����Ƃ��ĊJ������ɂ��Ă��A�S�̍\�����悭������Ȃ���
�ł͍��邩��ȁA�v
�u�͂��B����Ƃ����̂́A�嗤�Ζʂ�C�ꉺ�́A�\����̖����������Ă���Ƃ���
���Ƃł��傤���H�
�u���ށB�����炭�A�����������Ƃ��낤�B������ɂ��Ă��A�Ζ���V�R�K�X�����̖R����
���{�ɂƂ��ẮA�Q�O�O�J�C���o�ϐ��挗���ɑ��݂���ɂ߂ėL�]�Ȏ������B�ʓI��
����������悤���v
�u�ǂ̂��炢����̂ł��傤���H�v
�u���[�ށD�D�D��ȕ��z�́A������ʂ��g�쐼�����C�a�h�B���ꂩ��A����[�C�@�탊
�O�Œ������Ă���A�É�����O�艫����{�茧���ɂ����Ă��g��C�g���t�h�B�����āA
�g�[�����������h�A�ݏ֖������g�瓇�C�a�h�A�Ìy�C���������g���{�C�����h�A�ϒO
���������g�^�^�[���g���t�h�A�������g�I�z�[�c�N�C�h�Ƃ������Ƃ��납�D�D�D
�@ ���̌o�ϐ��挗���Ŏ����J�����\�ƌ����郁�^���̑��ʂ́A��V���S�O�O�O��
㎥�D�D�D�����̓V�R�K�X����ʂɂ��āA���悻�P�S�O�N���������v
�u�������ʂł��ˁv
�u���ށA�v�x���́A�{�Ɏ���B
�u�ł��A���ΔR���ł���ˁA������āH�
�u������v�x���́A������ɂ��낵���B�u�������A�Ĕ��N�A����͒P�Ȃ�T�Z�ł���
�Ȃ��B����ɁA���Ȃ�댯���������Ƃ��\�z�����̂��C�����肾�B����ɁA�̎Z����
��邩�ǂ������������Ă��Ȃ��B���ۂɁA���݂̋Z�p�͂ł͍���ȉۑ����������
�˂��D�D�D����ɁA�����������J���������ꍇ�́A���e���]�����d�v�ȉۑ�ɂ�
���Ă��邾�낤�v
�u�嗤�Ζʂ��A�C��n������N�����\���Ƃ������Ƃł��傤���H�v
�u�ނ��A������܂߂Ă��B���ӂ̘R�ꂽ���^���ŁA�C�����C���ω����Ă����邵�A
����Ő��Ԍn���ω����Ă�����킯���v
�u�͂��v
�u�P�X�X�W�N�̃p�v�A�j���[�M�j�A���P�����n�k�ƒÔg�́A���������n�C�h���[�g�w�̋}
���ȕ����ƁA����ɂ���Ĉ����N�����ꂽ�C��n����̉\�����w�E����Ă���B��
���A����ȏ،�������B�g�Ôg���P���Ă������A�C�ɉ��������h�A�g�Ώ��������h
�A�g�ςȏL�������āA�ڂ��h�����ꂽ�h�Ƃ����悤�ȕ��B����́A�����ʂ̃��^���K
�X�����݂������Ƃ��������킹����̂��v
�u�Ӂ[��D�D�D�v
�u�P�X�X�R�N�̉��K�����P�����n�k�B������A�n�C�h���[�g�w�̊֗^���w�E���Ă���w��
������B�܂�A���̃n�C�h���[�g�w�̂���嗤�Ζʂ́A�ɂ߂Ĕ����ȑ��݂Ȃ̂��B��
�������A�Ôg�������N�����ĊC�݂̓s�s��j���Ă��܂��v
�u����͍����ˁB���ꂶ��A�����J���͂���ς荢��Ȃ̂�����H�v
�u����A����ł́A�����������Ă����Ȃ��ʂ�����B�܂��A�Ζ������͂��łɌ�
�����n�߂Ă���B�����Ȃ�ƐΖ����{�́A���̃��^���n�C�h���[�g�Ɍ����킴���
���Ƃ������ʂ�����B�����Ƃ��A���̎R���L�]�Ȃ�̘b���B�����ŁA�O�ɂ�������
�悤�ɁA���̏������Ƃ��M�S�Ȃ͓̂��{���v
�u���́D�D�D�x������A�v
�u���ށA�����ˁH�v
�u���́A�C��n������A���܂��R���g���[���ł��Ȃ��̂�����B��������A�n�k��h��
�邱�Ƃɂ��A�v
�u�܁A�����������Ƃ��܂w�p�������낤�B�Ⴆ�A�n�C�h���[�g������������ɁA��
�̂����ƈ��肵�����̂��[�U���Ă����A�n�C�h���[�g�w�̂悤�Ɉ�C�ɒׂ�鎖����
���Ȃ�B�����Ȃ�A�C��n����̈������ɂȂ邱�Ƃ��h����킯���B�������A���̕�
���Ɏ������Ƃ����̂́A���ۏォ�Ȃ�댯�ȍ�Ƃɂ��Ȃ�v
�u�����v
�u���܂ł́A�����m��Ȃ��Œn�k��Ôg�̔�Q���Ă������A���x�͂�������m
�̏�ł̍�ƂɂȂ�킯���B���R�A���Ή^�����N���邾�낤�ȁv
�u�͂��D�D�D�v
�u�P�X�X�W�N�̃p�v�A�j���[�M�j�A�̒n�k���A�n�k�̋K�͂ɔ�ׂĒÔg�̔�Q���傫
�������ƌ����Ă���B����́A�܂�A�C��n����ɂ��n�k�̓����Ȃ̂����m��
��v
�u�ł��A�v���[�g�̒��ݍ��ݗ̈�ł́A��ɒn�k���������Ă����̂���Ȃ���������
��H�v
�u���ށB�܁A������ɂ��Ă��A�h�Џ�ł��d�v�Ȍ����ۑ�ɂȂ��Ă����悤���B������N
���A�ł���A�����J���̕����e�݂��������m���v
 ���Z�p�J���̓W�]�́D�D�D���@
���Z�p�J���̓W�]�́D�D�D���@
�u�O�ɂ��������悤�ɁA���E�̐[�C��ɖ��郁�^���̃n�C�h���[�g�̑��ʂ́A����܂�
�m���Ă������ΔR���̂Q�{�ȏ�ɂȂ�B�����Ƃ��A���ꂼ��Ō`�Ԃ��Ⴄ����A�Y
�f�Ɋ��Z���Ă̌v�Z�ɂȂ�B����́A���̒n���������ɂ�����Y�f�̕��z�A�Y�f
�̏z��ϑJ�Ƃ����Ӗ�������A���ɖʔ��������������v
�u���[��D�D�D����Ȍ����́A����܂łɂ������̂�����H�v
�u���������{�i�I�Ȑ[�C��̒������̂��A�Z�p�I�ɍ�������B���ꂪ�����Â�
�\�ɂȂ��Ă����̂́A�܂��ɂQ�O���I�����̍ŏI�i�K�Ƃ������Ƃ��납�ȁv
�@ �Ĕ��́A�ق��Ă��ȂÂ����B
�@
�u���āA����܂ł̃I�T���C�����˂Ă܂Ƃ߂Ă݂悤�D�D�D
�@
���̃��^���n�C�h���[�g�́A�l�ޕ�������ł��������ꂽ�ꏊ�ɂ��鉻�ΔR������
���B�[���C�̒�A���̂���ɒn�����S���[�g���̓D�ɍ�����X�̒��ɖ��郁�^�����B
���̊ܗL�ʂ́A���p�[�Z���g���琔�\�p�[�Z���g�A���ɂ͋���Ȍ���������D�D�D
�@
���̓D�ɍ��������X�́A�������������̂��B�����āA���̕X�̌��������i�����j�̒�
�ɁA���^�����q�������Ă���B���ꂪ���^���n�C�h���[�g���B���������āA�����ɂ͉���
�͊܂܂�Ȃ��킯���D�D�D
�@
�����A�������X�l�ނ̏Z�ފC��ֈ����グ�Ă���킯�����A�����͈�C�ɉ���
��A�t�ɐ����͈�C�ɏ㏸����B�[�C��ɂ����郁�^���n�C�h���[�g�̑��݂ł����
���́A���[�T�O�O���[�g���ȏ�A�X�_�O��̈��肵�����x������ȁB�܂�A���̂܂�
���^���n�C�h���[�g�������グ�Ă���A�����܂��X�͉����A���^���̓K�X�����ĎU�킵
�Ă��܂��B
�@
�������A���ɉ��Ƃ��n�C�h���[�g�̌`�ŊC��{�݂܂ʼn���ł����Ƃ��Ă��A�����
��ʂ̓D���̉�Ȃ̂��B�������烁�^��������̂͗e�Ղȍ�Ƃł͂Ȃ��B
�܂��A���������傫�Ȗ��ɂȂ�v
�u���ɕ��@�͂Ȃ��̂ł��傤���
�u�܁A�u��������@�v�Ƃ������@������B�������A������܂����S�Ɏ����ꂽ�킯�ł�
�Ȃ��B����́A���x�ƔS���������������̌@������@�ŁA�|���v�ŏ��C��M����
��������̂��B�܂�A�n�C�h���[�g�w�ɒB�����@��E�ɁA�|���v�ŏ��C��M���𑗂�
���ށB�܁A�ȒP�Ɍ����A�n�C�h���[�g���������ă��^���K�X�ɂ���킯���ȁB���ꂩ
��A���̃��^���K�X���A�ʂ̌@��E����z���グ��Ƃ������@���v
�u����́A���܂��s�������ˁv
�u�������A�嗤�ΖʂƂ����ꏊ���l����A����قǒP���Ȗ��ł�����܂��B����
�ɁA�C��n����Œn�k��Ôg���N����A�C��v���b�g�z�[���ɂ����R��Q�͋y�ԁB
�C��p�C�v���C�����A�����Ĉ��S�ł͂Ȃ��B����A�ނ���A�ɂ߂Ċ댯���Ƃ���������
�����v
�u���ꂶ��A�ǂ�����H�v
�u�܁A����Ō����A�ȒP�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�C��v���b�g�z�[���ŁA���^���K�X��
�t�����ĉ^��������@��A�C��ɐ��Y�ݔ������݂�����@�Ȃǂ���������Ă���B
���A������ɂ��Ă��A�嗤�ΖʂŃn�C�h���[�g��������邱�Ǝ��̂��A����ȊC��n
����̈������ɂȂ肩�˂Ȃ��D�D�D���[�ށD�D�D�����ŁA�h�Џォ����A�\���Ȍ�����
�K�v�ɂȂ��Ă���킯���
�u�͂��B����ł́A�x������A����͂��̕ӂł����ł��傤���H�
�u���ށB�Ō�Ɉꌾ�������Ă������B
�@ ���݁A������̐[�C�@��D�g�n�c�Q�P�h�iOcean
Drilling in the 21st Century�j�̌������i���
����B���̑D�́A���{���哱���č��ۋ��͂Ői�߂Ă���̂��ŁA���ʃn�C�h���[�g�w
�̒T������v�Ȏd���ɂȂ邾�낤�B���̍ŐV�s�̑D�Ȃ�A����܂ŏo���Ȃ������K�X
�����o�������ȊC��ł��A���S�Ɍ@�킷�邱�Ƃ��ł���ƌ����Ă���B���̑D�̐i
�����҂������������ȣ
�u�͂��B�����D�D�D����ł́A���̐V�W�J�Ɋ��҂��āA����͂����܂łƂ��܂��
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 ���^���n�C�h���[�g�̔���
���^���n�C�h���[�g�̔���

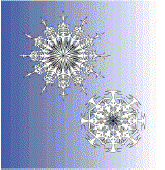 �@ �@
�@ �@
 �@�@
�@�@ 

 ���^���n�C�h���[�g�̔���
���^���n�C�h���[�g�̔���
