 人工万能細胞・掲示板
人工万能細胞・掲示板

胚性幹細胞/ES細胞(万能細胞)に似た・・・人工・多能性幹細胞/ iPS細胞
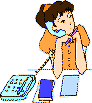


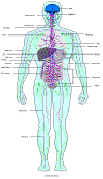
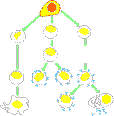
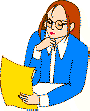
![]()
| Menu /生命科学/病気・生命科学・掲示板/人工万能細胞・掲示板 |
 人工万能細胞・掲示板
人工万能細胞・掲示板

胚性幹細胞/ES細胞(万能細胞)に似た・・・人工・多能性幹細胞/ iPS細胞 |
| トップページ/Hot Spot/Menu/最新のアップロード 担当: 厨川アン |
| No.1 | 人工・万能細胞の登場・・・・・受精卵を使わずに、多様に分化! | 2007.11.29 |
| No.2 | ガン遺伝子抜き・・・安全性向上に成功! | 2007.12. 2 |
| No.3 | マウスの肝臓と胃粘膜からも、人工・万能細胞! | 2008. 2.19 |
| No.4 | 新世代のiPS細胞!/ガン化回避に、道・・・ | 2008.10.11 |
| No.5 | iPS細胞で、病気の再現に成功! | 2009. 1. 8 |
|
<1> (2007.11.29) 人工・万能細胞の登場・・・・・ 受精卵を使わずに、多様に分化!
|
|
<2> (2007.12. 2) ガン遺伝子抜き・・・安全性向上に成功! 4つの遺伝子のうち...ガン遺伝子をのぞく、3つの遺伝子でも作製可能に! 「ええ、厨川アンです... 2007年12月1日/万能細胞・・・がん遺伝子なしで作製 2007年12月2日/ 核心/ 過剰規制の教訓生かせ
|
<3> (2008. 2.19)
|
|
<4> (2008.10.11)
中山伸弥・教授の研究グループ/世界で初めて成功!
はいかがかしら?」 「はは...」外山が、開け放された窓の方を見、ゆっくりと椅子に掛た。「いい日和(ひより)なの で、ちょうど散歩に出かけようと思っていた所です。気分はいいですよ」 「10月10日は、晴れの特異日だそうですわ」アンも、髪をすきあげ、窓の外を眺めた。「かつて の、体育の日ですわ。やっぱり晴れるんですね。 ええ、早速ですが、外山さん、“iPS細胞”でビッグ・ニュースがありました。ご存知かしら?」 「ええ、先ほど新聞を読みました...」外山が、作業テーブルの上の東京新聞を引き寄せた。 「はい...」アンがうなづいた。「ええと... 京都大学/中山伸弥教授の研究グループが...ベクターにウイルスを使わず...プラスミ ドを使って、“人工多能性幹細胞/iPS細胞”の作製に成功した模様です。もちろん、これは、マ ウスを使った実験ですね。この実験に、世界で初めて成功したということです。 ええと、これは、アメリカの科学雑誌/サイエンス電子版/9日付けに発表されたようです。 私はこれを、TV報道と、東京新聞/2008年10月10日/トップニュースで知りました」 「うーむ...」外山が肘を立て、両手を組み合わせた。「世の中が、騒然としてきました... そうした中で、日本人が4人も、ノーベル賞を同時受賞(物理学賞/南部陽一郎、益川敏英、小林誠の各 氏...化学賞/下村脩氏)しましたねえ。ともかく、久々の明るい話です。そうしたホットな中で、また また“iPS細胞”でクリーン・ヒットですか... まあ、この再生医療の分野でも、将来のノーベル賞が予想されますね」 「そうですね...」アンが、明るくうなづいた。「何よりも、大勢の患者を救うことになりますわ」 「日本は、政治・経済・文化が大混乱な中で...学術分野やスポーツ分野のように、“厳格なル ールが敷かれている世界”では...それなりに、良い実績を上げているようです。キッチリとし た夢の描ける世界が、そこにはあるのでしょう。 しかし、相撲のように、そこに曖昧さが入って来ると、とたんに既得権で囲い込んでしまうわ けです。政治・芸能・マスコミ文化と、全てが特権意識を持ち、社会的公器を私物化してしまっ ています...と、まあ、秋月茜さんが憤慨していました...私たちの担当外のことですが、」 「はい...」アンが、優しく目を細め、ため息を漏らした。「でも、ノーベル賞は明るいニュースで すわ... そして今回の、“iPS細胞”のホット・ニュースも、再生医療にとっては、将来展望の開けてくる 明るいニュースです。“iPS細胞”の安全性が大幅に高まり、臨床応用へ向けての、大きな前進 になりそうですね、」 「うーむ...」外山が、新聞を眺め、顎を撫でた。
「ええ、本題に入ります... これまで、遺伝子を導入するベクター(運び屋)は、主としてレトロウイルスが使われていました。 山中教授の研究グループでは、これをプラスミドと呼ばれる環状DNAに代え、“iPS細胞”の作 製に成功したようですね...世界で初めての成功ということです」 「4つの遺伝子を...3つと1つに分け、2種類のプラスミドに組み込んだようですねえ...それ を、マウスの胎児の皮膚細胞に導入したわけですか...ふーむ...」 「従来に比べて、効率は100分の1以下に下がるようですわ... でも、“iPS細胞”は作製できるということです。従来と同様に、様々な細胞に分化することも 確認できたようです。従来のレトロウイルスを使った場合は、導入する遺伝子が、染色体その ものに組み込まれるために、細胞がガン化する可能性がありました。これは、臨床応用に向け て、大きな障害になるものでした。 ところが、プラスミドを用いた“iPS細胞”では...半数以上で、遺伝子が染色体へは組み込 まれず...プラスミドも、数日で分解されることが確認できたようです...素晴らしいですわ。 詳しいことは分かりませんが、画期的な前進があったようですね。 ええと...安全性も、飛躍的に高まることになるようです。同時に、実験時の危険性や、コス ト問題も、改善されるようです。封じ込め機能を備えた設備での作業が、大幅に改善されるとい うことでしょうか。これは、次の大きな飛躍につながる、ステージそのものを拡大することになる のかも知れませんね」 「うーむ...まあ、だんだん安全なものになって行き、それだけヒトに、臨床応用に近づいて行 くということでしょう」 「はい... 山中教授も...“新世代のiPS細胞! 細胞移植治療に向けた大きな1歩! ”...と話し ているようですわ。現在、ヒトへの応用や、さらなる安全性の確認を進めているということです」 「ふーむ...」外山が、新聞を見ながら言った。「名古屋大学/大学院/室原豊明・教授も... “これまでのiPS細胞の中で1番安全!画期的な成果!”と評価していますね。同教授は、 “iPS細胞”から、血管や心筋への分化や...臨床応用を目指して研究されている方ですね、」 「はい...」アンが、小さくうなづいた。「ええと... これも、同じ名古屋大学/大学院/上田実・教授の話ですが...“iPS細胞の、最大の弱点 の1つを・・・解決する1歩!”、と高く評価しています...でも、実用化に向けては、“iPS細胞” が“本当に有効か?”、“本当に分化誘導できるのか?”といった問題が、まだたくさんあると指 摘しています...また、研究が進み、1日も早く、患者の治療に適用されることを願う、とも言っ ておられますわ...」
************************************************ 〔用語の解説〕 <ベクター> 「ええと...少し専門用語と、その周辺を解説しておきます... ベクター(運び屋)とは...本来は、感染症の病原体を媒介する動物の総称です。 1例をあげれば、マラリアにおける蚊などのことですね。遺伝子工学においては、ク ローニングでDNAを増殖する際に用いる、クローニング・ベクターと...今回のよう に、クローニングした遺伝子を細胞に導入するための、発現ベクターがあります。つ まり、ベクターとして、プラスミドやレトロウイルスを使うというわけです。 “iPS細胞”の研究では、レトロウイルスから、プラスミドに変えたわけですね。ま ず、“iPS細胞”の扉を開き、それから、ガン化の脅威を排除するために、プラスミド に切り替え、それに世界で初めて成功したというわけです」 <レトロウイルス> 「レトロウイルスというのは、これまでにも何度か説明して来ていますが、DNAでは なく、RNAに遺伝情報をもつウイルスです。 つまり、逆転写酵素を持つRNAウイルスです。ウイルスの遺伝情報が逆転写さ れ、宿主細胞のDNAに組み込まれます。そして、細胞のタンパク質合成機能を借用 し、増殖するというわけですね。 ええ...このレトロウイルスには、悪名高いヒト後天性免疫不全ウイルス(HIV)や、 成人T細胞白血病ウイルス(HTLV)も含まれるわけですね。 ともかく、遺伝子操作では...細胞に対して、効率よく遺伝子を導入するための、 ベクターとして優れているわけです。でも、予期せぬ突然変異が起こる可能性がある ということです。したがって作業も、一定の封じ込め機能を備えた設備が必要になり、 危険性とコストがかかるという話です。 今回の飛躍的な前進で、そうした状況が大幅に改善されるということでしょうか、」 <プラスミド> 「プラスミドというのは、細菌の核外遺伝子のことですね... このプラスミドというのは、細胞質の中で自律的に増殖します。でも、通常は生育 には必須のものではありません...代表的なプラスミドには、大腸菌のF因子やR 因子(薬剤耐性因子)などがありますね。 ええ、ともかく...プラスミドは大腸菌や酵母などの細胞質などに存在し...染 色体とは独立して増殖・機能する、小さな遺伝子の集合体です。2本のDNAが、環 状につながった構造が、一般的ですわ。 プラスミドは、今回の“新世代のiPS細胞”の研究開発にも使われたわけですが、 医薬品産業やバイオ研究の分野では、標的となる遺伝子を細胞に組み込むベクタ ーとして、広く用いられているものです。 それから、ええと...プラスミドそのものは...大腸菌などを使って、安全かつ大 量につくることが可能ですね。また、冷凍すれば、長期の保存も可能です... 今回の研究開発では...ベクターのプラスミドが、数日で分解されることも確認さ れたようですね。“iPS細胞”ができ上がってしまえば、後は余分な危険因子は存在し ない方がいいわけです」
************************************************
「ええ、厨川アンです... ご静聴、ありがとうございました。どうぞ、次の展開にご期待下さい...」 2008年10月10日/・・・iPS細胞 がん化回避/山中教授が新手法
|
|
<5> (2009. 1. 8)
病気の原因解明・新薬開発に強力な武器! アメリカ/ウィスコンシン大学/ジェームズ・トムソン教授らのチーム
「ええ...」アンが、片手でファックス・メモを取り上げながら言った。「さっそくですが... これは、昨年の年末に入って来た、“iPS細胞”に関するニュースです... 内容は...神経難病の患者の皮膚からつくった“iPS細胞”を...神経に成長させた後... “病気のために神経が死ぬ”のを...“試験管内で再現することに成功”した、というものです。こ うした成果は、かねてから予想されていたものですね...?」 「そうですね...」外山が言った。「ええと、これは... アメリカ/ウィスコンシン大学/ジェームズ・トムソン教授らのチームが...2008年12月30 日までに...成功したものです...“英科学誌ネイチャー”に発表したようですね」 「はい、」アンがうなづいた。「患者由来の“iPS細胞”を使い...“症状の再現”にまで到達できた のは、“世界初”ということですね。これは、病気の原因解明や、新薬の研究開発などで、“強力な 武器/・・・強力な道具の1つ”になると期待されています」 外山がうなづき、顎に手を当てた。 「ええと...」アンが、“参考文献”の東京新聞を脇へやった。「これは... 京都大学/中山伸弥教授の研究グループの成果とは違うものですが...同グループが開発 した“iPS細胞”が、いよいよ世界の最先端領域で、その威力を発揮し始めているものですね。そ れにしても、この方面の研究開発というのは、やはり資金、質・量ともに、アメリカが最も進んでい るのでしょうか?」 「うーむ...そういうことですねえ... しかし、もともとそうした状況の中で、“iPS細胞”という大ホームランを打ったのは、日本/京 都大学なのです...まあ、これからはそうもいかないでしょうが...良い成果というものは、単 なる資金力とは違うものです。そういうわけですから、日本も頑張ってほしいですね」 「はい、」アンが、コクリとうなづいた。「そういうことですね」 「ええ...ちなみに... この、ジェームズ・トムソン教授らのチームの実験は、もう少し詳しく説明すると、こういうことで す。まず、遺伝性の“重症型・脊髄性・筋委縮症(SMX/運動神経が徐々に減り、乳幼児期に死亡することが多い )”の男児の皮膚から、“iPS細胞”を作製し、運動神経を分化させました...そして、“病気のた めに神経が死ぬ”のを...“試験管内で再現することに成功した”...ということの様です」 「はい...」 「それから... 発症していない母親の皮膚からも、同様に運動神経を作製し、両方を別々に培養して、これら の状態を比較したようですね...遺伝性の難病ですから、母親からの“iPS細胞”も作製したの でしょう...“参考文献”は、新聞ですから、現在の所、これ以上の詳しい状況は分かりません」 「途中までは...」アンが、言った。「両細胞に、差は見られなかったわけですね?」 「うーむ...そうらしいですね... 約6週間培養を続けると...患者由来の細胞は、“数が減り始めた”とあります。同チームは、 “時間の経過に伴い、神経に異常が出ることが明らかになった。患者の体内で起きるため見えな かった現象を、試験管内で再現できるようになった”...としています」 「はい...」アンが、考えながらうなづいた。「ええ...今後、関連した成果が、続々と広がって行 くものと思います...どうぞ、ご期待下さい」 「そうですね」外山が、顎をなでた。
|
![]()