 ボス のTwitter
=2014年
ボス のTwitter
=2014年 
<正法眼蔵/・・・山水経 (山水が仏の教えを説くこと)
1 ~ 84
>
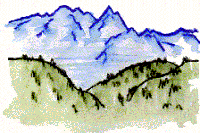



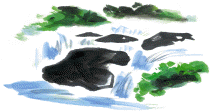
| Community Space /ボスの展望台/ボスのTwitter/仏道/正法眼蔵/山水経 |
|
<正法眼蔵/・・・山水経 (山水が仏の教えを説くこと)
1 ~ 84
> |
| トップページ/New Page Wave/Hot Spot/Menu/最新のアップロード/ 担当: ボス= 岡田 健吉 |

 ツイート の
記 録
ツイート の
記 録 


|
|
|
2月 5日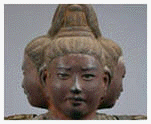 阿修羅/頭部拡大 (国宝) |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(195) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(101-1) ★【山水経/・・・山水が仏の教えを説くこと・・・】・・・(1) 今…ここに見られる山水は…諸仏の方々の悟った境地を現されている。山は山に なりきっており、水は水になりきっていて、その他の何者でもない。
奈良/興福寺/国宝館・・・ 乾漆八部衆立像/頭部拡大 (阿修羅をのぞく) (国宝)
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(196) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(102-2) それは… あらゆる時を超えた山水であるから、今ここに実現している。あらゆる時を超えた 自己であるから、自己であることを解脱している。 ( 自然は真理が実現される所であり・・・自己が自己を発見する所である )
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(197) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(103-3) 山の働きは、大きくて限りないから…雲に乗って空を行くものは、必ず山から出てい る。風に従って進むものは、必ず山から解脱している。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(198) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(104-4) 太陽山の道楷和尚(どうかい・おしょう/芙蓉道楷・禅師)が、一山の僧たちに示して言った。 「青山(せいざん)は常に運歩し、石女(うまずめ)は夜(よる)子(こ)を生む」 山の働きに欠けた所は無いから…山は常に安住し、常に歩むのである。その事を、 詳しく学ぶべきである。 |
| 2月 7日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(199) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(105-5) 山の歩みは、人の歩みと同じである。たとえ、表面的にはそのように見えなくても、 それを疑ってはならない。ここで道楷和尚(どうかい・おしょう/芙蓉道楷・禅師)の言っている ことは、仏道の根本問題であるから、真剣に学びなさい。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(200) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(106-6) 青山は、歩むことによって安住している。その歩みは風よりも速いが、山になりきっ ている人は、その事に気がつかない。山の中には一切世界が開いているが、山に なりきっている人は、その事に気がつかない。
|
| 2月 9日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(201) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(107-7) 山を見る眼がない者もまた、そのような道理を知ることがなく、見ることも聞くことも ない。もし、山の歩みを疑うならば、自己の歩みも分かっていない。自己の歩みを未 だ知らず、未だ明らかにしていない。 ( “山の歩み”とは・・・生滅するものの中に、永遠の相を見ること。それに気づいても、気づかなくても・・・人は永遠 の世界/永遠の現在を生きている)
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(202) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(108-8) 自己の歩みを知るように、青山の歩みを知るべきである。我々が青山を見る時、 青山も自己も、生物でも無生物でもなく、両者の間には何の隔たりもない。そのた め、青山の歩みを疑うことが出来ないのである。 ( 我が山を見ることによって・・・我が山と一体となる。それを、山が歩くと言い、山が山を見るとも言う・・・)
|
| 2月 10日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(203) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(109-9) 世界全体という立場から、青山を明らかにすべきことを人は知らない。真実を知る ためには、青山の歩み/自己の歩みを調べてみる必要がある。前へ進むばかりで なく、後ろへ退き歩むことを、調べてみるべきである。 ( 仏道においては・・・我という立場はとらず・・・無我の立場を説く。無我となるとき、物事は自ずと明らかになる)
|
| 2月 12日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(204) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(110-10) その歩みに休みがあるならば…諸仏祖(しょぶっそ)たちは現れなかったであろう。そ の歩みに極まりがあるならば、仏の教えは今日まで伝わらなかったであろう。進歩 も休まず、退歩も休まない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(205) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(111-11) 進歩は退歩にそむかず…退歩は進歩にそむかない。 このことを <山が流れる> といい、 <流れるのは・・・山である> という。 (ここにいう“山”とは・・・1瞬の滞りもない・・・永遠の万物流転の様相である・・・)
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(206) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(112-12) 青山自身も歩む事を学び、東山自身も水上を行く事を学ぶから…山を学ぶ事は、 山が山を学ぶ事… 山が山の姿のまま、自分の事を学ぶ。それを… 「青山が歩む事はない。東山が水上を行く事はない」 …と誹って(そしって/非難して)はならない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(207) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(113-13) 自己の考えが足りないから、青山運歩(せいざん・うんぽ)の言葉を怪しむ。見聞が浅い から、 <山が流れる> という言葉に驚く… その者達は <水が流れる> という事の真実さえ分からずに…自己の浅はかな見 解に溺れているのである…
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(208) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(114-14) このように…山の働きの全てが真理を現している。 山には山の歩みがあり、山の流れがあり、山が山を生む時がある。 山が山を学んで、諸仏となることにより…諸仏祖がこの様に、実現しているのであ る。
|
| 2月 13日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(209) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(115-15) たとえ… <山は…草木、土石、土塀によって成り立っている> …という見方があっても、それは取り立てて疑ったり、迷ったりすべきことではなく… またそれによって、山の全てが分かるわけではない。
|
2月 14日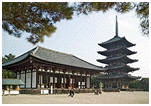 奈良/興福寺 東金堂と五重塔 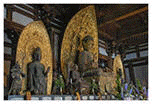 現在の東金堂には薬師三 尊像を中心とする諸仏を安 置する。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(210) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(116-16) また… <山は宝玉の輝く所である> …と見る時があっても、そればかりが真実ではない。 また… <山は諸物が修行する所である> …という考えがあっても、そのような考えに、執着してはならない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(211) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(117-17) また… <山は・・・仏の不思議な働きを現している> …という、最も適切な考え方が現れても、真実はそれだけではない。各の考えは、 その立場にもとずくのであって…諸仏祖が悟った事とは異なる、狭い考えである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(212) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(118-18) このように… <物> と <心> を分けて考えるのは、釈尊の戒められた所である。 <心> と <本質> を分けて説く事は、諸仏祖の求めなかった所である。 <心> や <本質> を表面的に見ようとするのは、異教徒の所業である。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(213) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(119-19) また… <言句> にこだわることも、悟りの道ではない。 さて…このような立場を超える事がある。それが今ここに言う… <青山が常に歩む> <東山が水上を行く> …ということである。このことを、詳しく学ぶべきである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(214) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(120-20) <石女(うまずめ)が夜(よる)子(こ)を生む> …とは、石の女が子を生む時は、ちょうど夜が全てを一体化してしまう様に、全て の対立から自由ということ… 石には…男石、女石、非男女石があって…天地の欠けた所を補っているという。
|
2月 18日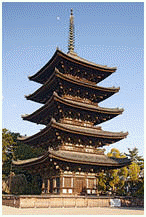 奈良/興福寺/五重塔 730年/天平2年に、 光明天皇が創建。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(215) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(121-21) また…天石、地石があるという。これは、俗世間の人の言うことであるが、知る人は 稀(まれ)である。 我々は、この <生児(せいじ/・・・生まれたばかりの子)> という言葉の真意を、学ぶべき である。 <生児の・・・時> には、親と子が別々にあるのではない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(216) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(122-22) 子を生んで、親となることも <生児> であり…親が子となる時にも <生児> が 実現することを、学ぶべきである。 (/真実の自分を悟ってみれば・・・それは元からの自分と別のものではない。親も子も1つだと知ることを、“石女が 子を生む ”・・・という。)
|
2月 19日 道元禅師 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(217) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(123-23) 雲門匡真大師(うんもん・きょうしん・だいし/雲門文偃(うんもん・ぶんえん)禅師のこと)が言っている。 「東山は水上を行く」 この意味は…全ての山が東山であり、全ての山が水上を行く…ということである。 それにより、九山(きゅうざん/・・・九山八海(くせん・はっかい)とは・・・仏教の世界観でいう、須弥山を順 に取り囲む九つの山と八つの海)やスメール山(/須弥山(しゅみせん)・・・古代インドの伝説で、世界の中 心にあったとされる山々)など、全ての山々が実現し、修行し、悟っているのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(218) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(124-24) しかし…雲門自身がはたして、東山について、そのような理解から解脱しているか どうかは分からない。 今…宋の国には、浅はかな者達が多く群をなしており、少数の真実者によって、撃 退することができない。 (/道元が入宋した頃...中国の仏教界全体が沈滞期に入っていた。禅宗のみは、隋・唐の黎明期・隆盛期から、 “五家七宗”といった流派に分かれ繁栄していた。しかし世俗化の波は、道元が訪れた天童山にも浸透していた。 道元は、日本から同行した師/明全とも別れ、天童山を去って諸山遊歴に出る。 そして、それにも失望した頃・・・天童山に新しい住持として如浄が就任したうわさを耳にし、帰山する。以後、如浄 のもとで坐禅弁道に励み、大悟した・・・)
|
2月 20日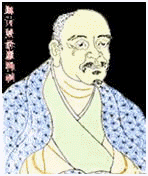 黄檗希運 (おうばく けうん) 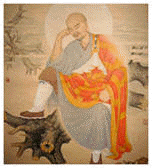 臨済義玄 (りんざいぎげん) 臨済宗の開祖 宗風は馬祖道一に始まる 禅風を究極まで推し進め、 中国禅宗史の頂点を極め た。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(219) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(125-25) 彼らは言う… 「【東山水上行(とうざん・すいじょうこう)の公案】や、南泉(/南泉普願・・・馬祖道一に師事)の 【鎌の公案(/『葛藤集』にある公案・・・江戸時代に妙心寺によってまとめられた公案集/二八二則)】は、 もともと理解できない。 何故なら、全て思慮によって理解できる語話は、禅の語話ではない。思慮に よって理解できないものこそ、先覚者の語話である」…と。
【鎌の公案】 ある僧が、南泉の名声をたより、南泉の住む庵を訪ねて来たが、山の中で迷ってしまった。 すると、丁度その時、南泉自身が鎌で草を刈っていた。僧は南泉とは気づかず、彼に南泉の 庵への道を聞いた。
「南泉さんへの道は、どっちに向かって行けばいいのでしょうか?」
「この私の鎌は、三十銭で買ったものです」 訊ねているのです」 南泉が言った。 「私が使って見て、ずいぶん使いやすく、気持ちよく切れますよ」
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(220) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(126-26) 従って… 黄檗(/黄檗希運(おうばく けうん)・・・臨斉義玄の師)の痛棒(/痛烈な打撃。また、座禅のときに、師が心の 定まらない者を打ちこらすのに用いる棒)や臨済(/黄檗希運に師事し、いわゆる黄檗三打の機縁で大悟)の大 喝(/(怒鳴ること)・・・を多用する峻烈な禅風)は、理解することができず…思慮によってはかり 知ることができないから…あらゆる時を超えた大悟である…というのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(221) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(127-27) そして… 「先覚者が人を導く手段として、はからいを絶つ言葉を用いたが、それらの言 葉は理解できない」…と言う。 そのように言う者は…未(いま)だ正しい師に逢わず、学ぶ力を持たない、取るに足 りない者達である。
|
2月 21日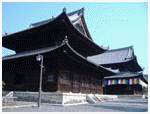 妙心寺 京都市/右京区花園にあ る臨済宗妙心寺派大本山 の寺院。 【鎌の公案】は、 江戸時代に妙心寺によって まとめられた公案集/『葛 藤集』にあるという。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(222) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(128-28) 宋の国には…二、三百年このかた、この様な悪者達が多い。哀しむべきことである。 正しい仏道が、すたれてしまっているのである。彼等の考えは、小乗の者に及ばず、 異教徒よりも愚かである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(223) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(129-29) 彼等は俗人でもなく僧侶でもなく、人間でもなく天人でもなく、仏道を学んでいる動 物たちよりも愚かである。 彼等が理解できないというのは、彼等ばかりが理解できないのであって、諸仏祖は そうではない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(224) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(130-30) 自分達が理解できないからといって、諸仏祖が理解した所を、見過ごしにしてはな らない。もし、理解することができないならば、彼等の… 「理解できない」 …という理解も、正しくないはずである。
|
2月 22日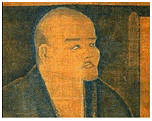 道元禅師/永平道元 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(225) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(131-31) そのような者達が、宋の国の諸方に多い。私が直に見聞きしてきたことで、哀れむ べきである。彼等は、先覚者の言葉が思慮ある言葉であることを知らず、そのよう な言葉の背後にある、思慮を超えることを知らない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(226) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(132-32) 宋の国にいた時…彼等を笑ったが、彼等は何も言えず、1語も答えなかった。彼等 の言う… 「理解ができない」 …という考えは、邪(よこしま)な考えに過ぎない。真実の師が無かったとはいえ、そ れは異端者の考えである。
|
| 2月 28日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(227) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(133-33) <東山が水上を行く> という言葉が… 諸仏の悟った真実であるという事を、知るべきである。 諸水が東山の麓に現れるから、諸山が雲に乗り天を歩む。諸水の上にあるのは 諸山であり、登りも下りも、共に水上を行く…
|
| 5月 26日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(228) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(134-34) 諸山の爪先は諸水を歩み、諸水を躍らせるから、その歩みは自由自在に修行・悟 りを実現する。 (<山が水上を行く>とは…我が解脱していると言うこと。そのことが分かれば、 先覚者の境地に到達する…)
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(229) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(135-35) 水は強弱、湿乾、動静、冷暖、有無といった差別を超えている。固まれば金剛石よ りも硬く、融ければ乳水よりも柔らかく、誰も破ることができない。従って、水が具え 現している性質を、疑うことはできない。
|
| 5月 27日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(230) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(136-36) 我々はしばらく、諸方の水をありのままに見ることを学ぶべきである。人間や天人 が水を学ぶ時ばかりが、学ぶ時ではない。水が水を見て、水を学ぶことがある。水 が水を悟るのであり、水が水のことを説いている。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(231) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(137-37) 我々はそのようにして、自己が自己に会う道を実現すべきである。他者が他者を学 び究め、それを越えて行くことを学ぶべきである。
|
| 5月 28日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(232) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(138-38) 山水の見方は、見るものの種類によって様々に異なる。ある経典によれば、我々が 水と呼んでいるものが、天人たちには玉飾りに見えるという。では天人たちは、我々 が何と思っているものを、水とするのであろうか。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(233) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(139-39) 我々は、天人たちが玉飾りと思っているものを水と考える。また天人たちは、水を麗 しい花と見るというが、水として用いるわけではない。餓鬼は水を猛火と見、濃血と 見る。竜魚は水を宮殿、楼閣、宝玉と見る。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(234) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(140-40) あるものは…水を樹林、土塀と見る。あるいは、悟りの本質と見、真実の人体と見、 心や姿と見る。そして…人間は、それを水と見る。 水はこのように、それぞれの立場によって、生かしたり殺したりされる。
|
| 5月 29日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(235) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(141-41) 諸類によって、見方が同じでないことを考えてみるべきである。1つのものを見るに、 見方が様々にあるのか。様々にあるものを、我々が1つのものと見誤っているのか。 このことを、繰(くり)返し考えてみるべきである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(236) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(142-42) このように…修行と悟りの道も、1つや2つではない。学び究めるべき所が、様々に あることを理解しなさい。 ( 同じものでも、見る立場が異なれば別のものに見えることを知り、広い視野で学ぶべきである…)
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(237) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(143-43) 例え…諸類で水が様々に見えるとしても、水そのものはなく、諸類共通の水もない ようだ。しかし水は、我々の心身により生じたものでなく、行いにより生じたものでも なく、自己や他者により生じたものでもない。
|
| 5月 30日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(238) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(144-44) 水は水でありながら、水であることを解脱している。水は、物質的要素、色彩的要 素、感覚的要素を解脱しつつ、物質として実現している。ゆえに、この世界が何に よって成立しているか、明らかにするのは難しい。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(239) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(145-45) 世界が円盤状の物質の上に乗っていると考えるのは、主観的にも客観的にも真実 でなく、あさはかな論にすぎない。何者かに頼らなけれは、安住することができない と思うから、そのように考えるのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(240) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(146-46) 釈尊が言われている。 <全ての物事は・・・ことごとく解脱していて・・・留まるところがない> 解脱していて…束縛されることが無いとはいえ、全ての物事が、それぞれのものに なりきっていることを知るべきである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(241) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(147-47) ところが、人間は水を見て…<水は流れて行くものである>と見るばかりである。 水の流れには様々あるのであるから…そのように見るのは、人間の部分的な見方 に過ぎない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(242) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(148-48) 水は…いわゆる地を流れ、空を流れ、上に向かって流れ、下に向かって流れる。 ある時には、河の一隅を流れ…ある時には、深い淵(ふち)を流れる。上っては雲と なり、下っては淵となる。
|
| 5月 31日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(243) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(149-49) 周(しゅう/紀元前の中国古代の王朝。殷を倒して王朝を開いた。)の文子(もんし)が言っている。 <水の道は・・・天に昇っては雨露となり・・・地に下っては江河となる・・・> 俗世間の人でさえ、この様に言っている。仏の子孫と称す者たちは、俗世間の者 よりも愚かなことを、恥ずべきである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(244) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(150-50) この言葉の意味は…水の道を水が知っているかどうかにかかわらず、水は水とし て働いていると言うこと… 文子が<天に昇って雨露となる・・・>と言う様に、水はどの様な上空上方へ昇っ ても、雨露となることを知れ…
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(245) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(151-51) 雨露は、行く世界によって様々な形をとる。水の至らない処があるというのは小乗 (/小乗仏教)の教えである。それとも仏道以外の誤った教えである。水は火焔(かえん) の内にも至り、心、思慮分別の内にも至り、仏の本質の内にも至る。
|
6月 1日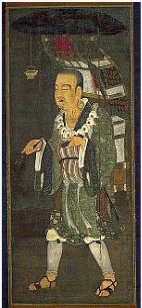 玄奘三蔵 の像 (げんじょう・さんぞう) <東京国立博物館 蔵 鎌倉時代 重文 > 尊称:三蔵法師 宗派:法相宗 寺院:大慈恩寺 著作:『大唐西域記』ほか、 仏教典多数 唐代の中国の訳経僧。玄 奘は戒名であり、俗名は陳 褘(ちんい)。尊称は三蔵法 師。鳩摩羅什(くまらじゅう) と共に二大訳聖。真諦と不 空金剛を含めて四大訳経 家とも呼ばれる。 629年に陸路でインドに向 かい、巡礼や仏教研究を行 って645年に経典657部 や仏像などを持って帰還。 以後、翻訳作業で従来の 誤りを正し、法相宗の開祖 となった。 また、インドへの旅を地誌 『大唐西域記』として著し、 これが後に伝奇小説/『西 遊記』の基ともなった。 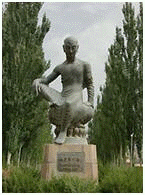 鳩摩羅什 の像 (くまらじゅう・・・ サンスクリットでは ・・・クマーラジーバ) (新疆ウイグル自治区/キ ジル石窟の入り口前広場 に、最近建てられた鳩摩羅 什の像) 新疆ウイグル自治区クチャ 県の西域僧。 後秦の時代に長安に来て 約300巻の仏典を漢訳し、 仏教普及に貢献した訳経 僧。 最初の三蔵法師。後に玄 奘など、多くの三蔵が現れ た。後の玄奘と共に二大訳 聖と言われる。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(246) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(152-52) また文子が…<地に下って江河となる>と言っている様に…水が地に下る時、 江河となり、江河の1滴がよく賢人になることを知るべきである。凡庸(ぼんよう)の もの達は、水は必ず、江河海川にあると思っている。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(247) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(153-53) しかし、そうではない… 水の中にも、江河があるのである。従って、江河でない処にも水はあるのであって、 水が地に下る時、江河を形づくるに過ぎない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(248) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(154-54) また… <水が江河をなしているのであるから・・・水の中に世界のあるはずがなく・・・ 仏の国のあるはずがない・・・> …と考えてはならない。1滴の水の中にも、無限に広い仏国土が実現するのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(249) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(155-55) 従って、仏の国の中に水があるとも言えず、水の中に仏の国があるとも言えない。 水は時間や存在のあり方に関わりなく、水としての真実を実現しているのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(250) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(156-56) 諸仏祖の行く処に、水は必ず行き、水の行く処に、諸仏祖が必ず現れるのである。 そのため諸仏祖たちは、必ず水を、自己の身心として学んできたのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(251) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(157-57) 従って<水が上に昇らない>という言葉は、仏道の内外の典籍にない。尤(もっと) もある経の中に、<火風は上に昇り・・・水火は下にくだる・・・>という1節があ る。ここにいう<上下>という言葉は、さらに検討する必要がある。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(252) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(158-58) それは、仏道の上での上下である。いわゆる、地や水の行く処を、仮に下とするの である。下として初めから定まっている処に、地や水が行くのではない。同じ様にし て、火や風の行く処を仮に上とするのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(253) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(159-59) 存在世界に、初めから、上下四方の差別があるのではない。物質の働きを基準と して、方角のある世界を考えるのである。天界は上、地獄は下にあるのではない。 地獄も一切世界にあり、天界も一切世界にある。
|
6月 2日 龍 樹 (りゅうじゅ/・・・ サンスクリットのナーガール ジュナの漢訳名) 頭上にナーガ(/インド神話 に起源を持つ、蛇の精霊あ るいは蛇神)をいだく龍樹 尊称: 龍樹菩薩、龍樹大士 生地: インド 没地: インド /2世紀に生 まれたインド仏教の僧 大乗仏教中観派の祖であ り、日本では、八宗の祖師 と称される。 真言宗では、真言八祖の1 人であり、浄土真宗の七高 僧の第一祖とされ龍樹菩 薩、龍樹大士と尊称。 密教系の仏教では、龍猛 (りゅうみょう)と呼ばれるこ ともある。 南インドのビダルバの出身 のバラモンと伝えられ、幼 い頃から多くの学問に通じ た。サータヴァーハナ朝の 保護の下でセイロン、カシミ ール、ガンダーラ、中国など からの僧侶のために院を設 けた。この地(古都ハイデラ バードの東 70 km)は後に ナーガールジュナ・コーンダ (丘)と呼ばれる。 釈尊が生まれたのは、紀元 前5世紀頃(/孔子がいた のもこの頃・・・紀元0年が キリストの誕生)だが... 龍樹が生まれた2世紀頃に は、大乗仏教が勃興してい て、この運動を体系化した ともいわれる。 ことに大乗仏教の基盤とな る『般若経』で強調された 「空」を、無自性に基礎を置 いた「空」であると論じて釈 迦の縁起を説明し、後の大 乗系仏教全般に決定的影 響を与える。 このことにより龍樹は大乗 八宗の祖として仰がれてい る。 彼の教えは、鳩摩羅什によ って中国に伝えられ、三論 宗が成立。 また、シャーンタラクシタに よってチベットに伝えられ、 ツォンカパを頂点とするチベ ット仏教教学の中核とな る。 8世紀以降のインド密教に おいても、龍樹作とされる 『五次第』などの多数の文 献が著された。 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(254) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(160-60) ところが、竜魚が水を宮殿と見る時には、ちょうど人がこの世の宮殿を見る時の様 に、宮殿が流れるとは思わないであろう。もし傍観者がいて、<お前が宮殿と見て いるものは・・・実は流水なのだ・・・>と言えば…
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(255) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(161-61) …我々が今<山が流れる>と聞いて驚くように、竜魚は忽(たちま)ち驚き疑うであ ろう。しかし中には、<宮殿楼閣の欄干や柱が・・・流水ということもあり得る> と、理解する竜魚もあろう。この道理を思い巡らすべきである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(256) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(162-62) 我々はこの様にして、対立した見方を超えることを学ばねばならない。それでなけ れば凡夫の身心を解脱することができず、諸仏祖の国土、凡夫の国土、凡夫の宮 殿を、正しく理解することができない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(257) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(163-63) 人間は海の中のもの、河の中のものが水とを知っているが、竜魚やその他のもの が、どの様なものを水として用いるかを知らない。自分が水と考えるものを、どの類 もみな水として用いると、愚かに決めてはならない。
|
| 6月 26日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(258) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(164-64) 今、仏道を学ぶ者が水を学ぶ時…人間の考えだけに止まってはならない。仏道の 上での水を学ぶべきである。諸仏祖が自由自在に用いる水を、どの様に見れば良 いかを学べ。先覚者の境地に、水が有るか無いかを学べ。
|
| 6月 28日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(259) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(165-65) 山は常に聖人達の住居(すまい)である。賢人も聖人も共に山に住居とし、山を身心 とする。賢人聖人によって山の真実の姿が現れるのである。 山には多くの聖賢が集まるが、山に入って誰も、その一人にも会ったことがない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(260) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(166-66) ただ山の働きが実現しているばかり…彼等が山に入った形跡は残っていない。 世間から山を眺める時と、山の中で山に会う時では、山の姿は遥かに異なる。山 が流れるとは、水が流れないという、竜魚と同じではない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(261) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(167-67) 人間や天神は、それぞれの世界に安住しており、それを他類が疑ったり疑わなかっ たりする。 そこで我々は、<山が流れる>という言葉を諸仏祖に学ぶべきである。徒らに、驚 きや疑いにまかせておいてはならない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(262) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(168-68) 同じことについて、一方は流れると言い、一方は流れないと言う。ある時は流れる と言い、ある時は流れないと言う。 このコトを学ばなければ…仏の教えを学んだとは言えない。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(263) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(169-69) 諸仏祖が言う… <焦熱地獄へ行きたくなくば、仏の教えを謗(そし/・・・謗る=人を悪くいう。非難する)って はならない> この言葉を身心に銘記(めいき/しっかりと、心に刻み込んで忘れないこと)しなさい。身心の内外 に銘記しなさい。形の無い所にも有る所にも銘記しなさい。木・石・田・里にも銘記し なさい。
|
| 6月 29日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(264) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(170-70) もともと… 山は国家に属しているとはいえ、山を愛する人に属している。山がその主(あるじ) を愛する時、聖賢、高徳の人は必ず山に入る。聖賢が山に住む時、山は彼等に 属するから、樹石は繁茂し、鳥獣はすぐれている。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(265) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(171-71) それは… 聖賢たちが彼等に徳を及ぼすからである。山が賢人聖人を好むことを、知るべきで ある。帝王たちが、しばしば山に行幸(ぎょうこう/天皇が出かけること。行き先が2か所以上の時は 巡幸という〕)して、賢人を拝し、聖人を拝して教えを乞うたことは、古今の誉れた事実 である。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(266) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(172-72) その様な時には… 帝は師礼をもって敬い、世間のしきたりに従わない。帝の権威が、山の賢人に及ぶ ことは全く無いのである。帝たちは、山が俗界から離れていることを、知っていたに 違いない。
|
| 6月 30日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(267) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(173-73) 黄帝(こうてい/神話伝説上では、三皇の治世を継ぎ、中国を統治した五帝の最初の帝であるとされる)が、崆 峒山(こうどうざん)に広成(こうせい/広成子は・・・古代の仙人で、崆峒山の石の部屋で暮らしていた。彼が 千二百歳の時に黄帝が至上の道の要旨について尋ねてきた)を訪ねた昔…帝は師を敬って膝で進 み、額づいて道を問うた。 また釈尊は…かつて父王(/浄飯王(じょうぼんおう))の王宮を出て山に入られた。しかし 父王は山を恨まず、山にあって王子釈尊を導いた者達を怪しまなかった。
|
| 7月 1日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(268) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(174-74) 釈尊は、12年の修行期間を殆(ほとん)ど山で過され、悟りを開かれたのも、山におい てである。転輪王(てんりんおう/古代インドの伝説上の理想的国王)の様な力を持った父王(/浄飯 王(じょうぼんおう))ですら、山に対して無理強いすることはなかったのである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(269) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(175-75) 山は人間界のものでなく、天界のものでもないことを知れ。人間の推し量りによって 山を考えてはならない。人間の狭い考えに促されさえしなければ、誰も山の流れる ことや、山の流れないことを、疑わないであろう。
|
| 7月 5日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(270) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(176-76) また…賢人聖人達が水に住むこともある。 魚を釣ることもあり、人を釣ることもあり、道を釣ることもある。水中の誉た趣 (ほまれたおもむき)である。 さらに…自己を釣り、釣ることを釣り…釣りに釣られ、道に釣られることもあろう。
|
| 7月 8日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(271) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(177-77) 昔…徳誠和尚(/急に薬山惟儼禅師の寺を離れて、川の畔に住んだ事跡がある。華亭江という川の畔でそこ を通りかかる賢人・聖人と会う事を目的としたのである。)が、唐の武宗(ぶそう/唐朝の第18代皇帝。道教に 傾斜するあまり“会昌の廃仏”と称される廃仏令を出している。)の弾圧にあう。慌(あわただ)しく薬山(や くざん/薬山惟儼禅師の住した、湖南省岳州府にある薬山。薬山は芍薬(しゃくやく)山とも呼ばれる。 山中に芍薬 が多かった。)を離れ、華亭江(かていこう)に舟を浮かべ住んでいた時、後に華亭江の賢 聖と呼ばれた爽山(かつさん)を弟子とした。これこそ、魚を釣ること、人を釣ること、水 を釣ることではなかろうか。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(272) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(178-78) 爽山(かつさん)が徳誠に会うことができたのは、彼が自分を捨てて徳誠に学んだから である。徳誠が爽山に接したということは、彼がまことの自己に会ったということで ある。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(273) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(179-79) 世界の中に水があるばかりでなく、水の中にも世界がある。雲の中にも、自己の世 界がある。風の中にも、火の中にも、地の中にも、存在世界の中にも、一茎の草の 中にも、一本の杖の中にも、自己の世界がある。
|
| 7月 9日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(274) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(180-80) そして… 自己の世界がある所には、必ず諸仏祖の世界がある。そのことを、よくよく、学ぶ べきである。 (★ 解脱者の立場から見れば・・・世界中の全てのものが・・・等しく解脱者の境地にある )
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(275) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(181-81) 従って水は… 真実を悟った竜が見た宮殿の様なもので、流れ去るばかりではない。水が流れると 独(ひと)り決めするのは、水を謗(そし)ることである。何故ならその様な者は、立場を 変えれば、水は流れないと決めるからである。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(276) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(182-82) しかし… 水は…ありのままの水なのである。水は水なのであって、流れではない… このようにして…一掬(ひとすく)いの水の、流れることや流れないことを学び究める時、 全ての物事の究極が、たちまち理解されるのである。 |
| 7月 10日 |
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(277) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(183-83) 山には… 宝の中に隠れている山があり、沢の中に隠れている山があり、空の中に隠れてい る山があり、山の中に隠れている山があり…さらには、隠れることの中に隠れてい る山があることを、学びなさい。
( 禅・・・ 日本における展開 )・・・(278) 《 道元・・・ 『正法眼蔵』 》・・・(184-84) 古仏曰く・・・ <山は山であり・・・水は水である> 真意は…山はただの山ではなく… 解脱者の見た山! その山を、身をもって学ぶべきである。山を学ぶとは自己が山となって学ぶことであ り、その山水が賢人聖人となる。
|