 Twitter/2021・・・12月
Twitter/2021・・・12月 







(ネットより画像借用)
| Menu/ボスの展望台/ボスのTwitter/2021年/12月 |
|
|
| トップページ/New Page Wave/Hot Spot/Menu/最新のアップロード/ 担当: ボス= 岡田 健吉 |
 |
|
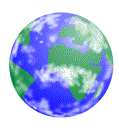 万能型 防護力 脱・戦争ゴッコ 脱・経済ゴッコ 脱・覇権ゴッコ 物理的 専守防衛 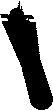  |
〔人間の巣/未来型都市/千年都市〕/〔極楽浄土インフラ〕 の・・・世界展開/ポスト民主主義社会の器!
★ 日本の社会インフラの再構築・・・ 激烈化する気候変動/豪雨・豪雪・熱波・寒波・ 地震・火山災害から・・・国民を完全防御! ★ 対核シェルター以上の・・・ 戦争ゴッコへの対応! 感染症パンデミックへの対応!万能型・防御力/地球近傍天体の衝突への対応! ★ 気候変動への長期的対応・・・世界中で可能な・・・ 脱・冷暖房社会! 脱・車社会への対応! 人口爆発への対応! コンパクト・分化・多様性・・・ スローフード・スローライフ社会への・・・回帰! |
| 12月 31日 |
お休みします |
| 12月 30日 |
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 245 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 10 )
中断している、《ブラックホールの・・・情報問題》 に戻りますが、ちょうど、<年末年始> になりますね。 ええと… 《MyWeekly Journal》 の方で、<時代的なコメント/・・・重要帰路の考察> があると いう事で、そちらを優先します。私達も、《MyWeekly Journal》 へ移動することにします。 1日お休みして、新年からになります。どうぞ、よいお年を! 」
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 244 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 9 )
ともかく、この <須磨> で、『笈の小文』 は終了です。 江戸への帰路は… くり返しますが、<中山道/木曽街道(/京と江戸を、美濃国および信濃国を経て結んでいた、山道の俗称) > を行き、姨捨(おばすて/・・・更科)で、<田毎の月(たごとのつき/長野県・更級郡・冠着山(かむりきやま /姨捨山)のふもとの、小さな水田の一つ一つに映る月。名月として知られます。)> を見て、<善光寺(ぜんこうじ /善光寺平・・・長野市にある、無宗派の単立仏教寺院。本尊は、日本最古と伝わる <一光三尊阿弥陀如来> で、絶対秘 仏)> を参拝する、 『更科紀行』 になるわけですね。 『更科紀行』 は、私達はすでに、考察を終了しています。そちらへどうぞ! 」 はい…」響子がうなづき、インターネット正面カメラの方を向き…
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 243 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 8 )
この、翌々年/1689年/元禄2年… 芭蕉は、『奥の細道』 へ、<当時、誰も経験していない・・・奥州/陸奥への、ヒッチハ イクでの大遠征> に、出発して行くわけですよね。 『笈の小文』 の帰路/『更科紀行』 に… 名句が多いというのも、芭蕉の俳人としての飛躍/超脱(ちょうだつ/普通の範囲、程度を越えること) が、この <須磨> であったのでしょうか?芭蕉の、<禅的境涯/・・・風雅風狂の、新た な側面> なのでしょうか?
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 242 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 7 )
<江戸時代初期/元禄の頃> に、詠まれたというより、何故か、現代的な感じがします わ。背景描写もそうですが、芭蕉の新たな側面を見たような気がします。
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 241 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 6 )
がは芭蕉です。印象派の絵を、彷彿(ほうふつ)とさせる描写ですわ。 それに… 芥子(けし)の花の間に、早朝の漁師が見え隠れするのは、動的な描写ですよね。これも新 鮮な感じがしました、」
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 240 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 5 )
「うーん…」マチコが言った。「今は… 須磨海岸は、海水浴場で賑わっているわよねえ。昔は寂しさの名所で、蟄居の地だったの かあ、」 「芭蕉は…」響子が言った。「<須磨> では…
|
| 12月 29日 |
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 239 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 4 )
とか。多くの歌に、詠まれているのでしょうか。ともかく、<歌枕の地> であり、そんな名所 でもあるわけですね。 あ、それから… 『伊勢物語(/在原業平を思わせる男を主人公としている)』 で、<在原業平(ありわらの・なりひら)> を紹介 しましたが、その <兄/在原行平(ありわらの・ゆきひら/・・・『小倉百人一首・・・16/中納言行平』 > が、理由は明確ではない様ですが、この <須磨に・・・ 一時、蟄居(ちっきょ/家の中にとじこもっ て外へ出ないこと。江戸時代に、武士に科した刑罰の1つ。)> …
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 238 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 3 )
<後鳥羽上皇/後鳥羽院は・・・島根県/隠岐島に・・・島流し・・・> に、されたわけで す。生涯許されず、一緒に、『新古今和歌集』 を編纂した、<藤原定家> との、歌の交流 もなく、その地で崩御しています。 <芭蕉> は… 夏の須磨は、主人の留守に…
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 237 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 2 )
<須磨は・・・古来・・・寂しい場所の代名詞の様な所・・・> ですが、難波からも近く、都 からそれほど遠い所ではありませんよね。 後の、<後鳥羽上皇> が、院宣(いんぜん/上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。 天 皇の発する宣旨に相当する。)によって鎌倉幕府に反旗を翻(ひるがえ)し、<承久の乱(じょうきゅうの・ら ん)> を引き起こしたほどの…
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 236 ) 【 支折の言葉・・・24/1 】・・・( 1 )
ですね… 私は… 恥ずかしながら、『源氏物語』 は全編を通して読んだことはなく、何度も食い齧(かじ)った仲 間の1人です。 そんな私が、説明するのも何ですが… <須磨> は、主人公/光源氏が…
|
|
12月 28日 (12月 5日) (12月 6日) に、先に考察してしま ったものを、正しい位 置に移動しました。 |
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 235 ) 【 支折の言葉・・・☆☆/☆ 】・・・( ☆ )
ウッカリの手違いで、<大和路/唐招提寺> の箇所が、抜け落ちていました。 こんなミスは初めてです。挿入し、前後を修正して置きます。 アップロード後、HP(HomePage)上で修正し、分類番号を正します。ミスの記録は残します。
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 234 ) 【 現代語訳・・・24/ 1 】・・・( 4 )
起きたばかりの・・・ 漁師の顔が・・・ 途切れ途切れの・・・ 芥子の花の合間に見える・・・ 朝の景色だなあ・・・
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 233 ) 【 現代語訳・・・24/ 1 】・・・( 3 )
中に黒っぽく見え、ほととぎすが鳴き始めそうな東の空も山ではなく海の方角からは やくも白みかかってくる。須磨寺一帯の上野と思われる所は、麦の穂波が赤らんで…
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 232 ) 【 現代語訳・・・24/ 1 】・・・( 2 )
何か物足りない感じだ・・・ 夏の須磨は・・・ 須磨は秋が一番だ・・・
卯月中ごろの空だが、朧(おぼろ)な春の夜の風情を残している。・・・
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 231 ) 【 現代語訳・・・24/ 1 】・・・( 1 )
出ているものの・・・ 主人の留守に訪ねた様な・・・ むなしさの漂う、須磨の夏だなあ・・・
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 230 ) 【 原文・・・24/ 1 】・・・( 2 )
ひて、漁人(ぎょじん)の軒ちかき芥子(けし)の花のたえゞに見渡さる。
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 229 ) 【 原文・・・24/ 1 】・・・( 1 )
卯月(うづき)中比(なかごろ)の空も朧(おぼろ)に残りて、はかなきみじか夜の月もいとゞ艶(え ん)なるに、山はわか葉にくろみかゝりて、ほとゝぎす鳴出づべきしのゝめも、・・・
|
| 12月 27日 |
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 228) 【 支折の言葉・・・23 /1 】・・・( 27 )
<須磨・明石夜泊> になるわけですが… 先に、申し上げた様に、<大和路> が抜け落ち、先にこちらを考察してしまったわけです ね。 申し訳ありませんでした。
< して、置きます。次回は、その作業になります」
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 227) 【 支折の言葉・・・23 /1 】・・・( 26 )
』 の旅の折、水口で芭蕉と再会を果たし、入門。)』 に… <此句は万菊を供して難波の一笑が本(もと)に旅ね(旅寝)の時也(ときなり)。一笑はいが (伊賀)にて紙や(屋)弥右衛門と云る旧友也。> …とありました」 「はい…」支折が、コクリとうなづいた。「有難うございます… ええ 『笈の小文』/<大和路> は、ここで終了します。
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 226) 【 支折の言葉・・・23 /1 】・・・( 25 )
『伊勢物語・・・第九段/・・・三河の八橋・・・』 を思わせる様な、見事なカキツバタが咲 いていた様です。ホホ、この一言を説明するのに、ずいぶん長い引用になりましたね。 さぞ… 一笑の屋敷には、<国宝・・・燕子花図(かきつばたず)・・・尾形光琳・筆> の様な、清楚(せ いそ/清らかで、さっぱりしていること)なカキツバタが咲いていたのでしょう。吉野山の桜を堪能して、 もうそんな季節に移っていたわけですか。 この、<芭蕉の・・・ 杜若(かきつばた)の句> に関しては、私も、ちょっと調べて置きました。
《 笈の小文・・・ 芭蕉/2 》・・・( 225) 【 支折の言葉・・・23 /1 】・・・( 24 )
これが、『伊勢物語・・・第九段/東下り』 です。次は、<第十段/みよし野> になりま すね、」 「はい…」響子が、支折にうなづいた。「ともかく…
|
| 12月 26日 |
|