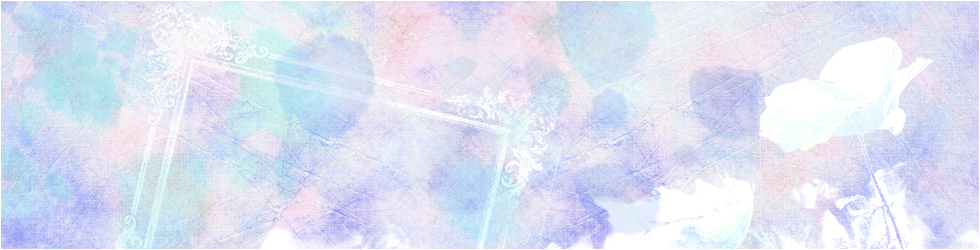
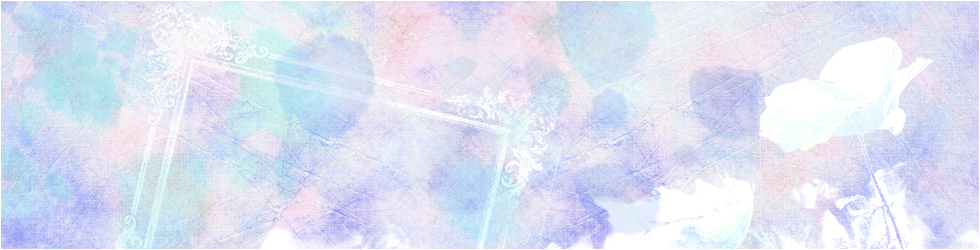
その日、足弱は今世王に内緒で城に来ていた。
レシェイヌが聴政を行うところを、少しだけこっそり見てみたいとの希望を口にしたからだ。
気づかれないように隠れ見た今世王は、足弱と共にいる時とは違い、どこから見ても聡明で賢明な王様だった。次々と決裁する姿に惚れ惚れする。
足弱は満足そうにしばらく眺めると、今世王に声をかけることもなく宮殿に戻った。
「よろしかったのですか?陛下に会わずに」
「はい。昨日も一緒だったし、少しだけでも顔が見られたので。王様のレシェイヌはキラキラしてて、すごく素敵ですね」
「はい。でも、兄上さまとご一緒の時の方が輝いて見えます」
「そんなこと、ない、です」
足弱は照れたような笑顔を見せたが、すぐに笑みを消した。
「命さん…おれ、病気かもしれない」
足弱は、悲痛な表情で傍らに控える命に話しかけた。
「兄上さま!どこか痛みますか?いつから?」
「胸が痛い。ぎゅってする」
「すぐにお医者を呼びますね」
使いを出そうとする命を、足弱は引き留めた。
「レシェがいないと……胸が苦しい」
足弱の言葉に、命ははっとした。
「……兄上さま。陛下と一緒の時はどうです?」
「痛くない」
(ああ、これは…)
命には、原因がわかってしまった。それは血族狂いの王族の病。王室病と並びどちらも命にかかわるもの。《恋狂い》または《恋煩い》とも呼ばれる病。
心が繋がる前に身体を繋げてしまったばかりに、しかも足弱は今世王以外の王族を知らない。王族どころか、ほとんど人と会わない生活をしていたのだ。今まで無縁の痛みだったのだろう。
王室病が体を病むのなら、恋狂いは心を病む。医者で治せるものではない。
「陛下をお呼びしますね。苦しいのを治していただきましょう」
「でも、レシェはお仕事たくさんあるから、邪魔してしまう」
「陛下は気にしません」
「おれが、気になる」
一度決めると、足弱は折れない。一途さがここに出てしまった。
「おれ、どうしたんだろう。どんどん胸が苦しくなる」
「兄上さまは……陛下に恋心をお持ちなのだと思います」
「恋?」
「好きより少し深いものです」
足弱は、儚く微笑んだ。
「これが恋っていうなら……ずいぶん、痛いものなのですね」
すぐに緊急狼会議が開かれた。
「…と。兄上さまは、これ以上好きが深くなるのが困ると、泣き出されました。陛下にどうお伝えしたらよいものか」
命は、足弱の現状を報告した。
「陛下はお喜びになるでしょう」
「でも兄上さまは苦しんでいらっしゃるのだ」
「恋はいきなり覚めることもあると聞きます」
「王族の恋は深すぎる。覚めることはないだろう」
「落ち着かれるまで、少し陛下に距離を置いていただいた方がいいでしょうか」
「よけい煽るだけかと」
「陛下も我慢できないと思われます」
狼たちは、数十年ぶりの王族の恋狂いに困惑していた。相談できる他の王族はもう誰もいないのだ。
「何か記録にないものですか?」
長官に視線が集中した。長官は、王族記録を全て読んでいた。古い記録から何かわかるかもしれない。狼たちの視線を集め、長官は語った。
「王族の歴史の中でも恋狂いの記録は少ないが、そのいずれもお相手が儚くなった時に、追うようにみまかられている」
狼たちはうつむいた。伴侶をなくした悲しみに、身体が堪えられないのだと。
「……しかし、ある王族の方が50以上も年下の方に発病した記録がある。その方の異能ゆえかわからぬが、お相手に合わせ身体の成長が止まり、いつまでもお若いまま記録的な長寿をまっとうされたという」
狼たちは息をのんだ。
もしかしたら、短命と言われている足弱の救いとなる病かもしれない。一筋の光明だった。
一進は挙手して発言した。
「……以前、陛下に恋をしたことがあるか?とたずねられたことがあります」
「ほう、してその時はどうされた?」
「若輩者ゆえ、申し訳ありません。経験不足をお詫び致しました。陛下は苦笑されてましたが、病とはいかぬまでも陛下も同じような痛みを感じていらっしゃるのでは?」
「両想いでいらっしゃるのなら、何も問題はないのではないか?」
「恋とはかように苦しむものなのか?」
「………」
狼たちは深く思考し、また言葉が途切れた。
「長官、恋を教えてください!」
狼たちの沈黙を破り、一進が叫ぶ。
「私は恋を知りません!陛下と兄上さまのお力になれない!長官なら経験豊富な知識がおありでしょう?」
「待ちなさい。今はそのような話をしている場合では…」
焦ったように、長官は一進をたしなめる。
「そうだ!陛下と兄上さまのために、ぜひとも長官の恋ばなを!」
「長官、初恋っていつでした?」
「告白はどちらから?」
しかし狼たちは、ここぞとばかりに一進の言葉にのった。
命は、自分に話がふられないよう、気配を消した。これこそ王族たちに自分の存在を気取られずお護りするためあみだした命の特技である。
(長官、お助けできず申し訳ありません)
命は心で詫びた。
狼たちが長官に奥方がいない事実に思い至るまで、議題の核はしばし長官の恋ばなに集中した。
結論として、兄上さまのお気持ちを、そのまま陛下にお伝えした方がいいということになった。足弱が想うように、今世王も足弱を想っているはず。対話の時間が何より大事。
「言葉にしなければ、何も始まらないのですよ」
会議の最中、誰かがこぼした言葉が採択された。
命は足弱の元に戻り、どうぞ陛下とお話くださいと懇願した。
「レシェイヌは、おれが重いと思わないだろうか…」
足弱はずっとそれを気にしていたが、最後はうなずいた。
命からの連絡を受け、一進も動いた。
一進は最初、足弱の病を聞いて喜んでしまった。我慢を強いる陛下の憂鬱が軽減されるのではと思った。しかし、王族の恋は、時に命も危うくするほど激しく強い。足弱の苦しみように、一進は自分を責めた。二人が幸せでなければ意味がない。どちらかが犠牲になってはいけない。
今世王が、落ち着いて行動してくれることを祈りながら口を開く。
「陛下、兄上さまが、お話があるそうです。兄上さまのために、どうか落ち着いて最後までお話を聞いていただけませんか」
「兄上に何かあったのか?すぐに申せ。一進!」
今世王が、キッと一進を睨み付けた。
冷静なる対話なんて無理ではなかろうかと思いながら、一進は低頭して続けた。
「聡明なる陛下。兄上さまは胸を痛めておいでです」
一呼吸置いて、続ける。
「兄上さまは、陛下への恋をわずらっておられます」
「……………」
今世王からの返答はなかった。俊足で足弱の元に駆けつけるであろうと考えていた一進の予想が外れた。
「陛下?」
恐る恐る顔を上げると、信じられないというように目を見開いた王が、膝から崩れ落ちた。
ぶつぶつとその場で祈りの言葉を口にし、拳を床に何度か打ち付けると、いつもと変わらぬ顔つきに戻り、「兄上の元へ行く」と言って立ち上がった。その手はかすかに震えていた。
「兄上、レシェイヌがやって参りました」
足弱は、自室の居間で王を出迎えた。椅子をすすめ、足弱も隣に座った。
「レシェ来てくれてうれしい。手紙を書こうかと思ったけど、やっぱり直接言うべきだと思った。聞いてくれ、レシェ。お願いだから最後まで全部聞いてほしい」
今世王は「はい」とうなずいた。何を言われても全て受け入れる覚悟できた。心を乱さぬよう何度も王は自分に言い聞かせた。
「おれにはこの想いがなんなのかよくわからない。レシェは、老人ともホンさんセイエさんともワンさんとも、もちろん命さんの好きとも違う。レシェだけが特別なんだ。レシェと離れていると胸が詰まって苦しい。ずっとレシェのことばかり考えている。触れたい。抱き締めてほしい、一緒にいたい。声が聞きたい。……いつも…何回も中でレシェが出すとお腹が裂けてしまうんじゃないかって恐くなる。だから、嫌だやめてって口に出してしまうけど、ほんとにやめてほしいわけじゃなくて。それにやめてって言ってもやめてくれないし……たまにレシェがこわい顔して、すごく激しくする時もあるけど、そういう時も嫌って言ってしまうけれど、そんなに嫌じゃないから。たまになら、激しくてもいい。あと、もう少しだけ腰を支えてくれたらいいと思う。レシェを抱きしめたいのに、力が入らなくなって、先に寝てしまってごめんなさい。朝、レシェがいないと寂しい。隣が冷たくて、随分早くに帰ってしまったんだなと思うと寂しい。たまに一緒に目が覚めると、ちょっと恥ずかしいけど嬉しくて。あの…寝てるおれに口づけするの、本当は気がついてた。寝てるふりしてた。ああ、楽器を教えてくれるとき、後ろから被さって手を添えてくれるのも胸が高鳴って静まらなくて。お仕事してるレシェはとても素敵だから、たまに見に行ってもいいかな?邪魔しないよう気をつける。あ、ダメならいいんだ。……恋は好きより深いものだって聞いた……たぶん、おれは、レシェに恋してるんだと思う。すごく深く好きだ。だから、レシェがいつも言ってくるあの、舐めてもいい?っていうの、大事なレシェにそんなことさせられないけど、どうしてもしたいっていうなら、おれもレシェのそこに口つけてもい…」
足弱の話を遮るように、パァンと何か打ち付けられる音が響いた。
「……レシェ?……レシェ!誰か!誰か来てください!レシェが」
足弱の叫び声に反応し、すぐに侍従たちが飛び込むと、王は頬を押さえてうずくまっていた。
「陛下!」
「レシェが、自分の頬をパァンってぶって……おれの、せい?」
足弱は泣きそうになっている。
「兄上、そんなことありません!」
顔をあげた王から、鼻血が吹き出した。
「だめです!陛下、下を向いてください!」
「これは夢なのか!?一進、余を殴れ」
「できません!」
王を介抱しながら一進が叫ぶ。
「レシェが、死んじゃう…」
「大丈夫です。兄上さま。落ち着いてください。泣かないで」
命が、真っ青で震えている足弱をなだめる。
「嫌だ。レシェが死んだらおれも死ぬ!」
「兄上!わたしは死にません!一進どけ」
頬を腫らし鼻に詰め物を入れながら、王は侍従たちを押し退け、足弱を胸の中に抱き込んだ。
「わかりました。もう全部兄上のお気持ちは伝わりましたから」
「レシェイヌ、おれ、重くないかな。嫌いになった?」
不安で揺れる黒い瞳に、金色の王は微笑んだ。
「よけいラフォスエヌのことが大好きになりました」
「レシェイヌ、かっこいい……」
頬を腫らして鼻に白い詰め物をしている王の姿は、どう見ても滑稽にしか見えないが、どうやらもうお互いしか見えていない。狼たちは、控えの間に下がって行った。
「レシェのこと、好きすぎてこわい」
「わたしの方が、もっと兄上のこと好きですよ」
「いや、おれの方がきっともっとだ」
「ふふ、では、もっと恐くなってしまいますね」
「それは……レシェが、恐いのも痛いのも治してくれるんだろう?」
そう言って笑う足弱に、王は深く唇を重ねた。
「あの兄上、さきほどお口でしてくださるっておっしゃいましたよね」
「ううっ……レシェが好きなことなら…おれも、好きに…なる。初めてだから、ちょっと恐いな」
恥ずかしそうに黒い濡れた瞳で足弱が見つめてくる。今世王の理性は、もうぶち切れ寸前だ。
「っ…そのような、お可愛らしいことをおっしゃると、もう、兄上をレシェの寝台に繋いでしまいますよ!」
「それは……」
口ごもる足弱に『冗談です』と王が続けようと口を開く前に、足弱は笑いながら言った。
「レシェは、縛るのが好きなのか?繋がなくても逃げないけど、レシェが縛りたいなら。…うん、そうだな……いつか、歩けなくなってしまったら、レシェの寝台をおれが占領してしまおうかな」
今世王は、自らの腫れている頬を強くつねる。
「レシェ何をやってるんだ!ああ!また鼻から血が!誰か来てください!」
侍従たちは、今度は聞こえないふりをした。二人の幸せが狼たちの幸せ。
しかし、部屋に入れない理由はそれだけではない。
数十年ぶりの王族の恋に当てられ、命以外の全員が、常に被っていた心を隠す仮面を壊していた。赤面した顔を足弱に見せるわけにはいかない。
恐ろしきは庶子…ではなく、恐ろしきはラフォスエヌであった。
恋騒動の事後報告を待ちながら、長官はつぶやく。
「私の恋ばななんて、話せるわけがない」
思い返せば赤面するようなものばかり。とくに初恋など口に出すのも面映ゆい。
「さて、ラフォスエヌ殿下はいかがかな」
相手が今世王であるなら、きっと幸せな恋ばなになるだろうことを、長官は疑わなかった。