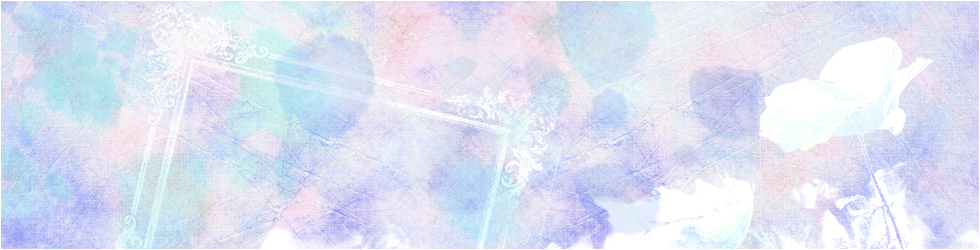
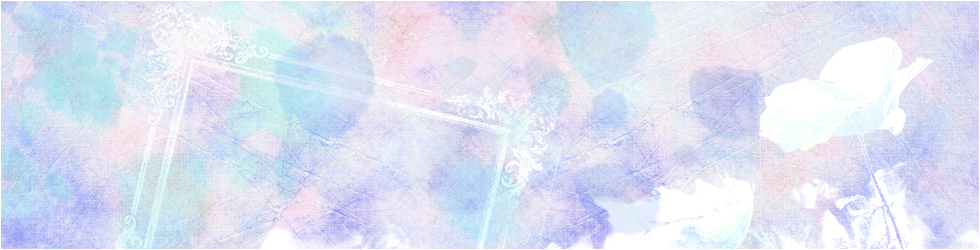
「レシェイヌ、お願いがあるんだけど」
夕餉の席で、足弱は隣に座る今世王に切り出した。
「何ですか?」
「今夜は、一人にしてほしい」
「レシェが訪ねるのがお嫌ですか?」
「違っ…そういうことじゃなくて……」
足弱は慌てて否定するが、その先の言葉が続かない。
「わかりました。大切な兄上のおねだりですから、レシェは一人寂しく朝を迎えることにします」
わざと拗ねてみせ、それでも許してくれる優しい弟に、足弱は微笑んだ。
「ありがとう」
今夜は嵐になるだろうことに、経験から足弱は気づいていた。
「命さん、今夜は早めに寝ることにします。なので控えている皆さんも付いていてくださらなくて結構です」
「兄上さま。我々はいつもお側におります。けしてお邪魔はいたしませんので、お気になさいませんように」
思ったとおりの返答に、足弱はそれ以上何も言わなかった。
狼たちを遠ざけることなどできはしない。強く言えば不信に思われるだけだ。
いつもと同じように、足弱は寝台に横たわる。
寝室から侍従たちが下がって行くけれど、控えの間でずっと誰かが付いていてくれている。
足弱に少しでも変わったことがあれば、すぐに飛んでくることだろう。
一人になれる時間の方が少ない。そんな毎日に慣れてしまっているけれど……。
強く、そして優しすぎる狼たち。彼らに気づかれないように、体を丸め頭から掛布を被る。
息を整える。アレがくる。
「……」
声を漏らさぬように、大丈夫、大丈夫だからと言い聞かせる。
右足が………軋む。
天気が急変するこんな夜は、足が痛んで何もできない。
薬も効かない。ただ堪えるしかない。
こんな姿を、見せたくなかった。あの優しい人たちが、足弱の足が不自由なことを自分たちのせいだと責めているのを知っている。
(ああ、痛い痛い痛い)
締め付けられるような痛みが収まらない。
「兄上さま、おやすみでいらっしゃいますか?」
不意に侍従長に声をかけられて、びくりと反応してしまった。起きていることがバレてしまった。
無言で、そのまま布を被り続ける。
「兄上さま。他には誰もおりません。命一人でございます。警護の者も少し遠くにやりました」
静かに、命は足弱に語りかける。
「兄上さまの痛みを、この命にもどうか分けてくださいませんか?」
「!!」
見透かされていた。
「どうか兄上さま。陛下にも他の者にも申しません。命ただひとりの胸のうちに留めます」
この老年の侍従に、隠し通すことなど最初からできはしないのだ。
足弱は、籠っていた布から顔を出した。痛みのせいなのか布を被っていたせいなのか、額から汗が流れる。
「このことは……みんなには……」
「兄上さまのお心のままに」
また強くなってきた痛みに、足弱は顔をしかめる。
命は、固く絞った布で足弱の汗を拭っていく。
「薬をお持ちしましょうか?」
足弱は首を横にふった。もうこうなっては何をしても痛みは取れない。
「失礼いたします。お嫌でしたらおっしゃってください」
命は足弱の痛んでいるであろう箇所に手を当て、撫で擦った。
「う…うう…」
ほんの少しだけ、痛みが和らいだ気がした。
痛みはいつも強くなったり弱くなったりしながら足弱を朝まで責め立てる。
「命さん…もう大丈夫です…」
「どうかこのまま、命にお任せくださいませ。お願いいたします」
「でも……」
(…朝までかかってしまうかもしれないのに)
「おつきあいさせてくださいませ。ぜひ」
口にしなかった心を、命に読まれた。
収まりつつあった痛みがまた増してきて、足弱は呻いた。
命は何も言わずに、足弱の痛みに寄り添った。
今までずっと一人きりで堪えてきた痛み。
やはり痛くて泣きたくなるけれど、今夜は朝がくる前に眠れそうな気がする。
温かな手のひらが心地よい。
そうして思い至った。
古傷を持つ者は足弱だけではない。
天気痛とも呼ばれる体調不良を、狼たちが知らないわけがない。
あの聡明な弟が、やけにあっさり身を引いたのは、足弱の心を尊重してのことではなかったか。
気づいていて、気づいてないふりをしてくれる。どこまでも優しい人たち。
「ありがとう…ございます……」
痛みではなく別の感情で泣きたくなる。
命は微笑み、足弱が眠りに落ちるまで、足弱の痛みに手をかざし続けた。
今世王も、今夜は眠れないでいるだろう。
嵐の夜。
早く去れと誰もが祈る夜の一幕