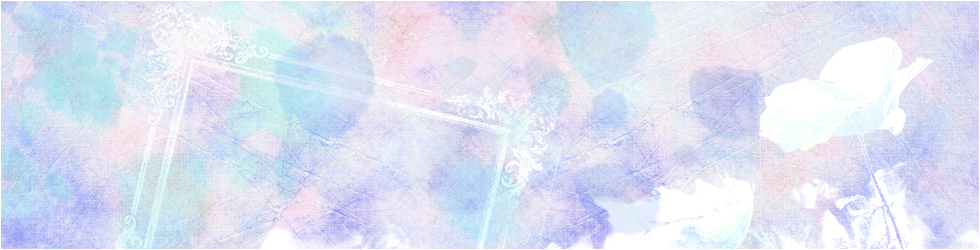
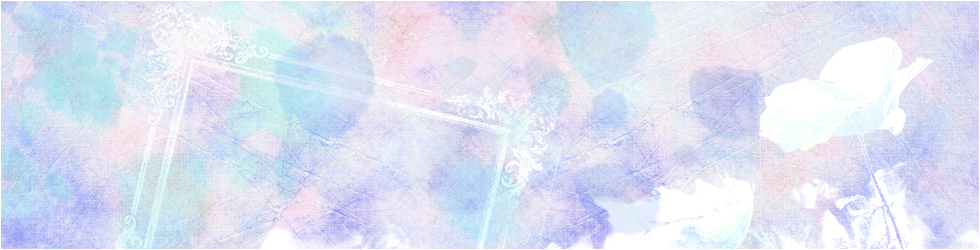
いつだったか、一人でいるときに、足弱は銀色の鳥に遇った。
鳥は、じっと足弱を見ていた。足弱も、じっと鳥を見ていた。
いつものようにまぐわい、何も変わったことなどない日常の中で、その日は何かが違っていた。
柔らかな寝台に指ひとつ動かせないほど消耗して横たわる足弱を清めるために、抱き起こそうとした王の手を掴み、足弱は自分の方へと引き寄せた。
「……もっと……ほし……」
珍しいことだった。
王族よりもずっと体力のない足弱に、いつも今世王は自重するべしと自分を戒めていたのだから。
それが求められている。
断る理由がどこにあろうか。
汗と体液で濡れる足弱を、王は愛情こめて抱き締めた。手を這わす。
「……はあっ…ああっ……」
熱い声が、寝台を満たしていく……。
翌日、朝まで愛を交わしていた王は上機嫌で執務をこなしていた。
時折思い出しては、ほうっと息をついて幸せそうな顔をする。
侍従たちも満足そうに笑みをかわす。二人が仲睦まじくあらせられることこそ望み。たった二人きりの王族に、全てを捧げお仕えしていた。
(今ごろ、兄上は寝台で足腰立たずに寝かされている頃だろうか)
夕餉にも起きられそうもないなら、寝室に食事を運ばせ一緒にとろうか、そう今世王は思いを巡らせていた。
「兄上はどうなさっている?」
執務の合間に一進にたずねた。
「体調もよく。起き上がられて、少しお食事を召し上がられたようです。そして…」
一進が一呼吸置いた。
「どうした?」
今世王は、侍従長に先を促す。
「今宵もお訪ねいただきたい、と」
「…………」
王は息を飲んだ。
足弱からの誘いはたまにあるものの、連続でまぐわうことはめったにない。
昨夜の、強く自分を求める足弱の姿を思い返し、何かが心にかかった。
「今から行く」
政務の残りを瞬く間に片付け、足弱の部屋へと駆け付けた。
「兄上?」
王が現れると、足弱は一瞬輝くような笑みを浮かべたが、まだ日が高いことに困惑し笑みを消した。
「執務は……」
「今日はもう終わりました」
「そうか……」
「身体に辛いところはございませんか?」
「いや、大丈夫だ」
他愛ない会話、けれど足弱は頬が少し赤い。
「兄上?」
今世王は手を伸ばし、足弱の額に触れた。
「少し熱くありませんか?医者を呼びましょう」
「いや。いい……違う……そうじゃ…なくて……」
足弱は、言葉にできない何かを抱えているようにみえた。
「あなたのレシェに、お心うちを教えていただけませんか?」
「…………………」
足弱は無言で手を伸ばし、目の前の王にくちづけると、両手で強く愛する王を抱き締めた。
「………………ほしい」
王にだけ聞こえるような、微かな声で白状した。
「よろこんで」
王は足弱を抱き上げると、絹の寝台へとその身を横たえた。
それから数日、足弱は意識のあるうちは今世王を求めた。
微笑ましく見守っていた侍従たちも、だんだんと不安の種が芽生えてきた。
食事も摂っているし、健康面も問題なしと医者は言っている。
何より王が、喜んでいる。
昼も夜もなく、足弱の熱い息が寝室を満たしていた。
王は足弱が求めるだけ応じた。執務は代行をたてた。傍にいられることが何より嬉しかった。
足弱の山で、見たこともない果実が実ったと報告があがった。金色に輝く、柔らかく甘い果実だった。
空には彩雲が頻繁にみられ、美しい音楽を耳にした者もいた。
それも半月を数える頃、事態は動き出した。
最初は小さなものだった。
足弱の、いつもの食事の量が減った。
ほとんど食べられなくなり、少しの果実のみ食べた。やつれはしても痩せてはいない。
そして、足弱の心が不安定に揺れ始めた。
「レシェ……レシェ…」
すがり付いて泣く。
夢を見たと、足弱は言った。
「どんな夢ですか?」と聞いても忘れたと言ってけして答えなかった。
足弱は、夢をみた。
10の太陽が頭上を回り、そのうち1つが降りてきた。
熱く、眩しく全身が焼かれる夢をみた。
目を覚ますと、まだ体の中が熱いような気がする。
「…熱い…?」
足弱の呟きは連日の疲れであると判断された。
濃密な期間はゆっくりと終わっていった。
次に、足弱は眠りを欲した。
昼も夜も眠り続ける。
今世王が訪ねてきていても、意識を保つのが難しいようだ。
何かの病なのだろうか?巻雲には皆目見当がつかなかった。
少し体温が高いだけで、健康のようにみえる。
意識が戻る度にオマエ草を煎じるものの一向に回復しない。
王は眠る足弱の手を握り、ずっと呼びかけていた。
「兄上、目を開けてください。レシェがここにいますよ」
その声が聞こえているのか、足弱は呼びかけられるごとに目を開けるけれど、ぼうっとしたまま会話もできない。
「巻雲さま。少しよろしいですか?」
女官長の憧れは、眉根を寄せて難しく考え込んでいる巻雲に声をかけた。
「兄上さまの症状に、ひとつ心当たりがあるのですが」
「何だ?」
藁にもすがる思いで、巻雲は憧れの言葉を聞いた。
「<眠りつわり>というものがございます」
巻雲は耳を疑った。今憧れは何と言ったか?
「そのような病は…」
「病ではありません。眠りつわりは妊娠中にまれに出る症状の1つです」
巻雲は驚愕に目を見開くと、すぐに足弱の寝室に駆けつけた。
看病を続ける今世王に、今すぐにもう一度診察させていただきたいと懇願し、許された。
震える手で、足弱の脈をとり心拍を確認し下腹部を触診する。
微かな波動も見逃してはならない。汗が流れ落ちる。
「ああ……」
巻雲はうめく。思い至らなかった自分を責めた。
「兄上はどうされたのだ?」
憔悴している主に、平伏して答えた。
「ご懐妊にございます」
「……………まことか?」
今世王の声が震えている。
「間違いなく。兄上さまはご懐妊されています。この症状はつわりの一種であり発生時期からみましてもそろそろ安定される頃と推察されます」
側仕えの狼たちが慌ただしい動きをみせるのを、今世王は制した。
「待て!」
(待ってくれ。まだ兄上と話をしていない)
巻雲と侍従たちは、兄弟を二人きりにするべく速やかに退出した。
「兄上。ラフォス…」
今世王が話しかけると、足弱は薄く目を開けた。
とめどなく涙を流す愛する弟の姿に、足弱は急激に覚醒した。
「どうしたんだ?レシェ。なんで泣いてる?」
「兄上。ラフォス……ラフォス……」
荒れ狂う感情に胸をしめつけられながら、今世王は兄に告げた。
「兄上は…身ごもられておいでです」
「………」
足弱は、取り乱すことなく今世王の言葉を聞いた
自分の身に何か起こっているか、確信はなくとも予想はしていた。
ずっと夢うつつのまま考えていた。
もしもそうなら、この身に命が宿っているのなら……。
「レシェイヌ…こども産んでもいいかな?」
子は、お互いが欲しなければできないと聞いていた。
ではこれは、今世王が望んだことなのだろう。
そして、足弱も望んだことなのだろう。
もしも足弱が先に命を落としても、王を独りにしないですむ。
その時は、家族が王を支えるだろう。
(けれど、怖い)
出産には、危険がつきものだとも聞いている。
女性でも大変なのに、足弱は男だ。どうなるかわからない。
「産んでもいいかな?」
泣き続ける弟に、もう一度尋ねた。
「ぜ、絶対に……」
今世王は、泣きじゃくりながら足弱を抱き締めた。
「…わたしを一人にしないで…ラフォス…」
「うん」
死という言葉を使うのを避けた。
「無事で……」
「うん」
「……産んでください」
「うん」
震える弟の頭を、落ち着くまでずっと撫でていた。
戸口で控えていた狼たちが、全員声を殺して泣いていた
喜びと怖れと不安と希望と、未来に。
懐妊の報告を受け、灰色狼は音を立てて立ち上がった。
勢いのあまり卓に置いてあった茶器が落ちて割れたがそんなこと気にも止めず、すぐに王のもとへと駆けつけた。
足弱の部屋から出て自室に戻ってきたばかりの王に、ひざまづいた。
「聞いたか狼。兄上がご懐妊あそばされた」
その声は、喜びとは遠いところにあった。
「兄上は、一人でお苦しみだったのだな……」
長官は、慎重に言葉を探した。
「お喜び申し上げます」
「狼!兄上は苦しんでおいでなのだぞ!」
「兄上さまに、陛下に、新しき御子さまに、まことにおめでとうございます」
今世王の不安もわかった上での祝辞であった。
飲み込まれてはならない。悪き言葉は悲劇をつれてくる。
王は長官を睨み付けていた目をそらした。
荒れ狂う心を静め、ただ足弱のことを想う。
「兄上を、お助けしてくれ」
命令ではなく助けてくれと。頼む、と。
王族の中の王族、今世王と呼ばれる男が誰にも見せない弱さをみせた。
長官は目を伏せ、深くぬかずいた。
狼たちの緊急会議が開かれた。
事の重大さは、誰もが最悪の想像をぬぐい去ることが困難なものであった。
「もし兄上さまの身に何かあったら…」
「女人でなければ堪えられぬ痛みであると」
ざわざわと騒ぎ立てるだけで、話が進まない。
長官がたしなめようとした時、一瞬早く憧れが一喝した。
「いい加減になさいませ皆さま!陛下と兄上さまのお決めになったことですよ!」
シンと場が静まり返った。
そう、われわれは狼。王族に身命を捧げた一族。
「王族方の幸福を守るためだけに我らはある」
長官が言葉をついだ。
会議のあと、長官は憧れを呼び寄せたずねてみた。
「ところで、出産の痛みというのは、どれほどの……その……」
「個人差がありますので一概には言えませんが。腰を金槌で砕かれた後に、鼻から西瓜が出てくるようなものです」
「ひっ…」
長官は、思わず卓の上の茶器を取り落して割った。
このところずっとぼやっとしていた頭がはっきりしてきた。
自分と今世王の御子。誰もが望んでいた未来が現実のものになったのだ。
「兄上さま、お水はいかがですか?果物をお持ちしましたよ」
足弱付侍従長の命は、さらに甲斐甲斐しく足弱の世話にいそしんだ。
「少し外をお歩きになりませんか?」
「命さん、ありがとう」
食事の最中でも突然睡魔に襲われ意識を失う足弱を、一時たりとも目を離すことができない
命は眠り続ける足弱を、誰よりも優しく見つめる。
新しき王族の誕生。あきらめていた希望が今目の前にある。なんという奇跡。
先日の会議で、憧れが言っていた言葉を思い出す。
「陛下と兄上さまが起こされた奇跡に、何を不安がることがありましょう。望まれ祝福された御子さまがご無事で誕生されることを疑うなどという醜態、恥ずかしゅうございます」
命を育む女人の、憧れの強さに、数十年の経験を持つ侍従長も圧倒された。
産後の手配は、すべて憧れに任された。
乳母に産着に清潔な部屋とたくさんの布。忙しそうに指示を出す憧れは、必ず毎日足弱の元にも顔を出し、話し相手になっていた。
注意点、心構えと、必ず楽しい話をしていく。
「とうとう長官が3つ目の茶器を割りまして、水明に怒られてましたのよ」
「それは、少し見てみたかったな」
気分が塞ぐことのないように、明るく楽しい話を兄上さまに。
そんな気遣いが、足弱は気恥ずかしくも嬉しかった。
憧れだけではない。今世王も長官も巻雲も、緑園殿にいる全ての狼たちが足弱に会いたがるので、命は足弱に無理をかけないよう采配するのに苦労した。
足弱の起きている時間が、少しずつ元に戻った。産み月が近い。
たまに足弱がゆっくりと池の回りを散策したりする時は、必ず今世王が寄り添った。
「ひとりで大丈夫だ」と足弱は主張するけれど、今世王が側を離れることはなかった。
王が足弱に話しかけるたび、足弱は幸せそうに微笑む。
そんな二人の姿を見かける度に、狼たちは喜びに震えていた。
この光景を忘れてはならない。一生の支えとして心に刻み付けておこう、と。
足弱懐妊の知らせは外には公布してはいなかったが、噂は風が全土に運び伝えていた。
城にも連日祝いの使者が詰めかけ、対応に追われていた。
皆が喜びに身を震わせながら、1つの懸念をいだいていた。
(どうぞご無事で……)
前例のない事態に、臣民の緊張が増していく。
(どうぞご無事で……)
「……あっ」
足弱は、腹がもぞりと動くのを感じた。
なんとも形容しがたい感覚に、腹を抑え前屈みに倒れた。
常に側に控えていた巻雲がすぐに支え、足弱を寝台に横たえる。
バタバタと人の動く気配を感じながら、全身から汗が吹き出し震えている自分を自覚したその時、体が跳ねるほどの激痛に襲われた。
「!!」
声にならない。
全身がバラバラに砕けそうだ。痛みが強弱をともなって次々とやってくる。
(痛い!痛い痛い痛い!!)
こんな痛みは知らない!
強く敷布を握りしめた手を、誰かが掴んだ。
「兄上!兄上!」
必死な今世王の声を耳にし、固く瞑っていた目を開けた。
激痛に歯が砕けそうなほど食い縛りながら、それでも見た。今にも死んでしまいそうなほど青ざめた愛する弟の顔を。
「あぁあああああああああぁーー!」
口を開けば悲鳴しか出てこない。
「兄上さま息を吸って吐いてください。兄上さま!」
巻雲の言う通り、大きく吸って吐いた。
ほんの少しだけ楽になったような気がした。しかし痛みはさらに増していく。叫びすぎて息が吸えない
(苦しい!)
握られている手に、足弱は指が折れそうなほどの力でしがみついた。
「ラフォス!」
何も考えられない痛みのなかで、今世王の声だけが届いた。
(このまま自分が命を落としたらレシェイヌはどうなる?絶対にここで死ぬことはできない。レシェイヌを残して逝くことはできない。絶対に!!)
「あ”あああああーーーーー!」
足弱は自分の叫びに交じって、鳥の声を聴いたような気がした。
つかの間の静寂の後、産声が部屋の中から聞こえた。
外で待機していた全ての狼たちは、固唾を飲んで一報を待っていた。
扉が開かれ、中からフラフラと侍従の一人が現れた。
「兄上さま、王子さまともにご無事です!!」
歓声が、喜びの絶叫が広がっていく。
泣いていない者は、一人もいなかった。
「兄上…」
今世王は足弱にしがみつかれて痣ができていた手で、疲れはてて眠る足弱の顔を撫でる。
産まれた王子は憧れにたくし、二人きりにしてもらった。
「兄上…ラフォス……」
足弱の頬に目に額に口づける。
「……レ、シェ…」
目を覚ました足弱は、掠れた声で今世王の名をを呼ぶ。
すっかり喉がおかしくなってしまったようだ。
今世王は、最愛の兄に口移しで水を飲ませた。
そのまま何度か唇を重ねて、兄を強く抱きしめた。
「ラフォス…よかった……無事で……」
やがて今世王は落ち着きを取り戻し、真剣な面持ちで足弱に言った。
「王子にお会いになる前にどうしても確認しておきたいのですが」
「なに?」
「兄上に最も愛されているのは、このレシェイヌですよね」
(何を言い出すんだこの王は)
足弱は目を丸くして、目の前の夫を見つめた。
「きちんと口に出して誓ってください。一番だって」
いろいろ心配をかけてしまった今世王への謝罪もかねて、微笑みながら待ち望まれている言葉を口にする。
「レシェイヌ愛してる。誰よりも、一番、愛してるよ」
御子は、黄金の髪に青い瞳の王子であった。
王族特有の美しき容姿に、力強さを感じる。
王子が豪奢な産着にくるまれて足弱の元に連れてこられた時、あまりの愛らしさに足弱は心を奪われそうになったが、傍らの今世王がくっと唇を噛みしめたことに気づき平静を装った。
「レシェもこんな感じだったのかな」
「そうですね。私の方が愛らしかったと思いますが。ところで兄上、王子はお手元に置いてお育てになりますか?」
足弱は言葉につまる。
愛しい我が子ではあると思うけれど、それとこれとはまた違うというか。
もう足弱にこれ以上余裕はない。今世王の相手だけで精一杯だ。
「あの…おれは子育てとかよくわからないし、おまかせ…したいです」
平伏していた狼たちに向き直り、王は命じる。
「兄上のおっしゃるとおり、王子はそなたらに任せる」
狼の長は、歓喜にうち震え拝命した。
その後、今世王は王子の側仕えに任命された者全てに厳命した。
「こころして聞け。我が王子をそなたらに託す。身命をとして仕えよ。そして日々、王子に<ラフォスエヌはこのレシェイヌのものである>ことを言い聞かせよ。厳命である」
以前「血族の恋敵には正々堂々戦おう」とか言ってなかったか?と狼たちの心を微かによぎったが、皆慎んで拝命した。
数日ののち、足弱は命をそば近くに呼んで、赤子をさしだした。
「抱いてあげてください」
侍従長は、おそれおおいことと平伏して後ずさった。
「命さんに、抱いてもらいたいんです」
誰よりも足弱の側にいて、誰よりも心を砕いていた侍従長を足弱は知っていた。
心の乱れを微塵も見せずに、静かに付き従ってくれた。
「命さんがいてくれたからこの子は産まれてこれたような気がします。いつも助けてくれてありがとう」
命は、恐る恐る輝く王子に手を伸ばす。
震える手で、けれど力強くしっかりと受け取った。赤子の重みを、両手に感じる。
見送った王族たちの過去の姿がよぎった。
「ああ…なんと……」
これ以上の喜びがあるだろうか。
「もう、わたしには過ぎたる光栄に存じます。いつ天に召されても悔いはありません」
足弱は慌てて声をかけた。
「そんな困ります!命さんには次の時にもお願いしようと思っているんですから」
「は?」
つい口から出てしまった言葉に、足弱はうろたえ照れたような困ったような顔で白状した。
「まだ誰にも、レシェにも言ってはダメですよ」
あんなに大変な経験をしてもなお、足弱はその先をみていた。
「まだ…もう少し先の話になると思いますし」
「…はい」
命は誓いを立てる。
「その時も、いついかなる時も、この命、兄上さまのお側を離れません」
足弱は、黄金に輝くような笑みを浮かべた。
ああ、ラセイヌは、緑土なり―――――永遠に