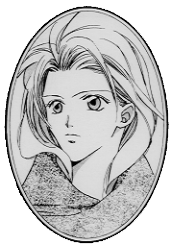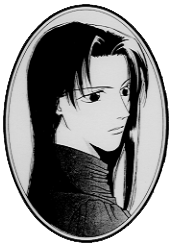マスカレードの長い夜
|
 |
 COPYRIGHT 集英社 |
マスカレードの長い夜 吉田 縁:著/桑原祐子:画 学都リプサリアで、 至高の神を描く聖像画家を目指し、 十年の沈黙の行を続ける少女ノーマ。 弟子入りを許されるまであと二ヶ月足らずと なったある日、ノーマは、神に似た容姿を持った学生、 フォルカ・アスカリナと出逢う。 その日以来、神に声を捧げた少女の心は 少しずつ揺らぎ始めた。一方フォルカも、 ノーマの祈る姿に心魅かれていき…。 ノーマとフォルカの聖なる愛を描く、中世ロマン! |
|||||||||||||
| 登場人物 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 冒頭部分だけ読めます↓ | ||||||||||||||
(プロローグ)(「マスカレードの長い夜」より抜粋) |
||||||||||||||