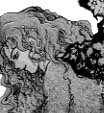プロローグ ――見つけたぞ……!
憎しみに満ちた声。虚ろな響き。
死霊たちは赤子を見ている。
泣き声も上げられないほど衰弱した赤ん坊を。
白い屍衣し いに包まれ、捨てられた赤子だ。
そこは修道院の門前であった。
赤子の頭上に十二対の手が伸びて、連れ去ろうとした。
死霊たちはうめく。
――それはおれの獲物だ。
――違う、私のさ。
――よこせ。
――何だ、化け物め。あたしがいただくんだ。
――わしのだ。わしがどんな目にあったか、こいつのせいで! こいつの犠牲になって!
――それはみんな同じなんだよ! みんな殺されたんじゃないか、こんなちっぽけなガキのために。
――こいつひとりを生かすために。身代わりになって。こいつのせいで!
――こいつを喰って生き返るんだ。
――おれが先だ!
――やめろ、やめろ、わしのものだ。
――引っ張るな、けだものめ。使いものにならなくなる。
――引き裂いて分けたらどうだ。
赤子はそれでも泣き声もたてられなかった。
――誰か来る! いやな奴だよ、まぶしい。
赤子を責め苛んでいたいくつかの手が動きを止めた。
――苦しい、近づけない。
死霊たちはうろたえる。
「この子はもういけないかも知れないね。だが手を尽くそう」
穏やかな声がした。
別の声が問いかける。
「ヴェネデット修道院長、嬰児みどりごに名前が必要です。いかがいたします」
「急がねばならない。名前も授けずに逝かせてはこの子が浮かばれない。そう……アドリアンと名づけよう、そして洗礼を」
朝の光の下で、赤子は新しい名と命を得た。
修道院の門の間際でヴェネデットは立ち止まり、灰褐色の双眸で虚空を睨んだ。
死霊たちは弾かれて霧散する。
――口惜しい。赤子が見えない。
――誰が守っておるんだ、あの赤子を。
――知らない、知るもんか。でも近づけないんだよ! 何も見えない!
――いつか必ず探し出す! ……そして殺す。
――いつかきっと……!
彼らはさまよい続ける――。 「あくまつき! あくまの子!」 子どもたちが騒いでいた。
「いたい! なにするんだ」
「だっておまえ、あくまの子だろう?」
「ちがう、ぼくはあくまなんかじゃない!」
「なぐっちゃえ」
甲高い子どもの声が中庭を騒がせていた。
修道院に付属する捨て子養育院だ。
「これ、これ、何をしておる」
老いた僧が仲裁に入った。
「修道院長様の御前で!」
ばらばらと子どもたちが散り、その中心にひとりの少年が残された。
他の子どもがみな褐色の髪と瞳をしているのに、彼だけはまばゆいような金の髪と瞳を持っていた。
老僧の横には三十を越えたばかりの修道院長が立っている。
「だってそいつ、あくまの子だもん」
「そうだ、そうだ、へんなこと言うんだ、そいつ」
ヴェネデット修道院長は、物静かな灰褐色の瞳で子どもたちを見回した。
「元気がありあまって、……なんとも」
老僧が狼狽して言った。
「元気なのは良いが――おまえ、大丈夫か。名前は何というのかね」
ヴェネデットはうずくまっている少年に話しかけた。
「……ぼく……アドリアン」
院長の表情がかすかに動いた。
「アドリアン? ……確かその名は」
「はい。院長様が名を授けなさった子どもです」
「ぼくはあくまじゃない!」
少年は金色の瞳をまっすぐに向けて訴えた。
「ほんとうにあそこにだれかいるんだ」
少年が指さした。
ヴェネデット修道院長はそれを視線で追った。
白い敷石の中庭の片隅だ。
ヴェネデットは瓶の陰にうずくまっている男を見た。他の者には見えない存在を。
「そら見ろ、うそつき、あくまつき」
別の子どもがまた騒いだ。
老僧があわててとりなした。
「これ、おまえたち。もう部屋に戻りなさい! 早く!」
ヴェネデット修道院長は視線を戻して金髪の少年を見た。
そして試すように問いかける。
「何がいるんだね」
「おとこのひと」
「瓶の模様がそう見えるだけでございましょう。子どもというものは想像力が豊かです」
老僧が言った。ヴェネデットが続ける。
「その男は何か言っているかね」
「いんちょうさまと話したいって言ってる」
「私と?」
「アドリアン!」と老僧がたしなめる。
「いいから、続けて」
「きてんしたい、って。そればかり。……きてん、ってなに?」
「――帰天(きてん)……!」
ヴェネデットが目を見張って言った。幼子の知る言葉ではない。
「それは、死んだ人の魂が天上の楽園に旅立つことだよ、アドリアン」
「死んだひと……! あのひと、死んでるの?」
「そうだ。だから他の者には見えないのだ」
人は死ぬと、生前の罪を悔い改め、魂の汚れを洗い落として天上へ旅立つと言われている。だが、悔い改めようもないほど罪深い魂は地獄に堕ち、心残りのあまり旅立てない魂はこの世にとどまっている。
「どうしてたびだちたいと言っているの?」
「死者にとってこの世は煉獄なのだから」
「院長様、……この少年は本当に何か憑いておるのでは?」
老僧の顔に不安な色がみえる。ヴェネデットは静かに首を振った。
「私とこの子ふたりだけにしてくれないか」
「……は……はい……かしこまりました」
老僧は遠巻きに見ている子どもたちを追い立てるようにして、養育院の中へと入った。
「ぼく、きてんさせてあげたいと思うけど、どうすればいいの」
「まず、死者は告解こっかいをしなければならない。自分のした悪いことをうちあけてあやまるんだ。そして地獄へいくか、この世でしばらくつぐないをするか、それとも帰天してよい魂なのか……裁きを受けなければならない」
「あのひとは、それをいんちょうさまに話したがっているんだね。どうしてぼくじゃだめなのかな」
「聴罪師ちょうざいしでなければ許されないのだよ。未熟な者たちが間違った裁きをしないように」
「ちょうざいし……」
「死者の告白を聞いて、帰天させるか、断罪するかを決める人だよ」
「ぼくはなれない?」
ヴェネデットは穏やかな目で少年を見つめた。
――この少年は、幼いながら……おそらく生まれながらにして聴罪師の資格を備えている。だが彼にはまだ加護が必要だ。あざとい死者に騙されてとりつかれてしまう危険があるから。
「おまえがかわりに聞いて私に教えてくれるかね」
「はい。……それでどうするか決めてあげるんだね」
アドリアンは死者の悩みをヴェネデットに伝えた。
ヴェネデットは静かにうなずき、瓶の後ろへ進んだ。
そして死者に話しかけた。
「よろしい。長い間ご苦労だった。修道士の道への志半ばで心残りだっただろうが、おまえは救われた。安心して逝くが良い。おまえに与えよう、永遠の安息をレクイエム センピテルナム」
ヴェネデットは死者に手を伸べた。
ふわり、と暖かい光が生まれた。
少年も真似をして、手を差し伸べて言った。
「えいえんのあんそくを」
突然少年の手の平から青い光が弾けた。
光に誘われて、死者の体が浮かんだ。
彼は帰天する。
永遠に苦しみのない天上の楽園へ――。
聴罪師――それは死者のことばを聞き、魂の汚れを落として癒す弔いびと。
そして罪深すぎる魂を断罪し、地獄へ落とすもの。
第一章 死霊(マネン)が来る 「なあんてちっぽけな村だよ、これじゃ大した稼ぎにもなりゃしない!」
馬車の中から女が叫んだ。馬を御していた少年が大儀そうに顔を動かして後ろを見た。馬車から三十近いと思われる女が顔を出した。彼女の豊かな赤褐色の巻き毛は無数の宝石をからめて無造作に束ねられていた。荒い語調でひとこと言ったきり、眼前に広がる畑をながめている。
「……カブか何かを植えつけてある」
馬をなだめながら御者の少年が的外れな答えをした。女は軽蔑したように鼻を鳴らした。
「誰もそんなこと聞いてやしないじゃないか、ダニエル。このぐうたらの役立たず!」
少年が屈辱をかみしめるように唇をかんだ。精悍な顔立ちをしてはいるが、体つきはまだどことなく頼りない。彼はたずなを巧妙にさばいた。
馬車の中から別のしわがれた声が聞こえた。
「ヴァルスネリア……ここに来ようと言ったのはあんたじゃないか」
「あたしが言ったんじゃない、この壺が言ったんだ!」
女はそう言うと、両手の平に小ぶりの壺をのせて目の高さにまで持ち上げた。釉薬を施した深紅の壺には粗布で蓋をして細い麻縄で固く縛ってある。ヴァルスネリアという女は、情熱的な大きな褐色の瞳やそれをふちどる長く濃いまつげといい厚い唇といい、全てがうるさいほどはっきりした顔立ちだ。よほど赤い色が好きなのか、壺ばかりか着ているものまで暗い赤の衣だ。壺を見つめた時、一瞬、女の目に恍惚とした表情が浮かんだが、老婆の声にすぐにかき消された。
「……だったら文句は壺に言えばいいだろ」
「しっ……! 壺が何か言ってる。……何、百姓のことがわかるのかい。あんまり金にならないことはしたくないが、退屈なのはもっと嫌いだよ。教えておくれ」
ヴァルスネリアが何かをあやすように言っている。老婆に向けられた言葉ではない。ひとりごとのようにも聞こえる。
しわがれた老婆の声が続いた。
「ダニエルを巻き添えにするんじゃないよ。ダニエルは馬のことはよく操れても、人に悪さなんかできないんだから」
「誰に向かって物を言ってるんだ。ろくに働きもしないで威張った口きくんじゃないよ。陰気くさい目でこっちを見ないでほしいね……おや、さっそく村人が来た。ちょっとからかってやろうじゃないか。ダニエル、人を集めるんだ!」
少年は無言で馬から下りると、腰のベルトにつけてあった革の鞘から角笛を出して吹き始めた。ヴァルスネリアも馬車を下りた。
朝の仕事に出てきた農夫が慌てて近づいてきた。
「何だあ、おまえたちは! わしの畑を踏み荒らす気じゃねえだろうな」
黄ばんだ膝丈のシャツをまくりあげて太股をむき出しにした農夫だ。ヴァルスネリアは彼の剣幕にいっこうにひるまず、なめるように農夫を見定めた。艶のある真っ赤な唇が官能的な笑みを作った。
「あんたは機嫌が悪いんだね。その理由を当ててやろうか」
彼女は含み笑いをし、農夫のあごをひとなでした。
「なっ、なんだあ、この女! おうい、みんな来い。よそから来たかささぎ女に植え付けたものを根こそぎ盗まれないうちにな」
農夫が大声をあげて仲間を呼んだ。かささぎ女、という言葉には侮蔑の響きがありありと見えていたが、ヴァルスネリアはかまわず話し続けた。
「あんたはなくしたんだ。銀の皿を。だが銀なんかじゃない。安っぽい木の皿にけちくさい鍍と銀ぎん(銀メッキ)をして体裁を整えただけのもんさ。それでも一家の宝物だ。このあたしの髪をごらんよ。あんたの探しているものは、あたしの髪を飾っている石粒の一個の値打ちもありゃしない。それでもあんたには大事、そういうことだね。あたしには何でもわかるさ」
ヴァルスネリアはそう言うと自分の髪から宝石のひとつを乱暴に引き離して農夫の目の前につきつけた。
農夫がぽかんと石を見た。
「おや、目を開けたまま眠っちまったのかい? だんな」
「どうした、何の騒ぎだ」
後から来た男たちが言った。
「うるさいねえ、おだまりよ。あたしがこのだんなのためになることを教えてやろうと言ってるんだよ、なくし物は木の根本さ。隣の家のさ。悪ガキが盗んで隠したんだよ。思いっきりひっぱたいて性根を直してやったほうがいいよ」
農夫が目を女に釘づけにしたまま口を開いたり閉じたりしていた。
「さあ早く行って確かめておいでよ。あたしの言ったことが本当か嘘かをさ!」
ヴァルスネリアが農夫の肩をこづいた。農夫は我に返って、一目散にかけ出した。ヴァルスネリアが高笑いをした。豊満な胸の前で腕を組んで、挑戦的な目で集まった村人をねめまわした。
「何だよ、ただでは占ってやらないよ」
「おまえは何だ」
別の男が言った。
「あたしかい? あたしは占い師のヴァルスネリアだよ。なくし物でもぴたりと当てるし、おまえの未来もお見通しだ。だが無駄な骨折りは大嫌いさ。貧乏人なんか相手じゃない。さっきのはお近づきのしるしだ。居酒屋でちょっと休んでさようならだ。まあこの村では仕事する気にならないからねえ。遊びにはつきあうよ、いつでもござれ!」
張りのある声で口上を終えて彼女は深紅の壺を高く掲げた。
「そこのあごひげのおじさん。あんた心配してるんだろう。かわいい女房が浮気っぽいんで、仕事も手につかないのさ。今もそら、女房がなくした角灯のことを聞きたくても聞けないでうずうずしてるんだよ。どこかよその男の枕元から出て来ちゃ大変だものねえ」
女占い師は耳障りな甲高い声で笑った。周りの者がいっせいにあごひげの男を見た。彼は苦々しい顔つきをしていた。
「なんという女だ! でたらめを言うでねえ」
「そうだ、なあ、ヤソンよ。的外れなことだろうさ」
村人たちがたたみかけるように言うが、かまわず女占い師は続けた。
「あんた、そら、近頃町へ出て帰らなかった日があっただろう? 思い当たるだろ? 角灯なんてものは、夜出歩く時に持つものだ。それを持って出てどこかに置き忘れるなんてさ、帰る頃には明るくなってたってことじゃないのかい」
あごひげの男は頭を両手で抱えて叫んだ。
「嘘だ! 嘘だ! ……だが本当に角灯がひとつ、この頃見あたらねえだ。だがサマサも慌てた様子もねえし、きかねえでおいたんだ」
周りがざわついた。
「どこだ! 教えてくれ。角灯はどこにあるんだ」
あごひげの男が懇願するように言った。
「ふうん……サマサってんだ、あんたのかわいい女房は。ただじゃ教えないって言ったろう?」
「礼は、する。教えてくれ」
「まあ、いいか。その言葉を忘れるんじゃないよ。ついて来なよ」
ヴァルスネリアは上機嫌で言った。
「ヴァルスネリア。どこ、……どこへ行くんだね」
馬車の中から老婆のとぎれがちな声が聞こえた。
「先に居酒屋へお行き……ダニエル、おまえもだよ。さあ行くんだ」
彼女はカブが植わっているらしい畑と家畜小屋の間の細い道を通り抜けた。戸惑いながらも十人ばかり村人たちがその後をついて歩いた。
畑を通り過ぎて木立の中を行くと、あばら屋がぽつんとたっていた。小さな明かり取りの窓から、規則正しい音が聞こえた。木の棒をつき合わせるような、乾いた軽い音だ。誰かが機織りをしているのだろう。
華やかな深紅の装束のヴァルスネリアを先頭に、男たちが取り巻きのようについている。
「ここさ。このぼろ屋にあるはずだ。これはおもしろそうだ。誰か呼び出しな」
あごひげの亭主は、蒼白な顔をして突っ立っていた。
「そら、ご亭主! ヤソンとか言ったっけ。とっととケリつけるんだ」
ヴァルスネリアが声高に言った。男はうなだれている。衝撃と恐怖で一歩も動けないというふうだ。周りの男たちは互いに顔を見合わせ、厄介な仕事をおしつけあっていた。
「わしらはつきあいがねえ。そこの親子とはな。よしたがええ、鉄細工師なんでな、その家には斧やら刃物やらがたんとある。怒らせたら物騒じゃ」
「おい、誰か、司祭様を呼んでこい」
あやしい雲行きを心配して村人のひとりが小声で言った。だがすぐにそれは否定される。
「だめだ、だめだ。あんな新米の司祭ではことが収められまい!」
「そうさなあ。剃髪もしていない司祭なんてよう。あてにならねえよ、呼んでも無駄だ」
ひそひそと彼らは言い合った。
「だがよ、朝の礼拝だけには行かねばな。異教徒と思われては一大事だからなあ」
「今はそんなこと言ってる場合ではねえ」
「それでも、とにかくあんな若え神父さんではだめだ」
「じゃ、どうすんだよ」
ヴァルスネリアは長い裾を引きずったまま立ち止まり、憤慨したように村人たちを睨んだ。
「何だい、腰抜けばかりだね、どいつもこいつも! 勇気のあるやつはいないのかい? そんならいいよ、あたしがじきじきにごあいさつだ!」
「ああっ」
村人たちが思わず叫んだ。女は勢い良く裾をまくり上げると、力任せに木戸を蹴った。
* * *
「アドリアン神父」
呼ばれて振り向くと、六十がらみの男が立っていた。髪はまばらだが、瞳と同じ褐色だっただろうとわかる。
アドリアン神父、と呼ばれた若い司祭は、現実に引き戻されてもしばらく言葉を返せない。
底なし沼のような悲しみにとらわれて、彼は長い間現実を現実とも思えないでいた。
あれほど慕い、あこがれ続けたヴェネデットの死という現実を。
――なかなか覚めない悪夢に違いない。
そうとでも思わなければ、彼の心はひずんで壊れてしまいそうだった。
「また考え事ですかな」
老人は農作業を終えたばかりという出で立ちで、土のついた鍬を片手に持っている。
相手の、年の割に屈託のない物言いにアドリアンは少しずつ自分を取り戻した。
彼はゆっくりととりつくろう。
「いや、何となく今朝は村が騒がしいような気がして……ボルヘ、何をしているんだ?」
若い司祭が問い返した。
「……はて。気がつきませんでしたな。騒がしいといえば、近隣の町や村で奇妙な事件が起こっているといいますが、御存知ですかな」
「事件?」
どうせ自分の気を引くものではない、と決めつけてアドリアンは関心なさそうに言った。
「はあ。そうです。人が死ぬんです」
「それがどうして奇妙なんだ?」
「……神父。死に方が奇妙なのですよ。どこといって傷もないのに体中の水気を全て搾り取られたようにひからびてしまうのです。たった一晩で、ですぞ」
アドリアンは相手にふと視線をとめた。
「……数は? 流行病なのか」
「いえ、いえ、そういうことはまだなさそうです。あちらの町にひとり、こちらの村にひとり、と言った具合なんですよ。ですが何とも気味の悪い話ではありませんか。そんなものが流行したら、いったいどうなってしまうんでしょうな」
「先取りして不安がるものでもないだろう。新しい奇病だろうという気はするけれども」
アドリアンが平然と答えた。彼にとっては世間で何が起こっていようが関係ないと思えるのだった。が、その態度はことのほか老いた助祭を元気づけたようだ。
「そうですな。人の不安というものほど厄介な病気はないですからな。……ところで騒がしいのはもっぱらご婦人たちでしょうよ。あなたを見て騒がないご婦人はおりませんよ」
「どういう意味だ」
「どうって……、鏡をご覧になればわかります。ご婦人は美しいものがことのほか好きですよ」
「卑しいことを。騒がしいのはそんな理由じゃないと思う」
アドリアンは物憂げな顔をして言った。
「そうですか。しかしあなたは司祭である前に二十才の青年です、いろいろな誘惑がないとも限りません。免疫もありませんしな」
最後の言葉だけは小声だったが、アドリアンは決して聞き逃してはいない。
「そうだな。生きた女性とはつき合ったことがないが、たいして変わらないだろう。そんな軽口に煩わされないためにも、早く年をとりたいもんだな」
「無理をおっしゃいますな。急がれることもありますまい。若いうちは浮き名を流されるのも経験のうちでしょう。そうでもなければ恋に悩む若者が告解にきた時、なんとします?」
アドリアンが金色の瞳を細めて言った。
「村にひとり破戒僧がいると報告しようか。なぜおまえのような者がこの道に入ったのかわからん。世俗に未練たっぷりのように見えるが……ところで鍬で何を?」
「畑を作っていたんです。春蒔きの種が手に入ったんで。わしは慣れておりますから。今に豆が食べられるようになりますよ」
「気長に待つとするか。村人がうちとけるのと同じくらいに」
アドリアンの意味ありげな言葉に、助祭がうなずいた。
「全く。閉鎖的な村ですな。……鉄細工師のモライシュという職人を御存知ですか。林の中のあばら屋で暮らしておるんです。彼はいつも仏頂面をしているが、唯一この村でどうにか話せる男です」
「あの偏屈そうな男が? ……そうも思えないが」
アドリアンがモライシュについて覚えていたのは、彼がどんな日でも朝まだ薄暗いうちに、人目を避けるように礼拝にやってくるからだ。それも敬虔だからというよりは、人との接触を嫌っているとしか思えない寡黙さで。
「彼もわしらと同様、よそ者だということですよ」
「よそ者?」
「二十年前にこの村にやってきたんだそうです。今は娘とふたり暮らしです」
「二十年も住んでいて、よそ者扱い!」
アドリアンが呆れた声で言った。
「なんて村だ!」
「わしは決して驚いてはおりませんよ。どこもそんなものです」
「しかし、娘は別だろう。この地で生まれているのだから。生え抜きであれば二十年住んだよそ者より当地で生まれた赤子のほうが……」
「いや、そうとばかりも。血は争えません。村人には珍しい容貌でしてね、父親ゆずりの。髪と目がカラスのように黒いんですよ。あればかりはどうにもなりゃしません」
「ボルヘ」
アドリアンが短く言った。ボルヘはしまった、という顔をしてアドリアンの瞳を見た。
「これは……失言でしたな。すみません……聴聞僧ちょうもんそうがいたなら告解して赦しを乞うところですが……」
アドリアンは無言できびすを返し、教会の奥へと歩いた。ボルヘはしばらくその後ろ姿を見ていたが、やがてあきらめたように首をふって教会を出ていった。鍬を片づけに行ったのだろう。若い司祭アドリアンは祭壇の前に立ち、目を伏せた。瞳や髪の色が周りの者と違うことは、彼も同じだ。美しいと言われても、遠回しな拒絶や疎外であることには変わりはない。ボルヘは誤解したかもしれない。失言によって息子、あるいは孫ほどの年下の司祭の機嫌をそこねてしまったのだと。本当はそうではなく、言い知れぬ孤独に襲われただけなのだ。
――ヴェネデット修道院長は……どんな時も誰に対してもわけへだてのない方だった……。
彼は祭壇に向かったまま、おぼろげな記憶をたどって、いつまでもよそ者のままのモライシュという男を思い浮かべた。黒髪で、黒い瞳の……おそらく異国では珍しくもない風貌だが、この村の閉鎖的な人々の癇にさわるのだろう。
ことさらに目立とうとはしないが、決して媚びることもない異邦人。モライシュの娘はかたわらにいたが、容貌どころか年の頃もわからなかった。いつも毛織りの頭巾を目深にかぶって、うつむいていたからだ。
アドリアンは金色の瞳で虚空を見つめた。
――不条理だが、しかし取るに足らないことだ。……村人がぼくを必要としないのは良いことだ。面倒さえ起こらなければいい。今のぼくにはヴェネデット様の加護もなく、死者の声も聞こえない。ヴェネデット様が亡くなってからというもの――。
聴罪ができない……。
アドリアンはつぶやき、祭壇の上の香炉に手をのばした。
「神父様!」
背後で女の金切り声が上がった。教会の入り口に、逆光に立つ人影があった。
「け、け、喧嘩になりそうなんです。隣の奥さんが知らせてくれたんだ。変な女がそそのかして……見たこともない女だって。早いとこ止めてくださいまし!」
「……喧嘩?」
乱れた足音が近づいた。
「あああ。うちの亭主が……。刃物沙汰になったらどうしよう! 相手はあのモライシュなんですよ」
アドリアンも祭壇から入り口に向き直り、礼拝席の間の通路を歩み出た。髪を振り乱した中年の女が転げるようにしてやって来て、アドリアンの前に膝をついた。
「モライシュ?」
「早く、早く! モライシュの家へ、こっちです、神父様」
アドリアンが女の後について教会を出た。朝の光のまぶしさに顔をしかめた。
前を行く女は、初めて頼って口をきいてきた村人だ。
ふとアドリアンは振り向き、教会の正面祭壇を見た。祭壇上の蝋燭の明かりが激しく揺れ動いていた。
――来る……。
忌まわしいものが。
「神父様」
泣き出しそうな女の声に呼び戻され、若い司祭は白い僧衣を翻した。
(「死者の告白─聴罪師アドリアン─」本文より抜粋)
|