表1 主要国首脳の年間給与 2.27朝日新聞朝刊より
| 国 | 年間総額 | 一般職最高位と 比較した指数 |
| 日本首相 | 4165万円 | 1.7 |
| 米大統領 | 40万ドル(4328万円) | 2.8 |
| 英首相 | 17万5414ポンド(3583万円) | 1.5 |
| 独首相 | 21万2816ユーロ(2917万円) | 1.8 |
| 仏大統領 | 163万4000ユーロ(2億2401万円) | 不明 |
一般職最高位(事務次官級)は日本では130万1000円/月
表2 一部上場企業の役員年収
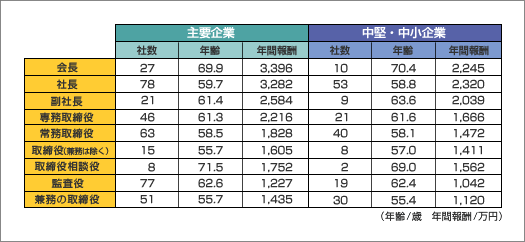
表3 一部上場企業の役職による報酬
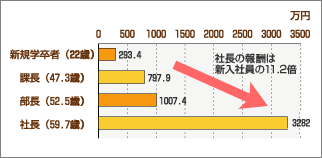
表4 退職慰労金
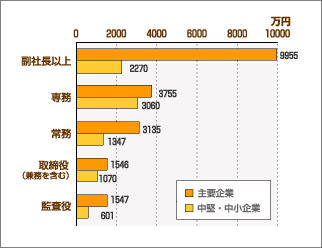
日本の主要企業の役員の年収は1600万円である。この年収で生活に困るわけではないが、さほど贅沢もできない。私がこの話をした人が、「日本の企業の役員は、さほど重要な判断をしていないのだ」と言っていたが、確かにそうかも知れぬ。しかし、これでは企業が活性化しない。給料どころか責任も、給料見合いでさほど大きくないのだとすると、だれも熾烈な競争をして役員になりたいと思わなくなる。企業は役員に、少なくとも総理大臣よりは多く、カネを出すべきと思う。業績を伸ばした経営者が厚遇されるアメリカの方がよほど働きがいがある。
2004年2月22日(日) 「ケータイを持ったサル」 MIT2004.2書評より
作者正高信男(まさたかのぶお)は京都大学霊長類研究所教授。みずからをサル学者と称しているから、長年サルの生態を研究した人らしい。
「我々がサルと区別されるのは、その個人にしかできない何かを達成し、自己実現を遂げるからです。そのためには「家の外」の領域に足を踏み出して自立することが不可欠です。ところが若者達の行動を見ていると、公共の場に於いても「家の中」にいる感覚だということに気付きます。だから地べたにじかに座ったり、電車の中で化粧をしたりするのも平気なのです。」
他者の存在を意識することが自我の確立、すなわち大人になること。今朝、長男に「足の爪を切れ、子供に言うようなことを言わすなよ」と言ったら、「子供に言うようなことを言うなよ」と反発されて、ちょっとうれしかったかも。
「最近では父性の影響力が非常に希薄になっている。一方母親のほうは情熱を子供にしか傾けられず子供に過剰な投資をし、母子密着が進む。居場所のない夫と子離れできない妻が多くの中年夫婦の姿。その結果子供はいつまでも自立しようとしない。」
然り。単身赴任は良くない。
「言語には二種あり、一つは外界の事物を正しく伝えるという公的な機能。もう一つは情緒的な絆を強めるという私的機能。「メル友」同士の交信内容は「元気?」といった単純なもので、言葉の公的機能に当たるようなメッセージは余り含まれていない。四六時中メールを交換してお互いにつながっているという感覚を持つことが大事なだけなのだ。これはニホンザルの「クーコール」と呼ばれる鳴き声に似ている。コミュニケーションのサル化だ。」
然り。ハタチ前の長男にはメシを喰っている間にも2度ぐらいメールが来る。それに瞬間に応答する。「クーコール」という言葉を広めよう。無理か。
「相手が自分にとって信頼できるか否かを判断する能力は社会的な「かしこさ」だといえるが、これは40際位になると衰えてくる。従って子供の気持ちがまったくわからないという状況が出てくる。そうするとモノを買い与えることで、子供の心をつなぎ止めようとする傾向が顕著になってくる。そして思春期を過ぎた子供に対しても「〜を買って上げる」という態度をとり続けて、いつまでも親に依存しなくては生きていけない子供を育ててしまう。」
若い人たちの気持ちがわからなくなっているのか。スタンスが変わっただけだと思っていたが。相手以上に相手のことが分かっていると思っていたかもしれぬ。
「人間は社会的文化的に涙ぐましい努力を経て人間らしくなる。サルのように動物的愛情のままに育児をすればまっとうな人間に育たない。21世紀に育ってきた子供達は先祖帰りしてサル化しつつあるのではないか。」
然り。そういえば上司の「ディスプレイ」的行動に、安心して盲従するミドルも既にサル化しているかもしれぬ。
「ケータイを持ったサル」 正高信男著 中公新書 700円
2004年2月17日(土) ロードオブザリング
莫大なカネをかけた大スペクタクル。さすがハリウッドという映画だ。本日3部作の第3作目が公開された。
CG技術はカネ次第だから、この映画のCGによる映像はリアルの極致だ。
CGが反乱すると、 ヒトは自分の目で見たモノは信じるから、だんだん真実がわからなくなってくるんではないか。これはウソだ、という感覚が次第に無くなってくるかもしれぬ。
ストーリははいつもながら、醜悪で下品な悪の集団を正義の軍団が容赦なく殺しまくるという単純な構図である。善集団にもクラスがあって、神は非常識な能力を与えられている、という設定である。まあエンタの中のエンタと言うところか。
第2作は、ロケ地となった、ニュージーランドの自然がすばらしい。この自然が、多すぎるCGに辟易するところを救っている。
2004年2月8日(日) 地下鉄テロと都市化
都市化の脆弱さは震災や停電だけでなく、無差別テロについても同様である。ロシアの地下鉄自爆テロが東京でも起こると、被害は最大千人近いものになるだろう。
都市で安全に生活してゆくためには、自然の中で暮らしてゆく知恵のように、親から子へ受け継がれるようなものではなく、添加物や栄養、大気汚染物質や環境ホルモン、防災やセキュリティ、ストレスなど、生物的に生きてゆくためだけであっても、広範で新しい情報が必要である。生活や仕事の人間関係は、田舎では親の作ってきたそれに依存する割合が大きいが、都市ではひとりひとりが自ら作ってゆく度合いがおおきい。つまり、都市で生活することは、一層個人の知恵や能力が必要なのだ。都市ではヒト、モノ、カネ、情報、全てが豊富で効率的であるように見えるが、高い住宅費や長い通勤時間に見合うか。生物的な(フィジカルにもメンタルにも)リスクが十分大きいと言える。そして一度都市のシステムが狂うと、突然大規模な本物のサバイバルが始まる。
END