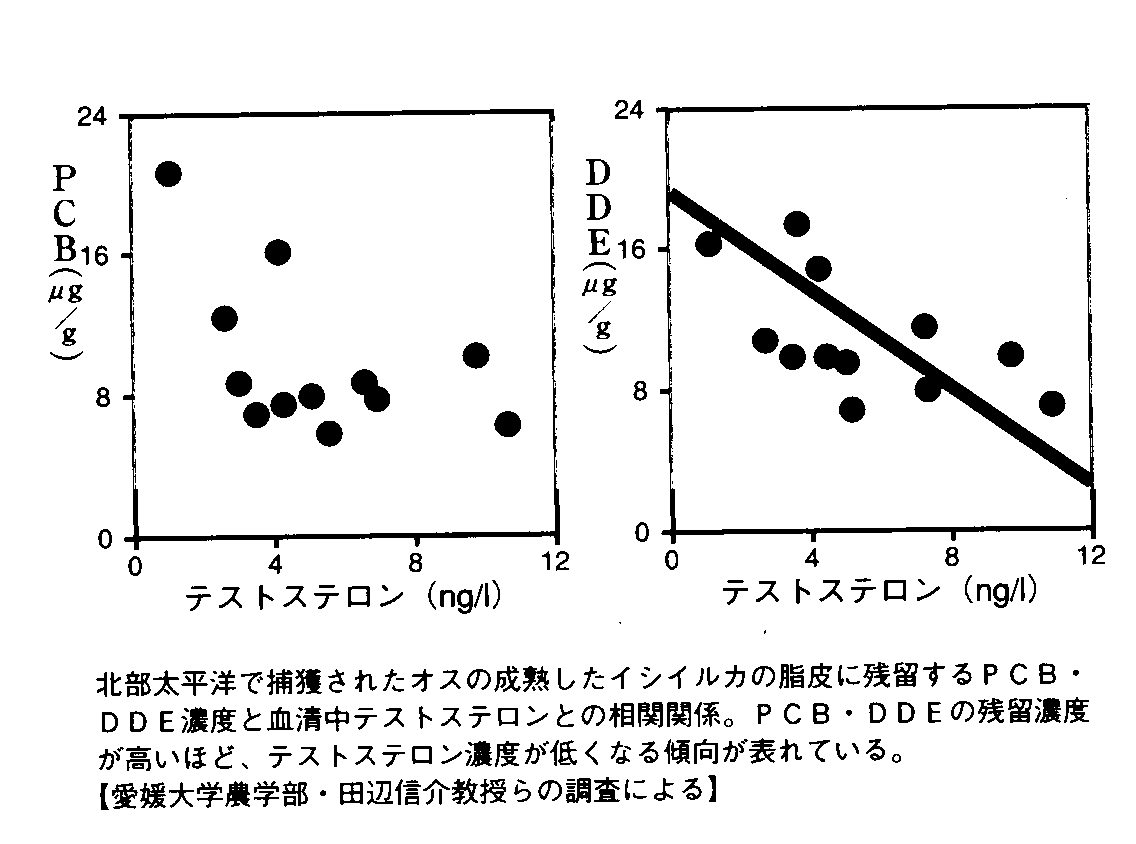3年選択理科 環境ホルモン3 月 日
3年 組 番 氏名( )
生物濃縮と食物連鎖一有機塩素化合物のはるかな旅
海洋哺乳動物の大量死の謎
その異変は、1987年から90年にかけて起こった。
87年、アメリカ東海岸のニュージャージー州からフロリダ州にかけて、バンドウイルカの死体が一頭、また一頭と岸辺に打ち上げられ、この沿岸に棲息する個体数の半分を超える740頭のイルカの命が失われたのだ。この大量死はほどなくメキシコ湾のイルカにも波及した。 異変はさらに続いた。同じく八七年、シベリアのバイカル湖では数千頭に及ぶバイカルアザラシの大量死が確認され、翌88年、北海・バルト海では1万8000頭ものゴマフアザラシが口から血を流して次々と死んだ。90年には、スペイン、フランス、イタリア沖の地中海で合計1万頭以上のスジイルカが大量死した……。
なぜ、このような海洋哺乳動物の大量死が連鎖的に起こったのか。これら一連の大量死には、何らかの関連性があるのだろうか。イルカの死骸を解剖してみると、皮膚や内職の器官がウイルスに冒されていた。だが、それは、健康な状態のイルカならほとんど問題にならないものだった。ゴマフアザラシの大量死は、犬のジステンパーウイルスに感染したのが原因だといわれている。しかし、アザラシが犬に噛まれることはそれほど珍しくないから、過去にもこのような大量死が発生していてもおかしくはない。つまり、イルカやアザラシの大量死の本当の原因は、いまだに解明されていないのである。 長い時間をかけた緩慢な大量死も起こっている。二十世紀の初め、カナダのセントローレンス川河口には5000頭以上のベルーガ(シロイルカ)が棲息していた。ところが今や、その数はー〇分の一に激減している。外洋に棲むクジラの仲間のいくつかは、もはや絶滅の危機に瀕している。
ヒトに限らず、動物はストレスが加わると病気になりやすいといわれている。ウイルスなど外敵を撃退する免疫のメカニズムが正常に働かなくなるからだ。この免疫機能の低下が、イルカやアザラシなど海洋哺乳動物の大量死の主因ではないか、という指摘もある。何らかの理由で免疫機能が損なわれ、それが病原体の活動を劇的に高め、大量死という深刻な事態を招いたのではないか、と考えられているのだ。
なぜ免疫機能が損なわれたのか、その理由は今のところはっきりわかっていない。だが、相次ぐ海洋哺乳動物の大量死との関連を深く疑われているものはある。PCBに代表される有機塩素化合物である。
PCB、DDT、ダイオキシンなどの有機塩素化合物に慢性的に暴露されると免疫機能が低下するという仮説は、バンドウイルカの血液サンプルで有機塩素化合物と免疫抑制との関係を調べた、アメリカの学者グループによつてすでに確かめられている。また、ベルーガの個体群が激減した、セントローレンス川の河口一帯は、有機塩素化合物など化学物質によって汚染されており、ここに棲息するベルーガからは卵巣の異常、妊娠個体の減少そして雌雄同体の成体の出現も確認されている。
化学物質は土壌から川や湖沼に流れ込み、大気中に拡散するが、最後は海にたどりつく。化学物質を分解し、浄化する役割を担っているのは地球の表面積の七割を占める海なのである。
イギリスの生態学者M・シモンズは、二十世紀に入って、イルカやアザラシなど海洋哺乳動物の大量死が世界中で11件起き、そのうち9件までが1970年代後半以降に集中している、と報告している。海洋哺乳動物の大量死が集中した時期は、化学物質による汚染が深刻化した時期とほぼ重なっているのである。しかも、これら大量死のほとんどは、欧米など先進諸国の沿岸で起こっている。 M・シモンズの調査は、化学物質による海洋汚染と海洋哺乳動物の大量死との関連性を示唆するものといっていいだろう。 そして今、汚染は先進諸国だけでなく、地球規模で拡大している。化学物質を生んだ現代文明とはおよそ無縁に見える北極圏のホッキョクグマやアザラシからも、PCBをはじめ有機塩素化合物が高濃度で検出されているのである。
先進諸国で、ほとんどの有機塩素化合物の生産・使用が禁じられてから、早くも二十年以上が経っている。にもかかわらず、なぜ汚染は拡大しているのか。最も厄介な化学物質といわれるPCBを例にとって、このことを検証してみよう。
PCBは分解されずに環境中に残留する
自然界では、土壌や水中に棲む微生物が化学物質分解の役目を担っている。また、紫外線によって分解される化学物質も少なくない。しかし微生物や紫外線も、PCBにはほとんど歯が立たない。このため、PCBの半減期(化学物質が分解し、濃度が半分に減るまでの年数)は数百年にも及ぶといわれている。
PCBは19世紀後半に初めて合成され、1930年代に入って商業ベースで生産されるようになった。後にモンサント社に吸収されるスワン社がまず先陣を切った。スワン社が製造したPCBの商品名は、「アロクロル」と名づけられた。
無色透明で粘り気のあるこの液体は、その頃、毒性のない安全な物質と考えられていた。当時の安全基準では急性毒性だけが問題にされており、環境中に残留しやすいかどうかという視点はすっぽり抜け落ちていたのである。
PCBは電気絶縁性をもち、燃えにくく、しかも化学的に安定な性質を有している。コンデンサー(蓄電器)やトランス(変圧器)の絶縁油や冷却液には、まさにおあつらえ向きの性質をもっていたのだ。
折しも二十世紀半ばは、電気化学工業が急速な発展を遂げた時期である。蛍光灯やラジオ、テレビ、冷蔵庫、エアコン――。さまざまな電気製品が先を争って開発され、人々の生活は飛躍的に豊かで便利になった。
そしてこれらの電気製品のほとんどに、PCB入りのコンデンサーやトランスが用いられたのだ。電気製品以外にも、複写用のノンカーボン紙の溶剤、プラスチックの可塑剤、機械の潤滑油など、その用途はどんどん広がっていった。PCBは、化学物質としては20世紀を代表するヒット商品といっていいだろう。
第二次世界大戦後の1954年、日本でも鐘淵化学工業が「カネクロール」という商品名でPCBの大量生産を始め、三菱モンサントもアメリカから輸入したPCBの販売を開始した。当時、日本は欧米にキャッチアップするため強力に工業化を推進していた。これに並行してPCBの生産も急速に伸び、用途も拡大していった。生産・使用が禁止されるまでの生産量は、日本国内で約6万トン、世界中では120万トンに上るといわれている。
PCBの安全性に初めて疑問が投げかけられたのは1966年のことだ。スウェーデンのストックホルム大学の分析化学者ソーレン・ヤンセンが科学雑誌『ニューサイエンティスト』に、オジロワシの体内からPCBが検出されたというショッキングなリポートを発表したのである。
翌1967年、アメリカのサンディエゴ自然史博物館のモンテ・カーペンもハヤブサの卵からPCBを検出した。
そして1968年には、PCBの人体への有害性を決定的に証明する忌まわしい事件が日本で起こった。北九州市のカネミ倉庫が製造したライスオイルにPCBが混入したのである。
ライスオイルは、天ぷらなどの調理用油として幅広く利用されていた。PCBが混入したライスオイルで調理した料理を食べた人は、激しい嘔吐に襲われ、肝臓障害や皮膚の色素沈着といった症状が現れた。症状が悪化し、死亡する被害者が続出し、患者の体内の脂肪組織からは高濃度のPCBとジベンゾフラン(ダイオキシンの一種)が検出された。だが、被害はそれだけに留まらなかった。母から子へと受け継がれ、妊娠中にPCB入りのライスオイルを摂取した母親の死産や流産、生まれた子どもの発育不全などが数多く見られたのだ。
結局、このカネミ油症事件は、死者298人、認定患者1871人(98年3月現在)という惨憺たる結果を招いた。そしてこの事件を機に、PCBは体内に蓄積されやすいこと、微生物などによってほとんど分解されないことなどが明らかになり、日本では1972年に生産及び使用が禁止された。その後、アメリカやヨーロッパなど先進諸国でも、相次いで生産中止の措置が取られることになる。
生産・使用禁止のはずのPCBが発展途上国で
前述のように、先進諸国でPCBの生産・使用が禁止されてから、すでに二十年以上過ぎている。にもかかわらず、PCB汚染は衰える気配を見せていない。例えば、南氷洋のミンククジラの場合、他の有機塩素化合物は濃度が横這い状態であるのに、PCBだけは徐々に増え続けているというデータもある。南氷洋におけるPCB汚染は、むしろ拡大傾向にあるといつてもいいだろう。北半球のPCB汚染も低減が遅いことが指摘されている。
これは、一体、なぜなのだろうか。
その理由として、まず第1に挙げられるのは、いまだにPCBの処理技術が確立されていないことだ。PCBには、液体のまま使われたものと固形化して使用されたものとがある。前者については、1000度以上の高熱で焼却し、安全に処理する技術が一応開発されているが、固形化されたものに関しては手の施しようがないというのが実情だ。
第二に、PCBを用いた製品がいまだに使われ続けていることだ。日本全国でPCB入りのコンデンサーは34万台、トランスは4万台あると推定されている。これらの製品の耐用年数は極めて長く、一説では50年ともいわれている。1997年3月、鳥取県のある高校で天井の古い蛍光灯が破損し、漏れ出したPCBのにおいを嗅いだ生徒四人の気分が悪くなるという事件が起こったが、今後、この種のPCB被害が発生しないとは断言できないのである。
どの製品にPCBが使用されているのか、素人目にはわからないことも、PCB汚染を深刻化、長期化させる一因となっている。古い住宅を建て替える時など、コンデンサーやトランスなどPCB入りの製品を、それと知らずに捨ててしまうことは誰にでもありうる。これらPCB入りの廃棄物は、ゴミ処理場で焼却されるか、そのまま放置されることになるだろう。焼却処理方法が適切でなければ、ダイオキシン汚染の発生源になる可能性が高いし、放置されたままだとPCBの二次的な汚染源になってしまうのだ。
前述の通り、生産・使用の禁止に至るまでに、日本で約6万トンのPCBが生産されている。そのうち回収命令が出て、適切に処理または管理されているものは約1万トン、すでに環境中に漏れ出たものは約2万トンと推定されている。
では、残りの3万トンはどこでどうなっているのか。それは誰も把握できていない。これから耐用年数の期限が切れるPCB入りの製品もあるだろうし、それらの製品の一部はすでに国外に持ち出されているともいわれている。
この指摘を裏づけるかのように、発展途上国では、今も半ば公然とPCB入りのコンデンサーやトランスが使用されている、という情報も寄せられている。
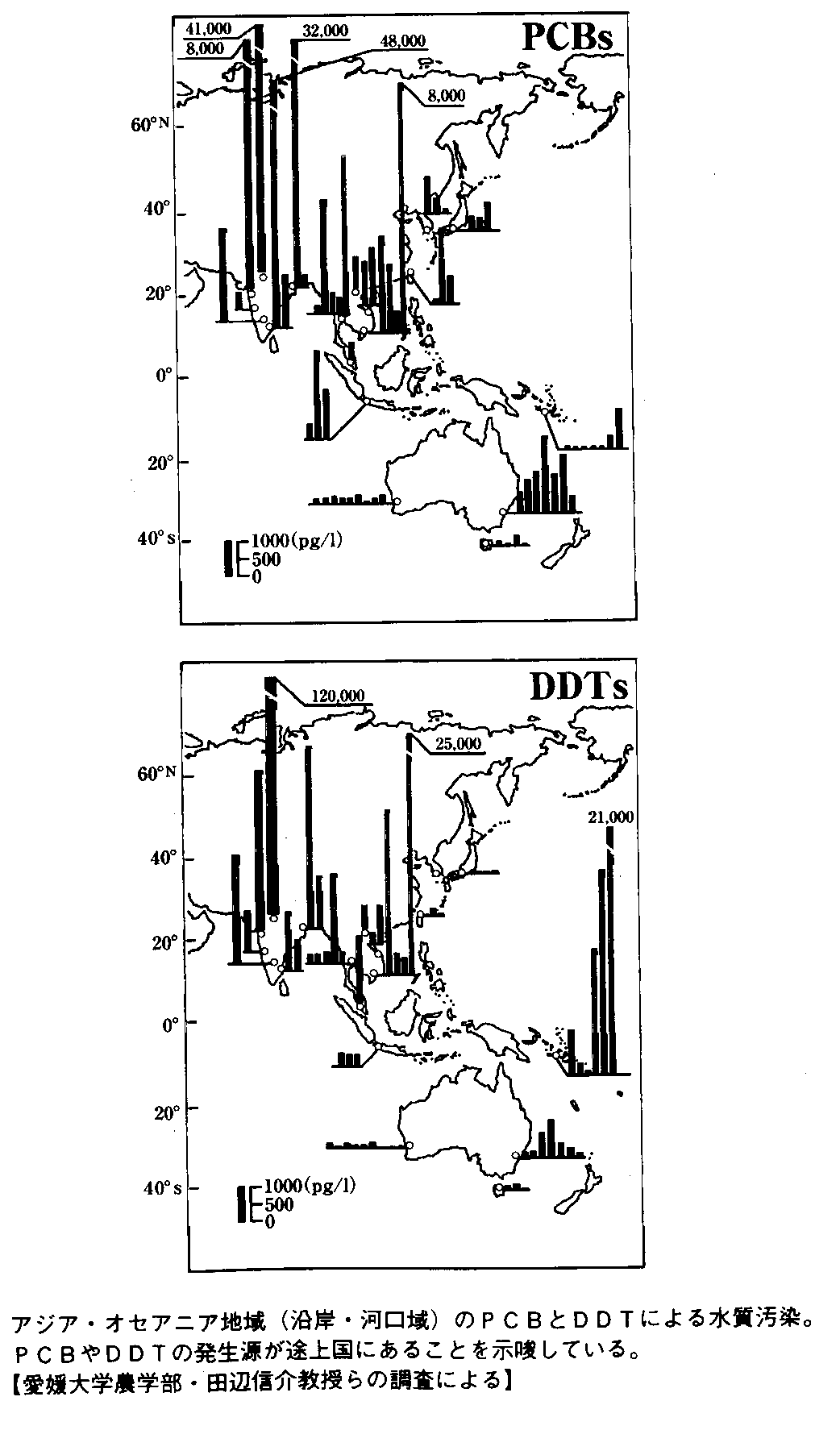 愛媛大学農学部の田辺信介教授は、かつてアジア・オセアニア地域でPCB濃度を調査したことがある。その結果、東南アジアやインドの沿岸・河口域でPCBが検出されたという。
愛媛大学農学部の田辺信介教授は、かつてアジア・オセアニア地域でPCB濃度を調査したことがある。その結果、東南アジアやインドの沿岸・河口域でPCBが検出されたという。
田辺教授は、途上国で日本製のコンデンサーが捨てられ、高濃度のPCBが漏れ出している現場にも遭遇している。
PCB自体はもちろん、PCB入りの製品も、今では国際条約によって輸出入が禁止されている。にもかかわらず、日本製の旧式コンデンサーが途上国に流出しているのだ。
発展途上国では、技術的な問題もあり、コンデンサーやトランスなど電気機器はほとんど国内では生産していない。先進諸国からの輸入に依存しており、それも新しい製品ではなく、中古品を輸入するケースが少なくない。
田辺教授は、次のようにも言う。
「タイのバンコク郊外にも、PCBを使ったトランスが捨てられていて大きな汚染源になっているというので、調査に行ったことがあります。トランスのパネルをはがすと、日本など先進国のトランス・メーカーの社名ロゴがついている。アフリカなどでかつて問題になりましたが、途上国は先進諸国の廃棄物を引き受けて、自国内で処理してしまうという側面がかなりあるのです」
PCB汚染の発生源は、先進国だけでなく、途上国にもあるといっていいだろう。
汚染はまず、PCBを大量生産した欧米や日本など先進諸国で確認され、その防止対策は今も十分に講じられていない。汚染は次に、PCBを使った製品の移動を介して発展途上国に飛び火した。そして今、途上国も発生源となり、PCB汚染は地球規模で拡大しているのである。
「恐らくPCB汚染のピークは二十世紀末、1990年代の終わりに来るだろうと予測されていました。トランスやコンデンサーの耐用年数からいっても、その可能性が大きいでしょう」
田辺教授はそう懸念する。
PCB汚染は、まさに今、本番を迎えているのである。
北極は”有機塩素化合物の集積地”と化している
発展途上国の多くは、熱帯・亜熱帯地域に位置している。年間を通じて気温が高く、乾季になると太陽がジリジリ照りつけ、水をまいてもみるみるうちに蒸発してしまう。
PCBなど有機塩素化合物も同様で、これら高温の地域では、そのほとんどが気化し、大気中に紛れ込んでしまうのである。
田辺教授はかつて南インドで、有機塩素系の農薬HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン。日本では1971年に農薬や家庭用殺虫剤としての使用が禁じられたが、インドなど途上国では今なお使用されている)を水田に散布し、どの程度、土壌に残留するか調査したことがある。すると、わずか二週間で、散布したHCHの九割以上が蒸発してしまったのだ。
田辺教授はさらに、甫インドのベラ川集水域でもHCHの汚染を調査してみたが、河口域まで達したHCHの量はわずか1パーセントにすぎなかった。つまり、川を下り、ベンガル湾に注ぐ河口域にたどりつくまでに、HCHの99パーセントは大気に揮散してしまつたのだ。化学物質は、水温が高ければ高いほど水溶性が低くなるといわれるから、残りの1パーセントも結局は大気中に紛れ込んでしまうと見なしていいだろう。
気温が高ければ大気に揮散しやすいという有機塩素化合物の性質は、熱帯・亜熱帯気候下にある途上国にとっては、あるいはプラスかもしれない。しかし、地球的視点で見た時、それはPCBなど有機塩素化合物の汚染を全世界に拡大させることを意味する。海や川、湖沼などから蒸発した大量の水蒸気は、やがて上空で雲となり、はるか北を目指してゆっくり移動していく。北に向かうのは、赤道付近にハドレーセルと呼ばれる巨大な空気の塊があり、これが北半球と南半球の大気の流れを分ける役割を果たしているからである。PCBなど有機塩素化合物の分子は、大気中の粒子に吸着して気流に乗り、東へ西へと移動しながら、徐々に北上していく。雨が降れば、いったんは地上に舞い戻るものの、天候が回復すれば再び空高く舞い上がり、さらに北へと向かう。最終目的地は北極圏だ。
最終目的地にたどりつくと、PCB分子は雪や雨に混じって海面へと降り立っていく。ここでは、水温が低いので、PCBなど有機塩素化合物の分子は水に溶けやすくなる。熱帯・亜熱帯地域に比べれば、大気への揮散はほとんどないと見なしていい。
海面に舞い降りた有機塩素化合物の分子は、あるものは海水中の微生物などに吸着して漂い、あるものは海底の土壌に沈殿して数百年の寿命をまっとうすることになるだろう。
「北極が、PCBなど有機塩素化合物の集積地、最終的に行き着く場所になっているかもしれない」 と田辺教授もにらんでいる。
PCBをはじめ有機塩素化合物はいったん北極の近くまで運ばれると、もはやそこから脱出することはできない。北極はいわば、地球全体の有機塩素化合物の”最終処分場”の役割を強いられているのだ。
PCB汚染は食物連鎖を経て拡大していく
PCB汚染の拡大ルートには、もう一つ忘れてはならないものがある。自然界における、いわゆる食物連鎖である。
環境中のPCBが生体内に濃縮(蓄積され、食物連鎖を経て、汚染の拡大・深刻化に拍車をかけているのである。
自然界の生物は、互いに捕食者・被食者の関係によってチェーンのようにつながっている。PCBは、この食物連鎖を介して、ある生物から他の生物へとバスを乗り換えるかのように移動していく。当然のことながら、食物連鎖のピラミッドの頂点に近づくにしたがって、PCBの生物濃縮の度合いも飛躍的に高まっていく。
陸上の食物連鎖の頂点に立つのはヒトであるが、ヒトの体内に残留しているPCB濃度は、例えば、日本人の場合、約1ppmといわれている。ところが、海洋動物の食物連鎖の頂点に立つシャチでは、なんと500ppmものPCB残留濃度が検出されているのである。 では、この生物濃縮と食物連鎖によるPCB汚染は、具体的にはどのようなプロセスを経て拡大するのだろうか。自然界の食物連鎖は複雑にして多岐にわたるが、あえて単純化してそのドラマを再現してみることにしよう。舞台は、日本沿岸海域を含む西部北太平洋だ。
わが国の沿岸部の川や湖沼にも、熱帯・亜熱帯地域から気流に乗って旅してきた有機塩素化合物が絶え間なく降り注いでいる。それが、この海域に流入している。もちろん直接、海水面に降り立ってくる有害物質分子も少なくないだろう。だが、この辺りの海水面のPCB濃度は、1リットル当たりわずか0.27ナノグラムにすぎない。最新鋭の機械でかろうじて測定できる程度のごくわずかな量だ。この超微量のPCB分子は、まず植物プランクトンに付着する。その植物プランクトンを動物プランクトンが平らげる。この段階でのPCB濃度は海水の約6400倍だ。
ハダカイワシやスルメイカは、この動物プランクトンを主食にしている。またハダカイワシは、動物プランクトンの捕食を通じてだけでなく、えらからも海水中のPCBを直接取り込んでいる。そのハダカイワシの体内のPCB残留濃度は海水の約17万倍、スルメイカのそれは約24万倍と測定されている。 そして、北太平洋を群れをなして泳ぐハダカイワシやスルメイカを好んで食べるのがスジイルカだ。この段階になると、体内のPCB残留濃度は3.7ppm、なんと海水濃度の2200万倍にも跳ね上がつてしまうのだ。
スジイルカの寿命はおよそ20年といわれ、その間、これらの小魚を食べ続けるわけだから、PCB濃度が高くなるのはやむをえないのかもしれない。しかし、それにしても生物濃縮と食物連鎖によるPCB汚染の拡大は恐るべきものといわざるをえない。それはまさに幾何級数的な拡大といっていいだろう。イルカやクジラさえ捕食するシャチに至っては、前述のように500ppmものPCB濃度が検出されている。しかも、そのシャチは肝臓がんに冒されていたのである。 そのがんがPCB汚染の影響かどうかはわからない。だが、田辺教授は、
「体内のPCB濃度が50ppmを超えると、免疫機能が抑制されたり、生殖異常が起こったりすることはラットやマウスの実験で明らかになっています。それが野生の高等動物に当てはまるかどうかはわからないけれども、いずれにせよ、50ppmが目安になることは間違いありません。問題は、50ppmを超える野生動物が少なからずいるということです」 と警告している。
すでに、PCBに発がん性、催奇形性、免疫毒性などがあることは、動物実験でわかっている。そして今、PCBの環境ホルモン作用による生殖異常の発生も指摘されている。PCB濃度50ppmのボーダーラインを超えたイルカやシャチなど海洋哺乳動物に、これらの異変がいつ起こってもおかしくないのである。
イルカやクジラのPCB濃度が高い理由
外洋に棲む海洋哺乳動物には、なぜ50ppmのボーダーラインを超えるものが多いのだろうか。普通に考えれば、北極近くの一部の海域を除き、外洋は陸上よりもPCB汚染がはるかに少ないはずだ。陸上で生活しているヒトは、PCBに汚染された物を食べ、寿命もイルカやクジラよりかなり長い。つまり、より長い期既にわたつてPCBを摂取してしまっている。にもかかわらず、ヒトのPCB残留濃度は、日本人の場合、1ppm程度で、海洋哺乳動物はその数十倍、数百倍ものPCBを体内にため込んでいるのである。これはいかなる理由によるものなのか。 理由として、次の三点が指摘されている。
その一つは、イルカやクジラなど海洋哺乳動物は、体内に「脂皮」と呼ばれる分厚い皮下脂肪を蓄えていることだ。脂皮は、海洋哺乳動物にとって欠くべからざるものといっていい。ダイバーは海に潜る時、ウェットスーツを着用する。裸で長時間潜っていると、体温を奪われてしまうからだ。同様に、海洋哺乳動物は分厚い皮下脂肪で体温が逃げるのを防いでいる。脂皮は、ダイバーにとってのウェットスーツのようなものなのだ。 ところが厄介なことに、この脂皮とPCBはすこぶる相性がいい。PCBは水に溶けにくい反面、脂肪親和性をもつので、いったん脂皮の中に入り込んでしまえば長期間そこに留まることになる。つまり、体温維持装置の脂皮が、同時にPCBの「貯蔵庫」の役割も果たしてしまうのだ。
二つめには、体内に濃縮・蓄積されたPCBが、授乳を通じて母から子へと母子間移行するからだと考えられている。スジイルカの場合、母親の体内に蓄積されたPCBの約60パーセントが、授乳によって子に移行するといわれている。当然のことながら、世代を重ねれば重ねるほど、体内に残留するPCBは増えていくことになる。特にオスは授乳という排出手段をもたないから、否が応でもPCB濃度が高くならざるをえない。
そして、三つめの理由として指摘されているのは、PCBなど有害物質を分解する酵素の有無の問題だ。ヒトをはじめ陸上で生活する動物のPCB濃度が低いのは、肝臓で合成される薬物代謝酵素系チトクロムP450の分解作用によるものだと考えられている。ところが、海洋哺乳動物には、このチトクロムP450という酵素が遺伝的に欠落しているか、ほとんど発達していないのだ。
チトクロムP450は、海から陸によがつた動物が、植物など天然の毒物から身を守るために、長い進化の過程で獲得したものといわれている。
もちろん、陸上に棲む動物も、体内の脂肪組織に入り込んだ有機塩素化合物のすべてを分解し、体外に排出できるわけではない。しかし、この薬物代謝酵素系の働きが、有機塩素化合物に対しても一定の効力を発揮するため、海洋哺乳動物よりもPCB濃度が低いのではないか、と考えられているのである。
事実、このチトクロムP450にはフェノバルビタール(PB)型とメチルコラントレン(MC)型という二つのタイプがあるが、イルカの場合、PB型は遺伝的に欠落しているし、MC型の働きも極めて弱い。
「海の中には陸上の植物のような強い毒性をもつものがないから、海洋哺乳動物には、解毒作用をもつ酵素系が発達しなかった、といわれていますが、これもちょっとおかしい。というのは、イルカやクジラは一回、陸に上がっているんです。だから、腹部に後ろ足の痕跡が骨として残つている。すなわち、もう一度海に戻った後で、その酵素系が退化してしまったのかもしれません」
と田辺教授も首をかしげるが、同じ海に棲む魚類もこのチトクロムP450かあまり発達していないといわれている。ただし、魚類の場合、体内の有害物質の濃度が一定のレベル以上になると、えらから排出される仕組みになっているので、イルカやクジラなど海洋・哺乳動物のようにとめどなく濃縮・蓄積することはないわけだ。
体内に蓄積されたPCBが母乳を通して子どもへ
再び繰り返すが、環境ホルモンは、女性ホルモンと類似の働きをするといわれている。女性ホルモンの受容体、エストロゲン・レセプターと結合して性ホルモンの分泌を撹乱し、生殖異索などを引き起こす、と考えられているのである。
ところが、209種類あるPCBの仲間のうち、一部には弱い女性ホルモン様作用が認められているものの、そのほとんどはエストロゲン・レセプターとは結合しないのだ。
PCBは、ダイオキシン同様、Ah(アリルハイドロカーボン)レセプターと呼ばれる受容体と結合する。Ahレセプターが細胞にどのような影響を及ぼしているのか、詳しいことはほとんどわかっていないが、PCBがAhレセプターと結合した結果、生体内にチトクロムP450が誘導されることだけは明らかになっている。
チトクロムP450は、解毒作用をもつだけでなく、発がん物質を作つたり、胸腺に作用して免疫機能を抑制したりする性質があることが確認されている。また、性ホルモンの代謝を促すこともわかっているから、そのバランスを崩すこともありうるだろう。
前述の通り、海洋哺乳動物には、このチトクロムP450が遺伝的に欠落しているか、ほとんど発達していない。PCBなど有機塩素化合物が高レベルで体内に濃縮・蓄積された結果、内分泌作用に異常が現れたとしてもおかしくはない。
事実、性ホルモンのバランスの乱れを示唆するデータも得られている。
下の図は、北部太平洋の冷水域に棲息するイシイルカのPCB及びDDE(DDTの代謝物質。DDTの一部は体内でDDEに変化する)残留濃度と、男性ホルモンのテストステロン濃度との相関関係を示したものだ。PCBやDDEの残留濃度が高ければ高いほど、テストステロン濃度が低くなるという傾向が表れている。一方、三陸沖のアザラシや黒潮域のコビレゴンドウ、地中海のスジイルカでは、PCB残留濃度が高くなるにしたがって、薬物代謝活性(薬物を分解する働き)が高くなるという正の相関関係が認められている。
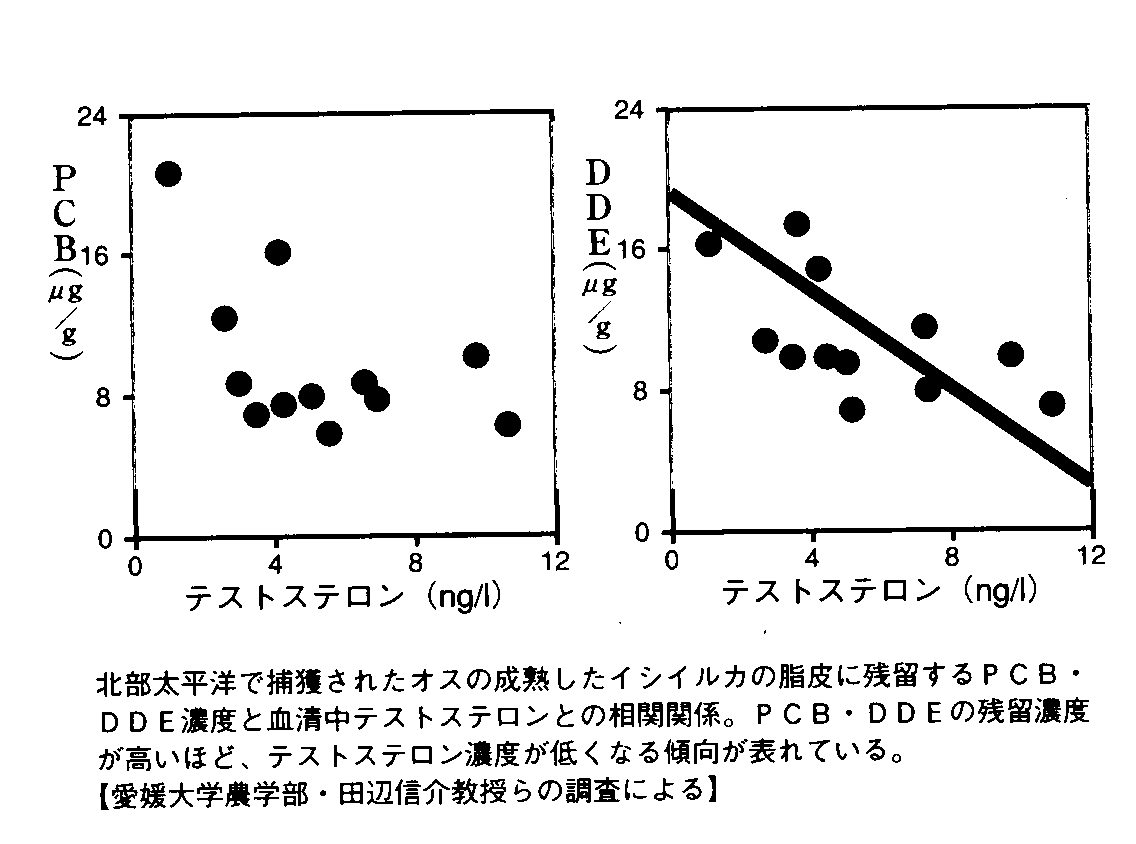
テストステロンは、オスの精子形成や性行動をコントロールする重要な性ホルモンだ。テストステロン濃度の低下は、精子数の減少、オスがメスと交尾しなくなるなど、性行動の異常をもたらすと見ていいだろう。
DDEは、男性ホルモンの受容体、アンドロゲン・レセプターに取りつき、体内で作られる男性ホルモンとの結合を妨げる作用をもつことが確認されている。テストステロン濃度の低下と相まって、深刻な生殖異変をもたらすことも懸念される。
PCBなど有機塩素化合物は、海洋哺乳動物にとつて、まさに新たな「天敵」といってもいいだろう。成熟したオスに対してさえ、著しい内分泌撹乱作用をもつからである。だが、もっと恐ろしいのは、これらの有害物質が母から子へと母子間移行していくことだ。イルカやクジラの赤ちゃんの体は、母親の10分の1にも満たない。その小さな体に、母親の体内に濃縮・蓄積された有機塩素化合物の60パーセントが受け継がれていく。
だが、さらにその前に忘れてはならないことがある。イルカやクジラの赤ちやんは、すでに母親の胎内で有機塩素化合物の慢性的な暴露を受けているということだ。胎仔は、生後間もない赤ちゃんに比べても、化学物質に対する感受性がはるかに高いのである。しかも、これは決してイルカやクジラに限ったことではない。授乳を通じてさまざまな化学物質を取り込んでいる点では、ヒトも同じだし、母親の胎内で有機塩素化合物に暴露されている点でも何ら変わりはない。
ヒトの体内のPCB濃度は1ppm程度にすぎない。これは、成人にとってはほとんど問題ないレベルといっていい。だが、この微量のPCBや他の有機塩素化合物が、母親の胎内に宿ったばかりの生命の内分泌作用を撹乱していないとは断言できない。
海洋哺乳動物の天敵が、ヒトの天敵にならないとも限らないのである。
海や川、湖沼などから蒸発した大量の水蒸気は、やがて上空で雲となり、はるか北を目指してゆっくり移動していく。北に向かうのは、赤道付近にハドレーセルと呼ばれる巨大な空気の塊があり、これが北半球と南半球の大気の流れを分ける役割を果たしているからである。
PCBなど有機塩素化合物の分子は、大気中の粒子に吸着して気流に乗り、東へ西へと移動しながら、徐々に北上していく。雨が降れば、いったんは地上に舞い戻るものの、天候が回復すれば再び空高く舞い上がり、さらに北へと向かう。最終目的地は北極圏だ。 最終目的地にたどりつくと、PCB分子は雪や雨に混じって海面へと降り立っていく。ここでは、水温が低いので、PCBなど有機塩素化合物の分子は水に溶けやすくなる。熱帯・亜熱帯地域に比べれば、大気への揮散はほとんどないと見なしていい。
海面に舞い降りた有機塩素化合物の分子は、あるものは海水中の微生物などに吸着して漂い、あるものは海底の土壌に沈殿して数百年の寿命をまっとうすることになるだろう。
「北極が、PCBなど有機塩素化合物の集積地、最終的に行き着く場所になっているかもしれない」
と田辺教授もにらんでいる。
--------------------ワークシート--------------------
3年選択理科 環境ホルモンについて3を読んで
- この文中には何という環境ホルモンが出てますか。
- PCBの持つ特徴を具体的に挙げよう。
- PCBの利用法にはどのようなものがありますか。
- PCBに関して、1968年に日本で起こった忌まわしい事件とは何ですか。
- 具体的にはどういう事件ですか。
- PCBで問題になったこととはなんですか。なるべく多く具体例を挙げよう。
- 北極は“有機塩素化合物の集積地”と化している とあるが、なぜこういうことになってしまうのですか。
- PCB汚染は食物連鎖を経て拡大していくとは、具体的にどういうことですか。
- イルカやクジラのPCB濃度が高い理由とは、具体的にどういうことですか。
- この文章について、感想を書こう。
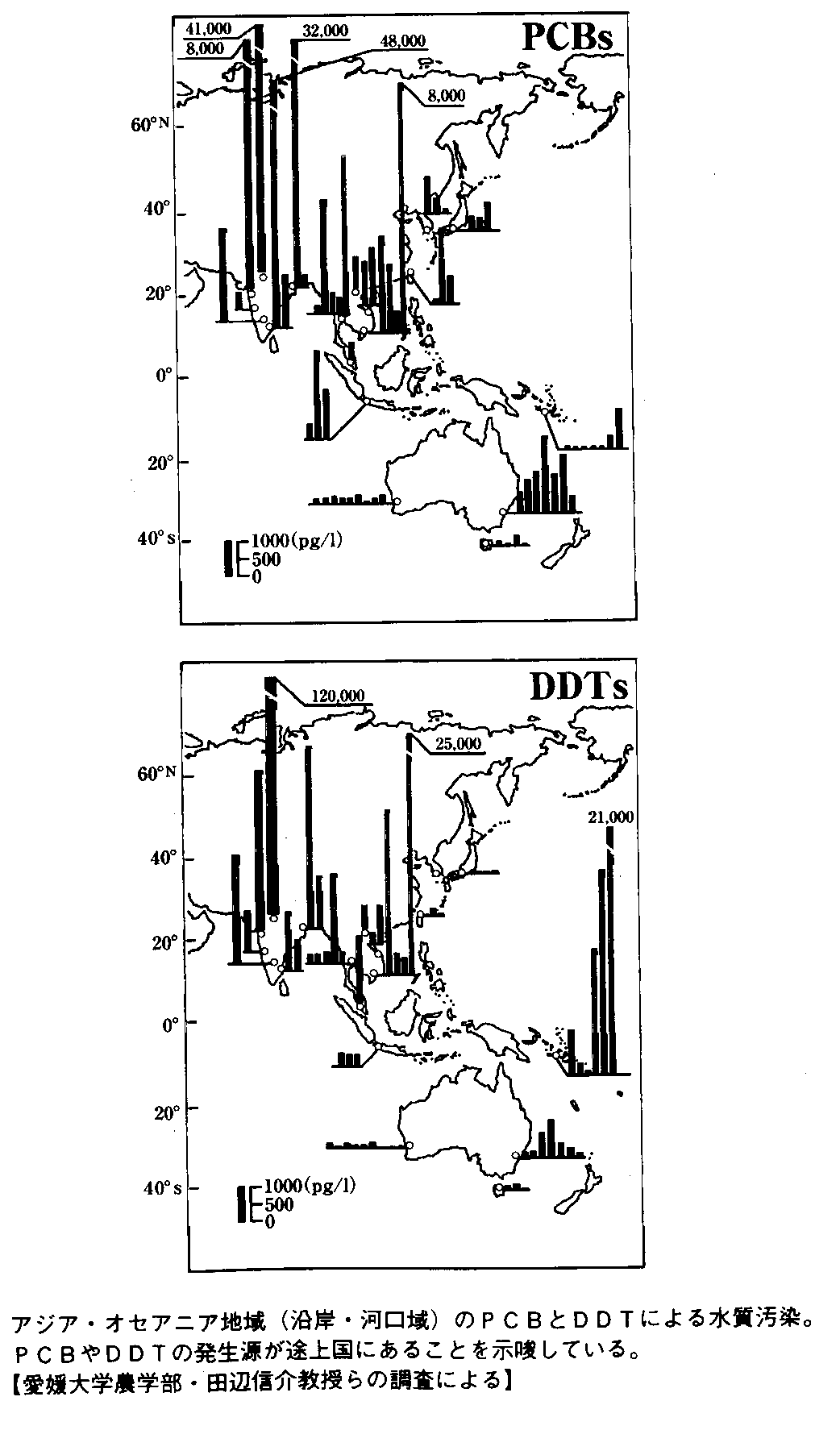 愛媛大学農学部の田辺信介教授は、かつてアジア・オセアニア地域でPCB濃度を調査したことがある。その結果、東南アジアやインドの沿岸・河口域でPCBが検出されたという。
愛媛大学農学部の田辺信介教授は、かつてアジア・オセアニア地域でPCB濃度を調査したことがある。その結果、東南アジアやインドの沿岸・河口域でPCBが検出されたという。