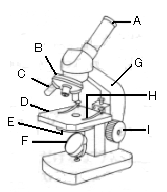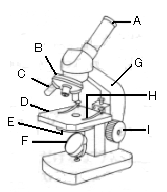パフォーマンステスト (1)顕微鏡の使い方
目的 顕微鏡を正しく使って観察できるか。
準備 顕微鏡、スライドガラス、カバーガラス、柄つき針、ピンセット、スポイト、ガーゼ、ろ紙
運搬方法
保管箱の運搬では、取っ手と箱の底を持ち、扉が開かないようにして運ぶ。
保管箱からとり出した顕微鏡を運ぶときは、アームと鏡脚をしっかり持って運ぶ。
観察場所
直射日光の当らない明るい場所にする。
顕微鏡は安定した水平な机や観察台の上に置き、落としたり、観察記録の妨げにならぬよう、
机の端には置かない。
顕微鏡の各部の名称(下の図に各部の名称を書く)
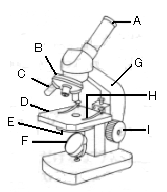
顕微鏡の倍率 接眼レンズ(×□) × 対物レンズ(×△)= 倍率は □ × △ 倍
例 接眼レンズ(×15) 対物レンズ(40) = 600倍
観察の方法
- 低倍率の接眼レンズを鏡筒上部にはめこむ。
- レボルバーに低倍率の対物レンズを一方の手でねじを回してとりつける。
(対物レンズを先にとりつけると、鏡筒内にほこりや水分が入り、対物レンズ上部に付着してしまう。と
りはずすときは、対物レンズから先に行う。レンズを落として傷つけないように両手で行う。)
- 低倍率の対物レンズにして、しぼりを全開にする。
- 接眼レンズをのぞきながら反射鏡の向きや角度を変えて、視野全体が一様に明るくなる所を探す。
- プレパラートをステージにのせて、試料が対物レンズの真下になるように移動し、クリップで止める。このとき、プレパラートを対物レンズにぶつけないように注意する。
- 横から見ながら調節ねじをゆっくり回して、対物レンズとプレパラートを接近させる。
- いきなり接眼レンズをのぞきながら調節ねじを回して接近させ、ピントを合わせようとしないこと。
- 接眼レンズをのぞきながら、調節ねじを対物レンズとプレパラートの距離が大きくなる向きにのみゆっくり回しながらピント合わせをする。下げつづけてもピントが合わないときは、もう一度5の状態に戻して、次の点を調べてみる。
- 見たい試料が視野の端にあるとき、スライドガラスを動かして、中央にくるようにする。顕微鏡で見られる像は、一般的に実物に対して上下左右が逆になっている。
- しぼりを調節し、観察しやすい明るさにする。
- レボルバーを回し、対物レンズを換えたり、接眼レンズを換えたりして、高倍率にして観察する。しぼりを使って視野を明るくするとき、全開にしてもまだ暗いときには、反射鏡を凹面鏡に換えて行ってみる。
プレパラートの作り方
- きれいで乾いたスライドガラスの中央に試料をのせ、スポイドで水を1滴かける。(プランクトンのような水生生物は、直接スポイトでとって1滴たらす)。試料が重ならないように、柄つき針やピンセットで広げておくようにする。
- 柄つき針を左手に持ち、試料の左側に密着させ、右手でピンセットを使ってカバーガラスを軽く落ちないようにはさむ。柄つき針の先端でカバーガラスの1辺を支えながら密着させ、気泡を追い出すようにしてふさいでいく(水が多すぎて、カバーガラスが浮いて移動してしまう場合は、ろ紙をちぎってカバーガラスの端につけて水を吸収する)。
観察結果(スケッチする)
感想