
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 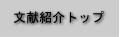 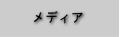   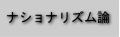 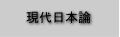
政治学
アプター・デヴィッド、内山秀夫訳(1965=1968)『近代化の政治学』 未来社
1950年代から1960年代の末まで、政治学の大きな潮流であった政治的近代化論。本書は、その中でも代表的な研究者といえるデヴィッド・アプターによる、政治的近代化を包括的に論じた大著です。アプターの議論は、欧米社会を近代化のゴールとして捉えるのではなく、近代社会は全て変動の過程にあるという認識のもとで展開されているので、ステレオタイプ的な近代化論批判(近代化論は、欧米社会を第三世界の発展のモデルとして提示した議論にすぎない、という批判)は乗り越えていると言えるでしょう。
が、それにしても、読みにくい。これは訳者のせいだけではなく、アプターの原文からも派生しているのだと思います(アプター自身の英語論文を読んだことがありますが、とても分かりにくい文章を書く人でした)。そんなわけで、本書を全部読もうとすると、ものすごいエネルギーが必要になります。読む人は、覚悟を決めて読むように。(2000年5月)
阿部斉(1991)『概説 現代政治の理論』 東京大学出版会
政治学の教科書というと、(初学者にとっては)非常に難解なものが多く、僕も何度も挫折しました。が、この阿部さんの本はとても分かりやすく、スッキリとまとまっていて、大学院の試験の時にはずいぶんお世話になりました。安部さんの教科書といえば岩波のテキストもあるのですが、こちらの方がより理論の説明に重点が置かれています。結局、難しいことを難しく書くのはそう難しいことではなく、難しいことを易しく書くことの方がずっと難しいわけで、いい教科書を書くというのは結構難しいことなのかもしれない、と思いました。(2000年5月)
石田雄(1968)『平和の政治学』 岩波新書
戦後日本社会において最も重要な価値として捉えられてきた「平和」。本書は、ただ「平和」が大切だ、というだけではなく、「平和」ということが何を意味するのか、そこにいかなる問題があるのかを論じています。古い本だけあって、問題点はいくつかあるように思われます。しかし、戦後日本社会を批判するあまり、「平和」ということをあまりに軽んじて戦争を賛美する愚劣な議論が横行する中、本書は今なお読むべき価値のある本だと言えるでしょう。(2000年5月)
石田雄(1990)『市民のための政治学』 明石書店
1989年、1990年の選挙における社会党の躍進を受けて、市民はいかにして政治にコミットしていくべきなのかを分かりやすく説いた本です。その後の政治状況の変転から、社会党あらため社民党は見る影もなくなってしまい、本書の意義もかなり薄れてしまったような気がしないでもないですが、それでも政治学や日本政治の入門書としてはよく書けている本なのではないでしょうか。また、社会党に媚びず、その問題点もきちんと指摘していることにも好感が持てますね。(2000年5月)
石田雄(1995)『社会科学再考』 東京大学出版会
日本を代表する政治学者の一人である石田雄さんが、戦後における社会科学(特に政治学)の流れを自らの研究の展開と重ね合わせながら整理した好著。近代化論など戦後政治学における重要問題のみならず、環境問題やジェンダー問題など最近の研究動向にまできちんと踏み込んでおり、非常に勉強になる本です。このように言っては失礼かもしれませんが、このお年にしてなお新たな研究の潮流を自らの内に取り込んでいかれる知的な貪欲さには頭が下がるばかりです。適当なところで研究を降りてしまう人が多いなか、石田さんのそうした姿勢は日本の社会科学者がぜひとも見習うべきものだといえるでしょう。(2000年5月)
ヴィンセント・アンドルー、重森臣広訳(1995=1998)『現代の政治イデオロギー』 昭和堂
自由主義、保守主義といった伝統的な政治イデオロギーからフェミニズムやエコロジズム、ナショナリズムといったイデオロギーまで、その由来や変遷などを網羅したテキストです。無政府主義などのあまり触れられることのないイデオロギーまで紹介されていて、勉強になりました(普通に考えられているほど、無茶苦茶なイデオロギーではない)。また、ファシズムに関する章では、イタリアのファシズムとドイツのナチズムの違いが明快に示されていて、両者を区別せずに論じるのは良くないと思いました。政治とイデオロギーはやはり切り離せない関係にあるわけで、その意味でも政治を学ぶためのよき参考書になるのではないでしょうか。(2000年5月)
ヴェーバー・マックス、脇圭平訳(1919=1980)『職業としての政治』 岩波文庫
政治における「心情倫理」と「責任倫理」との峻別の必要性を説いた、あまりにも有名なヴェーバーの公演をまとめたものです。別にこんなところで紹介する必要もないほどよく知られた本なのですが、現代の日本の政治家を見るに、ヴェーバーの言う「権力の中に身をひそめている悪魔の力と手をむすんだ」にもかかわらず、「それにもかかわらず!」と言うつもりのない連中が多すぎるのではないか、と思うわけです。あるいは、「政治の倫理がしょせん悪をなす倫理であることを」をあまりにも認識しなさすぎる人の多さにも問題があるのではないでしょうか。ともあれ、本書は、政治とは何かを考えるさいの最初の一歩となる書物であり続けていると思います。(2000年5月)
上杉忍(2000)『第二次大戦下の「アメリカ民主主義」』 講談社選書メチエ
第二次世界大戦において、アメリカにおける「自由」はどこまで保証されていたのか。「自由の国」を標榜する国家だからこそ直面するジレンマにおいて、著者はアメリカの自由を「国益を最優先させる制限的市民的自由論」として描き出します。もっとも、それは「戦争時には自由は抑圧されても仕方がない」などという単純な原理ではなかったわけですが、そこには黒人差別や日系人の強制収容、先住民への抑圧など、様々なジレンマや問題が内包されていました。戦争と自由という今日においても極めて重要な問題を考えるうえで、非常に面白い本だということができるでしょう。(2000年5月)
エーデルマン・マーレー、法貴良一訳(1985=1998)『政治の象徴作用』 中央大学出版部
政治においていかにシンボルは機能しうるのか。本書は、合理的な個人という通常の政治学の想定を脱し、シンボルの作用によって動かされる極めて非合理的な人間像を描き出しています。人々は自らの利益を合理的に計算し、それを政治に反映させているのではなく、様々なシンボルによって動かされる、ほとんど影響力をもち得ない存在に他ならない。そして選挙とは、人々が「政治に参加している」という意識を抱くための儀式でしかない、というわけです。意識やシンボルといった問題を扱っているので、やや理解が難しい個所があるのですが、かなり面白い本だと言えるでしょう。また、次のような指摘はかなり重要であるように思われます(本書18ページ)。「ある人が安堵感を覚えるものが別の人にとっては脅威となる以上、間違いなく、あらゆる人々にとって脅威はつねに存在する。」「人は常に危機の時代に生きているのであり、誰もが新聞を読むようになってからはなおさらだ。」(2000年5月)
カー・エドワード、井上茂訳(1939[1981]=1996)『危機の二十年』 岩波文庫
僕が読んだ政治学の本のなかでも(そんなにたくさん読んでいませんが)最も感銘を受けた一冊。国際政治におけるユートピアニズムを厳しく批判する一方、権力のみに基づく国際政治観をも排しながら、第二次世界大戦へと到る国際政治過程を分析しています。現代日本において読まれるべきポイントはやはりなんといっても、「平和」に関する記述やナショナリズムについての考察ではないかと思いますが、それ以外にも、国際政治を考えるうえでは外せない見解が満載されています。あと、ちょっと面白いと思ったのが、ユートピアニズムに対抗するものとしての権力政治観を代表するものとして、マルクス主義が挙げられているという点でしょうか。現代日本ではマルクス主義とはユートピアニズムの代名詞のような感すらありますが、同じ思想に対する評価も時代によって大きく異なるのだなぁ、と思いました。(2002年3月)
加藤哲郎(1986)『国家論のルネサンス』 青木書店
国家を単なる上部構造として捉える旧来のマルクス主義国家論は、1970年前後から大きな変化を遂げてきました。本書はそうしたマルクス主義国家論の「ルネサンス」の動向を分かりやすく論じています。僕もその代表的な論客であるプーランツァスの『資本主義国家の構造』を読んだことがあるのですが、あまりの難解さに途中で止まったままになってしまっています(でも、あの本が理解できないのは、僕の責任ではないような気もする…)。そんなわけで、この加藤さんの本のおかげでかなり助かりました。あと、ネオ・コーポラティズムに関する議論も勉強になりました。もっとも、ちょっとあまりにマルクス主義的色彩が強い本なので、閉口してしまうところもあるのですが…。(2000年5月)
カーノイ・マーティン、加藤哲郎ほか訳(1984=1992)『国家と政治理論』 御茶の水書房
マルクス主義国家論の展開をマルクスやエンゲルスからグラムシ、アルチュセール、そしてプーランツァスやオッフェなどまで全般的に論じているのが本書です。が、この本を読んで教科書的にマルクス主義国家論を勉強しようと考えてはいけません。なぜなら、本書は非常に難解で、かなり予習をした後でないと読みこなせないように思われるからです。マルクス主義国家論については、ここでも紹介している加藤哲郎さんの『国家論のルネサンス』などから読み始めるのがいいかもしれません。そんなわけで、本書を読むにはかなりの気合が必要なわけですが、従属論などについても論じられており、マルクス主義国家論の全体像を把握するのには役に立つように思われます。(2000年5月)
加茂利男(1975)『現代政治の思想像』 日本評論社
古本屋で偶然見つけて、なんとなく購入したのですが、思いのほか勉強になった本です。システム論的な政治学が中心的なテーマになるわけですが、日本における戦後民主主義の問題や大衆社会論争なども扱っており、戦後政治学の潮流を学ぶ上ではかなり参考になる本だと言えるでしょう。計算すると著者の加茂さんがなんと30歳のときの著作ということですが、あと3年でこんな著作が僕に書けるのかなぁ、などと思うとかなり不安になる今日このごろです。(2000年5月)
コーンハウザー・ウィリアム、辻村明訳(1959=1961)『大衆社会の政治』 東京創元社
大衆社会に対して異なる二つの見方(大衆によるエリート支配、エリートによる大衆操作)を統合し、大衆運動の発生を中間的集団の孤立化という観点から分析している名著。このように書くと地味な内容であるかのように思われるかもしれませんが、実際、地味な内容の本です。が、それだけに大衆社会論のエッセンスがぎっちりとつまった本だということができるでしょう。また、大衆社会と民主主義という現代においてなお重要な問題を扱っているので、民主主義などに関して興味のある人にも参考になる本でしょう。大衆社会論に対しては様々な批判がなされ、現代においてはその使命を終えたとの見方もあるわけですが、僕としては、大衆社会論から学ぶべきものはまだまだ多く、それゆえに本書も読まれるべき本だと思います。(2000年5月)
杉田敦(1998)『権力の系譜学』 岩波書店
本書は、アメリカの政治理論(特に権力論)とフーコーの理論との対話や、政治学の最新領域であるアイデンティティ・ポリティクスなどを扱った論集です。普通、フーコーの理論なんかを扱ってしまうとそればっかりになってしまうのですが、そこにアメリカの政治理論をぶつけてくるところに本書の野心的な特徴があると言えるでしょう。また、リベラル−コミュニタリアン論争の論点もわかりやすく抽出されているので、最新の理論に疎い僕には非常に勉強になりました。(2000年5月)
杉田敦(2001)『デモクラシーの論じ方』 ちくま新書
現代的なデモクラシーのあり方について、対話形式で綴られた入門書。一方が近代主義的なデモクラシーの支持者とすれば、もう一方がポスト・モダン的なより徹底したデモクラシーの支持者ということになるように思います。言い換えれば、一方が代表制に基礎を置く議会制民主主義にわりと忠実なのに対し、もう一方が代表制に縛られない、社会のなかのより多様な声を集めることに主眼を置く民主主義を目指している、ということができるでしょうか。非常に対立点がクリアに抽出されており、何が問題になっているのかを理解するのにはうってつけと言えるでしょう。欲をいえば、もっと保守的な発想の持ち主が混ざって、デモクラシーそのものに否定的な見解でもって前2者とのバトルを繰り広げてもらえるともっと楽しかったかと…。そうなると、収集がつかなくなるかな? (2001年10月)
ダール・ロバート、高畑通敏訳(1991=1999)『現代政治分析』 岩波書店
僕にとっては思い出の一冊。というのも、昔、僕がまだ学部生だったころ、僕の指導教授と一緒にこの本の原著であるModern
Political Analysisを読んでいたからです。あの頃はダールの英語で苦労していましたが、今にして思えば、とても読みやすい英語を書く人です。さて、本書は戦後アメリカ政治学を代表する一人であるダールがテキストとして書いたものです。原著も版を重ねており、この訳書の元になったのは第5版です(ちなみに僕が読んでいたのは第4版でした)。影響力という政治学における基本的な概念について詳細に論じ、また、ダールの有名な「ポリアーキー」論について簡潔に論じられています。さらに、ダールの権力論を批判したルークスの見解についても触れられており、その点も興味深いのではないでしょうか。(2000年5月)
ドイッチュ・カール、伊藤重行ほか訳(1966=1986)『サイバネティクスの政治理論』 早稲田大学出版部
政治過程を情報の流れという観点から分析するとどうなるか、というのが本書のテーマです。いわゆるサイバネティクスの政治学への応用ということで、かなり抽象的な議論が展開されるので、具体的な政治の動きなんかに興味がある人にはオススメしません(この、実際の政治との関連ということがこうした議論の弱点の一つのなのです)。が、もちろん、こうしたアプローチにはそれなりの良さがあって、たとえば政治システムが自己閉鎖に陥った場合に生じる危険性などに関する議論はかなり興味深いものがあります。つまり、政治システムから「不要な情報が過度に排除されてしまった際には、情報のネガティブ・フィードバックが不可能になり、その結果、政治システムの暴走が始まる、ということです。具体的に言えば、自らの方針に反するような言論を弾圧する政治体制は、自己を見失ってしまうということです。あれっ、こう書くと結構当たり前のことだなぁ。でも、なんかあるとやたら一致団結したがる人の多い日本社会には重要なことなのだと思うのですが。(2000年5月)
ヒゴット・リチャード、大木啓介ほか訳(1983=1987)『政治発展論』 芦書房
第二次大戦後にアメリカ政治学を席巻した政治的近代化論の発展、挫折、そして従属論の登場、といった学説の流れを把握するのに便利な一冊。なぜか非常に難解な本(訳書?)が多い政治的近代化論だったりするわけですが、本書は非常にわかりやすく、政治的近代化論にどういう問題点があったのか、従属論がいかなる背景のもと登場したのか、また従属論の問題点は何か、などが明快に論じられています。そして、政治的近代化論や従属論が国家の政策的な側面に対してあまり注意を払っていなかったということから、公共政策論に注目する必要性が説かれるわけです。あと、しっかりとした訳者付論もあり、本書の問題点を論じているので、そちらの方も参考になります。(2000年5月)
ベル・ダニエル、岡田直之訳(1960=1969)『イデオロギーの終焉』 東京創元社
「イデオロギーの終焉」という流行語(?)を産み出したほど、大きな反響を呼んだのが本書です。ダニエル・ベルというと、脱産業化社会論の論客で、やや軽い研究者と受け止められているような気もするのですが、本書を読めば実はかなり深い学識を持った人だということが分かります。もっとも、この「イデオロギーの終焉」には様々な批判が寄せられていて、「イデオロギーの終焉」自体がプラグマティックな自由主義イデオロギーだということも言われたりするわけですが、批判するにせよ、受け入れるにせよ、とにかく読んでおくべき本だと思います。また、なんだかんだ言っても卓見が随所に散りばめられているので、なかなか勉強になること間違いなしだとは思うのですが。(2000年5月)
三宅昭良(1997)『アメリカン・ファシズム』 講談社選書メチエ
ファシズムといえばイタリアやドイツのそれが一般には思い起こされるわけですが(実際にはファシズムとナチズムはかなり違う)、アメリカにもファシズムが存在したのだ、というのが本書です。本書の主人公(?)であるヒューイ・ロングは、1930年代に知事や連邦上院議員としてルイジアナ州に独裁に近い体制を打ち立て、大統領の座をも狙った人物です。デマゴーグと強引な政治手段によってルイジアナ州民の圧倒的支持を獲得する一方、州内の言論の自由を弾圧し、司法権までも手中に入れました。中でも面白かったのが、ロングがルーズベルト大統領と激しく対立し、議事妨害のために十五時間半の演説を連邦議会で行なった、という下りです。冒頭から合衆国憲法を読み上げ、それに解釈と分析を加えていき、挙句の果てには、カキフライの揚げ方やごみ箱をどうやって料理鍋に代用するか、ということまで話したそうな。とても読みやすく、面白い本で、アメリカ政治のあまり知られてない一面が語られています。また、ファシズムとは何か、それはいかなる時に生じてくるのか、という分析は現代日本の政治状況を考える上でも参考になるのではないでしょうか。(2000年5月)
ミューラー・クラウス(1973=1978)『政治と言語』 東京創元社
政治現象を言葉やコミュニケーションといった観点から分析し、現代社会における政治的なコミュニケーションの歪みを告発した名著。特に官僚制の発達する社会において、いかに政策の正当化が推し進められていくのかについての分析は非常に面白く、現代の日本政治を見る上でも参考になる本だと思います。たとえば、吉野川の可動堰に関する政府の「科学的合理性」という主張は、まさしく本書が描き出すテクノクラート支配の構図にぴったりと当てはまるということができるでしょう。ものすごくいい本なので、古本屋で見つけたら逃さず買っておきましょう。(2000年5月)
ミリバンド・ラルフ、田口富久治訳(1969=1970)『現代資本主義国家論』 未来社
1970年前後における「マルクス主義国家論ルネサンス」の先駆けとなったのが本書です。ミルズの『パワー・エリート』の国際版とも言われる本書は、アメリカのみならず、西欧諸国においてエリートがいかにして支配を行なっているのかをマルクス主義の観点から論じています。ミリバンドは国家を企業支配の道具として見るわけですが、ただし、企業全体の利益を保護するために個々の企業の利益に反する行動を国家がとる可能性がある、と指摘しているところが本書の特徴だと言えるでしょうか。このような道具的国家観を有するミリバンドは、国家を権力抗争のアリーナと見なすプーランツァスと有名な「プーランツァス・ミリバンド論争」を繰り広げるわけですが、プーランァスの本が難解を極めるのに対し、このミリバンドの本はとても読みやすい本だということが出来るでしょう。もっとも、その後のマルクス主義国家論の展開では、ミリバンドよりはむしろ、プーランツァスの方が重視されているようですが…。(2000年5月)
ミリバンド・ラルフ、北西充訳(1982=1984)『イギリスの民主政治』 青木書店
マルクス主義国家論を代表する一人、ミリバンドの手による、主に20世紀のイギリス政治に関する著作です。要するに、イギリスの政治がいかに資本家や政治エリートといった一部の支配層によって牛耳られてきたか、ということですね。既存の体制を根底から否定するような言説はマスコミによって黙殺され、労働組合は体制内化されていき、労働党も既存の支配体制を転換させることはできなかった、とミリバンドは論じています。これは、おそらく、この本が出版された当時に吹き荒れていたサッチャリズムの嵐に対するミリバンドの危機意識の表明と見ることもできるでしょう。ただやはり、「今の社会は一部の支配層によってコントロールされている」ということがまず結論としてあり、そこからすべての話が組み立てられている、という印象は拭えませんね。もちろん、そういう傾向はどの著作にもあるでしょうが、この本の場合、その度合いがちょっと強すぎるのではないか、と思うわけです。話の流れがクリアすぎる、とでも言ったところでしょうか。(2002年12月)
メロッシ・ダリオ、竹谷俊一訳(1990=1992)『社会統制の国家』 彩流社
本書は、政治学というよりも社会学的な観点から、現代国家における社会統制のあり方について論じた著作です。第一部ではマキャベリやホッブズに始まり、ルソーやヘーゲル、マルクス、デュルケム、ウェーバー、グラムシなどヨーロッパ系の論者による国家と社会統制に関する議論を整理し、第二部ではシカゴ学派やパーソンズ、ミルズなどの社会統制に関する見解を論じています。僕自身としては、特に第二部では近代的自我と社会統制との関係について、ミードとフーコーの比較などを行なった議論が面白かったです。また、「動機の語彙」というミルズの議論の面白いところを引っ張ってきているところにも著者の目配りの良さが伺えます。(2000年5月)
ラスウェル・ハロルド、久保田きぬ子訳(1951=1959)『政治』 岩波書店
アメリカ政治学を代表する政治学者であるラスウェルの手による、政治学の入門書(?)と言えるでしょうか。戦前のアメリカ政治学といえば、そのほとんどが政治制度のあり方を論じていたのに対して、ラスウェルは「社会的尊敬」「収入」「安全」をめぐって競合する人々の行動や心理のあり方に実証的にアプローチしようとするわけです。本書はそうしたラスウェルの発想を知る上で便利な本だと言えるでしょう(もっとも、あまり刺激的であるとは言えない本ですが…)。なお、この訳本では重要な用語の原語が何かが分からないので、図書館などで原著を用意しておいた方が良いように思います。(2000年7月)
ラスキ・ハロルド、飯坂良明訳(1948=1974)『近代国家における自由』 岩波書店
イギリスを代表する政治学者のひとりであるラスキの手による、「自由」のための書。ラスキは本書で、自由がいかに重要であり、自由の喪失が政治や社会にどのような害悪をもたらしうるのかを説いています。正直に言って、ものすごく刺激的な本だとは言い難いように思いますが、興味深い点がないわけではありません。たとえば、ラスキのいう「自由」に、経済的平等に対する要求が含まれるという点があります。つまり、新自由主義などで言う「自由」が「貧困の自由」をも容認するのに対し、ラスキは「貧困からの自由」を説いていると言えるでしょうか。いわば、同じ「自由」という言葉で、全く反対の内容が表現されたりするわけです。また、社会的危機や戦時に「言論の自由」を保持することがなぜ重要であるのかを論じた個所は、マスコミ論としても読むことができます。すぐに「一億火の玉」になりたがる日本社会を考えるうえでは参考になるのではないでしょうか。(2002年12月)
ルークス・スティーヴン、中島吉弘訳(1974=1995)『現代権力論批判』 未來社
本書において、ルークスは権力についての三つの見方を提示しています。本書の重要なポイントは、その中でもルークスが「三次元的権力観」と名づける権力に対する見方でしょう。つまり、権力の客体に対して、その真の利益を認識させないようにする権力と言えるでしょうか。言い換えれば、不利益を被っている人々に、彼らが不利益を被っていることを認識させないような権力ということです。そして、ルークスによれば、これこそが最も狡猾な権力の行使なのであり、無意識的に行使される権力なのだとか。実際の分析に使えるかどうかはまだわかりませんが、なかなか面白い指摘だと言えるのではないでしょうか。(1998年)
|

