
法政大学社会学部メディア社会学科 津田研究室
 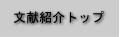    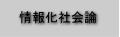 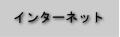
カルチュラル・スタディーズ
石田佐恵子(1998)『有名性という文化装置』 勁草書房
現代社会に跋扈する有名人、彼ら彼女らの存在を支える<有名性>とは、いったいどのような原理で成り立っているのか。本書では、メディアによって日々生み出されてゆく<有名性>の正体を明らかにすることで、現代社会における文化や共同体のあり方を問い直しています。また、カルチュラル・スタディーズの展開についても簡潔にまとめられており、その点に関しても参考になりました。ワイドショーなどちょっと珍しい題材を扱ってはいるものの、キワモノ的な内容に陥らず、しっかりした土台の上にある議論だと思いました。が、テーマや問題関心など、その意気や良しというところなのですが、もう少し踏み込んだ分析をすれば、もっと内容に深みが出たのではないか、とも思いました。(1998年)
サイード・エドワード、板垣雄三ほか監修、今沢紀子訳(1978=1993)『オリエンタリズム(上)(下)』 平凡社ライブラリー
西欧が東洋を知るために創始された東洋学。学問という形で客観性を装いつつ、東洋への偏見やステレオタイプを内在させた知のあり方(オリエンタリズム)への批判を本書でサイードは展開しています。膨大な量のテキストの分析によって導き出されたオリエンタリズムという概念は、社会学の範囲を超えて一般にまで広がりつつあると言えるでしょう。しかし、この本を読むのははっきり言ってたいへんです。忙しくて時間がとれなかったということもあるのですが、私はこの2冊を読むのに一ヶ月半かかってしまいました。しかし、読み終わったあとの充実感は相当なものです。この本もやっぱり、巻末(下巻)の解説から読むことをお勧めいたします。 (1997年)
スイングウッド・アラン、稲増龍夫訳(1977=1982)『大衆文化の神話』 東京創元社
本書ではまず、「大衆社会」や「大衆文化」がどのように語られ、論じられてきたのかをミルズやアドルノといった批判的な系譜とベルに代表される脱産業社会論の系譜との両方から論じていきます。「大衆文化や大衆社会は存在しない。あるのは、大衆文化と大衆社会に関するイデオロギーだけである」(本書p.168)という言葉に集約されているように、著者は静的で受動的な大衆の姿を前提とする「大衆文化」という概念には極めて批判的であり、そこから批判学派の研究を厳しく批判します。また、脱産業社会論にしても、それがペシミズムに陥るにつれて、そうした批判学派と視座を等しくしていった点を指摘しています。そして、よりダイナミックでより能動的な大衆像、社会像を描き出そうとするわけですが、このような視点はカルチュラル・スタディーズの視点と重なるように思います。その意味で、批判的な研究系譜からカルチュラル・スタディーズへの展開を見るうえでは参考になる文献ではないでしょうか。(2002年5月)
ターナー・グレアム、溝上由紀ほか訳(1996=1999)『カルチュラル・スタディーズ入門』
作品社
ここ数年、日本でも盛んなカルチュラル・スタディーズ。「カルチュラル・スタディーズとは何ぞや?」と興味をお持ちの方にオススメ…、と言いたいところなのですが、この本、入門というにはちょっと難しいかも、という気がしないでもないです。正直、カルチュラル・スタディーズに関して何も知識がない人がこの本をよんですっきり理解できるかといえば、僕には何ともいえないわけです。ただし、カルチュラル・スタディーズについてなんらかの知識をもってはいるものの、イマイチよく全体像がみえない、という方にはかなりオススメできる本です。この本を読むまで、僕も何かすっきりしないものがあったわけですが、この本のおかげでかなり明確になりました。もっとも、そうした全体像とか一貫性を求めること自体、カルチュラル・スタディーズの理念には反していたりもするわけですが…。(2000年9月)
ホガート・リチャード、香内三郎訳(1957=1974)『読み書き能力の効用』 晶文社
カルチュラル・スタディーズにおける古典的名著のひとつ。20世紀前半のイギリス労働者階級の生活を、「下からの視点」でいきいきと描き出しています。また、雑誌やラジオなどが人々の生活にどのように溶け込んでいったのかを見る際にも参考になる著作です。もっとも、ホガート自身がよく認識しているように、労働者階級の人々を理想化しているという批判もあり、人々の実際の生活を描くことの難しさということを痛感させられることも事実です。あと、イギリス社会に興味がないと、これをきちんと読むのはちょっと辛いかな、という気がしないでもないですね。(2002年3月)
李孝徳(1996)『表象空間の近代』 新曜社
日本三景などのいわゆる「名所」を書かない風景画はいかにして成立したのか、本書はこうした問題意識から、日本における遠近法の導入、文学における風景描写の変化などを分析してゆき、近代を可能にした「視点」の成立を論じてゆきます。そこから、「日本」がいかにして人々の心の中に生み出されてきたのかをメディア、交通、そして、御真影などの分析を行なっています。明治以前には、今日のような単一の存在として「日本」は捉えられておらず、人々の帰属意識は藩レベルであったことは広く指摘されていますが、それがどのようにして今日のような「想像の共同体」としての「日本」が相互主観的に生み出されてきたのかを本書は詳細に論じています。本書の傾向としては、私の主観なのですが、大澤真幸氏の影響をかなり色濃く受けているように感じました。そのせいか(?)、ちょっと分かり難いところもあるのですが、かなり面白く読めました。(1998年)
|

