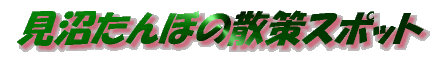
【氷川女体神社】
(ひかわにょたいじんじゃ)
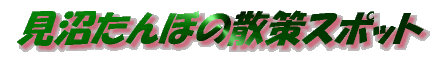
|
国昌寺橋から「氷川女体神社1.2Km」の道標に従って見沼たんぼを突っ切って西に進みます。 が、あれれ、芝川まで来るとここの道標は橋もないのに芝川を指してます。そうです、ここには以前新葭野橋があったのですが今はありません。 仕方がないので、芝川沿いに右にちょっと進んで見沼大橋を渡り、見沼代用水西縁に架かる敬助橋まで出て、見沼代用水西縁に沿って戻ります。 しばらく行くと赤い橋が見えてきます。これが氷川女体橋です。そしてこの橋の先の急な階段を上ると氷川女体神社です。 本殿は、鬱蒼とした森の中に立てられていて、格式の高さが感じられます。神額には、金色で「武蔵国一宮」と書かれています。 |
 |
 |  |
|
【歴史】 「氷川女体神社」
氷川女体神社は、埼玉県内屈指の古社で大宮氷川神社とともに武蔵国一宮といわれてきた。社伝では、崇神天皇の時につくられたと伝えられている。祭神は奇稲田姫命で、大己貴命と三穂津姫命が合祀されている。 大宮の氷川神社(男体社)、大宮市中川の中山神社(簸王子社)とともに見沼とは深い関係にあり、祭礼の「御船祭」は見沼の船上で行われていた。しかし、享保十二年(1727)に見沼が干拓され、これに代わって出島で「磐船祭」が行われるようになった。 この氷川女体神社には、鎌倉、室町時代の社宝が多く、三鱗文兵庫鎖太刀(国認定重要美術品)、牡丹文瓶子(埼玉県指定有形文化財)、大般若波羅密多経(同)、神輿(同)は特に著名である。 江戸時代には社領50石が寄進されており、現本殿は徳川家綱によって再建された。 また、境内の社叢は、浦和市指定天然記念物であるとともに埼玉県のふるさとの森として保護されている。 (氷川女体神社の掲示板から)
【見沼の伝説】 「鏡池と片目の魚」
この宮本の氷川女体神社の前、見沼代用水路西縁に架かる赤いらんかんの橋を渡って、まっすぐに行くと、その先は円形の広場になっています。周りを堀で囲み、上から見ると柄鏡のような形になっています。この池に住む魚は、みんな片目なのだそうです。そのいわれは、この神社の祭神であるクシイナダヒメが、戦いで負傷し、片目が見えなくなってしまったからなのだそうです。 また、別の話としては、クシイナダヒメがあやまってハスの茎で目を突いてしまい、片目が見えなくなってしまったから・・・・・という話なども伝わっています。 なお、そのために見沼たんぼではハスの栽培をしない風習ができたといいます。また、この池の魚を取ると神罰があるというので誰も取る人はなかったということです。 (氷川女体橋の掲示板から) |