初めての本格的登山は御嶽山であった。
御嶽山は、長野県と岐阜県にまたがり、東日本火山帯の西端に位置する標高3,067 mの複合成層火山である。
独立峰で活火山である。
2014年9月27日に7年ぶりに噴火して山頂付近にいた登山客が巻き込まれたのは記憶に新しい。
ウィキペディアによると、
「遠く三重県からも望め「王御嶽」(おんみたけ)とも呼ばれていた。古くは坐す神を王嶽蔵王権現とされ、修験者がこの山に対する尊称として「王の御嶽」(おうのみたけ)称して、「王嶽」(おうたけ)となった。
その後「御嶽」に変わったとされている。
修験者の総本山の金峯山は「金の御嶽」(かねのみたけ)と尊称され、その流れをくむ甲斐の御嶽、武蔵の御嶽などの「みたけ」と称される山と異なり「おんたけ」と称される。
日本全国で多数の山の中で、「山は富士、嶽は御嶽」と呼ばれるようになった」
ということである。
その御嶽山へは、1971年8月22日に串本から夜行列車を乗り継いで、麓でタクシーを頼み登山口まで行き、登りだした。
登りだした御嶽山は晴れると思えばガスって来、やはり3000mを越える山のすごさを感じた。
御嶽山は山岳信仰の山である。
ウィキペディアでは、
「通常は富士山、白山、立山で日本三霊山と言われているが、このうちの白山又は立山を御嶽山と入れ替えて三霊山とする説もある。
日本の山岳信仰史において、富士山(富士講)と並び講社として庶民の信仰を集めた霊山である。
教派神道の一つ御嶽教の信仰の対象とされている。
最高点の剣ヶ峰には大己貴尊とえびす様を祀った御嶽神社奥社がある。
鎌倉時代御嶽山一帯は修験者の行場であったが、その後衰退していった」
とある。
一緒に登った3人のうち、一人が高山病にかかりかけ、少し停滞したが持ち直したので、無事登頂し下山することが出来た。下山は濁河温泉側に下り、温泉に入って疲れを癒した。
3000mm級の山は初めてだったので最初は心配であったが何とかクリアできた。
この当時の登山スタイルは今では考えられない軽装備で、天候が持ってくれたので助かったが、当時の服装で悪天候の時はかなり厳しかっただろうと、写真を確認してつくづく感じた。
なにせ45年前の登山であり記憶も定かでなく、写真の前後もわからない。
最近でも少し高い山に登っているが、3000mを越える山に登ったのは、この御嶽山だけでそれ以来これを超える山には登っていない。

(いきなり雲が湧いてくる) |

(途中で麓が見える) |

(噴火で吹き飛ばしてきた) |

(たくさんの人が登っている) |
 |
 |
 |
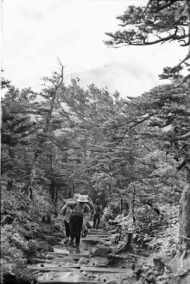
(えっちらおっちら登る) |

(ガスって何も見えないときもあった) |
 |
 |
 |
 |
 |
|