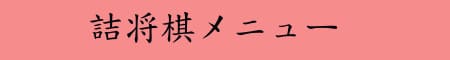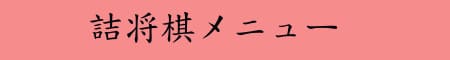詰将棋で使用される駒は、通常は、普通の将棋で使用される駒40枚のうち、攻め方の王を除
いた39枚です。駒の動かし方は、普通の将棋と同じです。但し、以下のような独特の決まり
があります。
- 初形で、盤面に配置された駒と攻方の持駒として示された駒以外は全て玉方の持駒とみなす。
- 攻方が常に先手。
- 攻方の手は必ず王手であること。
- 攻方の手はあらゆる玉方の手を考慮した上で、最も早く詰めることの出来る手を選ぶこと。
- 玉方は、必ず王手を避けること。王手を避ける手段がなくなった時点で詰みとみなし終了。
- 玉方の手は、攻方のあらゆる手段を考慮の上、詰みを避けられるか、詰む場合でも最も手数の長くなるような手を指すこと。
- 6で、最も手数が長くなる手順が複数存在する場合、その中で攻め方に駒が余る手順と余らない手順があれば、余らない手順を採用する。
- 玉方は、単に手数を伸ばすだけの無益な合駒(*注意1)はしないこと。
- 二歩、打歩詰、行き所のない駒などは通常の将棋と同様に禁じ手。
- 攻方の手が千日手(過去の経過局面と盤面と持駒が全く同一)または、持駒減少型千日手
(過去の経過局面と盤面と攻方持駒が減少)を引き起こす手であるときは、禁じ手とする。
- 玉方の手が、持駒増加型千日手(過去の経過局面と盤面と攻方持駒が増加)を引き起こす手で
あるときは、禁じ手とする。
以上のルールに基づいた上で、ある詰将棋の図面に対する詰め手順を探し出す作業を「詰将棋を解く」という。
また、詰将棋というのは通常、上記のルールに従って解いていけば、必ず単一でかつ最後に攻め方の駒が余らない詰め手順がみつかるようになっている。複数の詰め手順が存在するもの、最後に駒が余ってしまうもの、または、詰みがないものは、不完全作として図面に異常があると判断される。
また、攻方の玉が登場する詰将棋もある。その場合、手順の過程で攻方の玉に王手がかかったときは、王手を避けながら相手の玉に王手をかけなくてはいけない。その他は上記ルールと同じです。
*注意1
無益な合駒の判断は以下のような判断が一般的である。
- 本来の詰手順に対して、合駒をする玉方の手と合駒を取る攻方の手が加わるだけで、他に何も影響がない合駒。
- 合い駒が相手に渡って、後に盤面同一かつ攻方の持ち駒に合い駒が加わっただけの局面が出現する場合。