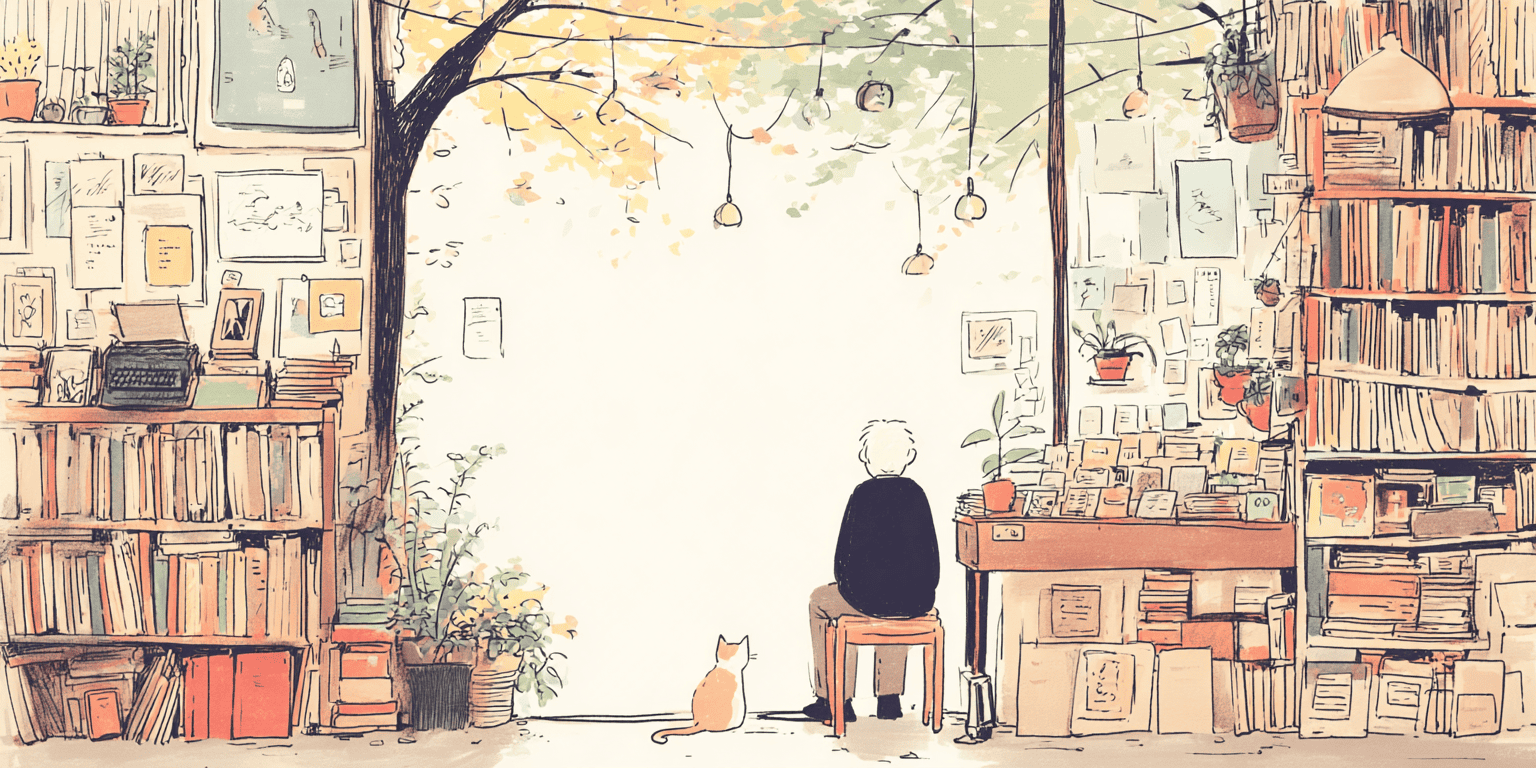おじさんと猫
「ミュー、ミュー、ミュー」と、おじさんのお腹に耳を当てると、いつでも子猫のなく可愛い声が聞こえました。おじさんは、暖かな時でもフカフカとした茶色のセーターを着ていて、その中に捨てられた子猫を飼っているのです。 「ミュー、ミュー、ミュー」と鳴いている子猫たちが動くと、おじさんのセーターがもぞもぞと動きますそれがおもしろくて、おじさんのお腹のところを触っていると、子猫がセーターの間から顔を出すことがあります。 おじさんのお腹の中の子猫には、目がパッチリとしたものもいれば、目も顔もぽってりとして、お団子のような顔のものもいました。目の色が、片方ずつ違う猫もいました。右目が空色をしていて、左目が鳶色をしているのです。そんな子猫たちのほとんどが、街中で捨てられた猫でした。 おじさんは町のはずれの、古本屋さんの主人です。たくさんの本が置いてある本棚の奥で、一人、静かに本を読んでいるのが常でした。そんなおじさんのお腹の温もりがうれしいのでしょう。子猫たちはセーターの中で甘えるように「ミュー、ミュー、ミュー」と鳴きます。その声を音楽にしながら、おじさんは本を読むのです。 「子猫が鳴いてもぞもぞと動くから、眠くらならなくていいのさ」と、おじさんは笑いながら話します。 時々、立派になってお店の中をうろつく猫が、子猫を押しのけて、セーターの中に無理やり入ってくるときがありました。おじさんのお腹の温もりが恋しくなったのでしょう。お腹に入ると「ミュー、ミュー、ミュー」と子猫のように甘えた声を出します。そんなときは、おじさんのお腹がとても大きく膨れているので、すぐにわかりました。 おじさんのお店には、おじさんが育てた猫がたくさんいて、おじさんの古本屋は別名「猫屋敷」と呼ばれていました。お店にはたくさんの猫がわがもの顔で寝転んでいたり、歩いていたりします。それでもどの猫も本棚にある本に悪戯をすることはありませんでした。悪戯をしたら大好きなおじさんが困ることを知っていたのでしょう。 おじさんのお店の入り口には「子猫譲ります」という看板と「捨て猫反対」という看板が小さくかかっていました。できるだけ可愛そうな捨て猫をなくしたいのと、子猫たちを幸せにしてくれる飼い主を探すためです。おじさんは、子猫が少し大きくなると、お店に来る人や近所の人に子猫いりませんかと声をかけていました。 そんな子猫のいる店ですから、古本屋さんは子供達のお気に入りの場所でした。そして私もそんな子供の一人だったのです。よく小学校の帰りに、おじさんの店によって、子猫をなでたり、おじさんのお腹に耳を当てて、子猫の鳴き声をいつまでも聞いていたのです。 「子猫、可愛いな。私も飼いたいな」 私がそう言うといつでもおじさんは、少し笑ったような目で 「お母さんがいいといったら、いちばん素直で、可愛い子猫をあげるよ」といいました。 私の家はマンションだったので子猫を飼うことは無理でした。それに子猫も、自由に表を散歩できなかったらかわいそうです。それを知っているくせにおじさんは意地悪だと私は思って、少し頬っぺたを膨らませるのです。おじさんは、そんな私を見て一層目を細めるのです。 子猫のなかでも、私がとても気にいっている猫がいました。黒斑の愛嬌のいい猫です。私がおじさんの店に行くと、いつでも一番に近づいてきて、私に甘えて擦り寄ってくるのです。だから私も抱き上げて、その子猫と鼻を合わせます。するとその黒斑君は、小さな舌で私を舐めてくれるのです。でも、その子猫の顔は、お店のなかではいちばん可愛くなくて、その上、子猫のくせに少し太っていました。ですから、他の友達からはあまり好かれていなかったようです。けれど、私にはお店の中で一番の可愛い子猫。それで時々こっそりと、おいしい給食の残りを黒斑君にだけ特別に持って行って、食べさせたりしていました。 おじさんがとても真剣な顔で小さな漢字だらけの本を読んでいるときがあるので 「おじさんは、何を読んでいるの」 そう私が尋ねると 「これはプラトンという昔の哲学者の本だよ。」 と、いつもの優しいおじさんの顔に戻って、そんな風に答えるのです。おじさんはいつでも難しい哲学の本を読んでいました。おじさんは有名な大学の、有名な哲学の先生だったのだそうです。自分でもたくさん本を書いているんだと話してくれたこともあります。 「おじさんは、何で先生を辞めてしまったの」 そう私が尋ねると、 「猫を撫でながら本を読んだり考えたりしている時が、いちばん頭の中がすっきりするからだよ」 とおじさんは笑いながら話すのです。 時々、おじさんがそんな偉い先生だと知っている人が、おじさんに色々と教えてもらいにやって来ます。そんな時のおじさんは時間を惜しみません。1時間も2時間も難しい話を聞いた後、お店にきた人は喜んで帰っていきます。おじさんは時々、お土産だとばかりに、本を貸してあげたりもしていました。 「次までに、これを読んでおいで。きっと勉強になるから」 そんな時のおじさんは、子猫がお腹でもぞもぞと動いているいつもの姿とは違って、とてもかっこよく見えるのです。 けれどお店には、難しい本以外に子供向けの本もいっぱい置いてありました。そうして、私たちに好きなだけ本を貸してくれたのです。ですからおじさんのお店には子供達も多く集まっていました。中には本を選んでいるうちにとても面白い本に出会って、立ったまま読んでいる子供もいました。おじさんはそんな私たちの様子をみては、にこにことしていました。 私もおじさんのところから、たくさんの本を借りて読みました。おじさんに、「面白そうな本は」と聞くと、いつもいつも私に合った本を勧めてくれました。そしてそのどれもこれもが面白いのです。今考えれば、おじさんは私達一人ひとりの様子をちゃんと見ていてくれたのでしょう。その時々に私に一番必要だった本を選んでくれていたのです。ですからおじさんから借りた本はどんどん頭の中に入ってきて忘れられなくなるのです。 「おじさんはどうして、ただで私達に本を貸してくれるの」 私は一度聞いてみたことがあります。 「楽しい水まきだよ」とおじさんは答えました。 私にはさっぱりその意味がわかりません。それでぽかんとしている私を見て、おじさんは言葉を続けるのです。 「子供達の心はまるで春の大地の様に、たくさんのものが勢いよく芽をだそうと準備をしているのさ。そんな楽しい大地には、きれいな水や栄養をあげれば、暖かな南風と太陽が集まってきて、土の中に眠るものが顔を出して、すくすくと育っていくんだ。その勢いには本当に驚くばかりだよ。本の中にはそんなほかほかとした大地に必要な水や栄養がたくさんつまっているから、それをみんなの胸にたくさん注ぎこんであげたいんだよ。」 「ふーん」 やっぱり私にはおじさんが何を言っているのかが、分かりませんでした。けれどおじさんが私達のことが大好きで、私達のためにいろいろ考えてくれていることだけは分かったのです。 私がある絵本を読んでいた時です。その絵本は私の一番のお気に入りの本で、すべてのページが私の大好きな絵で飾られていたのです。それで、思い出した様にその本をとりだしては、私は眺めていたのです。私は「フーッ」とため息をつきながら、おじさんに言いました。 「いいなあ、私もこんな絵がかけるようになればいいのに。どうすればこんな素敵な絵が描けるようになるんだろう。いいな。」 「ため息なんか似合わないよ」とおじさんが笑いながら言いました。 「絵が上手になる一番の方法を教えてあげようか。それは、絵を大好きなることだよ。そうして何度でも何度でも自分で絵を書いてみることさ。最初は、その本の絵を真似てね。何回も何回も書いているうちに目と自分の手とがつながって、きっとうまく書ける様になるもんだよ。あせっちゃ駄目だよ。諦めちゃだめだよ。何万回でも書いてみることさ。そのためには絵が大好きにならなければいけないんだよ。」 そうして、おじさんは、私が持っていた本を閉じて取り上げて、それからもう一度私にその本を丁寧に手渡してくれました。 「絵が大好きになることを約束してくれたら、この本をあげるよ。」 「おじさん、ほんと。」 「でも、これは、二人だけの秘密だよ。皆に本をあげていたら、読んでもらう本がなくなってしまうからね。」 「おじさん、ありがとう、絶対、絵が好きになる」 そう言いながら、私はおじさんと指切りをしました。絵を好きになる自信があったからです。決して針千本を飲んだりすることはないと思ったのです。 指きりの後、おじさんは言葉をつづけました。 「おじさんも、実は絵を書くのは大好きなのさ。子供の真白なキャンバスの上に、本という絵の具で素敵な色をつける。すると、そのキャンバスは生きているから、面白い様に動き出したり、おじさんが考えたこともない綺麗な色に輝き出しすんだ。おじさんはそんな一人ひとりのキラキラとしたキャンバスをみていることが、とても楽しくてしょうがないんだよ。」 おじさんの言うことは相変わらずよくわかりませんでした。私が素直にそう言うとおじさんはニコニコしながら、楽しそうに本に目を戻しました。 私にとっては、そんなとてもお気に入りの場所の古本屋さんですが、町のみんなが猫を好きなわけではありません。時々おじさんの本屋に文句を言いに来る人もいます。 「あなたが猫を預かるという噂をきいて、隣の町からも猫を捨てに来る人がいるというじゃありませんか。この町はあなたのせいで、猫だらけ。うるさいし、くさいったらありはしない。早く保健所に引き取ってもらってください」 そんなときのおじさんは、黙って文句を言う人の話しに耳を傾けているだけです。 「怒っている人のお腹の中には、おこりんぼの鬼がいて、それが時々さわぎだすのさ。その鬼が疲れて黙るまで、話しをきいてあげればそれですむのさ。」 おじいさんはよくそう話していました。 今日も、私が本屋にいると、文句を言いにきた人がいて、最後には「この変人」と捨て台詞を残して帰っていきました。そんなことを言う大人の人の心がとても悲しく思えて、私は少し泣きそうになりながら、おじさんの方を眺めました。その様子に気がついたのでしょう。おじさんは、私の頭をなでて、「だいじょうぶだよ」と声をかけてくれました。 「おじさんが捨て猫を飼うことは、悪い事なんかじゃないよね。」 私は聞きました。おじさんはゆっくりと言葉を継ぎます。 「捨て猫を飼うことが、いいことなのか悪いことなのか、正直私にも分からないよ。確かに猫が嫌いな人には迷惑をかけるだろうからね。けど、ほら見てごらん。」 そうしておじさんはお腹の中から猫を取り出しました。 「ほらこの猫の目の中に映るものが見えるかい」 おじさんの暖かいお腹から出されて、とまどったようにミューミューと鳴くその子猫の目の中には、本棚と、それから私の顔も映っていました。 「これから、この子猫はどんな世界を見るのだろうね。例えば人間が気づかない、道端の小さな花や水溜りに写る自分の面白い顔。おいしそうないわし雲も、春の木漏れ日のやさしさも、きっとその目の中に入るんだ。この子猫もそんなたくさんの美しいものを瞳に映し出すように生まれてきているんだよ。おじさんはそれを護ってあげたいだけなんだ。そうしてたくさんの綺麗なものを映した瞳は、七色のガラスのように透き通って、やがて美しい空のお星様になるんだよ。猫も人間もきっと変わるものじゃないんだ。」 おじさんは、一息ついて、 「子猫たちの見る世界がいつでも美しい世界であればいいのにね」といって、もう一度私の頭をなでてくれました。 猫たちもおじさんにかわいがられていた時のことが忘れられないのでしょう。もらわれていった先から、懐かしくて時々この店に戻ってきます。おじさんは、もらわれていった猫たちの顔も全部覚えていて、猫たちがやってくると、セーターの中にいれてあげるのです。すると大人の猫も子猫に戻ったようにミューミューと鳴いておじさんに甘えます。おじさんはそんな猫たちに声をかけてあげます。 「どうした、誰かに意地悪でもされたのかい」 やがて、気が済むまで、セーターの中で鳴いていた猫たちは、自分から顔を出して、家に帰っていくのです。おじさんは歩き去る猫たちを見送りながら声をかけます。 「寂しくなったらいつでも、遊びにおいで」 猫たちもその声に応えるように尻尾を振りながら帰っていきます。そんな猫たちにはもう、おじさんのセーターの中で鳴いていた甘えん坊の様子はありません。どこに出しても恥ずかしくない立派な大人の猫の姿なのです 「おじさんて魔法使いみたい」と私はおじさんといっしょに猫を見送りながら、いつも思うのでした。 時々は、おじさんの家の居心地が良くなってしまうのでしょう。2日も3日も家に戻らない猫がいます。そんな時でもおじさんは、何も言わずに猫を家においてやります。他の猫たちも勝手しったるものとばかりに、いつもと変わらずに過ごしています。 長い間、自分の猫が帰ってこないときには、だいたい飼い主の人がこの古本屋にやってきます。猫がいなくなったときには、このお店にいることがわかるからです。 猫を探しにきた飼い主は、まず決まっておじさんに相談します。すぐに連れて帰っていいものか、それとももうしばらくお店に預けておいた方がいいものか。するとおじさんは猫を抱き上げ「お前はどうしたい」と猫にたずねるのです。そうして「もう2、3日ここで遊びたいようですね」とか、「今日の夜には自分で帰るそうですよ」と、猫の言葉を飼い主に伝えるのです。 初めてそんなおじさんの言葉を聞く飼い主の人は、半分疑いながら帰って行くのですが、おじさんの言葉のとおりに猫が戻ってきたりするので、誰もおじさんを疑わなくなるのです。 普段は仲のよいお店の猫たちですが、時々、毛を逆立てながら、にらみ合っているときがあります。そんな猫の喧嘩の様子を私がハラハラとしながら見ていると、おじさんが猫たちの間に入って言葉をかけるのです。すると興奮していた猫たちの気分もだんだんと収まって、最後には顔をすり合わせていつものように仲良しに戻るのです。そんな様子を見ていると、おじさんは本当に猫の言葉がわかるのかなと不思議に思ってしまいます。 そんなある日のことでした。私は学校で一番仲の良い友達とけんかをしてしまいました。いつも一緒に遊んでいる友達で、喧嘩など一度もしたことはなかったのですが、ほんとうにつまらないことで、言い争いをしてしまったのです。 「もうマリちゃんとは口をきかない。絶対口きかないからね。」 放課後、私たちの他には誰もいなくなった教室で私はそう言うと、一目散に教室を飛び出しました。ほんとうはすぐにでもマリちゃんと仲直りをしたいことは、自分でもわかっていたのですが。それでも私のお腹の中の怒りんぼの鬼が、まだまだ力一杯動き回っていて「ぜったい私からは誤らない、マリちゃんが悪いんだから」と思っていたのです。 私は家にまっすぐ帰る気にもなれず、帰り道の川原、一人で座ってぐずぐずとしていました。大きな赤い太陽がゆっくりと空からすべり落ち初めて、少し冷たい風が私の肩に触りました。その風に怒りんぼの鬼も少し静かになって、私は楽しく遊んでいるマリちゃんのことを思い出していました。 その時です。後ろの方から私の名前を呼ぶ声がしました。それは聞き覚えのある古本屋のおじさんの声だったのです。私は後ろを振り返りました。 「どうしたんだい。こんなところで。」 おじさんは買い物がてらに、散歩にきていたのでしょう。手には、白いビニール袋を下げていました。 「おじさん。」 私の中で急に寂しさがこみあげてきました。私は少し泣き出しそうになりながら、おじさんにさっき学校であったことを話しました。そうして、お腹の中で怒りんぼの鬼たちが暴れていて、マリちゃんに素直に謝れそうもないことを。 おじさんは、私の話しを静かにうなずきながら聞き終わると、こう言いました。 「そうかい。ほらこちらにおいで。おじさんが素直になれる魔法をかけてあげるよ。」 そうして、何だろうと思い私が近寄ると、おじさんは私を抱き寄せて、頭から、いつも猫が入っているセーターをすっぽりとかぶせてくれたのです。 セーターの中は、猫のにおいがして、たくさんの子猫たちと一緒にいるようでした。そうして、セーターの中はとても暖かくて、その中にいるとどこかとても懐かしい気がしてくるのです。私のお腹の鬼もすっかりと素直になりました。私は悲しくなって子猫の様に、おじさんのセーターの中で甘えて泣いていたのです。 すっかりと泣いて、とても素直になれた私は、おじさんのセーターの間から顔を出しました。そうして恥ずかしさを隠すために 「私も、猫と一緒だね」 と言ったのです。おじさんは何も言わずに私の頭を撫でてくれました。 それから、私はおじさんとさよならをして、一目散に家までの道を走って帰りました。さっきまでは足がとても重かったのに、今は魔法の靴を履いたように足が軽く思えました。 家につくと直ぐに、私はマリちゃんに電話をして、さっきのことを謝りました。マリちゃんも、私との喧嘩がとても気になっていたようです。電話の向こうで何度も「私の方こそごめんね」と繰り返していました。 私はそれからも、毎日のようにおじさんの古本屋に通っています。おじさんは私とマリちゃんの喧嘩のことなんて覚えていないように、いつもと変わらず子猫をお腹に入れて本を読んでいます。 もう少しすると、私の家では家族が一人増えます。小さな小さな赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいるのです。 「赤ちゃんが産まれたら、このマンションからは引っ越さなければいけないね。」 とお父さんとお母さんは話しています。 「そうしたら、大きくなくていいから、猫が飼える一軒家に引っ越して。」 と私はお願いしています。その願いが果たしてかなうかどうかは分からないのですが、猫を飼えるようになったら、あの私のお気に入りの、少し不細工な黒斑の猫にするのだと、私は固く心に決めているのです。
# 童話 / おじさんと猫