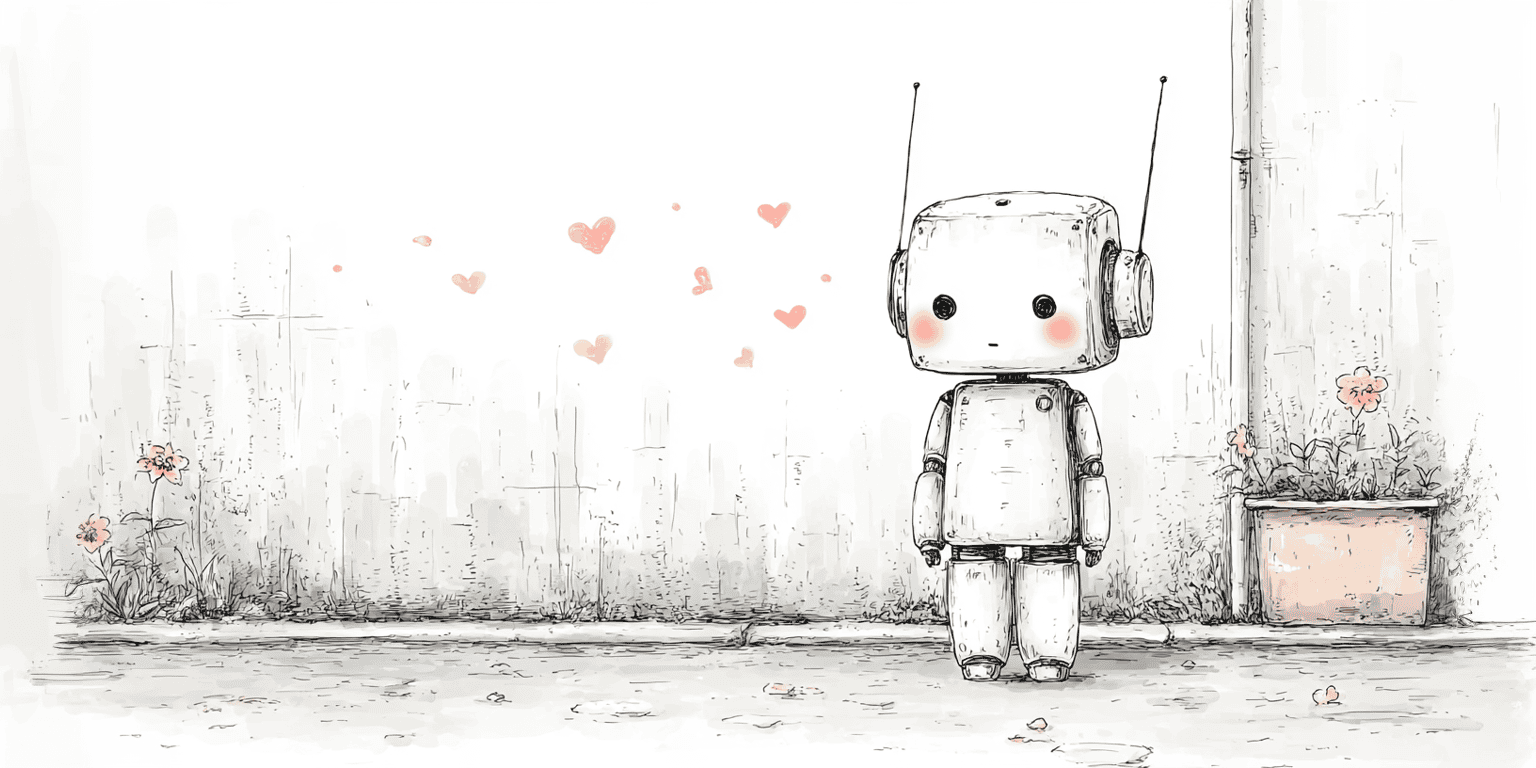僕のロボット
それはちらちらと白い粉雪が舞い落ちてくるクリスマスイブの夜でした。僕の家では綺麗なクリスマスツリーが飾られて、テーブルにはお母さんと僕とで作った、小さなケーキが置かれました。 時計の針が8時を鳴らすころには、おいしそうな料理もテーブルに並び湯気をたてていました。僕はお父さんの帰りを待ちわびて、時計を5分ごとに見たりとそわそわしていました。そんな僕の様子を見て、お鍋を洗ったりしていたお母さんはクスリクスリと笑っていました。 素敵なプレゼントをくれるサンタさんがお父さんだと分かったのは、小学校3年生だった去年のことです。そして今年は、「クリスマスのプレゼントを楽しみにしておいで」そう言いながらお父さんは家を出たのです。それで僕はその日一日を、クリスマスプレゼントのことで頭を一杯にしながら過ごしたのです。 「お父さんは何をプレゼントしてくれるんだろう。僕がこの前デパートでかっこいいと思った車のプラモデルかな」 でもそんなことはお父さんには話していないので、きっと違うのです。 「それとも僕の好きなおもしろい本」 僕はそのころ子供向けの推理小説を読むことが好きだったからです。 「でも本は図書館でも借りられるし、それとも僕がかわいいねとお父さんと話した手乗りの小鳥。 それとも、それとも……」 そんな風に僕は一日落ち着かずに、お父さんの帰りを待っていたのです。 8時をだいぶ回った頃、玄関の方で音がしました。お父さんに違いありません。それで僕は一目散に玄関にかけていき、ドアを開けました。お父さんは僕の頭をなでながら 「ただいま、よくベルを鳴らす前に帰ってきたのがわかったね」 そう言いながら、大きな箱を僕に渡してくれました。 「ほら、お前の一番欲しがっていたものだぞ。 重いから気をつけてな」それは僕が考えてもいなかった、自分の背丈よりも大きな箱だったのです。 「ねえ、すぐに開けてもいい」 僕はもうとても待ちきれなかったので、お父さんの「いいよ」という返事を聞く前に、箱を開けてしまいました。すると、大きな箱の中から出てきたのは、銀色の四角の体に四角の頭を乗せた大きなロボットでした。頭からは黒くて短いアンテナのようなものが伸びていて、丸い目がどこか笑っているようです。びっくりしている僕をニコニコと眺めながらお父さんは、 「さあ、早くおなかのとこにあるスイッチを押してごらん」 そう言いました。それで僕はおそるおそる、ロボットのおなかのスイッチを入れてみました。するとロボットのお腹の中で何かが動くような音がしたかと思うと、目がピカピカと光り、ロボットは箱の中から自分の足で出てきました。そうして僕の方を向いて 「こんばんは、京助君」と言ったのです。 ロボットが何故僕の名前を知っているのでしょう。僕は少し驚きながら「こんばんは」と応えました。するとロボットは丸い目を一層丸めて、うれしそうに「今日はクリスマスイブの夜ですね」と応えたのです。ロボットはすでにたくさんの言葉を知っていて、上手に会話をすることができたのです。僕の名前はお父さんが、家に帰ってくる前に教えていたのです。ロボットは、どんどん新しい言葉を覚えるように作られていました。 「京助。お前の一番欲しがっていた弟だよ」 お父さんはそんな僕とロボットの様子を見てニッコリと笑いながら言いました。 ロボットは歩くたびにギシギシと音を立てました。それで僕はそのギシギシという音と僕の名前を合わせ、ロボットのことを「ギシ助」と名づけました。ロボットはその名前をとても気に入ったようです。時々、思い出したように「ギシ助っていい名前だね」と言うのです。だから僕もギシ助という名前がとても好きでした。 お父さんはギシ助を僕の弟として買ってきてくれました。けれどギシ助は、僕のことをすっかりと弟のように考えていました。その頃はギシ助の方が僕よりも背が高く、ギシ助の方がたくさんのことを知っていたからです。だから、ギシ助は時々お兄さんのように言います。 例えば僕が高い塀の上を歩いていたりすると 「京助君、そんなことをしていたら危ないよ。高いところから落ちたら足の骨を折ったりするよ。足の骨を折るとギブスをつけなければいけないから早く下りておいで。」 「うるさい、ギシ助。落っこちないから大丈夫だよ」 そんなときに僕は少し腹を立てました。 けれど、お父さんとお母さんには内緒で、宿題を教えてくれるときのギシ助はほんとうに頼りになりました。昼間遊びすぎて、まぶたが重く、宿題をやらないで眠ってしまった日。目覚めると机の上に出しっぱなしの宿題がすっかりと片付いていることもありました。ギシ助が先生に怒られないようにとやってくれたのです。 僕の方が背が高くなった後も、ギシ助はいつまでも僕のことを弟のように思っていました。 そんな僕とギシ助ですから、ギシ助が来た日からどこへ行くにも一緒でした。寝るときにも一緒で、僕の布団の隣にギシ助が横になるのです。僕が眠につくまで、ギシ助と僕はいろいろな話しをしました。学校のこと、友達のこと、僕が将来サッカーの選手になりたいこと、頭に浮かんできたことすべてをです。そうして眠れないときなどは、しりとりをして遊びました。ギシ助は僕よりもたくさんの言葉を知っていて、しりとりではいつも僕が負けてしまいます。それで僕は、悔しいまま眠ることもありました。 僕がおやすみを言って部屋の電気を消すと、ギシ助は静かになります。けれどギシ助のお腹のなかからは、何かが動くような音がいつまでもしていて、それが僕の一番の子守唄でした。ただ、寝返りをうって触るギシ助の体はごつごつとして冷たく、その冷たさに目を覚ましてしまうこともありました。 僕が学校に行っている間は、ギシ助は家でお母さんのお手伝いをしていました。ギシ助の手は人間の手と同じように5本の指があって、家の掃除をしたり、洗濯物を干したりもできます。何よりギシ助は力があったので、重いものをもったりするときには大助かりでした。お母さんに頼まれて一人で買い物にいくこともありました。僕みたいに買ってきて欲しいものを忘れないので、お母さんは安心して買い物を任せていました。 「ギシ助はほんとうにいい子ね」お母さんからそう誉められるときのギシ助は、いつもうれしそうでした。それで気をよくしたギシ助は、こっそりと広告のチラシを見ては、 「今日はお肉が安いよ」とお母さんに教えたりしていました。 お手伝いと言えばこんなこともありました。僕がその日の最後の理科の授業で、試験管を持って実験をしている時でした。さっきまでは晴れていた空に大きな雲がもくもくと近寄ってきて、窓の外が暗くなったかと思うと、大粒の雨が降ってきたのです。その朝、学校に行くときには空はピカピカに晴れていたので、僕は傘など持って出ませんでした。置き傘もありません。 帰るときにも雨足は一向に衰える気配がありませんでした。それでしかたなく友達に「また明日」と挨拶をして、僕は走って校門を出たのです。雨の勢いはとても強くて、ほっぺたに当たる雨粒が痛いぐらい。僕の髪や背中のカバンはぐっしょりと濡れてしまいました。僕はカバンの中の教科書だけは濡れないようにと一生懸命走ったのです。 そうして家までの道をしばらく来ときです。遠くに見覚えのある姿が立っていました。ギシ助です。「ギシ助はきっと僕に傘を持ってきてくれたんだ」そう思いました。その証拠にギシ助の右手には、僕のお気に入りの青い傘が握り締められていました。 「おーい、ギシ助、僕はここだよ。」 雨音で僕の声に気づいていないのでしょうか。ギシ助は傘を持って立ったままです。「おかしいな」と僕は思いながら、ギシ助の側に走っていきました。 「どうしたのギシ助。僕に気がつかなかったの。」 ギシ助に近寄って傘を受け取ろうとすると、ギシ助が 「よかった、間に合って。京助君が穴に落ちて怪我しなくて。」 それて僕がギシ助の足元を見ると、確かにギシ助の立っているすぐ後ろに、小学生が入れるぐらいの穴があいているんのです。きっと工事中の看板を立てておくのを忘れてしまったのでしょう。 「よかった、間に合って。京助君が穴に落ちて怪我しなくて。」 もう一度そう言うと少しほっとしたように、ギシ助は僕に傘を手渡してくれました。 ギシ助は、突然雨が降り始めたことに気がづいて、僕に傘を届けようと家を出たのです。けれどその道の途中、この穴が開いているの見つけて、僕が穴に落っこちはしないか心配になって、ここで待っていてくれたのです。ギシ助はどれぐらいの長い間、ここに立っていたのでしょう。小さな傘に入りきらないギシ助の肩は雨に濡れて、体がいつもよりも冷たく感じられました。 「ありがとう、ギシ助」 青い傘をさしながら僕がそう言うと、ギシ助は、いつものようにうれしそうな様子で、 「よかった、間に合って。京助君が穴に落ちて怪我しなくて」 そう繰り返しました。それから今度は、手に持った自分の傘で穴をふさいで、傘が飛ばないように重石の石をのせました。 「ギシ助、それじゃあ君が濡れちゃうよ」 ギシ助が何をしているのかわからなかった僕にギシ助は答えました。 「こうすれば、京助君の友達も穴に落ちなくてすむでしょう」 ギシ助が僕の友達にも「穴があるから危ないよ」と、声をかけてくれたことを知ったのは次の日でした。その日、友達の間でもギシ助は人気者になっていて、僕は少し得意げでいられました。 ギシ助と一緒にピクニックに行ったこともありました。山の上にある湖の側に小さなロッジがあって、そこに家族皆で泊まったのです。まだ夏休みが始まったばかりの頃。お父さんが運転している車の窓を開けていると、とてもさわやかな風が僕の顔を一杯にしました。 初めて車に乗るギシ助も、窓の外の風景がどんどんと変わっていく様子を、とても楽しそうに見ていました。そうしてときどき、「京助君、楽しいね」と僕の方を見ながらつぶやくのです。そんなギシ助の様子をみていると、僕ももっと楽しくなれました。 僕らの目的地の湖に近づくにつれ、山道のカーブもきつくなり、ギシ助はときどき車の座席の上でひっくり返っていました。「助けてよ、京助君」そんなギシ助の、ほんとうに困ったような様子を見て、お父さんもお母さんも楽しそうに笑っていました。 小さなロッジで過ごしたのはたったの3日間でした。けれどお天気にも恵まれて、近くの花畑に行ったり、湖で釣りをしたりと、それはほんとうに楽しい毎日でした。きっと僕一人だけだったら遊び相手もいなくて、そんなにも楽しくはなかったでしょう。今でもそのときに撮ったギシ助との写真は大切な宝ものです。 ギシ助はたくさんの花の名前を知っていて、 「このお寺の鐘のような花が釣りがね草、たくさんの白い花を咲かせているのが虎の尾。ね、虎のやわらかな尻尾みたいだろう」 そんなふうに花を指差しては、一つ一つ教えてくれました。 僕がたくさんの花の香りにつつまれて横になっていると 「京助君、目を閉じて、大きく口を開けてごらん」 そう言うギシ助の声が聞こえて、その言葉どおりにした僕の口の中に、ギシ助はどこからか摘んできた木苺の実をどっさりと入れてくれました。噛みしめると素敵な味が口一杯に広がりました。 「これ、何? 甘酸っぱくておいしい。」 そんな僕の言葉にギシ助は自慢げな様子でした。 「そんなにおいしいかい京助君」 「うん、ほんとうにおいしい。ほっぺたが落ちそうだよ」 口を真っ赤にしてよろこんでいる僕の様子を見て、ギシ助は少し悲しそうな顔をしました。 「京助君。僕が人間だったら、一緒に木苺を食べられるから、もっと楽しいのにね」 僕は一瞬、言葉につまりました。そんな僕を見て、ギシ助はまた、いつもの明るい様子に戻って、 「ほら、まだこんなに木苺が残ってるんだよ。一杯積んできたから」 そうして、僕の手に残りの木苺をくれました。ギシ助が摘んできてくれた宝石のようにきれいな木苺を、僕は一つづつ大切にほおばりました。けれど、その味はどこか悲しくて、さっきのようにおいしくは感じられませんでした。僕はギシ助の胸の底の悲しい部分に触れてしまったみたいで、少し泣き出したくなりました。 それもとある夏休みの午後のことでした。僕が自由工作で作った竹細工の飛行機を、となり町の原っぱで飛ばしていると、その飛行機が強い風に吹かれて大きな木の天辺に引っかかってしまったのです。空は真っ青に晴れていて、真っ白な雲も楽しげに泳いでいます。けれど、僕だけが、ひっかかってしまった飛行機を見上げながら泣き出したい気持でした。飛行機は昨日の夜、お父さんに手伝ってもらって、ようやく出来上がったばかりだったのです。 そんな僕の様子を見ていたギシ助が 「まっていてよ京助君、僕が今とってきてあげるから」 そう言って大きな木の幹につかまったのです。 「危ないからいいよ。ギシ助。」 止めようとする僕の言葉を聞かずに、ギシ助は太い幹をゆっくりと上り始めました。 「京助君の大切な飛行機だろう。」 僕の心配をよそに、ギシ助はぐいぐいと木の上に登って行き、やがて生い茂った葉の中に姿が見えなくなりました。僕が大丈夫かなと心配していると、やがて飛行機のひっかかっている枝の所からギシ助が顔を出しました。そうして飛行機に手を伸ばした瞬間です。ギシ助の乗っていた木がギシ助の体重をささえきれずに折れてしまったのです。ギシ助は勢いよく、木の上から落ちてきました。僕の心臓はバクバクとなりました。ギシ助の体は銀色にギラリギラリと光ります。ギシ助が地面に落ちたとき、ドスンという大きな音が僕の耳に届きました。僕は飛行機のことなどもう考えていませんでした。ただ、ギシ助だけが無事ならばと思っていました。 僕がギシ助のそばに走りよると、ギシ助はむっくりと起きあがって 「ほら飛行機をとってきたよ」 と僕に言いました。折れた木と一緒に飛行機も落っこちてきたのです。 「よかったギシ助。体は何ともないかい」 「僕は大丈夫だよ。京助君。」 そう言ってギシ助は少し目を細めていつものように笑いました。けれどその日からギシ助は、少し脚を引きずりながら歩くようになりました。その様子を見るたびに、僕は少し胸が痛みました。 ギシ助が僕の家に来てからもう4年が過ぎました。小さな僕でしたが、それでも僕の体は年を追うごとに少しずつ大きくなりました。それとは逆にギシ助の体にはあちらこちらに傷ができて、最初に家に来たときのピカピカの体はどこか汚れたように見えました。歩くときのギシギシという音も、昔より大きく聞こえるようになりました。それでもその傷の一つ一つは僕とギシ助の大切な思い出を語ってくれます。僕はギシ助の腕や足を眺めながら、「ギシ助、これはピクニックに初めてでかけたときに、転んでできた傷だね」そんなことを独り言のように話します。そうしてギシ助はそのときの様子をすべてはっきりと覚えていて、僕が忘れかけていた楽しいことまで思い出させてくれました。 時々、ギシ助の傷が急に痛そうに思えて気になってしまい、ゴシゴシとその傷を擦ってみたこともありました。けれどギシ助の傷は二度と消えずに体の上に残ったままで、それが急に悲しく思えてしまうこともありました。 そんなある日のことでした。たいへんな事件が起こったのです。ある町で買い物をしていたロボットが急に人を殴ってしまい、怪我をさせたというのです。テレビに映ったロボットはギシ助と同じ姿をしていて、僕は小さな声で「ギシ助?」と言ってしまったほどです。 テレビの中ではアナウンサーが告げていました。 「この型のロボットが今後も同様の事件を起こす危険性も否定できず、メーカー側では各家庭に注意と製品の回収を呼びかけています。」 ギシ助にとても大変なことが起きていることは僕にもわかりました。けれど僕はこわくて何もきけずに、すぐ自分の部屋に閉じこもってしまいました。心臓が大きな音で頭の中を響き、テレビで見たギシ助と同じ姿のロボットの顔が、目の中に何度も浮かんでは消えていきました。 お父さんとお母さんは僕らが寝てしまった後に二人でギシ助のことを話していたようです。けれど僕にギシ助を返せとはとても言えなかったのです。 そうしてそのニュースはギシ助の耳にも入っていたのでしょう。いつものように二人で寝ているときに、ギシ助がつぶやくのです。 「ねえ、京助君。僕が知らない間に京助君やお母さんに怪我でもさせてしまったら、僕はとても悲しくなるよ」 僕は何も応えられずに、布団の中で息をこらして固くなるばかりでした。 そうしてついに、その日が来たのです。僕は学校から帰ってくると、教科書の入ったカバンを机の上に置いて、いつものように、ギシ助に声をかけました。 「ギシ助、ただいま」 けれど、返事がありません。きっとお母さんに頼まれて買い物にでも出かけているのでしょう。けれどその日は、なぜかギシ助がいないことがとても心配に思えました。それで台所にいたお母さんのところに走って行って、たずねたのです。 「ねえ、ギシ助はどこへ行ったの?」 するとお母さんは、 「そう言えばだいぶ前に買い物を頼んだんだけど、まだ帰ってこないわね。どうしたのかしら。」 その言葉を聞いて僕の胸は高鳴りました。僕は一目散に外に駆け出していたのです。ギシ助が買い物にでかけたはずのお店に向かって。 しばらく走っていくと、道のところにたくさんの人だかりができていました。僕にはそこにギシ助がいることがわかりました。僕はその人だかりまで駆けて行くと、「どいて」と大きな声を上げながら、人の間に割り込んでいきました。そうして人と人との間から、壁を背にしょって、ギシ助が銃を持った警察の人たちに囲まれているのが見えたのです。ギシ助はとても怖がっていました。 「僕がギシ助を守ってあげなくっちゃ、だってギシ助は何も悪いことをしていないんだ。僕の一番の友達なんだ。」 そう思いながら僕は大きな大人をさらにかきわけながら、 「ギシ助、ギシ助」と呼びました。そうして「ギシ助をいじめないで」と力一杯の声で叫んだのです。 僕のその声にギシ助は気がついたようです。ギシ助は僕の方を見ました。そうして人と人との隙間から、僕らの目線が合いました。その瞬間ギシ助は、どこかほっとしたように、うれしそうに笑ったのです。その時です。銃口が赤い動物の舌のようにいっせいに火花を吹いて、ギシ助は空中に舞ったのです。 「ありがとう、京助君」 僕の耳に空に舞ったギシ助の言葉が残りました。 ギシ助の側に駆けよると、僕は何度も何度もギシ助の名前を呼びました。僕のギシ助は穴だらけになって、もう動きませんでした。僕は「ギシ助、起きてよ、ねえ、起きてよ」と泣きながら、冷たい体やあの少し不自由になった足を揺らしていました。 「ごめんよ、坊や。この型のロボットはあちこちで事件を起こしているんだ。それにロボットはとても力があるから、もし本気でかかってこられたら、人間ではとてもかなわないんだよ」 銃を撃った人はすまなそうに、僕の頭をなでてくれました。 けれど、僕だけにはわかっていたのです。ギシ助が他のロボットのように、人に暴力を振るったりはしないこと。だってギシ助は、いつでも僕のいいお兄さんでいようとしてくれたからです。 その後のことはもうあまり覚えてはいません。ただ、夕焼けの中で車に乗せられ静かに運ばれていったギシ助の姿と、僕の肩を抱きながら家まで連れてきてくれた、お母さんの優しい手の感触だけをはっきりと今でも覚えています。 「ギシ助が、最後にありがとうっていうんだよ」 そう何度もお母さんに言いながら、僕は家までの道を泣きながら歩きました。それは僕が今まで歩いたどんな道よりも遠く、果てしなく思えました。 それからの僕は一人でたくさんの経験をしました。布団の中で、一人眠る夜には、ギシ助がいない寂しさを感じていました。 大人になった今でも、僕にはわからないことばかりです。ギシ助がそばにいて言葉を返してくれたら、どんなにいいだろうと、ときどき思います。 今でもギシ助が歩くときの、ギシギシという金属の音がすると、僕のギシ助が笑いながら歩いてくるような気がして、後ろを振り返ってしまうのです。 「僕こそほんとうにどうもありがとう。君に会えてよかった」 言えなかった言葉を、今でもギシ助に伝えたくって。
# 童話 / 僕のロボット