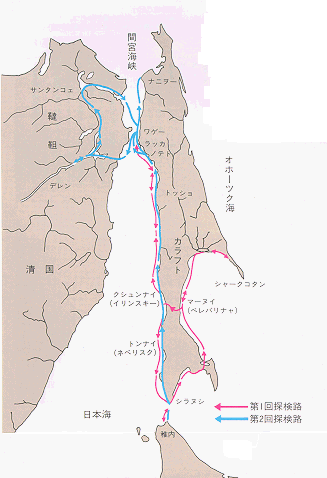 |
間宮海峡を発見
し、その名は現在でも世界地図上に明記されています。測量技術、移動手段が貧弱で、なおかつ北方に関する知識も皆無という当時の日本にあって、林蔵の探検は命懸けの仕事であったことでしょう。しかし、これは幕府にとっては避けては通れない国防にかかわる重要な任務でした。不屈の精神と忍耐力により林蔵は、見事にその任務を果たしたのです。
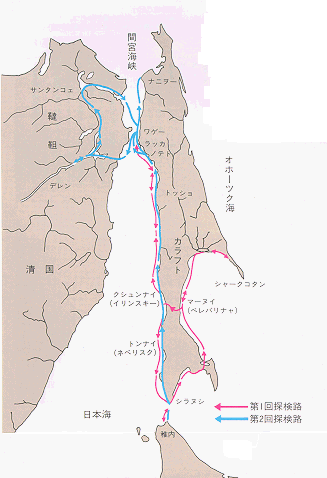 |
常陸国筑波郡上平柳村
に生まれました。名は倫宗(ともむね)号は蕪嵩(ぶすう)といい林蔵は通称です。林蔵は、父庄兵衛、母クマの間に一人っ子として生まれました。なかなか子宝に恵まれなかった林蔵の両親は、月読神社(現在の稲敷郡茎崎町)に詣で、林蔵をやっと授かったという言い伝えがあります。両親の愛情を一身に受けて育った林蔵は、幼い頃から神童と呼ばれ、幾つかのエピソードが語り継がれています。小貝川の堰止め工事の効果的な方法を教え幕府役人に認められ、江戸にでることになります。一人っ子として大切に育てられた林蔵ですから、いくら幕府役人に認められ江戸に修行に出るといっても、両親の思いは複雑であったに違いありません。蝦夷全土を測量
し、伊能忠敬の大日本沿海輿地全図(だいにっぽんえんかいよちぜんず)の北海道部分を完成させていることも大きな業績です。その成果はさらに、今日の北海道地図の基礎となる『蝦夷図』の完成となります。林蔵の『蝦夷図』には、主だった集落の名が驚くほど細かく記されています。林蔵が蝦夷地を測量した歳月は、何と12年間
にも及びます。このことは、とりもなをさず林蔵が、それらの土地土地を訪れていたのだということを意味しています。北海道の全市町村をくまなく、それも徒歩で廻る。それも正確に測量をしながら。林蔵は12年間、蝦夷地を歩き続けた
のです。誤った理解
です。勘定奉行川路聖謨(かわじとしあきら)
も林蔵の北方に関する知識を重要視し、親愛していたようです。彼が交渉に臨んだ日露和親条約締結が林蔵の北方に関する知識に助けられ、日本側が交渉を有利に進めたことはあまり知られていません。林蔵は、幕府役人として天保15年2月26日(1844)江戸の自宅で永眠します。享年65歳でした。その後の系図は次の通りです。
茨城伊奈間宮家(林蔵)−正平(鉄三郎)−梅吉−正倫−正倫−林蔵−雅章−正孝
東京間宮家 (林蔵)−孝順(鉄次郎)−孝義−馨−林栄
| ホームへ戻る |
| 目次へ戻る |