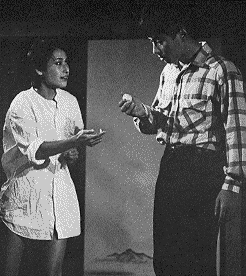

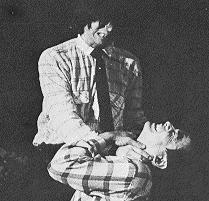
光永吉江(左)と藤堂貴也(右)
もたいまさこ(左)と渡辺えり子(右)
小野正隆(左)と藤堂貴也(右)
この文章は
三一書房刊「現代日本戯曲大系」月報12(1988・3)のために書かれました。
渡辺えり子
「ゲゲゲのげ」は、当時演劇雑誌「新劇」に連載していた、一話完結の童話の 中の、「酸っぱいビワの実吐き出せない」をモチーフにして書いた作品で、一九 八一年に発表した「夜の影-優しい怪談」の続編的意味合いを込めていた。
いじめられっ子マキオは「夜の影」の泡男とほぼ同一人物で、私の実際の弟 がモデルである。そして泡男の死んだ姉千草と、マキオの双子の姉一棄との関係 は、私逮姉弟の関係の見えない部分を増幅させていることも確かなのである。
私も弟もいじめられっ子であった苦い過去を持っていた。特に弟の方がひど い体験をしていた。いじめ、いじめられる関係の謎を解きながら、人間という生 き物の謎を解き、いつも大きな世界の犠牲にならざるを得えない、心優しく無垢 で名もない人々、つまり、はみ出すという事をよぎなくされる人々を描きたいと 考えていた。そしてそれが、弟を含めた声なき犠牲者達にとっての鎮魂劇として 昇華できないものかと思っていた
そこには、いじめる側の病んだ痛みも、いじめられる側が気付かぬうちに周 りに及ぽす加害的役割をも同時に描かねぱならないと考えていた。人は、その弱 さのために、常に立場を逆転させる恐さや醜さをも孕んでいる事を忘れてはなら ないと思っていたからでもあった。
「ゲゲゲの鬼太郎」という漫画の主人公を登場させたのは、鬼太郎というヒー ローが、単なるきれい事の正義の使者ではなく、死んだ妖怪の母親の腹を食い千 切って墓の中から這い出してきた魔性の少年であり、自分自身が汚れながら善業 と悪業の表裏一体を魂の中に抱え込む、孤独なダーティーヒーローであったから で、そうでなくては、痛んだ孤独な魂を救いあげ、見えない真実をあばき、主人 公の心の傷をえぐり出し、血を流させ、突き放すという、ある意味での残酷な役 割は果たせないのではないかと考えたからだった。
そしてもう一つ、当時江連卓氏率いる「幻想劇場」の役者だった小野正隆の 風貌が鬼太郎に良く似ていたという事があった。彼に鬼太郎を演じて貰いたいと いう遊び心が前述のテーマと一致したのだった。
劇団員の光永吉江が水木しげる氏に往復葉書を出した。葉書には、新作の中 に鬼太郎やその他の妖怪達を出演させて構わないかという旨が書かれ、「1良い 2悪い 3相談に応じる」この中の一つに丸をつけて送って欲しいと書いてあ った。多忙な水木氏を煩わせては申し訳ないという配慮からだったが、今考える と、子供っぽくて失礼な依頼書だったかも知れない。しかし当時の私達は、水木 氏はシャレの判る方に違いないから、きっと笑って送り返して下さるだろうとい う変な自信があった。そしてそれは的中し、氏から「1 良い」に大きな丸の印 がついた返事が返ってきた。
もう作品に取りかかっていたのだから、もしダメと言われていたらどうした のだろうとも思うが、なぜかダメなはずがないという妙な自信があったのだった 。
「ゲゲゲのげ」という題名には「下下下の下」という意味をかけていた。弟 の言った「中学までは人間じゃなかった。俺は高校に行ってから初めて人になれ た」という言葉が、忘れられなかったからである。
初演の稽古は大変な作業だった。役者一人ひとりの生き方や演劇観までを確 認し、さらけ出し、追いつめて行くような演出だった。仙太の役に抜擢した入団 したての男優は、「離人症」という不可思議な発作を起こした。真昼間に夢遊病 のような症状を見せるというもので、自分で自分が今どこにいるのか判らなくな ってしまうのである。
当時の私は、生きる事自体が演劇だと思っていた。劇団での芝居作りは哲学 だと信じ、自分自身も傷を負いながら、劇団の役者達にも同じ傷を与える作業を 強いていたように思う。そしてその代りに、全責任を自分が負うのだと考えてい た。役者の一人ひとりが精神的苦痛を乗り越えなければ、観客を楽しませること など不可能であると考えていた。
客の不幸を一手に抱き込み、昇華する役割を荷負うためには、役者自身が傷 ロを開き、痛みを越えて、優しさと強さを秘めなければならないと考えていたの だ。そうしなけれぱ、役者が自然と同化することばできないという主義があった 。
ーカ月ほどの稽古が終り、シアターグリーンの劇場入りの日、当時制作も兼 ねていた旗揚げメンバーのもたいまさこと光永吉江を呼んで、私は弱音を吐いた 。「思ったような作品に仕上がらなかった。これはもう駄作だと思う。中止にし たい」。その場には、当時の照明のスタッフ森田三郎氏も居たと思う。氏は、私 達の舞台芸術学院時代からの照明担当で、劇団の世話役も兼ねた存在だった。
三人は、いつものことだというように顔色も変えずにいたように思う。もた いが言った。「大丈夫。何があっても私達が責任を取るから、とにかくやろう。 みんな判ってる。判ってるんだから」。みんな大道具作りや仕込みのために徹夜 続きだった。そんななかで、私は又徹夜で愚痴をこぼし続けていたように思う。
シアターグリーンの小さな舞台に、本物の林と神社を作るという手品師のよ うな仕事を美術の松野潤氏がやってくれていた。私が幼児期に遊んだ山形のお山 王様という神社の境内がモデルだった。逢魔ケ時を体験したあの林は、この作品 に不可欠だった。
ろくに睡眠も取らないまま、初日の幕は開いた。中盤に少しだけ出演する私 は調光室にいた。劇団では昔から、自分が演出に力を注げるように、出番はいつ も中盤に少しだけと決めていた。作・演出と役者が両立できるような器用さがな いことを自分が良く知っていたからだった。
芝居が始まっても、三十人ほどの客はくすりともしない。笑えるはずの場面 でも、息一つ聞こえないのである。私はアセリながら登場し、まるで役者にダメ 出しするような表情で早口に台詞をまくし立てた。少しでもテンポをあげようと 躍起になっていた。なんとかしなくてはと思えぱ思うほど客は静まり返り、私は 演技以前のこわぱった固い表情、つまり恐い顔をして舞台に立ってしまっていた 。
とにかく芝居は終り、暗闇の中、役者全員が列を作って舞台に登場していた 。おじぎをしたまま、カーテンコールの明りが入る。顔をあげると、初めて客席 全体が明りの中に見えた。客は誰も動かない。みんな泣いていたのだ。三十人の 客達の全員が小刻みに体を揺らし、うつむいていた。そして、何とも言えない間 の後に、大きな拍手が続いた。百人はいればいっぱいのシアターグリーンにまば らに座った三十人の客達一人ひとりが精一杯の拍手を送ってくれていた。私は受 けた感動を悟られまいとして、又恐い顔をしたままお礼の言葉を告げ、退場した のだった。
翌日から観客の数が倍近くずつ増えていった。中日過ぎに朝日新聞に劇評が 載って、さらに客は増え続けた。そして千秋楽の日、マチネのみだった公演を当 日になって急遽七時の回を増やす事になった。急遽というのは、昼に入り切れな かった客達が帰らずに劇場の外で待っていたからだった。「夜の回を増やそうと 思うのですが、どうしますか?」と私が尋ねると、客たちのほぼ全員が、それま で待っていると言う。ぜひ昼にという客は、客席と廊下をつなぐ通路からのぞく だけでも良いという。キャパ百人の劇場になんと三百五十人の観客を入れてしま った。追加公演も鮨詰め状態で、うれしい悲鳴をあげながら初演の幕は降りたの だった。
私は当時二十七歳で、劇団員も三十歳前後がほとんどで、私も含め生活が余 りにも厳しかった。このまま劇団を続ける事は、結局仲間に対しても罪悪行為に 等しいのではないかと考えるようになっていた。若さと情熱だけではもう続けら れないのだという現実に全員が直面していたのである。もう劇団をやめた方が、 そんな思いに駆られていた。
岸田戯曲賞にノミネートされた時、高校の頃からあこがれていた諸先輩の作 家達に自分の戯曲を読んで貰えるのだということが飛びあがらんぱかりに嬉しか った。それだけで充分だと思っていた。正月で帰っていた山形の実家で受賞の電 話を貰った時はきつねにつままれた思いがした。そして何より劇団員が私以上に 喜んでくれた事が、本当に嬉しかった。戯曲はすぺて劇団の役者にあて書きして いたので、作品は自分達が私に書かせたものであるという自負をみんなが持って いたように思う。
まだまだやめられない、みんながそう思うようになったのだった。
池袋のアルバイト先のママさん達やお客さん達、私の行きつけの店の店主や 飲み仲間が、東武デパートの中華料理店で受賞パーティーを開いてくれた。その 時いただいた御祝儀が、戯曲賞の賞金よりも多かったのを覚えている。
マキオ役の藤堂貴也が美輪明宏氏の弟子だった事もあり、当時美輪氏には色 んな面でお世話になる事が多かった。Tシャツとジーンズしか持っていなかった 私を心配した美輪氏が受賞パーティーで着るようにと、白いスーツとアクセサリ ー類を買って下さった。同時受賞の野田秀樹氏が普段着で出席していたので、ひ どく気恥しかったのを覚えている。
こんな事を書き続けていたら、なんとも懐かしい思いが込みあげてきてしま った。
懐かしむ日が来ようとは当時は少しも思わなかった。懐かしむ事など当時は 許していなかった。
舞台は一回性の芸術で、束の間に消えることに価値があり、潔い事なのだと 考えていた。舞台をビデオに撮ったりすることは邪道なのだとみんなが思ってい た。
今のこの舞台、今の一瞬の呼吸、これがすべてだと思っていた。
一九年と半年続けた劇団を解散した今、自分が劇団を通じてこだわり続けて きた演劇とはなんだったのだろうと考える。あの一瞬一瞬の夢の時を積み重ね、 何が残ったのだろうと考えてみたりする。
けれど、旗揚げ当初から、何かを残そうとなどしていなかった事に思い当た る。束の間の幻を具現化する行為に身を費やすことがすべてだと考えていたはず なのである。今見えていることの不確かさ、自分という人間の不確かさ、生まれ 出でた瞬間からのあらがいようのない絶望感とせめぎ合いながら生かされ続ける 人間という生命体の不可思議な謎を解こうと躍起になってきた二十年ではなかっ たのか。
そして、生きても生きても次々に過去になって行く、時という魔物と戦いな がら、厄介な記憶のつまった入れ物である肉体をたずさえて、走り続けてきたの だった。私の書き続けてきたものは、人の記憶の話だったかも知れない。
見えないものを見ようとする厄介な人物達の話だった。そして、私自身が見 えないものを見ようとしてきたのであった。
今、捨て切れない荷物をだいじに抱え続けている愚かに年を取った自分がい る。それでいて胸に空いた洞穴は埋めようがない。自己の純粋によって傷を負う 、大人になり切れない中年の自分がいる。
十八年間仲間だった東銀之介、「ゲゲゲのげ」で半ズボンの小学生を演じた 初老の紳士も、記憶の星となった。
すベては、次に書く作品から始まるのであろう。
(劇作家)
|
|
|
|
|
光永吉江(左)と藤堂貴也(右) |
もたいまさこ(左)と渡辺えり子(右) |
小野正隆(左)と藤堂貴也(右) |