Go-21トピックス

Back Number~2001.04.15
![]()
| このページは現在社会で注目を集めている話題をとりあげてそれについてのコメントを掲載して行きたいと 考えています。会員各位の投稿も期待しています。 |
| 2001年4月15日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.04.01 ------------------------------------------------------------------- 最近、 発行間隔が2週間も空いてしまいました(すみません)。 この間、株価の乱高下、円安の進行、実質ゼロ金利政策への回帰など、金融市場は春の天気のよう にめまぐるしく動き、「解説しなくては・・」と思っていたのですが、時間がありませんでした。私でも忙し い時があるようです(珍しく)。 恐らく4月中旬頃迄は、発行が難しいかもしれませんが、こつこつ継続していきたいと思います。 いよいよ新年度。明るい気分で頑張りましょう! ------------------------------------------------------------------------------ ■構造改革とは?(最終回) ------------------------------------------------------------------------------ 前回で読者からの御寄稿を締切った後も続々とメールをいただいていたのですが、当初予定通り、一 旦同シリーズは終了し、次号からは金融・経済のトピックスに話題を移したいと思います。 さて、前々号でも紹介した日銀総裁講演でのフレーズを引用しますと、構造改革のスピードを速める為 には、「経済成長の源泉はイノベーションを通じた民間部門の活用にあるという事」「民間の活力は市 場メカニズムをフルに活用する事で引き出されるという事」「改革は、どうしてもある程度の痛みを伴う ものとならざるを得ないという事」を国民が共有する事が重要です。 民間部門の活用という観点から、米国経済の例を挙げてみましょう。90年代初めの米国の財政赤字 のGDP比は現在の日本とあまり変わりませんでしたが、今や黒字に転換。このきっかけとなったのは、 国防費の大幅削減です。勿論、冷戦の終結という背景もありますが、これが財政赤字の削減に寄与し ただけでなく、「軍民転換」(軍需産業が優秀な軍事技術とともに民間産業へ転換を果たした事)がその 後のIT産業の発展に寄与したとよく言われます。 日本には軍需産業は殆どありませんが、それに代るものとして膨大な公共投資事業が存在します。垂 れ流される赤字、膨らむ不良債権---市場メカニズムが作用しないところで、意味も無く延命措置が とられてきたというのが実状です。 「公」から「民」への転換。そして、規制緩和の強力な推進をはじめとする「民」の力を十分に引き出せる ような政策。痛みを覚悟しつつも実行できる政治のリーダーシップ。国民一人一人の自覚と理解。-- 必要なものは沢山ありますが、何事もまずは一歩から。前進していかないとね。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年4月8日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.03.18 ------------------------------------------------------------------- 最近、ドラえもんの映画のCMで「昔、のびた君だった君たちに・・」というキャッチコピーが流れていま すが、耳にする度に反応してしまいます。子供の頃は、のびた君と言えば「駄目でどうしようもない奴 の象徴」というイメージを持っていましたが、今振り返ると「平和と自由を愛し、純粋無垢で、将来に対し てとてつもなく大きな夢をもっている子の象徴」だったのだと思います。 理想と現実のギャップを認識する事も大切ですが、いつまでも夢を持って生きるという事も大切な事だ と思います。21世紀、子供達に大きな夢を与え続けていけるような社会を作りたいですね。 【編】 ------------------------------------------------------------------- ■公開質問に対する御回答~構造改革とは?(その3) ------------------------------------------------------------------- 読者からの御回答の掲載は、本号で最後です。今回は、「公」から「民」への転換が必要と唱えられる 方の意見を中心に掲載させていただきます。 【編】 ●Q3●構造改革とは?------------------------- 最近、政治家、マスコミ、エコノミスト皆が「構造改革が必要だ」と唱えていますが、具体性に欠け「構造 改革」の一言で片付けられているような気もします。 この「構造改革」を具体的に分かりやすく説明するとどのように表現する事ができるのでしょうか? ------------------------------------------------------------------------------ 世間的には、不良債権処理とか財政再建とかを指すようですが、そんなことをやって日本の経済は本 当に立ち直るのか?と思っています。不良債権の直接償却を進めれば、(連鎖的な)企業倒産、失業 率の上昇を招き、個人消費をさらに抑えこむでしょう。財政再建は、着手しても何十年もの緊縮財政が 必要でしょう。どちらにしても経済は回復しないのでは? 私の個人的な意見としては、公務員の身分保証を廃止し、公務員をNPO団体の職員に移しかえれば、 民間への影響を抑えながら、(少しですけど)国の歳出を減らしていけるのでは、と考えています。 現在の公益法人のように官僚の天下り先のようではなく、NPOの財源を企業からの寄付とし、寄付を 行う企業に税制面で優遇を設ける。国や自治体がおこなっている業務をNPOに移管し、「小さな政府」 を目指す。異動した公務員はNPOの安い給与体系に組み込む。 効果があるかどうかはわからないですけど、国が痛みを分かちあわない増税は道理が通らないし、公 務員の身分保証は、彼らから危機感と現実を直視する目を奪っているように思えます。 特に地方の状況は、東京よりも各段に深刻です。 私が住んでいる地域では、人口12万程度の小さな街に、マイカル・サティが2店舗、ダイエー1店舗、 マックス・バリュー、阪急オアシス、ニノミヤ無線、ミドリ電気3店舗、マツヤ電気、ロイヤルホームセン ター、コーナン、アサヒペン系のホームセンター、と大手量販店が軒を連ねて出店しています。 近々、阪急百貨店も来るそうな。 おかげで地元の業者は見る影もなし、地域経済は完全に破壊されてしまいました。 地元の商工会が間抜けなのか、市役所が機能していないのか、よくもこれだけの大型店の進出を認め たものだ、と呆れてしまいます。 自治体は完全に地域経済の敵です。中小事業者を大量に潰しておいて、税金を納めない大型店ばか りを増やしていく、こんなことで税収が回復するはずはないでしょう。もちろん正規の雇用も減るはずで す。シドニーのように大型店がない方が、経済にとってよかったのではないでしょうか。いまさら、「大店 法」のこと を言っても仕方ないですけど。 とにかく公務員の「意識改革」を待つのではなく、彼らの身分保証を廃止して現実を知ってもらうしかな い。こんな小さな地方都市の市役所でも、公務員は平気で天下りしてるみたいですしね。 東京ではあまり注目されない地方経済の現状は、こんなところです。無論、評判のいい自治体もあるに はあるのですが...。東京でリストラされて出身地に戻ってこようとするサラリーマンも増えると思いま すけど、受け皿になれる余力は地方にはもうほとんどないんじゃないでしょうか?長野県が少し羨まし いです。 (匿名) ------------------------------------------------------------------------------ 確かに、抽象的な使われ方をされていますが、ひとりのサラリーマンとして私は以下の3点と考えます。 第一に、自民党の利益誘導型政治の打破。 彼等は政治屋であって政治家ではなくなってしまった。 第二に、小さな政府の実現。郵政民営化に象徴される 官業による民業の圧迫やビジネス機会の喪失を排除すること。 第三に、透明性の確保と機会の平等。 これは、上記2項目にもかかわることで例えば、公共事業での完全自由入札など。 最後に自由な議論と異論や少数意見を尊重する風潮を作ること。 非常に抽象的ですが、マスコミにしろ政治家にしろ議論が下手で確信に迫れない。 テレビでの政治家同士、評論家との議論など全く噛み合わない。日本人は、異論を唱えると敵視された り、排除されたりする傾向があり、そのことが、政治・会社・学校などの閉塞感につながっている。違った 意見を尊重し合い、一定の結論を得る過程が下手である。 いいたい事は、まだたくさん有るが要点は以上と考えます。 (35才 サラリーマン 左藤康太郎) ------------------------------------------------------------------------------ 構造改革について私は、長い間作り上げてきた自分達の悪しき風習を払拭することだと思います。 いつまで経っても変わらない官と民の癒着、自分一人が甘い汁を吸う構造一生懸命働く人がいる一方 で、このような状態を見たり聞いたり読んだりすると、たまらなくむなしさを感じます。 こんな構造を誰か改革してくれ~!!!! (甘い汁の味がわからんサラリ-マン) 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年4月1日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.03.15 ------------------------------------------------------------------- シリーズ2回目は、バラエティーに富んだご意見を幾つかご紹介させていただきたいと思います(読者 の皆様から色々な考え方を教えていただき、私の方が勉強になります。又、文量が多くなって申し訳あ りません)。 このうち田村様の「間接金融から直接金融へのシフト」というご意見は、ピンとこない方もいらっしゃる かもしれませんが、、御寄稿をいただいた数日後、日銀総裁が内外情勢調査会での講演(「最近の金 融経済情勢と金融政策」の締め括りで、「構造改革として具体的に何が重要であるか」を述べたもの) において、別の角度から補足説明がされておりますので、以下にその抜粋も紹介させていただきたい と思います。 【編】 ・ ・ ・ (「構造改革として具体的に何が重要であるか」について、私(=日銀総裁)が常日頃考えている2つ のポイントとして)第1のポイントは、銀行の不良債権問題の解決です。(中略) 第2のポイントは、銀行の不良債権問題の解決や構造改革を推進していくためには、現在1,380兆円 にも達している個人の金融資産の54%が現金や預金という状況から、これら資金を株式市場や債券 市場へ流入させることがどうしても必要だということです。こうした間接金融から直接金融への移行を 近年うまく行い、リスク・キャピタルの増大に成功した事例としてはドイツが挙げられますので、簡単に 紹介します。 ドイツでは、90年代前半から98年までの間に3回に亘り金融・資本市場振興法を成立させ、株式市 場や投資信託の改革を進めました。具体的には、株式の最低額面金額の大幅引き下げ、ファンド・オ ブ・ファンズの自由化、投資信託の商品性改善、高齢者ファンドの育成などです。この結果、家計部門 の金融資産に占める現預金の比率は91年から99年の間で、日本では50.8%から54.0%まで上 昇したのに対し、独では45.8%から35.2%へと減少、また同期間における株式・投資信託の比率 は日本では10.9%から10.4%へと減少しているのに対し、独では14.6%から27.3%へと急上 昇するなど、劇的な変化が生じています。 日本においても、投資信託あるいはミューチュアルファンドなどの増加が期待されるわけですが、その ためには、投資信託の商品性改善が急務であり、特に家計が安心して投資できる、家計の様々なニー ズに合致し、しかもバラエティに富んだ投資信託が多数設定されることが望まれます。 さらにリスク・キャピタルを通じた資金の流れを太くする方策としては投資組合の設立が考えられます。 長銀を購入し新生銀行を設立したリップルウッド、東京相和銀行を購入したローンスターなどはいずれ もプライベート・エクィティ・ファンドと称する投資組合であり、その出資者は投資信託、個人年金の運 用主体である年金基金、大学財団などであります。日本でもこうしたファンドが多数設立されることを バックアップする施策が講じられることが必要でありましょう。 このように、現在、現金や預金に偏っている個人金融資産が様々なパイプを通じて金融・資本市場に 流入することにより、不良債権問題の早期解決を含めた金融システムの安定性が確保され、同時に 構造改革がさらに進むことを期待するものであります。 =================================== 公開質問に対する御回答~構造改革とは?(その2) =================================== ●Q3●構造改革とは?------------------------- 最近、政治家、マスコミ、エコノミスト皆が「構造改革が必要だ」と唱えていますが、具体性に欠け「構造 改革」の一言で片付けられているような気もします。 この「構造改革」を具体的に分かりやすく説明するとどのように表現する事ができるのでしょうか? ------------------------------------------------------------------------------ 構造改革なる言葉が頻繁に使われますのは、それが都合の良い言葉だからでしょう。頻繁に使いすぎ ると、その意味さえ失われてしまいますが、自らの意見を正当化させ、相手(誰であれ)を攻撃するため の都合の良い言葉なのでしょう。 民主主義という言葉も同じように使われているように思われます。誰もこの言葉に反対はしないでしょう。 そして、事あるごとに、民主主義に反する、と言います。 しかし、実際には、政治学の分野では民主主義と独裁が両立しうることは当然のことでありますし、民主 主義の教祖たるルソーが現在の各国の政治を見て、それが民主主義であると言うことは無いでしょう。 もちろん、ソクラテスが見ても同じでしょう。 ただ、民主主義には、制限的ながらその意味はあります。要するところ、私は、単に「民衆(これも人民 なり、国民なり市民なり色々な言われ方により意味が異なるやに思われますが)が国家権力に介入す ることが出来ること」と解釈しています。従って、独裁、は可能になるわけです。ドイツのナチに対する言 論封殺も民主主義には反することになります。一方、ドイツはそれを「戦う民主主義」と名付けています。 構造改革は、私なりに解釈いたしますと、「人類の試行錯誤の結果によって繰り替えさえる宗教的原罪 に対する抵抗」となりましょうか。簡単に言えば温故知新、ですか。いつの時代にも必要なものだと思わ れます。 貴紙が言われますように、「構造改革」という言葉を使わずに言論を戦わせることが、現在の言論界に おける構造改革なのかも知れませんね。 温故知新、今なら、中曽根氏を見習うことから始めましょうか・・・。彼や、その思想を受け継いだと思わ れる橋本氏の意見が「温故知新」であり、その他のものは、「構造改革」なのでしょう。とりとめもなくな りましたが。(荒井智行) ------------------------------------------------------------------------------- 「構造改革」についてですが、つい最近、「不動産証券化」で論文を提出(修士ですけど)しまして感じた ことが、間接金融と直接金融へのシフトではないかという事です。 特段、目新しいことではないかもしれませんが、従来の企業と金融機関という関係から投資家と企業 (事業)という関係への転換が求められることが構造改革のような気がします。 戦後、日本の高度成長を支えたのは、間違いなく間接金融でしたが、間接金融の成立条件は、日本で は土地神話による担保土地の資産価値が重要であったわけで、それを可能とさせた条件は右肩上がり の経済成長期待であったと思います。しかし、そういう右肩あがりもアメリカの世界制覇(いろんな意味で) の終焉する1980年代から徐々に失速する傾向になり、結果、次にアメリカが目を付ける問題は、対日 貿易赤字となったのだと思います。 つまり、この時、日本の「円」は、世界を席巻するマネーと位置づけられたと考えられますが依然として、 企業と金融機関という閉じた世界でマネーを回すことが中心で、しかも、金融リスクを一極集中させるこ とになったために、現在の経済低迷に繋がったと思います。もはや、日本経済は生産活動でマネーを稼 ぐような国ではなく、散々稼いでタンス預金に近い形の固定された個人マネーを如何に運用していくかを 考えることが重要なことではないでしょうか。 そして、多くの自己責任のとれる投資家をつくり、厳しく多くの事業に投資できる社会・経済の実現こそが 構造改革であって、抽象的な表現をすれば、より民主的、大衆的経済・社会経済への転換であると思い ます。 そのためには多くのことを解体または再生しないといけないため、構造改革がぼんやりするのではない でしょうか?私が従事していた建設には、多くの問題があったように思いますが・・・。 ながながとなりましたが、現在の私の意見です。(田村とおる、28歳、学生) ------------------------------------------------------------------------------- 構造改革とは、まず自民党の古い田中角栄以来の土建政治と地方への利益誘導政治をやめること、 財政の建て直し、などよく言われるようなこともそうだと思いますが、それだけではなくて、ハイリスクな 社会構造を改革するということではないでしょうか。 一度弱者になると戻れないような社会になってはいないでしょうか。あるいは何か事業を起こすときに 安心して力を発揮できない環境がないでしょうか。つまり起業するリスクが高いということです。 放っておけば、一度「負け組」(私はこの言葉が嫌いです)になった弱者は切り捨てられる、文字通りの 弱肉強食社会になる様々な圧力を私は感じます。そういう社会が公平な社会だとは思えませんし、そも そも私はそんな社会には住みたくありません。別にこの思いはわがままではないと思いますし、経済学 もそもそも公平な分配はどうあるべきか考えてきたのがその歴史ではないでしょうか。それを今は「いか に弱肉強食社会に耐えるか」、あるいは「弱肉強食でも仕方がない」という本音が底に流れているよう な議論が強いように思えます。そんな議論をする人が「弱者への政策が大切であることには変わりな い」と言ったところで信用できません。 また雇用の流動化で行くならば、同時にそれを支える堅固なセーフティーネットの整備が必要です。 それと、歳出構造の改革も挙げられると思います。共産党などが言うように、お金の使い方を変えれば 福祉重視は不可能ではないはずです。これは景気刺激という名目のばらまきからの脱却とも関係があ るでしょう。 最近の友人(私は彼らは典型的な現代の若者だと思っています)の言葉に非常に違和感のあるものが ありました。ドライブの最中、横を多くのトラックが追い越していきます。それを見ながら、「受験競争に負 けて落ちこぼれたからトラック運転してるんだろ?『負け組』じゃないか。」、そういう趣旨のことを言ったの です。 面と向かって批判できなかった私にも大きな問題はありますが、仮にもそれなりに偏差値の高い大学の 学生の言葉にしては、非常に問題があるような気がしました。まず、どの労働にも尊い価値があることを 分かっているのかどうか怪しい。 また、仮に運転手さんが「負け組」であるにしても(私は決してそうは思いませんが)、彼の考え方では、 とかく「負け組」に冷たいと言われる日本社会のハイリスクな構造を改革する意欲はまず生まれ得ない と感じます。そのことは、先ほどの経済に関する議論の底の本音と通じているとも感じます。 青臭い憤りに満ち満ちた文章、あるいはもう一つ具体性に欠き、論理的に甘い文章だったかも知れませ んが、専門家ではない普通の若者の声としてお聞き下されば幸いです。言い足りないことがあればまた お伝えしたいと思います。(伊藤知行、都内私大2年) ------------------------------------------------------------------------------- 人間が自由に考え、発言し、行動する事が構造改革では。現在の日本は、あまりにも世間体、連帯感が 強すぎると感じます。海外にいて、この意識が障害になることがしばしばです。 (アセアン、54歳、工場管理) 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年3月25日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.03.13 ------------------------------------------------------------------- 公開質問を行なって以来、約2週間が経ちましたが、その間、株価は更なる下落を続け、政府も日銀も 世論もエコノミストも「構造改革」の大合唱です。 そして、読者の皆様からも沢山の御寄稿をいただきました。読者の経済に対する関心の高さをあらため て実感するとともに、様々なご意見をいただける事を大変嬉しく、光栄に思いました。 文量的に全てを掲載する事はできないかもしれませんが、本号より3回に分けて掲載させていただきま す。 1回目は、「意識改革こそ構造改革」と考えられる読者の意見を掲載しました。 意識改革というのは一見抽象的なことのようですが、国民一人一人が誰でもできる、非常に身近なもの だと思います。自分一人が意識を変えたところで、政治や済がよくなるわけではない、業績や給料がよく なるわけではない--そんな無気力感が国民感に蔓延しておりますが、この他力本願的な意識が、財 政や金融政策に依存したまま抜け出せない日本経済の泥沼構造を作り出しているのかもしれません。 (つづく) 【編】 =================================================================== 公開質問に対する御回答~構造改革とは?(その1) =================================================================== ●Q3●構造改革とは? 最近、政治家、マスコミ、エコノミスト皆が「構造改革が必要だ」と唱えていますが、具体性に欠け「構造 改革」の一言で片付けられているような気もします。 この「構造改革」を具体的に分かりやすく説明するとどのように表現する事ができるのでしょうか? ------------------------------------------------------------------- 日本という「システム」の改革を意味すると考えます。 カレル・ヴァン・ウォルフレンが指摘するところの、日本的な、あまりに日本的な「政治・経済・社会シス テム」では、グローバルスタンダードで進行する世界との協調と共生がうまく機能しないことが、すなわ ち永続的な繁栄を維持できないことが失われた10年を通してやっとコンセンサスを獲得したといえる。 戦後から続いていた閉じられた日本という共同幻想では「システム」が十分に機能していたが、情報化 し国際化した多くの日本人はすでに日本的「システム」のもつアンフェアさ、不可解さ、遅さなどから感 じる「停滞性」 ひどいときには「逆行性」に、NOをつきつけている。 しかし、これを改革することは、「システム」にどっぷりと依存してきた政党や官僚もさることながら、ゼネ コンや各種団体の自己基盤を根底から否定することになる。広義には日本人そのものの自己否定に つながるものである。 このため、困ったことに、スクラップ&ビルドという発想の乏しい積算型の日本人マインドでは、自己改 革しなければならないとわかっていながらも「多数決」をとれば易きに流れてしまい、一向に「システム」 の改革が進まないことになる。 「今までそれでうまくやってきたんだからいいじゃないか」というわけである。しかし、今までの成功体験 がこれからの成功をも保証することはなく、むしろ、必然的改革の障害となっていることは周知のとおり である。 結論。 構造改革とは日本的「システム」の改革。日本人の根底的意識改革とそれにともなう抜本的制度改革 のことである。意識改革なくして制度改革は意味を持たず、 制度改革なくして意識改革の進展はありえない。この両柱を骨にして行われるべき、日本的なあまりに 日本的な「システム」の改革を意味する。 (Yasuhiro、28歳、会社員) ------------------------------------------------------------------- 構造改革とは、意識改革に他ならないと思います。 政治的に言えば、いわるゆる自社両党による55年体制が崩壊し、連立政権の時代であるにもかかわ らず、政治を考える視点は未だ55年体制のままというのが構造改革が進んでいない状態といえます。 これはマスコミ報道の随所に見られます。最近の森降ろしはその典型です。森総理が他の誰かに変わ っても日本の政治が急に良くなることはありません。衆院480名、参院252名の中からしか総理は選 べないわけですから、誰がなってもどんぐりの背比べです。 こうしたことを一番わかっているのが政治記者であり、マスコミです。しかし、毎日の記事は総理交代に より日本の政治が変わるという森勢力と対立する政治家の発言を取り上げております。政治面のワイ ドショー化です。これは、別に、森総理を擁護しているわけではありません。日本の政治にとって総理の 交代は大きな意味を持ちますから、重要な事件とも言えます。報道する価値はあると思いますが、ワイ ドショー化した政治報道からは、何も生まれないと思います。英国のチャーチルが選挙で落選したよう なことは日本の政治風土ではありえないのです。 連立時代という観点から考えれば、今、政治は何を守らなければならないのか、どこを改善しなけばな らないのか、明確にすることであると思います。 こうした観点から、冷静に論理的に政治を論じることができるようになり、国民の意識が変化する時、政 治的には構造改革が進んだ、といえるのではないでしょうか。(高島) 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年3月18日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.03.11 ------------------------------------------------------------------- 米景気の行方は?~グリーンスパンの利下げ効果か? ブッシュの減税効果か? ------------------------------------------------------------------- 本コラムは、米国にてフリーライターとして活躍していらっしゃる方からの御寄稿です。JEREPでは寄稿 家も募集しておりますので、是非御参加下さい。【編】 →http://www.jerep.com/jclub.htm ------------------------------------------------------------------- 『グリーンスパン米連邦準備理事会(FRB)議長、景気先行きに警戒感示すが、緊急利下げは示唆せ ず』という大見出しが、2月28日付けNYTimesを始めとした主要新聞の一面に出ました。これは、議会 金融サービス委員会に対する証言を受けてのもの。2週間前の上院委員会での証言とはややニュア ンスが異なります。 「今後さらに米経済にとって険しい道のりが待ち構えている」と、長年その景気操縦の腕を誇ってきたベ テラン議長に言われると、米国民は心細くなってしまいますが、3月20日に予定されている定例米連邦 準備委員会までは、利下げは行わないことを示唆したわけですから、そこまで事態は悪化していないと 見ても良いかもしれません。 しかし、米株式市場は大きく失望。今のベアマーケットを救うのは、グリーンスパン議長の緊急利下げし かないというほど、待ちに待っていたのですから、その反動はひどいもので、主要株価指数は軒並み下 落となりました。 エコノミストの間では、米経済の実際の減速度は、グリーンスパン議長が述べたよりも、さらに深刻であ るとの見方もありますが、議長が公に米経済低下を証言することによる市場への影響と、経済成長低 下が現在進行中のブッシュ大統領減税案の拡大に利用されることを恐れて、その深刻度を認めること を躊躇したともいわれています。 ・ ・ ・ 一方、ブッシュ大統領は、28日、選挙時の公約であった景気刺激対策をうたった減税案を議会に提案 しましたが、民主党は、その減税内容について、高所得層に恩恵を与えるだけの減税であると、激しい 非難をあびせています。 民主党によれば、ブッシュ大統領減税案は、減税による総還元額のうち43%もが、米国のたった1% を占める最高所得者層に還元されるということです。また、巨額な米国債等の赤字債権を減らさない限 り、リスクプレミアムの増大に伴う利子率の上昇を招き、減速する経済状況を悪化させかねないと、懸念 する向きも多々あります。 グリーンスパン議長は、連邦剰余金を国債買い戻し等の赤字減少に使うべきだとの立場をとっていまし たが、通例となった、新大統領がグリーンスパン議長を招くという談話会に出席し、和やかに今後の経 済政策をつまみにしながらお茶を飲んだ数日後、減税支持を示唆するようなコメントを出しました(政治 家からのいかなる圧力にも屈せず、米連邦準備理事会の独立性を信ずることで有名なグリーンスパン 議長だったはずが、と文句を言いたくなってしまいます)。 ただし、万が一、当減税案が議会を通過し、減税が実施されたとしても、それは早くても2002年後半で あるとのこと(今年度から遡って減税対象期間にするとブッシュ陣は唱っていますが)。減税効果が、実 際の景気に影響するのは、実施後、さらに最低半年、1年はかかる事を考えれば、2003年以降にな って初めて、減税の景気刺激効果が起るわけです。低迷する景気を救うには、今何らかの対策が必要 なのです。3年後なんて、、、、さてさて、一体何のための減税でしょう? ・ ・ ・ グリーンスパン議長は、3日、ややトーンを変えて、長期的経済のために、国債の返済を急速に進める べきであると、語りましたが、一方、5日には、リンゼー大統領補佐官が、経済は、ブッシュ大統領提案 の減税案という保険を必要としていると、減税の景気刺激効果に(しつこく)熱弁を奮っています。 3月20日に予定されている定例米連邦準備委員会での半ポイントの利下げはまず間違いないと、巷で は予想されていますが、この利下げがどこまで、刺激策となるやら。「リセッション」虫がぬくぬくと育って しまう前に、ここらで、早い目に手を打つ必要があるのではないでしょうか、、、、 【ハベリナ】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年3月11日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.03.04 ------------------------------------------------------------------- 強制評価減の脅威 ------------------------------------------------------------------- 日本経済はデフレ色を強め、株価の下落も一段と強まっています。今年から有価証券の時価評価が 始まっていますが、これにより株価の変動は企業の会計上の利益にもインパクトを与える事となりま す。 ただし、時価評価の適用は、有価証券の保有目的によって異なります。 例えば、子会社・関連会社株式については、上場・非上場にかかわらず時価ではなく取得原価で評価 する事となっています。つまり、株価が下落して、含み損を抱えていたとしても、子会社・関連会社株式 (20%以上の持ち株比率などの要件を満たす必要あり)については、原則として会計上の損益には一 切あらわれてこない事となります。 「原則として」という事は「例外」もあります。時価が著しく下落(具体的には取得原価に対して50%以 上下落)した時は、回復する見込がある場合を除き時価で評価しなれればなりません。これを「強制評 価減」と言います。 特に昨年のネットバブルの頃に、株価割高感の強かった企業に出資を行ない子会社・関連会社とした 企業の中には、当該株式が50%以上下落し、「強制評価減」の適用を受けるところも出てくるでしょう。 そして、多額の含み損が次々と表面化してくると、2000年度前半迄の景気回復のキーワードだった 「好調な企業収益」も幻想に過ぎなかった、なんて言う事もありうるわけです。 株価下落が進行する中、時価評価の対象から逃れていた株式を保有していた企業も、「強制評価減」 によりその洗礼を浴びる可能性があるという事も認識しておく必要がありそうです。 【編】 -(参考)------------------------------ 平成12年度から導入された有価証券の評価基準は以下の通りとなります。 有価証券の種類 貸借対照表計上価額 評価差額の処理 売買目的有価証券 時価 当期の損益 満期保有目的有価証券 取得原価+償却原価法 原則として生じない 子会社・関連会社株式 取得原価 原則として生じない その他有価証券 時価 原則として資本の部に記載 市場価格のない有価証券 取得原価 原則として生じない 運用目的の金銭信託 時価 当期の損益 デリバティブ取引 時価 当期の損益 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年3月4日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.02.27&03.01 ------------------------------------------------------------------- オールド銘柄の逆襲 ------------------------------------------------------------------- 28日は日銀の連続利下げ、1日は株価安値更新、債券急伸、・・・と金融マーケットは荒れ模様です。 一見「最終局面」に見られがちな動きですが、もう少し見極める必要がありそうです。 「日経平均株価、バブル崩壊後最安値更新」--新聞の見出しはだいたいこうなるのでしょう。 1日、日経平均株価は米国株安を受け、前日比201円88銭安の1万2681円66銭となり、終値でも バブル経済崩壊後の最安値を更新。なんと15年4カ月ぶりの水準に下落してしまいました。 日経平均株価は、昨年4月の銘柄入替でハイテク関連銘柄の組み入れを増やしており、指標としての 連続性を失っていますから、過去の数字と比較するのは妥当ではないのですが、売られてしまってい るのは事実です。 但し、相場全体が急落する中で堅調に推移する株価もあります。1日で言えば、三菱重工、川崎製鉄、 新日鉄、日産など。日産自動車は一時、4ヶ月ぶりに昨年来高値を更新しています。生き残りの為に、 必至にリストラや業界再編などを行なったオールドエコノミー銘柄逆襲の胎動が僅かながら感じられま す。 【編】 ==================================== ■鉱工業生産の悪化と連続利下げ ==================================== 28日発表された1月の鉱工業生産指数は、前月比▲3.9%と大きく悪化。海外経済の失速→輸出の 急減→生産の縮小という動きが顕著にあらわれており、今後の企業収益の悪化も示唆される事となり ました。先月発表された1-3月期の機械受注見通しや日経新聞調査による2001年度民間企業設 備投資計画のマイナス転換等も勘案すると、現状の景気判断を行なう上では、もはや「緩やかな回復」 というよりかは「足踏み」或いは「悪化」という言葉の方が適切とも言えるでしょう。 そんななか、日銀金融政策決定会合が同日開催されていたわけですが、現状維持との見方が市場参 加者の予想の大勢を占めていた中、利下げ(無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.25%から0. 15%へと引下げ、公定歩合を0.35%から0.25%へと引下げ)を実施しました。 昨年9月に利上げを断行した際、「後戻りはしない」と断言していたにもかかわらずの政策変更。しかも 先日の公定歩合引下げに続いての連続利下げ。鉱工業生産指数等ファンダメンタルズの悪化が見ら れる事、株価の下落が止まらない事、政府からの金融緩和圧力というヤジをかわす事、構造改革進展 の催促、硬直性の強かった日本の金融政策の柔軟の柔軟路線への転換のアピールする事、様々な背 景はあるかと思いますが、何よりも景気の先行き不安感を日銀自身も強く感じているという事のあらわ れと言えるでしょう。 【編】 ◆---------------------------------------------------------------------------- 国債格下と構造改革 ------------------------------------------------------------------- 当レポートも創刊4年目へと突入しました(長い間ご愛読いただいている皆様有り難うございます)。こ れまで、国債格下に関するレポートは何度となく書いておりますので、もう改めて記事にする事もない かなと思いつつ、簡記致します。 先週末、米格付会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社は、日本政府が発行・保証する債券 (国債・政府保証債)の長期格付を、最上級のトリプルAからダブルAプラスに1段階引き下げました。 昨年、S&Pは、政府債務格付け責任者の講演で、『将来、格付け変更のアクションを起こすとすれば 財政再建がどのような速度で行われるか、構造改革と規制緩和の進捗状況がどうなるかだ』と述べて いましたが、格付のネガティブ転換など、格下げを示唆する具体的な動きは見せていませんでしたから 今回の格下げの発表のタイミングはあまりに突然だったと言えるでしょう。 この「突然の発表」の真意については定かではありませんが、もはやマーケットは冷静です。既に米格 付会社ムーディーズ社より格下げを受けていた事、そして、市場参加者の間に格下げされるのも無理 も無いという諦めムードが(悲しいかな)漂っている事もあるでしょう(特に、目を覆いたくなるような政 治の混迷ぶりもあってか)。確かに、昨年のS&Pによる講演で示唆された「進捗状況」を速めていく為 には、強力な政治のリーダーシップは必要不可欠と言えるでしょう。 ところで、「構造改革」という言葉は、日本経済についてコメントされる時に頻繁に使われております (「構造改革が必要だ」「構造改革なくして、真の景気回復は成し得ない」とか)。この言葉の中には、不 良債権処理とか財政再建とか規制緩和とか、様々な事柄が含まれているようなのですが、今ひとつ具 体性がなく、ピンと来ません。(なので、できるだけ自分ではこの言葉は使わないように心がけているの ですが、「長々と説明するのがメンドーだ」という時に、つい使ってしまいます。) 気にすれば気にする程、政治家もマスコミも格付機関もエコノミストも、「構造改革」という言葉を極め て頻繁に使っている事が分かるでしょう。良く言えば「便利でカッコいい言葉」だと思いますが、悪く言 えば「抽象的過ぎる」気もします。例えば「構造改革、構造改革」と唱えている政治家が具体的に何を やりたいのか、何をやっているのか等がはっきり分からない事も多いでしょう。 長い前置きでしたが、「構造改革」って分かりやすく説明すると何なのだと思われますか?読者の皆様 の忌憚の無いご意見をいただければと思います。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年2月25日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.02.22 ◆---------------------------------------------------------------------------- 新旧バブル精算 ------------------------------------------------------------------- 経営不振に陥っていた大型リゾート施設「シーガイア」を経営する第三セクターのフェニックスリゾート が19日会社更正法の適用申請に追い込まれました。リゾート法第1号指定を受けて設立された同社 が経営した「シーガイア」はバブルの産物そのもの。当初680億円とされた総事業費は約3倍に膨ら み、追加の出資、融資、県の補助金による延命策も空しく、オープン以来一度も利益を出さぬまま幕 を閉じる事となりました。いまだに10年以上前のバブルの精算か・・と溜め息が漏れてしまいます。 一方、昨年沸いたネット株バブルの崩壊を受け、米国に続き国内のベンチャー企業にも淘汰の波が押 し寄せ始めているようです。 コミュニティーサイトを運営していたジェイサイド・ドットコム。タレントの大橋巨泉氏をキャラクターに、大 々的な広告を打ったものの、年間の広告予算は十億円と、資本金の半分にも及ぶ過大な広告投資の ツケに襲われ、サイトの営業権を他社に譲渡し、今月末に会社を精算する事となりました。又、検索サ ービスや掲示板などのサイトを手掛けたブーク・ドットコム。ここも、昨年6月の立ち上げ時に4億円も の広告投資を行ないましたが、会員数は当初目標の8分の1にとどまり、僅か半年で経営が行き詰ま る事となりました。 ・ ・ ・ さて、当レポートの2000年1月18日号。ネット株が急騰し、個人投資家の投資熱が盛り上がる頃で すが、筆者は以下のような記事を書いています。 『証券会社が実施する個人投資家向けのセミナーの多くは、情報関連銘柄を推奨するのであるが、リ スクシナリオにはあまり触れないケースが多い。リスクシナリオという点では、12日付(2000年1月) の日経新聞の記事の一文が参考になる。--- 「社名にドットコムと付けば株価が上がるというのは神話だ。昨年大幅に上昇したナスダックも、50% の銘柄は下落した。米ネット株は絶えず銘柄の入れ替えを繰り返し、総体として価値を高めてきた。日 本の市場は多産多死型のメカニズムによる株価上昇をまだ経験していない。・・」』 ・ ・ ・ インターネットは100年前の自動車に匹敵する歴史的なテクノロジー等とよく言われます。ただ、自動 車メーカーも1900年初頭は3000社以上ありましたが、その後はビックスリーへと集約されておりま す。産業の発展の為には「淘汰」はつきもの。投資家の選別眼がますます要求されてくる事でしょう。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年2月18日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.02.12 =================================== 公定歩合引下げの効果 =================================== 映画「ペイ・フォワード」を見てきました。そういえば「先ず与える事から始めなさい。」と中学の校長も新 学期の挨拶とかで言っていたなぁ。 「情報を受信する為には先ず発信を」というのは私が常に思う事です。例えば、米国の市場調査をする 為に米国に出張した時は、先ず質問する前に日本の市場の事を色々と教えてあげる--そうすると相 手も米国の事も色々と教えてくれるものです。当メールマガジンも情報を発信しているようで、実は様々 な情報を沢山の読者からいただいてきております。 「ペイ・フォワード」は感動の作品です。是非お子様と一緒に行かれてはどうでしょうか。もし、あなたが 世界を変えたいと思ったら、どうする?--そのきっかけを掴めるかもしれません。【編】 →http://www.payforward-jp.com/ ------------------------------------------------------------------- 日銀は9日の金融政策決定会合で、公定歩合(用語解説御参照)を0.15%引下げ、年0.35%にす る事と決めました。公定歩合の引下げは95年9月8日以来、5年5ヶ月ぶり。同時に、金融機関の申し 出に応じて資金を公定歩合で貸出す制度(ロンバート型貸出し制度)の導入の方針や短期国債買い切 りオペレーションの積極活用等を決めました。一方、現在の金融政策の中核を成す無担保コール翌日 物金利は0.25%据置きと現状維持となりました。 結論(私見ではありますが)を先に言うと、実体経済の影響は殆どないでしょう。市場金利を決定づける 無担保コール翌日物金利は変わっていませんし、公定歩合が下がったといっても所詮0.15%。ロン バート型貸出し制度も非常時の安全弁とはなるでしょうが、通常時においては市場金利よりも高い金利 で借入を行なう金融機関は極めて限られる為です。 それにしても、驚くべきは、「公定歩合」のアナウンスメント効果。短期金融市場の現場にいる人間にとっ ては、形骸化している公定歩合の引下げよりもそれに附随する一連の措置に注目するのでしょうが、大 手新聞紙面の一面には「公定歩合引下げ」の見出しが全面に押し出されているからです。違和感を感 じつつも、金融緩和姿勢をアピールするという点については今なお絶大な効果があるものだと思わず感 心してしまいました。 ・ ・ ・ 実体経済の影響は兎も角としても、日銀の硬直的な金融政策運営から微調整型の柔軟な金融政策運 営への転換を示した事は評価してもいいかと思います。しかし、新聞では大々的には取りあげられては いないのですが、一つ非常に残念な事があります。 それは、今回の「公定歩合引下げ」という情報が結果発表の何時間も前に一部マスコミに漏れていた 事です。 これは、情報管理の甘さを指摘できるだけでなく、金融政策決定会合の形骸化が露呈されてしまったと も言えます(今回の措置も決定会合で議論して決めたのではなく、議論される前に結果は決まっていた んでしょ。じゃあ、決定会合って一体何なの?単なる雑談会?という感じでしょう。) マスコミは情報を公表前に仕入れて報道する事が仕事の一つですから、情報漏洩に対する強い批判は 自己否定となり、積極的に批判する事はまずないのですが、このような事が日銀だけでなく、日本の信 認低下につながりかねないという事を強く意識してもらいたいものです。 【編】 =================================== ■用語解説:公定歩合 =================================== 日銀が民間金融機関に資金を貸出す際の基準金利。従来は日銀の金融政策のの主要な手段であり、 市場金利も公定歩合を軸に形成されていたが、95年移行から無担保コール翌日物金利の誘導目標 が金融政策の主要手段となった事、公定歩合は市場金利を上回る水準に据置かれ一種のペナルティ ー金利としての意味合いが強まった事等から、形骸化して現在に至っております(実際、日銀が公定歩 合で金融機関に貸出すという例はここ数年で激減しています)。 今回の公定歩合の引下げも、市場金利より高い水準に据置かれているという点では変化無く、引き続 きペナルティー金利的な意味合いが残る事でしょう。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年2月11日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.02.04 ==================================== 景気変調の見極め方 ==================================== 米連邦準備理事会(FRB)は1月31日に追加利下げに踏み切り、1月3日の緊急利下げと合せて僅か 1ヶ月で1%も金利(具体的には、FFレートの誘導目標)を引き下げました。米国景気失速を早期に防ぐ 為に行なわれたものですが、最近は米国のバブル崩壊懸念に関する話題が尽きませんね。 個人投資家が、バブルの崩壊やら、景気の不穏な動きやらを一早く察知するのは、なかなか困難な事 ですが、もし「何か分かりやすい見極め方を」と尋ねられたら、例えば「長短金利(長期金利と短期金利) の動向をチェックする事」を提案すると思います(具体例でいうと10年物の国債と3ヶ月物短期国債の 金利の比較)。 一般的に、期間が長くなればなる程、金利は高くなります。期間が長い程、その資金に対して流動性リ スクに応じたプレミアム(上乗せ金利)が付せられるからです。通常の経済状態であれば「長期金利> 短期金利」と考えてもよいでしょう。 (勿論、「長期金利>短期金利」だから経済が正常とは言えませんが)。 一方で、「短期金利>長期金利」となるのはかなり稀なケースです。「現在の金利では、景気の維持は 困難」「景気を維持していく為には、金融当局は政策金利は下げていかざるを得ない(結果として、中長 期的に金利は下がっていく→従って、長期金利が短期金利を下回っているのは不思議ではない)」と考 える市場の総意に基づくものですが、現状の景気や金融政策に対する「市場の警鐘」と言ってもよいで しょう。 ・ ・ ・ この長短金利逆転現象が見られた代表例として、バブル崩壊直後の日本(90年10月)が挙げられま す。しかし、利下げを催促する「市場の警鐘」に直ちに対応できなかった日銀。この判断の遅れがバブ ル崩壊後の景気低迷長期化の一因となった事は、現在の日銀も自認している事です。 もう一つの代表例は、現在の米国です。昨年の5月から米国では長短金利が逆転。当時こそ、それほ ど深刻には考えられておりませんでしたが、その後の米ナスダック店頭株指数の暴落等を思いおこせ ば、「市場の警鐘」は正しかったと言えるのでしょう。(米金融当局は、利下げのタイミングこそ遅れまし たが、上述の通り、今年に入ってから一気に大幅な金利引下げを実施。引き続き、バブル崩壊の火種 は燻っておりますが、日銀の失敗から得た教訓を十分に活かしているところです。) ・ ・ ・ 為替や株式市場とは異なり、金利のマーケット(債券市場など)はプロの投資家やディーラーが中心と なり構成される冷静な市場(個人投資家の視点では陽の当らないマーケットのようですが)。参考にす る価値はあると思います。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年2月4日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.01.25 ==================================== 家計のバランスシート不況 ==================================== 個人の抱える住宅ローンの残高が増えています。 日銀によると2000年9月末の家計部門の住宅ローン残高は約182兆円となり、統計開始(89年度) 以降、最高の残高となりました。当然の事ながら、負債の拡大に伴い、月々の返済額も着実に増えてお り、住宅ローンを抱えた世帯に限っては可処分所得(給料から税金や社会保障費等を差し引いた手取 り額)の約2割に達しています。 返済は増える中、所得の改善は遅々として進まず、消費を抑制せざるを得ない---これが個人消費 低迷の一因となっています。 住宅ローン残高の拡大は、1)住宅金融公庫の融資枠拡大や住宅ローン減税の拡充など景気対策と して住宅取得促進策を進めてきた事、2)低金利や地価の下落が個人の住宅購入インセンティブを高 めた事、3)収益力回復を目指す民間金融機関が利鞘の大きい個人向け住宅ローンの販売強化に努 めた事などが主な要因です。 勿論、住宅ローン残高の拡大に比例して、99年央より住宅投資は前年比二桁水準で増加の一途を辿 ってきており、これが景気の回復に大きく貢献してきたわけですが、とりわけ上記1)による要因が大きい と思われ、「需要の先食い」に対する(住宅投資の)反動減が気になるところです。 又、この反動減を警戒し、住宅減税の期限は延長される事となりましたが、住宅ローン残高の増加、及 び、これに伴う返済負担の増加は「家計のバランスシート不況」とも言え、引き続き個人消費を抑制し ていく事となるでしょう。 【編】 ==================================== ■用語解説:バランスシート不況 ==================================== エコノミストが今の日本経済を説明する時によく使う言葉で、企業が企業活動によって得られたキャッ シュを、せっせと借金返済(負債圧縮)へと回し、自社のバランスシートの修復・改善を図ろうとする為、 設備投資に振り向ける余資が無くなり、内需がなかなか上向かないというような経済状況を言います (この場合は「企業のバランスシート不況」)。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年1月28日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.01.21 ==================================== 自社買いと金庫株 ==================================== 先週16日にトヨタ自動車が「2500億円を上限とする自社株式を三月末までに買入れ消却する」と正 式発表した事が、株式市場で好感されましたね。政府の株価対策よりも企業の自助努力が市場に求め られているという事の現れかもしれません。 自社株買いは、読んで字のごとく、企業が自社の発行した株式を買い戻すこと。日本で同制度が可能と なったのは、つい最近の事で、税制特例措置が実現した95年から実質的に始まり、97年からは定款 を変更すれば取締役会の決議で行なえるようになりました。 自社株買いのメリットとしては、(1)(短期的に)株式需給を改善させる、(2)株主資本の減少によるR OE(株主資本利益率)を上昇させる、(3)「自社の株価が割安」である事をアナウンスする効果がある 、等が挙げられます。 但し、制限もあり、その目的は消却やストックオプション等に限定されており、又、ストックオプション目的 の取得の場合は、発行済み株式総数の10%迄という上限もあります。米国では、目的に制限なく、取得 ・保有ができる「金庫株」が解禁されておりますが(取得数量も剰余金の範囲ならば、規制なし)、この解 禁が現在与党の株価対策として挙げられているものです(解禁には、商法の改正が必要。又、株価のつ り上げやインサイダー取引に利用されないように証券取引法を改正し、その防止を図る事も必要となる はず)。 自社株の取得制限が無くなれば、取得した株式をストックオプションとして使う余地も増えますし、株式交 換制度を使った企業買収や企業年金の充実化も図れるでしょうし、財務戦略上の自由度が高まる事は 確かでしょう。 しかし、株価対策になるかというと、・・・?というところで、自社の利益を使って自社の株を買うのですか ら、理論的にはその企業価値は変わらないはずで、短期的には需給が改善したり、投資家が錯覚して、 株価が上昇する事はあるのでしょうが、長期的には元の水準に戻るものなのです(企業価値を最大限に 引き出せる株主資本の適正水準というのもあるでしょうが、トヨタのように手元流動性が豊かで、借金も少 ない企業はは極めて限られるというのが実状でしょう)。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年1月21日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.01.14 ==================================== 円安効果のタイムラグ ==================================== 先週、米国では利下げを好感して、ナスダック総合指数は前週末比9.1%高と反発。一方で、米国の 反面教師となっている日本は、日経平均株価が年初来安値を更新。そして、為替も1ドル118円台へと 円安ドル高傾向の加速。米国の電撃的な利下げを受けて、金融市場はだいぶ活気づいて来ました。 とりわけ昨年なかなか105-110円のレンジを抜けられずにいた為替の動向(円安の進行)が目に付 くところです。円安は日本経済にどのような影響を与えるでしょうか。 一般的には、大幅な貿易収支黒字を抱える(輸出超過国)日本にとって、円安はプラスの側面が強いと 言えるでしょう(但し、ユニクロやマクドナルド等、輸入中心の企業にとっては円安が原材料や製品価格 を上昇させ、減益要因。今元気の良い企業だけに気掛かりですが)。 先ず、円安によって輸出数量が増加し(円安→ドルベースでの国内製品価格の低下→価格競争力強化 →輸出増)、国内生産増加へとつながります。又、輸出採算の向上による(輸出企業の)収益増加や、 輸入物価上昇(円ベースでの海外製品価格の上昇)によるデフレ圧力の緩和にも寄与する事でしょう。 但し、円安となってからそのプラス効果が現れる迄にはタイムラグがある点には留意しておく必要があり ます。円安による相対価格の下落が、海外の小売り店に迄浸透して、外需を喚起する迄は少なくとも数 カ月の時間を要すると思われます。 従って、プラス効果が現れる迄に、現在顕在化している米国景気の減退に伴う外需の落込みというマイ ナス要因が先ず現れるという事も意識しておく必要があるでしょう。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2001」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2001年1月14日 生命保険特論「生命保険会社の選択法」 第3回 -------------------------------------------------------------------- 本稿は、FP講座に掲載していましたが、今回はトピックスに掲載します。 尚、本稿では、生保の安全性評価について順位付けをしていますが、これは、あくまでも私の私見に基づ くものであり、その予測結果を保証するものではありません。 6.生保の安全性評価 これまで説明して来た通り、契約者側の生保峻別意識が向上して来たことでこれまでの伝統的な国内漢 字生保が保有契約を減少させカタカナ生保をはじめとする新興生保へシフトしている現象は当面続くもの と思われる。しかしながら、この状況にあっても国内生保の保有契約高のシェアは93%を占めているわけ であり、以下に財務数値を中心にした指標を比較することでこれら国内生保の安全性を探ってみることし たい。 生保安全性評価 (99年度決算値ベース) 金額単位:億円 |
| 会社名 | 個人保険 年金保有 契約増減率 |
同左 順位 |
総資産 | 純含み益 A |
逆鞘累積額 B |
A-B=C | C対総資産 比率 |
同左 順位 |
順位数計 |
| 大 同 | -0.54% | 3 | 57,335 | 1,695 | 1,341 | 354 | 0.62% | 3 | 6 |
| 日 本 | -3.27% | 7 | 432,054 | 45,873 | 23,700 | 22,173 | 5.13% | 1 | 8 |
| 太 陽 | 0.37% | 2 | 70,816 | 2,823 | 5,460 | -2,637 | -3.72% | 8 | 10 |
| 富 国 | 1.07% | 1 | 46,138 | 1,286 | 1,960 | -674 | -1.46% | 6 | 7 |
| 第 一 | -2.76% | 5 | 300,423 | 18,330 | 15,500 | 2,830 | 0.94% | 2 | 7 |
| 安 田 | -3.11% | 6 | 100,802 | 3,722 | 4,720 | -998 | -0.99% | 5 | 11 |
| 明 治 | -5.52% | 10 | 168,462 | 8,940 | 10,200 | -1,206 | -0.75% | 4 | 14 |
| 住 友 | -2.39% | 4 | 236,825 | 6,585 | 15,700 | -9,115 | -3.85% | 9 | 13 |
| 三 井 | -4.74% | 8 | 100,700 | 2,684 | 6,311 | -3,627 | -3.60% | 7 | 15 |
| 朝 日 | -5.13% | 9 | 113,221 | 1,307 | 8,000 | -6,693 | -5.91% | 10 | 19 |
| 日 団 | -6.00% | 11 | 34,200 | - 806 | 1,840 | -2,646 | -7.74% | 11 | 22 |
| 東 京 | -6.89% | 12 | 10,953 | - 583 | 950 | -1,533 | -14.00% | 13 | 25 |
| 協 栄 | -7.08% | 13 | 46,099 | -1,038 | 3,900 | -4,938 | -10.71% | 12 | 25 |
| 千代田 | -9.72% | 14 | 35,019 | -2,602 | 3,990 | -6,592 | -18.82% | 14 | 28 |
| 会社名 | ソルベンジー マージン比率 |
同左 順位 |
含み益0の 日経平均株価 |
同左 順位 |
収支コア バランス度 |
同左 順位 |
順位数 合計 |
総合順位 |
| 大 同 | 1004.2% | 3 | 10,600円 | 2 | 86.1% | 1 | 12 | 1 |
| 日 本 | 1095.8% | 1 | 10,100円 | 1 | 96.9% | 3 | 13 | 2 |
| 太 陽 | 1050.3% | 2 | 10,880円 | 3 | 105.3% | 5 | 20 | 3 |
| 富 国 | 906.5% | 4 | 14,000円 | 7 | 89.2% | 2 | 20 | 3 |
| 第 一 | 865.6% | 5 | 11,400円 | 4 | 115.9% | 6 | 22 | 5 |
| 安 田 | 808.5% | 6 | 12,800円 | 6 | 101.9% | 4 | 27 | 6 |
| 明 治 | 731.0% | 8 | 12,000円 | 5 | 125.0% | 7 | 34 | 7 |
| 住 友 | 675.7% | 10 | 14,500円 | 9 | 125.0% | 7 | 39 | 8 |
| 三 井 | 676.7% | 9 | 14,000円 | 7 | 136.4% | 9 | 40 | 9 |
| 朝 日 | 732.7% | 7 | 15,500円 | 10 | 165.3% | 11 | 47 | 10 |
| 日 団 | 425.9% | 12 | 18,300円 | 11 | 145.9% | 10 | 55 | 11 |
| 東 京 | 446.7% | 11 | 20,800円 | 12 | 201.4% | 13 | 61 | 12 |
| 協 栄 | 210.6% | 14 | 21,000円 | 13 | 172.4% | 12 | 64 | 13 |
| 千代田 | 263.1% | 13 | 22,000円 | 14 | 237.8% | 14 | 69 | 14 |
| [説 明] 純含み益:株式含み益-不良債権額+貸倒引当金 逆鞘額累積値:7年間の逆鞘額の合計値 ソルベンシーマージン比率:solvency marginとは支払余力という意味。生保会社は、将来の保険金等 の支払に備えて責任準備金を積み立てているため通常予想出来る範囲のリスクについては対応 出来るとされるが、大災害や株式の大暴落等の予想出来ないリスクに対応出来る支払余力を有し ているかどうかを判定するための行政監督上の指標の一つ。 ソルベンシーマージン比率=ソルベンシーマージン総額/リスクの合計額×0.5×100 ソルベンシーマージン=基金(資本金)、価格変動準備金、貸倒引当金、株式含み益、劣後ローンなど リスクの合計額=保険リスク、資産運用リスク、経営管理リスクなど通常予想出来る範囲を超え るリスクを数値化して算出する。 この比率が200%を下回った場合には、監督当局によって早期に経営の健全性の回復を図るため の措置=早期是正措置が採られる。 しかし、この比率は、経営の健全性を示す一つの指標ではあるが、破綻した千代田が昨年3月末 で263.1%、協栄が210.6%で両社とも200%を達成していたことで信頼性に疑問が投げかけられてい る状況にある。11月1日の衆院大蔵委員会で、相沢委員長から算定方式の見直しを検討する答 弁がなされている。 収支コアバランス度:(保険金等支払金+事業費)÷保険料等収入×100 出 典:週間エコノミスト6月20日・11月7日号より引用。 |
| 2001年1月7日 JAPAN ECONOMIC REPORT 01.01.04 ================================== 米、緊急利下げ実施 ================================== 3日、FRBは緊急FOMCを開催し、異例とも言える利下げを実施しました。 声明文要約は「FOMCは、FFレートの目標水準を0.5%引下げ公定歩合の0.25%引下げを承認。 これら政策変更は、売上と生産の更なる軟化、消費者信頼感の低下、金融市場の一部で逼迫状況、 家計や企業の購買力を削ぐ高いエネルギー価格が背景。物価安定および持続可能な経済成長という 長期的な目標と、現在入手可能な情報から勘案すると、リスクは予見可能な将来に経済活動の一段 の悪化をもたらしかねない状況の方向にあると判断する。」と。 冒頭で「異例」と延べたのは、(1)定例のFOMCではなく、緊急にFOMCを開催して決定された事、 (2)下げ幅が通常の0.25%ではなく0.50%であった事が背景。グリーンスパンFRB議長就任後の 金融政策転換としては、極めて稀で、同様のケースは87年ブラックマンデー直後だけとなります。 景気に配慮した利下げの実施(”グリーンスパンのお年玉”と言う人もいましたが)を受けて、米国株市 場は急騰。米ナスダック総合指数は前日比325ポイント(14%)高と、上げ幅・率とも過去最大の上げ を演じる事となりました。 尤も、これは短期的・反射神経的な反応と言えるでしょう。企業業績が急速に悪化している中、このま ま株価が上昇傾向へと転じると見る向きは少数派です(昨年12月にグリーンスパン議長が利下げを 示唆する発言をした時も、米株の反発は1日限りで終った実績もあるだけに)。そもそもFRBが異例の 利下げを実施した事自体、米経済は相当なリスクシナリオを内包している事の裏返しなのです。 国内株式市場も朝方こそ買い先行でスタートしたものの、結局反落して初日を終了。リスクシナリオを 強く意識している事の顕われとも言えるでしょう。利下げは景気の下支え要因となるのは確かですが、 引続き強弱感が入り交じる荒っぽい相場展開が続きそうです。 【編】 ================================== ■用語解説 ================================== ●FRB:米連邦準備理事会。米国の金融当局です。 ●FOMC:連邦公開市場委員会。米国版金融政策決定会合です。 ●FFレート: フェデラルファンドレート。日本の無担保コール翌日物金利に相当。民間銀行は余った資金や必要な 資金を日々他の銀行と融通しあうのですが、この貸し借りの際に付与される金利です。中央銀行は日 々の市場の資金需給を見つつ、資金供給や吸収を実行し、金利を目標水準へと誘導していくのです。 そして、「利下げ」というのはFFレートの目標水準を引下げる事を指します。(同様の政策金利として 「公定歩合」もありますが、日本同様にやや形骸化しています。) ●利下げと景気の関係: 金利を下げると・・「企業や家計にとっては資金調達(借入)コストが低くなる→借金をして設備投資を 活発化させる企業や消費を増やす個人が増える→国内需要が増大する→景気が回復する。」 「資金調達コストの低減化による企業業績が改善、預金等金利商品の投資妙味が減退し、株式へと 投資がシフトする。→株価上昇→景気に対する強気な見通しが台頭、消費や投資も活発化→景気が 回復。」 ・・等々、一概には言えませんし、他にも様々な説明をする事ができますが、いずれにしても一般論とし ては「金利を下げると景気が回復する」事となります。【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
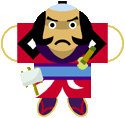
| 2001年1月1日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.12.26 今年も残すところあと僅かとなりました。当レポートも本号を以て今年は配信終了致します。今年と言う か20世紀も終りという事で、なんか感慨深いですね。 さて、毎年この時期に作成している来年の景気シナリオを完成させました。一言で言うと、またしても「悲 観シナリオ」色が強くなってしまいました(いつも今回こそは「楽観シナリオ」を、と思っているのですが・・) 何か明るい話題ないかなぁ。 それでは、皆様には良いお年を!そして、世界中が平和な21世紀となりますように。 【編】 =================================== 人の行く裏に =================================== 本年もご愛読いただき大変有難うございました。今年最終号なので本年金融市場の総括でもさせて下 さい。 今年の相場は、あまり動かなかったようで、結構動きましたね。年初はネット株が高騰する等、株式市 場も好調。民需(特に民間設備投資)主導型の景気回復の色合いが強まり、日本経済に対する楽観論 が支配しました。 この中、緊急非難的な措置として継続されていた「ゼロ金利政策」解除の議論が台頭。デフレ懸念払拭 の蓋然性が高まった事から、遂に日銀は9月にゼロ金利政策を解除し、政策金利の0.25%引き上げ を実施しました。 一見、これで長く暗い不況のトンネルからの脱出が出来たかと思われましたが、「トンネルを抜けると、 そこはまたトンネル」でした。 相次ぐ生保の破綻。増加する企業倒産。好調な企業業績の犠牲となり、低迷する個人所得並びに個人 消費。日米政局の不透明感。米経済の失速、そして日米株価の大幅安。円相場も年初来安値を更新。 質への逃避の動きから、年末にかけては債券価格が急騰(=利回りは急低下)。尤も、円債は財政悪化 に伴う需給悪化懸念から上値余地は限定的ですが、米債については利下げ期待も強まり、次々と上値 を更新(=利回りは低下)していっています。 年初は誰もが株式投資に目を向けていたのですが、結局、株ではなく債券、とりわけ米国債に投資した 方がインカムゲイン(高い米国金利による収益)、キャピタルゲイン(価格値上がりに伴う益)、(円安に よる)為替差益を享受でき、高パフォーマンスを達成された事でしょう。 「人の行く裏に道あり花の山」---ですね。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年12月25日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.12.21 =================================== 米、金融緩和方針変更 =================================== 米連邦理事会は、19日開催した連邦公開市場委員会(FOMC)で、当面の金融政策の運営方針を変 更。米金融政策方針については、「インフレ警戒型」「中立型」「景気配慮型」の3つがあるのですが、今 回は「インフレ警戒型」から「景気配慮型」へと、「中立型」を飛び越え、一気に金融緩和スタンス(金利 引下げ方向への金融政策スタンス)へと転換しました。 FOMCの声明文では「消費者の自信が揺らいでおり、エネルギー価格の上昇が需要や企業収益への 障害となりつつある。これに加え、売り上げや利益の急減に関する報告、金融市場での引き締りもあり、 経済が減速の度合いを強めている」云々・・。米景気減速ペースの予想以上の速まりに加え、株価も大 きく売られている事から、金融面での景気の下支えを図ろうというものです。 しかし、今回は実際の利下げは見送り。ほぼ織り込み済みと見られていましたが、同FOMCでの利下げ 断行という期待もかなりあったのか、失望感からナスダック総合指数は大きく売られました(そして日経平 均株価も年初来安値を更新)。 売りの主役はやはりハイテク関連株ですが、これらの企業はもともと有利子負債(借金)の比率が低く、 金利感応度(金利の上下による業績への影響)はそれ程大きくないとも言われていた業種です。とすれ ば、多少の利下げが実施されたとしても減速する半導体需要の底入れが確認されない限り、業績の底 入れも見込めないという事にもなりかねません。神経質な状況が続きそうです。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年12月23日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.12.19 先週、千葉幕張地区に開店した仏カルフール。メーカーとの直接取引等により安値実現を目指している 同社ですが、交渉はまとまらず、卸(問屋)を経由する日本の商慣習の壁に悩まされているようです。 「そうは問屋が卸さない」ではなくて、「そうは問屋に卸させろ」? 【編】 =================================== 保護主義的な措置に伴うリスク =================================== 19日、ユニクロを展開するファーストリテーリングの株価が急落しました。国内繊維製品業界が中国か らの輸入製品業界に歯止めをかける為に、年明けにも政府に対して緊急輸入措置(セーフガード)の発 動を申請する事が伝わった事によるものです。業績好調なファーストリ社は、製品の9割を中国で生産。 安価な輸入品の急増は、価格競争力の劣る他の国内メーカーの経営を直撃し、セーフガード申請はそ の危機感の顕われと言えるでしょう。 しかし、一方で、ファーストリ社の成功モデルに続けとばかりに、イトキン、セシール等、相次いでコスト の安い海外に生産拠点を移す動き国内メーカーも増えています。 こうなってくると、セーフガード発動は、時代に逆行する保護主義的な措置という点において世論の賛成 が得にくく、構造改革の進展も見込めないという問題に加え、競争に生き残る為に進めた自らの退路(生 産拠点の海外シフト)を断つという事にもつながりかねず、根本的な生き残り策にはなりません。 ここ数年を見ると、ユニクロのファーストリテイリング、日本マクドナルド、百円ショップのダイソー等々、日 本の古き商慣行から脱皮し、グローバルに資材を調達してきた企業の躍進が目立ちます。もし、これら勝 ち組企業のビジネスモデルを制約する保護主義的な措置が行なわれれば、景気回復の牽引役を失い、 日本経済の活力を減退させる事へとつながる気がしてなりません。 【編】 =================================== ■用語解説:緊急輸入制限措置(セーフガード) =================================== 世界貿易機関(WTO)で認められているもので、特定品目の輸入が急増し、国内の産業に重大な損害 を与えかねないように、政府が輸入を制限する措置。業界団体が品目別に申請し、発動されると特定品 目、特定国に対して輸入量が三年間制限されます。ただ、過去1年の輸入実績の6%増迄は輸入が認 められますので、輸入量は一気に減らす効果はありません。 これまで、国内では一般産品では発動の例はなく、又、発動すると日本への輸出に力を入れる国からの 対抗措置が講じられる事も懸念されます。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年12月19日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.12.14 日銀短観が景気の足踏みを示唆する内容だった事、米大統領選も漸く決着した事等から為替相場はド ル高円安方向へ。レンジを放れ、一時年初来安値を更新しました。 ところで、お歳暮&クリスマスプレゼントの用意はされましたか?ネットで繰り広げられる「eクリスマス」 激戦の中、各社とも様々な特集・企画を実施しているようです。【編】 →http://oseibo.rakuten.co.jp/?PR001245 ==================================== 設備投資依存型回復 ==================================== 先週発表された7-9月期のGDP。個人消費は前期比横ばい、輸出の頭打ちで外需も落込み、公共 投資の急減から公的需要は減少という厳しい状況下、設備投資は前期比+7.8%と、80年以降最大 の伸びを記録。この1年間の経済成長は設備投資だけで説明できてしまう程でした(尤も、その後発表 された法人企業統計に基づけば、設備投資が下方修正され、同GDPもマイナスに転じる見込)。 13日、注目を浴びていた日銀短観の発表がありました。発表された今年度設備投資計画を見てみると 、こちらも予想よりも上振れし、「設備投資依存の景気回復」をあらためて裏付けるものとなりました。 一方、二年来続いてきた企業の業況感の回復は頭打ちです。先行きの見通しも下振れし、今年度下期 の経常利益計画の下方修正や国内外での需給緩和感の台頭が影響しているようです。又、業種別に 見ると、これまで景気回復の牽引役となっていた電機機械等の業況感悪化が目立ちます。半導体の出 荷も伸び悩み、「シリコンサイクル」の動向が意識されているところでしょう(半導体出荷の増加率をグラ フに描くと規則的なサイクルが見られるのですが、現在は下を向きつつある事から、今後の半導体需要 の失速懸念が出ているもの)。 結局、強弱材料入り交じりといった感じなのですが、個人消費が伸び悩み、又、公的需要や外需の鈍 化傾向が続きそうな中、設備投資に過度に依存した景気回復には何時ブレーキが掛かってもおかしく ない状況と言えるでしょう。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年12月10日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.12.07 さて、5日、景気減速懸念から下落していた米ナスダック総合指数は、グリーンスパンFRB議長が景 気減速を認める発言を行なった事で過去最大の上げを記録。 実に矛盾した動きではありますが、これもグリーンスパン信仰の顕われと言えるのでしょう。 しかし、6日はその矛盾からか反落。下記コラムは、たまには楽観的な方向でと、前日に書いたので すが、やはり不透明感は残ります。日々の動きに追われてしまうと「木を見て森を見ず」という状況に なりかねないので、御注意を。 【編】 =================================== 下値不安払拭か? =================================== 米国株安と米国景気のハードランディング懸念、日本の政局及び米国大統領選の混迷、ユーロ安及 び原油高による企業収益圧迫観測、国内景気失速観測の台頭など、年度下期の国内株式市場を取 り巻く環境は厳しいものでした。 ただ、最近は幾つかの情勢の変化も見られます。 先ずは、米国動向。景気の鈍化を示す経済統計が続いていますが(11月の全米購買部協会の総合 景況指数は4ヶ月連続の4ヶ月の50割れ、10月の個人所得は2年振りの減少、失業保険の申請者 数は直近週の統計で過去2年間で最大、等々)、意外にも株価は反発しています。 5日のNY市場。グリーンスパンFRB議長が米景気減速懸念を表明した事を受けて金融緩和観測が 広がり株価は急伸。「景気減速→金融緩和→ハードランディングではなく、ソフトランディングへ→好 景気持続へ」という連想です。 又、米大統領選挙はブッシュ勝利の方向で固まりつつあり、国内政局も「取り敢えず」は落ち着きを取 り戻しております。先行きが全く分からなかった数週間前と比べれば、不安心理はかなり払拭。そして、 ユーロも反発傾向、原油高も30ドルを割り込みピークアウトした感があります。 尤も、これらを受けて株価底打ち感も出ておりますが、上値を試す好材料があるわけでもありません。 グリーンスパン議長が警鐘している逆資産効果(「資産価値の低下が家計や企業の消費活動を下押 しするかもしれない・・・」)を回避する事ができるか等、引き続き見極めていく必要がありそうです。【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年12月3日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.11.23 ========================================== 日本版REIT解禁 ========================================== 小口の投資資金を不特定多数の投資家から集めてビルやマンションを購入し、そこから得られる賃 料収入や売却益などを投資家に配当していく不動産投資信託が11月末の改正投資信託法施行に 伴い解禁されます。 従来からも、投資家から集めた資金で不動産を運用する商品は存在しましたが、相場は一口数百万 円。しかし、今回の解禁により一口単位は5~10万円単位程度となる予定です。 又、来年3月には東京証券取引所が売買市場を創設する事から、流動性も高まりやすくなります(用 語解説「流動性リスク」御参照)。 不動産投信の特徴は、ミドルリスク・ミドルリターン。配当はビルやマンションの賃料・稼動率が反映 され、不動産価格の変動(値上がり・値下がり)の影響を直接的に受ける事は無く、利回りは年4~5 %程度になると見られております(勿論、投信の市場価格が購入価格を下回る事はありますが)。 問題点として指摘されているのは、投資対象不動産の情報開示の問題。特に不動産投資に不慣れな 個人投資家の保護等に重点を置き、法制度の整備を進めていく必要があるでしょう。 米国では「REIT」と呼ばれ90年代に入って急成長。上場のREITの時価総額は14兆円にのぼって います。不動産好きの日本人。国内市場でどの程度裾野を広げていく事ができるでしょうか。 【編】 ========================================== ■用語解説:流動性リスク ========================================== 個人が投資を行なう時、「市場リスク(価格変動リスク)」にはかなり神経質になるのですが、意外に 見落とされがちなのがこの「流動性リスク」。 「流動性がある」というのは、その市場に常に売り手や買い手が存在し、売買が活発に行なわれてい る状態の事。このような状況においては、投資家は何時でも売りたい時、買いたい時(或いは、利益 や損失を確定したい時に)に自由に売買ができるわけです。 一方で、「流動性がない」というのはその逆。例えば、売って損失を確定したくても売れない、そうこう しているうちに損失が益々膨らんでいく。流動性の乏しい「東証マザーズ」に参加している投資家な どは、今年このような苦労をされた事も多い事でしょう。 「市場リスク(価格変動リスク)」があまりないのに、利回りが高いというような、一見ローリスク・ハイ リターン型の金融商品の裏側には、高い流動性リスクが潜んでいる事が多々ある事なので、御注意 下さい。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年11月26日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.11.23 23日はサンクス・ギビング・デー。皆様、有意義な休日を過ごされましたか? 米国では、この日を境に一気にクリスマスモードが強まります。そして、小売業のクリスマス商戦もいよ いよ本格化。減速感が漂いつつある米国の個人消費の先行きを占う同商戦は、4年振りに前年を下回 る見通しです。 昨年は、クリスマス商戦をバネとしたネット販売の普及に関連して「eクリスマス」という言葉がよく聞か れましたが、果たして今年は良いクリスマスになるでしょうか。 22日の米国市場はナスダック総合指数がまたしても崩れておりますが、東京市場はいかに。 【編】 ==================================== 個人金融資産、統計と実感のズレ ==================================== 個人金融資産1400兆円。--よく出てくる数字ですが、これは日銀の資金循環統計に基づくもので す。 しかし、これを単純に人口で割り出すと、1人当りの金融資産は約1100万円。うーん、実感にあいませ んね。 先日、日銀が「我が国の金融構造」というレポートを公表していましたが、その中で個人金融資産の数字 が過大評価になっていないかを検証するコラムがありました。 曰く、「資金循環の定義上、(1)金融資産の中に、年金準備金(生保の年金商品など)、預け金(ゴルフ 会員権など)など自らの金融資産とは認識し難い金融商品が含まれている、(2)家計部門には、個人 ではなく、個人事業主の事業性資金も含まれており、これらを割引いて考えた方が良い点もある」と。 そうすると1人当り800万円。 でもやっぱり実感にあわない。きっと、ものすごくお金持ちの人が少数でもいるのでしょう。 【編】 ==================================== ■用語解説:個人金融資産 ==================================== 解説というよりか、補足ですが、総務庁の「貯蓄動向調査」では99年12月時点で1人当り500万円 (含、事業性資金)、貯蓄広報中央委員会の「貯蓄と消費に関する世論調査」では2000年6月時点で 1人当り400万円(除、事業性資金)という結果が出ております。こちらの方がまだ実感にあいますね。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年11月19日 江戸(繁盛)しぐさ 11月11日に実施しました第19回定例会で富士常葉大学流通経済学部の竹内教授は、我国のこれか らの在り方について次の4つの提言をされました。 1.自助意識の確立が大前提 政治家、官僚など「お上意識」からの脱却をすべきであり、そのためには、日本版ペコラ委員会を 設置し、この20年間の経済・金融失政を総括して責任を取らせる。 2.国民全体がゼロエミッション立国を共通認識 環境安全保障戦略「世界が日本を失うと環境制約をクリアー出来なくなる」状況を作る。 地政学的に日本にとっては不可欠(中国と隣接し偏西風が吹く) 3.アジア経済・文化圏の確立 円の決済通貨への提供、為替リスクなしに成長経済圏に投資出来る体制をつくる。 日本の世代間問題解決にも一役。 4.江戸商人文化を参考に 「江戸しぐさ」・・・880項目、人間観察の極意、300年前に世界に先駆けて循環型共生社会を実現。 私は、特に上記の内4.の江戸商人文化の話に感銘を受けましたので、今回は、「江戸しぐさ」につ いて少し触れてみたいと思います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 「しぐさ」は、表情のひとつであり、「しぐさ」は人が人への思いやりでもあります。それ は「共生の知恵」とも言うことが出来ます。 「江戸しぐさ」とは、江戸時代半ばに江戸市中で生まれた譲り合いの精神だったとされていま |
| 2000年11月12日 JAPAN ECONOMIC REPORT 00.11.09 無利子国債 ================================================================== 政府自民党が2001年度の税制改正での相続税軽減策として、無利子国債の導入を検討し始めて います。 無利子国債は、(1)記名制、(2)無利子、(3)購入者は額面全額を相続税の課税対象から控除で きる、等の特色を持つ国債で、政府の利点として、(1)国債の消化を促し長期金利の上昇を抑制でき る、(2)国債利払い費を軽減できる等が挙げられております。(97年に旧国鉄の長期債務処理策を 議論する過程で浮上し、又、99年に国債の大量発行が不可避となるなかで、その円滑消化を図る事 を理由として検討された事もあります。) しかし、一方で(1)一部の金持ち優遇策、(2)国債利払費の軽減分より相続税収の落ち込みの方が 大きくなる、(3)優遇税制がないと売れないという悪いイメージを与える等という批判論も多くなってお ります。 ただ、実施の有無に関わらず金融市場へのインパクトは殆どないでしょう。相続税が課税されるのは、 全死亡者の約5%、税収全体に占める相続税収のウェイトも軽微なものです。相続税対策に悩む人 が少ないのですから、仮に無利子国債が導入されたとしても、購入ニーズは乏しく、発行金額も限定 的となる見込みです。 国債消化の為に、様々な事を考えていく事はそれはそれで良いと思います。尤も、財政運営スタンス を変えずに優遇税制のみ導入するという政策は、抜本的な解決にはつながりにくいかと思いますが。 【編】 「JAPAN ECONOMIC REPORT編集部 Copyright(C), 1998-2000」 URL<http://www.jerep.com/> |
| 2000年11月5日 遠距離介護について考える その8 前回の介護保険入門クイズを皆さんトライして頂けたでしょうか?身近に介護の問題を抱えている人と、そ うでない人では関心度合いが違うのでしょうが、今、介護の問題に直面していなくても、いつかは皆さんに関 ることですので、基本的な事項の認識はして頂きたいと思います。 しかし、このクイズはFP試験の問題の様にひっかけ問題みたいなところがありまして、私自身、介護の問題 を講演している立場でありながらこのクイズの正解率は60%でしたし、実際、介護施設でケアマネージャーを されている方でも回答に窮している方がおいででした。 このことは、やはり、この制度を国民に周知させるにはもっと努力と工夫が必要なことを示しているのだと思 いました。 --------------------------------------------------------------------------------- 介護保険入門クイズ 問1:介護保険では、40歳以上であれば誰でも介護保険サービスを受ける事が出来る? はい ・ いいえ 解答:いいえ→65歳以上の第1号被保険者は認定に応じたサービスを受けることが出来ますが、40歳以上 65歳未満の第2号被保険者(医療保険加入者)は、初老期痴呆や脳血管障害など、老化にともなう 病気によって介護が必要な人が対象になります。 問2:介護保険のサービスを利用する前には、必ず訪問調査を行います。訪問調査は、市の職員かケアマ ネージャーが行いますが、基本調査項目は、何項目あるでしょうか? 75項目 ・ 85項目 ・ 95項目 解答:85項目→主として日常生活と身心の状態に関する事項を調査します。この結果はコンピューターに 入力され介護に要する手間の程度が要介護認定基準時間という数値で出され、認定の段階に仮区 分されます。これが1次判定です。 問3:介護保険の認定の結果は、何段階に分れているでしょうか? 5段階 ・ 6段階 ・ 7段階 解答:7段階→自立・要支援・要介護1~5となります。 問4:介護保険サービスが受けられるのはいつからでしょう? 申請日 ・ 介護度が決まった日 解答:申請日→要介護認定にかかる期間はおおよそ30日とされています。但し、急を要する場合は、認定 前であっても、先ず先にサービスの給付を受け、認定を事後に行う事が出来ます。その場合、取り 合えず利用者が立替払いをし、後で利用者負担の1割を除く費用の給付を受けることになります。 問5:介護サービスを受けるためには、ケアプランを作成しますが、ケアプランはケアマネージャーに依頼し ても、自分で作成してもどちらでも良い? はい ・ いいえ 解答:はい→利用者本人がケアプランを作ることも出来ますが、ケアマネージャーと相談して作成する方が 効率的でしょう。 問6:介護度によって、使用できるサービスの利用量(限度額)が決まっている? はい ・ いいえ 解答:はい→標準地域における利用上限額は以下の通りです。 要介護度 上限月額 短期入所利用日数 要支援 61,500円 7日 要介護1 165,800円 14日 要介護2 194,800円 14日 要介護3 267,500円 21日 要介護4 306,000円 21日 要介護5 358,300円 42日 問7:福祉用品は1年間に10万円まで購入することが出来ますが、必要な物は何でも購入出来る? はい ・ いいえ 解答:いいえ→福祉用具購入費用として支給されますので「何でも」とはなりません。 問8:介護保険の認定を受けた人は、誰でも施設介護サービスを利用することが出来る? はい ・ いいえ 解答:いいえ→要支援の人は対象となりません。(ショートスティは可) 問9:介護保険で利用出来る施設サービスは3種類ありますが、目的によって使用する施設を選ぶことが出 来ます 適合する施設名と使用目的を選択して下さい。 施設名: ・ 介護老人福祉施設 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護療養型医療施設 使用目的: ・治療が中心 ・介護が中心 ・機能訓練が中心 解答:介護老人福祉施設→治療が中心 介護老人保健施設→機能訓練が中心 介護療養型医療施設→治療が中心 問10:認定された介護度の有効期間は、原則として6ヶ月となっていますが、有効期間内は一度決まってし まった介護度は変えることが出来ない? はい ・ いいえ 解答:いいえ→要介護認定は一定の期間(3~6ヶ月)毎に見直されますし、重度になった場合には要介護度 の変更も適宜可能です。 さて、皆さんの正答率はどの位だったでしょうか? |
| 2000年10月29日 遠距離介護について考える その7 これまで遠距離介護についてこれまでの私の経験を通じて考えたことをご紹介して来ましたが、ここで今年 の4月から開始された介護保険制度について触れてみたいと思います。 手始めに藤沢市介護保険課が主催した「介護教室」にて実施された「介護保険入門クイズ」を紹介しますの で、貴方の介護保険の理解度を試して見て下さい。回答例と解説は次回に掲載します。 ---------------------------------------------------------------------------------- 介護保険入門クイズ 問1:介護保険では、40歳以上であれば誰でも介護保険サービスを受ける事が出来る? はい ・ いいえ 問2:介護保険のサービスを利用する前には、必ず訪問調査を行います。訪問調査は、市の職員かケアマ ネージャーが行いますが、基本調査項目は、何項目あるでしょうか? 75項目 ・ 85項目 ・ 95項目 問3:介護保険の認定の結果は、何段階に分れているでしょうか? 5段階 ・ 6段階 ・ 7段階 問4:介護保険サービスが受けられるのはいつからでしょう? 申請日 ・ 介護度が決まった日 問5:介護サービスを受けるためには、ケアプランを作成しますが、ケアプランはケアマネージャーに依頼し ても、自分で作成してもどちらでも良い? はい ・ いいえ 問6:介護度によって、使用できるサービスの利用量(限度額)が決まっている? はい ・ いいえ 問7:福祉用品は1年間に10万円まで購入することが出来ますが、必要な物は何でも購入出来る? はい ・ いいえ 問8:介護保険の認定を受けた人は、誰でも施設介護サービスを利用することが出来る? はい ・ いいえ 問9:介護保険で利用出来る施設サービスは3種類ありますが、目的によって使用する施設を選ぶことが出 来ます 適合する施設名と使用目的を選択して下さい。 施設名: ・ 介護老人福祉施設 ・ 介護老人保健施設 ・ 介護療養型医療施設 使用目的: ・治療が中心 ・介護が中心 ・機能訓練が中心 問10:認定された介護度の有効期間は、原則として6ヶ月となっていますが、有効期間内は一度決まってし まった介護度は変えることが出来ない? はい ・ いいえ 以上、初見で貴方はどれだけ正解出来るでしょうか? |
| 2000年10月22日 遠距離介護について考える その6 [参考資料] 1.ホームヘルパーについて ホームヘルパーは、ヘルパー養成研修で訓練を積み、その研修時間によって1~3級に分れる。 国で定められた研修時間は50~230時間で、1級が主任ヘルパーになる。 介護保険制度導入にあたり、17万人のホームヘルパー育成が目標になったが、導入後の現在もまだ まだ足りない。 在宅介護の場合、家事援助や身体介護等ホームヘルパーが大きな役割を果たすが、多くの優秀なヘ ルパーをどれだけ確保出来るかが在宅介護成否の大きなカギとなっている。 ホームヘルパーの仕事 ・ 身体介護:食事・排泄・着替えや入浴の介助等 ・ 家事援助:調理・洗濯・掃除等 ・ 複合型:身体介護と家事援助の中間型 親の介護でヘルパーさんを頼む場合、どうしてもヘルパーさんの質が気になるところです。 当家の場合、大分の母親にお願いしているヘルパーさんに問題があったため対応に苦慮したことがあ ります。初めて派遣をお願いする際ヘルパーさんを指名出来る機関はないでしょうから、派遣の契約 を結ぶ前に契約書やパンフレットに利用者の都合によるホームヘ ルパーの交代の条項があるか確認することが必要です。 しかし、ホームヘルパーの実態は非常勤やパート扱いが多く1日の実働5時間分が他の仕事の8時間 分に相当し、賃金も10数万円程度であり、移動時間等が無給部分が多い実態がある。ホームヘルパー の増員にはこれらの雇用条件や環境が課題になっている。 ホームヘルパーを確保しにくい離島・山間過疎地等で市町村長が認めた場合、ヘルパー資格保有者の 家族ヘルパーが認められる。但し、ケアプランに沿った身体介護に限られる。 また、家族介護慰労金は家族ヘルパーとは別のもので、介護保険の枠外。要介護認定で介護度4か5と 判定され、1年間は介護保険のサービスを申請せず、家族で介護をした場合に年間10万円を限度に支 払われる。(2001年度以降)他にオムツ代など10万円を限度に介護用品を支給する制度もある。 (2000年度より) 2. 介護施設サービスについて 介護サービスは、在宅サービスを重視する制度と言われるが、高齢者世帯が増え、施設で暮らしたい と望む人は多い。介護保険では利用者が施設を選び契約する。 この制度上では、以下の三施設が対象となっている。 ① 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):常に介護が必要で在宅生活が難しい人向き、常勤 の医師はいないが部屋の面積(10.65㎡)や隣のベッドとの間隔等は他の2施設よりは余裕があり食堂 もある。 これまで本人や扶養義務者の収入に応じて、最高で月24万円の利用者負担があったが介護保健制度 では、月5万円程度の負担で利用出来るようになった。 ② 介護老人保健施設(老人保健施設):病状が安定していてリハビリや看護・介護を必要とする人向 き、リハビリ施設が整い自宅に復帰するための施設と位置付けられる。 ③介護療養型医療施設(療養型病床群・老人性痴呆疾患療養病棟・介護力強化病院):長期の 療養を必要とする人が入る。医師が常駐しており、緊急事態には安心して対応が可能。 1ヶ月当りの平均利用者負担額(介護+食費):円 特別養護老人ホーム 老人保健施設 療養型病床群 標 準 50,000 53,000 60,000 市町村民税世帯非課税者 40,000 40,000 40,000 老齢福祉年金受給者 24,000 24,000 24,000 介護保険では、利用者と施設の契約で入所が決まるが、厚生省は原則として、申込み順で入所させるよ うに指導している。 短期入所サービス利用の注意点 要介護度によって、半年間に1~6週間の利用枠がある。要介護認定の更新4ヶ月前と3ヶ月前の2ヶ月 間、ホームヘルプ等訪問通所サービスの利用実績が6割未満の人は2倍(要介護5のみ1.5倍)拡大出来 る。 また、訪問通所サービスの利用限度学の範囲内なら、1ヶ月に2週間を限度にショートスティに振替える ことが可能。 短期入所サービス利用枠 要支援:1週間、要介護1・2:2週間、要介護3・4:3週間→、要介護5:6週間。 ディサービス・ディケア(日帰りサービス)の利用 心身の機能が低下して来ると、外出する気力が失われてきて家に閉じこもりがちになるケースが多い。 これをそのまま放置しておくと益々心身機能が低下するので、こんな場合にディサービスやディケアを 勧めてみることも必要。 ディサービス:ディサービスセンターでの生活指導、日常生活訓練、食事、入浴などが受けられる。 ディケア:老人保健施設や病院などの医療機関で、食事、入浴、機能訓練などのサービスが受けら れる。 実際のところ、このサービスは老人のための良い社交場の機能もあるようで、私どもの大分の母親は 非常に楽しみにしています。 利用する時の注意点 上記の通り、大分の母親は外交的な性格のためこのサービスを好んで利用していますが、逆に富山 の母親のように人との交わりを苦手とする親は利用を望まないケースもあります。 嫌がるものを無理強いしない様に心がけ、複数の施設のサ-ビス内容を比較しながら本人に あったサービスを検討する必要があります。 次回へ |
| 2000年10月15日UP 遠距離介護について考える その5 ハ. 医療費控除や健康保険の利用 扶養家族が認められた場合、子供が払った親の医療費を医療費控除出来るので領収書は取って おきましょう。医療費控除の対象は判断が難しいものがあるので不明なものは税務署に確認しまし ょう。 [医療費控除] ・ 200万円を限度に支払った医療費を所得から引く事が出来る。年末調整ではなく確定申告が必要。 ・ 既に支払った金額だけが控除の対象になる。未払い分は、支払った年に控除が可能となる。 ・保険などで補填を受けた場合は、医療費から差引かなければならない。 ニ. 帰省交通費の節約方法 航空機を利用する場合は、日本エアシステムの「介護帰省割引」がお薦めです。これは、介護保険 で「要支援」「要介護」の認定を受けた親を介護するためにその子供が帰省する場合、配偶者など二 親等までの親族の運賃を普通運賃より約37%割り引きとなります。この割引は、親と子の住居の最寄 の空港に限り何回でも適用されます。座席制限がなく、当日予約や予約変更も可能です。但し、この 割引を利用するためには、日本エアシステムの支店で事前に登録を済ませ証明書(介護帰省パス) の発行を受けておく必要があります。また、JASが運行していない地域や介護認定が自立となった場 合は、各社の事前購入割引の利用や金券ショップの利用を検討すべきです。 ③ 介護退職は避けるべき 最初に私が申し上げたいのは、「介護は一生続かない」と言う事です。遠距離介護が長引くと心身とも に疲れ果て、仕事を辞めて親の介護に専念しようと考え始める人は多いと思います。しかし、会社を辞 める事で親の介護の問題は、解決出来ても自らの収入の道は断たれることになります。自分の家族に も大きな影響が生じることにもなるわけで「自分が仕事を辞めれば解決するか」といえば決して単純な 問題ではありません。実際の話、私の様に会社を辞めた翌日に父親が亡くなり介護が終わることもあ るのです。 また、仕事を辞めて介護をしろと周りから言われるのは、たいていの場合、娘にあたる人や息子の連れ 合いの人など女性が多い傾向があります。仕事を続けたい意志が強い場合は、夫婦で良く話し合って 継続する方法を考えるべきです。 最近、介護を必要とする家族のために一定の期間休業出来る「介護休業制度」が法制化されました。 期間契約者等の一部の人を除き雇われて働いている人が対象となります。 対象となる家族とは、二週間以上の期間に亘り常時介護を必要とする状態にある人で、配偶者、父母、 配偶者の父母、子及び、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫とされています。休業出来る期間 は、連続する3ヶ月を限度として、要介護者一人に対して一回です。休業期間の賃金は事業主が決めて いいことになっていますが、多くの場合が無給です。実際に利用する場合に問題点は多々ありますが、 知っていて損はない制度でしょう。 ④ 施設入所を考慮する。 これまで介護を在宅を前提として話して来ましたが、介護には施設介護という形態もあります。親世代 のほとんどは住みなれた住いで介護を受けることを望んでいます。しかし、介護は、介護を受ける者と 介護を行う者の両者がいてこそ成り立つものであり、親が在宅介護を要望しても行う者に出来ない事情 があれば成り立ちません。在宅での遠距離介護がどうしても無理になったら施設の利用も考慮にいれ るべきです。 施設といっても終の住処となるところばかりでなく「老人保険施設」のように家庭復帰を目的としている 施設もあります。この施設は概ね3ヶ月程度の入居期限があることが多く、介護する者が一時的に通 えなくなった場合に利用する方法もあります。 施設利用の場合は、親と事前にじっくりと話し合う必要があります。そのことが結局はお互いのために なる可能性が大きいと思います。 4.おわりに ひとことで「遠距離介護」といっても人によってその状況は異なるが、どんな状況にせよ親の介護に は、お互いの距離が障害になることは共通しています。 誰しも歴史を後戻りすることは出来ず。自分が今置かれている状況の中で最善をつくすしかないの ではないかと思います。離れていても親子の気持を繋げる方法を工夫すれば、一緒に住んでいるよ りも効果的なこともあるでしょう。 ここにあげた全ての方法が万人に適するものではありませんが参考になれば幸いです。 次回はホームヘルパーと介護施設サービスについてお話します。 |
2000年10月8日
遠距離介護について考える
その4
| 3.遠距離介護に限界を感じる前に ① 周囲からの小言は無視する。 遠距離介護は、世間一般からは理解を得られているとは言い難いでしょう。特に私や配偶者の故郷 ではなかなか受け入れられる状況にありません。親の世話は子供が行う事は当然という考え方が 根強いからです。実家のご近所や親戚の方が親の状況を把握していることも多く「何故、同居しな いのか?」「親を放置しておくのは親不孝」と指摘されることがよくあります。特に非難されやすいの は長男の嫁の立場にある人でしょう。 遠距離介護が考えた末の結論であれば、外野の声をあえて無視することも必要です。周囲の人は 結局、口は出すけれど手は出さないのですから。 大切なのは、他人の意見ではなく子供と親の気持ちだと思います。 ② 介護貧乏にならないために 遠距離介護をする者にとって「お金」の問題は切実なことです。介護が必要になると何かと費用が 嵩み、子供が仕送り等の形で負担するケースも見られます。 また、実家へ赴く時の交通費も頻度によりますが、私の場合富山までの往復で交通費で概ね5万 円はかかりますので、毎週帰省していた時は月に20万円は支出していたことになります。 実際のところ、親の介護が必要になる頃は子供の方もその子供の教育費や家のローンに追われ る時期と重なることが多く家計的に苦しいのではないでしょうか? それに対して、親の方が結構裕福だったりするケースもあります。そんな時には、親が子供にお金 を渡すこともあると思います。 私の場合もそうで、最初は親からお金を貰う事に抵抗があったことは事実ですが、その方が親の 気持の負担が軽くなることもあり、「ありがとう」と受け取ることにしました。 私のケースはともかく、いろいろな工夫をして経済的負担を少しでも軽くすべきです。以下に具体的 な方法を紹介します。 イ. 親を扶養家族にして税金の控除を受ける。 親の収入が僅かで子供が親に仕送りを行う場合は、例え離れて暮らしていても同一生計というこ になり所得税の扶養控除が認められます。 ロ. 身体障害者手帳は貰えないか? 身体障害者手帳とは、身体の特定部位に永続的な障害のある人がいろいろな社会福祉制度を受 けられるようになる手帳です。障害の程度により1級から6級の段階があります。 交付対象者:上肢・下肢・体幹・目・耳・言語・心臓・呼吸器・腎臓・膀胱・直腸・小腸に一定以上の 永続する障害を有する者 申請方法:市区町村の指定医による診断書、印鑑、写真を用意し市区町村の窓口に申請する。 受けられるサービス:人工関節の手術や人工透析といった医療の給付 義足や車イス等、補装具の給付 ホームヘルパーの派遣 JR、バス、飛行機等の旅客運賃の割引 所得税、地方税、自動車税、自動車取得税の控除、減免 但し、身障者と認定される親の気持は決して良いものではありませんのでその点についての配慮 が予め必要です。 イとロにおける所得税控除は以下の様になります。 ① 生活費を負担している証明がある②親の所得が38万円以下である③他の誰か(兄弟等)の 控除対象になっていない。という条件を満たしていれば→38万円の扶養控除が受けられる。さら に親が70歳以上の場合+10万円。更に親が身体障害者手帳を交付されていたら27万円の障害 者控除が受けられる。また、障害の程度が1級・2級の場合等は特別障害者控除として40万円 が認められます。 老人・障害者関連所得税・個人住民税人的控除(万円) 項 目 所得税 個人住民税 扶養控除 扶養親族 38 33 老人扶養親族70歳以上 48 38 同居老親等加算 +10 +7 同居特別障害者加算 +35 +23 老年者控除(本人) 50 48 障害者控除 障害者 (本人、配偶者、親族) 27 26 特別障害者(同上) 40 30 次回に続く |
2000年10月1日UP
遠距離介護について考える
その3
| 2. 親の心身の状態が衰えてきたら… ① 近所の人を味方につける 親が弱ってくると子供としても心配になるし親の方も不安になり、頻繁に子供に電話してくるように なります。近くに住んでいれば直ぐに会いに行けるのですが、遠隔地に住んでいればそれもまま なりません。 この様に遠距離に暮らしているのなら「直ぐには親の面倒を見られない」ことはしっかり認識して おくべきです。自分が行けないのなら自分に代わる人を確保する必要があります。家の近くに親 戚があれば良いのですが、そうでないのならこれはと思う近所のお宅に事情を説明して協力をお 願いしておくことです。 そのためにも、以前から帰省の度に土産品を持って行き頭を下げておくことが必要でしょう。まさ に「遠くの親戚よりも近くの他人」でしょうか? 私も富山・大分へ帰省する際は何年も前からこれを行って来ました。 ② 一人で悩まず相談機関を活用すること。 いよいよ介護が始まるとどうしたら良いのか迷ってしまう局面が多くなります。 親との電話の中で所謂「ボケ」症状が感じられたとしても、それが単なる加齢に伴う単なる「物忘れ」 なのかあるいは「痴呆」症状なのか素人では見極めが難しいものです。 こんな時は一人で悩まず、専門の相談機関を利用すべきです。 代表的なところでは、各都道府県にある「高齢者総合相談センター」でしょうか? 最寄のセンターにはプッシュホン回線で「#8080」を押せば通じますが、親の暮らす都道府県の センターを利用する方がその地域の状況が分かって便利です。その他、internetを利用して地域の 市役所等のHPを調べることで沢山の情報を得る事が出来ます。 ③ ホームヘルプサービスの利用 親の老齢化に伴う体力低下により、これまで当り前の様にこなしてきた家事が出来なくなってきま す。離れて暮らす子供にとって心配なことですが、そんな時にはホームヘルプサービスの利用を 考慮したいものです。 ホームヘルプサービスを受ける際には、先ず「介護保険」を申請します。保険料を支払うのですか ら利用しない手はありません。 もし、介護保険の対象とならない時や介護保険枠以上のサービスを受けたい場合は自己負担にな りますが民間のサービスを利用する方法もあります。 親が居住する地域の在宅介護支援センターに問い合わせるとどんなサービスが受けられるかおお よそのことが分ります。 介護保険には含まれませんが、多くの自治体で昼食や夕食の配達サービスを実施していますの で考慮すればと思います。 しかし、私の母親の場合、ホームヘルプサービスを勧めてもなかなか納得してくれませんでした。 その理由は、やはり他人に家に出入りして欲しくないというものでした。しかし、私達が日常の面倒 を看ることが出来ない以上、プロにお願いするしかないので説得するしかありませんでしたが、こ んな時は、日頃お世話になっている主治医の先生に必要性を説いてもらうことも良いのではと思 います。 ④ 兄弟姉妹の協力態勢 現在の民法では、兄弟姉妹の立場は皆平等です。長子相続制が存在した昔ならいざ知らず、親の 介護の責任も長男に限定されるものではありません。従って、兄弟姉妹は等しく親の介護に同様の 責任があることになります。 しかしながら、現実的には親が田舎に暮らしているほど兄弟姉妹が皆、都会に出てしまっているケ ースが多いと思います。しかし、皆が別々に暮らしていたしても、団結することで遠距離介護はスム ーズになります。 勿論、兄弟姉妹それぞれの状況が異なるため完全に平等な介護ローテーションは組めないけれど、 「出来る者が出来ることを行う」ことを基本に労力の提供が出来ない者は介護する者の交通費やホ ームヘルパーの費用を負担することで参加出来るのです。 この際に注意すべきポイントは… イ. 代理人として妻を表に出さない。親の面倒は実子が看ることを基本に旦那も介護に参加するべき。 ロ. 他の兄弟の看護にケチをつけない。誰にも得て不得手はあるもので、一生懸命にやっている限り は「ありがとう」の一言を忘れずに。 ハ. 出来れば介護をコントロールする役目を決める。ばらばらの介護は不効率になる。(長男・長女に 拘らず、一番近くに住む兄弟姉妹でも可) 次回に続く |
2000年9月23日UP
遠距離介護について考える
その2
| 1. 親が元気な内にすべきこと ① 将来介護を受ける場所を親と話し合っておく。 親の介護の方法をUターン、呼び寄せ、遠距離介護のどれを選択するにしろ子供が勝手に決められ るものではありません。親が倒れるのは突然です。倒れてしまっからでは子供は介護方法の選択に 戸惑うことになります。親が元気なうちに親の意思を確認しておくことが大切です。 一般的に親は子供がUターンし故郷に戻ってくることを最も望んでいると考えられます。その希望に子 供が沿えない事情があるのであれば、子供の希望もあらじめ親に伝えてお互いの意思の擦り合せを しておくことが必要です。 「親は将来どこで介護を受けたいか?」(高齢者の健康に関する意識調査98年総務庁) 自宅で介護:47.8% 病院等の医療施設:19.4% 福祉施設:9.5% わからない:8.4% 子供の家:6.6% 老人保健施設:6.2% 民間有料老人ホーム:1.6% 親族の家:0.4% その他0.1% ② マメに連絡する事で親の様子を察知する。 老親にとって「便りがないのは無事の証拠」というのは誤り、一般に親は子供に負担や心配をかけま いと具合が良くない事を隠したりする傾向があります。 頻繁に電話で話す事でいつもと違う声の様子から親の異変を察知することが出来たりします。配偶 者の母親も私に遠慮があるせいかなかなか病気のことは言わない傾向がありましたが、現在毎週 日曜日にお互い電話を掛け合うことにしています。また、電話機にも緊急連絡機能を持ったものが ありますので早目に交換することも良いことですし、一般に老人は聴力が低下する傾向があり、元 気な内にFAX電話にしたり難聴用の電話にしておくことも考慮しましょう。 (これらの場合行政側で無償で設置してくれたり、費用の援助がある可能性がありますので確認しま しょう。) 尚、これらの処置はなるべく早目に対応しておくことをお勧めします。何故ならば、年齢を重ねるにつ れ新しい機械の操作を覚えるのが困難になるからです。 いずれにしても連絡を密にしておくことは、親の介護状態への進行の予防になります。 ③ もしもの時役に立つ情報を収集しておく 親の介護は多くの場合突然必要になります。突然の出来事に対して遠く離れた土地でテキパキ行 動するためには日頃の情報収集が大切です。 私の場合internetを利用して富山市役所のHPから介護・福祉関係の情報を入手していたことが、実 家の母親の介護問題に大変役に立ちました。 ④ 親と話し合っておきたい「お金のこと」 親の介護をするにあたってある程度は親の資産状況や収入を掴んでおくことが必要です。高齢にな って、住宅ローンや教育費の支払から開放されていたとしても毎月それなりの支出が生じます。一般 的に親の世代の方が子供の世代より資産は多いと言われていますが、これからの医療費や介護資 金を考えると親は出来るだけ貯蓄には手をつけたくないでしょう。また、既に定年を迎えているため、 定収入は年金のみというケースも多いと思われます。 その時が来た時慌てなくてもいい様に親にさりげなく確認しておくべきでしょう。 年金については、総務庁統計局の「家計調査年報」等の数値を参考にして推定することも可能です。 1998年版の数値は以下の通りです。 [老齢年金の平均年金月額] 国民年金のみ加入:4.7万円 国民年金+厚生年金に加入:17.2万円 国民年金+共済組合に加入:22.3万円 ⑤ 夫婦で親の介護のことを話し合っておく 親の介護の問題は夫側の親の場合当然嫁の負担になることが多く、また嫁姑の確執があったりす ると余計に夫から切り出しにくいものですし、逆に嫁の立場からも言出しにくいものですが、実際、親 に介護が必要な状態になってからもめるケースが多いです。もしも、嫁の方が夫の親と同居や介護 の意志が予めない場合、最悪介護離婚になる場合もあります。 一般に夫婦2人に対して親は4人います。しかし、その中でも大切に思う順位はあります。当然のこ とながら、一番大切なのは自分の実父母でしょう。 一昔前までは、女性が結婚するということは「婚家の嫁」になることだったのでしょうが、現代ではそ の考え方は薄れてきており、妻にとっても一番大切なのは夫の親の方ではなく自分の親なのです。 従って、親のことを話題に出す時は連れ合いの親のことにも気を使う様にすべきです。要はバラン ス感覚を持って対処する気持が必要になります。ただ、私は双方の親の介護はどちらもある程度健 康な状態であれば良いのですが、どちらかの具合が悪くなった時に介護する側の力の入れ方はア ンバランスなものになります。 私は、お互いの親の介護問題は、山登りと同じで弱った方に合わせるしかないのではと考えていま すが、この点についても事前に夫婦で納得し合うことが必要だと考えています。 我家のケースはお互い一人息子・娘なので逃げ様がありませんが、少子高齢化の現代では、夫婦 それぞれが、それぞれの親の介護を担当する覚悟をすべきでしょう。連れ合いはサポート役として 機能すべきです。 いずれにせよこの問題は短時間で結論が出る事ではありませんので事前の話し合いはしておくべ きでしょう。 次回へ続く |
2000年9月16日UP
遠距離介護について考える
| はじめに 老親と子供が離れて暮らすことは、今では珍しいことではありません。 進学・就職,や結婚する際に多くの子供は故郷を離れて行きます。その時は親はまだ若く子供 の独立を嬉しい気持で見送り、子供の方もこれからの人生に希望を持って出発したことでしょう。 その時はお互い何の心配もなかった様に思えたものでした。 ところが、それから20~30年も経過すると情勢は大きく変化して来ます。 すなわち、あれほど元気であった親の老化は進行してきますし、それに対して子供は既に結婚し て、親が2人から4人に増えています。 親の老化がさらに進行し、夫婦それぞれの実家から、「具合が悪い」「入院した」といった連絡を 受けるようになると今更ながら、故郷と自分達が暮らす土地との距離を実感するわけです。 かくいう私も全く上記と同じプロセスを経て現在に至っています。 私は、18歳の時に大学進学のため郷里の富山を離れ上京し、大学卒業後も故郷へ戻ることなく こちらで就職し結婚をしました。配偶者も同様に故郷大分を進学就職のため離れていましたので この時点で遠距離介護の前提条件は揃っていたことになります。上記よりも条件がきついのは、 私は実家を養子に出されたため私の両親が4人と配偶者の両親2人で計6人であったことと配偶 者が一人娘であり、介護責任を他の兄弟に転嫁することが出来ない状況にありました。 会社に就職して5年目に私の実の父親が70歳で心臓発作のため急死しましたが、私の養子先の 両親もこのころは健在でしたので特段の負担は感じませんでした。 しかし、昭和が平成に変った頃から親の介護問題に直面することになりました。 最初に養子先の母親が脳梗塞で倒れ3年間の闘病生活の末、平成2年9月5日に享年80歳で亡 くなり、翌年9月1日、母親の介護疲れのせいか養子先の父親が亡くなりました。更には、その翌 年の平成4年8月20日に配偶者の父親が食道癌のため他界しました。 何と平成2~4年の3年間に毎年葬式を出すことになってしまいましたがその間の介護の苦労は 筆舌につくし難いものがありました。 そして、今年の4月から介護保険制度が始まりましたが、現在は、要介護2の認定を受けた私の 実母と要介護1の認定を受けた配偶者の母親が富山と大分に存在しています。 遠く離れた親が老いて行くのを子供としては放置しておくわけには行きません。そこで考えられる 方法は二つです。自分達が故郷にUターンするか。あるいは親を自分達のところへ呼び寄せる かでしょう。 しかし、これらの二つの方法はなかなか上手くは行きません。Uターンだと一般的には現在の仕 事を辞め子供を転校させることになります。更に夫の実家にUターンするか妻の実家にUターン するのかは大きな問題となります。逆に親を呼び寄せる場合には、長年住み慣れた土地から見 知らぬ土地へ移る事への親の抵抗、実家の土地・建物等の処理、そして、例え親子とはいえ何 十年も別居していた者同士が、同じ屋根の下で一緒に暮らすことは難しい問題が存在しています。 この様に考えると結局は現状のまま、親子は別の場所で暮らし続けるという結論に達するケース が多いのではないでしょうか? 我家も紆余曲折の末、同じ結論になってしまいました。遠距離介護とはまさにこの離れて暮らす 親を子供が遠隔地からケアして行く事です。 遠距離介護にはそれなりの努力が必要になります。お互いの家が遠い程同居の介護より、体力 的、時間的、経済的に負担が重くなるのです。 遠距離介護には、飛行機や列車を利用して度々自宅と実家を往復することになりますが、当然そ の肉体的負担は大変なものになります。 私の場合、養子先の父親の容態が悪くなり始めた頃から、毎週金曜日に東京を発ち日曜日の夜 にこちらへ戻る生活が長く続きました。 当然、精神的な負担も重くなりますが、私の場合は先の見えない介護に対する不安もありまし たが、実家が地方であるため「親の世話は子供がするもの」という概念があり近所や親戚から 「一緒に暮らさないのは親不孝」と指摘されたりすることから受ける精神的負担の方が応えまし た。 また、当然のことですが、遠距離介護は同居の介護以上にお金がかかります。実家との距離が 遠ければ遠いほど交通費・電話等の通信費は嵩んできます。 この遠距離介護についてこれまでの経験を通していろいろな失敗から学んだノウハウをお知らせ することで、現在そして将来に必ず親の介護に直面するであろう皆さんのお役に立つことが出来 れば幸いです。 何か身の上話の様になりましたが、親の介護の問題はプライベートな問題である ため皆さんお話することに躊躇いがあるでしょう。しかしながら、それでは介護のノ ウハウの伝承が出来ません。少子高齢化が進み老人を社会全体で見なければな らなくなった現在、親の介護の問題を皆で共有化して行く必要があると私は考えて います。それでは、次回をお楽しみに・・・ |
