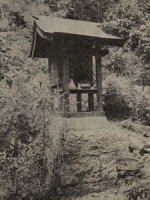鎮守様
鎮守様は、各家の守り神として祭祀され同族的意識、結合の象徴となっている。佐々木彦一郎氏は、その著『村の人文地理』の中で次ぎのように書いている。
「居住地の中心に本家に当たる者が長百姓として住み、その中心に分家が同姓を名乗って本家の土地を耕作している。また精神的生活の中心として、必ず本家の屋敷内に一族の神社が祀られてあるのが常である。同族の団結も、家の神社の精神的生活の中心に統一せられて社会から重んぜられた位置にあったが、家の神社が荒れ果てて、廃園の雑草の裡に埋もれているように、分家も本家を中心とせず、自らの家を中心として、分離して行くのもやむを得ない時代に変わってきた・・・」と書いている。
私たちの村にある鎮守さまと祭日を列挙すると次のようになる。
| 地区 |
祭神 |
祭日 |
家名 |
軒数 |
| 山田(坪井) |
御崎様 |
旧四月三日 |
中山家の一部 |
四軒 |
| (坪井) |
田槌様 |
旧四月四日、旧九月四日 |
俣野及び坪井家 |
十三軒 |
| (坪井) |
若宮大明神 |
旧四月三日、旧九月三日 |
吉田家 |
八軒 |
| (本村) |
摩利支天 |
五月十七日、十月十七日 |
岡 家 |
十一軒 |
| (本村) |
摩利支天 |
五月十七日、十月十七日 |
笠石家 |
十五軒 |
| (高尾) |
春日大明神
河羅大明神 |
旧四月八日、旧八月十八日 |
河口家 |
十五軒 |
| (高尾) |
天神様 |
旧四月二十四日、旧八月二十四日 |
永瀬家 |
十五軒 |
| 妹尾崎 |
稲荷様 |
旧三月二十五日、旧九月二十五日 |
蜂谷家 |
二十軒 |
| |
摩利支天 |
五月二十四日、九月二十四日 |
料治家 |
二十軒 |
| |
大蔵様 |
旧四月四日、旧十月十九日 |
久山家 |
三十三件 |
| 古新田 |
当家初代の人 |
旧三月十五日、旧八月十五日 |
渡辺家 |
二十五件 |
| 大福 |
八幡様 |
|
陶山氏 |
現在 在村せず |
 |
|
 |
| 第81写真 御崎さま 中山家 |
|
第82写真 田槌様 俣野家・坪井家 |
 |
 |
| 第83写真 若宮大明神 吉田家 |
第84写真 摩利支天 |
村内の人で、他の町村へ行って鎮守様を祀る場合がある。それは、その人の出身地に鎮守様があるからである。
守り神と奉祀家族は、かつては強い絆で結ばれていたが、現在はその結びつきも弱くなっている。それは、文化や教育、時代のうつりかわり、人間関係が複雑になってきたことなどの原因によるものと考えられる。
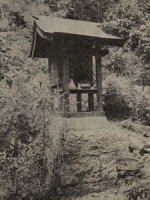 |
|
 |
| 第85写真 摩利支天 笠石家 |
|
第86写真 春日大明神・河羅大明神 河口家 |
 |
 |
| 第87写真 天神様 永瀬家 |
第88写真 柿ノ木稲荷 蜂谷家 |
 |
 |
| 第89写真 摩利支天 料治家 |
第90写真 大蔵さま 久山家 |
ところで、苗字は、その村落にながく住みついている人々と密接にむすびついている。地区と苗字は関係が深く、一つの地域性をもっている。
「一部落に同姓の多い理由の一つとして、明治の初年にそろって同一家名をつけたという事情もあり、同姓が人口の増加につれて、むやみと数をました。・・・」(豊田武著『苗字の歴史』)
このことは、当初のことからみれば、内容の構成が変わってきたことを意味する。
転入者が多くなるにつれて、いろんな苗字が見られるようになるが、そのことは、集落の地域性をうすくすることになるが、反面それは、新しい郷土を作り出す発展への過程であるともいえるだろう。
 |
| 第91写真 お先祖様 渡辺家 |
大年様
山田の大年部落にある。坪井に行く登り道の傍に鎮座する。祭日は、十月二十五日、信徒は三十六軒。
祇園様
妹尾崎にある。祭日は、旧暦十四日、向かって左側が祇園様、中央が荒神さま、右が地神さまで、別に木山神社を祀る。祭日には、地域をあげて賑わう。
 |
|
 |
| 第92写真 大年さま |
|
第93写真 祇園さま |