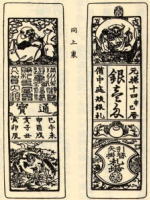
助郷村山田
五街道の幹線に対して、数々の支線がありこれを、脇街道と称した。脇街道の宿駅でも旅人や貨物の継立や逓伝(郵便物・貨物を、つぎつぎと引きついで目的地に届けること)を行ったが、幹線にくらべると小規模であった。中国路(山陽道)はこの脇街道であった。中国路は大阪より下関に至り、さらに大里から小倉までの行路であり、五十二宿であった。このうち、備前・備中の国には次ぎの八駅があった。三ツ石・片上・藤井・岡山・板倉・川辺・矢掛・七日市。
宿というのは、人馬をいつも用意して運輸・通信・宿泊の営業を行うところで、旅籠屋・茶屋・飛脚問屋などが軒を連ねていた。
人馬の利用はすべて次の宿までで、その先は乗り継いでいくのが原則であった。
宿駅で常備している人馬は屋敷持ちに対し、その間口に応じて割り当てられてた。その宿で準備する人馬の数は決められていて、決められた数は毎日提供する義務がある。
宿人馬御定之事
1.東海道 百匹 百人
1.中仙道 五十匹 五十人
1.日光 奥州道中 二十五匹 二十五人
山陽道の場合も二十五匹、二十五人という御定人馬であって、板倉宿駅でもこれだけを常備しなければならなかった。
この人馬を利用できるのは、まず幕府の公用旅行者が優先する。
幕府関係者の次に人馬を利用するのは、参勤交代の大名などである。大名は、石高によって一日に使用できる人馬の数は決められていて、その数までは御定賃銭を支払って使用するが、それを越えると宿の問屋と話し合いできめた相対賃銭を払う。御定賃銭はふつうの賃銭より安いので人馬を集めにくいからである。相対賃銭は、御定賃銭より割増料金になっている。
板倉宿などの場合は、たいてい三割増し料金になっている。
第三位の利用者は一般旅行者である。これらも、本来は御定賃銭で利用できるはずなのだが、武士はともかくとして、町人、農民などは相対できめるのである。幕府公用旅行者に安く利用された分を町人・百姓でうめあわせしようとしたのかもしれない。
このように常備されている宿駅の人馬で不足のときには、付近から応援の人馬がかり出されたが、一定の村に決められていた。助人馬を出す村を助郷といった。これは一種の課役にあたり、村高百石について人足二人、馬二匹という決まりで調達された。
山田村、山田入作村は板倉宿の定助郷になっていた。天保九年の庭瀬領賀陽郡村鑑抄(板倉村庄屋東方豊太郎筆録)の中に次のような記録がある。
1.板倉宿場定助郷
賀陽郡宮内村 川入村 中田村 平野村 延友村 冲分 東花尻村 板倉村 立田村
都窪郡矢部村
築山茂左衛門様御代官所都宇郡山田村 入作
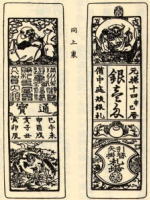 |
| 庭瀬藩(銀札四種ノ内)表、裏 |
花房大膳様御知行所都宇郡加茂村 新庄上村
賀陽郡原古才村 中島村 和井元村
榊原左兵衛様御知行所都宇郡津寺村
築山茂左衛門御代官所都宇郡新庄下村
右宿より登り備前岡山宿へ道法二里十二町
人足一人之賃銭 四十七文 三割増 十四文 〆 六十一文
本馬一匹之賃銭 九十四文 三割増 二十八文 〆百二十二文
軽尻一匹之賃銭 七十五文 三割増 二十三文 〆 九十八文
同下り川辺宿へ道法三里
人足一人之賃銭 五十七文 三割増 十七文 〆 七十四文
本馬一匹之賃銭 百十九文 三割増 三十五文 〆百五十四文
軽尻一匹之賃銭 九十四文 三割増 二十八文 〆百二十二文
但し御定人足二十五人馬二十五匹之分
1.庭瀬町御通行人馬継立
中田村 川入村 宮内村 板倉村 立田村 矢部村 西花尻村 東花尻村 冲分 平野村 延友村 山田村 入作〆十 三か村
庭瀬より岡山宿迄道法二里人馬賃銭
人足一人之賃銭 四十文 三割増 十二文 〆 五十二文
本馬一匹之賃銭 八十文 三割増 二十四文 〆 百四文
軽尻一匹之賃銭 五十三文 三割増 十六文 〆 六十九文
同所より倉敷へ道法二里八丁人馬賃銭
人足一人之賃銭 四十六文 三割増 十四文 〆 六十文
本馬一匹之賃銭 九十文 三割増 二十七文 〆 百十七文
軽尻一匹之賃銭 六十文 三割増 十八文 〆 七十八文
同所より板倉宿迄道法一里人馬賃銭
人足一人之賃銭 二十四文 三割増 七文 〆 三十一文
本馬一匹之賃銭 四十八文 三割増 十四文 〆 六十二文
軽尻一匹之賃銭 三十六文 三割増 十一文 〆 四十七文
定助郷というのは、宿駅から一〜二里を隔てた近隣の村々に助人馬を課役したものである。この定助郷の人馬の不足をさらに補うために五〜六里の遠方の諸村から加助郷を調達していた。
助郷人足や馬子には御定め賃銭または、それに相当する賃銭が支払われるのが原則であったが、その額は一般に利用される賃銭より安いものであった。しかも、それは宿駅と宿駅の間の賃銭に限られるので、助郷村山田から板倉までの往復についての給与はない。
板倉まで人足として出かけても、仕事がなく「不用楊返し」として村へ帰る場合には、まったくのむだ足になってしまう。
人馬の継立ては、助郷人馬を使用する時、朝に当てることが多かった。宿場の問屋から助郷当状を持った人足が各村に対し、前日までに必要人数と集合時間刻を告げ知らせてまわる。
村では、それに応じて村人に割り当てをし、宰領をつけて夜中までに、時には子の刻(夜中十一時〜一時)とか、丑の刻 (一時〜三時)ごろまでに宿場へ到着させることもあった。
問屋では、人数を調べて必要数より多ければ、その分は帰らせて、定員内の者には木札を渡し、あとでこれと引き換えに、宰領に対して賃金を支払うしくみになっていた。
助郷村で出す人馬は、村人の持ち高に応じて平等には出しにくいので、事後に調整していた。助郷人足、馬子として出る者は、十五歳から六十歳までの強健な男子ということになっていた。
御定賃金をもらっても、その額は一般の労働者より安かったので、出勤した人足や馬子には、村の方でその不足分を補給している。その補給金は、村入用として村人に賦課されたが、その額は相当なものになって、村入用の大部分を占めるようになった。そのために村の財政支出が膨張し、ほとんど貢租に匹敵するようになった。
助郷の負担が増大するにつれて、宿の人馬の触れ当て方について、問屋と助郷がわとの利害が対立し、争いがくり返され、所によっては一揆の原因ともなっている。
庭瀬は岡山瓦町から鴨方方面へ通じる庭瀬往来の馬継所であった。馬継所というのは、宿駅の小規模なものであり、宿駅同様に人馬継立の機能を果たすものであった。