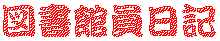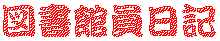
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 12月28日(木)
御用納め。書架の大掃除。本を全部出して棚を拭く。二階のカウンター
の位置をずらす。電算関係のケーブルなどがカウンターの裏を這っている
ので、大丈夫なのかな、と思いつつも、大人数でテキトーになんとかした
のであった。書架の掃除は全部は終わらなかった。沢山の本棚があるのだ
なあ、としみじみ思った私であった。あとは来年。
- 12月27日(水)
朝、一人職員が休むとの連絡があった。「ではローテーションを変えな
ければいけないね」と暢気に答えた私であったが、今日はおたのしみ会が
あったりなんだりで人のやりくりが大変。なんとかむりやりローテーショ
ンを組んだ。
さすがに今年最後の開館日。いつもは三人でなんとかなっている一階の
受付に一時的に六人の職員が必要であったりした。たまたま昼休でなくて
良かったが。利用者用端末に列ができたりもした。「こちらで調べますの
でどうぞ」とカウンターに来てもらうと、カウンターの二台の端末もすで
にふさがっていたり。一年の終わりらしい日であった。
- 12月26日(火)
朝からばたばた。一日ばたばたであった。中高生だけでなく、大人の人
の調べものもなかなか沢山あった。
- 12月24日(日)
冬休の日曜日。貸出は5000冊を越えた。宿題の調べものも多い。先週
から出ていたある中学の宿題は邦楽について。あまり本がない分野なので、
貸し出せる本はほとんど借りられている。百科辞典などを案内。明後日、
明々後日もまだ中学生が来るのだろうなあ、って、来るに決まっているの
だが。
- 12月23日(土)
さすがに冬休。利用者がいっぱい。登録者も多い。ばたばたしていた一
日であった。
- 12月22日(金)
館内整理日。通年開館の話はおさまったのだが、延長開館をすることに
なった。今よりも一時間長く、七時まで開ける。夏休みは九時まで。人件
費は少し。ま、なんとかするよりほかあるまい。
読書感想文コンクールの文集の校正を全職員でする。なかなか大変。
- 12月19日(火)
朝からレファレンスがいっぱい。夕方に厳しいレファレンス。イギリス
の詩人の書いた詩について数件の質問をFAXで送ってきた。明日、私は休
みなので、今日中に回答を送っておかねば、と終業時近くにばたばたとし
たのであった。
とある出版社の見計らいがやってきた。ほとんど購入しているものばか
り。資料費の予算が沢山あるのは幸せなことであるな、と改めて思う。
- 12月17日(日)
ばたばたの一日であった。風邪で倒れた職員がいたりしてローテーショ
ンがぎりぎり。昼休時間に持病が痛みだした職員もいたりしたが、なんと
か切り抜ける。師走であるなあ、としみじみ思う。
このところずっとレファレンス多し。
- 12月15日(金)
朝、急に市報に新着案内を載せたいので原稿が欲しいと広報から連絡が
ある。大急ぎで原稿を書く。今日の予定が少し狂ったが、なんとか新着図
書の発注も終えた。ばたばたした一日であった。
三浦按針のことを調べにきた利用者がいた。不慣れな職員が対応しよう
としていたので、「ウィリアム・アダムスでも探さないといけないよ」と
指示。手が空いたので臨時職員と交代。その人は漂流した人全般に渡って
の調べものをしている人とわかる。ある程度知識がないと対応ができない
レファレンスであった。しかしその利用者、ひどい延滞をしていたため、
何も借りられずに帰っていったのであった。
- 12月14日(木)
朝、予算査定がある。財政状況が厳しいので、あれこれ切られるであろうか
と予想していたのだが、順調に終わる。
午後、ある作家の若い頃の盗作疑惑に関するレファレンス。関連資料が我が
館にありそうでなさそうでスリリングであったが、証拠不十分に終わった。残
念。
- 12月13日(水)
朝ポストは1000冊。たいしたことはないといえばたいしたことはない分
量ではあるが、小さな図書館の一日分の貸出冊数くらいはあるわけで、それ
を朝のうちに本棚にしまわねばならないのであった。図書館員の仕事の半分
以上は肉体労働であるとの認識を世の中のどれくらいの人がわかっているで
あろうか。
30日以上延滞をしていたおじさんが同じ本を続けて借りたいと言う。「勘
弁してくださいよ」と思わず口をついて出る。継続貸出は一度だけ。さらに
もう一度借りたいときは間をあけてください、としている我が館。14日の貸
出期間なのにすでに三倍以上借りているのにどの口がそういうことを言う、と
口を捻り上げてやりたいような気分になる私であった。そんなに長く抱えて
いたければ買うか、コピーをするかすれば良いと思うぞ。
閉架で行方不明になっている本がこの頃多い。不慣れな臨時職員がしまうこ
とと関係しているのかもしれないなあ。細かなところにプロっぽい仕事が沢山
あるのが図書館。しかし、そんなことを言っても図書館に興味のない人たちに
はなんの意味もないことであるよなあ。司書の正職員は来年も増えない。
帰りがけに利用者が多く、ばたばたする。
- 12月10日(日)
あちこちの棚がいっぱいになってきたなあ、と思っていたのだが、今日が
終わったら、ある程度空いた。利用者がなかなか沢山来たのであった。
このところ、あまり面白い調べものがない。たまには突拍子もない調べも
のがあるとうれしいのだが。
- 12月9日(土)
第二土曜日だというのに中高生は少なかった。寒いからであろうか。
発注業務をする。
レファレンス多し。
- 12月8日(金)
真珠湾攻撃は知らないけれども、ジョン・レノンが殺されたことはよく
覚えている。あれから20年が経ったのだなあ。世の中はどうなってゆくの
であろうか。
利用者は多くはなかった。平穏な日。
- 12月6日(水)
レファレンスや本の有無についての質問は相変わらず多い。
見計らいをした。
近所の大学生、来館。しかし葉書か電話で事前に質問内容等を連絡して
きはしないのであろうか。何を訊くのかもまとめてきていない。三十人ほ
どが受けている講義で十グループにわかれて調べているのだそうな。なん
となく中学生の調べ学習と水準が変わらないような気がする。もしかする
と中学生の方がするどかったりすることもあるかもしれない、などとも思
う。
- 12月5日(火)
朝、ブックポストにはそれほど沢山の本は返ってきていなかったのだが、
ガイドブックがなぜか多く、棚に入らない。どうしてそんなに旅行に行く
のであろうか、行くくらいならば帰ってこなければ良いのに、などと理不
尽な怒りが沸くが、本当に我が儘で理不尽であることが自分でもわかり、
しかたなく閉架にしまったりなんだりする。
「その本ならば返しました」と言い張っていた本を、「友達が勝手に持
っていたから」と窓口に返しにきた年輩の男の人。借りてから二ヶ月ほど
になるのだが、「ごめんなさい」の一言もない。数人の職員が本棚に本当
にないかどうかを確かめ、トラブルの扱いとし、本はすでに電算上、異動
処理しているのであった。「良いお友達をお持ちですね」と言いそうにな
ったが口からでるまえにとまった。
- 12月2日(土)
テスト期間が終わったためか、二階の学習用の部屋はがらんとしていた。
レファレンス多し。ばたばたと一日が過ぎてゆく。
ガイドブックの棚がいっぱいである。どれを閉架にしまおうか、と悩む。
近所の大学で、市内の公共施設について調べてきなさい、と宿題が出た
らしく、突然カウンターで大学生が質問をはじめた。事務室に入ってもら
い、やりとりをした。
- 12月1日(金)
本棚がいっぱいになってきている。発行されている本が多く、貸し出されて
いる冊数が多くないとそういうことになる。普段、あまり整理をしていない参
考資料コーナーを見るとかなりぐちゃぐちゃ。揃えたのであった。
- 11月30日(木)
「としょかんだより」をつくる。なんとかできあがる。明日から12月だ。時
の流れは早い。
- 11月28日(火)
利用者はいつもの火曜日ほどではなかった。しかし、質問が増えている。良い
ことなのではあるが、大変でもある。「トールペインティングの本はありますか」
「貸出中のものがほとんどです」「赤ちゃんの名前のつけ方の本はどこにありま
すか」(またきた)「少し古い本しかありませんので、閉架から出してきます」
「この人の名前の読み方はわかりますか。どこまでが名字かもわからないのです
が」「ううむ、どういった分野の人でしょうか。昭和人名辞典のここにあるから、
名字はこうですね。名前はどうかなあ。おお、この本にありました」などとあれ
これのうちに一日が終わってゆく。
市報の新刊案内と「としょかんだより」の締切が近いことに気づく。慌てて、
原稿を書きはじめるのであった。
- 11月26日(日)
6月から開放してきた学習用の部屋がいよいよ満席になってきた。夏休みを無
事乗り切って、「これは塾などに行く子供が多いからかもしれない」と思ってい
たのだが、甘かった。1時半に見回りに行った際、机がすべて埋まっていた。こ
れはまずい、と思っていると、ぞくぞくと閲覧席に座るテスト勉強のみを目的と
する中高生。二人、四人、二人、四人、二人。三十分で十四人の学生に、「ここ
は図書館の資料を使うところなので、家から持ってきたものだけで勉強するのは
よしてね」と説明。学習用の部屋の机は三人掛けだから、一人しか座っていない
人の横を使ったり、工夫をしてください、とも言う。割とすんなり空けてくれた。
学生の数が増えてくると、なかなか空けてくれなくなるのだよなあ、と考えると
私の頭がいらいらしてきた。閉架の資料の利用、参考資料の利用が増えている現
在、朝からわさわさと多くの学生がくるようになったら、と想像するとたまらな
い。今日は幸い十四人来た後は来なかった。今後どうなることやら。
利用者多し。今日もまた赤ちゃんの名前のつけ方の本はないかと訊かれる。私
の勤める町は出産ラッシュなのであろうか。
- 11月25日(土)
不幸のあった職員がいるためもあって手薄なところへ利用者多し。
とてつもない宿題を出された高校生がいた。いくつものテーマが書かれたその
プリントを前にも見たことがあるので、うわっとのけぞった。「この先生はなか
なか厳しいようですよね。大学生でも難しいような問題を出すのだからなあ」と
言うと高校生は苦笑していた。学習指導要領の改訂の際、どこがどのように変わ
ったのか、というのが問題。私の勤める図書館には89年改訂のものと、現行法規
総覧があるだけなので、あとは教育関連の辞典にまとめられているくらいのこと
がらしかわからない。89年の改訂を中心に書いてみてはどうだろうか、と勧めて
みる。
閉架の図書の利用が増えている。閉架があることが知られてきたのであろう。
足が鍛えられる日々である。
- 11月24日(金)
館内整理日。緑陰閲覧席を片づける。職員総出で、なかなかの大仕事。来年は
止そう、と話し合う。確かに外で本を読んだり勉強をしたりするのは、季候が良
ければ利用者にとって快適であろうけれど、葦簀の準備が大変であったり、雨降
りの前、あとの机、椅子の片づけ、掃除などの仕事はかなりの分量なのであった。
読書感想画コンクール展示も残すところあと僅か。もうじき読書感想画関連の
仕事がすべて片づく。
- 11月23日(木)
ボリショイサーカスの謎、判明。やはりキグレサーカスであった。
タレントの書いた本をリクエストした利用者に、基本的にはタレントが書いた
本を購入しない旨を説明。よほど話題になるか、ベストセラーとなるか、リクエ
ストが沢山入るか、そのタレントがエッセイストとして認められている場合は別
である、と。するとその利用者は、「ならばひとまずリクエストしておいて図書
館が買うかどうかの連絡を待てば良いのですね」と言う。「そうではなく、ほと
んどは買わないのだから、リクエストをご遠慮願いたい」と言うと怪訝そうな顔
をしていた。しかし、タレント本を買ったり読んだりするのって少しうしろめた
くないのかな。世の中が変わってきたのであろうなあ。マンガや軽そうなベスト
セラー、タレントの本などは少しこそこそと読んでいた記憶があるのだけれども。
それだけでなく、筒井康隆さんの本だってこそこそと読んでいたなあ。私がこそ
こそとしていただけなのであろうか。ううむ。少なくともタレントの本を、本屋
で尋ねたりはしなかったけれども、図書館に堂々とリクエストをする時代になっ
たらしい。
市内の、しかし住んでいる地域とはかなり離れた町の江戸時代の新田の歴史に
ついて先生が調べてきなさいと小学四年生が言われてやってきた。到底小学四年
生にわかりそうもない資料しかないため、どうしようか、と思っていたところ、
お母さんも一緒についてきていることが判明。しかし旧字旧かなの本や、大人が
見たって簡単にはわからないような本しかない。「先生は何で調べたらわかると
思ったのだろうか」と、お母さんと私は首をかしげていたのであった。住んでい
る地域ならばお祖父さんやお祖母さんに聞けばある程度わかるであろうけれども。
無茶な宿題を出さないでもらいたい、と思うのであった。
- 11月22日(水)
じっくりと新刊書の見計らいをする。じっくりと見れば見るほど、買いたくな
い本が増えている気がする。
勤務している町に二十数年前、サーカスが来たときのことが職員の間で話題と
なる。来たのはキグレサーカスだと私は記憶しているのだが、ボリショイサーカ
スだった、と言い切る職員が三名。尤も当時四、五歳だったのだから記憶の混乱
もしかたあるまい。昼休にそのことを調べようとしたのだが、資料が見つからな
い。いまもって三名はボリショイサーカスを見たと言い張っているのであった。
- 11月21日(火)
火曜日の朝はブックポストの本をコンピュータで返却処理し、本棚に返すとこ
ろからはじまる。って、毎朝そうなのだが。ガイドブックの本棚がいっぱい。は
あ。と、ためいきをつく。同じ本が毎年出版されていて、しかし、去年の本、一
昨年の本は汚れていたり、よく貸し出されていたり、盗まれていたりするので、
毎年買っているわけで、スペースが限られていれば、借りてゆく人の数が倍ほど
にならねば、そこはいっぱいになる。同じ本のうち、古いのを閉架へしまう、あ
るいは廃棄することにする。
新刊図書の見計らいをする。
視聴覚資料の予約の連絡をする。以前よりかなり減っているが、それでも日に
三十軒ほどは電話をかける。
- 11月19日(日)
今日も朝、人出が少なかったのでゆったりとした一日になるかも、と思ったが
そんなことはなかった。
東京ディズニーランドのガイドブックはありませんか、と昨日も今日も尋ねら
れた。開架にあることになっている本が何冊かあるのだが、ない。困ったことに
盗んでゆく人が多いのである。しかし、ガイドブックって図書館に必要なのだろ
うか、と時折思う。旅行に行くほどの生活に余裕のある人の為のガイドブックな
のである。毎週のように出版されているのである。そして図書館で買うと盗んで
ゆく人がかなりいたりするのである。コンピュータのアプリケーションソフトの
マニュアルの本についても同様な気持ちになる。あらゆる資料を利用者の求めに
応じて、が、ゆきすぎてはいないだろうか。私の勤務先は幸い資料費が近隣の館
よりだいぶ多いのでそうした要望に応えているわけだが、先日、コンピュータの
アプリケーションソフト関連資料をどうしようかと悩んでいると訪ねてきた館の
気持ちはよくわかるのである。安くなったとは言え、十万円くらいはするパソコ
ンを買うことのできる人が二千円前後の、頻繁に使うであろうマニュアルを買わ
ずに図書館で借り、コピーなどをして使う。なんとなく変なのではなかろうか。
旅行のガイドブックを借りていって、旅先に忘れてくる利用者も時折いたりする。
海外旅行に何十万かをつかうけれど、本に千数百円出すのは惜しいという人のた
めにも図書館はあるのだ、と心の底から納得をしている図書館員っているのかな。
私は腑に落ちないのだが。でも、今から急に「ガイドブックを今後購入いたしま
せん」というふうにはできないだろうな。
今月は市内で沢山の出産があるのか、子供の名づけ方の本が開架に一冊もなく
なっていた。二十冊くらいは出してあるのだが。「十年ほど前の本ならば、閉架
にありますが」と案内すると新しい本が良いです、とのことなので予約をしても
らう。すでに予約をしている人がいる。寒い一月二月あたりに励んだ方たちが多
かったのであろうな。良い名前をつけた子が良い世をつくってくれることを祈る。
- 11月18日(土)
朝方、利用者が少なかったので平穏な一日となるかな、と予想していたが、さ
にあらず。人だらけの午後であった。私の勤務先の利用者用端末は使い方がやや
こしいのと、処理が遅いのとでほとんど役立たずなのであるが、処理が早くたっ
て、それを調べることはできまい、という本を探す利用者のなんと多いことであ
ろうか。そうした人を手助けするのが図書館の大きな仕事なのだが、ないがしろ
にされているのではなかろうか。
- 11月17日(金)
利用者はそれほど多くないのだが、調べものの人が多い、という日がこの頃続
く。日本人の平均身長の推移を栄養摂取との関連で調べたいとのレファレンス。
なにかそのことについて書かれた本があったような気がするのだが、思い出せな
い。ひとまず、日本長期統計年鑑と日本統計年鑑で数字はわかるので、提供をし
た。
発注業務をしていると、出ても出なくてもいいよなあ、と思われる本の多さに
驚くときがある。そんなことを図書館員が考えてはいけないような気もするのだ
が、柳の下の泥鰌を狙ったようなタイトルの本や、類書がいっぱいある、分野と
しては人気があるからそこそこ売れるであろうとの読みで出したような本。売れ
ずに返本され、倉庫に長く置いておくわけにもいかず、処分される本の数は膨大
であろうなあ。ケナフを植えるより、本の出版点数を減らした方がよくはないか、
と思ったりする。
- 11月16日(木)
中学生の体験学習。二人の女子中学生が来たのだが、二人ともご近所。一人は
三十年前に死んだ私の祖母の昔の大家さんのお孫さんであった。なんとなくやり
にくかった。閉架書庫や和本がしまってある特別資料室を見せ、「将来、こうし
た資料を使うことがあるかもしれないから覚えておいてね」などと説明をする私。
図書館に本を受け入れるまでの仕事、受け入れてから書架に出すまでの仕事、出
したあとの仕事を短い時間なのでざっと話す。二人とも賢そうでやや抽象的な話
もわかってくれたようであった。将来は本に関わる仕事に就きたいとのこと。こ
うした子が沢山いれば日本の未来も暗くはないかな、と思う私であった。
明治末か大正に山窩について調べたある人の著作がないかとの問い合わせが遠
方より電話で数日前にあり、調べてみたがわからない。その人の著作はあったの
だが、山窩についてのものではない。大正期の雑誌にその人が山窩の調査をした
との記述があった由。調査をしたのであれば、本になってはいずとも、地方の新
聞か雑誌に記載された可能性は高いのだが、雑誌は現在残っているのかいないの
か、どの雑誌なのかの検討もつかないわけで、その旨を連絡する。
- 11月15日(水)
二日休館したので朝ブックポストがいっぱい。小さなブックポストに無理矢理
美術書の大きなのを突っ込む乱暴な人がいる。大きなブックポストがあることを
知らなかったのであろうか。美術書がかわいそうだ。今朝は1200冊以上返却され
ていた。
取次から返ってきた事故伝票を見ていたら、九月に出たばかりの小澤書店の本
のスリップに「廃業」と書かれていた。「嘘だろ」と思い、小澤書店の電話番号
にかけてみる。「お客様の都合により通話ができなくなっております」。正字舊
かなのうつくしい本を出す立派な出版社がなくなってしまったのだろうか。割と
最近、週刊文春で高島俊夫さんがこの出版社を褒めていたな、などと思い出す。
森銑三の「びいどろ障子」(なんとかわいらしい装丁の本なのだろうか)、「柴
田宵曲文集」、「小川国夫全集」、「大原富枝全集」、ディラン・トマスやギュ
ンター・グラスの詩集、最近では小沼丹の「福壽草」、青木玉の対談集「祖父の
こと母のこと」。本らしい本を出す大好きな出版社だったのだが、どうして。
利用者多し。大学生の宿題がかなりある。午後、小学生も沢山来た。
明日、中学生が体験学習に来るとのことなので、レジュメをつくる。ばたばた
した一日であった。
- 11月14日(火)
いつまでも暖かいせいか、どうも何もする気が起きず、ふと気がつくとこの日
記を三週間も書いていなかったことに気づく。10月24日の火曜には、「日本で
ゴミを燃やす際の国の方針について書かれた本はありますか。十年ほど前に見た
ことがあるのですが」と訊かれ、はて、と考え込んだのでしたが、これは法律の
ことだと思い当たる。保健所に問い合わせて該当の法を聞き、『現行法規総覧』
を探したのであった。
25日には難しい質問があった。「『フランダースの犬』の実話について書かれ
ている本を読みたい」と大人の女の人。「は?」と問い返す私。「『フランダー
スの犬』は本当にあった話を元にしているんですよね」「そうなのですか。それ
は知りませんでしたが、どこかに書かれていたのですか」「有名ですよ」「はあ」。
児童書に『フランダースの犬』に関連した町を旅した人の書いた本があったので
提供。実話ではないであろうことを文庫本の解説などを示して幾度か話してみた
が、私の話を信じてはもらえなさそうであった。
26日、読書感想画コンクールの式次第を印刷する寸前、上司が、小学校長の学
校名が違っていることを発見してくれた。危ないところであった。幾度か確認し
ても間違うのだから困る私である。
27日は館内整理日。読書感想画コンクールの表彰式の準備をした。去年までは
絵を額に入れ、ややこしい展示をしていたのだが、今年はパーテーションに直接
画鋲で絵を貼ることに決定。黒板のある部屋での表彰式なので、黒板の前にカー
テンを吊していたのだが、それも面倒なので省く。黒板があったっていいじゃな
いか、と私と館長の意見が一致。別に反対する人もいなかったので平和な解決。
28日、読書感想画の表彰式。「今年は戸田君が担当だから怖いから厭だ」と、
言う上司をなだめ、受賞者の名前を読みあげる係をしてもらう。幸い間違いがな
く、とどこおりなく表彰式が終わった。子供達がうれしそうでめでたい式である。
ここだけを見ていると甲斐のある仕事であったような気がするが、感想画を書か
されたことで本を嫌いになった子供は何人いただろうな、と陰気なことを考えて
みたりもする。
29日の日曜日は午前中はそれほど利用者がいなかったのに終わってみると貸出
冊数5375冊と大変な一日であった。午後からわけわかんなくなっていた。
11月に入ってからなにかあったっけかなあ。思い出せないので省略。思い出し
たらまた書きます。このところぼおっとしているのでぼちぼちと気持ちをひきし
めねば、と思うのであった。
- 10月22日(日)
調べ学習の子供多し。
貸出、返却ともに4000冊くらいでそれほどの混み方ではなかったのだが、慌
ただしい一日であった。
- 10月21日(土)
印の押し方のついている本を職員が見つけてきた。印矩を使わずフリーハンド
で押した方が良いとの考え方もあると書かれていて安心。
さすがに土曜日である。ばたばたの一日。
- 10月20日(金)
調べ学習の小学生、中学生がやってくる。どうやらこの「調べ学習」とやらは、
文部省の方針ではじまっているらしいのだが、その前に公共図書館の状況をなん
とかしてもらいたいと思うのは私だけであろうか。司書を増やし、児童サービス
を向上するように仕向けてもらわねば、大勢の児童生徒の調べものに対応できる
はずがない。机上だけでテキトーなことを考えて、あとはなんとかなるだろう、
といった感覚なのであろうなあ。その為にどことどこをどのようにしてゆかねば
なるまい、とは考えないのであろうか。国中を動かす人たちが頭が悪いんじゃど
うにもならないよなあ、と思う。中国の首相朱熔輝さんの話ぶりをテレビで観て
るとどこかの国の首相とは知的水準がかなり違うな、と感じたりするわけで、ま、
そんな国なのだよな。残念ながら。
読書感想画コンクールの表彰状に角印を押してなかったことに気づく。去年ま
では印矩というものを使って、かなり丁寧に押していたそうで、全部押すのに三
時間くらいかかったとのこと。私の場合、そのようなことをすると、かえって下
手くそに押してしまうであろう、と言うと、皆が同意する。私が不器用であるこ
とをこの頃では誰もが知っているのであった。そこで、フリーハンドで押すこと
にした。教育委員会まで出かけての作業。約一時間で終わる。手が痛くなったが、
なんとか無事に押せた。
- 10月19日(木)
昨日と同じような感じの日。混んではいないのだが、調べものやコピーが多い。
こういう日は頭を使うのでなかなか大変なのである。
卒論の資料を探しているという大学四年生が来る。テーマは決まっていると言
う。探しているのは郷土資料ではない。中規模の公共図書館にあるような概説的
な資料よりも学術雑誌の論文を大学で探してはいかがか、と勧めたが、概説的な
資料を借りてゆく。卒論の締切までどれほどの期間があるのかなあ。どんな卒論
が書けるのであろうか、とひとごとながら心配になる。これから先、大学の学生
数が減るから私学は水準がどんどん落ちることとなるようだが、今よりさらにす
ごいことになるということなのだろうなあ、と思うとわくわくしてくる。
新刊発注をする。
- 10月18日(水)
朝、小学校の教頭先生から電話。校長先生に宛てた文書の肩書が違っていたこと
が判明。大失敗。平謝りの私。急いでいたとはいえ、失礼極まりないことであった。
間違えぬよう、よく確認したつもりだったのだけれども。
空いているようで混んでいる。図書の貸出返却業務をしながら、利用者用検索端
末を見ていると、悩んでいる人が多いのである。「この機械、遅いので、よろしけ
ればカウンターで調べますよ」と声をかけると案外レファレンスだったりする。そ
れはこの端末では調べられるはずがなかろう、と資料を探しはじめると大変だった
りするのだ。探せないまま帰る利用者のなんと多いことか。これはきっと全国に多
いのだ、と私は思う。ほかで調べてわかった、わからないけど、さして問題になら
なかった、というような解決がついているため、潜っているだけ。そのようにして
案外戦後が済んできていたりして、などと考えると面白い。図書館への要求がそう
した人たちから沢山出てきていれば、日本の図書館行政はきっと今のようではなか
ったのだろうが。今から変わってゆくのが、そういった方向へであれば良いが。
- 10月17日(火)
近所の小学三年生が調べ学習にやってきた。事前に先生にほかの職員が、「子供
さんの調べものは難しいテーマを考えてくることが多く、資料がない場合がありま
す」と説明をしておいたとのことだが、比較的調べやすいテーマにしてきた子供が
多かった。「戦時中のくらしについて」、「昔のおもちゃについて」など。ただ、
同じ調べものをするグループがあり、そんなに沢山類書はないので、先生に説明し
たところ、順番に見ていたようだった。今回難しかったテーマは「昔の釣り竿につ
いて」。大人の本でも調べるのが大変。結局ほかのにかえてもらったのであった。
にぎやかな一家が時折来るのだが、今日はそんな一家が沢山来た。階段を二、
三歳の子がずるずると降りるのを平気で眺める母親。事故があったら大変なので、
「危険なので手を引くなりしていただけますか」と言うと、「大丈夫です」とのこ
と。大丈夫じゃない、と私は思ったが、それ以上どうすることもできず、見ないよ
うにした。絵本をふんづけて奇声をあげて走り回ったり、階段をずるずる降りたり、
床で転がったりしている子供をなんとも思わない母親達。そして子供はそんな風で
そのまま大きくなったりするのだな。日本にまともな未来はないと考える私である。
- 10月13日(金)
明日、明後日と私は休みなので、今日のうちに沢山の仕事を片づけねばならな
い、というのに、読書感想画コンクールの表彰式の案内を入れた封筒に書類を入
れ忘れたことに気づき、教育委員会の交換箱(各学校に配布する資料を入れてお
く箱)へ行き、封をはがして入れ直したのであった。しかし早く気づいてよかっ
た。ともあれミスはよくない。確認はしっかりせねばと心に誓う。
教育委員会から戻り、視聴覚資料の窓口に出ると土日以上の利用者がわさわさ
とやってきていたのであった。あまりきっと利用者はいないから発注業務ができ
るだろう、と甘い見通しを立てていたのだが、それどころではなく、いつも平日
はひとりで間に合う窓口がふたりでもたいへんだったのであった。
なんとかしかし、今日中にしてしまわねばならないことはしたのだった。
- 10月12日(木)
えらい人が外国の町に行くので、日本とその町の過去について調べねば、との
調べもの。なかなかたいへんな過去があり、うっかりしたことをその町で言うと
とんでもないことになるな、と心配。
見計らいの本屋さんが来る。その本ならば私が個人的に買おうかどうしようか
悩んだ記憶がある。「出版社はどこそこで、編者は確か○○さんでしたよね」と
言うと、「よくご存じですね」と驚いている本屋さん。私は本については自分で
欲しがることが多いのでよく覚えられるのだな、と気づく。しかし私は図書館で
本を借りることはほとんどない。買ってしまうのであった。
新刊本の見計らいをする。一日がばたばたと過ぎた。
- 10月9日(月)
このところ、物忘れが激しい。調べものに来た人の顔に確かに見覚えがあるの
だが、誰であったかまったく思い出せない。はて、しかし調べている内容は学生
のようであるし、当たり障りのないように応対をせねば、と、ま、粗相がないよ
うに接した私。その人が帰ってから、「ん。そうだ」と思い出した。役所の職員
であったのだ。ならば決して学生ではない。少し頓珍漢なやりとりをしたかもし
れない。
調べものは今日もとても多かったのだった。
割と利用者の少なかった一日であったため、抽斗のなかに溜め込んである本の
パンフレットを取り出し、選書をする。
- 10月8日(日)
朝、がらがらだったので、一日こんな塩梅なのであろうか、と思いきや、やは
り午後からが大変だったのでした。調べもの多し。修学旅行のための調べものの
小学生、先生がテーマを決めての中学生。中学生はてきぱきとしている子たちが
多く、なかなか良い感じであった。日本の未来はそんなに暗くもないのかもな、
などとも思う。ほんと、この国はどうなってゆくのかなあ。
我が館の利用者用端末は書名と著者名でしか探せない上、遅いので役に立たず、
何かを探している人を見つける機械なのだが、もしも件名などで探すことができ、
速い機械であったとしても、利用者だけでは見つからない場合というのはしばし
ばあるはずなのだ。例えば、今日の調べもの二つ。「体の歪みを治す本」。これ
を「体」とか「歪み」で探していた人がいたのであった。また、どうやらビール
についての本を探している様子の方があったので、588の分類に案内すればいい
のかな、と話を聞いてみると、各ビール会社の売り上げを調べているとのこと。
「会社年鑑」などを見なくてはわからないのである。やはり司書は要るよな、と
再確認した一日であった。
- 10月6日(金)
新刊書の発注業務を行った。このところ、これは読んでみたい、と思われる本
がとても減っているのは私が歳をとったせいであろうか。
感想画コンクールの賞品を決定。これはなかなか良い選択のような気がする。
- 10月5日(木)
読書感想画の表彰式が近づいてきているのだけれど、招待する人への案内状な
どをまだつくっておらず、つくっていないから当然、決裁もおわっていないわけ
で、これは急がねばと焦った私であった。しかしこれがまるで私に向いていない
仕事。この人たちにはこの文書を、彼らにはこの文書を、そして式次第は、うわ
ああ、めんどくさい、と途中で叫んでいたりしたのでしたが、ほかの職員はかわ
るがわる毎年この仕事を黙々としていたのであった。「文句を言うのは戸田さん
だけだ」と言われてしまったが、そもそも私は読書感想画も読書感想文も本好き
な子供をつくるよりも本嫌いな子供をつくるのではなかろうか、と考えているし、
そんなことよりもなによりもこまこまとした仕事に性格的に向いていないのであ
った。図書館の中枢の仕事以外はほとんど苦手なのではなかろうか。向いていな
い仕事の多さを市民課で痛感したが、この仕事をしていても痛感したのであった。
今日は市報の原稿の締切でもあったので、これも焦った。こちらはしかし楽し
い作業。
隣町の図書館の人が来て、「アプリケーションソフトのマニュアルを今までは
買ってなかったのですが、要望があったため、購入を検討しようと見学にきまし
た」とのこと。どのソフトのものを買うかリクエストが増えたときの線引きがむ
ずかしいこと、附属CD−ROMをどう貸すか、動画が入ったものを貸し出せない
問題などについて話したのであった。
- 10月3日(火)
読書感想画の賞品選びをする。1500円くらいで喜ばれる文房具って、今の世
にはないのではなかろうか、という気がしてくる。若い職員に小中学生の頃、ほ
しかった文房具を訊いてみるが、彼らの時代にはすでにそれほどほしいものがな
かったらしい。日本は裕福になってきていたのだなあ。私は欲しいものがいっぱ
いあったけれど、それは軸に押すところがついているシャープペンシルであった
り、と今ではないようなへんちくりんなものばかりで一般性がないので元々私の
意見は通りそうもないので言わなかったのであった。文房具のカタログと、ギフ
トのカタログを間違えてひっぱりだした職員がいて、別の職員が、「それはカニ
缶とかそういうのしか載っていないぞ」と言ったので、「文房具よりもカニ缶の
方がもらってうれしくはないだろうか」と言ってみた私。いっそ奇をてらってイ
カの塩辛とかホヤを賞品にしてはどうかなどとも言ってみたのですが、却下され
ました。はて、なににしよう。候補はいくつかあるものの決定しなかった今日で
した。
本の見計らい、お金の計算などばたばたした一日でありました。
- 10月1日(日)
「としょかんだより」をなんとか作り終えた。ふう。
朝、空いていたのだが、終わってみると貸出4396冊、返却4543冊。なかなか
の人出であった。返却が多いと本棚がいっぱいになる。来週も閉架への移動処理
か。ふう。
- 9月30日(土)
朝、がらがらだった。今日は平和な日なのであろうか、と思っていたら、大間違
い。昼からどかどかどかどかと来館者。調べものの人、所蔵してるかを尋ねる人多
数。
「としょかんだより」をまだ作り終えていない。明日には作り終えねば。
- 9月29日(金)
三歳くらいの子供を利用者用検索端末機の置いてあるカウンターに靴を脱がせて
立たせている母親に注意をする。何を言われているのかがわからぬ様子。赤ん坊を
乗せる母親はこのごろさらに増えてきているが、見るからに汚い足の裏の子供をカ
ウンターに乗せている母親を見たのははじめてである。いずれはあちこちの台の上
を皆が裸足で歩く時代が来るのであろうか。それはそれで笑えるが。
かなり遠くの町から調べものに来ている大学生がいた。私の勤務地の特産物に関
連した調べものだからであろうが、熱心である。郷土資料も喜んでいることであろ
う。って、ここんとこずっとこんなことを書いている私である。立派な大学生も確
かにいるのだな。
読書感想画の作品集の校正を終える。
- 9月28日(木)
高校生が難しい宿題を出されていた。近隣の高校でなければ良いが。大学生に出
したって簡単ではないような宿題。同じ問題を数年前にも見た記憶がある。同じ先
生なのであろうか。公共図書館に資料があるかどうかを確認してから出してもらい
たい、といつものことではあるが思った私。
ようやく閉架の「谷崎潤一郎全集」を開架に出すことができた。
閉架へしまう本を今日も二時間ほど選んだ。くらくらした。
大正時代に出版された本を利用する大学生がいた。本も喜んでいることであろう。
- 9月27日(水)
閉架にしまう本をまた二時間ほど選ぶ。神経を集中しすぎているためか、気持ち
が悪くなってくる。
新刊書の見計らいをする。このほうがやはり楽だ。
大学生の宿題を調べにくるのが多い。「大学図書館で雑誌の論文を探したほうが
楽ですよ」と言っても聞かず、それでレポートが書けるのであろうかと思われる本
を借りてゆく。きっと締切まで間がないのであろう。しかしそれで良いのか。そう
した大学生を片っ端から落とす無茶な先生だらけだと面白いのだが、そんなことを
すると大学の経営が成り立たないのだろうなあ。
明治時代に出版された本を利用する大学生がいた。本も喜んでいることであろう。
- 9月26日(火)
本の移動、小説のトまできた。あとひといきである。
夏休に貸し出した本が沢山返ってきたためか、なにやらよくわからないが、開架
のあちこちが本でいっぱい。本の上に横にして本が置いてあったりして大変。閉架
にしまう本を二時間ほど選ぶ。頭がくらくらしてくる。買う本を選ぶのよりもずっ
と大変な作業なのである。閉架にしまうということは、一種の検閲であり、もしか
するとその本は二度と借りられることがなくなるやもしれないのである。しかしな
んというか、言いたくないが、本は出過ぎているのだよなあ。
八月に実習を受けていた大学生がお菓子を持って来館。このときの実習生は見る
からに熱心だったのだよなあ、としみじみ思ったりした。時の流れを早く感じるの
は歳のせいであろうか。
ぼちぼち「としょかんだより」の原稿を書かねばならないし、実習生の所見を書
かなければならないし、読書感想画コンクールのあれこれはあるし、と仕事が妙に
多いのであった。
- 9月23日(土)
朝、少し、「谷崎潤一郎全集」の為のスペースをつくるための移動。まだ小説の
ハのところ。タまではかなりあるのであった。
実習生を私が受け持つのは今日でおしまい。なんとなくばたばたの三週間であっ
た。
- 9月22日(金)
館内整理日。「谷崎潤一郎全集」が閉架に入っているのを開架に出さねばなあ、
とずっと思っていたのであるが、スペースがないからどうしようか、と悩んでいる
頃に役所に異動。先日そのことを思い出したので実行しようと考えたのでした。し
かし、開架は以前にも増していっぱい。このあたりの本を閉架に入れて、ずうっと
動かしてゆけばいいや、と考え、皆に話すと、「今日のうちに終わるんですか」と
言われる。「それはわからぬ」と情けない返事を返しつつも作業をはじめたのであ
った。二万冊ほどの本を動かしてスペースを作るという遠大な計画。しかし谷崎の
小説、例えば「瘋癲老人日記」や「鍵」や「痴人の愛」や「卍」を閉架から出して
ください、と言いづらい利用者は多かろう、との見解には同意する職員が多く、ず
りずりと本を動かしたのであったが、三分の二ほどの位置で時間切れとなったのだ
った。来週のうちには終わることであろう。図書館には本が沢山あり、順番に並べ
てないとまずいのであれこれと大変な仕事があるのである。
- 9月21日(木)
南アフリカがスロバキアの負けたおかげでなんとか予選突破。と、ここ数年サッ
カーをこまめに観ている私。ワールドユース選手権はNHKBSで放送してる分をす
べて観たのであった。ナイジェリアが暑かったせいか、高原が持っていたバリカン
で稲本、中田浩二も坊主頭にしたのだったなあ。ほかに辻本、遠藤、氏家、加地と
いった選手も坊主にしていて、準優勝のあとの映像では坊主だらけでおかしかった。
あのとき坊主にしなかった小野君はその後坊主にしたけど今回出られなくて気の毒。
今回はみんな坊主にしないんだろうか。中田浩二の怪我の塩梅はどうなのだろ。酒
井君はへろへろになっていたけれど、アメリカ戦に出られるのだろうか。ううむ、
とうなったような状態の私ではあるが、仕事をしたのであった。
よくある話なのではあるが、「息子の授業での発表のために調べに来た」という
母親。貸出ができますよ、と言うと館内で私が見てゆくと答える。「宿題は子供さ
んが直接調べるべきですね」と一応資料を渡しながら言う私。「部活で忙しいから」
と母親。この親子を気持ち悪い、と感じるのは私だけか。
利用者がとても少ないなあ、と油断していたら、帰り際にばたばたと調べものの
人がきました。
- 9月19日(火)
ブックポストへの返却本は相変わらず多かったが、火曜日の割に利用者が少ない
一日であった。
水害により、先週見計らい本が届かなかったため、二週分の本を見計らう。実習
生に、一冊ずつなぜその本を蔵書とすべきと考えるのかを説明しながらの作業。頭
がぐるぐるしてきて倒れそうであった。
- 9月16日(土)
雨降りだというのに午後から利用者多し。
今週は新刊や発注した本の荷が来なかったため、仕事の予定が狂い、調子がおか
しい。
実習生、レファレンス問題、割と沢山解いていた。まずは大きな辞書から調べる
との原則(例えば漢和辞典ならば「大漢和辞典」、国語辞典ならば「日本国語大辞
典」から調べれば小さな辞書よりも記載されている可能性が高いわけで、ちまちま
とした小さな辞書をはじめに引くのは無駄なのである)を知らなかったが、学校で
習っていなかったのであろうか。しかし、職員はこの原則を知っているだろうな、
と不安になる私。次回、館内整理日の研修の際、念のために訊いてみなくては。
- 9月15日(金)
祝日にしては利用者が少ないな、と思っていたら、終わり近くにどかどかと来る。
夏休には沢山の本が貸し出されるのだが、それがこの季節には戻ってくる。書架
のあちこちがきつくなるため、閉架へしまわねばならない。本にとって気の毒では
ある。
このごろ本の切り取りが多い。画集、写真集の頁をカッターで切ってしまう気違
いがいるのである。額に入れたりするのであろうか。「里山物語」のカマキリの写
真を二枚切られていたが、それを見て欲情していたりはしないだろうなあ。気違い
に刃物、という言葉をなぜか思い出す。
実習生にレファレンス問題を渡す。苦労していたようであった。
- 9月13日(水)
休館日の一昨日の夜、雨がひどい降りなので、今からこちらへ来なさいと役所よ
り呼び出しがあった。報道の通り、かなりひどい雨であった。本の取次会社が浸水
したとの連絡。新刊はしばらく来ないのであった。
実習生の今日の予定は図書館で行う講座の見学と新刊見計らいであったが予定が
狂う。閉架へ本をしまう作業と図書館だよりに掲載する本の選び方について説明を
した。
- 9月10日(日)
私の母の家系が公家につながっていると聞いて調べようと思う、との電話が私が
休みの昨日にかかってきたとのこと。八百年ほど前と八十年ほど前の人の名がつな
がるところまで家系図が必要だという。しかし、この手の調べ物でつながったため
しはない。また、お公家さんが近所にいたという話を聞いたこともない。その町の
町史を調べたところ、お客さんの言う姓の人は確かに京都から来てはいるのだが、
公家ではなく、江戸時代の前で断絶している。江戸時代以降にお公家さんがその町
に来たとの記述もない。その旨、電話でお知らせする。ご高齢の方はご自分の血筋
が気になるものらしい。しかし、知らないまま、思いこんでいた方が幸せな場合も
あるのではなかろうか、調べた結果を知らせることで寿命を縮めてしまったりはし
ていないだろうか、などとそんなことをふと思ったりする秋の一日であった。
朝、空いていたので、今日は平穏じゃのお、などとのんびりしていたら、昼から
どかどかと人が沢山来館。
- 9月8日(金)
朝、分館の見学のため、実習生を送ってゆく。自動車で通ってきているものだと
ばかり思っていたらバスで来ているとのことであった。
利用者から聞かれた四字熟語の意味が日本国語大辞典にも大漢和辞典にも載ってお
らず、ほかのいくつかの辞書にも中国学芸事典にも載っていなかったので、これは漢
籍から来ているのではなく、新しい熟語なのかもしれませんねえ、とわからぬまま帰
してしまったのち、見落としていた四字熟語辞典で発見。電話番号を聞いておけばよ
かったのが、後の祭りであった。
- 9月7日(木)
なごんできたのか、今日の実習生は聞く気で聞いていたようである。選書の実務。
吉本隆明の名を知らないというのには驚いた。ただ、ふと、もしや正職員のなかにも
知らない奴がいたりはしないだろうな、と考えたりもしてぞっとした。怖くていまさ
ら聞けないぞ。図書館学を勉強している大学三年生とはこんなものであろうか。そう
いえば前に実習を受けていた学生二人は野坂昭如を知らないと言ったなあ。「『火垂
るの墓』の作者です」と言ったら、「ああ、ああ」とうなずいていたが、アニメーシ
ョンを観たのであろうか。しかしもしかして正職員のなかに野坂昭如を知らぬものが
いやしないか。怖くていまさら聞けないが。いろいろと怖いことを想像してだんだん
と怖くなってくる、ぼのぼののような私であった。
実習はあと二週間ちょっと。来週の日程表を作り始めた。普段の仕事をしつつ、実
習をうけもつわけだが、なかなか大変なのであった。
- 9月6日(水)
実習生には私以外に二人の職員が説明した。やはり、聞いてくれているのかどうか
わからないと彼らも言う。ところが実習日誌を読むとよく聞いているようではある。
ただ、感想の欄に質問が書かれている。何故だ。「質問はありませんか」と私は幾度
も問うたのだ。そのとき疑問に思わずとも明日にでも訊けば良いではないか。失礼で
ある。しかしこのところ人間が穏和になった私は、「質問があれば直接尋ねてくださ
い」とだけ言っておく。
- 9月5日(火)
実習生来る。朝、ブックポストに1026冊の本の返却。まずこれを書架まで返して
しまわないと仕事がはじまらない。実習は10時半から。しかし図書館関連の学科って
私にはいまひとつぴんとこないな、と思う。何か一つ、専門分野の学問をおさめるよ
うにはしたほうがよいのではあるまいか。今回の実習生は私の話を聞いているのかい
ないのかがよくわからない。前回の実習生が熱心であっただけに、このつかみどころ
のなさは体に悪い。
- 9月3日(日)
今日もまた午前中に人があまり来なかったので、おお、今日は気楽であるな、と思
っていたところ、午後かなり混む。
実習生の日程表を作り終え、さてぼちぼち書架整理に出かけようか、と考えていた
とき、ふと、広報の原稿締切はいつであったっけ、と思い出す。明後日だった。明後
日から実習がはじまるわけで、つまりは今日のうちに原稿を書いてしまわねばならな
い。三十分でなんとか書く。
- 9月2日(土)
来週から三週間、図書館実習に大学生が来る。前回の大学は一週間であったが、今
度は三週間。そんなに長い実習をこれまでしたことがないため、日程を考えると頭が
痛くなってくる。ひとまず、来週の分だけ考えることにした。
夏休が終わったから利用者は多くないな、と思っていたら、午後、どかどかと人が
来る。やはり土曜日なのであった。
- 9月1日(金)
夏休が終わるとうそのように利用者が減る。それはもうほんとにうそのようなのだ。
私も気が抜けてしまうほどに利用者が少ないのであった。そんな気が抜けた状態のとこ
ろに、「文化祭で発表するための調べ物なんだけれど」と女子高生が五人やってきた。
「朝鮮のことを調べるの」「朝鮮のいつの時代のどんなこと」「戦争のこと」「朝鮮戦
争、第二次世界大戦?それとももっとずっと前」「いつのことだろ」どうやらまるでな
にもわからぬままに調べはじめる様子。資料を見せながら、朝鮮史のアウトラインを説
明。「ああ、きっと日本に占領されていたころのことだよね」「そうだね」と時代がわ
かり、資料を案内したのであった。夏休が終わったからといって油断していてはいけな
い。次は文化祭なのだ。
- 8月30日(水)
小学生が「お化け屋敷」の起源について調べにくる。「明治事物起源」にもさまざま
な百科事典にも風俗辞典、民俗学辞典にも「日本国語大辞典」にもない。小学生は時折
簡単に探せない自由研究のテーマを設定するのである。急がないのであればなんとか調
べてあとから連絡するが、と一応言ってみるが、明日までに調べなければならないこと
はこちらもわかっているのであった。
いよいよ宿題の追い込みのシーズン。そのためかえって中高生はあまり来ないのであ
った。
- 8月29日(火)
夏休もあと三日で終わるというのでかは知らないが、近所の中学で出ている宿題を母
親が調べにくる。「それは○○中学の宿題ですよね」といやがらせに訊いてやるが、全
然なんとも思っていないからやってくるのであった。
貸出はそれほど多くなかったが、中高生の調べ物が山のよう。しかしこれももうじき
終わる。
- 8月26日(土)
夏休の最後の土曜日は大抵は混まないものなのだが、今年はなかなか沢山の人。夏は
学生だけでなくなぜか大人の人も沢山来館なさるのであった。昼休の人手の少ないとき
に難しい質問が相次ぐ。「寺田寅彦の『船をかじる虫』を読みたいのですが」。なにか
聞いたことがあるタイトル。『寺田寅彦全集』があるので、入っているはず。文学総覧
シリーズで作品名から探してみるがない。内容総覧で全部の作品を追ってゆくと、「鉛
をかじる蟲」を発見。これならば読んだことがある。お客さんが紙に控える際、偏を間
違えたのであった。「ウイリアム・ブレイクの本はありますか」「詩集でいいですか」
「できれば詩ではなく、ブレイクについて書かれたものを」。ううむ。と、頭をひねり、
古い資料で電算入力がまともにされていないもののなかから見つけた私であった。しか
し思えば、専門職員がいない図書館において、こうした調べ物がきたらどうなるのであ
ろうなあ、などとふと思う。テキトーにさがして、「ありません」と答えてもその場が
済んでしまうのが図書館のこわいところだ。
- 8月25日(金)
館内整理日。偉い人がうち合わせの最中、突然やってきて、「今日は休みか。何をし
ているのだ」「打ち合わせや本棚の本の移動です」「ふん。本の移動か。ごくろうさん」
と突然帰ってゆく。見る人によっては尊敬されなくなるような態度であるかもしれない
なあ、などと思う。
館内整理日をなくせ、との話も出ているようであるが、今後年中無休開館となれば、
全職員が顔を合わせられる日はなくなるわけで、民主的な運営のためにも、本の大がか
りな移動のためにも必要な日であると思われる。ただ、夏休の7月、8月だけは館内整理
日をなくすというのは考えても良いと思うが。
延滞督促をしてもしても返してくれない利用者のもとへ回収に出向くことが決まる。
館内整理日には参考業務についての簡単な研修も行っている。今日は、「知っていな
いと引けない参考資料」について。柏書房の「宛字外来語辞典」や、日外アソシエーツ
の文学綜覧シリーズ、郷土資料の「旧町名新町名地番説明書」について話す。「宛字外
来語辞典」は外国の地名や人名などが漢字で書かれているのを読むための辞典。この辞
典以外で探すのは困難なものが多い。逆に言えば、この辞典があることを知っていれば
引ける。「旧町名新町名地番説明書」は昔のこの番地は今のどこですかとの問い合わせ
に使うもの。この質問を受けるとなんとなく、古い地図を出してきたくなる職員が多い
ようなので、こういうものがあるのを知っていないと答えられないぜ、と教える。知っ
ていればなんということもないのだが。日外アソシエーツの文学綜覧シリーズはすばら
しいレファレンスツール。短篇や詩をタイトルから検索し、どの全集のどの巻、どのペ
ージに入っているかを調べることができる。ただし、こういうこともある。我が館にあ
る「谷崎潤一郎全集」は28巻だが、ここに収録されているのは30巻である。かならず
しも巻数ページ数が一致するわけではないのでよく確かめること、などといった注意を
する。また、旧字旧仮名の全集、新字新仮名の全集があるので中高生の夏休の宿題に出
す時には中央公論社の「日本の文学」(初の新字新仮名の文学全集)以前、昭和30年代
よりも前の全集であるか否か、といったあたりを考え、さらにぱらぱらめくってから提
供するようにすれば学生からうらまれないぞ、と細かな話をしたのでありました。館内
整理日にはすることが結構あるのであった。ただ閉めてるわけではないのだ。
美術書の開架と閉架の入れ替えをする。開架のスペースがいっぱいで出し切れないの
だが、閉架にもきれいな美術全集がしまってあるので、三ヶ月に一度替えるのだ。
リースが切れるため、来年導入予定の電算システムのデモンストレーションが隣町の
図書館であり、見学させてもらう。もっとできがよくないと思っていたのだが、かなり
よくできていた。二時間半、スクリーンに映し出されたパソコン画面を眺めていたら、
少しくらくらしてきた。隣町の図書館のご好意に感謝。
- 8月24日(木)
時折あるレファレンスに、「この書はどう読むのでしょうね」というのがある。大抵
読めない。しかも今日のは中国人が書いた書。何文字かは読めるがあとはさっぱり。お
まけに書かれているのが知られている漢詩などではない。たまに、有名な詩人の詩が書
かれていることがあり、そうした場合には索引のついている漢詩集などでみつけること
ができるのだが、今日のはさっぱりであった。こういうのを読める人にあたりをつけて
いる図書館もあるのだろうか。
入館者、貸出冊数は少なかったが、調べ物、多し。
- 8月23日(水)
昨日、空いていたので今日は混む。そうしたものである。
本の見計らいを終える。
- 8月22日(火)
比較的空いていた夏休の火曜日であった。とはいえ、夏休。近所の高校の宿題で学生
が沢山。利用者用端末のあたりで若者がたむろしている場合、大抵は宿題で悩んでいる。
「この町のあれこれを調べる宿題かな」と聞くと「そうです」と言う。「ほとんどすで
にきっと君たちの学校の子たちが資料を借りていってしまっているよ」と言うとがっか
りする。このがっかりした若者を見るのが私は好きだ。しかし館内利用のできる資料が
実はまだ沢山あるのである。何を調べるのかを尋ね、資料を出してくる。三、四人で来
ているわりに静かに調べてゆく。夏休も終わりに近づきせっぱ詰まっているのであろう。
今年も高校生の親が子供の宿題のための資料を借りにくる。恥の概念がこの国ではな
くなってきているのだなあ。
- 8月20日(日)
実習、最終日。蔵書点検、延滞督促について説明。図書館の暗黒な箇所である。蔵書
は年間どれだけ不明になるか、その為の仕事がどれほどあるか、盗む人がいなければ、
これだけの仕事がなくなるのである、延滞督促をどれほどしているか。視聴覚資料に関
しては、日に平均30件ほど電話をしている。図書は3週間に1度、300枚ほども督促葉書
を出している。人件費も葉書代も電話代もなかなかのものなのである。どこか山のなか
の図書館では自動貸出機を置いて無人にしてあって24時間開けているそうだけれども、
住民に悪い人がいなければ、いろんな方法をとることができて良いだろうな、と話す。
レファレンス問題をもう10問作っておいたのだが、こちらは前回よりもさらに意地悪
な問題。さすがに半分ほどしかできていなかった。それでもなかなかのものである。
図書館の問題、出版の問題、国の問題などなど、話しているうちに、私が嫌になってき
たりもした。ともあれ今日で実習は終わり。大変できの良い熱心な実習生であった。こ
うした若者のためにも文化行政が良くなり、国が、人が良くなってゆくと良いのだが。
普段の日曜日ほどの貸出だったが、調べものはとても多かった。なぜ夏は学生だけで
なく、普通の大人の人の調べ物も増えるのだろ。
- 8月18日(金)
今日の実習生は1人欠席。朝、分館の見学、午後から参考業務。レファレンスの問題
を10問作り参考資料や一般資料を使って調べてみてください、と言って一時間半ほど調
べさせておいたところ、7問正解。授業でこの手の宿題が出るのだそうだが、果たして
うちの若い職員はこんなに解けるだろうか、と驚いたのでした。即戦力として使えそう
である。
今日もとてつもなく人だらけ。
- 8月17日(木)
今日の実習生は、朝、分類と装備、午後、郷土資料、予約、リクエスト、休憩をは
さんで視聴覚資料、身障者サービス。私は予約、リクエストを受け持ち、ほかは担当職
員にまかせた。よく理解し、熱心である。
利用者、多し。近所の高校生の宿題、先生が図書館で調べなさい、としているのだが、
その宿題に使えそうな図書館の資料はほとんど貸し出されてしまった。うまい設定をし
ている学生がいて、「おお、それなら調べられるね」と感心する。中学生、高校生の宿
題続々。つくつくぼうしが鳴きはじめた。
- 8月16日(水)
入館者が1742人。土日並である。お盆休みはいつも来館者が少ないから、と実習期
間に設定したのだが、実習生に説明している間にもあれこれと仕事が入る。
実習は見計らい選書、資料の廃棄、閲覧実務についての予定であったが、閲覧カウン
ターに出てもらうには人だらけであり、遠くから見るだけにとどめた。見計らい選書は、
先週出版された本のうちの幾冊かが取次から図書館に運ばれてくる中から選ぶ仕事。選
書の基準、どんなことに留意すべきか、どんな知識を持っていなくてはならないか、そ
のための日頃の生活の上での心がけなどについて話す。話があちらこちらに飛んでしま
った感もあるが、選書という図書館における根幹業務についてある程度話せたと思う。
それにしても世の中はものすごい速さで変化しているよなあ、と話をしながら、しみじ
み思うのであった。本は世を写す鏡なので、世の動きを把握するようにと意識しなけれ
ばならないのが、時折面倒になる。
- 8月15日(火)
お盆だからあまり人が来ないだろう、と予想していたところ、見事にはずれる。人だ
らけである。
今日から図書館実習の大学生が2名。6日間、図書館の仕事のあれこれについて学んで
ゆくわけである。私の勤める図書館の歴史について、とどんな仕事があるか、図書館と
関連する法律についてをざっと話した。ふたりともなかなか理解力がある。実習生をう
けもったことは十回くらいあるのだが、今回の学生は割と熱心であるな、と感じた。
- 8月12日(土)
久々に入館者が2000人を越えた。
質問がとても多かったのであった。そしてそれらがなかなかわからない。国立国会図
書館が持ってない、TRCの児童図書検索CDにも載っていない児童書についての質問であ
ったり、児童用の邦訳が出ているかがはっきりしない本についての質問であったり、ほ
んとに出てるかどうかわからない本についての質問だったりして、手間どった。書架に
あるはずの本がなくて、探しにいっても見つからず、急いでいるとのこと故、分館に行
ってもらうなどというケースもあった。
夏休は新聞のコピーもとても多い。綴じをはずしたり、コピー機の蓋をはずしたり、
となかなか手間のかかる仕事。
へろへろになった一日であった。
- 8月11日(金)
近所の高校でとんでもない宿題が出ていることがわかる。まだあまり質問をされてい
ないので、もしかすると図書館に調べにこないのかもしれない、と楽観的な性格の私は
思ったりもするのだが、住んでるところの近くの歴史、地理を調べようとの宿題で、図
書館へ行って昔と今の地図を比較しよう、などと書かれているプリントを高校生が持っ
ていたのだった。「地図はいいけど、著作権法でまるまるコピーをとることはできない
ぜ」とついつい高校生の前でこぼす私。ほかの設問も図書館で調べないと難しいものが
多く、ある程度事前に連絡が欲しいな、と思ったのでした。
近隣の図書館から12時に事務上の質問。夏休の昼休憩の時間に暇な図書館もあるのか、
と呆れる。私が勤務している図書館では利用者登録やレファレンス、閉架の資料を取り
にいったりなんだりで、昼の時間帯は事務室にひとりいるかいないか、といった状況で
ある。土日や夏休に同業者が電話をしてくる時間ではなかろうて。「ただいま、大変ば
たばたいたしております。1時半頃にまたこちらから連絡いたします」と用件を聞いて
おいて切る。複数の質問があるときはFAXかメールにしてほしいと思うのであった。
とんでもない一家を見た。2、3歳の子2人とその親、祖母が絵本コーナーにいたのだ
が、絵本を開きっぱなしにしてあちこち散らかっている状態で走り回っていただけでな
く、ねころがってごろごろとその開いてある絵本の上を通り過ぎる。祖母は笑って、
「はい、こっちこっち」などところがってこちらへきなさいと手招きをしている。私は、
「図書館ではお静かに願います。絵本は大変こわれやすく、特にひらいたまま、真ん中
に負荷がかかると表紙からはずれます。お気をつけください」とおそらくはとても怖い
顔をして注意をした。そんなこと、注意されなきゃわからないか。これから10年くらい
経った日本を思うと嫌になる。
- 8月10日(木)
利用者多し。頭くらくら。もうじき世間様では大型連休がやってくるので、その前に
沢山借りておこうということなのであろう。
マイクロフィルムで新聞を見たい人が多い日であった。少人数の職員の図書館にとっ
てはなかなか大変な仕事である。利便をはかろうとすると金と人が必要なのが文化行政
の大変なところ。そして図書館では決してお金は儲からない。力を入れようとしない市
町が多いのもこのごろではよくわかる。市長や教育長がとても調べものが好き、本が好
き、とか、長期の留学経験がある、といったようなことでもないと、図書館の質を高め
るとはどういうことかがそもそもわからないのである。
来週から大学生の図書館実習もはじまる。その準備もしたのであった。
- 8月9日(水)
月、火と休みのあとの水曜日はブックポストにいつも沢山の本が返っている。しかし
今日は量が違った。2000冊を越えていたことであろう。
開館から受付に入っていた私であったが、人だらけ。開館30分で入館者カウンターは
150を越えている。この機械、往復して「1」なのだが、30分で帰った人は少ないわけ
で、ということは300人来てる。うわ。このまま8時間あけておくと4800人だよお、と
頭がくらくらする。貸出も1時間で800冊を越える。このままだと6000冊を越えるなあ、
と思っていたのだが、午後からは空いた。貸出4793冊、返却5950冊。夏休みが早く終
わらないものかなあ。しかし夏休みとは無関係な人も沢山来ていたなあ。頭がくらくら
するほど質問を受けたりあれこれした一日であった。充実しすぎてるほど。
- 8月6日(日)
アンケートの回収などでばたばた。
さすがに日曜日、宿題の学生が多かったのであった。
自習スペースは今のところ平和だが、アンケートの回答に、「学習室を設けてほしい」
というのが結構沢山ある。知らずにいる人が多いのであった。知られてしまうと以前と
同じ状況になるであろうなあ。一応、広報と新聞で知らせたので、これ以上派手にPRを
する予定はないのだが。
- 8月5日(土)
土曜日の割に空いていた。貸出3833冊、返却3812冊。
アンケートの回答に電算、ガイドブックの新しい本がないとの声が多かったので、新
しい本はほかの人が借りているのだよ、リクエスト予約の制度を利用してね、との旨の
看板をつくることにする。しかし、ガイドブックなんてお金に余裕のある人が出かける
旅行のためのものなのだし、電算なんて機械だけでも結構な値段なわけで、持ってるの
はある程度裕福な人。しかもマニュアルのような本はずっと持っていなければ意味がな
いわけで、なかには延々と延長して借りる悪質な利用者もいたりして、時々図書館がこ
っそり予約をかけて、その人の延長をさえぎったりしてたりもするのだけれど、図書館
になくてはならない資料なのだろうか、などとふと思う。旅の思い出になる千円前後の
ガイドブック、年に何度も開く二千円前後のマニュアル。ま、確かに本だし、あらゆる
資料を収集するのが図書館だが、予約やリクエストをして借りるより買ってはいかがか、
と感じるのは私だけなのであろうか。
以前に借りた、タイトルも著者もわからない本を上しか読んでないのだが、私の借り
た本の一覧を出してはくれないかと言う利用者。図書館ではプライヴァシー保護の為、
返すと同時に何を借りたかの記録が電算から消えることにしてある、と説明。北朝鮮と
日本の間に戦争が起きる一昨年くらいに出た本だった、とのことで、帯を読んだ記憶が
あった私はみっけたのであった。「宣戦布告」(麻生幾著)。
このところ内容だけしか知らないのだが、とやってくる利用者が多い。これはなかな
かつらいレファレンスなのであった。
- 8月4日(金)
今日から三日間アンケートをとることになった。年中無休と延長開館についてだけで
はなく、いろいろな利用者の声を聞くことが目的とのこと。アンケート結果は面白い。
「貸出期間が短い」「予約の本を早く借りたいので貸出期間を短くして欲しい」と、ま
ったく矛盾した回答があったりする。「新しい本が少ない」「IT時代なのにコンピュ
ータの本がほとんどない。古い本ばかりだ」。新しい本を買っていないと面白い図書館
なのだが、残念ながらかなり買っている。副本も買っている。なのにないと言われる。
なぜだ。あなた以外の人が沢山借りてるからなのだぁぁぁぁぁ、と叫びだしたくなるよ
うな回答ではあるのだが、リクエスト・予約システムをあまり知られていないのだな、
と自分を抑える私であった。表示もしてあるし、「図書館だより」にも書いているのだ
けれどもなあ。そうだ、今度作る日限票(返却日をお知らせする紙)に印刷するように
しよう。と、いろいろと参考になる意見があるのであった。延長については、今のまま
(午前10時から午後6時)で良いという人が一番多いが、7時まで開けて欲しいとの声
も多い。いずれにせよ、上層部からの命令で時間は決まりそうなのであるが。
私が役所に行っている二年の間に資料費を800万円も切られたとのことだったので、
かなり控えめに発注していたのだが、控えすぎていたかもしれない、と気づく。
絵本コーナーに男2人と女2人が来ていて、膝枕で寝ていたりなんだりかんだりして
いると女の職員が言うので、見にゆくと、「なんか言いに来たの?」と立ち上がった
細身の若者は真っ茶色の紙で両耳にピアスをしており、眉毛がなく、背が2メートルく
らいある。この若者に上から殴られたら痛いだろうなあ、と思いつつも、「ここは小
さい子が絵本を読むところだからさ」と言うと、「今、絵本を読んでたんだ」とのこ
と。「ああ。絵本を読むだけならば良いのだけれどね」と、背の高いにいちゃんとほ
かのふたりを見回しながら言う私。そんなに不機嫌な風ではない。「ああ」と首を上
下に振りながら答えた若者。やがて図書館から去っていったのであった。夏は色々な
人がやってくる。カップルと言えば昔、書架の間で接吻をしていた制服姿の男女もい
たなあ。かれこれ10年ほど前。彼らはその後どうなったことであろうか。
- 8月3日(木)
再来週からの図書館実習の日程表とテキストを作りはじめる。6年前につくったものを
見ると、以前は余裕があったのだなあ、と思う。そして今よりも頭が冴えていたことが
わかる。レファレンスの問題集を作ろうとしたのだが、すぐには思いつかなくて、歳の
せいかな、などと考えたりしたのであった。
自習スペースは今日も平穏。
利用者は今日もたくさん。
- 8月2日(水)
中学生の体験学習という行事が毎年ある。あちこちの町で行われているようだが、これ
はしかし何かの役に立つのかな。夏休を減らして義務教育期間を減らして早く世に出して
しまった方が早くはないか、などと思ったりもする私。ともあれやってきた中学生は図書
館が好きだという男の子が二人。保存年限の切れた新聞の移動や書架整理といった肉体労
働もしてもらう。かなり疲れた様子である。
分館についての構想を練り、決裁をあげる。締切はまだかなり先なのだが、この仕事は
どうもいまひとつ気乗りがしないので早く終わらせたのであった。
利用者、とても多し。中学生の音楽の宿題、今日も多かった。
絵を描くために、とある鳥ととある乗り物の絵か写真の載った本を探しているとの質問
があった。これがなかなか大変なのである。画集、写真集は重くでかい。どこに目的のも
のが載っているのか、目次などを見ないとわからないことが多い(画集については最近、
日外アソシエーツが良い参考資料を出してくれたため、タイトルがわかれば探せるように
なったのだけれど、タイトルでなく、題材から探す場合には探せないのであった)。大き
な本を何冊もばたばたと音を立ててカウンターで開き、「これはどうでしょうねえ」など
とやりとりをするのだが、なかなか良いのがないのであった。閉架から二十冊ほどの画集
を出したのでした。沢山一度に持つと腰を痛めるので気をつけねばならぬ作業。
- 8月1日(火)
三カ年実施計画のヒアリングというのがあった。電算機の更新についての説明がなかな
かわかってもらえず、大変であった。
貸出冊数3835冊、返却冊数3456冊。夏は平日も利用者が多い。
中学生の音楽の宿題、ひと学年すべてに出ているとのことで、毎日やってくる。私はす
でに飽ききっているが、彼らは初めてくるのである。対応に気をつけねばと思う。気分は
うんざりなのだが、中学生のせいではないのである。折角図書館に来てくれているのであ
るから、ばれないように接しなくては。
- 7月30日(日)
館務実習生のテキストを作る。
レファレンスがいっぱい。さすがに日曜日である。貸出冊数5471冊、返却冊数5068冊。
自習スペースには全部で三十人ほど。閲覧席に座っている自習利用者に、「二階の部屋を
ご利用ください」と言えるうちは平和である。「どこもいっぱいです」と説明しなくては
ならなくなると、閲覧席が埋まることとなる。
- 7月29日(土)
図書館だよりを作る。館務実習生のレジュメを作る。
貸出冊数5356冊、返却冊数4687冊。ばたばたの一日。夏は本棚ががらがらになる
のであった。
- 7月28日(金)
館内整理日。年中無休開館だけでなく、延長開館の話も出ているとのことで、それ
に対して図書館としてどのように対応してゆくかを検討。市民課では土日に開ける予
定はないのか、窓口の延長を特定の曜日だけでなく、ほかの曜日もしないのか、とし
ばしば聞かれたが、約十五年働いている図書館で夜もっと長く開けていてくれ、とか、
月曜も開けろ、という話を聞いたことがない。三十年以上働いている職員も聞いたこ
とがない、と言う。しかし、話が出ている以上はなにかがどうにかなってゆくのであ
ろうなあ。世の中は失業者がいっぱいであり、サービス残業をしている会社も多くあ
るわけで、それに比べたら仕事があるだけでもありがたい、と思わねばならないよな、
と考えたりする昨今である。
午後、今ある建物を壊して新しい建物を複合施設として建てる計画についての会議。
どうやら図書館の分館をそこにどうでも入れなければならないらしい。早ければ五年
くらい先に建つとのことだが、財政状況が厳しいのでもっと先になるだろうが、この
話あるにはあったものの、ここまで具体的な話になっていることを図書館職員は誰も
聞いておらず、もし早く建っちゃったら職員の体制はどういうことになってしまうの
であろう、年中無休や延長で、ただでさえ少ない職員が大変なことになろうとしてい
るのに、さらにその上分館かあ、と考えると憂鬱になってしまう。分館ができること
自体はとっても良いことなのだが、文化行政に対する国やまちの取り組みを思うと、
なんだか変だよなあ、と思うのである。
- 7月27日(木)
来月のなかばに図書館学を学ぶ大学三年生が館務実習にやってくるので、時間割を
つくる。しかしなかなか図書館で働くのは難しいのだよなあ。
今日も利用者多し。しかし、幸いなことに自習スペースはまだいっぱいになってい
ない。六年閉めてきて、閲覧席に利用者が沢山座っている状況ができたこととも無関
係ではないな、と思う。時間の問題かもしれぬが。
- 7月26日(水)
ようやく研修が終わり、普通の日々。発注書のチェック。本の見計らい。夏休みな
ので利用者は多い。
ふと気がつくと私のホームページのカウンタが一万人を突破している。いったいい
つからカウンタをつけたのだっただろうか、とすっかり忘れていますが、ともあれあ
りがたいことです。ご覧の方々、ありがとうございます。この記念にまた何か新しい
企画を考えようかと思います。
- 7月23日(日)
研修やら代休やらでわけのわからぬ一週間も今日で終わりだなあ、とのんびりして
いるわけにもいかぬほどの人手。貸出5265冊。中学の宿題に今年亡くなった人につ
いて調べよ、というのがあり、毎日尋ねられる。訊く方は一度だが、訊かれる方はす
でに飽きていたりする。図書館員にとって面白味のある調べものを宿題にだして欲し
いなあ、などと我が儘勝手なことを思う。
- 7月20日(木)
今週は今日以外はずっと研修と代休なのであった。感想画の入賞者の報告書を作り、
今週の見計らい本をチェックし、新刊情報から新刊を発注し、DMに目を通し、視聴
覚資料の貸出返却受付に立ち、レファレンスを受け、タウン誌から依頼のあった原稿
を書く。利用者が比較的少なかったのと先週発行された本の数が少なかったので、な
んとか終えることができた。集中しすぎて、少し頭がくらくらした。
- 7月16日(日)
なかなか利用者の多い一日であった。貸出冊数は5,885冊。過去のベスト5に入る
数。登録者が31人。これは紛失による再発行は含まれていない数。新たな利用者がど
んどん増えているのであった。ありがたいことではあるが、パンク寸前でもある。
- 7月15日(土)
読書感想画の入賞者の名前、学校名、学年、作品名を入力する作業。これまた粗忽
な私に向かない仕事。私の使っているコンピュータは調子が悪く、よく凍るのだが、
今回は無事であった。来週は研修があるので、今日明日中にいろいろな仕事をすまさ
ねばならず、なかなかばたばたした。
- 7月14日(金)
週刊の新刊情報からの発注作業。頭を集中させて一気に行うのが私の方法。そして
もう一度リストを見直す。
レファレンス、多し。大学生が以前にもまして宿題の本探しにやってくる。大学図
書館の使い方を大学でしっかりと説明してもらいたいとしみじみ思う。もっともなか
には論文を読めるのかなあ、と思われるような学生もいたりするが。
携帯電話が良く鳴る。出てすぐ切る人がほとんどだが、時折長く話をする人がいる。
見つけたら注意をするようにしているが、カウンターから遠いところで小さな声で延
々と話していたらわからないだろうなあ。そんなに電話で話をする用事が世の中にあ
るのだろうか。
読書感想画の最終審査会。美術の先生の絵を選ぶ作業をずっと見ているとなぜだか
頭がくらくらしてくる私であった。
- 7月12日(水)
昨日、一昨日と休館日だったので、ブックポストに沢山の本が返ってきていた。約
1400冊。
レファレンスが多い。法律関連の具体的な質問があったりもする。これは答えられ
ないので、無料法律相談の案内を見せる。パンの作り方の本が全然ない、と言われる。
開架の分は全部貸出中だった。料理の本はそういうことがしばしばあるのだ。過去に
はある分野の本をごっそり盗まれることもあったりした。
新刊本の見計らい。
感想画コンクールの最終審査のための準備の仕事。私にとても不向き。揃えたり数
を数えたりといった仕事をよく間違えるのであった。
- 7月8日(土)
テスト期間が終わったため、自習スペースはがらがらであった。しかし利用者は大
変多く、レファレンスも山のよう。「日本の右翼はどうして極右になる傾向があるの
か。玄洋社と愛国社の活動から考察せよ」といった内容の宿題を高校生が持ってくる。
参考資料として挙げられていた二冊の本のうち一冊は貸出中、一冊は以前盗難にあっ
た本であった。この宿題、かなり特殊で難しいんじゃないだろうか。閉館間際に来館
したので、「右翼事典」を複写したくらい。頭山満の伝記があったのでこれも貸す。
昭和史関連の本を探せば少しは出てくるだろうけれども。何人に出した宿題か知らな
いけれど、印刷された数の多くない本二冊だけしか参考資料に挙げていないのは問題
ではなかろうか。生徒のうち誰か一人が二冊借りちゃったら終わりだもの。調べ学習
の宿題を出すのが大変なのはわかるけれども。
- 7月5日(水)
読書感想画コンクールの第一次審査会。さすがにプロの美術の先生。てきぱきと作
品を選んでゆくのが見事。ここで選ばれた作品の元の本を探す仕事。
- 7月4日(火)
明日が読書感想画の審査会。学校ごとにかたまっている絵をばらばらにまぜる。こ
れもなかなかの大仕事。今年初めて担当になったのだが、今までほかの職員はよくこ
んな大変な仕事をしていたものだと思う。
- 7月2日(日)
さすがに日曜日だけあって利用者が多い一日であった。
閲覧席に自習をしている学生が多数いた。自習用の部屋があることを説明して移動
してもらった。しかし今後自習の席が埋まったらうんざりする状態がまたはじまるの
であろうなあ。自習の部屋を見て回るとちょうどペットボトルのお茶を飲んでいた学
生がいたので注意。ペットボトルや菓子を持ってきている学生は沢山いる。きっと飲
み食いしているのであろうなあ。日本の古き良き時代を思ったりするのであった。
小学生から「ボルボクス」について質問があった。子供用の資料が全然ないような
分野についての調べものがときどきあるのが楽しい。
感想画の点数を数え、学年別にわける。私に向かない仕事だとしみじみ思う。なん
とか終わった。
- 7月1日(土)
感想画の点数を数える。孤独な作業。段々と嫌になってくる。
自習の席のための指定席券を作る。
大学生のレポートの宿題多し。大学の図書館で紀要や専門雑誌の論文をコピーし
た方が早く、良いものが書けるよ、と説明する。「ああ、そういう方法があるので
すか」と言う学生。「締切まで間がない」という学生。「とにかく出しさえすれば
いいんだから」という学生。いろんなことが間違っていると思う。
- 6月30日(金)
明後日はきっと自習の学生が多く来るであろう、と机と椅子を視聴覚室に増やす。
黒板に備えつけてあるチョーク入れを灰皿にしてあるのを見つける。自習スペース
の開放をはじめて十日。早くも悪い奴がいるようである。
応募された感想画の点数を数える。なかなか大仕事。
- 6月29日(木)
来月開かれるOA審査会に提出する資料を作る。今年度で電算機のリース期間が
終了するので、新しい機器構成を考え、あれこれするわけだが、昨年、説明したら
一年あとにしなさい、と言われたとのこと。しかし、ハードディスクの増設が今の
本体では不可能だし、すでにディスクの容量はかなりのところに来ているし、端末
に入っているOSはWin3.1だったりするし、と変えないわけにはいかないのだが。
私の勤務する町は貧乏なのである。どこも不景気だから仕方がないのではあるが。
- 6月28日(水)
新刊図書の見計らいをする。この頃の新刊、魅力のある本が減っているような気
がする。7月5日に行われる感想画コンクール審査会の案内文を作成する。
- 6月25日(日)
貸出の多い日だった。4909冊。「図書館だより」に載せる本を選び、ワープロに
打つ。目が疲れ、気持ち悪くなる。一日で終えてしまおうと思うことがそもそも無理
なのだが、何日もかけて作ると飽きてしまう性分なのであった。
- 6月23日(金)
館内整理日。面倒だけれど、夏休みやテスト期間中にやってくる自習目的の少年
少女への対応をどうすべきかを検討する。指定席券を開館前に配り、一日有効とし、
途中で帰るときには箱に入れていってもらうことにする。席に番号を貼る作業。
出版社十社で作っているグループが見計らいに来る。大抵の本をすでに購入済み
の我が館。勧められても、ああ、それはもう買っています。と答えることになる。
しかし少しずつ予算を削られているので、いずれは、「勧められても予算がなくて
買えません」と言う日がやってくるのであろうか。なんだか楽しそうな将来がまる
で見えない。これはしかし図書館だけでなく、日本中、いや、世界中がそうなのか
もしれないなあ。
- 6月22日(木)
特別整理期間の前二週間ほどの返却期限を今日にしてあったためかとても沢山
の利用者が来たのでした。貸出が3713件、返却が4855件。日曜日並。調べもの
のお客さんもとても多かった。
なにげなく私の机の上にビニール袋入りの本が置いてある。以前、精液のつい
た本が置かれていたときの空気と似ているので、「これはなあに」と近くにいた
職員に訊くと、「くさいんです。汚れています」と言うので、「うんこがついて
るのかなあ」と念のために訊いてみる私。「いえ、ただ、もしかすると尿かもし
れないんです」とのこと。「除籍の処理は?」「しています」「えらいなあ」
その本はそのまま廃棄処分。しかしどうしてページにおしっこがつくのだ。本が
とってもかわいそうだ。
- 6月20日(火)
今日から自習スペースの開放。外は暑く、蚊も多いのだが、葦簀の下の机が案
外多くの人に利用されていた。学生のテスト期間ではないので閲覧スペースは無
事だったが、夏休みなどはどうなるのであろうか、と思うと憂鬱になる。
このところページの切り取りが多い。ひどいのになると買って新刊棚に出した
ばかりの一万数千円の画集の絵を幾枚も切る奴がいる。同じシリーズが何冊も同
様の被害に遭っており、借りている人もわかっているのだが、そいつは、「その
前からこうなっていた」と言うに決まっている人間なので、新しく整理した分に
ついては閉架へしまうことにした。これはかなり特殊な例だが、雑誌のレシピや
地図などはなんだかとても気楽に切ってある。本も月に数冊は見つかる。世の中
にはろくでもない人が多いようである。公徳心のない人はしかし今後減るのであ
ろうか。
- 6月16日(金)
開館を待ちわびていたかのように、十時になると沢山の人。ありがたいことで
ある。
年中無休開館の話は年末年始は除かれるらしい。しかしまだほかに時間延長開
館の話もあるとのこと。仕事の質を落とさずにそうしたことをするためにどのよ
うにすべきかを検討したのちに出てきた話ではないあたりが変。長い時間ただ開
けておけさえば良いと考えるのは素人である。図書館はただの建物ではないのだ。
住民がすべてよい人ばかりであり、予約の件数が多くなく、質問も多くないとい
う町であれば、自動貸出機を置いて年中無休、24時間開館、無人の時が一日の半
分以上ということもそれがよいかどうかは別として不可能ではないのだが。
- 6月15日(木)
いよいよ明日から開館。開架から閉架へ二千冊ほど本の移動。朝から晩まで。
95年以前に受け入れた本のなかで開架に置いておいてもそれほどの利用がなさそ
うな本と閉架に入れても、「ありますか」と問われるであろう本を選ぶのだが、
二年間のブランクと歳のせいか、目と頭が疲れて吐きそうになる。
閉架の移動作業は途中だが、開架はかなりすっきりした。明日が楽しみだ。
- 6月14日(水)
開架から閉架へ移動する本を千冊ほど抜く。頭がくらくら。午後、図書館の外に
葦簀をはる。ここを緑陰閲覧席とし、閲覧と自習をするスペースにする。六人がか
りでまるまる半日の仕事。台風がこなければ良いが。
新刊書籍の見計らいもする。ばたばたしていた。
- 6月11日(日)
今日も閉架で一日作業。閉架の一階は移動が終わった。二階は特別整理期間中に
終わりそうにない。体の節々が痛い。
- 6月10日(土)
朝から閉架の移動作業。エアコンの入らないところでずっと肉体労働をしている
と、段々わけがわからなくなってきて気持ちいいのが不思議。ほかの職員も閉架の
もっと暑い場所で大がかりな移動作業。途中で謎の笑い声が聞こえてきたりもする。
いわゆるナチュラルハイではなかろうか、という気さえする。閉架はやや、空気の
薄い場所なのであった。この作業によってあと二、三年は閉架のスペースが確保で
きたのではなかろうか、という気がするが、実は半年ほどでいっぱいになったりす
るかもしれない。私の予想を誰も信用しないのは、数年前に閉架の移動をした際、
「十年はもつことであろう」と私が言ったそうなのだが、三年でいっぱいになった
という実績があるためである。しかし私はそんなこと言ったっけ、と答えたりし、
余計に信用をなくしていたりもするのであった。
見出板を今まで手書きで書いていたのだが、ワープロで打った方がきれいではな
かろうか、との話があり、新しい見出板についてはワープロで打つことにした。確
かにきれいなのだが、なかなかの手間がかかる。
- 6月9日(金)
電算業者が直したとのことなので、確認すると、分館の本は分館になっていたが、
本館開架でスキャンした閉架の本は閉架のままであった。ま、別段大きな問題はな
いからこのままで良いことにした。ややこしいことを頼むとさらに危険な事態をひ
きおこす可能性もあるやもしれぬ。
ブックポストに返却された本の返却処理をする。
「不明本」のコメントが正確に入っているかどうかを確認すると、閉架の郷土資
料で不明になっている分にコメントが入っていないことが判明。電算業者に連絡。
一昨年に入れなくていい、と言われたとの返答。一昨年と今年は違うに決まってい
るのだが、直してもらい、許してやる。
雨降りで湿度が高く、なかなか厳しい状態の中、閉架の図書の異動作業が続く。
若い女子職員が「ダイエットになって良い」などと言っている。私は少し歳を感
じる。
- 6月8日(木)
昨晩のうちに電算業者が修復作業を終えたとのことで不明図書リストを出す。無
事、分館の一般書も載っていた。不明図書リストのうち、ただのスキャンミスの本
もある。リストをばらばらにし、手分けして本棚を探す。古い電算データは片仮名
で入力してあり、分類番号とラベルのシールが違っているものもあったりしてほと
んど暗号解読の世界だったりする。それもまた楽しい。この作業も今日のうちにほ
とんど終わる。
スキャンミスの本を再度スキャンし、電算に流し込み、不明図書からはずす。
本当の不明図書に「不明本」とのコメントを入れる処理を電算でしたあと、本館開
架の区分でスキャンした本を「本館開架」へ、本館閉架の区分でスキャンした本を
「本館閉架」へ、分館の区分でスキャンした本を「分館」へ区分異動を電算でする。
確認してみると、本館開架の区分でスキャンした元々閉架の本は閉架のままになっ
ており、分館の区分でスキャンした分館の本がすべて「本館開架」になっている。
電算業者に連絡をする。今日中に終わらないことが判明。なかなか困った業者であ
る。
手のあいた人から閉架での作業をしてもらう。今日も暑い。
- 6月7日(水)
特別整理期間二日目。すべての本のスキャンを終える。全部で約三十万冊。思え
ば恐ろしい数である。不明図書のリストを打ち出すと、分館の一般書の分が出てこ
ない。電算業者は去年も一昨年もミスをしたとのこと。今日中に終わらないことが
わかる。
電算の処理が終わるまで閉架の図書の移動作業を指示する。閉架はエアコンが入
らない。温度、湿度が高い日は大変なのであった。
- 6月6日(火)
朝から疲れる話を聞く。首長がいくつかの施設について年中無休にしなさい、と
言っているとのこと。しかもどうも本気らしい。元日も開館することになるのであ
ろうか。勤務を要しない日がなくなるわけで、ううむ、なにやら大変な話。今現在
の図書館の状況も決して余裕があるわけでなく、本館には正規の職員が11人(うち
司書が8人)臨時職員が平日に6人(うち司書が4人)、土日のみの臨時職員が3人
(うち司書が1人)いて、分館に正規の職員が2人(2人とも司書)、臨時職員が1人
(司書)、土日のみの臨時職員が1人(司書)といった塩梅であるのだが、年間貸
出冊数は100万冊を越えている。1989年に日本図書館協会図書館政策特別委員会
が出した「公共図書館の任務と目標」の附録「数量的な目標」によれば120万冊を
目標にするのであれば職員は60人必要である、とされている。単純に考えると私の
勤務先には50人の職員が要るのだが、土日の臨時職員を合わせても24人。正職員
だけだと13人しかいないのだ。しかし現実にはこれでも恵まれている方だったり
するから日本の公共図書館の現状は恐ろしいのである。そんななか沢山開けなさい
といった話が出てくるのである。もちろん開館日数を増やすことはサービスには違
いないが。質を落とさずに開けるためには増員が必要不可欠。そのあたりを果たし
て理解してもらえるのであろうか。ひとつ間違うと民間委託なんてな話が出てきた
りはしないか、とびくびくしてしまうのであった。このところ楽しい話が少ない。
世の中が全般的にそうなのだけれども。
今日から特別整理期間。年中無休となると棚卸もできなくなって不明本だかどう
だかもわかんなくなっちゃうってことなのであろうか。ううむ。
- 6月3日(土)
小学生の宿題。「テレビの発明と、それにより人々の暮らしがどのように変化し
たかを調べてきなさい」とのこと。「テレビの発明についならば百科事典などに載
っているけれど、人々の暮らしがどう変わったかについては大人の本でもあまり書
かれていないんじゃないかなあ。先生はどうやって調べるように言ってたのかな」
と私が訊いたのは、きっと先生はおじいさんやおばあさんに訊いてきなさい、と子
供達に言ったのではなかろうか、と思ったからだったのだが、「図書館で調べてき
なさいって先生は言ってた」とのこと。先生はまず図書館で一度調べてから宿題を
出すべきだと思う。テレビの発明についての調べ方の説明をし、暮らしの変化につ
いてはおじいさんやおばあさんに訊いてみてね、と言っておいた。
明後日から特別整理期間なのでであろう、沢山の来館者であった。
- 6月2日(金)
今日も涼しかった。
幕末の志士の写真は、どうやら明治二年に撮影されたものと判明。キャプション
が怪しい。西郷隆盛の写真ではないかと騒がれたものらしいが、それも否定されて
いる。西郷隆盛の写真は現存していないはずだがなあ、と思っていたが、やはり現
存していないようである。明治二年に撮影されたものであれば坂本龍馬はすでにこ
の世に亡いはず。実は生きていた、という話であろうか。元は読み物風の文の多い
雑誌に推論として書かれている文章なのではあるが、ううむ。
著者や出版社からの寄贈本があれこれ来る。顔を水でよく洗う美容法とか、自動
書記で書かれたと書いてあるおばあさんが書いた本とか。あまりに眉唾くさいもの
は蔵書にしないのだが、こうした本にはある種の魅力がある。
- 6月1日(木)
涼しい日であった。閉架の蔵書点検作業が楽。暑いとなかなか大変なのである。
- 5月30日(火)
もうじき特別整理期間なので、貸出期間を長くしている。沢山借りていってくだ
さいね、とカウンターでお客さんに声をかける。棚の本が減れば、棚卸作業が楽に
なるのである。
坂本龍馬と西郷隆盛と勝海舟と副島種臣と桂小五郎とその他幾人か
の幕末の志士が一緒にうつっている写真がある。写真にうつった人物は本当に彼ら
か、との問いがある。普通に考えれば、キャプションが誤っていると思われるのだ
が、ある雑誌に書かれたものであるとのこと。一応調べることにする。
- 5月28日(日)
さすがに日曜日。利用者がいっぱいであった。昨日も今日も貸出が約五千冊。閉
架蔵書点検も並行して行っているのでばたばたしている。「図書館だより」を作る。
- 5月27日(土)
雨降りだというのになかなかのヒトデ。ではなかった人手。試験勉強の中学生が
来ていたので、「夏にはそういうスペースができるかもしれないけれども、今はこ
こは館内の本や新聞を読むだけのための席だから、調べもので使ってね」と注意。
延べで十人来ていた。みんな素直な良い子ですんなりあっさり帰っていった。自習
スペースを設けた後も閲覧席から素直に移動してくれる子ばかりならば良いのだが、
6年で人間はそんなに変わっていることであろうか。注意して刺されたりするかも
しれないな、などと思う。
交代で閉架での棚卸作業。雨降りなので窓を開けて換気扇を回すことができず、
暑かった。閉架にはエアコンが入っていない。ま、真夏ではないので蒸し風呂とま
ではゆかなかったが、汗だくになったのでした。
今年から富山県内の公共図書館で働いているShiretexさんという人から
メールをいただいた。そのひとのホームページ
を拝見したところ、図書館で働こうと思っている人に大変役立つ情報が沢山あり、
新人司書らしい慌ただしい日常も綴られており、趣味のページも楽しかったので
した。必見のページ、かも知れません。
- 5月26日(金)
館内整理日。自習用の部屋開放について。部屋の予定が急に入ることもあるため、
指定席券を早くから渡すことは無理とのこと。ほかのなんらかの規制をしてから開
放してはどうかとの案を出したのだが、その手間を閲覧スペース死守(笑)に向け
るべきではないかとの意見が若い職員から出て、ま、それもそうか、ある程度制限
をしてもどのみち学生はわんさかやってくるな、と少し投げ遣りな気持ちにもなり、
ほぼなんの策もとらずに開放することになった。六年前、当時の館長たちと大変な
苦労をして閉めたことを思うと感慨深い。「元のようにはならないかもしれない」
と根拠のない楽観的な発言をする人がいたので、私は「予言をしてもいいが、元の
ようになります」と言っておいた。ならなければならないに越したことはないが、
なったからと言って誰かがなんとかしてくれるわけではなく、結局は閲覧スペース
に利用者を沢山案内しようと、まともな仕事をしようとする専門職員のみが困るの
である。物言えば唇寒し、である。
- 5月25日(木)
遠方よりレファレンスの依頼。明治時代の地番が今のどこにあたるのか、そのあ
たりの部分の地図の複写をして欲しいとのこと。明治の地番から現在の地番になる
までにその住所は二度地名が変更している。また、変更後の地番が地図に出ていな
いところもあり、固定資産税の担当を以前していた人にも電話をして尋ねる。丁度
市役所にいたときに知り合った人に詳しい人がいて依頼された内容を満たす調べも
のができた。と安心していたところ、調べものを頼んだ市役所の人から逆に調べも
のを頼まれたのであった。
閉架の棚卸。郷土資料には函に入ったものも多く、本体にしかバーコードシール
が貼ってないものもあって、しかもとっても大きく、重い本だったりして苦労した。
明日は筋肉痛になるのではあるまいか。
- 5月24日(水)
再来週から特別整理期間に入り、棚卸をするのだが、その前に閉架の本の棚卸を
はじめる。閉架はエアコンがなく、とても暑く、郷土資料もあって、なかなか大変
である。郷土資料は何が大変かというと、ぱらぱらとした細かなパンフレット一枚
ものの書類などが多く、それらについたバーコードシールをひとつひとつスキャナ
ーで読みとるわけで、読み落とすと不明資料になり、本当にあるのかないのかを探
すのがまた大仕事となり、そんなよなことで大変なのである。
- 5月23日(火)
小学三年生の図書館見学の最終日。今日の学校は少し時間が短めだったので、説
明を端折ったせいか、あまり質問が出なかった。
利用者用端末(OPAC)の前で悩んでいるお客さん多数。訊きにゆくとすぐに
わかる本ばかり。職員に訊くより自分で調べた方が良いのかな。気楽に訊いてもら
える環境にせねばと思う。
- 5月20日(土)
調べものの多い一日。書架まで案内することが多く、足が疲れた。体力が落ちて
いる気がする。
- 5月19日(金)
一部屋だけを学習用に開放するのかと思っていたところ、二部屋開け、さらにテ
ントも張るとのこと。なんだかめちゃめちゃな展開。いまさらあまり役にも立たな
いのだが、学習スペースを開放していたときと、閉めてからの比較統計をつくる。
当然ながら学習スペースを開放していたときは異様にに入館者が多い。うろうろし
ている学生がいっぱいいるということである。一般の利用者が普通に図書館を使え
なくなるあの状態になることだけはなんとしても避けたいのだが、むずかしいのだ
ろうか。
- 5月17日(水)
予想はしていたが、とんでもない話が持ち上がった。図書館の外にテントを張る
よりも会議室を学習スペースとして開放した方が良い、と首長が言い出したのであ
った。そしてなんと命令が下ったとのこと。「教委決定ではテントを張るというこ
とだったのに、いきなり『学習室をあけろ』と話が変わった。どう説明してもダメ
なようだ」と館長。「そんなことしたら元の木阿弥ですよ」と幾人もの職員が館長
に言うが、ま、こりゃしょうがないみたいだ。
学習スペースの利用希望者が1000人ほどいることは間違いないわけで、席の数
は48。何の制約もしなければ、朝殺到し、階段を駆け上がり、席を確保できなかっ
た生徒は閲覧スペースを占拠し、そこにも座れなかった生徒は書架のまわりをぐる
ぐるとまわる。「閲覧スペースは館内の資料の利用以外に使ってはいけません」と
生徒に注意しても、ほとんど誰も動きはしない。聞き分けの良い子が動くとほかの
子が座る。ほかの子にもどの子にも注意をするわけだが、その数が延べ何百人(大
袈裟な話ではないのであった。今は夏休みのピーク時の入館者数が1800人ほどで
あるのだが、過去に学習スペースが150あったころには2700人もの入館者があっ
たことがあるのだ。その差900。今の方が貸出利用者は増えているのである。出た
り入ったりする子供を引いたとしてもなかなかの数であることは確かだ)となるわ
けで、大変。堂々と席の数を公表し、事前に往復はがきなどで申し込んでもらい、
利用券を発行し、利用券のない者は使用できない、とすれば無駄に来館する生徒が
減るのではなかろうか、などと考える私であった。学習利用者が多すぎる館ではど
のように対応しているのであろうか。ほったらかしにして、閲覧席が埋まっても
「早い者勝ちです」と言えばよい、という上司もいたりする。そうなったらいった
いなんのために参考資料があるのかがまるでわからなくなる。買わなくても良い、
図書館などなくても死ぬひとはいやしない、と言われたらそれまでなのではあるが。
大変な苦労が水泡に帰すのは一瞬だな、としみじみ思うのでした。なぜ、どこでも
できる勉強を図書館でしたがる子供が多いのか、させたがる親が多いのであろう。
ただのイメージと昔の図書館の歴史、現在の近隣の図書館の現実、ドラマでの図書
館の扱い、といったところでしょうな。「それは違うのだ」と多くの人に思わせな
ければどうしようもない。でも、無理に近いみたい。ところで、すべての子供が学
校の勉強を熱心にするのが良いと思っている世の中って不思議。閲覧スペースで学
習している子供に注意しにゆくと、「勉強をしにきたのになぜ注意されなければな
らないんだ」という態度がありありの子だらけなのですが、勉強するって、そんな
に偉いことなのか、と私は思うのでした。でも、「勉強しに行ったら帰れと言われ
た」と親があとから電話で怒鳴ってきたりするわけで、そんなような世なのですな。
猫を追うより皿を引けと言います。決まってしまったことなので、なんとかひどい
ことにならないように対応を考えねばならないのでした。うんざりしますが。
- 5月16日(火)
レファレンスの多い日であった。酒井抱一の絵が何に入っているかは日外アソシ
エーツの「日本美術作品レファレンス事典」を見ればわかるのだが、そこに載って
いる本を所蔵しているかどうかを調べるのがなかなか大変。その全集は持っている
はずだけれど、その巻があるかどうかについてはわからなかったりするのである。
ひとつわからぬままのレファレンスを抱えている。「戦後すぐくらいに私が読ん
だ本の続きを読みたい。日本人が書いた小説で、題は『大地』だったと思う。青年
が結婚した後、大陸へ渡り、帰国をするときにいろいろな人と離ればなれになる。
この小説は前編と後編に別れていて、私は前編しか読んでいないので、後編を読み
たいのだ」とのこと。しかし、『大地』というタイトルの日本の小説は国立国会図
書館のデータでは見つからず、『大地』が書名に含まれる本でそれらしいものもな
さそう。誰の書いたなんという本か見当のつく方がいらしたら、ご一報ください。
- 5月14日(日)
レファレンスの多い日であった。中学生が「星はどうして☆のマークに書くの」
と訊いてきたのが一番大変だった。貸出も返却もかなり多いのは日曜日だからしか
たがないのであった。
- 5月12日(金)
余裕のある一日であった。市民課への異動の前に置いていったあれこれのうち、
ごみを片づけようとしたところ、ほとんどがごみであることに気づく。
- 5月11日(木)
新刊書に分類番号をつける作業をする。
分館があるため同じ本が複数冊あるのだが、本棚がいっぱいになってくると一冊
をお客さんに無料で渡している。これをボランティアの人に頼んでバザーで売って
もらい、ボランティアの活動資金にしてはどうか、との話が館長からあった。すで
にそのようにしている図書館もあることは知っているのだが、仕事の量が増えるた
め、せずにいることである。また、ある本は無料、ある本は有料としても良いので
あろうか、といったような説明をしておいた。本の出過ぎがいけないとも思ったり
もする私。
調べもののお客さんが多い日だった。
- 5月10日(水)
二日間閉館していたため、ブックポストへの返却がなかなか多かった。1268冊。
新しいスポーツについての質問があったが、「ニュースポーツ百科」には載っ
ていなかった。残念。
リクエスト図書の処理をする。直販でしか買えないものなどもあり、なかなか手
間のかかる作業である。
- 5月7日(日)
さすがにゴールデンウイークの最終日。視聴覚資料の窓口は休みなくお客さん
がやってきた。よく歩いたため、足が痛くなった。
南方熊楠についての概説書はないかと訊かれる。沢山ある。この中でどれがよ
いだろうか、と訊かれる。ううむ、と唸る私。訊いているこの人がどんな人かが
よくわからないとそれはわからないのである。「岩波ジュニア新書は高校生向け
くらい。あとはそれぞれ特色がありますので、こちらでご覧になってから借りて
いっていただいてはいかがでしょうか」と答えた私であった。
- 5月6日(土)
世間様のゴールデンウイークももうじき終わり。しかし今日も割と空いていた。
大学生の宿題が多い。難解な調べもの。学校図書館に行って紀要や雑誌の論文を
読んだ方が簡単に書けるよ、と教えてあげる。しかし、締切が間近に迫っていた
りするのであろう。何かないかと随分探すようである。大学図書館で調べてもど
うにもならないような宿題を持ってきた学生もいた。いろいろな学問分野が世の
中にはあるのだなあ、としみじみ思った私であった。
- 5月5日(金)
今日も空いていた。天気もいいし、みんな遊びにいっているのであろう。
新刊書の発注作業、アンケートへの回答をする。
- 5月4日(木)
今日も空いていた。新刊本に分類をつける作業と、受入明細書を確認する作
業。
開架が慢性的にいっぱいなので、あまりにきつくなったところからぼちぼち
と抜き、閉架に入れているのだが、この選択がとても難しいのであった。一応
の基準としては、
1.出版年が古いもの
2.利用があまり多くないもの
3.利用はある程度多いが、きっとお客さんが尋ねてくれるであろうもの
といった感じなのではある。しかし、例えば「痔」の本や「夜尿症」の本の
古くなったものなどは、それほど利用も多くなく、ううむ、とかなり悩む。ま、
ここまで極端な例をあげることもないのだが、閉架にしまってしまえば利用は
かなり減るわけで、これはある種の検閲のような行為でもあり、かといって開
架に書架を置くスペースはもうなくなってしまっており、ともあれ困ったこと
なのでありました。そして閉架もいっぱいになってきているのでした。ちなみ
に開架に十万冊くらい、閉架は十二万冊くらい入っています。これから建てる
中規模図書館は開架に三十万冊くらい入るようにしておかないとすぐにいっぱ
いになることでありましょう。出版点数が多すぎるという気もするけれども。
- 5月3日(水)
祝日なのだが、この時期は毎年比較的利用者が少ない。
このところ、あちこちからアンケートがくる。図書館の問題点を訊かれたり
する。問題は山積みだが、まずは、専門職を必要な人数分配置するところから
しかはじまらないのではなかろうか、と思う。
新刊本の見計らい。柳の下のどじょうを狙った本がこのところ増えているよ
うな気がする。
- 5月2日(火)
久々に視聴覚資料の受付に出る。どこになにがあるか、さっぱりわからない
私であった。質問がまるでなく、忙しいのだが、退屈だった。
- 4月30日(日)
高校生が難しい宿題を持ってくる。一冊、二冊の本ではなんともならないし、
参考資料をいくつか見ても厳しそう。先生は参考資料を示していませんか、と
尋ねると「現代用語の基礎知識」「Imidas」、「知恵蔵」を挙げてあっ
たが、その三冊ではどうにもならないと思われる内容であった。一人にひとつ
ずつ宿題が出されているそうで、一時間の授業を順に行ってゆくとのこと。も
しや、先生が授業を行わずに済ませよう、という魂胆ではあるまいか、と勘ぐ
ってしまう私であった。ま、そんなことはないだろうが。
図書館だよりをつくる。二年の間に凝ったレイアウトになり、選ぶ本の数も
増え、なかなか大変。
さすがに連休の日曜日らしく、混んでいた。
- 4月28日(金)
館内整理日。読書感想画の案内文を学校に送る。閉架の本を大がかりに異動。
- 4月27日(木)
調べものの多い一日であった。ばたばたしていた。
- 4月26日(水)
小学三年生の図書館見学に私も久々に参加。「図書館が建つ前、ここはどうなって
いたのですか」「図書館は(世界史のなかでは)いつからあるのですか」などなど、
楽しい質問がいっぱい出た。建つ前は山だったのだ。そこを崩して平らにして建てた。
なんとなく答えにくい話だよなあ、と思うが、事実だからしかたがない。彼らが楽し
く、日常的に図書館を利用してくれれば、世が少しはかわってゆくかもしれない、な
どと夢想する。
- 4月25日(火)
首長が図書館を見に来る日だというので、大阪の堺市や千葉の成田市のホームペー
ジの図書館に於ける貸席に対する回答をコピーし、館長に見せて再度説明する。また、
「公共図書館の任務と目標」のなかの『席借りのみの自習は図書館の本質的機能では
ない。自習席の設置は、むしろ図書館サービスの遂行を妨げることになる』との箇所
についても説明。館長からの理解は得られた。しかし、問題は首長であった。私は一
緒にまわらなかったのだが、館内の部屋を見るたび、「ええとこがあるじゃないか」
と言い、図書館から離れた共有スペースの日本庭園に、「ここにテントを張ってはど
うか」と言い、となかなか大変だったとのこと。結果、当初の予定通り、夏休み期間
に三十席ほどを図書館東側のスペースにつくり、テントを張ることになったそうな。
本気かな、という気がしないでもないが、ともあれそんなことになったようである。
真夏に、「勉強するところは外にだけあります。あとはありません」と言ってどれく
らいの人が納得してくれることであろうなあ。寝た子を起こすようなことになるので
はなかろうか。夏が楽しみである。
小学三年生の図書館見学。今日の子供達は静かだった。
- 4月23日(日)
日曜日らしい日曜日。お客さんがとても沢山来ました。調べものも沢山。閉架の資
料を利用なさる方も多く、歩いたり走ったりした一日でした。
「前に一度借りたことのある本なのだけれども、黄色い表紙で、あのあたりの棚に
あった。タイトルは「すまい」というのがついたと思うがはっきりしない。これだけ
では探せないか」との問い合わせ。この検索は難しい。無理かもしれない。「ほかに
何かわかりませんか」と訊く私。「書いてる人が沢山いて、女の人もいた」これでは
やはりわからない。「新しい本でしたか」「たしか、去年出た本だと思う」それなら
ばなんとかなる。タイトルと発行年、分類番号の二桁を掛け合わせると七冊に絞りこ
めた。タイトルの一覧の出たモニターを見てもらうと、「あ、きっとこの本だ」との
こと。貸出中だったので予約をしていってもらう。司書の仕事は探偵の仕事と少し似
ていると思う。
- 4月22日(土)
学習スペースを作れ、と首長宛の手紙がやたらと来るそうで(きっと大した数では
ないと思うのだが)、どうあっても学習スペースを作らねばならない、と館長と一人
の副館長が言うのでありました。過去、どのようなことがあったのかを説明したので
すが、新しく変わってきた館長はいまひとつ状況が飲み込めないようであり、副館長
も過去の、毎日二、三百人の学生がわさわさと押し寄せていた頃のことをご存じない
のでした。しかし、当然私だけでなく、ほかの職員も反対しているわけで、そのあた
りを多少考慮し、学習スペースとして使えるのは開架の外のスペースのみ、三十席ほ
ど、期間は夏休みの間だけとするとのこと。そんな案がしかし首長にとおるのであろ
うか、と心配なのだが、もし通ったとして、そんな暑いところで勉強したがる中高生
が多くいるとは思われず、当然涼しいところに逃げてくる。はじめからあまり来なけ
れば良いのだけれどもね。学習スペースをなくして六年。ようやく落ち着いてきた二
十数席の閲覧席に涼を求めて怒濤のように学習目的の学生が押し寄せはしないか。ま
た、期間限定とは言うものの、市民の要望により学習スペースをつくることになった
ということであれば、市民の要望でその期間は長くなりはしないか、涼しい室内では
どうして学習できないのだ、との声が多くあがるようになりはしないか、と不安は募
るばかり。そのあたりのことを私も他の職員も説明したのではあるが、館長と副館長
はすでに決めてしまっているのであった。わやなことになる、と私は思う。私が勉強
をしにきた中高生であれば、まず間違いなく苦情を言うことであろう。苦肉の策とは
こういうことを言うのであろうなあ。しかし、館長副館長をさしおいて、首長に説明
に行く根気もなく、できればあまり学習の学生がこないと良いな、と祈る私でありま
した。ま、万が一、閲覧スペースが埋まってしまうような事態が起きたとしたら、椅
子を置かないようにし、閲覧利用の方は受付へお申し出ください、とし、その度、椅
子を持ってゆくようにすればなんとかなるかな、などと考えてはいるのでした。そし
て閲覧が終わって帰るときにはまたお申し出いただき、椅子を事務室へひっこめるの
である。とても面倒だけれども。椅子のない中途半端に背の低い机で学習をしようと
いう根性のすわった中高生は多分あまりおらず、閲覧利用者限定のスペース確保がで
きる良い方法ではあるまいか、と私は自分で勝手に思っているのでした。学習スペー
スがある図書館で学習する中高生だらけの図書館はしかしいったいどのようにしてい
るのでありましょうか。六年前、私の勤務先はぐっちゃぐちゃでした。棲み分けは当
然していたのだけれど、言うことを聞く中高生はとても少なく、閲覧利用者は事務室
のなかの机で読んでいたりしました。これは変だ、と、議会でつつかれたり、上司に
反対されながら、また、利用者からの苦情をいっぱいうけながらも止したのです。そ
れは筆舌につくしがたいほど嫌で面倒で、こんなことならばまた学習スペースをつく
ってしまおうか、と幾度も思った仕事でしたが、三年ほどで落ち着き、去年も一昨年
もほとんど学習利用の中高生は来なくなったとのことで、ほっとしていたのでしたが。
ま、しかし、いつかはこういう日がやってきますな。愛知県内で学習スペースが全く
ないのは私の勤務する図書館だけであり、全国的にも「図書館は学校の勉強をすると
ころ」というイメージが強いのですから。このイメージが消えない限りは、「図書館
に行ったのに勉強するところがないなんておかしい」との声は永久になくなるはずは
ないもの。一館だけが力んでいても、屁のつっぱりにもならないのでした。図書館界
の問題なのか国の文化水準の問題なのか、学校制度の問題なのか民度の問題なのか。
多くのことが変わってゆかなければ、文化行政がめちゃめちゃであってもしょうがね
えなあ、などとこの頃思うのでした。私にできることはとりあえず、利用者の探して
る本を提供すること。提供するためにどうしたら良いかを考えること。日々の仕事が
どんな風なのかをホームページに書くこと。まずいことはどんなことなのか、どこが
どのように変わればまずくなくなるのかを考えてホームページに書くこと。それくら
いしかないのです。それで何かが大きく変わるかもしれない、などという夢ははじめ
から抱いてないのだけれど、ほんと、何にも変わりはしないのだなあ、としみじみ思
うのでありました。悪い方には変わってゆくだろうけれども。
- 4月20日(木)
こないだの日曜日に通信講座で司書の資格をとっている人からアンケートを頼まれ、
今度の日曜日に受け取りに来るとのことだったのでした。「はい、ではそれまでに記
入しておきましょう」と答えた私。しかし、これがなかなか大変なアンケートだった
のでした。貸出冊数、蔵書冊数などと過去五年にわたって拾わねばならず、開架部分
の面積の足し算をせねばならず、と細かな作業が沢山。今週は研修があったり、あれ
これの準備があったりしてばたばたな週であったことをすっかり失念していたのでし
た。後悔しきり。なんとか記入を終え、市内小中学校に発送する読書感想画コンクー
ルの案内文の作成作業などをしたのでした。このコンクールは市制何周年かのときに
一回こっきりで行ったはずが、やめることができないようになってしまったもので、
学校側からも止してほしいかのような話があったこともあったのでしたが、沢山の学
校の関係した業務でもあり、簡単に止すことはできないようなのでした。本を読んで
絵を描く、なんてとても大変だと思うし、学校から強制的に行うとなると本好きで絵
の苦手な子供が本を嫌いになったりしないだろうか、などと心配になったりもする私。
読書感想文コンクールもそうなのだけれど、学校も図書館もかなり大変な仕事となる
わけで、子供と本をつなぐのに良いのか悪いのかがよくわからない企画でもあり、そ
ろそろ見直した方が良いように私個人としては思います。
- 4月18日(火)
ブックポストには五百冊ほど。ま、ぼちぼち。開架の棚がぎゅうづめになっている
ところが多く、閉架にしまわねばならない。しかし閉架の棚もかなりすごいことにな
ってきていて、さてどうしようか、といったような状態。ま、閉架の本をどこか別の
場所に移すか、捨てるかしかないのだが、これはどちらにしても大変な作業。どれを
どのように選ぶのかが実に難しい。しかしそろそろ考えねばなるまい。
延滞を減らすことを考えるべきだ、と新館長に言われる。確かにそのとおりだと思
う。延滞利用者に対して、遅延料を取る、貸出停止にするといった方法がまず考えら
れるわけだが、遅延料を徴収するとなると領収書発行の手間がかかるし、その日に持
ち合わせがない場合どうするのか、また、お金を払わなければならないならば返さな
いといった無茶な利用者が増えはしないか、といった危惧がある。貸出停止をすると
なると何日延滞からなのか、累積したらにするのか、その基準はどう決めるのか、ま
たこちらも遅延料と同様、どうせ借りられなくなるのであれば返すのを止しておこう、
と考える悪質な利用者がいそうだ、などと考え込んでしまうわけである。なにか良い
手はないものであろうか。また、館内整理日にでも討議するか。なんとなく時間の無
駄に終わるような気がしないでもないのだが。
調べものの利用者が多くて楽しい一日であった。
- 4月16日(日)
さすがに日曜日である。ばたばたであった。利用者用検索端末で悩んでいるお客さ
んがとても多かった。訊いてもらえばすぐにわかる本が多い。あるいはしばらくは見
当もつかない本を探している場合もあったりするが。
何かを探しているのであろうな、と見てすぐにわかるお客さんに声をかけるとやは
り何かを探している。フロアワークは大事だな、としみじみ思った。そして私はフロ
アワークがかなり好きだ。探し物はひとつひとつ違うから、飽きないのだ。しかしな
かなか書架の間を歩きまわる時間がないのである。今日はほかの仕事があまりなかっ
たこともあってよく歩きまわることができた。
- 4月14日(金)
空いていた一日。視聴覚資料の延滞が相変わらずとても多い。電話をするとうんざ
りするような答えが返ってくる。「こないだ途中まで行ったのだが、坂を上るのがエ
ラくて(エラい=大変の意。中部以西で使われている)、帰ってきた。いつ行けるか
がわからない」と三十代女性。どうやって借りにきたのだ。「忙しくて当分行けませ
ん」などと言う奴もいる。ならば借りるな、と言いたい。一週間の返却期限なのに三
週間借りていて、「今度の火曜日じゃ駄目ですか」と言うのもいる。「駄目です。明
日にでも来てください」と言ってやる。遅延料を取ると多少ましになると思うのだが、
そのためには人手が要るのであった。
- 4月13日(木)
朝から難しい質問が沢山くる。借地借家法に関する本について質問を受け、貸し終え
てしばらくしてから、「そういえば、借家の法律変わったんじゃないかなあ」と同僚が
言う。おおい、早く言ってくれええ、貸したのは四年も前の本だったのだ。借りた人が
わかっていたので、のちほど電話をして詫びる。竹の栽培法について。中世欧州の演劇
事情について。水の濾過について。相続税の計算方法について。図書館は本当にいろい
ろなことを訊かれる。楽しい。しかし、あまり本が出ていない分野もあり、宿題にさせ
てもらった調べ物もあった。
- 4月12日(水)
ブックポストに1318冊の本が返っていた。朝からばたばた。
脳細胞がだいぶ死んでいる。ある画家の名前が出てこなくて、ううううむ、とうなり、
ある小説の中にその画家の名があったことを思い出し、閉架の本で確認したのち、その
画家の関連の本を見つけた。質問にかする本であろうとの予想ははずれていなかったの
でひとまずは安心。日本十進分類もかなり忘れているし、やはり二年は長かったと思う。
歳のせいもあるかもしれないけれども。
水曜日だというのに割と混んだ。貸出3191冊、返却4362冊。
新刊の見計らいをする。楽しい作業。しかしなんだかこの頃、「この本はどうあって
も図書館で買っておかなくてはいけないぞ」といった感じの本が減っている気がする。
少し淋しい。
- 4月9日(日)
日曜日にしてはお客さんの少ない日だなあ、と思っていたら、帰り際に沢山の人。
少しばたばたしました。閉架の本がどんどん増えているため、利用も当然増えていま
す。増えたなあ、と思うのが、住宅地図の利用。ま、図書館を利用してもらうのは悪
いことではないけれど、住宅地図を見るためだけにいらっしゃる人というのもなんだ
かなあ、という気分にはなるのでした。
ある本が、別の本と同一か否かとの問いに、「はて」、「さあ」としか答えられな
かったのでした。四十年ほど前に文庫本で出ていた本。五年前に同じ書名、著者名
(団体著者)、出版社でハードカヴァーで出ている。どちらも所蔵しておらず、J-BISC
にも同一かどうかの記載がない。同一名称の別団体の可能性があるし、同じ団体が四
十年経って、同一のタイトルの別の本を作ったかもしれず、結局わからずじまいだっ
たのでした。
貸出3632冊、返却3634冊。
- 4月8日(土)
土曜日にしてはお客さんの少ない日であった。利用者用端末は以前と変わっておら
ず、タイトルや書名がしっかり正しく入っていないと決して探している本にはたどり
つけないのでした。時折、検索項目をこっそり見にゆき、探せないであろうな、と思
える場合に、「よろしければ、こちらで探しますよ。この機械では、テーマなどで探
すことができませんし、沢山拾ってしまうと、絞り込むこともできないものですから」
と、カウンターに来ていただき、私が検索をします。なかには、「なんとかについて
の本を探しているんだ」とすぐにテーマを言ってくださる方もいらっしゃって、そん
なときには直接その分類の書架まで案内をするのでした。見ていないだけで、実は本
を探している人、悩んでいる人はとても沢山います。そうした人をいかに早く見つけ、
うまく声をかけるか、このあたりの仕事はとても面白いのでした。難しいのだけれど
も。
- 4月7日(金)
新刊の選書、リクエスト本発注など。リクエストは相変わらず多い。リクエストの
幅も広がっているようだ。
いろいろな人が、「もどっていらしたのですね」「ようやくもどれましたね」と声
をかけてくださる。ありがたいことだ。
- 4月6日(木)
相変わらず延滞利用者が多いようである。視聴覚資料の延滞督促の電話をする。こ
の時間はもったいないよなあ、と思う。
電算システムの変わったところについてエンジニアから説明を聞く。世の中はあれ
これと変わっているのだなあ、としみじみ思う。
- 4月5日(水)
水曜日は割と利用者が多いようだ。昭和の初めの頃の物の値段を知りたいとのレフ
ァレンスを図書館に勤めて十年になる司書が受けて悩んでいた。「明治大正昭和値段
の風俗史」を見れば良いではないか、と言うと、「そういえばそんな本がありました
ね」などと言うので、「あれは基本的なレファレンスツールだ。忘れてはいけない」
と注意しておいたのであった。まだそれほどボケてはいない私であった。
- 4月4日(火)
ブックポストへの返却が減っているとのこと。なぜだろう。1000冊もないほど。
これならば楽である。3人の臨時職員の勤務時間が30分早くなったとのことで、そ
のおかげもあって書架が早く整理できた。
市報の締切が今日までとのことで、それならば私の手が空いているから、と市報
に載せる本を選び、原稿を書く。以前はファクシミリで送っていたが、メールで送
れるようになっていた。
高額の見計らいの本が一般書担当の間に回されていて、「購入する」の欄に三人
チェックを入れていた。しかし、私は類書がある、と思った。環境行政についての
本である。訊いてみると彼らは、「類書はないと思います」「検索もしてみたので
すが」などと言っていたのであるが、本棚を私が見にゆくと、間違いなく似た本が
ある。私もまだぼけてはいないな、と少し安心する。類書は少し古かったので、見
計らい本は購入することにしたのだが、そうした本があることを知っているかいな
いかが、利用者からの質問に答える際に大きな違いとなるのである。一冊ずつの性
格を少しでもいいから把握する。司書の仕事はその積み重ねである。
- 4月1日(土)
図書館に戻った。あれこれ聞くとめまいのしそうな話もいくつかあるようである。
市のトップが、市民から意見を聞くため、投書箱を設けているのだが、そのなかに
学習室をつくってほしいとの要望がいくつかあり、「つくれ」という話が出ている
とのこと。ほかにも状況の説明を聞かず、頭ごなしにいくつかの話を持ち込んでき
ているらしい。図書館に対して市民から出てくる話は昔から変わらず、「延長開館
をしてほしい」「年中無休にしてほしい」「学習室をつくってほしい」である。可
能にするためには職員を増やすか、建物を造り直すかをしなくてはならないわけだ
が、そうなってくると次に出てくるのは窓口に出ているのは司書でなくても構わな
い、本は多くなくても構わない、といった話ではなかろうか、などと先を読んでし
まうと憂鬱になる。さらにいろいろなものを「値切れ」との指示が出ているそうだ。
役所が値切ることは良いことである。大義名分を持って値切ることができるのが役
所の仕事の楽しいところだと私は思っている。しかし、構造的に安くはならないも
のを理由も訊かず値切れ、と言われては大変なのであった。将来の見通しは明るく
はなさそうである。
久々に窓口に出た。いくつかレファレンスもあった。日本十進分類を忘れずにい
た私であることに気づいた。「ありがとう」と利用者が言ってくれる窓口はやはり
良いな、と思う。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]