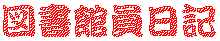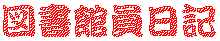
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 3月24日(火)
今日、突如として市民課への異動がきまった私である。司書として役所に入庁して14年。「司書は土日が勤務であることははじめからわかっているはずだ」などと上司に言われたりしたものである。去年3月4日に行革の説明会で質問した際に、「仕事に支障をきたすような専門職の異動は行わない」との回答を得たが、今回私の替わりに入るのは図書館で一度も仕事をしたことのない、通信教育で司書資格をとった職員である。ぎりぎりの人数しかよこさない当局はぎりぎりの状態のまま、14年勤務した私と未経験の職員を異動させて仕事に支障をきたさない、と考えているらしい。彼らにとってはサービスの水準などどうでもよく、おそらくは職員の疲労などもどうでもよいと思っているのであろう。「専門職の異動は今のところ考えていない」とも去年言ったはずである。役所の職員は異動先の希望を出すことができる。専門職の我々は前提として異動がないことになっているため、希望先を出すことはない。希望が受け入れられるか否かはともかく、これは平等ではないではないか。出先の人間のことなど少しも考えていないことは明らかである。専門職として採用しておいて異動させるのは道義に反している。異動があるのであれば、入庁試験を受ける以前に知らせておくべきではないのか。例えば市民病院の医師がいきなり事務職に異動されることがありうるか。建築士を事務職に異動することがあるのか。司書を軽く扱っているとしか思えない。はじめから司書として採用しなければ良い。そうすれば私は別の仕事をしていたことであろう。役所の空気をしばらく吸ってくると勉強になると上司は言うが、その間の出版状況、電算ツールの変化などについて知ることが困難となるわけで、それは司書として大いにマイナスである。役所の雰囲気が良かろうが悪かろうが、図書館員にとって無関係である。横のつながりができる、というが、一緒に仕事をしないとつながれないような人間とつながらないと運営できないような町の状態自体に問題があるとは考えないのであろうか。曖昧で判然としない理由だけで役所の空気とやらを吸わねばならぬとは情けないかぎりである。
- 3月3日(火)
ふと気がつくと3月。1月半ばに風邪をひいてぼろぼろになってしまい、この日記を書かずにいたところ、全然再開する根気がなくなってしまっていた私である。実際のところ、そろそろ日記を書くのに飽きている。ページの刷新をしようかな、と考えはじめてもいる。そんなわけで、この日記、もうしばらく中断することにします。私は生きてはいますので、少数の愛読者の方はご心配なきよう。
- 1月16日(金)
なぜか昨年の1月16日は混んだので、今年も混むのではないかとびくびくしていたのだが、割と空いていたのであった。ほっ。
受付のローテーション作成と新刊書の発注業務。
- 1月15日(木)
成人の日である。混む。受験勉強の追い込み時期のせいか閲覧席に受験勉強の若者がいる。事情を説明して席をあけてもらおうとするが、納得してもらえないので、事務室に呼んで説明をする。雨降りに図書館に勉強に来て、なぜ席を使っていけないのかという疑問はもっともな気もするのであるが、ひとりだけ認めるわけにはいかないのである(「一図書館員から見た日本」第四回 参照)。三年前、閲覧席を閲覧利用以外不可にしたときの利用者との厳しいやりとりを思いだしてしまい、少し参る。
登録者多し。貸出冊数2999冊、返却冊数2078冊。貸出が返却よりも900冊以上多かった。利用する人はどんどん増えているのであるが、職員は増えず、予約連絡の仕事を軽減しようと、電話での連絡を葉書にかえたい、と葉書を予算にあげたら、利用者から葉書代を徴収すればいいと言われ(そのやりとりに人員がいるし、そもそも図書館法に反している発想である)といった状況に暗澹とした気持ちになる。
- 1月14日(水)
月、火と休みだったため、平日の割に混んだのであった。貸出2146冊、返却2787冊。
古い郷土資料の複写の利用者で、家で製本したいからきれいにとって欲しいとの要望。私の勤務先では貴重図書は綴じ目が傷まないように上からスキャンして読みとるコピー機でとっているのだが、デジタル補正をしているため、真ん中に合わせると左右の文字が大きくなったりするし、左右に合わせると真ん中の文字が小さくなったりするわけで、きれいにはとれない旨、説明する。気持ちはわからないでもないが、幾度かとり直しをしながらの説明で時間がかかり、ほかの利用者を待たせていることもあって少しいらいらしてしまった。職員数に余裕が欲しいとしみじみ思う。
- 1月11日(日)
休み明けの最初の日曜日とあって、天気が悪いのにもかかわらず、ばたばたであった。貸出冊数4455冊、返却冊数4289冊。
小学生の調べもの、中学生の調べもの多し。大学生も多し。大学の教科書として使っている本を借りに母親と一緒にやってきた女子学生もいた。今までいったいどうやって授業を受けていたのであろうか。類書でもいいとのことであったが、テストやレポートであれば、その先生がどう考えているかということが重要になるであろうし、雑誌の論文を読まなければどうにもならない中身であったので、その旨伝える。親は学費がもったいないとは思わないのであろうか。学費を出して教科書代を出さないはずはなく、この女子学生の独断で買わなかったのではあろうが。
- 1月10日(土)
第二土曜日である。利用者多し。貸出3956冊、返却3454冊。
大学生のレファレンス、多し。大学図書館で調べた方が早いであろうと思われるものが7割ほど。
行燈のデザインを知りたいとのレファレンス。過去、民俗学関連では風鈴、提燈に苦労した記憶があり、今回も難航するであろうと思われたが、やはりあまり良い資料がなかった。昔どこにでもあった、こわれやすい、安価なものは調べにくいようだ。
- 1月9日(金)
来週分の受付のローテーション表を組むみ終えてほっとしていたら、土日の臨職さんの一人が病気で明日明後日と出られないとの連絡があり、明日と明後日の三交代のローテーションを組み直す。
コピーとレファレンス多し。大学生がよく来る。
新刊図書の発注業務をする。
- 1月8日(木)
久しぶりにネクタイをするのを忘れて出勤する。ごまかすために普段は暑くて着ていない事務服を着る。
郵便番号プログラムの修正にSEが来る。しかしあの7桁への変更というのはどれくらい郵便局にとって便利になるのであろうか。手書きで手紙を出す人間にとっては迷惑この上ないのだが。また町によって郵便番号の増え方がまるで違うのはどうしてなのだろうか。人口がそろそろ5万人になろうという隣町の郵便番号は5種類、3万5千人ほどの町の郵便番号は50種くらい。なんなんだろ。
暮れに新聞社に送っておいたオンラインデータベースで新聞記事を検索したのちにプリントアウトやフロッピーへのコピーをしてもいいかどうかの問い合わせ文書に対して朝日新聞社から早速回答が届く。紙へのプリントアウトは良いが、データを落としたディスクからフロッピーへのコピーはいけないとのこと。プリントアウトしたものを一部利用者に渡すことも構わないそうで、図書館としての運用が楽になる。
- 1月7日(水)
小中高校の始業式である。
午後、大学生などからのレファレンスが相次ぐ。、「妙好人浅井才一」についての本、と聞かれ、妙好人を号だと思ってしまって恥を書いた私であった。世の中に知らないことは実に多い。
今日もまた視聴覚資料の督促電話。感じの良い延滞利用者(笑)が多かった。にこやかにしなくてもいいから、遅れずに返してもらいたいものである。
- 1月6日(火)
今日から開館である。混む。小中学生の宿題、大学生の宿題、男子大学生の宿題用資料を探す母親などレファレンスも多数。
読書感想文コンクールというのをかれこれ30年行っていて、その文集というのを毎年出しているのだが(30年続いていると止めたくても止められないし、担当部署を替えてもらうことも難しいらしく、このコンクールに要する人員が多いだけにここ数年、実は悩みの種ともなっているのであった)、ゲラが刷り上がってきたので、職員で手分けして受付の合間に校正をする。
視聴覚資料の延滞督促の電話をかける。昨年末までの返却期限になっているのに返していない人が100人ほどもいる。中に、「図書と同じ期限ではありませんでしたか」という人がいたので、「視聴覚資料は一週間の期限ですので、12月17日に借りてゆかれたビデオは24日が返却期限です。図書は28日から年末の休みに入ったため、期限を長くとっていたのですが」と答えたところ、がさがさとなにやら確認をして、「確かに図書と同じだと言われました」と言うので、年末の図書と視聴覚資料についての返却期限を淡々と再度説明したら、「しかし私は、図書と同じですねと確認をした。その紋切型の話はどういうことですか」と怒る。「返却期限の紙をこちらが渡さなかったのでしょうか」と聞くと、もらっていない、とのこと。過去13年間にはなかった例ではあるが、丁重に謝る。いいわけめくが、督促電話を紋切型でかけ、利用者の話をすぐには信じないのには理由がある。「図書と同じ期限だと思っていた」と答える利用者は実に多い。貸出券を発行する際に期限が異なることを説明し、そう書いているパンフレットを渡し、カウンターに返却日のカレンダーを置き、貸出の時に返却日を書いた短冊状の紙を渡しているにもかかわらず、である。その数は年間数十人にものぼろうか。中には返却日を知った上でそういう人間さえいる。督促の電話をすると、「暮れに休みだったので返しにゆけなかった」とか「雨が降っていていけなかった」だの「風邪をひいていたので」という答えをする人がいたりもする。返却期限は遥か前であるのに、である。今回怒った利用者の気持ちもわかるし、図書館のミスであったとおっしゃるのであるから、そうであると信じた上でさらに言うのだが、年末の返却期限変更については何カ所かにポスターを貼ってお知らせしており、貸出カウンターに返却期限の卓上カレンダーを表示してあり、1点であれ貸出の際に期限のスタンプを押した短冊状の紙を渡しているはずなのである。この紙を渡さずにいて、「図書と同じ期限ですよ」と職員が言ったとおっしゃるのであるからそうであったと思うしかなく、そうであったとすればこちらの大きなミスなのであるが、貸出をしたのが平日であり、その日は経験の長い職員がカウンターに出ていたことでもあり、あまりに珍しいミスなのでついつい疑ってしまったのであった。多分今までに一度も延滞をしたことのない利用者なのであろう。申し訳ないことをしたと思う。今までも考えられないようなミスは幾度か起きており、可能性のあることはすべて図書館の側を疑ったうえで、利用者に接しなければならないな、としみじみ思ったのであった。
帰宅して夕刊を見ると安江良介氏の訃報。二年前の滋賀県での図書館の集まりで、安江氏と前川恒夫氏とのシンポジウムにおいて安江氏が、「これからは司書が現場から情報を発信していってほしい」といった内容の発言をしておられたことがきっかけとなって私はこのホームページを開いたのである。実に知的でリベラルな人であるとの印象を持った。一目でそう思えるような人を私はそれほど知らない。出版界は実に惜しい人を亡くしたと思う。ご冥福をお祈りいたします。
- 1月5日(月)
御用始めである。ブックポストへの返却本は割と少なく1200冊ほどであった。
書架整理をし、としょかんだよりを作り、受付のローテーション表を作る。延滞の督促電話もかける。この頃は変な電話機が多い。コール音のあと、「お呼び出しいたしますので、しばらくお待ちください」などと電話機が言うものがあるが、受ける先が自分に対して敬語を使うのはおかしいのではなかろうかと思う。おまけに「FAXの方は送信してください。電話の方はおかけ直しください」などと言ったりする。お電話ではないのである。その上、電話代10円は確実にかかっている。変だ。留守番電話機能付きFAXって、そんなに誰にも要るものなのだろうか。世の中がどんどん失礼になっているような気がするのは私だけなのであろうか。と、年のはじめから腹を立ててははいけないのである。
星新一さんの訃報に衝撃をうける。
- 1月1日(木)
あけましておめでとうございます。
年末年始の休み中、ずっとブックポストに返ってきた本をほったらかしておくとブックポストがあふれてしまうため、交代で本をかきだしにゆくのであるが、今日は私が当番であった。なかなか沢山返ってきていたが、前回の当番の人の方がずっと多かったようであるので、今年は運がよかったと思った私であった。
- 12月27日(土)
今年最後の開館日。私は午後から宴会があったので「うらぎりものぉ」などと言われながら、早引けをしたのであった。
- 12月26日(金)
今年最後の館内整理日。机の上を片づけたり、来年のとしょかんだよりを作ったり、書架の整理をしたり、資源ゴミをまとめて出しにいってもらったりした。
- 12月25日(木)
冬休みである。混む。
利用者が、学生にアンケートを頼まれたが、その学生がいなくなったので用紙を預かって欲しいとカウンターに言ってきた。ほかの職員に尋ねたが、アンケートをとっていることを誰もしらない。中身は真面目な学術的な調査なのだが、無断で館内でアンケートをとるのは非常識である。しばらくして学生を発見。いかにも真面目そうな学生である。館長に注意をしてもらう。無断で建物のなかでアンケートをとってはいけないとは考えていなかったらしい。どこか変だ。匿名のアンケートではあったが、プライヴァシー保護のことなどを考えると図書館内でのアンケート調査は問題がありそうでもあるが、とりあえず今回は許可をしたのであった。今後もそれほど例はないと思うが。
- 12月23日(火)
祝日は日曜日ほどには混まないのであるが、冬休み初日ということもあって小中学生が多い。まだ調べものの宿題について訊かれはしなかったが、なにやらこつこつと調べていた中学生がいたから、やがてたくさんの中学生がやってくることであろう。
閉架の資料を出す回数が多い一日であった。閉架があることを知っている人が増えているのは良いことである。知らなければ開架だけ見て、古い本がないのだな、と思われるのであるから。
- 12月21日(日)
28日から休みなので、今年最後の日曜日。さすがに混む。レファレンスがめちゃめちゃ多かった。
- 12月19日(金)
郵便番号がなぜか7桁になる為、コンピュータのプログラムを替えねばならない。
図書館の所在する市内の町名はすべてコード化してあったので、割と簡単に替えることができるのだが、隣町は町でひとつのコードしか作ってなかったりしたのでややこしい。いままでとは異なった規則性で郵便番号がつくられているところもあったりして、コードを沢山つくらないと対応できなかったりする。
ぼろぼろになった本のうち、買い直しができるものを発注する。
- 12月18日(木)
カウンターに乳幼児を乗せる親はここ一二年で急増している。いずれはそちらが常識になるのではないかという気がする。女子高生売春が援助交際と名をかえ、さしてマスコミが非難もせずにほったらかしている風潮から考えれば何が常識になったとて不思議ではない。おむつを直接カウンターにのっけていた母親がいたのに呆れたが、
そこを職員があとから拭けばよい、あるいは赤ん坊の尻は清潔なのである、というのが常識になるのかもしれない、と考えて腹を立てないようにする。
延滞督促葉書をコンピュータで打ち出しているのだが、プログラムに修正してもらいたい箇所があったので依頼。なおってきたら、ほかの箇所に影響が起き、そこをなおしてもらい、いざ葉書を打ち出すと名前のあとの「様」が抜けていた。一カ所なおると一カ所壊れるのはなぜだ。
- 12月17日(水)
比較的空いていた一日であった。
オンラインデータベースで新聞記事を検索し、ダウンロードしたものを利用者に見てもらい、必要な号の新聞を出しているのだが、記事データを直接プリントアウトして利用者に渡してはいけないのかどうかを各新聞社に問い合わせる文面を考える。図書館と著作権の問題は今後ますますややこしくなってゆくことであろう。
- 12月16日(火)
休んだ職員が多かったので、ばたばたの一日であった。
ブックポストへの返却は約700冊。片づけに午前中いっぱいかかった。貸出は1871冊。なかなか沢山の人がきたのであった。
- 12月14日(日)
さすがに日曜日である。ひどく混んだ。
新聞のコピーの人が多かった。古い新聞は穴を四つ開けて、プラスチックのパイプを通して綴じてあるので、綴じ目の近くをコピーするときには全部はずさねばならず、大変なのである。もっと古い新聞であればマイクロフィルムがあるので楽なのだけど。
レファレンスが多くてめまいがおきそうになるほどであった。年の瀬である。
- 12月13日(土)
朝、プリンタの修理の人が来る。本当はCPUボードを交換したほうが良いのだが、飛んでしまったシステムを入れ直したら、とりあえず動いたので、しばらくは大丈夫とのこと。
プリンタがなおった直後、J-BISCのデータをプリントアウトしてほしい、との依頼があった。プリンタがなおらなければ出せないところであった。あぶないあぶない。
レファレンスがとても多い一日であった。次から次へと難しい質問を受け七転八倒していた私。今日もまた大学生が多く、「雑誌記事索引」というものの存在、閉架書庫が大学図書館にある、といった説明をした。
- 12月12日(金)
朝、「ネットワークプリンタの液晶が表示されない」と同僚が騒いでいた。今日一日の不幸のはじまりであった。
早速電算メーカーに電話をすると、営業担当が出張に出ていて、プリンタの保守会社の連絡先がわからないという。朝のミーティングで、プリンタが使えない旨を職員に通達。が、よく考えてみると、私だけが今日中にプリントしなければならない仕事があったのであった。再度電算メーカーに電話。「かわりのネットワークプリンタを持ってきてもらうか、ほかのプリンタに接続して使えるようにできるのかを確認して欲しい」と言うと、「私の一存では答えられないので相談して連絡をする」とのことなので、連絡を待つと、「プリンタのメインテナンスは依頼しました。来週の頭には行けるとのことです」と営業のひとから呑気な電話。「先ほど伝えましたように、今日中に打ち出したい書類があるので、かわりのプリンタを持ってきていただくか、現在あるほかのプリンタを使えるようにする手段設定などを教えていただきたい」と言うと、今日中には無理だ、といったような答えをされたので逆上した。「今年までは保守料が無料であるからともかく、来年からは高い保守料を払うのである。どこも壊れなければドブに捨てるような金である。今日、すぐになんとかしてもらいたい、と言っているのに、こういう対応をするのが保守であれば、来年から何のために金を払うことになるのかわからない。今日のうちにプリントできるようにするためにはどうしたら良いか、を考えるのがあなたの仕事ではないのか」と言う、と、「また連絡します」との答えであった。落ちついて考えると分館のプリンタはパラレルポートでスタンドアローンで繋がっており、本体からの帳票打ち出しはシリアルポートに繋がっているわけで、本館でも同様の接続ができるわけである。再度電算屋に連絡をし、ドライバがあるが、できるだろうか、と尋ねる。「できるはずだ」との答え。が、ケーブルがない。パソコン屋にケーブルを買いに出かける。接続し、ドライバをインストールし、プリントしようとする。だが、プリンタはうんともすんともぴーとも言わない。設定をあれこれかえてみるがだめ。Win3.1用のドライバを3.1ののっかってる機械にインストールしたのである。ケーブルだって新品だし、マニュアルをしっかり読んでいるというのにどうなっておるのだ。京セラのなんとか6550というプリンタである。電算屋に電話してSEに尋ねる。dosのコマンドでプリントしようとするが、やはり、プリンタはなんともいわない。恐ろしく無駄な時間をくってしまっているのである。「もしかしてケーブルが不良品だったりして」と私が言うと、SEが、「試しに95マシンにつないでみましょうか」と言う。ラップトップの95マシンを持ってきて、ドライバの設定をし、テストプリントをしてみると、印字される。どうなっておるのだ。「ならば、これでなんとかなりますね」とSEが言う。そりゃ、3.1で作った文書をフロッピに落とし、95マシンに入れてプリントすればいいわけだが、めんどうくさいではないか。ま、ネットワークプリンタがなおるまでの辛抱ではあるが、3.1マシンのドライバはどうなっているのか。来週また考えましょう、とのことで、一応の解決がついたのは終業時間の一時間前であった。コンピュータのトラブルがひとつあると、とても大変である。
- 12月11日(木)
昨日とは違い、利用者の少ない一日であった。
が、またしても大学生の宿題多し。大抵、「学校の図書館の本はもうみんなが借りちゃっててないんです」と言うのである。閉架に貸出のできない専門雑誌があることを大学は説明しておきなさい、と言いたい。
パンフレットが机の上にたまったので片づける。本は沢山出版されているのであるなぁ、としみじみ思う。
「世界大百科事典」のCD-ROM版の案内に日販のひとが来る。プリントアウトしたものを利用者に渡すことはできるのだろうか、と訊くと、また聞いておきます、とのこと。いずれにしても図書館でCD-ROMを購入する場合、沢山考えねばならないことがあるのだが。いずれ、それについては改めて書こうと思う。
- 12月10日(水)
朝、ブックポストに返っていた本は約1300冊。電算で返却処理をし、書架に戻す。
休館日あけということもあってか、平日なのにかなり混む。先週と同じく、大学生の宿題多し。またしても雑誌論文を読まなければどうにもならない英文科の学生のもの。
- 12月7日(日)
他市町の登録者多し。図書館のある町の人はその町の図書館を沢山使って、要望を出していったほうが良いと思うのだが。
雨降りの日曜日とあって、ものすごい人。貸出返却とも5000冊ほどであった。入館者は1600人ほど。
大学生がレポートのタイトルをそのまま持ってきて、それに関する本はないか、という質問が2件。大学図書館の使い方について、雑誌論文というものがあるのだ、といったことについて、大学で教えておいてもらいたいと本気で思う昨今である。これって、しかし私もどこかで習ったかなぁ。たまたま古本好きで、雑誌まで(マンガだが)集めてたりしたので、雑誌に載っても単行本にならないことはよくあることである、と知っており、単行本を読むよりも、テーマに関連の深い雑誌論文を数多く読んだ方がレポートが書きやすいことに気づいたのだが、誰かに教えてもらったわけではないように思う。雑誌記事索引というものがあることについては先輩に教えてもらったような記憶があるが。調べる、という行為にはある程度の知識が必要だ、ということを調べ慣れている人は案外忘れているのではないだろうか。
- 12月6日(土)
昨日病院にいったおかげで、鼻水はなんとか垂れないようになった。
空くときと混むときの差が激しい一日だった。がらがらだなぁ、と思ってると、立て続けに登録の人が五人やってくるわ、レファレンスとコピーの人がくるわ、貸出返却に列はできるわ、とめちゃめちゃな状態になったりするのである。
図書館の新聞を持って男子便所に入ったのを見た、と臨職さんが言うので、男子便所に入ると、時すでに遅し。ドアはしまっており、中からうなり声が聞こえている。外から、「新聞を返してくださぁい」と叫ぶわけにもいかない。出てくるのを待ち、「図書館の新聞をトイレに持ち込まないでください」と注意すると、「え、どこかに書いてありましたか」と彼は言ったのであった。「常識で考えてください。沢山の人がご覧になる資料ですよ」と叱る私。いろんな人が世の中にはいるのである。
「印旛沼の干拓のことが出てくる、二宮尊徳の出てくる、水野忠邦も出てくる時代小説をこないだ名古屋の本屋で途中まで読んだのですが、題名をはっきり覚えていないし、著者もわからない。出版社もいつの本かもわからないのですが、図書館にはありますか」との質問を受ける。時代小説のマニアが職場にいない為、残念ながらわからないまま終わってしまった。どなたかご存じでしたら、ご一報ください。
- 12月4日(木)
風邪をひいてしまって、鼻水がおちてきそうで、大変なカウンター業務だった。マイティッシュをカウンターの内側に置いて、利用者が来ない隙に音を立てずに鼻をかみ、ゴミ箱に入れた大きな古封筒に使用済みティッシュを捨てるという作業の繰り返し。利用者が多くなかったので助かった。新館開館の日に鼻水が落ちてきて困った記憶が蘇ってきた。幸い鼻は落ちなかったが。
近隣図書館の集まりが私の勤務する図書館であった。私は出席しなかったので鼻水をすすりながら発言することにならずにすんだ。
- 12月3日(水)
パンフレットが机に山積み状態となっていたので、朝から昼までかかって、一通り目を通す。パンフレットは一日平均20枚くらい来るのではあるまいか。ほおっておくと、文字どおり山となるのである。頭がくらくらしてきたところで昼休み時間となる。
書道関連の見計らい本の会社の人が来る。和綴じの良い本のパンフレットと現物を見せてもらったのだが、和綴じの本は背にタイトルがなく、また本自体に腰がないので、立てて置いておくとへにゃへにゃになってしまう。開架では扱いに困るので、閉架に入れておくしかないのだが、その資料があることを利用者に知ってもらわねばならないわけで、買っていきなり閉架に仕舞うのもどうかな、とあれこれ悩む。しばらく検討することにする。内容ではなく形態で、図書館むきでない本というのがあるのである。
比較的利用者の少ない一日であった。
- 12月2日(火)
朝、ブックポストに返ってきた本と一昨日の返却本を書架に戻す。全部で3,000冊ほど。
平日なのになかなか混む。
出版社の営業の人が新しく出版される本の見本を持ってくる。CDとセットになったもの。視聴覚資料の貸出期間は1週間、本の貸出期間は2週間なのだが、本とセットになっている視聴覚資料は2週間、貸出をしている。が、本と一緒に開架に出しておくと、CDはすぐに盗まれてしまうため、カウンターの中に置いてある。その種類が増えてきて、なかなか大変なことになってきてもいる。今回の見計らい本のセットのCDのうち、3割ほどはまるで同じ録音のものをすでに所蔵しており、2割ほどは他の演奏家の同じ曲のCDがあるため、購入を見合わせることにする。今後、CDやCD-ROMと本がセットになったものが沢山出版されることになるだろうが、図書館で、どのように貸出をしてゆけばよいかは、なかなか頭の痛い問題である。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]