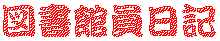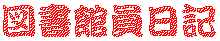
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 11月30日(日)
休んだ職員が多く、大変であろうな、と予測はしていたのだが、利用者がいつもより沢山来たので、てんやわんやの大騒ぎであった。貸出5152冊、返却4797冊。近所の大学生に宿題が出たらしく、新聞のコピーが多い。古い新聞はプラスチックのパイプを使って綴じてあるため、綴じ目に近い部分のコピーが必要な場合はその綴じをはずさねばならないのだが、これがなかなか時間がかかるのである。
登録者も多く、レファレンスも多かった。何をしていたのかわからないうちに過ぎたような一日であった。
- 11月29日(土)
今週は職員の一人が体調をくずし、読書感想文コンクールの審査会があり、一人が長期の出張に行き、さらに今日は講座とお楽しみ会があったりしたので、一週間分の仕事が終わっておらず、土曜日だというのに残業をしたのであった。
土砂降りだというのに、利用者は多かった。この頃、本の入っている本棚に凭れて座って通路で本を読む子供が多い。そのたび、椅子があるから、そっちで読んでね。本に凭れると本が悪くなるよ、と注意にゆく。体力が落ちているのだろうか。
本の扱いがどんどんひどくなる昨今ではあるが、今日はすごいのを見た。絵本コーナーで兄弟と思われる幼児が二人。絵本で雑巾掛けをしていたのである。一冊は表紙が取れかけている。すぐ横に母親がいる。呆れながら、「本が傷むから止めようね」と、子供に言い、母親に、「お子さんを見ていてくださいね。本は大勢の人が読むのだから大事にしてくださいね」と注意。この母親、どういう育ち方をしたのだろうか。
- 11月28日(金)
館内整理日。午前中、ミーティング。
午後から市報に載せる新着案内ととしょかんだよりに載せる新着案内の原稿を書く。両方で50冊ほどの本を選ばねばならず、大変な作業となった。もう少し早いうちに選んでおけばいいのに、締切直前まで手をつけなかった報いである。
カウンターのローテーション表を組む。昼を三交代でとらねばならない日が多く、面倒であった。
- 11月27日(木)
気がつくと、この日記をつけはじめてから一年が過ぎていました。ずっと読んでこられた方はそろそろ飽きてきてはいないでしょうか。私は少し飽きてきたので別の企画を考えようか、と思っていたりします。まだ頭のなかだけですけれども。ご愛読、ありがとうございます。
机の上に郵便物がたまっている。とりあえず早く処理をしないとまずそうなものと、しばらくほおっておいてもよさそうなものとを選り分ける。
利用者、多し。難しいレファレンスがあった。市内のとある池のなりたちについての調べもの。古地図をおってゆくと江戸時代中期にはすでにある。それ以前にため池として掘られたものか自然の池か。市誌にも記述はなく、論文も見あたらない。念のためにと古文書目録を見てみたが、関わりのありそうなものは残っていない。一時間ほど調べたが、結局不明のままであった。
- 11月24日(月)
本来の休館日の月曜と祝日が重なった日は比較的空いているのだが、今日はなかなか来館者が多かった。
三歳くらいの幼児が絵本を読んでいる。隣に母親と父親がいる。なにげない普通の光景である。が、幼児がどのように本を扱っているかを見ていない。ページをちからいっぱい折り曲げながらめくる。本の上に肘をのせ、全体重をかけて読んでいる。その力でページが本から剥がれる。恐らく借りていって家でもそうしているのであろうし、こういう家庭は多いのだとは思うが、見てしまった以上、ほおってもおけず、注意にゆく。「ページをめくるときには角を持ってゆっくりめくるようにしてください。折れ目がつくと、そこから破れてきます。また、本にお子さんの体の重さが乗ると真ん中から割れたり、ページがはずれたりしますので、できればお子さんが読むのを見ていていただくか、お母さん、お父さんが読んであげるようにしてください」「どうもすみませんでした。気をつけます」礼儀正しい母親であった。が、そのお母さん、子供が読むのを見てはいるのだが、本への荒い扱いに対して注意をしない。混んできたことと、二度も注意にゆくのもどうかと思ったので、そのままでいると、帰り際、「さきほどはどうもすみませんでした。○○ちゃんも、ごめんなさいしましょうね」と、実に丁寧に詫びてゆかれた。良い人なのである。が、本を大事にするとはどういうことなのかがわかっていない。そうした指導までが必要な世の中になっているのであろうか。
昔、私が子供の頃は本や新聞をまたぐと当然叱られたのだが、最近の絵本コーナーでは子供が絵本を踏んづけて走っていても注意しない親が増えている。床に本を置いてねそべって読む子供の隣に親がいて、平然としていたりもする。本の荒い扱いを注意すると、それならばこういう読み方はいけない、と書いておいてください、と言った母親もいた。なぜいけないのかがまるでわかっていないのである。本を書いた人のために、本をつくったひとのために、あとから借りる人のために、本を大事に扱うのは当たり前のことだ、と考えている人が減ってきている。哀しいことだと思う。
- 11月23日(日)
日曜日はばたばた。レファレンスも多い。
大学生のお母さんが「ボードレールについて書かれた本を借りてきてくれ、と頼まれた」とやってくる。ボードレールも墓の下で泣いているのではあるまいかと思う。いったいその大学生はなんだって大学へ行くのかな。アルバイトをするためか遊ぶためか。私も、よく勉強した大学生だったわけではないが、「ボードレールについて書かれた本」をひとに借りてきてもらうという発想はなかった。家庭や文部省は、まずなんのために大学にゆくのかということを考えられる人間を育てなければならないのではないのか。この大学生がなんにも考えていないであろうことは誰の目にもあきらかだと私は思うのであるが、この大学生が特別な大学生というわけでもなさそうな昨今なのである。もうじきこの大学生は社会人になるのである。こういう社会人がいっぱいになった世の中はさぞかし良い世の中であろうなぁ。狂った国だ。
- 11月22日(土)
さすがに第4土曜日である。雨降りだというのに混む。
以前からそうであるが野放しの幼児が多い。カウンター内に入ってくる子供(個人情報の記載された申請書などもあるのだから持っていかれたり、破られたりしたら大変である。注意してるから今のところないのだが、このごろの子供は動きが早くておっかない)や、利用者用端末の置いてあるカウンターに乗っかって遊んでいる子供がいたりする。パトロールの必要があるかもしれないが、不景気で職員は増えないのである。乳幼児をカウンターに乗っける人は増え続けている。恐らくは車が増えたせい。以前、主婦は乳幼児を負ぶうか乳母車に乗せて歩いてあちこちに出かけていたため、乳幼児を負ぶい紐なしに歩かせたり、持ち上げたりしなかったのだが、車のベビーシートに乗せてくると、負ぶい紐やベビーカーなしであちこちに行けるようになるのである。荷物をなんとかしたり、鞄の中身を出すときに机の上に赤ん坊を乗せることが当然のようになっており、どこでもそうした光景を見かける。先日は懐石料理屋の食卓に赤ん坊を乗せている人を見た。個人的には、どうかしてるんじゃないか、と思うが、いずれ普通のことになるのかもしれない。今はもちろん注意をしているが。
中学生の調べものがある。明日も混むかなぁ。
- 11月21日(金)
比較的利用者が少ない一日であった。
一本の電話回線が通話はできるが、パソコン通信ができないという不思議なことになり、NTTを呼ぶが解決せず。屋内配線業者に聞いてみてくださいとのこと。7年前から使いはじめ、半月前までは何の問題もなかったのだが。その間、何かをかえたということもない。謎である。
- 11月20日(木)
市内の小学校のPTAの人たちが広報誌に図書館のことを載せたいとのことで来館。所蔵調査から予約リクエストの流れ、CD-ROMによる資料検索、オンラインでの新聞記事検索等について説明。
見計らいの業者来館。書架がいっぱいになってきているので大冊のものを購入すべきかどうかで悩むことが増えた。当然、棚よりも本のほうが大事なのだが、いきなり閉架に入れねばスペースが足りないような資料の場合、閉架にあっても利用がどれほどあるのかといったことも考えねばならない。
- 11月18日(火)
朝、ブックポストに500冊ほど。割と少ない。
レファレンス、多し。地方行政資料や郷土資料の閲覧請求も増えている。ぺらぺらなものが多いのでいちどきに沢山の資料を見たいという際、閉架で探すのに時間がかかる。また貴重図書扱いにしてあり、複本がないものは貸出不可なので複写も多い。
なにやらばたばたした一日であった。
- 11月16日(日)
さすがに日曜日である。混んだ。
長期延滞利用者への督促がらみのトラブルが結構ある。三年前に借りていて、督促葉書を幾度も送っている利用者から、借りていないし、行ったこともない、などと言われたりする。対応が大変であるが、論理的に説明をして弁償してもらうことにしている。システム上、図書館に来たことのない人の貸出券をスキャンするはずがないのである。督促葉書がはじめにきた段階で何も言ってこず、幾度も連絡した末にこうしたことを言うのはどういう感覚なのだろうか。こちらももちろん間違いはあるが、恐ろしく非常識な人が世の中には結構たくさんいる。
30日の延滞ということは貸出期間14日と合わせて44日借りていた人が続けて貸してほしいという。できない、というと、ならば明日貸してくれるか、と訊ねる。明日は休みだが、明後日も貸せない、最長で28日しか貸していないのであるから、すでにあなたはそれを越えている。できれば一月ほどの間を置いていただきたい。棚にないとその本をほかの人が目にする機会が減る、と説明する。説明が要るような事柄か。どうしても長期間要るというのであれば、購入するかコピーをとれば良いのである。この人、なんとなく学校関係の人のようであった。まさかとは思うが。
中学生の調べもの、今日も多し。
- 11月15日(土)
利用者多し。中学生の調べものもどかどかとあった。とてもくたびれてしまった私はカウンターに6時間出ていたのでした。体力が落ちているので4時間半くらいまでに
したいと思うのだけれども、人手が足りないのである。
- 11月14日(金)
延滞をした上、「もう一度同じ本を貸してください」という人がこの頃多い。どういう神経なのだろうかと思う。同じ本を続けて借りるのは一度だけ、最長28日間。さらに借りたい場合は期間をあけて借りてください、ということにしているので(そうでなければ、予約が入らない限り同じ人が永遠に借りることだって可能になってしまい、本棚で他の人の目に触れる機会がなくなってしまう)、すでに長い期間借りておられるのであるかた、一旦棚に戻して、しばらくのちにまた借りてください、と説明する。「ああ、そうですか」とここではじめて納得するのである。きついことを言うようだが、期間に返せないのであれば借りなければいいのである。長く借りることは条例に違反するわけだし、ほかの人に迷惑をかけることになるのであるが、なぜか図書館界は長らく延滞利用者に甘く接してきている。私の勤める図書館では一日でも延滞している図書が一冊でもあると、その貸出券は使えないようにしている。また、貸出券は本人以外使用不可としている。そうしたことで延滞資料を何冊か残して返す人は激減した。厳しくすると利用者が減る、といったことがよく言われてきたのだが、そうでもないと思う。ルールはルールとして平等に守ってもらいながら、資料提供を充実してゆけば、利用者が減ることもないのである。延滞は悪いことだ、というくらいは利用者すべてがわかっているのである。わかっていながらしていても許してもらえるのであれば、少しくらいは良いのではないか、と甘えるのである。国民性なのか人間の本質なのかはわからないが、多くの人が気持ちよく図書館を使うためには延滞する利用者と延滞をしない利用者とを同様に扱うべきではないと思う。延滞資料があるまま貸している図書館はしかしどのようにしているのであろう。ひどい人になると、返すのが、360日遅れている本が3冊あっても、別の本を貸してください、と言ってくる。現実に私の勤務先であった例である。1日遅れている本が残っていても貸さないので、「貸せません。遅れている本をまず返してください」と答えたのだが、何日以上遅れている場合は貸さない、というような取り決めがあるのだろうか、あるのだろうなぁ。が、例えば14日以上遅れていたらほかの本を貸さないというルールを作っているとしたら、13日までは遅れてもいいと言っているのに等しいわけで、はじめから貸出期限を13日延ばしておけば良いように思う。融通をきかせて、利用しやすいようにとの意図はわからぬでもないが、なるべく皆が損をしないようにしてゆかねば、正直者が馬鹿を見ることになると私は思う。
- 11月13日(木)
中学生に調べものの宿題がいくつか出ているようで、団体がやってきた。調べ学習も良いのだが、事前に先生が一度図書館を見に来た上で、借りた本は早く返してほかの生徒が利用できるようにしなさいとか、大勢で図書館に行って騒いではいけないといったような指導をしておいてもらえないものであろうか、と思う。また図書館側へ、「こういう宿題を出してありますのでよろしく」くらいのことを言ってきても良いのではないだろうか。先生が忙しいのはわかるが、図書館とて暇ではないのである。急に大量の生徒から同様の質問を受けても同じ資料は沢山はないし、類書を探しにくい種類の調べものは大変なのである。
一般利用者のレファレンスも多い。登録者も多い。平日も土日も登録者、レファレンスの数はさほど変わらなくなってきた。入館者数、貸出冊数は少ないが。
- 11月12日(水)
朝、ブックポストに1200冊ほどの本が返っていた。
「小屋と馬車と犬と人がついている絵のついている本を見せてくれ。馬を洗っている人もついていた。前にこの図書館で見た。写実的な絵だった」とおっしゃる利用者がいらした。誰の何という絵かどの画集かいつの時代の絵かどこの国の画家かもさっぱりわからない。画面が黒っぽかったというのでレンブラントの画集を持っていくが、違うとのこと。ターナーの画集を持っていくが違うとのこと。これくらいの大きさ、厚さの本だったとのことなので、その全集と、それとは別の同じくらいの厚さ大きさの全集のなかで写実的な画家の分を閉架から出し、見てもらうことにしたが、利用者に時間もなく、見つからなかった。
ま、これだけしかわからないと絵によほど詳しい人でないとわからないような気がするのだが、美術専門のレファレンスの施設、音楽専門のレファレンスの施設といったものは必要なのではあるまいかという気がする。
和本の黄表紙を見せて欲しいとのご要望があった。目録が不備なので御迷惑をかける。半年ほど集中して整理すれば和本の目録作業が終わるのだが、その時間がとれないまま五年ほどになる。利用の少ない資料の整理はどうしてもあとまわしになってしまう。一応冊子目録をつくるところまではいったのだが、それ以前、約一万冊の和本は三十年以上ほったらかしにされていたのであった。
レファレンスがとても多い一日だった。貸出も2600冊を越えた。ばたばた。
- 11月7日(金)
見計らいの新刊図書と新刊リストを付け合わせる作業と分類。ブックトラック(ワゴン)に並べた本をリストをつけあわせながら、分類を付してゆく仕事なのだが、本の数が多いと抜いてしまうだけでもなかなかの重労働だったりするのであった。
難しいレファレンスが多い。利用者が多様化してきている。
- 11月6日(木)
受付のローテーション表をつくる。来週は出張の職員がいたり、役所で交通安全研修があったりするのでローテーションを組みにくくて参った。
曖昧な書名からの検索多し。ま、蔵書の有無についての問い合わせの三割ほどは正確な書名ではないのだけれども。利用者検索用コンピュータを置いて事足れりとしている図書館もあるが、正確な書誌事項を利用者が持ってきていなければ探せないことを見落としている。曖昧な書誌から目的の資料を探すことは難しい仕事であるが、こうした仕事こそが司書のすべきことであると思う。そうしたことをしないのであれば、司書はいらないと言われても仕方がないように思う。
- 11月5日(水)
朝、ブックポストの本、700冊ほど。割と少なかった。昨日休みだったため、利用者多し。
本の見計らいをする。
- 11月3日(月)
定期休館日の月曜日と祝日が重なった日は大抵利用者が少ない。今日も平日並であった。昨日のレファレンス、なんとか資料が見つかり、連絡。小学生が先生に問い合わせたものと聞き、「そういう調べものが難しいのですよね」と話す。
- 11月2日(日)
三連休のせいか、それほど利用者の来ない日曜日であった。
難しいレファレンスが何件かあった。きっとそれはこうに違いない、まず間違いないと思うものの、そのことを記載してある資料が見つからないことほどいらだたしいことはない。そうしたレファレンスの資料が得られず、のちほど連絡します、と連絡先を利用者に聞いておいたのであった。
- 10月31日(金)
午前中カウンター業務。不快なことが多い。返却図書に栞がわりのゼムピンをページに挟んでいる人がいる。「ページをゼムでとめると痛みますので、栞を挟むようにしてください」と注意する。五十歳くらいの人である。この人はいつも家でこうしていたのであろうなぁ、ほかにもいたりするのだろうな、と思うと気が重くなる。
開いた本の上で薄いメモに字を書く人、綴じた本の上で薄いメモに字を書く人が多い。そのたび注意をする。本を大事にするという感覚がまるでない大人がいっぱいいるのはどうしてなのだろう。私が子供の頃はまたいで通っても叱られたものだが。
新しい号のビジネス雑誌のページが破られていた、と利用者が持ってきてくれる。手できたなく破ってある。最新号は著作権法で複写ができないから、とこういうことをした人間がいるのだろうか。それともカラーページが欲しかったのか。いずれにしてもまともではない。腐った人間がいるものである。
としょかんだより完成。
ローテーション表をつくる。来週は休む職員が少ないので二交代の日が多く、組みやすかった。勤務日と開館日が一致していないと毎日休みの職員がいるわけで、なかなか大変なのである。
- 10月30日(木)
図書の延滞督促をする。予約がかからない図書の場合、三週間以上の延滞で連絡をし、予約がかかった図書は三日延滞でする。視聴覚資料は五日延滞、とまちまちでよくないのだが、全ての資料に対して早い時期に督促処理をするとなると量がものすごいことになり、職員、郵便代、電話代が足りないのである。「借りておられる図書が返却期限を過ぎていまして、あとに予約の方が待っておられるものがありますので、お早めにお返しください」と電話で連絡するのだが、なかに、「どれですか」と尋ねる人がいる。予約のかかった資料だけ返せばいいと考えるのであろうか。あろうなぁ。「期限を過ぎている資料をすべてお返しくださいね」と答える私である。
早いもので明後日から11月。としょかんだよりの原稿を書く。
- 10月29日(水)
毎週のように図書館に来ていた利用者が亡くなったと聞いた。いつも気楽に、「これちょっと教えてくれん?」とか「この本、あるかどうか調べてえ?」(名古屋弁で、「調べてくださいな」というようなニュアンスの尋ね方」)、と尋ねに来ておられた人だった。なかなか難しい調べものが多く、こちらも勉強させていただいた。調べていたことが見つかると、「おお、これこれ。わしが探しておったのはこれだ。ありがとう」と、とても喜んでくださっていた。お元気だった記憶しかないように思うのだが、最後にお見かけしたときには、「ちょっと入院しちゃってね。調子悪いんだ」と言っておられ、かなり痩せていた。半年ほど前とは別人のようだった。図書館に勤めて14年になるが、利用者が亡くなったと聞いてショックを受けたのは初めてである。それほどよく図書館を使っておられた方であった。72歳とのこと。ご冥福をお祈りいたします。
- 10月28日(火)
登録者多し。調べものの人多し。閉架資料の利用多し。
としょかんだよりに載せる新刊を選ぶ。
本の見計らいをする。
督促電話をかける。さしてなにもない一日であった。
- 10月24日(金)
館内整理日。議題は延滞督促をしている人でどこにいってしまったかを調べる手段がなくなってしまった、いわゆる行方不明者についてどうするか、開架に出してある新聞のバックナンバーについての検討、新聞の綴じ方についての検討などであった。以前から問題となっている事柄が多く、過去の経緯などを説明しているだけで時間がかかってしまった。
延滞督促の連絡をする。大抵、「遅れてしまってごめんなさい」と言わない。家族に伝言する場合でも言わない人が多くなってきた。時代なのだろうか。期限を守らないような人だから謝らない、そのまた家族も謝らない、ということなのだろうか。10年ほど前はそうでもなかったように思うのだが。
- 10月23日(木)
来週のローテーションを組む。昼御飯三交代の日が多くてうんざりしてくる。職員を増やしてくれないものであろうか。あるいは休館日を増やすとか。月火休みの図書館もあるのだそうだ。そうなると開館日と出勤日が一致するので、それ以外の休みは年休や夏休み忌引きくらいとなり、休む職員の数が減るのでローテーションを組みやすくなるのであるが、無理であろうなぁ。
今日も平日だというのにレファレンスやコピー、登録が多かった。
- 10月22日(水)
平日だというのにレファレンスの利用者や登録者が多い。ばたばたであった。
不機嫌なお客さんがくる。「○○という本は入ってるかっ。調べてくれっ」と不機嫌にお尋ねになる。調べると予約者がすでに一人いる。「現在貸出中で予約の方がすでにお一人いらっしゃいますが、よろしければ予約なさってください」と言うと「返ってくるのはいつごろだ」とお尋ねになられたので、「一ヶ月くらいあとになります」と答えると、「なにぃ、一ヶ月。そんじゃいらんっ」と怒鳴って去っていったのでした。現在貸出中で予約の人が一人いれば二週間+二週間くらいはかかるとすぐにはわからなかったのであろう。はじめから怒鳴るようにしてやって来られたのだけれど、なにか家庭か会社でつらいことでもあったのかなぁ、としばらく考えてしまった。この人、育ち方にも問題があったのかもしれない。
- 10月21日(火)
凧の宿題、別の学校の子がきているようである。なかなか難しい調べものなのだが、先生は調べてみたことがあるのだろうか。
小学生の男の子が泣いていたとのこと。同級の女の子にいじめられていたのだそうだ。恐ろしい世の中になったなぁ、と話していると、主査(45歳)が、「僕も小学生の頃、女の子にいじめらたことがある」と静かに語った。ちなみにこの人、独り身である。世の中にはいろいろなことがある。
- 10月19日(日)
図書館近くでお祭りだったのと市内小学校のいくつかで運動会があったので午前中は空いていたのだが、夕方混雑。貸出3918冊、返却3661冊。
幾度も同じ本を何冊も借りる人がいる。図書館の本の背表紙をコピーして、この本とこの本、ありますか、と訊く。継続貸出については制限をしているが、間を置いて借りるのであれば構わないということにしてある。だが、幾度も読み返すのであれば購入するなり、必要個所をコピーすべきではないのか。同じ人が幾度も幾度も借りる為に選書をしているわけではない。沢山の人の目に触れて欲しいと思うのである。その旨その方にお伝えはしたが、ご理解いただけたかどうか。いろんな人がいる。
- 10月18日(土)
朝、大学生の問い合わせにより、オンラインデータベースから新聞記事の検索。が、記事がみつからない。確かに読んだはずとのことだが、よくよく聞くと父親からのまた聞きだったのだそうだ。関連施設に電話で問えばわかるとのこと故、そうしてもらう。この業務に一時間ほどかかる。このサービス、今のところ無料だが、有料化の検討もすべきであろう。どのように料金体系をつくるかが難だが。
CD-ROMの案内が沢山きている。朝日新聞社の「民力」などは十年分がまとまっているので使いやすいし、書籍を廃棄することができるので良いとは思うのだが、利用者すべてがパソコンを使えるわけではないので、CD-ROM購入に踏み切れない。現在書籍を買わずにCD-ROMだけを利用者に提供しているのは「判例体系CD-ROM」と「雑誌記事索引」だけである。前者は利用する人が限られており、後者はCD-ROMしか出版されていないという理由により、書籍を購入していないのである。
朝、利用者が少なかったのだが、夕方から人だらけ。さすがに土曜日である。
- 10月17日(金)
督促電話のリストを調べると、昨日の電話の人、確かに二ヶ月前に返したと言っていることが判明。その際、書架を確認したところ本はなかったとのことだが、そのことについて連絡をしていなかったそうだ。言ったもの勝ちのような話ではあるが、本が返されていなかったと断言することもできない為、今回についてはトラブル扱いの返却処理をすることにする。判然としない処理ではある。
カウンターのローテーション表作成。来週も昼休み三交代の日だらけ。時間がかかる。
- 10月16日(木)
督促電話。一年以上の延滞しているはずの本を返したと言う利用者。が、一年ほど前に立て続けに葉書で督促したのち、電話でも督促しているはずなのである。いずれかの電話の時に返したと言ったのにそちらが連絡してこなかったと言われる。そういうことがあったとすれば、その件に関してはこちらのミスである。が、本棚に本はないのであった。釈然としないがこの人が返したあとに盗難にあったという可能性も全くないわけではないわけで、対応について明日また検討することにする。
登録者多し。
- 10月15日(水)
ブックポストへの返却本1500冊。多すぎる。なんとかしてくれぇ、と叫びたくなる。
本の見計らい、督促電話、予約連絡。
コケと凧は終わったようだが、アメリカの宿題はまだ終わっていないようで、母親が本を借りにきた。忙しい中学生も多いようだ。
- 10月12日(日)
コケと凧、今日も多し。公害についての調べもの、アメリカについての調べものの宿題も出ているようであった。コケの中学生、多すぎ。整理するのが大変であった。貸出のできるものについては借りて帰ってもらって、家でB紙に書いてね、と頼む。だんだん人数が増えてきて、10人しか座るところのない通路の狭い児童用の閲覧席に20人ほどが集まってがやがやと話をしているので注意をする。図書館入口で立ち話をする中学生もいる。入館者カウンターのセンサー前でも話をする。少ない職員であちこちに注意にゆく。公害の調べものの親子連れに閲覧席近くで資料を見ながら説明をしている際、コケの中学生がずっと話していて説明しづらく、また荷物が書架のど真ん前に置いてあったりもする。幾度か注意したのち、ついに切れる。「君たちに注意をするだけが図書館の仕事ではないんだ。そもそも多人数で話し合いながらの調べものができるスペースはこの図書館にはないから静かにしていてほしい、と何度か注意したはずだ。それができないようなら、ほかの人の迷惑になるので必要や個所をコピーするなりしてから、帰ってほしい。君たちだけの席ではないのだ」とB紙を広げて10人ほどでわいわいがやがやの中学生を叱り飛ばす。館内の資料を使っているわけだし、賑やか過ぎるのはともかく、本来はその程度の調べものができるような場所はあるべきだとも思うのだが、椅子と机を常に置いておけば、勉強だけをしにくる生徒が大勢使うようになるわけだし、かといって整理券を配りまた回収し、時折見回るほど職員の手がない。利用の度、資料利用票のようなものを書いてももらわねばならないことになろうし、どこかの部屋をその為に開けることになれば、整理券を持っていない勉強目的の学生がやはり入る。番人を置かねばならないようなことになる。やはり、学校の勉強は学校でしてもらうようにすべきであろう。土日、祝日に学校を閉めていることは問題であると思う。土日は公共図書館で調べものをしてきなさい、と先生が生徒に言ってもらえるほどには、公共図書館は充実してはいないのである。先生は一度くらいは図書館に来てから言っているのであろうか。ま、充実している図書館もあるのかもしれないが。
貸出冊数4248冊、返却冊数3893冊。貸出の方が多いということは、利用者が増えているのであろうなぁ。職員はしかし増えない。今日は臨時職員を合わせて8人の職員で交代をしながらカウンター業務をしていたのであった。
- 10月11日(土)
コケと凧の宿題の生徒多し。コケはグループに別れての調べもので、B紙を広げて書かねばならないらしく、児童用の閲覧席が賑わう。
登録者多し。ばたばたであった。
- 10月10日(金)
コケについての調べものは昨日の生徒たちだけではなく、三クラスに出されて宿題であったそうで、朝から調べにくる生徒が多かったのだが、本は植物図鑑か百科事典くらいしかなく、書きうつす場所も多くはないわけで、混む。コピーをとっていったりもした。
小学生には凧についての調べものの宿題が出ているらしく、親子で調べに来ていたりもした。凧の作り方の本は割とあるのだが、どの県でどんな凧が作られているかという記述のある本はとても少ない。先生は知っていて宿題を出しているのであろうか。
高校生はテスト期間らしく、久々に勉強道具だけを持って閲覧席につく学生の姿があるな、と朝には思ったのだが、一日で延べ三十人ほども来たのには驚いた。もちろん館内の資料の閲覧の席しかない旨を説明してご遠慮ねがった。なかに一人不満げな女子学生がおり、私の顔を睨みながら筆箱をしめていた。三年前に閲覧席をしめた経緯もゆっくりと説明したのだが、自分のしたいことをしたいようにできないのが気に要らないとでも言いたげであった。家庭に問題があるのかなぁ、と少し気の毒に思ったりもした私であった。
利用者用端末では書名か著者名がある程度わかっている図書以外は検索できない。どうやら件名のようなものから探している中年女性がいらしたので、「この機械では書名がある程度わかっていないと探しきれませんので、よろしければ職員の使う端末でお調べしますよ」と声をかけたところ、「この機械を使って探しいてはいけないのですか」と声を荒げられてしまった。「いえいえ、そういうことではないのですが、この機械で出てこないデータの入り方の本も何冊かあるものですから」と説明する。「棚の場所はわかっていて、そこを見てもなかったから探しているんですが」とおっしゃるので、「ですから、この機械では閉架の本を分類番号から探すといったことができないものですから、よろしければ、こちらで探しますのでどうぞ」とさらに説明したのだが、もう少しこの機械で探すとのことであった。難しい人の多い昨今である。
- 10月9日(木)
職員の数が少ない日であった。
中学生が調べものにやってきた。コケと藻類についてとのこと。本の少ない分野である。貸出のできるものすべてを借りていった。
- 10月7日(火)
朝、ブックポストに返っている本が多い。ま、休み明けはいつもそうなのであるが。
本の見計らい。今週は本が多い。この作業はゆっくりできるととても楽しいのだが、時間に余裕がないとつらい仕事となるのであった。今日は割と時間があった。
今月は視聴覚資料の延滞督促連絡当番。「ごめんなさい」を言う人が極端に少ない。予約をして借りていったCDやビデオを期限のうちに返さない神経というのがわからないのだが。あとに予約をしている人のことはどうでもいいのであろうか。あろうなぁ。
- 10月5日(日)
「続けて借りていいですか」との質問をよく受ける。「続けて借りるのは一度だけにしてくださいね。同じ方がずっと借りておられると、ほかの方が借りられなくなってしまいますから」と、答えるわけだが、返却と同時に誰が何を借りていたかの記録をプライヴァシー保護のため、抹消しているので、実際は誰が何をどれだけ続けて借りたかはわからない。どうも同じ本を続けて借りっぱなしの人がいるような気がしてならないのだが、何を借りたかを職員が覚えていることはいいはずがないわけで、ま、それ自体は仕方がないとしても、それを利用者に話すとなると、「どうして私が何をいつ借りたかを覚えているのだ」と不信感を抱かれるわけだが、何カ月も同じ本ばかり借りる人がどうやらいるのである。と、文章がヘンになっているが、そんなにずっと借りていたいのであれば、要るところをコピーするとか、買える本ならば買えばいいのにな、と思う私である。世の中には不思議な人がいるのであった。
読書感想文コンクールというのを毎年開いている。かれこれ三十年。数年前から、職員の間では、このコンクール、やめるわけにはいかないのだろうか。仕事がどんどん増えているなかで、図書館との繋がりがいまひとつわからない、子供を本好きにするとも思えないコンクールを図書館が中心となって行ってゆかねばならないのはどうしてなのだろうなぁ、歴史があるから仕方がないのであろうなぁ、学校の夏休みの宿題になっちゃっていたりもするしなぁ、仕事が多いから止しますなどと言えば、まるで勤労意欲がないかのように響くだろうしなぁ、仕方がないのだろうな、などと話していたりする。このコンクールの仕事量が結構多いのである。各学校にコンクールを行う旨の案内を出し、原稿を集め、応募票をチェックし、数を数え、審査員に審査のお願いをし、誰が書いた原稿であるかを審査員に判らなくするため、応募票と原稿にナンバリングを押し、ばらばらにし、一次審査、二次審査、トロフィーの発注、名入れ、受賞者を各学校に連絡、利用者の多い土曜日に表彰式、と、ざっとこんな仕事である。一人でするとなると延べ半年以上の仕事となる。さらに読書感想画コンクールというのもある。これも止したいね、などと職員は話していたりもするのであるが、歴史というのは恐ろしいものなのである。利用者の数が多くない、とか、職員の数に余裕があるという図書館の状態の時にはじめたわけだが、そうではなくなるとなかなかきついのであった。と、これでは愚痴だ。しかし感想文とか感想画って、大人が書くのだって難しいのだが、子供全員に無理矢理のようにかかせて、どうしようというのだろうな、ということはよく思う私である。そんなよなわけで、今日は利用者が比較的少なかったので、応募票を切り離す作業をしたのであった。
- 10月4日(土)
比較的利用者が少ない土曜日であった。貸出3293冊、返却3181冊。
- 10月2日(木)
来週のローテーションを組む。来週は休む職員が多く、三交代の日ばかり。組むのに苦労する。
見計らい本の続き。
- 10月1日(水)
同僚のお父さんが、倒れたとのことで、急遽、受付ローテーションを組み直す。別の人のお爺さんがなくなったとのことで、明日からのローテーションも組み直す。
新刊図書の見計らい。今週は多い。
文庫本の棚が一杯なので、文庫本スペースを広げ、移動する。なかなかの大仕事なのだが、人数が少ないので、一人で動かす。
風邪がなおらない。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]