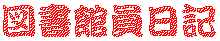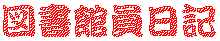
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 5月31日(土)
土曜日はばたばた。
合間をぬって人事考課の面接を受ける。
- 5月30日(金)
朝、受付。15日延滞の利用者に、「今度から遅れないようにお気をつけくださいね」と言うと、「すみません。雨が降ったりしたものですから」とおっしゃる。昔からこの理由はよく聞く。
午後、「としょかんだより」を作成。風邪をひいたらしく頭ががんがんする。「としょかんだより」の原稿完成後、早退。
- 5月29日(木)
朝、受付。図書館の本を三冊持ったまま、便所に入った男性客がいた。おいおい。注意をしに便所に入るのも気がひける。出てきてから注意をすべきかどうかと悩むが、なかなか出てこない。十分ほどして水を流す大きな音。もしかして用を足しながら図書館の本を読んでいたりはしないだろうな、と考え込んでいるうちに男は姿を消した。図書館の本を触ったあとはよく手を洗いましょう。
特別整理期間の段取り、ほぼまとまる。
- 5月28日(水)
朝、受付。幼児、乳幼児を連れた主婦が多い。それにしても笛のついた靴はなんとかならないものだろうか。歩く度ぴーぴーとなる靴である。子供の音感が悪くなるのではなかろうか、などといらぬ心配をしてしまう私。ま、子供のことは知らぬが、図書館ではほかの方に迷惑となるので、「笛の部分をはずすかセロテープで笛の穴をふさぐと音が出ませんので、図書館にいる間はそうしていただくとありがたいのですが」とお願いすることにしている。隣を歩く母親はあの気持ちの悪い音が気にならないのであろうか。あろうな。
乱暴な子供が多かった。持ってきたぬいぐるみを投げる。館内を走る。本に凭れる。親は叱らない。靴を履いたまま椅子の上を歩く。近頃では大人もこういうことを平気でしているから子供ならばなおさらするであろうな、などと考える昨今である。野球場の椅子を靴を履いたままずんずん歩くおっさんおばさんを数年前に観た時、日本もここまで来たか、と思ったものである。やはりどうやらここまで来ていると思う。私だけが思っているのかもしれないが。
本のページの上で紙切れにボールペンでメモをとる中年男性に注意。どうも朝の受付は精神衛生上よくない。これからますますよくなくなることであろう。
特別整理期間のあれこれを考える。
- 5月27日(火)
来週からの特別整理期間のあれこれを相談。書架の移動に伴うなにやらが結構大変である。
取次店の人が来る。新しい担当者が女の人。重たい仕事が多くはないのかな、と少し思うが、図書館も重たい仕事が多いが、力持ちの女の人がいっぱいいるわけで、ま、別にどうということもないか、と考え直す。
マイクロフィルムのピントがあわないので販売店の人に来てもらう。
本の見計らい。
たまったパンフレットを見て選書。
利用者、なかなか多し。
- 5月25日(日)
貸出冊数5200冊。大ばたばた。来週半ばから特別整理期間で10日間休館するのと関係があるのだろうか。この大ばたばたの中、テスト期間らしく、学習に来ている学生が延べ10名以上。「館内資料の閲覧だけに限らせてもらっているのですよ」と皆、ご遠慮願う。皆、素直に聞き入れてくださった。この限定を始めてから、かれこれ3年になるのだが、学習利用者がまだいるのはやはり愛知県中の図書館で私の勤務先だけが館内資料閲覧に限る、としていることと関係があるのだろうか。そうしないとレファレンスだけでなく、いくつもの業務のが滞ってしまったという経緯が我が館にはあるのだが、他館はそうはならないのだろうか。あってもほったらかしにしているのだろうか。自習室的利用者の多さに、遠慮して(あるいは呆れて)帰ってしまう館内資料利用者がいることが気にならないのであろうか、気がつくつもりがないのだろうか、そうした利用者がずっと来なくなっててはじめからいないものだと考えているのだろうか、資料の利用者などいなくてもいいと考えているのだろうか、参考資料を何の為に買っているのだろうと選書に空しくなったりする図書館員がいないのであろうか、などと考える暇もなく大ばたばたで一日が過ぎた。
- 5月24日(土)
貸出冊数5000冊を越す。ばたばた。大にぎわいの中、子供を野放しにしている母親が多かったが、注意をしている時間さえ、あまりなかった。時折閲覧席を見にゆくと、建築関係の資格試験の勉強をしている人や、土木関係の資格試験の勉強をしている人や、マンガのネームを入れている人がいたので、「館内資料の閲覧の方に限らせていただいております」と注意。丸刈りの大人の人に注意するときには少しどきどきした。
再来週からの特別整理期間のあれこれについても話し合う。
- 5月23日(金)
館内整理日。特別整理期間に行う書架増設に伴うあれこれについて話し合う。午後、事務室の片づけ。書架整理。
- 5月22日(木)
朝、月次比較の統計を出す。午後、特別整理期間の作業手順を作成。ばたばた。
- 5月20日(火)
朝、ブックポストへの返却本、約530冊。朝、カウンター業務。利用者なかなか多し。
市内の小学校からオンライン接続をしたいとの申し出あり。すでに一館、接続したのでその話を聞いてとのこと。つながることはつながるけれども、そこから先の図書予約、取り置き等は職員が少なくできない旨、伝える。オンラインによる検索はたしかにすごそうなことのように思えるが、ファクシミリによる問い合わせの方が図書館が探す分だけ効率がよかったりするのだが。担当の先生が詳細を知りたいと来館。
市内の中学校から夏休みに生徒に体験学習をさせたいので受け入れてほしいとの電話。数年前からはじまった行事である。図書館の仕事で中学生に簡単に手伝ってもらえることはほとんどないのではあるが、力仕事が少しあるので三、四人であれば平日に来ていただいても構わないと答える。数校あるからばたばたの夏休みに受け入れるのも案外馬鹿にならないのだが、なかに図書館を好きな学生もいて、図書館がどんなところなのかを知ってもらう良い機会でもあるからと受けている。ひどい生徒もいたりするが。
中学生の難しい調べもの。「渋染一揆」について詳しく知りたいとのこと。渋染の部落で幕末に起きた一揆なのだが、私が中学のころには全然教わらなかった。今は教科書に半ページほど記載がある。私はたまたまこの一揆について以前何かで読んだことがあるのだが、中学生向けの資料と言われて困ってしまった。閉館間際でもあった。210の歴史の分類よりも361の社会学の分類に本がありそうだとあたりをつけて探すと記載のある資料があった。この本を貸し出す。そこに参考文献も載っており、所蔵していたので、その資料を複写。なんとかなった。
- 5月18日(日)
貸出冊数が約4800冊、入館者数が約1600人。ばたばたであった。
中学生が学校対抗でディベートをするとのことで、テーマはアルゼンチン、オーストラリアの憲法についてその他。日本語の資料があまりなさそうなので、その旨、告げると、英語の資料でも構いませんとのこと。が、中規模の公共図書館に英語の資料はないのであった。その学生はインターネットも利用しているとのことなので、オーストラリアの憲法については探せるのではなかろうか、と答える。アルゼンチンの憲法についてはラテンアメリカ協会が関連書を出版しているのを見つけたので、直接問い合わせるのが早いのではないか、と連絡先を調べた。その他のテーマについては近隣の大学図書館が一般に開放しているので、そこで尋ねた方が恐らく早くわかるのではないかと答える。とても知的水準の高い中学生であった。アホな大学生もいっぱい
いるというのにこの差はなんだろう。公共図書館は役に立たないところだな、と思われたのではなかろうか、と少し不安になる。
- 5月17日(土)
利用者多し。予約リクエスト、書架案内、新聞の複写、登録が立て続けに入る。来週と明日のカウンターローテーションを組む。来月の休みの表を作る。開館日と勤務日が一致しないので休みをとるのがなかなか大変なのだ。全職員が出勤している日はほとんどない。
- 5月15日(木)
午前中、小学生の見学、午後から視察でばたばた。視察にきた市の人たちはすごく熱心。二時間以上質問を受けた。そういえば数年前に今の元になる機種を導入する際にはかなり長い時間を費やして検討したなぁ、と質問に答えているうちに思い出した。ほかにも当時、いろいろ考えていたことを思い出した。忘れていることが実に多い。コンピュータでものすごく沢山のことができるかのような錯覚を持っている職員がその頃には多くいた。それ以前に5年間ほかのコンピュータを使っていたにもかかわらずである。今でもコンピュータを魔法の箱のように考えている人がいるように思う。図書館でコンピュータを導入してできるようになること早くできるようになることは貸出返却の処理速度をあげること、予約図書の発見、リアルタイムでの所蔵状況、貸出状況把握、統計処理、棚卸、発注処理の簡素化、MARCを使った早い図書登録などであろうか。かなり沢山あることはあるのだが、実際に使っていない人たちはもっとずっと沢山あれこれできるかのような気がしてしまうようなので、「それほど大したことはできませんので、多くを期待しないほうが良いと思います」と話した私。
- 5月14日(水)
明日視察に来る館へのアンケート回答に手間取る。なぜこんなに細かい点まで訊くのだろうか、とよくよく考えてみると、その館はまだ電算化されておらず、今回はじめて電算を導入するのであった。それならば沢山質問しておかないと不安であろうな、と納得はしたものの、かなり手こずった。
市のある課のアドバイザーである大学の先生が市の古い事柄についての調べものの為、ご来館。戦前の行政関係の資料はほとんど残っていない。多くの市町がそうであるようだ。昭和六年に出版されたある資料の序に、昭和四年に出版した資料に書かれていることは今回略したといった内容の記述があるのだが、その昭和四年の資料を所蔵しておらず、略すなよぉ、と言いたくなるが、持っていないのが悪いのである。これでも行政資料、郷土関係資料をあとから随分集めたのであるが。現在出ている資料についても五十年ほど経てば似たような状態になる可能性がある。意識的に保存してゆかねば、という思いを新たにする。また古書のチェックも怠ってはならないのである。保存の為の整理は人手のいる作業である。多くの資料の提供に数時間かかった。難解なレファレンスが増えれば、人手が必要となるのである。無理解な行政の職員は人手がかかるのならばそういう仕事は止めればいい、と気楽に言ったりするらしい。過去の行政資料が保存されていないのはそれほど不思議なことではない。現在の方がもっと危ないかもしれないのである。
- 5月11日(日)
利用者多し。レファレンス、書架案内、登録が随分ある。
樋口一葉と与謝野明子についての評論を探しているという女子学生がいたので、大学生だと思い、「大学の図書館の方が資料が充実していますよ」と言うと、なんと高校生。選択科目での宿題とのこと。締切ぎりぎりのテキトーな女子大生がまた来たのか、と考えた私であったが、勉強熱心な女子高校生だったのであった。何事も決めつけてかかってはいけない、と反省。
- 5月10日(土)
朝から利用者が多い。登録者が随分いる。利用はこれからも増え続けるのであろうか。職員は増えないのだろうか。少し怖くなる。
レファレンスが多い。訊けばわかるかもしれない、という雰囲気が出てきたのか口コミで広がったのか。訊いてもわからない、と口コミで広がってしまうとその認識を変えるのは難しい。図書館では日々の仕事が重要なのである。が、多くのレファレンスに対応できる職員は簡単には育たない。私も全然まだまだである。
- 5月9日(金)
昼休みに「図書館界」の前川恒雄氏の論文を読む。河合弘志氏の論文への反論なのだが、実にスリリング。「私は図書の価値をはかることは、ほとんど人間の価値をはかることと異ならないと考える。だから一見科学的客観的で精緻に見える尺度ほど、真の価値から遠ざかるように思える」との図書選択についての言葉は至言。
前川さんは名著「市民の図書館」(日本図書館協会)の実質的な著者で、「われらの図書館」(筑摩書房)の著者。日本の図書館界の不幸は70年に出版された「市民の図書館」の精神に共鳴した人が多くいたにも関わらず、席貸し業務はさして減っておらず、貸出業務、児童サービスを今だに軽く見ている図書館が多いことである、としみじみ思う。「市民の図書館」を読んで共鳴した人が図書館からみんなすぐに異動してしまったのかもしれない。その後移ってきた人が読んでないんだ、きっと。それとも読んでも中身のすごさに気づかなかったかのどっちかだな。実務経験のない図書館学の人の図書選択についての空論が、実務を経て叩き上げた理論よりも高いものとして捉えられるかもしれないのだなぁ、と図書館関連の論文を読んでときどき思う。
去年電算機を変え、年次統計の取り方を変えたのだが、大丈夫であろう、と確認しなかったものがぼろぼろ。SEに連絡をとって修正依頼。
- 5月8日(木)
色々な人がいる。バーコードシールが上になるようにカウンターの隅で本を揃えている人、その前を大股で横切る60代と30代の親子。バーコードがどちらについてようがお構いなくぐちゃぐちゃに本をカウンターに出す。その横には本を揃えている人。
ぐちゃぐちゃ本の人は返却日をとうに過ぎている。「今度から遅れないようにお気をつけくださいね」「はい」。その親は、「一冊探したんだけど、どうしても見つからないんだわ。弁償しないといかんよね。探したら出てくるかもしれないのだけれど」と訊く。「できれば探していただいて返してくださると助かるのですが。ただ、その本が期限を過ぎているので、ほかの本を借りることができませんのでそれだけはご承知おきいただけますか」「そう。続けて借りたい本があったんだけどしょうがないねぇ。もう一回探してくるわ」
続けて借りたいと言われることはままある。その本に予約が入ってなければ一度だけ継続貸出をしている。が、すでに延滞している場合、続けて貸さないようにしている。ま、普通に考えれば当然のような気もするのだけれども。話が長くなりそうなので、続けて借りる場合についての話は止した。お詫びの言葉は聞かなかった。
しばらくの間、後ろで待っていた、本を揃えていた人が返却窓口に本を出す。
「お待たせいたしました」「いえいえ」
その人はにっこり微笑んだ。色々な人がいる。
日本図書館協会からのアンケートと近々見学に来る他館からのアンケートに回答を書く。アンケートへの記入は結構時間がかかるものである。意図が見えない設問があるとさらに時間がかかる。
- 5月7日(水)
統計数字を拾う作業や、備品購入の打ち合わせでばたばた。
新聞記事の検索依頼二件。オンラインデータベースでの検索は時間がかかる。職員数が少ない図書館にはきついのであるが、新聞をめくるよりずっと早いに決まっている。難しいほどの件数のある子供関連の事柄については、「月刊子ども論」を見てもらう。そういう雑誌の有無を知っているかいないかで手間が全然違ってくるわけで、情報収集は司書に必須な要件なのであった。「できません」とか「ありません」と言っちゃえばそれで済んでいってしまうから困るのだけども。そういう図書館も現実にあり、そこは利用者が減るだけのことでなぜだか問題になってこなかったわけで、これからもきっと問題にならないのではなかろうか、と思うと図書館で普通に仕事をすることは空しいことであるなぁ、と感じるのであった。
- 5月5日(月)
利用者少なし。
統計数字がおかしい、と上司が言うのでチェックすると変。去年電算機を変え、統計の取り方を少し変えたため。数年前に電算機を変えたときに統計でひどい目にあったので、去年は若い職員二人に頼んで、私は相談に乗るだけということにしておいたのだが、うまくできあがっていなかったようだ。頭から見直すといくつか問題箇所があった。電算屋さんは早く対応してくれるであろうか。ま、処理速度が早くなっているから、以前のように、「直りました」と言われて一週間ほどかけて出してみて、「まだおかしいところがあります」と連絡し、直してもらい、また一週間かけて出して駄目、ということはないからましだけども。
資料費の配分についてもチェック。慣れぬ数字ばかり見ていたら朦朧としてきた。
- 5月4日(日)
市内でお祭りのところがあるせいか、割と利用者が少なかった。小学生がナポレオンについてと平安時代についての調べもの。昨日のうちに沢山の本を貸した為、貸出のできない百科事典何種類かを案内。
- 5月3日(土)
朝から人だらけであった。ばたばたの一日。
- 5月1日(木)
することが多い一日であった。本の見計らい、受付、6月に入れる書架の見出し板が何枚いるかを検討、MARCの流し込み、カウンターローテーションの作成、予約電話連絡。
四十年ほど前に町名変更でできた町名の由来を知りたいというレファレンス。古い町名については由来が残っているものが多いのだが、新しくできた町名がどうしてついたのかの記録は残っていない。当時の総務課勤務の人に尋ねると、関係者の多くは亡くなっているとのこと。幾人か紹介していただく。電話してみるが留守。知らない人に質問の電話をするのは少し気が重いが、これよりほか方法がないのである。
- 4月30日(水)
「としょかんだより」を作成。最近本の扱いが荒い人が多いので、「おねがい」の文章を書く。薄い本を炎天下に車に入れっぱなしにして反らす人とか、表紙も本体も薄い本や雑誌を丸めて持ってくる人、やたらと書き込む人、ページの端を折る人、風呂で本を読んだのではなかろうかと思われる人、絵本を開いた上に乳幼児がのっかってるのに注意しない両親などなど、いろんな人がいる。本のありがたみがどんどん薄くなっているのと公共のものを大事にしない風潮の昨今なのであろうか。嫌な世の中である。
大学生の宿題。国文科の学生が古典の古注釈本の訳本がないかとの問い合わせ。あるはずがないだろうなぁ、と思いながら調べるとやはりない。探すことはともかく、こういうことを訊くのに抵抗がないことがなんとなく怖いと思う。日本の教育は絶対どっか変だと思う。勉強しなくても良い性質の人が無理矢理していることがそもそも不自然だ。中身のない学歴なぞ無意味だと思うのだけれども。週休二日制もよくわからない。義務教育期間を短くした方がさっぱりするのではないか。したくないことはしない方が体に良いと思う。
- 4月29日(火)
利用者多し。レファレンス沢山。きれいなおねえさんがなぜか多い一日であった。
法律書関係のレファレンスがあった。図書館で答えてならないレファレンスに法律相談がある。現在どういう状況で困っているかを長らくお話しくださって、その事例に具体的に対応した本はないかとの質問であった。素人が聞いてもどうやらこの方に有利になりそうな状況にないのではあったが、個別の事例にあてはまるような本はなく、またやや特殊な事柄でもあったので、J-BISCで検索してもほとんど本がなさそうであった。「市が無料法律相談というのを開いていますので、そちらにまず行かれてはいかがでしょうか。そこでどうしたら良いかをお尋ねになるのがよろしいかと思いますが」と答える。実際にその方が困っていることは間違いないわけで、こうしたレファレンスは本を見つけることができない割になんだか時間がかかるのであった。
- 4月25日(金)
館内整理日。6月に書架を増やす為、どこにどんな本を置くか、現在あるソファはどうするか、と悩む。
開架が現在本だらけ。4月は利用がやや少ないせいかもしれない。本の上に本が横になっている。一日休館してそんな状態ではまずい、と少し残業して書架整理。とりあえず書架の増える6月までもたせねば。が、本はずっと増え続けるのであった。「買いすぎだ」との声もある。出すぎでもあると思う。いずれにせよ本棚よりも本が多くなる日は遠くない。どこの図書館でも問題となっている事柄である。
- 4月24日(木)
今日も小学生の見学。大人数の学校だったので心配だったが、割と静かに終わった。小学生からの質問は楽しい。「図書館はどんな仕事をしているんですか」って、案外大人にも知られていないかもしれない。
午後からカウンターのローテーションを組む。来週からゴールデンウイーク。
- 4月23日(水)
小学3年生の見学がはじまった。今年から開館前に来てもらうことにし、担当職員が早出。午前中にも利用者が多くなってきたため、どうしようか、と話しあった際、若い職員が皆、早出をしてでも見学をしてもらおう、との意見だったのだ。3年生というのは図書館を利用しはじめるのに良い歳だ、と思う。今から利用しなくとも、図書館についていろんなことを知ってもらい(閉架があることや特別資料室に江戸期の資料があること、プライヴァシーの保護のこと、閲覧席の使い方のこと等など)、頭の片隅にでも残しておいてもらえると良いな、と思う。
- 4月22日(火)
ブックポストへの返却図書550冊ほど。割と少ない。
明日からの小学3年生の見学の準備。
図書の見計らい。
パンフレットが毎日沢山郵送されてくるのでほったらかしておくと、すぐにたまってしまう為、こまめにチェックした後、再生用回収。分館に勤務していたときは毎日送られてくるパンフレットが楽しみだったのだが、本館で一般書担当となってからは分館の数倍の分量に悲鳴を上げている。出版点数が多いのだなぁ、としみじみ思う。
- 4月20日(日)
やはり宿題の調べものの中学生多数。ばたばた。
大学生の調べもの、社会人の調べものも多く、閉架と開架の行き来で足が痛くなった。
登録者も多数。このまま利用者が増え続け、職員数が増えないのであろうなぁ、などといつものように考えるが、そんなことを考える間もないほどばたばたであった。
- 4月19日(土)
困った中年女性が来た。閲覧席で仕事をしておられる様子なので、「館内の資料はお使いになられますか」と尋ねると、「使いません」とのことだったので、「一昨年から閲覧席は館内資料の閲覧に限らせていただいております。以前は利用の制限をしなかったのですが、学習やお仕事だけでのご利用が増え、資料を見る為のスペースがなくなってしまったため、申し訳ありませんが、閲覧以外のご利用はご遠慮ください」と説明したのだが、「十年ぶりに来たのだから使っても良いでしょ。もう次からは来ないから。今は空いているのだから構わないでしょう。混んできたら帰るから。家に大きな机がないのだから仕方がないじゃないの」と大きな声で主張なさる。「何年ぶりにいらしたのであっても皆さんにそのようにお願いしています。今は空いているとのことですが、制限をしない時には空いているから、ととても沢山の方が利用なさったのです。原則は館内資料の閲覧に限るということですのでご了解いただけませんか」と言うと、「いいわ。市長さんと話をするから」と言うので、「市長だろうと議員だろうとどなたと話をしていただいても構いません。市報にもお願いはすでに載せてありますし。ただ飽くまで原則は館内資料の閲覧に限らせていただくということです。ご理解ください」とその場を去ると、さらにカウンターまで来て、「十年ぶりに来て、空いた席を使ってなんでいけないの。すぐに終わったら帰るから」と繰り返す。埒が開かないので、「以後そのようにお願いします」と今回は黙認し、説明を投げた。ところがこの方、すぐには帰らない。三十分おきくらいに職員が交代で見にゆくと、あとからあとから閲覧利用者が沢山いらっしゃる。館内資料を使わない利用者が来た時に注意をするとなれば、またこの人に説明をせねばならないな、などと気が気でない。が、皆、館内資料の利用者。注意の後四時間くらいして帰っていただいたようだ。やはりいくら大声で謎の主張をされても説得をしておかねばならないとつくづく思った。「十年ぶりに来て休館日だったら、十年ぶりなんだから開けてくれとおっしゃいますか」「大きな机がないから仕方がないということならば、大抵の方は使えることになります。こんな大きな机は普通の家庭にはありません」と、これだけで論破は可能であることはわかっているのだが、こう言ってしまうと揉めるに決まっているのだ。そもそも「この机は館内の本や新聞を見るための机です」という看板が机の上に置いてあるのに、平気で使っていて注意をすると「市長に言いつける」と言い出すのだから普通の人ではないだが。しかし何かというと我を通そうとした末に、「君は名前はなんという。よく覚えておく。市長にも言っておくからな」などとわけのわかんないことを言う人たちの頭の中はどうなっているのだろうなぁ。市長は自分の為にいる、議員は自分の為にいる、内容の検討はしないが、私に都合のよい人に投票する、という人物が案外世の中に多かったりしたら怖いだろうなぁ、などと思ったりした。
中学生の調べものの宿題が出ていて、ばたばたする。一学年皆に出ているらしいので明日も混雑することであろう。
- 4月18日(金)
毎週の仕事なのだが、ローテーション表作成がしんどい。
登録者が多い一日だった。登録者が増えるということは、貸出冊数が増えるということでもある。利用は伸びる一方。職員は増えない。
- 4月16日(水)
開架の書架がいっぱいである。閉架へうつしてもうつしてもすぐいっぱいになる。この季節、いつもよりも貸出が落ちているのかもしれない。6月には新しい書架が入る予定。
カウンターに赤ん坊を気楽に乗せる母親が久々にいたので、「カウンターは机と同じですので、お子さんを乗せないでくださいね」と言うと、ものすごい表情で睨みつけられる。もしかするとこの人は机に腰掛ける生活をしてきたのかもしれない、とも思う。借りていた本を返却台に返すのに、棚に垂直に立てずに横積みにしてもいた。和本ではないのだが。子供はいったいどのように育つことであろうか。将来が楽しみである。
漢籍についてのレファレンス。私が読めるわけではないのに調べ物のお手伝いができるのは不思議。「おお、それだけわかれば助かります」と言っていただくことは司書にとって至上の喜びである。
人手不足について館長と少し話をする。どこの課でも似たような状況だ。市全体が不景気だ、とのこと。金がないのならば、市が儲けてはどうか、と話す。赤字のところも多いとのこと。とんとんにしてゆくか、ほかで黒字を出すようにすれば良いのではないか、とも話す。これからはそうしたことを考えてゆかねばならない、と意見の一致。が、こんな話をしていたとて職員が増えるわけではない。
- 4月15日(火)
電波系の方が久々にいらっしゃった。春だなぁ。対応に時間がかからなければユニークな人とのやりとりは結構楽しかったりするのだが。
このホームページをご覧になってメールをくださった「図書館友の会」の活動をなさっている方から会報誌をいただきました。耳の痛い話が沢山。図書館のボランティアのこと。臨時職員のこと。結局は正規の司書が全然足りないことが原因。行政側は「それで進んでいってできているのだから良いではないか」との認識。確かにどこの課も人手不足ではあるのだろうけれども、利用者がいくら増えてもそれに応じて職員が増えないのでは、真っ当な仕事をして利用者に喜んでもらえるようになればなるほど大変な状況になるわけで、手を抜かないとバカを見る、ということか。どうかしてるとしか思えない。
- 4月13日(日)
今日もお祭りの日なので、利用者が多くなかった。が、レファレンスや書架案内、閉架資料の閲覧、新規登録がかなりあり、ばたばたはしていた。やはり日曜日である。乳幼児、幼児があまり暴れない一日であった。
- 4月12日(土)
お祭りの日なので、利用者が少ない。山車が図書館の近くを通るとき交通規制で車が通れないのを知っている人は来館しないのであった。
しかし、それでも3000冊ほどの貸出。やはり土曜日である。
- 4月11日(金)
受付のローテーションを組む。平日四人休むと三交代にしないといけない。休館日と休業日が一致していないから、一人が月に三回か四回は必ず休まねばならないわけで、毎日誰かが休むことになり、ローテーションを組むのがなかなかの大仕事なのであった。せめて二交代で回るくらいの人員が欲しいぞ。
図書館見学についての打ち合わせ会。今までで一番すんなり終わった。あと二週間ほどで楽し恐ろしい見学がはじまる。
- 4月10日(木)
明日行われる小学3年生図書館見学の学校との打ち合わせ会の為の打ち合わせをする。今月末から市内全小学校から児童がバスに乗って見学に来るのである。本とはじめて出会う年頃の子供達に図書館の使い方を説明できるとても良い行事。今回で五回目。突拍子もない質問が出たりして楽しみなのでした。職員数が少なくてかなりばたばたするのが難だけれども。
図書館の歓送迎会。前館長の挨拶がとても良かった。
- 4月9日(水)
朝、ブックポストへの返却本1200冊。昼まで仕舞い終わらなかった。
利用者多し。春休みが終わったのに多い。暖かいからだろうか。
- 4月6日(日)
雨降りなのに混む。
新しいアルバイトに窓口に座ってもらう。閉架に資料を仕舞う仕事も説明する。
久しぶりに閲覧席についての質問。以前の状況を説明すると納得していただけた。「この図書館を良いと思っているのですよ。これからもがんばってください」と言っていただけた。ありがたいことだ。
- 4月5日(土)
新しいアルバイトの学生が来る。貸出の窓口で貸出処理だけして、レファレンスなどは正職員のいる隣の受付に案内してもらうというのが主な仕事となるのだが、なかなか重要な問題のからむ業務でもあり、気をつけねばならない点を説明。プライヴァシー保護、延滞資料のある利用者に貸し出さない、本人の貸出券のみしか使えない、こちら側のミス、利用者側の勘違いなどなど、簡単に説明できることだけで一時間くらい。いろいろなトラブルに即座に対応できるようになるまでには三年くらいかかる。本来は慣れた司書が出るべきなのだが。
雨降りだというのに利用者多し。書架案内がかなりの件数。
館内呼び出しの依頼電話が数件。「一図書館員から見た日本」にも書いたが、プライヴァシー保護のため、呼び出しは緊急の場合以外断っている。どこにいても連絡が取れて当然と考える人の多さはなんなのだろう。もちろん必要なこともあるわけだが、そんなに連絡しないといけないのかな、とか、ひとりでいるのを邪魔されたくない時はないのだろうか、などと昨今の風潮を見てときどき思う。私は自分の携帯電話を持つことは恐らくあるまい。
- 4月4日(金)
相変わらずばたばた。
昨日できあがった統計プログラムを最終チェック。途中のチェックを若い職員にまかせておいたのだが、ものすごい落ちがあったのでSEに連絡。
「図書館史」に整合性のとれていない箇所がある、と役所のある課長から連絡があり、確認すると、あるページに載っている日付と別のページに載っている日付が異なっていたりする。古い資料の記述がまちまちなので、細かく見たつもりでいたのだが、最近のことがらにも同様のことがあったのを見落としていたのだ。大失敗である。
来週のカウンターローテーションを組む。土曜日までの分をなんとか昼休みを二交代で組めた。
- 4月3日(木)
調べものや問い合わせの多い一日であった。
年度はじめはばたばたである。経理関連の処理やら書店への連絡などで忙殺される。その合間にレファレンスがはいる。統計プログラムなどの修正に来ているSEに確認を求められるといった風でどたばたじたばたであった。
- 4月2日(水)
午前中、受付。登録者が多いのは引っ越してきた人などがいるからなのだろうか。って、引っ越してきてすぐに図書館で登録する人が多いというのも不思議だからそういうわけでもないのだろうなぁ。
ない本を問われる。ないことを知っているから、それはシリーズなのですが、数年前に出たきりで、次の巻が出ていないのですよ、と答え、念の為、J-BISC(国立国会図書館所蔵和書目録CD-ROM)の画面を示す。ある市の区史や、各県史といったシリーズで、何年か前に途中まで出て刊行中止になったり、長い期間があいている資料
はすでに発行されている、と思うのが普通の人の感覚である。が、まだ出ていなかったり、今後も出なかったりするからこわい。
午後、分館分の本棚のことで業者来館。「図書館史」を配布に回る。
- 4月1日(火)
新年度。まだ春休みなので利用者多し。普段の火曜日よりも職員が三人少ないため、ばたばた。
新館長来る。
今年度は本棚を購入するので、仕様などの相談のため、業者に連絡。
「図書館史」、寄贈先に発送準備。細かい仕事が多い。
親子連れの利用者がものすごく多い。子供に注意しながら、静かに早く帰る親子。走り回る子供をほったらかしにして、長々と自分の本を選んでいる母親。様々である。
10年ほど前に来たきり、久しぶりに来たという利用者が、「随分様子が変わりましたね」とのこと。開館当初は空間が多く、書棚に余裕があったのに、今は書架だらけ。本だらけ。様子は随分変わったのであった。空間が欲しいが、建て直さないとどうしようもないし、当然職員も必要である。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]