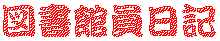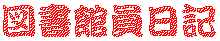
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 3月31日(月)
昨日はグランパス対大分トリニータ戦。一番前の良い席を取れたので喜んでいたのだが、瑞穂陸上競技場は前の方には屋根がないのであった。しかし、攻撃的でつなぎの美しいサッカーは観ていてわくわくする。マギヌンのシュートはすぐそばで見ることができた。試合開始前、マギヌンに声をかけたファンに、「がんばります」とにこやかに返していた。ブラジルから祖父母がきていたとのこと。良い試合であった。
書評の宿題が終わると次の書評の準備をせねばならない。仕事を持ちながら週一とかの書評を書いている人たちはいったいどのようにしているのであろうなあ。朝から晩まで本を読んで映画を観て何もしないでお金が入ってくる仕事はないものであろうか。って、ないな。蛭子能収作詞の、ムーンライダーズが歌った『だるい人』という曲があって、「金さえあれば四十代。ああ金が欲しい。自由が欲しい。何もしたくない」という箇所があるのだが、実にそんな気分の昨今である。
- 3月29日(土)
気がつくと年度もおしまい。今日から三連休の私。俳句の同人誌に書評を書かねば、と思いつつ、なかなか書かずにいて、年度末の慌ただしさで何が何やらな状態の中なんとか過ごす。
今週の出来事。あやしい書名と著者名の本を、それらしきタイトルの本を閉架から持ってきて利用者にみてもらおう、とぱらぱらすると執筆者の一人が利用者の書いてきた名と一致。多くの執筆者がある本についてすべての情報が入力されているわけではなく、利用者の話を真に受けて漢字入力をしたら決して出てこない本を探すという仕事には司書の専門性が生かせるな、と思ったのであった。
『スルース』を観る。マイケル・ケインとジュード・ロウが火花を散らすような演技。ハロルド・ピンターの脚本にしてはひねりと結末があっさりしすぎていたかな、と思わぬでもないが、それは欲張りな感想かもしれない。この二人を観るためだけに出かけても惜しくはないと思う。
- 3月18日(火)
休み。『ノー・カントリー』を観る。おしまいがあまり好きではないが、面白い作品。場面のひとつひとつがとても美しい。ハビエル・バルデムが怖い。どこかで観た役者だな、と調べるとペドロ・アルモドヴァル監督の『ハイヒール』や『ライブ・フレッシュ』に出ている。以前はもっと細い感じだった記憶が蘇る。いかにもアカデミー助演男優賞の演技。なぜだか全盛期のコント55号の萩本欽一演じる人を思い浮かべてしまった。不条理な人物が自分の論理で淡々と過ごしている、なんてことは別にいまや不思議ではないのだが。
- 3月17日(月)
昨日、一昨日とばたばた。年度末である。
『ダージリン急行』を観る。ほのぼのとした映画。兄弟の個性がそれぞれ強烈で良かった。
書評の本を決めたのだが、どうもいまひとつ気乗りがしない。以前は稀代の文章家であったはずのひとの文章が良くなくなっているのは悲しい。
- 3月12日(水)
朝、ブックポストに1400冊返却されていた。その処理が終わった時点でなんとなくよれよれになった私。歳を感じたのであった。
- 3月11日(火)
『迷子の警察音楽隊』を観る。かわいらしい映画。イスラエルに演奏旅行に行ったエジプトの警察音楽隊が迷子になって一夜を過ごすというだけの話なのだが、実によくできている。映像がきれい。
- 3月10日(月)
昨日の夜、無言電話。ふうむ。
名古屋シネマテークに『雪の女王』と『鉛の兵隊』を観にゆく。隣の隣におばあさんと未就学の孫らしき二人連れ。ルビのない字幕のアニメーションであったが、割と静かに観ていた。『雪の女王』を観るのは何度目だろう。歳のせいか、話の甘さが気になった。『鉛の兵隊』ははじめて観た。美しいアニメーションであった。
行きに、ちくさ正文館に、帰りにウニタ書店に寄る。『公共図書館の論点整理』(田村俊作、小川俊彦編 勁草書房)という本が私が書こうかなと考えていた論文を書くのに使えそうで気になったが、なんとなくあまりこのところ書くつもりがなくなってきたので、買うのを止した。澤誌の書評に取り上げる本をぼちぼち決めねば、と思いつつ、なかなか決まらない。なんとなくこの頃、書評を書くために本を探したり読んだりしている感じがして、これはこれで面白いのだけれど、少し疲れる。
- 3月8日(土)
開幕戦である。ストイコビッチ監督がどんなサッカーを見せてくれるのか、とわくわくして出かけた豊田スタジアムは少し寒かった。竹内彬と小川佳純の若手二人が楽しみ。バヤリッツァは素晴らしい選手である。今シーズンは期待できそう。
- 3月7日(金)
年度末である。なんとなくばたばたとして過ぎてゆく。
目の端で年輩の利用者が借りてゆくのが文学全集であるのがわかり、古い全集は閉架書庫にありますので、またお尋ねくださいね、と声をかけると、字が大きいのはあるのかね、と問われる。そのひとが借りようとしているのが、ほるぷ出版の『日本の文学』であるのがわかり、これは文学全集のなかで一番字が大きいので、それ以上大きなのは大活字本しかありませんが、個人の全集ならば、かなり大きめのものがありますよ、例えば谷崎とか、と言うと、ちょうど谷崎で探しているものがある、とのこと。うちにあるのは今のところ出ている最大の30巻本ではなく、その前に出た28巻のものなのですが、と言い、タイトルを聞き、「ああそれはかなり晩年の作品ですね」と答えると、「詳しいね」と言われる。世界的に著名な文学者の長編小説がいつくらいに書かれたものかくらいは知っていないと公共図書館の司書でござい、とは言えない気はするが、日本の図書館の現状ははなはだこころもとない。該当の巻を出すと、「索引はないのかな」との質問。「30巻本についてならば文学綜覧シリーズでわかるのですが、28巻本のはないのですよ。タイトルを言ってくだされば出してきますよ。これ、小説が発表年代順で編纂されているので、だいたいの年がわかれば見当がつきますし」と答えると、「ならば巻を遡ってゆけば新しい順に読めるね」とお客さん。「そうですね。この巻の前に『鍵』が入っている、という風です」と言うと、「ああ、そうしてゆこう」と喜んで帰ってゆかれたのであった。2002年のレファレンス講習の講師をした際、図書館員は営業をしてゆくべき、と話した。それはつまりこうした実践を指す。資料と人を結びつけるために何をすれば良いかを常に考えて動く。その知識を蓄えるために日々何をすると良いかを頭のなかに転がしておくのが司書の訓練。ってことがわかったのは最近で、私は中学生くらいの時からそんな風に日常生活をたまたま過ごしているだけだったりするのであるが。
東野圭吾のある本の返却時に、「これって犯人が書かれていないのでしたよね」と言い、「解決編が何かにあったはずです」と言ってしまってからそれが何にあったかを忘れていることを思い出した。今は推理小説というジャンル自体を全く読まなくなってしまった私だが、彼の二つの解決編のない小説の犯人を当てっこする遊びを昔、アサヒネットでしたことがあった。どちらも私は当てたのだったが、内容は見事に覚えていない。利用者が知りたがったのでインターネットであれこれ調べると文庫版に入っていることが判明。しかし当館にはない。一般のひとのサイトに解決編が載っているところがあるようなので、それを説明してお茶を濁しておいた。帰宅後、その頃のメールを探して読む。とんでもない推理をしたひとがいたりして盛り上がったことを懐かしく思い出す。ひどい推理をしたひとからたまたま電話があり、その頃のことを少し話した。この小説を幾人かに勧めて推理をはずすのをメールで読んで面白がっていたな、と9年前の穏やかな日々にしばらく戻っていた私であった。
- 2月29日(金)
ひさびさに団体貸出の配本に出かける。体力が落ちていることがはっきりわかる。階段がまったくないところに何箱か本を運んだだけで息があがっていたのであった。歳である。
- 2月28日(木)
気がつけば2月もおしまいが近づいている。なんとなく焦りながら仕事をしていた1日であった。
斎藤由香の『猛女と呼ばれた淑女』を読む。参考文献に彼女のお父さんの茂吉四部作がないのが気になる。まさか彼女のおばさんにあたるひとについてお父さんがどう書いていたのかを知っていないままこの本を書いたのではあるまいな、などと意地悪なことを思った私であった。よそのうちのことなのでどうでも良いといえばどうでも良いのであるが。彼女のお父さんの躁鬱が69年にはじまった、というのが興味深かった。それより以前に睡眠薬を常用していたことを別の作家が書いていたので、あの大作を書いていたときもそうだったのかな、と思っていたのだ。斎藤輝子はテレビで幾度か観、二人の息子さんの文を読んでいたが、随分知らないことも多かったのだな、とこの本を読んで思った。37キロの小柄なひとだったというのには驚いた。
- 2月27日(水)
長らく映画を観ていない。
先週も土日は混んだ。
高齢のかたからの漢籍についてのレファレンスがこのところ多い。大漢和辞典、中国学芸事典、文学綜覧シリーズの『世界文学詩歌全集』などを探すのであるが、なかなか見つからない。困るのが、解釈が知りたい、というケース。どこかで額にかかっていた文の、などという場合などがしばしばあるが、これが難しい。ってことは、これに通じたひとは良い商売ができる、という話でもあるなあ、などと、考えたり。
ひさびさに夜中に電話が鳴ってすぐに切れる。このところ猫のノラも午前2時、3時あたりに暴れるようになった。春である。
- 2月22日(金)
変わったレファレンスがいくつかあった一日であった。探しにくかったのが、チェコのマリオネットの写真が載った本。とりあえず館内で1冊見つけ、国立国会図書館でNDCから探してみてそれらしい本を県内の図書館から相互借受することとする。京都の豆人形についての本、というのも難しかった。人形とか玩具はある分野においてはやたらと本があり、ないとなるとまるでないのが面白い。
- 2月21日(木)
火曜の朝のブックポストには800冊ほどの返却があった。昨日と今日は比較的平穏。
明治雑誌新聞文庫で複写した郷土関連の新聞を著作権の確認をした上で複刻したひとが来館。1ヶ月文だけを複刻したのだが、この新聞だけで1年以上出ており、その後違う新聞も出ていて、明治新聞雑誌文庫で現在はすべてマイクロ化されていると教えてくださる。これをあればレファレンスにかなり役立つなあ、としばらく考えていて、帰宅後思い出したのだが、県図書館が確かマイクロを揃えたはず。そういえば図書館員の重要な役目として、利用者に、うちの図書館にはないのだけれど、世の中にはこうした資料があり、それを使うとこんな調べ方ができますよ、という説明をする、というのがあるわけだが、こんなふとした話を覚えておき、探してみたり、資料に加えたりする、なんてことを日々行うのも司書としての生活での心がけではある。私の場合、気になっておちつかない、ただの性格であり、なんとなく覚えているのは因果なサガみたいなものなのであるが。
- 2月18日(月)
先週は木、金、土、日の4日で貸出が1万5千冊を超え、ばたばたと過ぎた。
朝、皮膚科へゆく。老人性乾癬の痒みはおさまってきているのだが、痕は3月にならないと治らないとか。年々ひどくなるらしい。すっかりぢぢいである。
午後、図書館問題研究会のミニ研究集会にゆく。この団体の集まりに出かけたのははじめて。ATTTのファンだという変わったひと岡崎のHさんの発表と名古屋のホープSさんの発表があるので行ったのだった。Hさんは落ち着いた発表で、YAの活動報告をした。驚いたのはSさんの話。児童担当である彼は、「なんでも聞いてください」と掲示してあるけれど、ほんとうに子供からの質問に答えられるのかを自問し、小学校の教科書を読んで、単元ごとに関連する資料を拾うという作業をしはじめたとのこと。授業に関連した質問や調べ学習のために来館する子供がこれだけ多いのに、今まで公共図書館で働くひとからこんな視点出てきたことがあったっけ、と唖然とした私。目から鱗が落ちる、とはこういうときに使う言葉であるなあ、としみじみ感じたのであった。あとで尋ねると彼は名古屋市で使っている教科書すべて(算数は買わなかったとのこと)を自分で買い、読んで考えると言う方法をとったという。教科書を蔵書とし、単元と資料との対応表を排架することにより、小学生だけでなく、一般市民にも小学校でどんな勉強をしているかを示すことができ、また、学校で調べきれなかった子供に公共図書館での利用を促すことともなる。Sさんは現在の小学校で教えていることは生涯学習とつながる方法であり、今までとは別の日本人を作ろうとしているように感じられると話していた。図書館で働きはじめて3年目とのことであるが、地に足がついた仕事をし、大きな視野でものごとを捉えている。日本の未来は暗くないかもしれない、という気がした私であった。
- 2月14日(木)
朝、1600冊ブックポストに返ってきていたとのこと。貸出は4200冊。ばたばたと過ぎた一日であった。
昼休にラジオから大瀧詠一の『ブルー・ヴァレンタイン・デイ』が流れていた。どうもヴァレンタイン・デイは苦手である。チョコレイト会社の陰謀だったはず、とウィキペディアを見ると、とある製菓会社のキャンペインから広がったらしいことが書かれている。この会社は、1950年代に大きな事件を起こしていて、70年にそれを認めている、と調べていてなんだか背筋がぞっとした。
平良夏芽さんのスピーチを日本人全員が聴いたほうが良いような気がする私。人殺しをするためだけに鍛えられている人達の存在自体が誤りである、との認識をどこかで忘れてしまっていた私に気づいた今日であった。
- 2月13日(水)
『ひげがあろうがなかろうが』(今江祥智作、田島征三絵、解放出版社)を読む。めちゃめちゃおもしろかったのであった。
- 2月12日(火)
ロイ・シャイダーの訃報。朝日新聞の取り扱いは少し小さい、と感じる。代表作は『ジョーズ』となっていたが、あの映画の主役はサメだった気がしてしまう。『オール・ザット・ジャズ』について触れてほしかった。
- 2月11日(月)
一昨日、雪のため来られなかったひとが多かったからか、今日も混む。調べもののひとがかなりいて、閉架の図書の利用もたくさんであった。
- 2月10日(日)
昨日、雪のため来られなかったひとが多かったからか、今日は混む。かなりよれよれになったのであった。
- 2月9日(土)
大雪。近所の人が車できたものの、駐車場にまで車を入れることができず、職員数人で手伝うなどという事件があったりもした。
長靴を探していてロッカーの上のものを動かしたところ、カップヌードルの缶詰が発見された。変人の上司がいた2000年に購入し、2010年になったら食べるように、と指示した上で後輩にプレゼントした品。すでに8年も経ったのか、と時の流れを思ったり。
帰宅するしばらく前に雪は雨に変わり、道はなんということもなくなっていた。
- 2月6日(水)
昨日来館したお客さんと『実録連合赤軍』の話を少ししたせいか、休みの今日、観にゆきたくなり、出かける。そのひとは初日の舞台挨拶を観たとのこと。映画が終わり、電気がつくとそのひとがいた。2回観る価値のある映画ですね、などと話す。愛知県図書館にゆき、あさま山荘事件の犯人少年Bの手記を閲覧。
レファレンス探検隊にゆく。クイックレファレンスでのF本さんの出題は、JAS規格が何に載っているか。はるか昔、利用者に尋ねられた記憶が蘇る。果たして何に載っていたのか。答えを聞いて思い出した。そのときは見つけられなかったのだった。農林水産省の省令なのだから現行法規総覧などにあるのは当たり前なのになぜ気づけなかったのか、と今ごろ反省。架空人物についてのS田さんの問題が興味深かった。本当に架空である、と突き止めるのはかなり難しいのである。作中人物の場合、モデルがいたりして、それが本当にモデルなのか、という問題になったりするわけで、しかし、尋ねたいのがモデルでなく、本人かどうかといったあたりだけであれば、そういうひとはいない、と言えるのであるから、ううむ、と、私の中でしばらくこの件がぐるぐるとした。
- 2月5日(火)
とある全集になにが収録されているかが一覧になっている資料はないか、との問い合わせ。日外アソシエーツの文学綜覧シリーズにあるはず、と案内すると、そこを見たのだがとのこと。第一期から第三期まである日本の個人文学全集の何期にあたるかというところがわかるかどうかがミソ。私は第二期の発行年が92年か3年であり、その全集が出たのはその1年後あたり、と、だいたいのところが読めたため、第三期の内容総覧を見ると果たしてすぐに見つかる。お客さんは、あれ、おかしいな、と首をひねる。「これが商売ですので」と笑い、種明かしをする。
- 2月3日(日)
『サラエボの花』を観る。なんとも重い映画。私の好みではないが、良い作品であった。
『越境者松田優作』を読む。松田優作のはじめの妻である松田美智子がドキュメンタリー作家であるのは知っていたが、これほど冷静に抑えた筆致で関わりの深かった人物を描けるひとであることに驚く。もっとあからさまに書きたいだろうなあ、と読んでいて苦しくなるような箇所がある。私は名古屋の白川公園で鈴木清順監督の『陽炎座』を上映したときの松田優作の舞台挨拶を見ているのだが、この映画での演技に悩んだことが書かれていて、その挨拶の意味を思ったりもした。松田優作ファン必読の書。
- 2月2日(土)
今日から3連休。昨日までの数日間の仕事はなかなかばたばたであった。
朝、『アメリカン・ギャングスター』を観る。上手い役者2人の共演は贅沢。良くできた娯楽作であった。リドリー・スコット監督の作品ということで松田優作を思い出す。
書評の締切が終わると次の書評の締切が気になる。本について話す友達がほとんどいなくなったことに気づく。そうしたやりとりをしていた友達が忙しくなったり、環境が変わったり、死んじゃったりしたのだなあ、と思う。
- 1月28日(月)
『ぜんぶ、フィデルのせい』を観る。主演の女の子がかわいい。キューバ革命で国をおわれた家政婦が、「ぜんぶフィデル・カストロのせい」、と言うセリフがタイトルになっている。スペインのフランコ独裁反対運動をしていた姉の夫が死んだのを機にチリに出かけた弁護士とその妻が活動的なコミュニストとなる話なのだが、その娘が主人公。70年代はじめのフランスが舞台。図書館が出てくる場面もある。
- 1月21日(月)
びっくりした話。国はアメリカのために沖縄の海岸線を全部なくすらしい。
『スウィニー・トッド』を観る。ティム・バートン監督らしい作品。
トサケンにあれこれ書いているのだが、頭の中が取り散らかるような感覚に襲われる。私は24年にもわたって公共図書館について毎日あれこれ考えていて、自分のなかではかなり飽きてもしまっているのだと気づいた。どうにかなりそうなところと、どうにもなりそうにないところも随分わかってきているな、という気分になる。公共図書館というのは名前は一緒でも、しっかりとした司書が多いところもあれば、本に何の興味もないひとばかりで運営されているところもあり、利用者に対しての説明を丁寧にするところもあれば、訊かれてわからないと、「わかりません」と素直に答えるところもある。これらを全部まとめて論じるのは無理なのだけれども、現在、かなり統一されている点は貸出重視、利用者の要求重視という路線。それを私の勤務先ではつきつめる形で20年近くおこなってきていて、その限界がなんとなく私のなかでは見えてきている。
- 1月20日(日)
大学生がレポートを書くための本探しに来館。中小規模の公共図書館にはなさそうな分野であり、提出期限にも間があるので、大学で雑誌論文を探す方法を示す。この頃こうした学生が以前にも増して増えている。本が図書館にある、とか、あの図書館で探せばなんとかなる、という認識があがってきているのであろうか。それで実際何とかなる場合もあるが、大学生の調べもののほとんどはなんともならなかったりするのだが。
- 1月19日(土)
混んだり空いたりの波が激しい日であった。ばたばた。
- 1月18日(金)
CDの選定発注、図書の見計らい。暮れに貸し出した図書の返却期限設定日が今日であったため混む。なぜか登録も多い。
- 1月17日(木)
トサケンで昨日起きた事柄のおおもとが気になり、ログを遡る。物好きな私である。数年前、mixiに入った頃、まだ全部のコミュニティを読むことができたので、毎日全部読んでいて疲れてしまい、ここからは逃げたほうが良いと考えて逃げた。どうも世界のすべてを知りたいという欲求が私のなかにはあるようなのだが、頭がついてゆけるはずもなく、身体もついてゆけないし、そんなこと誰にもできはしないのであった。小さな世界があって、そこの全てを知って、あとのほかの世界はない、ということになっていたらかなり幸せなのではなかろうか、などとヘンなことを思ったのは小規模のパソコン通信に参加していたとき。小さなパソコン通信局を友達が開いた時、「神様の気持ちが少しわかったような気がします」とメールしてきたことがあったのを思い出す。いくつもの仮想世界があるところに迷い込んだら出られなくなる可能性があるな、と10数年前に感じたのだったが、今やなにやらわからぬことになってきている。トサケンの現在のログの数は300弱。電脳筒井線の1日分くらいなのだな、と遠い昔を思い出す。あそこを過ごせばあとはどこでも怖くないし、物足りない。なんだかあれからのずっとが余生であるかのようにも感じてしまう。しかし人生は死ぬまで続くのである。
川上未映子の芥川賞受賞は喜ばしい。
- 1月16日(水)
視聴覚資料の選定発注と図書の発注作業などをする。さしたる事件はなかった。
- 1月15日(火)
『グミ・チョコレート・パイン』を観る。柄本佑演じる山之上が強烈であった。原作のキャラクターもすごいのだけれども。かなり原作とは異なる映画。高橋ひとみと山崎一が大橋くんの両親役。高橋ひとみみたいなお母さんがいたらヤだな、と思った。ケラリーノ・サンドロビッチらしい細かな笑いが沢山詰まった作品。ただなんというかこじんまりしている感じを受けた。じんとする箇所も少し。
- 1月14日(月)
比較的空いていた。
視聴覚資料の選定、発注作業。老眼のため、細かな目録やサイトの文字を見るのがつらくなってきている。
- 1月13日(日)
昨日とは逆に私が受付にいる時間は空いていた。貸出は4500冊ほど。ばたばたしていた。
- 1月12日(土)
貸出が4000冊ほど。私が受付に入っていた4時間半にこのうちの2700冊貸出をしたのであった。殺人的な状況であった。登録もなぜか多かった。よれよれになって帰宅。
昨日、去年登録し、こないだ入れることになった図書館サービス計画研究所の全ログを頭から読み、挨拶文を書いたところ、去年著作権講習会を一緒に受講なさった方から丁寧なご挨拶を頂戴したのであった。この図書館サービス研究所、略称トサケンは大学図書館関係者が多いようである。まだあまり動いていないけれど、何かがどうかなってゆくかもしれない感じの場所。
- 1月11日(金)
気がつけば1月も半ばになっている。年末年始は沢山本を読むことができた。
年明けのブックポストには思ったほど返却図書がなかった。10年ほど前には3000冊以上返ってきたこともあったが、今年は700冊ほど。開館した日には異様なほど利用者がきていたものだが、そんなこともなく、割と平穏な状況。年末に借りる分の返却日設定を眺めにしていることも影響している。ただ、調べものの利用者がなぜか多く、ばたばたしている。
去年の今ごろにも書いたが、BSの『日めくりタイムトラベル』が面白かった。日大闘争のフィルムに若いひとたちが衝撃を受けていた。
8日に名古屋シネマスコーレで若松孝二監督の『実録連合赤軍』を観た。あさま山荘事件の時は小学4年生だった私は、トイレにもいけやしない、と野次馬的性格の母に感化され、学校から走って帰宅し、夜遅くまでテレビを眺めていた記憶がある。あの鉄のでかい玉が出てきたときのことをよく覚えている。総括、粛正について詳細を知ったのは関連図書を読んだことによる。忘れたい、なかったことにしたいような陰惨な事件。それを真正面から逃げずに描き出している映画。すぐそばの町に連合赤軍のメンバーが住んでいたことを思い出した。あの時代にその年齢で、どこかにきっかけがあったら、彼らのなかの誰かに自分がなっていなかった可能性がありはしないか、などと考え込んでしまった。また、今と70年前後とで一体何が変わったのか。問題が表面に出なかったり、しっかりとまずい事柄はあるのに知らぬふりをだけだったりはしないのであろうか。実にスリリングで、美しく、あとで効いてくる良い映画だった。地曳豪の森恒夫、並木愛枝の永田洋子、ARATAの坂口弘ら見事なキャスティング。細かな取材、調査と、少しのフィクションによって重厚な作品となっている。あとあとまで残る映画となることであろう。
新風舎の倒産には驚いた。これから団塊の世代が退職し、自費出版希望者が増え、儲かってゆくであろうなあ、と思っていたのだったが。新風舎文庫はなかなか良い本もあり、残念である。
草思社の倒産にもびっくり。最近でもベストセラー、ロングセラーがあったのにどうしたことであろう。
- 12月31日(月)
パソコンが不調となる。文を書いている途中で凍る。これもどこかで凍るかもしれない。さすがに10年めのパソコンである。
22日にオールナイトで『ゴッドファーザー』3部作を観た。アル・パチーノの上手さといったらない。ひとりで来ている女のひとの多さに驚く。パート2の途中でいびきが響く。まわりをみると沢山寝ている。電気が点いて振り返ると、2つの席をつかって思いっきり寝ている若い娘さんがいたりもする。
冬休は利用者が多かった。いつもどおりばたばたとした年末。
岩国市長の辞任はニュースになっていたが、詳しい中身の話があまりなかった。日米関係の根幹に関わることではないのであろうか。ここを読んでいるとバランスがとれる気がする。
CDを選ぶのが大変な仕事となっている。すでに沢山のCDがあるため、当然のことながらそれ以外のものを選ばねばならない。コレクション全体を俯瞰し、足りないものを探す。ミュージシャン、作曲家についてよく調べねばならない。そうして発注すると品切のものがいっぱい。インターネットの店と大きな店以外ではCDを買いにくくなっているのである。流通というものはしかたがないのであろうが、こうした現象が本について起きるとしたら、と考えるとかなり怖い気がする。音楽はネットで試聴できるから良いのかもしれないけれども。どうもなんとなくすっきりしない気分が残るのはレコードの時代の感覚を私がひきずっているからかもしれない。CDよりレコードのほうが音が豊かである、と今でも思っているし。
25日に『魍魎の匣』を観た。原作を読み終えたとき、うわあ、と思った記憶があり、前作『姑獲鳥の夏』の映画も悪くなかったので期待していったのだったが、おしまいのあたりがなんだかなあ、といった感じの作品であった。
気がつけば今年も終わり。読んでくださったかたがた、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
- 12月18日(火)
午後、研修。図書館関連の法令についてであったのだが、図書館法の第13条の規定「公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置く」とあるのを真っ直ぐに読むと、図書館を指定管理にできないのではないか、というお話があり、そりゃそうだよなあ、と目から鱗が落ちた。講師は20年ほど前、行政改革の担当をしていて、図書館を民間委託しようと考え、当時の文部省に尋ねたところ、教育委員会が館長や職員を任命しなくてはいけないと図書館法にあるので、委託は適当ではない、との見解を示されたとのこと。するのであれば構わないが、問題が起きる可能性がある、とも言われたとか。その後図書館法は変わっていないにもかかわらず、文部科学省は指定管理を認めている。
文化庁の見解では1953年製作の映画の著作権は保護されていることになっており、ホームページにもそう書かれていたが、最高裁は消滅しているとの判断をした。省庁の見解がいつも正しいとは限らないようである。
- 12月17日(月)
久々に近所の古本屋さんにゆく。20年ほど前によく古本屋さんで見かけた本が、最近出た書評の本に載っていたので、ないかと尋ねると、その本ならば何冊でもある、と倉庫から出してくれる。「ほら、あの、臙脂色の箱に入った、帯のない」などと、本の形態をよく記憶している私。ただのマニアであるな、と我ながら思ったり。
浦沢直樹と和久井光司の『ディランを語ろう』を読む。この和久井というひと、名前を知らずにいた私だが、なんだか見たことあるな、と写真を見て思う。screenのヴォーカル。ああ、ムーンライダーズファンのバンドであるな、と気づく。名古屋大須のELLでのライブをよく覚えている。85年だったか。対バンが、ケラリーノ・サンドロビッチ(当時はケラ)がヴォーカルをしていた有頂天で、客のほとんどは有頂天を目当てにしてきていたのでscreenの演奏に乗るひとは少なく、彼はかなりイラだち、水を口に含んで客席に吐くというパフォーマンスをしていたのであった。そんなことを覚えていてほしくないだろうなあ、と思うが、変なことだけ記憶に残る体質の私である。ディランの『ライク・ア・ローリング・ストーン』を人気絶頂の頃の浦沢直樹が聴いて、自分に向けられた歌であったのか、と感じたという話が良かった。どこかまで登ったから、と、これでよいのだ、などと思ってはいけないことをひとは忘れがちである。
- 12月16日(日)
混む。貸出が5000冊を超えた。
年賀状を書かねば、とか、選句をせねば、とか、書評の締切が、とか、あれこれ考えていると気が重くなり、早く寝る。
- 12月15日(土)
土曜らしく混む。2週間後が年末の休みになるため、貸出期間を伸ばしているので、それを知っている利用者が沢山借りてゆくのであった。延滞督促電話。
- 12月14日(金)
視聴覚資料の発注、延滞督促。CDが買いにくい、というか、品切が多い。大型店とWebでの販売がほとんどとなり、CD会社の在庫がないという状況らしい。CDを20年以上前から購入している我が館。欠けているものを探したり、ミュージシャンの評価を確認したり、かなり手間をかけて選ぶわけだが、発注すると品切との答えがやたらとくると仕事が無駄となってしまうわけで、なんとかならぬものか、と思うが、そうした世の中になったのである。流通の変化はまだこれから先も様々な分野で大きく動いてゆくことであろう。それが果たして何かを生みだすのかどうか。
検証がなされないまま、ずるずると進んでゆく事柄がますます増えてきている。電気の普及、交通の発達は人類にとって何をもたらしたのであろう。便利になるのが善であり、不便は悪であるとの考えは果たして正しいのか。長生きはそんなに良いことか。などということを考えているうちにみんな死んでゆくのであろうなあ。
曇り空の合間から流れ星が見えた。空がいつまでも空であるのは大したことである。
- 12月13日(木)
昨日休んだせいもあってばたばたと一日が過ぎる。
明日はふたご座流星群がいちばんよく見える日とのことだが、曇るのではあるまいか。
- 12月12日(水)
天野天街監督の94年作品『トワイライツ』を上映するというので愛知県芸術文化センターで開かれているアート・フィルム・フェスティバルへ出かける。ドイツのオーバーハウゼン国際短編映画祭とメルボルン映画祭短編部門でグランプリを受賞した作品。なんともノスタルジックでメランコリックで、35分とは思えぬ密度。
- 12月10日(月)
田壮壮監督の『呉清源』を観る。映像はとてもきれいだったが、南果歩が出てきたあたりからの話の展開がよくわからない。なんだか不思議な映画であった。
- 12月9日(日)
利用者が、「この本ありますか」と尋ねる60年ほど前に出た本が国立国会図書館にもない。著者名が怪しそうなので、この本の情報が載っていた資料は何ですか、と尋ねるとうちの参考資料コーナーにもある本であったので確認。やはり著者が違っている。原綴りしかないため、利用者は訳者とタイトルを控え、タイトル中にあった名を著者と誤ったようである。その著者はとても有名な哲学者であり、全集も所蔵しているため、少し安心。国立国会図書館のOPACで著者名を入れ、書名の断片を入れて検索すると、訳者は異なるが全集に入っていることが判明。これはレファレンス講習の問題に使えそうだなあ、などと考える。今日はほかにもなかなか厄介な調べものがあり、楽しい日であった。司書が必要なケースというのは間違いなくあるのではある。
なかなか混む。延滞督促電話をかける。発注するCDを選ぶ。CDジャーナルを見ていると、老眼が確実に進んでいる事実と向き合わねばならない。
- 12月8日(土)
ジョン・レノンの命日。6年前にレノン忌の句を作ったのを思い出す。そういえば生の句会に出たのはそれきりである。ついこないだのような気がするのだが。
私が受付に出ている時間だけ混んだ気がしたのは被害妄想であろうか。ばたばたであった。督促電話をかける。この仕事、明らかに正義がこちら側にある、とはっきりしている珍しいもの。私はかなり好きだったりする。
- 12月7日(金)
開架に出ていないといけない感じの資料がいつの間にか閉架にあることに気づく。利用者から出してください、と言われぬと気づかずにいたりする場合がある。カウンターに司書もいないといけないのはこんなことがあるから。しかし、こうした場面が多いわけではないのが難。公共図書館に司書はなぜ必要か、というのは大変な命題であると思われるのだが、多くの司書は向き合っていない。数年前までのレファレンスは大抵、ウィキペディアに書かれているくらいわかればそれで良い、といった感じのものであったのであることに気づかねばなるまい。分類、目録の仕事がなくなり、インターネットが普及している現在と15年前とで司書が何か進歩したのかといったあたりについて考えねばならない時期はもはや過ぎてしまったような気がしないでもない。
督促電話。
- 12月6日(木)
選書をする。視聴覚資料選びをする。延滞督促電話をかける。
- 12月5日(水)
郷土資料はどこまでが郷土資料なのかが難しいところである。先日、日本の古本屋で、私の勤務館あたりの地名を書名欄に入れて検索をしていたら昭和のはじめに書かれた紀行文が載った有名雑誌があったので購入。著者は画家でもあった水島爾保布。このひとの息子は今日泊亜蘭さんである。当時の様子がよくわかり、絵も載っていて、字数は少なくても立派な郷土資料である、と良い本を買ったなと感じたのであった。このあたりの資料は素人ではなかなか見つけられないのではなかろうか、というか、こうした検索をそもそもあまりしないであろう。と、自慢する私。また、郷土出身の作家の恋人がいた女子高等女学校の文集がなぜか大量に古本屋さんから出たりもしていて、この学校があったのも勤務館の町なので購入。この作家の恋人は3人知られているのだが、そのうちの2人が同じ本に文や短歌を載せていたりもして、また、昭和初年の町の様子もわかり、これもいかにも郷土資料であった。問題となるのが、どの地域までを集めるか、どれくらいの量がそのエリアについて書かれていると集めるのか、といったあたりである。ご当地ミステリがテレビドラマにしやすいこともあって20年ほど前から流行っているのだが、明らかに訪れていなくて誤りがあったりもするような小説のなかに少しリアルな地名が入っている、といったような本をどうするかで悩んだりもする。ともあれこの時代にこの町について書かれたということならば良いではないか、50年経てば、そんな本があったのか、と驚くし、郷土史研究者の役に立つかもしれない、などとも思わないでもないわけで、そんなあたりが、なかなか難しいものである。
昨日休んだので仕事がなかなかたまっていたのであった。延滞督促電話を50軒ほどかける。
- 12月3日(月)
名古屋シネマテークでカウリスマキ監督の特集をしていて、今日は『マッチ工場の少女』。この作品を初めて観る私だが、既視感がある。70年代半ばの『ガロ』の感じと似ている気がする。鈴木翁二とか安部慎一とかつげ忠男とか、そんな雰囲気とどことなくなのだけれども。おしまいの方の展開が良い映画であった。
- 12月2日(日)
さすがに日曜日である。混む。新着資料の分類作業、新刊書の発注などをする。延滞督促の電話をかける。
- 12月1日(土)
分館に勤務。子供が工作をするのを手伝う。私がその年齢の頃であったら決してできなかったに違いない工作を楽々とこなしてゆく子供ばかりで、いまひとつ面白くなかったが、怪我人も出ず、無事に終わる。
- 11月30日(金)
休み。『僕のピアノコンチェルト』を観る。頭から尻尾まであんこが入ったたい焼きのような作品。しっかりと作られている。
- 11月29日(木)
ひさしぶりの友達からメールがくる。このところめったにメールがこないので、うれしい。スパムメールは日に100通以上くるが。
としょかんだよりの選書完了。なんとなくばたばた。
- 11月28日(水)
視聴覚資料選びをする。
句会でご一緒している方から句集をご寄贈していただいた。とてもきれいな本。形の良い佳句が多く、わあ、こんなすごいひとと句会をしていたのか、と気づく。
- 11月27日(火)
ぼちぼちと混む。としょかんだよりのための選書をする。
- 11月26日(月)
三木聡監督の『転々』を観る。三浦友和、オダギリジョー、小泉今日子が上手いのは今更言うまでもないが、吉高由里子がわけのわからない役を見事に演じていた。私がいちばん可笑しかったのは、コスプレの店で、それ何のコスプレ、と問われた三浦友和が、「つげ義春の『池袋百店会』の・・・」と答えたところ。『亡き王女のためのパヴァーヌ』について、どんな下手くそが弾いても良い曲は良い、というのも名言。映画のなかとラストでムーンライダーズのファーストアルバムから2曲使われていたのも印象的だった。
つげ義春と言えば、『李さん一家』の李さんの妻のひとと貫地谷しほりがとても似ていると思うのは私だけであろうか。
- 11月25日(日)
書評原稿締切日。出勤前になんとか書き終える。
新着資料の分類作業と新刊発注をする。日曜なので混む。帰るとよれよれになっていた。
- 11月24日(土)
土曜の割に空いていた。
としょかんだよりのための選書をする。
- 11月23日(金)
さすがに祝日。なかなか混む。
図書館を紹介してくれる記事の校正をする。
- 11月22日(木)
休み。もうじき締切の同人誌の書評を書かねば、とじたばたしてみたが、あまり進まず。
- 11月21日(水)
選書をする。今日もあまり混まなかった。
- 11月20日(火)
それほど混まない平穏な一日であった。
- 11月19日(月)
『タロットカード殺人事件』を観る。スカーレット・ヨハンソンが見事なコメディエンヌぶりであった。しかし、ウディ・アレンはどうしてしまったのであろう。良いところが少ない映画であった。体力が落ちているのかな。
- 11月18日(日)
貸出が5000冊を超える。登録が30人ほど。このところずっと返却よりも貸出のほうがずっと多い。どうなっているのであろうなあ。
- 11月17日(土)
さすがに土曜日である。ばたばたと過ぎる。
昨日申請した私立大学図書館の資料の複写がもう届いた。
- 11月16日(金)
一昨日、国立大学法人図書館に雑誌論文の複写を申請したのだった。以前、公立図書館に複写申込をする際には、必ず手書きで沢山の書類を書いて郵送し、届いたことを知らせる通知が大学からあり、それから振り込み、しばらく後かかなり後になってやっと届くという風であったが、今はメールで申し込み、先に複写物を送ってきてくれてあとから振り込めば良いとのこと。恐ろしい変わりようである。ところが申請した大学の所蔵情報を良く確認していなかったため、欠けていた号を申し込んでしまっていたのであった。そこで私立大学の図書館に依頼することにした。以前、私立大学には大抵断られていたため、多少知った方がいる館に電話をし、その人に話しはじめると、担当にかわります、と、あっさり言われてしまったので、うろたえる私。担当の方に訊くと、FAXで申し込めば振替用紙と一緒に複写物を送ってくださるとのこと。時代は変わってきているのである。
公共図書館の司書の専門性は雑誌論文を大学や県立図書館に申し込む仕事や、自館の郷土資料を充実させたり、レファレンスにこたえるあたりにはまだあるのだよな、などと思う。大きな本屋さんやインターネット書店であればどこにでも売っている一過性の本だけを扱うのであれば、それほどの専門性は要らないし、そのなかでの専門性を語っても図書館関係者や図書館利用者以外のひとへの説得力を持たないということに気づかねばならない、と私は考える。
- 11月15日(木)
県のレファレンス講習の講師がなんとか無事終わる。文学関連の問題についての説明の際、試みに純文学の文芸誌4誌をあげてみてください、とふたりに質問してみたが、出てこなかった。司書が知らないくらいなのであるから、文芸誌は読まれていないのであろうなあ。レファレンスが得意になるためにどうしたら良いかというようなことを以前はよくわかっていなかった私であったが、ここ数年、そんなことを意識してきたので、なんとなくわかるようになってきた。書架整理のとき、仕舞った本の近くの本を気にする、とか、書誌事項が無闇に気になるのでついつい奥付を見てしまう、といったような癖が私にはあるのである。そうしたことが日に日に積もって、書誌事項に詳しくなってくるらしい。今回の講習では今ひとつ笑いがとれなかったのが少し残念であった。
帰りに東海道線が動いていないことに愕然とする。架線の電信柱にトラックがぶつかった、とか。大回りして帰る。
- 11月14日(水)
貸出が4000冊を超える。ばたばたであった。
大学生が図書館関連の授業の宿題でインタビューにくる。図書館の最終目標は、と問われ、老若男女、皆が気楽に使える図書館に、というようなことを言うが、実のところ公共図書館の最終目標ってなんなのであろうなあ、と考え込む。世界征服とかではなさそうだが。
- 11月13日(火)
朝、眼科へゆく。黄斑部変性の検査。前と変わっていないとのこと。安心する。瞳孔が開く目薬を注したため、本が読めないし、光がまぶしい。歩いていると気持ちが悪い。耳がなんとなく変なのと喉が痛いのとで耳鼻科へゆく。帰宅後もまだ眼が変。しばらくして普通の世界が戻ってきたので、よその図書館へ出かけ、明後日の講習の準備。静かで落ち着いていて良い図書館。利用者はこれくらい来てくれたらそれで良いのではないか、と感じる。公共図書館はところによってあまりに違う。同じような方法論(貸出を増やし、市民の要望にこたえる)で進んできたはずなのだが、どうしてこんなにも差があるのか、と考えたりもする。
- 11月12日(月)
『Onceダブリンの街角で』を観る。余韻の残る良い作品であった。歌はあまり私の好みではなかったが。
明々後日がレファレンス講習の講師の日なので準備。
- 11月11日(日)
貸出が約5300冊、返却が約4700冊。ばたばたであった。貸出が増えているのはなぜであろう。
- 11月10日(土)
混む。DVDの選択作業をする。
県図書館からレファレンス講習の回答集が送られてくる。5問出題し、3問答えてもらうことになっている。誰がどの問題に答えたかの一覧がついていて便利。しかし答えた問題が偏っているのはなぜであろう。あるところまでインターネットで調べて挫折し、ほかの問題にうつったのではないか、などと想像したりする。5日後が講習の日。あれこれの作業はなかなか苦しいが、楽しみでもある。
- 11月9日(金)
新刊を選ぶ。
分類目録作業について考えをめぐらす。取次会社が発売するMARC(機械可読目録)の普及により、電算入力を各館で行わなくとも精度の高い電算目録を持つことができるようになったのは15年ほど前から。MARCのなかには分類番号も入っていて、分類作業をそれぞれでせずとも良くなった。以前は1冊ずつの本と向き合い、分類をし、目録カードを書き、カードを複写し、分類目録、書名目録、著者名目録のそれぞれの抽斗の正しい位置に排列するという仕事をしていたのが、MARCを買って、そこに記されている分類番号を付し、カードは書かず、電算にローカルデータを入力し、MARCのデータをくっつける、という仕事に変化したのである。分類や目録の作業に携わるためには専門能力が当然必要であった。素人がみたら、なんだか難しそうなことをしているなあ、と思えるくらいにはなんとなく玄人ぽかったのである。インターネットがなく、国立国会図書館の電算データもなかった時代には、利用者が尋ねる本がそもそも出版されているかどうかすら確認する手だてがなく、司書の記憶や検索能力が問われたわけだが、今、その段階で苦労することはない。利用者の断片的な話から1冊の本を探して提供すると、「まるで魔法みたいですね」と言われたりしたものだが、今はインターネットで断片を入力すると魔法みたいに見つけられるようになっている。こうした変化を公共図書館の職員は認識し、検証してきたのかな、と私は自分を省みつつ思うのであった。
- 11月8日(木)
昨日のレファレンス探検隊での懇親会、Kさんが歯痛で休んだことが少し話題となっていた。30歳を過ぎて、急に歯が痛くなるってどういうことなのかな、と、とある女のひとが話していたのであった。Kさんは昔風の硬派みたいなところがあるので、あるいは歯を磨いていないのではないか、と私は想像したのであった。80年代半ばに野坂昭如が、糸井重里が司会をしていたNHK教育『YOU』という番組で男らしさ、といったようなテーマの回のゲストとして出演していて、「男は歯なんて磨かなくていいんだ。私は戦後歯を磨いていません」と発言し、スタジオがどよめいたことがあったのを思い出した。
DVDを選ぶ。利用者、なかなか多し。
- 11月7日(水)
休み。『続ALLWAYS』を観る。泣かせようとする手が見える感じがして厭だな、と感じた私がひねくれているのかもしれない。「本誌初の芥川賞か」と雑誌の表紙にあるのはおかしくないか。賞の詳細について調べるつもりがないのであれば、いっそ架空の賞名にしたほうが良かったのではなかろうか。
晩、レファレンス探検隊にゆく。3名以上の著者の場合、目録規則で、はじめの1人のみを書き[ほか]、とするということを、目録カードを書いた世代の司書は知っているのだが、電算データ、それもフルマークしか扱っていない司書は知らないのである、と気づいた。古い、手入力の時代の書誌データと現在の形の書誌データが異なっている場合があるのは当然なのだが、以前のものをひどく不便、と感じる、あるいはその時期の規則を知らない人たちは誤ってデータを読んでしまう、というわけで、なんだか、これって図書館の世界だけの話でなくって、まるでどこかに完璧な世界があるかのような誤解になりたって色々なものが作られてゆくようで、あれこれ考えていたら頭がくらくらしてきた私であった。全部ができあがっている状態なんてつまんないに決まってる、と感じるのは私だけなのであろうか。完全な何かを作ろうと大勢が考えているのが現代なのかなあ。止したほうがいいと思うが。
- 11月6日(火)
書籍のパンフレットがたまってきているのに目を通す。老眼が進んできているので辛い感じである。そろそろ眼鏡を買わねば。
- 11月5日(月)
しばらく前から手の甲、足、尻などが痒いので近所で評判の皮膚科にゆく。評判なだけあって病院に入ると狭い待合室に50人くらいのひと。帰ろうか、と考えたが思いとどまる。湿疹の状態を診た医者は、「乾いた肌やねえ。年齢は45。はあこれは歳や」と言う。加齢により皮膚が乾き、冬になるとできる湿疹とのこと。このところ老眼も進んできたし、しっかりと老人力がついてきた感じである。
- 11月4日(日)
グランパス対ザスパ草津を観に瑞穂へゆく。吉村圭司のうそみたいなシュートが決まった1点目と、もっとうそみたいなシュートが決まった3点目にぞくぞくした。ザスパが『草津節』を応援歌にしているのに驚いた。名古屋も『名古屋囃子』を応援歌にしてはどうか、などと思った私。
晩に、15日に行うレファレンス講習の課題の回答集がメールできた。ぱらぱらと眺めると楽しい。疑い方の甘い答えがあるとうれしくなってくるのは私のひとの悪さに起因しているのであろう。調べものの基本はすべてを疑うことである。そんなふうにして毎日を過ごすとろくな人間になれない気がするが。
- 11月2日(金)
カウンターローテーション作成。新刊書発注。明日、明後日と休みなので、ばたばたと過ごす。
- 11月1日(木)
午前、カウンターに入ったのち、沢山予約のかかっている本の一覧を作る。新刊書見計らいもする。午後、分館勤務。空いた日であった。客層が本館と微妙に違うのが面白い。
- 10月31日(水)
月のおしまいは仕事がたまっている。
- 10月30日(火)
ヘアスプレーを観にゆく。ミシェル・ファイファーが良かった。基本的に私は太った人を好きではないのだが、なかなか楽しい映画であった。
- 10月28日(日)
混む。2週間前に混んでいたのだから当然ではあるが、5000冊というのはなかなか厳しいものがある。新刊書の発注作業をする。
- 10月27日(土)
混む。さすがに土曜である。
- 10月26日(金)
カウンターローテーション作りと図書館だよりに載せる本選び。ばたばたと一日が過ぎる。星の名前についての調べものがしばらく前にあった。こんなときは野尻抱影の著作の目次をぱらぱらと眺めれば出てきたりする、というのが昔の対応であった。その分野についてあまり書いたひとがいないのを知っているのは司書の仕事として重要なのであるが、今はインターネットのせいで、そうした知識を蓄積する必要がなくなってきているように思われる。どんどんと物を知らずに済む世の中になってゆく。
友達から気の毒なメール。しばらくものを考えられなくなったのち、神について少し考えをめぐらす。
- 10月25日(木)
休み。刈谷市美術館に岸田劉生展を観にゆく。朝早く出かけたので空いていたが、帰る頃にはひとだらけであった。麗子ちゃんにはなんだか惹かれる私。
雨宮処凛の『プレカリアート』を読む。非正規雇用のひとが増えているのは知っていたが、こんなすさまじい国になっていたとは驚きである。なんということになってしまっているのであろうか。日本をこんな国にするために過ごしてきたのか、と暗澹たる気持ちになる。
- 10月24日(水)
昨晩無言電話。この頃件数が増えていて良い感じである。
朝、分館とのラインが繋がっていない、インターネットも使えないという恐ろしい状況であったが昼頃復旧。いまやインターネットが使えないことはかなりとてつもない事態となるのであるが、これは正しい状態なのであろうか。つい10年ほど前はこうではなかったのだが。何かが出現し、それに頼り切る。電気、ガス、鉄道、自動車。なくても死にはしない、という点について日々よくよく考えたほうが良い気がする。柏崎の地震のあと、テレビ番組で山の中に住むおばあさんへの取材で、「水を遠くまで汲みにいかなければならなくなった」とそのおばあさんが語っていて、あとは小屋に貯めた薪で炊事をしているのを映していた。この人のライフラインは電気ガス水道、ではなく、水道であり、少し先の川まで汲みにゆけばとりあえず、それ以前の生活ができるということに私は驚いたのであった。人間の進歩というのはいったいなんなのであろうなあ。
- 10月23日(火)
ぼちぼちと混む。CDを発注する。
- 10月22日(月)
『ファンタスティック・フォー/銀河の危機』を隣町の映画館で観る。ほかに誰も客がおらず、私一人だけの貸切状態であった。なぜあの人が生きていたのかが気にかかるところではあるが、良くできたエンタテインメント。
宿題の書評をなんとか書き終える。
- 10月21日(日)
早朝、というか夜中に無言電話。このひと、何か私に用があるのではなかろうか、と気になる。寝ていたノラが起きだして暴れる。
朝空いていたので平穏な日になるかな、と思っていたら午後から混む。4500冊ほどの貸出があった。延滞督促の電話をかける。
- 10月20日(土)
混む。新刊図書の分類作業をする。
- 10月19日(金)
小便器から水があふれる、という大事件があった。男子トイレの水があふれた床を通って小便器へとたどりつくまでがなんとなく『ポセイドン・アドベンチャー』みたいであった。
民主党石井一議員が冬柴国土交通大臣へ質問したP献金の問題を扱う大マスコミは深夜のよみうりテレビだけだったのかなあ。800万人を敵にまわすのは恐ろしいことであろうから仕方がないのか。亀田父子よりもずっと重要なことがいっぱいあるはずだが。チョムスキーがプロスポーツを害毒のように論ずる気持ちがわかるこの頃である。多くのアメリカ人がアメリカンフットボールの難しいルールをみんな知っているのはおかしい、と彼は語っているのであった。何かから目を背けるための報道ばかりをしているうち、マスコミは何を流すべきか否かもわからなくなってきているのではあるまいか。インターネットは武器となる、と、10年ほど前に友達が言っていたが、ある意味においてはそうかもしれないな、とこの頃少し思えてきた。しかし、読み手が何をどう選ぶか、ではある。このあたりの仕事に司書は関わるべきであろうが、どのような要望にどこまで応えるか、といった点が問題となろう。
- 10月18日(木)
名古屋のTさんに電話で質問。Kさんが担当というので尋ねる。てきぱきと回答をしてもらうのが心地よい。
- 10月17日(水)
朝早く、というか、深夜無言電話。
ぼちぼちと混む。
- 10月16日(火)
休館日あけなので混む。CDの入力作業をする。
- 10月15日(月)
珍しく映画館にゆかない休日であった。宿題がたまっている。
- 10月14日(日)
混む。貸出が5000冊を超えると身体が大変である。よれよれになる。
- 10月13日(土)
混む。ひさびさに視聴覚資料の受付に入ったら、壮絶な混み方。何をしているのかよくわからなくなってくるほど。
延滞督促電話を100件ほどかける。予約をしているのに沢山予約のかかっていることがわかっている本を延滞しているなどという悪質な人もいたりする。貸出重視、リクエスト予約重視で進んできた日本の公共図書館活動がないがしろにしてきたのが、延滞利用者に対するペナルティである。『市民の図書館』には貸出期間停止などのペナルティを課すべきとあるが、関東圏の図書館には延滞を幾日していても(それが1年とかであっても)、ペナルティを課さず、別の本の貸出を認めているところがある。それで貸出が増えた、と喜んでいるのは、普通に返却期限を守っている利用者との平等性の観点からどうなのであろうなあ、と思う。
私の勤務する館では1冊でも1日でも遅れている本があれば貸出不可としている。また、家族の券は本人が来館していなければ利用不可ともしている。多くの館では本人の券で延滞があっても、来館していない家族の貸出券の利用を認めているため、実質的に延滞があっても貸出可というルールになっている場合が多い。これはインチキであると私は思うが、そうは思っていない館が多いのか、仕事が増えるので止しているのか。仕事は実に増えるのである。来ていない家族の券を使えない旨の説明をする必要があるというのもなかなかの仕事であるし、返却処理のミスがまったくないわけではないため、「返しました」と言われるとリアルタイムで書架を探す必要がある。本が棚に見つからなかった場合は、返したとの利用者の言葉を重んじ、トラブル票を作ったうえで、貸出をしている。多くは利用者の勘違いで、帰宅するとその本があったりするのであるが。また、時折はこっそりブックポストに当該図書が返ってきたりもする。貸出をやめちゃう、というのはどうなのかな、と最近の私はしばしば空想する。
- 10月12日(金)
休み。朝、『長江哀歌』を観る。私の好みではないとわかって観た映画。映像が美しかった。昼ご飯を食べたあと、白川公園にゆく。晩にパレスチナ・キャラバン公演『アザリアのピノッキオ』があり、テントが張られている。実行委員に大学時代の知人2人の名前があったので、いないかな、と思っていってみたのだった。驢馬が木に繋がれていたり、サックスの練習をしていたり、アコーディオンの練習をしていたり、といかにもテント芝居の前といった雰囲気でわくわくしてくる。時間に余裕があるのでミリオン座で『パンズ・ラビリンス』を観る。こないだ観た『題名のない子守歌』でも思ったが、不自然なほどなかなか死なない登場人物って結構いるものであるなあ。おっかなくて懐かしくてなかなか良い映画だった。
大須のあたりをうろうろしていたら、なぜかF本さんと遭遇した。危険なエリアかもしれない。
晩、『アザリアのピノッキオ』を観る。パレスチナの役者4人も出演。字幕が出る。はじめのうちの展開がゆるやか。おしまいのほうはたたみこむように収斂していってエンディングにテント芝居ならではの演出。あまり私の好みではなかったけれど、良い芝居であった。13日、14日にも行われる。そばにやたらと欠伸をするひとがいたり、スタッフが写真をとる液晶のパネルがまぶしかったりして落ち着かなかった。帰りに大学の時の知人、加藤くんと少し話をする。彼は就職活動の時期に、親に、芝居をするので就職をしない、と宣言し、頭をつるつるにしてしまったというエピソードを持っているのであった。20年以上会っていなかったが、元気そうであった。
- 10月11日(木)
山のような予約連絡電話をかける。予約がかかっているのは娯楽読物やベストセラーがほとんどという状況なのだが、ここ30年ほどの日本の公共図書館活動は正しかったのであろうか、とこのところずっと考えている私。電話をし終えるのに1時間半かかった。これとほぼ同じ分はメール連絡で済んでいる。100冊を超えているのであるなあ。延滞督促電話をそのあとかける。くらくらになる。
- 10月10日(水)
アレルギー性鼻炎がはじまったので医者へゆく。
ゆきづまっているレファレンス講習の課題作成をなんとかせねば、と近くの図書館に出かけ、参考資料をテキトーに開くと15分ほどで数問できあがってしまった。この図書館、建物の造りが良く、ただいるだけでなんとなくおりこうになる感じがある。7月10日に出かけたときに良い印象を持ったのであった。知りあいの職員さんがいるのだが、今日はなんとなく誰とも会いたくない気分であった。
- 10月9日(火)
『題名のない子守歌』を観る。私の好みではなかった。
宿題が沢山あるのだが、なかなか片づかない。
- 10月8日(月)
月曜日と祝日が重なる日はそれほど混まなかったのであるが、今日は混んだ。延滞督促電話を沢山かける。
- 10月4日(木)
私が受付にいると混む気がする。延滞督促の電話を50件ほどかける。留守番電話が多くなっている。知らない電話番号からの電話についてはみな留守番電話にしているのであろうか。なんとなく失礼な感じをうける。しばらく前から、長らく待たせた後、「FAXの方は送信してください。電話の方は恐れ入りますがあとからお掛け直しください」とのメッセージを言う電話が増えている。厭な気分になるのは私だけであろうか。ちなみにわが家は留守番電話はない。友達がいないからめったに電話がかかってこないので、何の支障もない。
- 10月3日(水)
人間ドック。身長が大学生の頃に戻り、やや小さくなった。
- 10月2日(火)
午前は本館、午後は分館勤務。朝のうちに片づけねばならぬ仕事が沢山ありばたばたであった。
- 10月1日(月)
このところ宿題が多い。いくつかは片付いたが、まだいくつか残っている。
『エディット・ピアフ』を観る。『Taxi』シリーズや『ビッグ・フィッシュ』のマリオン・コティヤールが実に良かった。薬物中毒になった晩年を演じるために毛を抜いたと、ラジオで聞いた。鬼気迫る芝居。しかし一番背中がぞくぞくしたのは子役が歌うところであった。良い映画だった。
- 9月30日(日)
2時間で1600冊の貸出があったりする。私が受付にいる時間にやたらと混む。5500冊ほどの貸出であった。
- 9月29日(土)
さすがに土曜である。混む。
『澤』に同人一句鑑賞が載る。同誌編集長でもある同人の押野裕さんの句「子の尿の燦々として山眠る」を選んで感想を書いたのだが、おしっこを気にしての文。富士見書房の『俳句研究』が廃刊になったとのことで、今号から高橋睦郎さんの「百枕」が『澤』誌で連載されている。目次に私の名前と高橋さんのお名前が並んでいる。次号からは私が書評「詩文学芸書を読む」欄で連載することになっており、しばらくそういうことが続くのであるなあ、と思うと少し怖くなる。久々に「澤四十句」に選ばれた。こんな句。「この世の終はりに誰とゐたいか夏の暮」
- 9月28日(金)
割と空いていた。選書、リクエスト本の処理などをする。
- 9月27日(木)
割と空いていた。図書館だよりの本を選ぶ作業などをする。
- 9月26日(水)
ブックポストには800冊ほど本が返ってきていた。利用者多し。貸出が3000冊を超える。
- 9月25日(火)
9月のおしまいから10月にかけてはなんとなく気分が重めである。
荻上直子監督の『めがね』を観る。『バーバー吉野』、『かもめ食堂』を好きだったので期待していったのだが、ううむ。悪くはないのだけれど、それほど好きではない映画であった。薬師丸ひろ子が強烈だった。
- 9月24日(月)
混み方にムラのある日であった。くたびれた。
20日に書いた事柄について誤りがあった。『善き人のためのソナタ』と『厨房で逢いましょう』の監督は別人とのご指摘を古い友人で数少ない読者であるひとから頂戴した。『善き人のためのソナタ』の監督はフロリアン・ヘンケル・フォン・ドナースマルク。慎んで訂正します。まるで名前も作風も違っていたのにどこでどう間違えたのであろうなあ。
日本人の税金を使ってインド洋で給油しているアメリカ軍がイラクやソマリアを爆撃しているということは、我々がお金を払って悪くもない人たちを殺しているのであるな、と、しみじみ思う。国内にある基地の維持の為にも随分お金を使っているけれど、そこまで払わないといけないのかどうか。税金、年金、郵便貯金などがどのように使われているかについて多くのひとがあまり興味を持っていない。私も実のところそんなに興味がない。今、私の手元にないお金だからである。このことについての報道がかなり断片的にしかされていなくて、それは恣意的であったりもするからよくわからなかったりもする。本気で調べればもちろんわかるのだけれど、なんとなくケチみたいでするのが厭な行為のような感じがしてしまう。民主党が、国民が支払った年金をほかのことに使わないようにする法案を出す、との話が出てきてはじめて、年金がほかのことに使われていたのか、と言った知人がいたが、そんなものである。しかし、もうじき郵便屋さんのあれこれが変わっちゃうのだよなあ。みんなが変えたいって本当に思ったのであろうか。民営化によって何がどう変わるかを、あの選挙の前に詳しく報道したメディアはあったっけ。自分ちのそばの郵便局がなくなっちゃったり、振込手数料が高くなっちゃったりするかもよ、なんて話をさまざまな新聞があのとき書いていたとしたら、与党が大勝したかどうか。民営になれば儲からないことをしていたら潰れるのだから、どうなるかは想像できるだろうけれども。ところで潰れたらどうなっちゃうのだろうなあ。
沖縄の友達のブログによると、辺野古に動きがあるみたいである。
大勢で同じことをするのが楽しいひとたちが昔からいて、別に悪いことではないけれど、みんなが楽しそうだからきっと楽しいに違いない、くらいにしか思ってないひとばかりだったりするケースもしばしば。幾人もの若者が道行く政治家の名を連呼する映像が実に不気味だった。ファシズムが台頭してきたって何の不思議もない気がする国。様々なことをわかった上で名を連呼するのならば別に良いけれども、みんながしているから、との理由だけでしているとしか思えないような顔つきの若者がいたりもする。ひとりひとりが物事をしっかりと考えるようにならないとろくなことにならないのは歴史を振り返ればはっきりしているのだけれどもさ。小さいうちから英語を習うよりもほかにすることがあるのではなかろうか。ふと思ったんだけれど、英語で考える訓練をすると英米人みたいな考え方になって、世界中の土地が全部自分たちのものになれば良いのに、と夢想するようになったりするのであろうか。って、そんなわけないか。
お金儲けの本の多さはなんだろうか。私が小さな頃の日本ではお金の話をするのは汚いことである、とされてきたのだけれど、今は全然そんなことはないみたいである。なんだかどんどん汚い国になってゆくような気がする。
- 9月23日(日)
比較的空いた日曜だった。さして何事もなく過ぎる。
- 9月22日(土)
比較的空いた土曜だった。さして何事もなく過ぎる。
- 9月21日(金)
宿題がいくつかあるのだが、そのひとつを終えた。
シネマテークで『そして、ブルノーの森へ』を観る。ミステリアスで面白い映画であった。ポーランドの景色がきれいだった。
TOKUZOでPANTAを観る。頭脳警察の再結成はかれこれ20年ほど前であったか。どこにこういう人たちがいたのかな、という雰囲気の方々が名古屋パルコのクラブクワトロにわさわさと集まってきて怖い雰囲気であった。鈴木慶一とPANTAが2人で行ったライブも面白かった。少数ではあったが、目つきの怖い謎めいた雰囲気のお客さんがいたりもした。今回の客席は不思議なほど穏やか。PANTAはしばらく前、TOKUZOでライブをしたとき階段で転んで骨折をしたとのこと。その足のまま芝居『毛皮のマリー』でマリーを演じていたとか。ずっと浴槽に入っているので問題はなかったそうである。
重信房子と書簡のやりとりをしていて、彼女の詞にPANTAが曲をつけた作品が今度出た『オリーブの樹の下で』というアルバムに入っているとのことで、その中から何曲か、と、頭脳警察時代の曲、アルバム『クリスタル・ナハト』の出る前に発売された12インチシングル(懐かしい)『プラハからの手紙』などを演奏した。重信房子の詞に曲をつけるとフォーキーになってしまうとか。PANTA&HALの時代の曲は演奏されなかった。『七月のムスターファ』と『ライラのバラード』が印象に残った。おしまいは寺山修司の詞に曲をつけた『時代はサーカスの象に乗って』。
- 9月20日(木)
今日明日と休みの私。Yohji Yamamotoが名鉄百貨店にうつったとのことなので、行ってみる。見たことのない変梃なディスプレイに笑う。山本耀司自らの指示だとか。名古屋近隣にお住いの方は見るだけのためにも出かけてはいかがだろうか。珍しい服の並べ方がされているのである。長く生きていると色々なものを見ることができる。
名演小劇場で『厨房で逢いましょう』を観る。『善き人のためのソナタ』のミヒャエル・ホーフマン監督の作品。小品だが、変梃な官能性があって面白い。谷崎の『美食倶楽部』を連想したりもした。
柳家小三治独演会を聴きにゆく。15年ほど前に聴いたきり。まくらが長くなったとは知っていたが、すさまじい長さ。演じたのは『蒟蒻問答』と『一眼国』。なんとなく以前のほうがうまかったような気がしたのであった。
- 9月19日(水)
混む。不思議な利用者がきたりもする。
日本図書館協会のメールマガジンによると、「☆子どもの読書活動の推進 1005百万円(今年度771百万円)」だそうである。私は読書推進に対して懐疑的な者である。本を読んで世の中の多くのひとが私のようになったら、と考えるとぞっとする。ならないだろうが。読書欲を増す為には本を減らすことである。終戦直後、本がない時、西田幾多郎の『善の研究』を買うのに行列ができたのはなぜか。何でも良いから読みたい、という状態になったためである。これもあれもそれもあるから、いつでも読める、という状況より、どこにゆくと本というものはあるのであろう、という風になるのが理想的ではあるまいか。私が子供のころ、実はそれに近い環境であった。隣町にしか公共図書館はなく、私は貸してもらえなかった。学校図書館には旧字旧かなの本があったりするのだけれど、面白そうな本はみんな読んでしまった。面白くなさそうな本を読んでみるとやはり面白くない。私の読みたい本はどこにあるのだろうか。本屋さんの本は高くて子供では買えない。ああ読みたい読みたい、と、飢えていたのである。本が沢山あったり、面白いから読め読めと勧めるばかりが読書推進活動ではない気がするが。読む子は読むし、読まない子は読まない。それで別になにがどうということもない。読む大人は読むし、読まない大人は読まないのである。読むといってもトンデモ本やお金の儲けかたの本ばかりだったりする場合もあり、別に読書家であることに意味はないと思うけれども。明治時代から大正の頭にかけての多くの日本の庶民は外国人から見てかなり立派だったようだけれど、本を読んでいたから、ということではないはずである。
- 9月18日(火)
『ミス・ポター』を観る。景色の綺麗な映画。レニー・ゼルヴィガーはとても上手いが、ミスキャストのような気がしないでもない。
- 9月17日(月)
『僕はパパを殺すことに決めた』についての朝日新聞の報道に驚く。家庭裁判所の指示からはじまったことではあるが、出版差し止めもされていない、まだ本屋で買える本の利用制限を図書館がするのはどういう話なのであろうか。国民の知る自由についてまともに考えたことのない人がいっぱい図書館で働いているのだろうな。これからはそういう人ばかりになるやも知れない。
- 9月16日(日)
ばたばたと混む。なにがなにやらわからなくなるほどの利用者の数であった。
- 9月15日(土)
さすがに土曜である。混む。難しいレファレンスもいくつかあった。大学図書館でなければなんともならないものや、英語の文献しかなさそうなものなど。
- 9月14日(金)
比較的空いていた。
電算機のデモ。返却時に借りている残りの書名が出るようにできていて、それは出さないようにできぬとのこと。借りているひとが返しにくるとは限らないわけで、不慣れなひとがカウンターにいる場合、その画面を見て、○○という本をまだ借りていますね、と言ってしまうケースがあろうなあ、と思う。返却を他人にまかしたひとは、その人に何を借りているか知られても構わない、ということか。私の働く館では貸出画面で本人の貸出券をスキャンしたときにしか借りている図書のタイトルを教えないことにしていて、これは大変面倒ではあるが、読書の秘密を守る為に当然せねばならない手間であると考えている。多くの館がこの点について無頓着なのであろうな、多くの図書館利用者がこんなことどうでもいいと思っているのであろうな、と、あれこれ考えてしまった私であった。
- 9月12日(水)
ばたばた。貸出が4000冊近く。土日並であった。朝にはブックポストに1500冊が返ってきていた。本棚がぎゅう詰め状態である。
上司が、「安倍がじいだって」と言うので、思わず「オナニーですか」と返してしまった。それほど驚いた、というか呆れた。元々この政権について何の興味も持てずにいた、というか、ゆくところまでゆくのであろうなあ、国民が選んだ党が立てたのだからしかたがあるまい、と眺めていたが、このわけのわからないタイミングで辞めるとは。
- 9月11日(火)
911で大騒ぎするかと思ったら意外と静か。こんなひどいことをするテロリスト達の国をやっつけるため、給油が必要なのだ、と報道するのではないか、と考えていた私。イラクに向かう戦闘機に給油していることにはなっていなかったのだが、どうなのか。アメリカだけが正義だ、と考えるアメリカ人の多さがそもそもの問題だと思う。みんな元々住んでいた国に帰って、あの土地はネイティヴアメリカンの方々に戻したらどうか。って、無理か。
- 9月10日(月)
ミリオン座に『インランド・エンパイア』を観にゆく。いかにもデヴィッド・リンチであった。もっとひどい終わり方になるのかな、と思っていたら、そうでもなく、なんとなく私はこの作品を好きである。私の好きな裕木奈江が出てくるとは聞いていたが、かなりセリフのある重要な役であってうれしかったのだった。
名古屋シネマテークにガス・ヴァン・サント監督の幻のデビュー作『マラノーチェ』を観にゆく。何の予備知識も持たずにいったのだが、マイノリティとホモセクシャルの映画で、胃が重くなったのだった。映像はきれいだったが。
- 9月9日(日)
夏休以上に混む。貸出が5000冊ほど。閉架の資料の出し入れも多く、くらくらする。なぜか調べものも多かったりする。
- 9月8日(土)
さすがに夏休あけの土曜である。混む。何をしていたのかよくわからぬうちに一日が過ぎる。
- 9月7日(金)
分館勤務。昼間は割と空いているのだが4時を過ぎたあたりから異様なほど混む。
- 9月6日(木)
休み。『Taxi4』を観る。私の好きな署長が大活躍。なかなか馬鹿馬鹿しくて良かった。
- 9月5日(水)
平穏な混み方。普段の図書館といった感じになっている。
宿題が多く、頭の中がばたばたしているが、なかなか進まないのであった
- 9月4日(火)
朝、ブックポストには900冊ほど。どこの図書館もこれほどには返ってこないらしい。ばたばたと一日が過ぎるが、夏休が終わっているのでなんとなく気楽である。
- 9月3日(月)
ツアー2日目。あちこちまわる。感心したのは竹島水族館のアシカショー。ATTTもアシカさんを見習わねば、と思ったり。海辺の文学館はオルゴールの音楽がエンドレスで流れていて、私は途中で逃げ出した。蒲郡プリンスホテルの喫茶店でF本(仮名)さんと向かい合ってコーヒーを飲んだが、女のひとと飲みたかった気がしないでもない。ともあれ無事ツアーは終わる。
- 9月2日(日)
休み。夏休が終わり、気がぬけた感じになっている私だが、今日、明日となごやレファレンス探検隊のツアー。蒲郡の図書館を見学。昔懐かしい感じの図書館であった。晩にはATTTの演奏。宴会場にマイクがあることは聞いていたが、モニタースピーカーがない、という当然のことに気づいておらず、ややパニックになった私であったが、なんとか無事に演奏も終了。名古屋の図書館のTさんはお揃いのTシャツ(ほんとうはあまり着たくなかった私^^;)と、みなさんに配るための小さなうちわを用意。実にマメなひとである。私の作った曲『ゆけゆけF本(仮名)』も好評なようであった。
- 9月1日(土)
休み。名古屋シネマテークで『低開発の記憶』を観る。私の好みではなかった。瑞穂でガンバ大阪戦を観る。見事な負け試合であった。
- 8月29日(水)
中学生の職場体験も今日から3日でおしまい。閉架の新聞について説明する際、またしても第二次世界大戦がいつ終わったかを質問してみる。中学2年生10人のうち10人が知らなかった。昭和20年も8月15日も8月6日も8月9日も。ほんの62年前に自分の住んでいる国がどうされたかを知らない若者がいっぱいいる不思議。気持ちが悪いほどである。英語を小さいうちに習わせるよりも、世界の中の日本についてを学ばせることのほうがよほど重要ではないか。
ランガナタンの5法則をいつも念頭において仕事をしている。5年前、愛知県でのレファレンス講習の講師をした際、図書館員も地道な営業をすべきだ、と言った。書架の間で何かを探しているのではないか、困っているのではないか、と思われる利用者がいたら、声をかけるところから司書と利用者との関係性が生まれるという話。それがランガナタンの5法則の4番目「Save the time of the reader. 」に繋がる。勇気もいるし、ひとつ間違うとうるさく思われるが、数をこなせば上手くなるはず。どんなこともそうだが、はじめないことにははじまらない。参考にするのは服屋の店員さんの声のかけ方。「実は、こんなことを探そうとしているのですが、わかりませんよね」と言ってもらえればしめたもの。「自分で探せそうなので結構ですよ」と言われることのほうが多かったりもするが。小さなところから司書の仕事を知ってもらえるようになるのであるが、その小さなことをせずにいれば知られぬままとなる。私のしている司書という仕事はどんな仕事でどのような意味を持つか。あるいは持たないのか。そんなことばかりを考えている気がする。
- 8月28日(火)
休館日あけにしては空いていた。課題図書の予約キャンセルが多い。どうも私はキャンセルということが好きになれないのだが、このところ増えてきている気がする。国民性は少しずつ変化しているのであろうか。
- 8月27日(月)
『ラッシュアワー3』を観る。真田広之と工藤夕貴が出ているとは知らなかった。ストーリーが無茶。笑える箇所を笑う為の映画、と割り切って観ていれば良い訳だが。イヴァン・アタルが出ていることも知らずにいた。彼の存在感は強烈。
- 8月26日(日)
昨日飲んだ蜂の酒がなかなか強烈であった。口のなかが一日中蜂のにおい。
豊橋市美術博物館に「野田弘志展」を観にゆく。大学の時、朝日新聞に連載されていた加賀乙彦の『湿原』の挿絵で知った画家。写実的な絵を私はあまり好きではないのだが、なんとなくこの人には惹かれる。ガラスケースのなかの絵にむかってストロボを焚いて写真を撮っているひとがいるので、「写真撮影はだめですよ」と注意すると、「どこにも書いてないじゃないか」と言うので、チケットの裏に書かれていると教える。どのみちまともな写真は撮れていないだろうが、非常識なひとがいるものである。こんなときに刺されたりするのかもしれないな、と思ったり。
- 8月25日(土)
今日から3連休。知多市歴史民俗博物館に「板谷波山展」を観にゆく。鳥や花を題材とした美しい造型の作品たち。きれいなものは良い。
夜、瑞穂にグランパス対アルディージャ戦を観にゆく。5対0で快勝。帰りに飲み屋さんで蜂の入った焼酎を飲む。
- 8月24日(金)
もうじき夏休が終わるからか、利用者がやや減った感じ。
夜、名古屋シネマテークに『イラク−狼の谷』を観にゆく。イラクにいる悪いアメリカ人をトルコ人やクルド人がやっつける話。勧善懲悪のステレオタイプの作品であるが、現実にもこれに近いことがアメリカ人達によって行われているのではあるまいか、と感じられ、報道の偏りについて思ったり。アメリカではこの映画、上映されないそうである。役者が良い。
- 8月23日(木)
職場体験の生徒のうち、本が好きそうな子にやや難しい箇所の本の排架を頼むとかなり凝る。
図書館の職員採用試験に書架整理を入れるのは良いのではないか、と感じる。見ていて本が好きかどうかがすぐにわかるのである。排架のルールを知らせずにひと棚をぐちゃぐちゃにして時間を計って並べさせる試験なんて意地が悪くて楽しそうだが、どうだろう。
- 8月22日(水)
中学生の職場体験。午前に5人、午後に5人。図書館や本が好きな生徒と、全然好きそうでない生徒がいて面白い。
ぼちぼちと混む。
- 8月21日(火)
朝、ブックポストへの返却750冊ほど。利用者多し。ばたばたであった。
- 8月20日(月)
『夕凪の街、桜の国』を観る。静かな佳作である。多くのアメリカ人に是非観てもらいたい気がする。はじめのうち、涙が出てきてしまって困った。歳で涙腺がゆるゆるになっているのである。麻生久美子が素晴らしい。子役の頃から好きだった伊崎充則君が太っていたのに驚く。田中麗奈はスターのアウラのようなものが薄くなっていはしないか。中越典子が良かった。
- 8月19日(日)
日曜日の割には空いていた。私が図書館に入った年とその次の年に一緒に出張に行ったりした隣町の年長の職員が来館。今はほかのセクションの管理職とのこと。退職後、どこかの図書館でバイトで使ってくれないかな、などと冗談なのか本気なのかわからぬことを言っていた。専門職制をとっていないが、図書館に就いた職員に夏季講習で司書資格を取るようにしていた市で、彼はかなり図書館について学んでいて、出張に行ったら必ず何か質問をするように、と当時の館長に言われていたため、鋭い質問を浦安でしたりしていた。ビデオの貸出を1985年の著作権法改正以前に行っていたのが全国で私の勤務館と彼の勤務館だけだったため、情報交換をしたり、当時の日図協会長が講演をしたあと、厭な質問を二人で交互にしたこともあった。時の流れは早いものである。
- 8月18日(土)
土曜日にしてはそれほど混まない。しかし、閲覧利用者の多さはなんだろう。外の暑さとも関係しているのであろうなあ。
- 8月16日(木)
夏休も半分以上が過ぎた。利用者多し。
- 8月15日(水)
ブックポストへ返ってきていた本が1549冊。多いときは2000冊を超えていたので、たいしたことはない、とも言えるが、ばたばたであった。利用者多し。調べものも多い。
- 8月13日(月)
名古屋市の図書館のT氏とATTTの練習。6時間ほどギターを弾き歌を歌う。左手がヘンになってくる。譜面台を立て、立って演奏もしてみたり。かなり力を入れているが、はたして当日はどうなるのであろうか。
- 8月12日(日)
比較的混まない日曜。お盆のあたりは平日に混むかわりに土日がそれほどでもないのである。延滞督促電話をかける。
- 8月11日(土)
比較的空いた土曜であった。延滞督促電話を沢山かける。
近くの図書館のひとが来館。あまり話ができなくて残念だった。
- 8月10日(金)
暑い日であった。混む。夏休も半分が過ぎた。
- 8月9日(木)
ばたばたであった。時はこうして流れてゆくのであるなあ。
夜、なにげなくニュースを眺めていたら、長崎の平和宣言のなかに「非核三原則の法制化」の文言を今回入れずにおこうかとも検討されていたとのこと。久間防衛大臣の発言によって入れねばならない、と考え直したそうである。ところで劣化核ウラン弾はどうなのだ。と、また書く私。あの首相は非核三原則の中身をわかって喋っているのであろうか、と不安になるのは私だけなのかな。
- 8月8日(水)
体験学習の中学生が来る。終戦の年を尋ねると4人のうち1人が知っていた。広島に原爆が落とされた日について尋ねると、一昨日あれだけ報道されていたのにこれもまた1人しか知らない。長崎は、と問うと、これも1人。原爆投下について知っていた生徒は自分の誕生日であるからとのことであった。戦争は確実に風化してきている。夏は、くどいくらいの報道でちょうど良いのだ。
晩になごやレファレンス探検隊にゆく。F本さんはしばらく前、メキシコにいったため、ミル・マスカラスのお面をつけていた。今回はコメンテイターであった私。従軍慰安婦への補償の是非についての問題を出したのであった。回答をくださった方が誰も4月27日の最高裁判決について触れていないことを指摘。司書は、大きな、1面に載るような判決の骨子は読んでおくべきではないか、と話す。また、意見が分かれる事柄について回答する際、両極の主張を持つ資料を何冊かずつ提供するのは当然なのだけれども、司書個人としての見解は持った上で、それは出さずにしまったまま利用者と接するようにすべきではなかろうか、とも言う。様々なことに自分なりの意見を持つようにしないと、情報の質についての判断をくだす人にはなれない、と私は考えるのであった。情報の選択、抽出能力は司書の柱となるもの。それをいかに作るのか。実のところ私にはよくわからないのだけれども。
帰りに懇親会。名古屋の若い男の職員と話す。朝起きてゆきたい、と思う仕事でないとできないと考えて、司書になったとのこと。なかなか良い話。
- 8月7日(火)
混む。今週は遅番。夕方からの利用者が実に多い。延滞督促電話をかける。延滞のひとも沢山いるのであった。
- 8月6日(月)
休み。朝、ニュースで広島の式典を見る。首相が非核三原則を守るそうだ。沖縄にある劣化核ウラン弾というのは核兵器ではないのか。メディアはどうしてあれをとりあげないのだろうなあ。多くのひとが知ったら、そんなもの持って帰れ、という話になりはしないだろうか。
- 8月5日(日)
混む。とある事件が起きる。ばたばたであった。
- 8月4日(土)
頭の中を『The end of the world』がぐるぐるしていた一日であった。昨日の少年王者舘の影響。2003年に彼らの『それいゆ』にも使われていたこの曲には中毒性がある。
比較的空いた土曜日であった。調べものは多い。
このところひとがよく亡くなる。小田実、ベルイマン、アントニオーニ、阿久悠。阿久悠の訃報に「昭和最大の作詞家」とあるのが気になる。私にとって昭和最大の作詞家はなかにし礼である。阿久悠が偉大であったことは誰もが知っているし、私も彼の詞に好きな作品が多い。しかし、最大、と書くのはどうか。捉え方によって異なるのではないだろうか。
- 8月3日(金)
休み。名古屋シネマテークで『ストーン・カウンシル』を観る。設定が無茶な作品。モニカ・ベルッチとカトリーヌ・ドヌーブ目当なのでまあ良いが。『素粒子』のモーリッツ・ブライブトロイが渋い役で出ていた。アキ・カウリスマキ監督の『街のあかり』も観る。おしまいのところで泣けてきてしまった。どうして自分が泣いているのかがよくわからない感じ。良い映画を観たときに起きる不思議な現象
晩、大須の七ツ寺共同スタジオで少年王者舘の『シフォン』初日を観る。天野天街ではなく虎馬鯨の脚本。暗い雰囲気の芝居だが、それでも前を向く感じが良かった。友達の杉浦君は三都市公演のうち名古屋と大阪にだけ出るとのことで、それを楽屋落ちにしていた。随分と太っているのに驚いた。一昨年はそれほどでもなかったし、大学生の頃は栄養失調ではないか、と思われるほど痩せていたのだったが。
- 8月2日(木)
夏には子供だけでなく、大人も多くやってきて、新規登録も増える。へんなひともきたりする。暑いことと関係していると思われる。
- 8月1日(水)
中学生の職場体験。去年からの全県挙げての行事で3日続けて働いてもらうのである。主な仕事は書架整理。
やっと8月。利用者多し。
- 7月31日(火)
今週は早番。朝昼はそれほどには混まなくて平穏である。新館見計らい、CDの発注。CDは品切のペースが早くて大変。もうじきこのメディアはなくなってゆくのであろうか。ダウンロードした音はかなりひどく、そればかりになってしまうとなると聴きたくない気がする。
- 7月30日(月)
9月のフォークユニットATTT再結成のための打ち合わせとリハーサルを名古屋の図書館のTさんとで行う。曲目決定。新たに私が作ったテキトーなオリジナルもあったりする。Tさんはノラが破った襖に興味があるようであった。助走なしで1メートル20くらいの高さまでは普通に飛ぶ12歳の猫。
- 7月29日(日)
昨日と同じような感じの混み方。先週と比べると穏やか。
- 7月28日(土)
割と平均的に混む。6時からが怖かったが、それほどでもなく過ぎた。明日はどうなることであろうか。『としょかんだより』をつくる。
- 7月27日(金)
比較的空いていたが、調べものが多い。夏休になると子供達が沢山くるでしょう、とよく言われるのだが、なぜか大人も増えるのである。レファレンスも大人からのものがかなりあったりする。
- 7月26日(木)
夏休をとる。名演小劇場に『チョムスキーとメディア』を観にゆく。わけのわからない若者に言論の自由についての説明をしたり、虚偽に満ちたテレビキャスターにアメリカのした悪い事柄について淡々と尋ねたり、実に根気の良い人であるな、と胸が熱くなった。彼の戦う姿勢には勇気づけられたが、彼が思い描いている未来がやってくる日がくるのかな、と考えると気が重くなったり。
- 7月25日(水)
混む。またしても貸出は3000冊を超えたのであった。何をしているのかわからぬうちに一日が過ぎてゆく感じ。ばたばた。
- 7月24日(火)
混む。貸出が3500冊くらい。登録も多い。早く夏休が終わってくれないかなあ、と早くも思えてくるのであった。
- 7月22日(日)
朝、比較的空いていたので、昨日かなり来館者が多かったからなあ、などと油断していたのだったが、午後から膨大な利用者。午後6時から7時までの貸出冊数が850冊。合計で5372冊。登録者は32人。コピーの申請もレファレンスも小学生の宿題の問い合わせも多く、頭がくらくらしているうちに時が過ぎていったのであった。
- 7月21日(土)
さすがに夏休初日である。貸出が5000冊を超える。登録者も20人を超える。なにがなにやらわからぬままに一日が終わった感じ。
- 7月20日(金)
さすがに終業式の日である。混む。調べもの多し。課題図書への予約が6月のはじめからぼちぼちとあり、すでに夏休中に返ってくるかどうかわからぬものがあったり。
- 7月19日(木)
波があった日であった。混んだりすいたり。
被災地は暑かったとのこと。原発の被害の大きさを語る報道が増えている。
- 7月18日(水)
ばたばたであった。貸出が3500冊ほど。
『日本の活断層』(東京大学出版局)は旧版(1980年)と新編(1992年)とでは活断層の位置が違っていて、原子力発電所が活断層の上に建ったら、なくなったりしている、というのを調べていた利用者が過去にいらした。詳細については尋ねなかったが、学術資料がそんなことになっているのか、と驚いた記憶がある。
ライフラインについての報道によって、柏崎市への電気は東北電力から来ているのがわかるのであるが、柏崎刈羽原発というところの事故については東京電力が語っている。原発に興味のある人は昔から知っているのだが、これは実に不思議な話である。危ないかもしれない施設で作られている電気は遙か遠くへ運ばれ、自分たちが使う電気は別の電力会社からやってきているのである。想定した2.5倍の地震が起きた、ということは、原子炉がどうにかなってしまっている、という内容を報道したいけれど、できずにいる、のではないのか、と疑う私。毀れるはずのないものが毀れたのではないのか。放射性物質が漏れている危険な地域がすでに存在している、というのでなければよいが。
- 7月17日(火)
なごやレファレンス探検隊のツアーで、名古屋の図書館のTさんとのユニットATTTを再結成してはどうか、との話があり、その気になり、Tさんと連絡をとる。『論座』の件について少し話す。名古屋の図書館での日曜開館と政令指定都市での日曜開館について調査しているそうで、名古屋では恐らく開館当初から日曜は開けていたはずとのこと。私の勤務先も昭和21年から日曜に開館しており、名古屋市とはライバルのようであった、と当時の館長が言っていたりもした。多分戦後すぐには日曜開館していたのではあるまいか。となると、『論座』での柳氏の発言は事実と異なるわけで、その前後の文脈で語られた内容についても疑義が生じてしまう。載せた朝日新聞社も名指しでひとつの市を非難しているわけであるから裏を取るべきであったろう。大きな媒体の小さな誤りによって、読者に誤った印象を植えることとなるわけで、今更ながらにマスコミの恐ろしさを思うのであった。
- 7月16日(月)
利用者多し。ばたばたであった。
柏崎で地震。原発から火が出ているそうだよ、と昼休に弁当を買いにいったら教えてくれた。恐ろしいことだ。
- 7月15日(日)
休み。クロード・シャブロル監督の『石の微笑』を観る。どうしてあの謎の女に惹かれるのかがいまひとつわからない。終わり方がすっきりしない。しかし、映像は実にきれいであった。なんとなく物足りない気分であったため、同じ建物で上映している『ひまわり』を観る。画像と音声のひどいところのあるプリント。この映画、英語だっけ。歳を経て観ると、20歳前後で観たときとまるで印象が異なる。
昨日、無言電話があった。
- 7月12日(木)
昨日とは別の学校の夏休体験学習の中学生が来館。シャイな感じ、で好感が持てる。
なごやレファレンス探検隊では9月にツアーがあるとのこと。
- 7月11日(水)
ブックポストに返却されていた本が1500冊ほど。くらくらする。しかし、一番多かった時には2500冊返ってきていたわけで、あの頃は一体どのように処理をしていたのであろうか、と考えるのだが、きれいに忘れてしまっている。
夏休の中学生体験学習の打ち合わせに中学生が10人来館。みんな感じの良い子たちであるのに驚く。私は中学生の頃、もっとずっと感じの悪い子であったはずだ。
レファレンス探検隊のコメントをなんとか書きあげる。
- 7月10日(火)
次回のレファレンス探検隊コメントで使う本がわが家にあるはずなのだが見つからず、休館日でない図書館をあちこち検索。見たい本がすべて返却済になっているところがあるので出かける。きれいな図書館。実に機能的であり、学習の利用者が使えないスペースもできている。設計にたずさわった館長が事故で亡くなったと聞いたことがある。休館日明けで開館したばかりなのに利用者が多くない。私の勤務先の3割ほど。はじめて出かけた館なので、あちこち回る。視聴覚資料と楽譜が一緒に並んでいる。参考資料の7割ほどを貸出可としている。どのような方向を目指して建てられた図書館であるかについてしばらく思いをめぐらせる。司書で運営されている館。思想のある建物。まだまだ様々なことができるのではないか、とよそのことながら、あれこれ考えたのであった。
帰りに魚市場で鰯と岩牡蠣を買う。大きな岩牡蠣が4つで500円。蒸して食べたらとてもうまかった。
- 7月9日(月)
『吉祥天女』を観る。鈴木杏が凄みがあった。テレビドラマ『青い鳥』の女の子がここまでになったのか、と感慨ひとしお。『サイドカーに犬』を観る。竹内結子演じる洋子というひとはいったいどういうひとなのかがぴんとこなかった。
- 7月8日(日)
論座8月号に「特集図書館が日本を救う」とあるので買う。座談会「転換期を迎える図書館サービスの今」が面白い。浦安市立図書館前館長の常世田良さんが、「世界でいちばん先進的と言われるアメリカの図書館では、予算が削られた場合、最初に削るのは開館時間なんです」と語っているが、我が国ではあり得ない気がする。ここ十数年、流通関連業界は長時間開けることにかなりの力を注いできて、多くのひとは夜遅くまで店が開いていてありがたい、とか、正月にも買い物ができる、と喜んでいる。店員の質の低下を気にするひとはほとんど存在しない。図書館に対しても同様である。多くの館が延長開館をした理由に、「勉強を長い間させていたいから図書館を長く開けていて欲しい」との学生の親からの要望がある。ここには資料の利用をする人達への視点は欠けている。千代田区区民生活部副参事(特命担当)兼教育委員会事務局副参事(文化財担当)の柳与志夫氏が名古屋市の図書館を名指しで批判している。「たとえば、制度的に司書職制が整っている名古屋市図書館ですが、私はひどいと思っています。というのは、それだけ身分が保障されているにもかかわらず、この何十年にわたって新しいサービスを開発していないし、政令指定都市で最後まで日曜開館していなかったひとつが名古屋市です」との発言。政令指定都市のなかで日曜開館をするのが遅かった、というのはいったいいつの話であろう。少なくとも20年前には開いていたと思うけれども。このあたりは『論座』編集部が裏を取る必要があったのではなかろうか。また、東京都の図書館に司書職制がなくなった経緯を語ったほうがわかりやすかった気がするが、遠慮があったのか。名古屋市が専門職制を敷いていたことで達成できたことも大きいと私は考える。例えば1976年のピノキオ問題である。障害者差別の記述箇所がある図書を図書館でどのように扱うかの指針を定めたのである。この問題の後、検討の三原則が作られた。1.問題資料の検討は職員集団全員で、2.広く市民参加で、3.当事者の意見を。というもの。何十年の「何」がどれだけなのかは不明であるし、名古屋市の司書のなかには優れたひともあれば、そうでないひともあり、感じがよくないひとがいたり、わかりにくい排架がされていたりといったこともあるが、現在の名古屋市の図書館を全否定するかのような発言はいかがかと感じた。ともあれなかなか興味深い対談であったが、森まゆみさんの次の言葉が印象に残った。「中学・高校時代は小石川図書館に入り浸って、そこで日本映画を岩崎昶さんの解説で毎月見たり、溝口健二も今村昌平も「戦艦ポチョムキン」も全部。スコアとLPを借りて指揮の勉強もした」。今の時代は映画も音楽も気楽に楽しめるわけだが、「文化」や「知」とは何かを図書館が示すのは重要なのではないか、と私は思うのである。新しいサービスよりも根本についてを考えてゆかねばならない時期なのではないだろうか。
- 7月5日(木)
一人で沢山の予約、リクエスト用紙を出すひとが幾人もいちどきに来て少しパニック状態となった。大抵は軽い内容の本。軽い内容の本を沢山読むより、重い本を一冊じっくり読んだほうが良いと私は考えるのだけれども。
- 7月4日(水)
休み。テオ・アンゲロプロス監督の『こうのとり、たちずさんで』と、『マルチェロ・マストロヤンニ甘い追憶』を観る。名演小劇場ではマストロヤンニの特集である。たちずさんで、という日本語は変だな、と以前思っていたが、中原昌也が芥川賞選考委員の池澤夏樹(アンゲロプロス作品の字幕の仕事を多くしている)を非難した文で使っているのを『文学賞メッタ斬り2007年版』の豊崎由美、大森望、中原昌也の対談で引いていたのに笑った。アンゲロプロスの作品は、映像が美しく、観たあとで生きることの意味について考え込んだりするようになるのが良い気がする。
- 7月3日(火)
なぜか登録者の多い日であった。図書紛失汚損などのトラブルもあり、利用者が多くない割にばたばたとしていた。
久しぶりに時間に余裕のある大学生の調べものについてのレファレンス。大抵は明日がレポートの提出日なので、なんでも良いから本を出してください、といった感じなのであるが、「提出期限に間はあるのですか」と問うと、「ええ」との答え。雑誌記事索引、webcatの引き方を説明する。書架へ案内。巻末の参考文献から他の資料をあたる方法について話す。大学によってこのあたりのレクチャーがなされていたりなされていなかったりしているのはどうしてなのであろうか。といつものことながら思う。
久間防衛大臣辞任。イラクにアメリカが攻めたことに対しての就任当時の発言に、リベラルな人が就いたのであろうか、と思ったのだったが、ただただ何も考えていない感じの人であったとのちに判明。後任が小池百合子とのことだが、政党をころころ変わっている人にこんなポストをまかせて大丈夫なのであろうか。戦争をはじめられる法律ができたら、攻撃目標をあちこち変えたりしそうで怖いぞ(←ただの悪い冗談なので目くじらを立てぬよう)。
- 7月2日(月)
6月30日公開の映画が多くて大変である。しかも大抵2週間しか上映しない。今日は『素粒子』、『春のめざめ』、『ボルベール』を観た。ウエルベックの小説『素粒子』は、どうしてこんなものを読みはじめてしまったのだろうか、と途中で悔いたが、読み終えて何とも言えぬ感覚に襲われた記憶がある。映画は小説の中程にある重々しいところをすっきりあっさりと描き、見事なラストへとつなげた。傑作である。映画は音楽を使えるのが強みであるな、と、改めて思ったり。アニメーション『春のめざめ』はテレビで製作過程を放送しているのを観てから気になっていたのであった。なんとも不思議な目への刺激である。どきりとしたり、ぞくりとしたり。この作品の前に短篇『岸辺の二人』が上映された。これは実に良い作品であった。ペドロ・アルモドヴァル監督の『ボルベール』、ペネロペ・クルスが出てくるだけでなんだかうれしい私。女優5人がアカデミー賞というのも肯ける。存在感のある上手い役者ばかり。ただ、アルモドヴァル作品としてはいまひとつもの足りない感じが残った。これは期待の度合いの問題なのだけれども。
- 7月1日(日)
混む。朝から勉強に来る学生も多かった。しかし、閲覧専用の席に座ってはいけない、という感覚は多くの学生が持っているようである。閲覧の利用者も幾人か朝早く来て晩までいるからかもしれない。
先月は我が家への無言電話が2度あった。今月は何回あるであろうか。
- 6月30日(土)
混む。勉強にやってくる学生多し。行事もあり、ばたばたであった。
- 6月29日(金)
図書館見学が二日続いたので、普段の仕事がたまったのを片づけた。
夜、友達と電話で話す。朝日ソノラマがなくなる話をしばらくする。友達はソノラマ文庫のファンであったとのこと。私は物心つかない頃、父にソノシートをよく買ってもらっていて、それを出しているところが朝日ソノラマである、と知って以来のつきあい。もう40年以上も前。友達がソノラマ文庫、光瀬龍の『暁はただ銀色』を持っている、と言い、NHKの少年ドラマシリーズの話となる。テレサ野田が出ていたこの作品の最終回を思い出して、私は怒りがこみあげてきた。「このドラマはここで終わる」と、突然終わってしまったのだった。毎回、どうなるのか、とわくわくして観ていたのに、こんな終わり方があるか、と、家族揃って怒っていた記憶がある。我が家はかなり気合いを入れてテレビドラマを観ていたのである。
朝日ソノラマのマンガをどれだけ買っただろう。山上たつひこの『光る風』、『おお、わがいとしのマスク』、『旅立てひらりん』、岡田史子の『ガラス玉』、『ほんのすこしの水』、筒井さん原作の永井豪『混乱列島』、ジョージ秋山の『日本列島蝦蟇蛙』、石森、水木、松本零士、永島慎二。千冊くらいは読んだのではないだろうか。絶版も多く、毎週近所の古本屋を回って集めたりもしたものだ。中学、高校生の頃のこと。書誌についての感覚が身についたのは私の場合、マンガによってであった気がする。
- 6月28日(木)
今日も図書館見学。電動書架を動かすと驚くのが毎回の楽しみである。質問も沢山出た。
- 6月27日(水)
朝、小学三年生が見学にくる。5クラスある学校であったが、静かに見てくれた。見ている途中や、質問の時間に、「これ幾ら」とか、「どれが一番のお宝」と訊く子が幾人かいて、まだ10歳にもならないうちにお金のことがそんなに気になる時代となっているのか、と少し驚く。お金以外の質問も沢山出て、しっかりと見ていってくれたようであった。
- 6月26日(火)
『毛皮のエロス』を観る。ニコール・キッドマンが目当てである。信頼のおける批評家が褒めていなかったので、映画そのものにあまり期待せずに行ったのであった。もしもダイアン・アーバスが観たらどう感じたかな、などとよくわからぬ想像をしたり。あまりエロスを感じない作品であった。原題はただの「FUR」だから仕方がないのかもしれないが。
- 6月25日(月)
リメイク版『転校生』を観る。客席にはなぜか腹の出たおじさんが多かった。思えば同年代のひとたちか。始まるときにどきどきしたが、どうしても頭の中でオリジナル版と比べてしまい、勝ち負けを考えてしまったりもして、いまひとつ素直に観ることができなかった。今リメイクする意味はなんなのかな、と少し考えてしまった。蓮佛美沙子はこれから期待できる役者だと感じた。
- 6月24日(日)
雨降りなのに利用者多し。貸出、返却とも5000冊ほど。ばたばたと過ぎていった一日であった。
- 6月23日(土)
かなり混む。新規登録も多し。このところレファレンスが少ない。インターネットの普及と関係があるのであろうなあ。
好きな言葉を問われると答えられないが、嫌いな言葉は山のようにある。子供の頃から厭なのが「努力」、「一所懸命」。これらの言葉は体質的に合わないのである。
一昨日、次回のレファレンス探検隊回答が届いた。私が出題者でコメントをすることになっているのである。はじめにテキトーに考えた問題をF本さんに、ほかの方の問題と似た分野であるとの理由で断られ、もっとテキトーに考えた8月向け戦争関連問題で、F本さんに、タイムリーですね、などとおだてられたのだったが、出した直後、この事柄についての大きな事件があり、タイムリーすぎたなあ、と困っちゃっていたのだが、回答のなかにその点について触れられたものがまるでなかったのにびっくり。新聞やテレビを見ていないひとが世の中には多いのでありましょうか。この詳細については次回レファレンス探検隊にて話す予定。
Tさんにメールした中に、「30代、40代の読み物ばかりを読んでいた人があるときから急に哲学書や社会科学の難しい本を読み出すなんてケースを20年働いていても見たことがありません」と書く。『市民の図書館』以後の中小公共図書館の運動は、貸出をすることによって、読者の知的水準を高めるという意図があったはずなのだが、そんなひとは世の中にほとんど存在していないような気がしているのである。いや、しかし、落ち着いて考えるとこういう人はいるのである。私の知人にもいる。ただ彼らは図書館に行かず、本屋や古本屋に出かける。「知」を求める人が、図書館によってそうなったというケースは世の中にどれくらいあるのであろうか。気になるところである。
- 6月22日(金)
今日もまた特別整理期間前の返却日に設定してある日だったため、やや混む。なぜか新規登録が多いのが不思議である。
- 6月21日(木)
特別整理期間前の返却日に設定してある日だったため、かなり混む。返却図書が4000冊以上。ばたばたであった。
- 6月20日(水)
ぼちぼちと混む。
名古屋の図書館のTさんからメールを頂く。図書館はどこもなかなか厳しい状況のようである。司書はひとりひとり何をすべきか、何ができるか、をしっかり考えねばならない。
- 6月19日(火)
割と空いていた日であった。
明石書店が見計らいに来た。人権関連の図書などを出している出版社で、最近は発達障害児童関連の書物を多く出している。選書は、出版社を知るところからはじまるわけだが、案外と多くの司書がこの点に気づいていないらしいことに最近思い至った私。雑誌を何冊か読むとある程度その出版社の傾向が見えてくるようである。ようである、と書いたのは、私にとっては普通の生活をしているだけなので、司書としてすべきノウハウといったようなことが実のところよくわからないのであった。
- 6月18日(月)
『舞妓Haaaan』を観る。面白い作品であった。
- 6月17日(日)
梅田にゆき、古本屋をまわる。ブンブン堂こと加藤京文堂で、店主のひとがアルバイトの子とグレちゃんについて話していたのを盗み聞きしたり。
- 6月16日(土)
大阪へゆく。天満のあたりをまわる。迷子になったりする。なんとも大阪らしいエリアであった。
大阪城野外音楽堂で「FANKY大百科」を観る。レキシ、ハナレグミ、マボロシ、SUPER BUTTER DOG。なかなかファンキーで良い感じだった。レキシに、足軽先生という名でいとうせいこうがいるのに驚く。「いとうせいこうとタイニーパンクス」は日本でラップを最初期に行っていたのだったな、と思い出す。1985年のこと。
- 6月15日(金)
なかなか混む。
- 6月14日(木)
朝、ブックポストへ返ってきていた本は30冊ほど。随分少ない。不気味である。来週あたり、やたらと混むのではあるまいか。
「彷書月刊」に連載されていたグレゴリ青山の『ブンブン堂のグレちゃん』というマンガを読む。古本屋でアルバイトをするグレちゃんが主人公の作品。なかなか面白かった。巻末に大阪の古本屋地図があり、大阪第3ビルの地下2階には何軒が古本屋があったことを知る。こないだ出かけた時は気づかなかったのであった。天満のあたりにはかなり古本屋が増えているようである。また探検せねば。
- 6月13日(水)
朝、ブックポストへの返却は766冊。特別整理期間の前に貸し出した分の期限を長くしているので、まだ返ってこないのである。
- 6月12日(火)
部屋を片づける予定でいたのだが、またも挫折。衣替もぼちぼちせねば。
- 6月11日(月)
『鉄人28号白昼の残月』を観る。予告篇が良かったので何日も前から楽しみにしていたのだが、無理のある箇所があり、期待したほどではなかった。
- 6月10日(日)
混む。よれよれとなる。今日も新規登録多し。
- 6月9日(土)
長い休館日のあとなので利用者が殺到。貸出返却はそれほど多くないが、レファレンスがずいぶんとあり、なぜか、新規登録も多かった。
『群像』には筒井康隆さんと東浩紀さんの対談もあり、そのなかで東氏が、「僕は『朝のガスパール』を傑作だと思っているんです」と語っている。現在の目で読み直さねばならない気がするが、電脳筒井線での発言で大きな出来事を起こしている私は怖くて連載以来まだ読みかえせずにいるのであった。
- 6月8日(金)
特別整理期間のおしまいの日。開架から閉架にしまわないと、本が溢れている分類がまだまだあり、選んでしまう。ずっとこの作業をしていると、くらくらしてくる。画集の開架、閉架の入れ替えもする。
『群像』今月号の大江健三郎と長嶋有さんの対談がとても面白かった。長嶋さんは昔、アサヒネットでパソコン通信をしていた。アサヒネットで行われた第1回パスカル文学賞の頃の彼は大学生で生意気であり、私の友人と会議室上であれこれあったりもし、あまり良い印象を持っていなかった。そもそも私は若い男が嫌いなのである。共通の友人が亡くなった時、彼は追悼文集を編んだ。私は亡くなった友人とアサヒネットで知り合った中で一番古いつきあいであったため、彼がどの会議室に書いていたかを恐らく詳しく知っており、それに気づいた長嶋さんからメールをいただき、多少、その文集のお手伝いをした。長嶋さんはその時デビュー前。31歳で亡くなった友達に対して、多くのひとが何かをしたい、と考えてはいたが、結局のところ、誰もしなかった。実際に俳句の同人誌の特別号として1冊を編む体力には驚いた。大したひとであるな、と思っていたのだが、私はそもそも若い男を嫌いであった。彼は名古屋と関わりのある企業に就職し、こちら方面に来ることがあったら会いましょう、とメールをくれたりもした。律儀なひとである。私はそれにどういう返事を書いたのであったかもすっかり忘れている。若い男を敬遠する傾向があるのである。その会社を辞めた、と聞いたのは、日間賀島での句会の時であった。1998年のこと。長嶋さんと面識のある小澤實師匠が、「もったいないなあ」と言っていたのを憶えている。しかし、彼は見事に作家となった。2001年『サイドカーに犬』で文學界新人賞を受賞されたときには驚いた。この作品は私の好きな根岸吉太郎監督の映画となり、名古屋でも近々公開される。実にスタイリッシュな小説であった。『猛スピードで母は』で芥川賞をとったとき、彼の所属する同人誌のひとと、しばらく彼の作品の良さについて語ったりもした。そして第1回大江健三郎賞。大きな賞である。そして第1回というのはこれから先、もう誰もとることができない。遅ればせながらお祝い申しあげます。おめでとうございます。
- 6月7日(木)
とある出版社が本の見計らいに来館。幻想文学や、民俗学など、地味だが良い本を出しているところ。過去に出していた全集から良いものを選んで新書か文庫にしてはどうか、と提案すると、営業が強くないと、ペーパーバックス類は難しいとのこと。そういえば白水社Uブックスなども、大きな本屋さんでないと置いてないな、と気づく。レファレンスツールについては、Webで無料で調べられるようになったので大変であるとのこと。図書館に調べものに来る人も年々減ってきている。どういうひとにとって司書が必要であるのか、司書はこれから何を身につけてゆかねばならないのか、を、出版社のひとが、何を出版してゆくべきか、を思うのと同じくらいに考えるべきであろう。
『論壇の戦後史』(奥武則著、平凡社新書)を読む。私にとってかなり興味深い本であった。
- 6月6日(水)
閉架の図書のなかから古い法律関連図書、古い未来予測の本などを一般書担当で相談しあって廃棄。開架から閉架へうつす本を選ぶ。日に万の単位の本についてあれこれしているので、少しくらくらしてくる。
整理方法に悩んだままであった数年前にいただいた短冊や、以前いた臨時職員さんに途中まで読んででもらったくずし字で書かれた明治のチラシなどを前に悩んだり。
- 6月5日(火)
閉架を整理。20年ほど前に見たきりのもの、見たことのないものなどが出てくる。スペースに余裕があるうちは、いろいろなものを保存しておき、毎日目にしているので、かなり汚い状態であっても気にならないのだが、冷静になると、かなりひどい状態である。私の部屋よりはましだが。
- 6月4日(月)
北野武監督の『監督・ばんざい』をみる。コントが沢山集まった映画である。それでこれからどうするのであろう、と思えた。希望のないところからはじめる、ということなのであろうか。良い作品である、とは言えない映画であった。江守徹の怪演がうれしかった。
- 6月3日(日)
昨日のうちに18万冊のスキャンが終わる。ひたすらポスター整理。こんな行事もあったなあ、と最初は懐かしがっていたりもしたのだが、量が多すぎて段々と気持ちが悪くなってくる。
我が家に来るメールを誤って消してしまう場合がしばしばある。パソコン通信ソフトでアサヒネットのコマンドを使ってチェックをしつつ、削除をしてゆくのだが、知らない人からの怪しげな標題のものはぱしぱしと捨ててしまっている。よく知っている人からの普通の標題のメールもこの頃は目が衰えているためか、時折捨ててしまったり。スパムメールが日に200ほどあるので、やや乱暴になってきているこの頃の私。何か別の捨て方を考えねば、と思っているのでした。ところで、昨日捨てたなかに、まともな大学のアカウントのものがあったのをあとから発見。お心当たりのかたは再送願います。_●_
- 6月2日(土)
特別整理期間。ひたすら本をスキャン。
長らく整理していなかった郷土関連のポスターを片づけはじめる。膨大な量。
- 6月1日(金)
特別整理期間。ひたすら本をスキャン。肩がこる。
本の間から不思議な紙がいろいろと出てくる。手紙の下書、ロト6のはずれ券、ひとには言えないようなもの。
- 5月31日(木)
混む。レファレンスも多し。ばたばたと一日が過ぎる。
気がつけば5月も終わりである。そういえば島での訓練の話はどうなったのであったっけ、と遠い地域のことはついつい忘れがち。こんな記事があるが、下関の地方版。全国民に知らせなくても良い話なのであろうか。武装工作員が島までどうやってくるのかが疑問。泳いでくるのであろうか。不審船ならば、島に来る前に見つけてほしいぞ。
- 5月30日(水)
晩になって随分と混む。2時間で1000冊ほどの貸出があった。頭がくらくらした。
- 5月28日(月)
名古屋シネマテークで、『明日、君がいない』と『フランドル』を観る。『明日、君がいない』はあとから効いてくる感じの映画。思春期というのは実に厭なものだと思う。おじさんになってよかった、としみじみ感じる。
『フランドル』、性交シーンの時間がほとんど犬猫並であるのに少し驚いた。中東のどこかの国を7人で行軍してゆくのが実に奇妙で怖かった。戦争はしみじみ厭だ。フランドルの景色はとても美しかった。しかし、私の好みの作品ではなかった。
- 5月27日(日)
利用者多し。貸出は5000冊を超えた。
近くの町に住む高齢の方から所蔵調査の電話。住民登録は私の勤務館の町に移したそうだが、70年住んでいるのは別の町。うちの館におたずねの本がないので、住んでおられる町の館をWeb検索するとある。そこの登録規定を読むと旧郡部5つの町に在住在勤、となっていたため、電話で確認。すると、公的な証明が登録に必要であり、住んでいても住民登録されていなければ利用ができないとの返事。利用者にその旨を知らせると、閲覧だけで良いとのことであった。しかし、様々な理由で住民登録ができていない人がいるわけで、住んでいることの確認ができれば貸出を行えば良いのではないか、と私は考える。住民登録をしているから間違いなく返却をするというわけではなく、悪いひとを例にあげれば、本を借りたまま外国に引っ越してしまう人だっているわけで、そのひとがまともな利用者であるかどうかは何の保証もないのである。住んでいることさえはっきりしていれば貸出券を発行すべきではないかと思うのだが。ところでこの館、児童の登録はどうしているのであろう。最初の敷居を高くしてしまうと、図書館なんて二度とゆくか、と、なりかねない。このあたりの問題に多分正解はないのではあるが、慎重に考えるべきであろう。
- 5月26日(土)
利用者多し。職員が少なく、ばたばた。歳のせいか閉架と開架の往復に息が切れる。貸出は4500冊ほど。入館者は1400人ほど。ふう。
- 5月25日(金)
選書をする。
県図書館のひとに去年話していたことについて、担当が変わり、少し違う話がかえってきた。数十年前の図書館日誌を以前に読んでいて、ああ、このころは県と市町の図書館の関係がこんなにほのぼのとしていたのか、とうらやましく思ったことがあった。その時代から続いていた共同作業について大きな変化があるのである。各館に司書がいないせいか、連絡がうまくいっていないせいか、歴史のある重要で専門性の高い仕事が終わる。私の中には疑問が残るのだが、電算化でこういうことが起きる可能性は想像していたので、それほどの衝撃をうけはしなかった。
- 5月24日(木)
朝から難しいレファレンス。明治時代の地元のお金持ちについての質問。何屋さんだったのか、どんなことをしたのか。郷土関連の調べものはその土地の図書館でなければできない。公共図書館と司書の必要性について語る場合、ここを一番強調すべきであろう。保存用と提供用で複数の資料を収集するようにしている。非売本も多く、集めるのには専門的な能力がいる。指定管理者制度を導入した館はこの分野についてどうなってゆくのであろう。過去に集めた資料は散逸したり、傷んだり、死蔵されたりし、今後の資料は穴だらけになったりするやもしれぬ。それでもその町の人々の多くはそれほど不自由するわけではない。地域、国、世界、宇宙の歴史を今作っているのは今生きている人間である、という認識を多くのひとが持つべきではなかろうか。未来になれば現在は歴史なのである。しかし、人類に未来がいつまであるかどうかを考えるとどうでも良いのかもしれない、という気がしないでもないが。
- 5月23日(水)
来週から特別整理期間がはじまるためか、利用者多し。
- 5月22日(火)
火曜は比較的空いているのだが、晩にばたばたとお客さんがいらしたのであった。帰りにはややよれよれになった。
ふと思いついたのだが、我が国のひとびとは、漬物石みたいなものが乗っかっていないと不安なのかもしれない。江戸時代にはお殿様、戦前までは現人神であり、戦後は人間になった人とアメリカ様が乗っかっている感じであったのが、頭の上が寂しくなった雰囲気の現在、落ち着かなくなって軍隊様を乗っけようとしているのではないか。マーク・ゲインが『ニッポン日記』で、戦後、共産党幹部が帰国して演説をしたときの大衆の熱狂を冷静に書いていたのを思い出す。何でも良いから仰いでいないと不安。なんでもいいから乗っけておかないといけない国民性なのではないか、と、そんなことをぼんやりと考えたのであった。テレビ様が、これを乗っけると良い、などと語ると、納豆でも乗せかねない人達で成り立っている国なのかもしれない。納豆ならばねばねばするだけで、平穏であろうが。
- 5月21日(月)
シャルロット・ゲーンズブールをめあてに『恋愛睡眠のすすめ』をみにゆく。ずいぶんと気が違った感じでよい映画であった。ガエル・ガルシア・ベルナルが良い。上司ギィの役のアラン・シャバがなんとも馬鹿馬鹿しくて可笑しい。
- 5月20日(日)
さすがに日曜日である。混む。休んでいる職員がいたりもして、ばたばたで、へろへろになった。貸出と返却をあわせると1万冊ほど。よく本が動く。
- 5月19日(土)
利用者多し。
あまり近づかぬようにしている若者が集うサイトをいくつか眺める。平和が悪で戦争万歳、みたいな乱暴な論がかなりある。憲法9条をかえて軍隊を作り、戦争をはじめたい人達も増えている。退屈しているのであろうな、と想像する。しかし、敵はどこだ。味方は誰だ。そこと戦うとどんな良い未来が待っているのか。歴史の浅いその国は世界中を自分の国にしたいだけではないのか。単純な若者はお金儲けをしたいひとたちのために命を落とすだけではないのか。自分は戦場に行かないのに、戦争がはじまろうとするとお金が儲かる人間がこの世に存在する、と彼らは知っているのか。若者の命が彼らの商品。安い元手で多くを稼ぐ。商品は自分たちからやってきてくれる。敵はどこだって構わない。こないだは鬼畜米英であり、今度はなぜか危険な隣の国であったりするのであろうか。軍備増強がはじまれば潤う産業があり、関連会社に親族がいる偉いひとにはとても沢山のお金が入ってくる。だから戦争ができる国にしたいのである。戦争に出かけて死ぬ若者の親族にはあまり沢山のお金は入ってこない。それでもなぜだか戦争にゆきたがる若者がいる。一握りの、儲けを得られるひとになれないのであれば、戦争はしないほうが得であろう。純粋な若者達は戦争とお金の関わりについてあまり考えないらしい。さきの戦争が終わってほんの62年。ドイツでは戦争で非道なことをした人物、責任のあった人物を自国民が裁いたし、今も責任を追及しているが、不思議の国日本では他国が裁いてくれたあと、過ぎたことは忘れられた。爆弾をいっぱい落として100万人以上の無辜の市民を殺したのがどこの国であったのかさえ忘れ、その国のための戦争に行って命を落としてきなさい、と言われて、戦争に行きたがっている若者がいっぱいいる。平和が厭ならば戦争をしている国に見にいったらどうかと思う。戦争が終わったばかりの国でも良い。兵隊になりたければ、我が国がついてゆこうとしている国が契約している会社の傭兵になる手もあろう。一番偉いひとが言っていることが正しい、と考える素直さは美しい日本に欠かせない美しい心なのであろうか。
- 5月18日(金)
環境調査に自衛隊が出てくるというのは不思議な話。テレビ局は報道しているのかなあ。これはトップ記事ではないのであろうか。撃ちてし止まん、とか、そんな感じですな。今からしばらくの間、おかしな事柄について、しっかりと「おかしい」と言っておかないと、「おかしい」とも言えない世の中に変化してゆくのではなかろうか。
『図書館の自由に関する宣言』第4に、「図書館はすべての検閲に反対する」とある。検閲に近いことがはじまっているのではないのか。自主規制という形をとってはいるが、圧力がありはしないのか。今、この段階で反対せねばならぬことが図書館員として、ひととしてあるのではないか、と私は感じている。
- 5月17日(木)
選書をする。
長久手町の立てこもり事件の場所は幾度か通ったことのあるあたり。撃たれた警官が長時間そのままにされていたのが痛ましい。助けに入った警官は亡くなってしまった。
銃器は厭だな、と思う。戦争にゆく人達はみんな持ってゆくのであり、沖縄の基地にはこれのでかいのがどかどかと置いてあるのであり、戦地では、人が痛い状態でほったらかしにされることも多いのであろうなあ。
- 5月16日(水)
発注するCDを選ぶ。『CDジャーナル』を眺めていると、老眼が進んできている気がする。そろそろ老眼鏡の歳か。異動をしてきた上司は市民課にいたとき一緒だった本好きなひとで、「良い仕事だねえ」と時折言う。趣味なんだか仕事なんだか遊びなんだかわからない仕事である、とは言える。昔、新刊案内パンフレットの山をみながら選書をしていたとき、本を溺愛しているタイプの臨時職員さんに、「これ、仕事なんですよね」と問われ、「うん、そう。買う本を選んでいるの」と答えると、「仕事とは思えませんよね。いいな」としみじみ言われたこともあった。本やCDが好きなひとからみると、羨ましい仕事なのである、と図書館員はよくよく知っていたほうが良い気がする。本やCDに興味がないひとにすれば、ただの「仕事」なのであるが。
- 5月15日(火)
『輝ける女たち』を観る。カトリーヌ・ドヌーヴとエマニュエル・ベアールを目的に行ったのだが、ニッキー役のジェラール・ランヴァンが主役であり、実に細かい演技をしていた。ニノ役のミヒャエル・コーエンがとても存在感があった。それにしてもフランス人というのは恋愛に対して寛大というか頓着しないというか、食べているものが違う感じである。
沖縄の本土復帰35年である。1972年5月15日のことは良く憶えている。第2次切手ブームであり、復帰の切手が発売され、母がこれを買うため、郵便局に並んだ。昼に学校の放送で、「今日、沖縄が日本に復帰しました」と言っていた。沖縄県ができたのだった。それから35年、しかし結局沖縄はまだアメリカの持ち物のままなのではないのか。基地が沖縄にいっぱいあるのを日本人の多くはなんとなく仕方がないことだと思い込んでいる。沖縄にだけ沢山あるのは不公平だから、うちの町でひとつもらってやろう、と考えるひとはあまりいない。米軍基地があれば米兵がいて、乱暴なことをするかもしれないわけだし、誤って戦闘機が落ちてきたり、爆弾が破裂するかもしれない。しかし海を越えた遠い土地での出来事。パスポートなしでいったりきたりできるようになったり、移住したりできるようになったというくらいで、72年以前と大きく変わったところはあるのであろうか。辺野古にジュゴンはいつまでいられるのであろう。
- 5月13日(日)
さすがに日曜日である。混む。しかし、このところレファレンスが減っている気がする。インターネットでかなり調べられるようになってきたのであろうか。わけのわからない調べものがどかどかとやってきていた日々を懐かしく思う。
- 5月12日(土)
混む。閉架の資料の利用がこのところ随分と増えている。インターネットで検索し、プリントアウトした紙を持って来館するひともしばしば。
- 5月11日(金)
比較的空いた日であった。視聴覚資料の入力、新刊図書の選書をした。
本棚から出てきた永島慎二の『若者たち』を読む。『黄色い涙』の原作である。私が永島慎二を知ったのは「ガロ」に連載されていた『その場しのぎの犯罪』であった。そこから遡って様々な作品を読んだ。しかし、時代の違いのためか、いまひとつぴんとこないところがあったりもした。違和感が残ると言おうか。ただ、彼の作品のいくつかはよくわからぬまま身体の中に残る。
『黄色い涙』上映の前に嵐の5人が作品について語る映像を流していたのだが、「昭和」を強調していたのが気になったのを思い出した。「の方」という言葉も気になったが。昭和全部を古き良き時代というイメージにされてしまうと随分ととんでもないことになりそうである。昭和はかなり長い。1926年から1989年までである。1945年の前と後とでは憲法が違っている。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約は1960年に改定され、1970年に自動延長された。1963年という設定はもしかして安保を避けたのであろうか。第二次大戦中も懐かしい時代になってしまったり、憧れの時代になってしまう可能性がある、どころか、すでになっているのかな。1962年早生まれの私が子供の頃には、戦争で子供を亡くして気が違ってしまっている人がいたり、手や足がないひとが町の公園にいけばいたりしたし、貧乏もまだあちこちにあったので、戦争の悲惨さ、というのがなんとなく実感できたが、20歳下くらいになると、そのあたりの感覚がまるで違っているわけで、「昭和」をひとまとめにして、ああ懐かしい、良さそうな時代だ、なんてことになるやもしれぬ、とそんな想像をして段々と怖くなってきた。国民投票法案が参議院で可決だそうだ。ここまでの報道の小ささは、これから先の時代がどうなるかを予感させる。
- 5月10日(木)
『黄色い涙』を観る。永島慎二の原作は高校生の時、幾度か読んだ。60年代末から70年代はじめにかけての彼のマンガに私より10歳から15歳くらい上のひとたちは随分と影響を受けたらしい。永島慎二はマンガ表現史上にも功績を残している。目を白く抜くのは彼がはじめたのではなかったか。映画は、原作では昭和43年であったのを、5年前の昭和38年に設定したことで失敗した、と私は感じた。歌手をめざす人物が歌うのがフォーク調の音楽であったが、あれはあの時点では新しすぎる。服飾は垢抜けすぎている。バミューダパンツは昭和38年にどれくらい履かれていただろうか。自炊をまったくしなかった人が住むアパートであれば、部屋に流し台が元々あるのであろうか、共同の炊事場のほうが一般的であったのではないか、などとあれこれ考えてしまった。これが昭和43年であれば、ほとんど気にならなかったであろう。冒頭のシーン、救急車で母親を大学病院に運ぶ手段に無理がありすぎる。バイト代2000円は今だと数万円である。中の話が良いし、嵐のメンバーの芝居も良いだけに、こうした細かなところが残念であった。エンドロールに、「ヒッチコックマガジン 小林信彦」とあったのに驚いた。拳銃の写真が載った雑誌が少し映り、おや、ヒッチコックマガジンのようだ、とは思ったが。小林氏が犬童一心監督を評価している文章を読んだが、気難しい作家とこの監督とがどんなやりとりをしているのであろうか。
辺野古の坐りこみに自衛隊が出動するとか。六連島の話も報道されていない。マスコミは大丈夫か。
- 5月9日(水)
朝、ブックポストへの返却図書1806冊。2日間でよくこれだけ返ってくるなあ、と感心したが、以前は2500冊返ってきたこともあったのを思い出す。利用者も多し。ばたばたであった。
晩、消化試合となったナビスコカップを観にゆく。グランパス対鹿島アントラーズ戦。1対0で前半を折り返したので、試合終了後、今日おこなわれているレファレンス探検隊の懇親会に出席する旨を連絡したのだが、後半4点も入れられる。なんとも重たい気持ちで懇親会に出る。
レファレンス探検隊ではどうして図書館員になったかを語る時間があったそうで、それについての話を聴いたりした。学生のとき、図書委員をしていた人の数がかなりあったとのこと。そういえば私も小学、中学、高校と図書委員をしたことがあった。必須クラブは読書部や文芸部であった。高校の時、館報に山上たつひこの『光る風』について書いたことがあったな、と変な記憶が蘇る。名古屋市のYさんが小学生の時、図書委員になりたくても希望者が多いため、なれなくて、ベルマーク委員をしていたという話がよかった。私はどうして図書館員になったのかな、としばらく考える。虚業に就きたい、と思っていたのは確かである。あってもなくってもなくってもなくっても良い職業に就いて、でも、その仕事は必要なのだ、とひとに感じさせられるような仕事をしたい、できれば世の中を良い方向に変化させたい、とそんなようなことを考えていた。Yさんは高校生の時、新聞の縮刷版を趣味で読んでいたとのこと。私は泉谷しげるが雑誌(自由国民社から出ていた『ギターライフ』)の広告で勧めていた『現代用語の基礎知識』という本が中学の図書室にあるのに気づき、昼休にぼちぼちと読んだ記憶がある。レファレンスツールを読む体質であることと、図書館員になる、とはどこかで繋がっているのかもしれない。
指定管理者制度の波はあちこちにあるようだ。地道にしてきた仕事を足元からさらうような方向ではある。しかし、世間に、図書館員がなぜ要るのか、をしっかりわかってもらう仕事を多くの図書館員がしてきていなかった結果のようにも感じる。子供の頃から図書館員に憧れて就職し、働いてきた人も多いが、たまたま異動させられて、早く役所に戻りたい、と思いながら働いている人はもっと多い不思議な世界。「公共図書館」の水準はまちまちであり、内容もそれぞれ。アメリカでは市民の声によって左右されたりもするが、日本ではそのあたりのシステムがうまくできていない。ベストセラーの複本を沢山購入したり、俗な本が増えたことで館長をリコールする国とはまるで違うのである。日本の公共図書館の進路に影響を与えたのは『中小レポート』や『市民の図書館』であったわけだが、しっかりとした図書館活動をしてゆくにつれ、民度がいずれ上がるであろうとの前提で運営されてきた日本各地の図書館の現在はどうなのかを、一度しっかりと検証すべきであろう。遅きに失した感があるが。出版状況、国民の経済状況、情報媒体の変化をさして気にとめず、要望のある図書を、水準を気にせず市民のためと購入し、総体的にみた場合、段々と要求される資料の基準が下がってきている現状をまねいたのはなぜなのか、このまま、ご不浄を掃除すると運が良くなるといった内容のオカルトめいた本や、レシピ、ガイドブックを市民のため、と限られた予算で買ってゆくことが図書館員の主な仕事であり続けるのだとすれば、専門職がどうして要るのか、を世の人に説明するのは困難なままなのではなかろうか、と最近つくづく感じている。出版される本の大半が、世界にとってあまり意味のないものとなってきているのに、ありがたい本が多かった時代の理屈で同様に進めばどうなるか、という程度の想像力をどこかの段階で我々は持つべきであったのではなかろうか、と自らの反省もこめて思う。下の世代の図書館員に対して申し訳ない気持ちである。そしてこれからの公共図書館をどうしてゆくのか、ゆけるのか、国はどうなってゆくのか、といった問題に思いを馳せると明るい気持ちにはあまりなれなかったりもするのであるが、ここから逃げてはいけないと考える。
歳をとると、古いことを知っている。若者が物心つく前、生まれる前に様々な経験をしている。解散したバンド、絶頂期であったバンドを観ていたりもする。そうしたことを自慢気に言う年長のひとたちを苦々しく感じていたが、気がつくと私もそういう行為をしばしばしている。これは多分、もう一生の半分以上を生きてしまったので、若者が憎たらしいのである。今のうちに厭がらせをしておかないと、死んでしまったらできないわけで、「ええい、ざまみろざまみろ」と言っておきたくなるというようなことではないかと考える。これからもそうした厭がらせを若い人達にしてゆくことであろう。そういえば電脳筒井線に乗り遅れたひとが、「乗りたかったのに」とぶつぶつ言っていたとき、「乗らなかったのがいけない。生活を犠牲にして我々は参加していたのだ。乗れなかったとはいい気味だ。悔しかったら今から乗ってみろ」と幾人かでいじめたことがあった。単なる嫌味な性格なのかもしれない。以前から若い男が嫌いであったが、年齢とともにそれがひどくなってきている。遙か昔、生放送中に酔っぱらっていた野坂昭如が石橋貴明を殴った事件が起きた時、野坂が、「とにかく若い男というだけで気に入らない」と不条理なことを言っていたが、なんとなくその気持ちがわかるようになってきた昨今である。殴ったりはしないが。偏屈な年寄になりたい、と若い頃に考えていたが、順調にその道を歩んできているような気がする。
- 5月8日(火)
4連休が終わる。部屋はほとんど片づかなかった。
- 5月7日(月)
『スパイダーマン3』を観る。良い終わり方であったと思う。
- 5月6日(日)
ジェットコースター事故の報道で、営業運転中の死亡事故をきいたことがない、と国土交通省がコメントしているのだが、86年の夏に確かにあった。止まりきれなかったという事故。私が乗ったのと同じジェットコースターで翌日に起きたのである。それ以来私はあの手のものに乗っていない。
『パラダイス・ナウ』を観る。空爆に対抗するための自爆。虐げられている彼らの選択肢は多くない。
- 5月5日(土)
休みなので、部屋の大掃除をする。6時間ほど本を片づけた。200冊ほど処分するのを選び、多のを部屋に戻したら、どこがどう変わったのかがさっぱりわからない。ちょっとやそっとでどうにかなる汚さでないことをしみじみ感じる。
- 5月4日(金)
カウンターローテーション表作成。選書、発注、見計らい。
- 5月3日(木)
朝日新聞の8ページにわたる社説には驚いた。改憲論がかまびすしい昨今、護憲を堂々と主張するのはたいしたものである。
連休中はそれほどには混まない。とは言えなぜか登録者が多かったり、調べもののひとがあったり、旅行関係の本の利用者が多かったり。
- 5月2日(水)
朝、ブックポストの本はそれほど多くなかった。午後、ばたばた。
- 5月1日(火)
『バベル』を観る。ゴールデンウイークの映画の日なので朝一番の回なのに満席。モロッコの子ども達がかわいい。どうでもよいことではあるが、メキシコの甥の役のひと(ガエル・ガルシア・ベルナル)は『バッド・エデュケーション』に出ていた時には思わなかったけれども、オダギリジョーに似ている。3つの場所での話それぞれに無茶な箇所があったりするのだが、面白い作品であった。菊池凛子は強烈な印象。
- 4月30日(月)
朝は混んだが、午後から空いていた。
「SFJAPAN」春号(徳間書店)に載っている森青花さんの『うさぎが、ぴょん!』を読む。怖いのに懐かしくかわいらしい不思議な短篇。やや展開がはげしい気もしないではないが、いかにも日本のSFである。
- 4月29日(日)
ゴールデンウイークは比較的空いている。しかしなぜか新規登録者や、久しぶりに来館なさる方が多かった。延滞督促電話をかける。
- 4月28日(土)
世間ではゴールデンウイークがはじまったようである。インターネット予約の件数を5件から10件に最近増やしたのだが、一晩に35件も入っていると処理がなかなか大変ではある。朝から沢山の利用者。午後、やや空く。早いうちに多くの本を借りて、ずっと読んで過ごすひともいるのであろう。
昼にポットの湯を片づけていて、ふとしたことを思い出す。3時には石鹸箱を洗う。
ソリッドレコードの『BEST OF SOLID VOL.1』を聴く。フォーク・クルセイダーズの『イムジン河』がはじめて正式に発売されたのはこの時であった、と思い出す。黒沢進の仕事の大きさはもっと評価されて良い。
- 4月27日(金)
週刊文春に小林信彦が『落花流水』(渡辺千萬子著、岩波書店)について書いていた。この本のなかで触れられている評論家をどうも私は元々好きになれないところがあるのだが、かなり非礼なひとでもあると知ったのであった。男女間の微妙なことがわからないのは自ら「もてない」と名乗っていられるのであるから無理もない気がする。それよりも2億円あったら谷崎はどうしていたのか、が気になる。取材をして書かれなかった作品も気になる。晩年、千萬子が谷崎のそばにいたのは谷崎作品が好きなひとにとっては大変幸運であった、と思う。
- 4月26日(木)
見計らい、受付でばたばた。
友達のブログに休みの国の『悪魔巣取金愚』について書かれていたので、聴きたくなり、CDを探すが出てこない。確かこれ、黒沢進さんが関わっていたソリッドレコードから出ていたのだった。
- 4月25日(水)
やや大きな失敗をしていたことに気づき、あれこれする。
- 4月24日(火)
ばたばた。朝、ブックポストには500冊ほど。
黒沢進さんが亡くなったのを知り、ジャックスを聴く。早川義夫やジャックスを聴きたいとずっと考えていた頃のことを思い出す。ラジオに河島英五が出ていて、彼が好きだという『サルビアの花』を聴いたのが1977年。もとまろのバージョンしか知らなかったのだった。早川義夫が活動休止をしてから7年が経っていたのであったが、子供の頃ジャックスというグループサウンズがあったな、とそれから気になりはじめたのだった。その頃、『からっぽの世界』は放送禁止で、レコードはすべて廃盤だった。当時、しばらく文通していた赤田祐一氏も早川義夫の『かっこいいことはなんてかっこ悪いんだろう』を探していた記憶がある。1980年にこのアルバムが再発売され、すぐに買った。地の底から響くような早川義夫の声は中毒になる性質を持っていた。1986年にたまたま名古屋のレコード屋で購入した早川義夫のソロシングル『前口上』はクロヤマレコードという聞いたことのないレコード会社から出ていたのだが、これは黒沢さんが音源を発掘したものであったとのこと。彼と高護さんとの共著、白夜書房から発売された『定本ジャックス』はうれしかった。今は幻の本となっているらしい。ジャックスが再評価されたのには黒沢さんの力が大きかったのではないか。彼がいなければあるいは早川義夫の活動再開もなかったかもしれない。GS、日本のロック、ポップスについての彼の仕事は地道で大きなものであった。ご冥福をお祈りします。
- 4月23日(月)
『ハンニバル・ライジング』をみる。鎧兜を拝む奴はいないだろ、とか、わけのわからん浮世絵の飾り方だな、とか、日本人の目からみておかしなところがいくつもあったり、話に無理のあるところはあったが、派手で、楽しい映画であった。
昨日BS2の週刊ブックレビューで泉麻人がとりあげていた『昆虫にとってコンビニとは何か?』(高橋敬一著、朝日選書)を読む。とても興味深い本であった。シデムシやカメムシが好きなひとの視点は独特である。著者はずいぶんとシニカルな書きようをしているが、多くのことに絶望した末であろうと感じた。
- 4月22日(日)
名古屋シネマテークに『孔雀』をみにゆく。短篇が沢山集まったような作品であり、少し物足りなかったが、映像が美しい。チャン・チンチューが嘘つきの女の役でとても良かった。
- 4月21日(土)
今日から3連休である。岡崎市美術博物館に『シュルレアリスム展』をみにゆく。子供の頃からシュールレアリズムを好きな私。
瑞穂陸上競技場にグランパス対ヴィッセル神戸戦をみにゆく。昨日帰国したばかりの本田圭佑がよく走っていた。金正友のクロスにヨンセンがあわせた1点目、中村直志の見事なクロスに杉本恵太が飛び込んだ2点目、どちらも美しかった。櫛野のファインセーブ、要所をおさえた米山も偉かった。今日はゆく予定ではなかったのだが、出かけて良かった。
- 4月20日(金)
昼休に、幾度となく読んだ小林信彦の『山川方夫のこと』を読み、喪失感について考えを巡らす。
幾つかの図書館から様々な質問を受けた日であった。なかに、利用者の名前をうっかり告げようとしたひとがあったので慌てて制した。個人情報を自館以外に漏らさぬ意識だけは常に持っていないといけないと思うのであった。
- 4月19日(木)
休み。ミカ・カウリスマキ監督の『モロ・ノ・ブラジル』を名演小劇場に観にゆく。おしまいのあたりで、血がざわざわした感じになってきた。南米の音楽に私はあまり惹かれなかったのだが、この映画を観て興味がでてきた。
- 4月18日(水)
朝、混む。返却よりも貸し出しが500冊ほど多かった。棚がぎゅう詰めになってきているので、沢山借りていってもらえるとありがたい。
- 4月17日(火)
空いていた一日であった。入力作業をする。
- 4月16日(月)
足立正生監督の『幽閉者』を観る。田口トモロヲは怖いくらいうまい。わかってはいたが、すさまじい迫力であった。パンタは不思議な役を演じていたが、よく似合っていた。実に何とも息苦しい映画であった。ところで、60年代末にはこの国に革命家がいっぱいいて、敵は確かアメリカであったはずなのだが、彼らは今何をしているのであろうか。
- 4月15日(日)
春のせいか、不思議な利用者が幾人か来館。延滞督促電話を沢山かける。
- 4月14日(土)
1時間ほど同じお客さんと接している職員がいるので、話を聞きにゆくと、お金の絡む事柄が裏側に隠れているように思えた為、それとなく探るとやはりそのようであった。いわば被害者であり、その解決はかなり難しそうであり、本人もそれがわかっていて、しかし、調べれば何か手がかりが見つかるかもしれない、と思っておられるのであった。恐らく図書館ではなんともならないのだけれども。口に出していること以外の内容がもぐっているかもしれない、と疑うのもレファレンスでは重要なのだが、そこまでするかどうかは性格のような気がする。
- 4月12日(木)
昨年度の仕事の処理のいくつかがまだ終わっていなかったりする。利用者多し。督促電話多し。開架から閉架へしまう本を選ぶ。閉架から除籍にする本を選ぶ。当たり前だが、除籍にしたら2度と図書館からはなくなってしまうわけで、これは最も慎重に行わねばならぬ仕事。頭と体力と両方を使う作業でもあり、消耗するのであった。
- 4月11日(水)
利用者多し。ブックポストへの返却本が1700冊ほどあったため、書架がめちゃめちゃな状態となっていた。延滞督促電話60件ほど。これだけで1時間近くかかる。指定管理にしている館はどうしているのであろうなあ。
- 4月10日(火)
『松ヶ根乱射事件』を観る。オープニングの男の子が、いかにも男の子で良かったが、いくらのことにも暗い話であった。救いのない話のところどころに、なんともブラックな笑いがある。三浦友和がとても良かった。山下敦弘監督、20代最後の作品とのこと。様々な映画をこれからも撮っていってもらいたいものである。
- 4月9日(月)
『蟲師』を観る。オダギリジョーと大森南朋が目当てであったので、さほど幻滅しなかったが、大友克洋はマンガに専念してほしい、と思ったのは私だけであろうか。
- 4月8日(日)
混む。延滞督促電話を沢山かける。
- 4月7日(土)
朝、空いていたので油断していたら、夕方から混む。延滞督促電話を沢山かける。1日以上延滞している利用者は全体の2、3割存在するのではあるまいか、と想像し、この国の歴史と現在について少し暗い気持ちになる。。
- 4月6日(金)
慌ただしく一日が過ぎる。延滞督促電話を沢山かける。
- 4月5日(木)
本の見計らい。本らしい本と、これは本なのであろうか、といった感じの本。中間の本が減っている気がする。延滞督促の電話と予約連絡の電話をする。ばたばたと一日が過ぎた。
- 4月4日(水)
休み。『バッテリー』を観る。子ども達がかわいかった。はじめのシーンで、どこかの塁にランナーがいるのにワインドアップで投げていて、おいおいこの映画大丈夫かいな、と心配であったが、同点で迎えた最終回の裏にランナー3塁で三振に打ち取ろうとしているシーンであった。それでも本盗を警戒してセットアップで投げると思うが。弟の投球フォームが随分ひどかった。直す時間がなかったのであろうか。と、どうも細かいところに目がいってしまうのは子供の頃、野球マニアであったからかもしれない。ともあれ爽やかな映画であった。春休で小学生が沢山客席にいたため、騒いだりしないだろうか、と怯えていたが、皆静かに観ていた。作品に引きこまれていたのであろう。滝田洋二郎監督はどこかが狂ったような映画はもう撮らないのだろうか。
- 4月3日(火)
予約件数の多い図書リストを作る。私が市民課に異動した98年か99年からはじめられたものであるが、このところ、眉唾めいた本もあったりして、果たしてこれは意味があるのであろうか、と考えぬでもない。しかし、多くの館でこうしたリストがあるようだし、掲示することにより、予約システムがあることを知るひともあるし、こまめにチェックをし、予約なさってゆくひともあるので必要なのであろう。ベストセラーと本の質とが必ずしも比例しない、と多くのひとは知っているのか、と時折心配になる。人気の高い政治家も同様。人気度についての報道は眉唾であっては困る。納豆で大騒ぎし、関西テレビのみが処分されるようであるが、起きていること、起きようとしていることをを報道せずにいるマスコミには罪がないのであろうか。憲法改正の国民投票について、テレビでわかりやすい説明はなされているのか。法律ができたら解説がはじまるのであろうか。身近な郵便局が消えることを想像せずに投票をしたひとたちが今度は戦争を起こせる法律をつくるのに加担し、そのせいで自分たちや、その子ども達が戦地へとかりだされる。戦争が終わったら、みんな誰かのせいにし、平和憲法をつくり、また数十年経ったら戦争をはじめるのであろうか。第二次世界大戦前にも制限選挙ではあるが、国民が政治に参加はしていたのだ。戦争を起こそうとしているひとだけでは戦争は起こせない。知ってか知らずかそれを支える多くのひとたちが存在するのである。
友人が面白いと教えてくれた中江兆民の『三酔人経綸問答』を岩波文庫の現代語訳で読む。はじめ原文で読もうとしてしんどかったのである。確かに面白い。現代でも古びていないのに驚く。
- 4月2日(月)
『ナイト・ミュージアム』を観る。楽しい映画であった。
黄砂ひどし。
- 4月1日(日)
年度のはじまりである。ばたばたと過ごす。レファレンス多し。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]