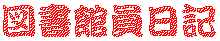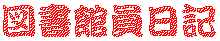
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん下 ]
- 3月31日(土)
年度の終わりである。ばたばたと過ごす。利用者は比較的少なかった。
- 3月28日(水)
日本図書館協会のメールマガジンを読んでいたら、衆議院内閣委員会会議録の中の平成19年2月21日号の戸井田とおる議員の質問とそれに対する黒澤隆雄国立国会図書館長の回答とが書かれていた。戸井田氏は、国立国会図書館所蔵資料にある明らかな間違いは訂正を貼付けるなり、ホームページに公開するなどの対処すべきだとの考え。南京大虐殺、従軍慰安婦に関する資料についてへの要望であるが、どちらも膨大な量の関連書、論文があるわけで、私が読んだ少ない数のなかにも怪しいところが様々ある。これらのすべてについて「事実」ではない箇所への訂正を求めるというのはかなり大変な話である。国会図書館長が答えた通り、憲法第21条の保障する表現の自由に関わるものであり「当館がみずからの判断に基づい
て資料の利用を制限したり、誤りであると判断することは、国民の人権の侵害につながる」のである。「事実」でないことが書かれている本は世の中には山のようにある。乱暴なことを書いてしまうと、すべての部分が正確な事実によって書かれている本は多くないのではないか。理科系の資料においては新しい発見があれば、その箇所が古い内容の資料をすべて訂正せねばならないこととなる。例えば、今までの資料に書かれていた冥王星についてすべて訂正するのか、といった話になるわけである。近い時代の我が国の歴史が他国によって歪められている点を許せないとの気持ちはわかるが、いささか無理のある要望であると思われる。しかし、今後こういった話がいろいろ出てきそうな気がする。先日は3館から盗まれた1400冊もの本が竹薮に捨てられるという事件があり、それが憲法や東京裁判、日米安保関連の図書であったとのこと。『図書館の自由に関する宣言』にあるように、「図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守」らねばならないのだが、その方法についてもしっかりと考えてゆく時期ではなかろうか。
- 3月27日(火)
とあることについて、近隣の二つの図書館の司書と相談をする。どちらも真面目な方で、機会があれば、多くの上司に『図書館の自由に関する宣言』の内容を知ってもらおうとしているとわかり、ああ、そうした時が私にもあったな、と、思い出す。「知」とあまり縁がない生活をしているひとに対して説明がうまくできるかどうかを、この頃は先に考えてしまう。憲法の、表現の自由については我が国に初めから存在したわけではなく、守る気で守ってゆかねばないがしろにされてゆくのはすでに今のマスコミの状況などをみればわかるわけだが、多くのひとが、このことを真剣に考える気がなかったり、自分と無縁だと思っていたりするのだから大変である。中学高校の日本史は古いところからでなく、新しいところかさ遡って教えるべきではないか、といったようなことを山本夏彦が書いていたが、私も同感である。ほんの60数年前の我が国の言論の状況を多くのひとが思い出す必要があるのではなかろうか。
植木等が亡くなった。子供の頃からテレビで観ているひとはなんとなく永遠にこの世に存在しているかのような気でいるのだが、特に植木さんはずっとお元気で、「お呼びでない、お呼びでない」と言っているのではないかと感じていた。ライブで一度、前のほうの席でみたことがあった。全身からなんとも言えない明るい空気を発していて、まばゆいほどであった。治安維持法で投獄されたこともあるお父さん植木徹誠のことを書いた『夢を食いつづけた男』は好きな本。ご冥福をお祈りします。
- 3月26日(月)
『ホリデイ』を観る。ジャック・ブラックがとても良かった。一瞬のカメオ出演の大物俳優には笑ってしまった。悪くない作品。
BS2のムーンライダーズの番組を観る。選曲が見事だった。
- 3月25日(日)
今年初のサッカー観戦。グランパスは見事に負けたのであった。中2日、中3日という試合が続いているのでばてているのであろうが、条件は甲府も同じ。甲府のディフェンダー山本英臣が良かった。増島も良いし、点が取れそうになかった。敵のシュートはポストに当たったり、クロスバーさんに助けられたりしていたのだけれど、観ていてずっと、これでは勝てないな、といった感じが漂っていたのであった。
午後7時20分から10時までNHKFMでムーンライダーズの特集を聴いた。メンバー6人が出演し、30年の歴史を振り返るという番組。白井良明が、斉藤哲夫と一緒に活動していたとき、かぐや姫の前座、井上陽水の前座など、前座を沢山つとめて、前座の神様と言われていたと話し、鈴木慶一が、「前座の哲学者」と茶々を入れたのが、とても面白くてしばらく笑っていた。斉藤哲夫は18歳でデビューしたとき、「若き哲学者」と言われていたことで有名。良明の最初に作ったバンドが「スピロヘータズ」だとか慶一さんの作ったバンドが「エレクトリック・マスターベーションズ」だとか、実にくだらなくてなんとも素敵な番組であった。ムーンライダーズは今日の深夜にもBS2で特番があるらしい。私の中のムーンライダーズ熱が少しずつわいてきている。
- 3月24日(土)
久しぶりの土日休み。見事に雨降りである。安城歴史博物館と埋蔵文化財センターにゆく。立派な建物。お客さんはあまりいなかった。安城市は古墳が多く出土し、縄文、弥生、古墳時代の土器も沢山出ていて、大きな集落があったらしい。私の仕事場で20年ほど前にここに邪馬台国があった、と長時間説明してくれたひとがいたことを思い出す。
日本対ペルー戦をテレビでみる。オシム監督になってからのサッカーはみていてわくわくする。高原の成長ぶりに目をみはる。
- 3月23日(金)
視聴覚資料の整理をする。年度末にせねばならない大きなことはだいたい終わった。
- 3月22日(木)
年度末である。利用者は割と少なかったのであったが、ばたばたざわざわであった。早く年度末が終わらないかな、と思う。
- 3月21日(水)
年度末には不思議な不安が襲ってくる。年度がしっかりと締められるのであろうか、という感じ。仕事多し。祝日なので、利用者もなかなかいた。
- 3月20日(火)
休み明け。ブックポストには600冊ほど。年度末でばたばた。
帰りに空を見上げると霞のかかった月と金星と夕焼がなんともいえない風情であった。
- 3月19日(月)
自分のホームページを久しぶりに見る。「一図書館員から見た日本」のいくつかは書いてから10年以上が経っているため状況が変わっているなあ、などと思う。「幼児、乳幼児の問題」は10年前のほうがずっとひどかった。書いた当時は悪化の一途を辿るのではなかろうか、と考えていたのであったが。そういえばいつ書いたのかの記録さえないなあ。だいたいの年と、今の時点における註釈をつけねば、と思う。
- 3月18日(日)
混む。年度末であるため、せねばならぬ仕事があれこれあり、気が焦っている。
30年ほど前に書かれた本に、とあるところに所蔵されているとされている資料についての質問があり、尋ねてみるとどうやら整理されていないらしい。図書館に限らず資料整理というのはなかなか大変な仕事であり、系統立てて誤り少なくそれをこなせるのは専門職であり、排架、保存にはお金がかかる。そしてそういう仕事はまるで儲からない。美術館、博物館、図書館を指定管理者の手に委ねれば、お金がかかるけれど収益につながらない作業はあとまわしにされる。幸い我が館はなんとか進んでいっているが、多くの館では今だって人手が足りていないからあとまわしになっている仕事なのである。歴史のある大学の図書館でもマイクロフィルムが塊になって転がっているところがある、と耳にする。高松塚古墳をあんなふうにしてしまう国なのだから、江戸や明治あたりのもの、まして大正、昭和の資料などどうでも良いと考えているのかもしれないが、素人ばかりが資料と関わるようになれば、いずれその仕事をせねばならない、と考えるより、無きものにしてしまえ、と考えるようになるかもしれない(噂レヴェルでは、貴重な資料を価値を知らないひとが廃棄してしまった、と他の施設で聞いたことがある)。地方に様々残る資料の保存を国が本気で考えたことは果たしてあるのだろうか。地方行政に委ねていて、それぞれの市町で考え方はまちまちで、どうなっちゃったかわからないもの、どうなってゆくかわからないものがいっぱいあるのであるのではあるまいか。
- 3月17日(土)
さすがに土曜日であった。記憶にない郷土資料のことを尋ねられ、いや、その年には出版されていないと思いますが、などと答えていたのだが、電算の入力が違っていたりしたため見つからなかっただけで、実際は存在しており、謝ったり、と、あれこれあった。
朝日新聞夕刊「なごやまる」に、ある図書館で無断で撮影され、テレビで放送されたひとのことが報じられていた。PFIが導入された館である。プライバシーについてPFIや指定管理の図書館は大丈夫なのかな、と前から心配しているのだが、館内におけるテレビ局の撮影で利用者を写さぬようにしてもらう、あるいはよくよく許諾を得て行うなどという最も基本的なところがないがしろにされているのか、とぞっとした。図書館ではとても沢山の個人情報を扱うわけで、貸出記録のように頭の中をのぞけるようなものまである可能性もあったりするのだが、大丈夫なのかなあ。普通の図書館では返却と同時に貸出履歴を抹消しているけれども、せずに記録することも当然可能であり、それをお金に換えたり、どこかに協力することもできるのだが、多くの人たちが果たして知っているのか、といったあたりが気にかかる。
これってすごくない。島のひとを全員島から出しちゃうんだって。報道ヘリを飛ばして中継してもらいたいと思うのは私だけだろうか。しかし迷惑な話であるなあ。
仮想敵は報道でいくらでも大きくなる。どこかの時点で極端に変わったわけでもない(20年程前まで、良い国だと書いていた大新聞社や大出版社があり、眉に唾をつけて読んでいたことを私は記憶している)北朝鮮が、日本において急に危険な国になったのは拉致被害者が帰ってきた2002年からであることを覚えておくべきだと思う。
- 3月16日(金)
このところ、私が受付に入ると混む気がする。その時間だけカウンターの人口密度があがる感じ。ばたばた。
サエキけんぞうの『さよならセブンティーズ』を読む。58年生まれなのにリアルタイムでビートルズの『ホワイトアルバム』を擦りきれるまで聴いていたというのがすごい。70年代の日本語ロックの現場にあちこち出かけているフットワークの軽やかさ。時代の空気のようなものがくっきりと切り取られている文章。ややマニアックかもしれないけれども良い本だった。
- 3月15日(木)
木曜日だというのになかなか混んだ。開架の書棚に本がいっぱいになっている箇所があり、閉架へしまう本を選ぶ。閉架に異動してしまうと、利用されることが減る。閉架にあっても利用がありそうな本と、開架にあってもさほど利用されなくなっている本をさがす。簡単な作業ではない。古い順にしまえば楽だし、それほど大きな問題はないのかもしれないが、ある本とある人とが結びつくべきであったのを、図書館員の手で摘んでしまうようなことを避けたいと思うのである。本は1冊ずつ全部違う、ということを忘れてはならない。人がひとりひとり違うように。
- 3月14日(水)
2日閉めたあとはブックポストに本がいっぱい。1300冊ほどあった。朝、利用者も
殺到。午前の2時間で貸出が1000冊ほど。
とある本について、他館がどのようにするかを電話で尋ねる。この件について、大変温厚なことで知られる人がかなり気分を害していらした、と耳にし、その理由を聞き、ああ、それは怒るよな、と納得する。図書館の現場では、「知」の自由について悩む場面が幾度も起きる。それは、憲法で保障されている「知る自由」と関わる事柄であるからなのだが、図書館以外の場所にいるひとで、本や「知」について何の興味もないひと、あるいは多少興味があっても、それほどたいしたことではないと思っているひと、つまり我が国の9割くらいのひとにとって、どうでもいいかもしれないことを、様々考え込むときがある。それがどういう意味を持つのかを説明してわかるひとはその9割くらいのひとのうちの半分くらいであろうか。しかしそれは人間の頭の中と関係のある、今まで人類が築いてきた財産と関わる重要な内容である。経験を積み、研鑽を重ねた司書であれば、前提を省いて検討に入れる話なのだが、そうでないひとたちにとってはどうでも良いわけで、テキトーに済ませることも可能であり、多くのひとたちにとって何の影響もないことでもある。司書はやはり要るのだがな、と感じるが、それがどうしてなのか、は、国の「知」に対する感覚の問題と大きく繋がっているわけで、国が「知」をないがしろにし、国民の大半がどうでも良いと考えれば、必要ではないのかもしれない、などと、ふと思う。
鈴木ヒロミツが亡くなった。モップスをラジオで初めて聴いたのは小学5年生。父の車のラジオで、『月光仮面』が流れた時の衝撃をよく覚えている。拓郎の『たどり着いたらいつも雨降り』よりも私はモップスのほうが好きだった。ご冥福をお祈りする。
- 3月13日(火)
『パフューム』を観る。予告でかなり話を割ってしまっているので、観るのを止そうかな、と考えていたのだが、面白かった。冒頭の魚市場のシーンが強烈。ヨーロッパの都市は現代になるまでかなり不潔であったと、読んだり聞いたりするが、絵にされるとのけぞる。香り、という映像化しづらいものが見事に画面にあらわれていた。
午後、電話が鳴ってすぐに切れた。思えば電話が最後にかかってきたのはいつであったろう。ほとんどのことをメールで済ます日々である。
- 3月12日(月)
ミリオン座で溝口健二の特集があるので出かける。『赤線地帯』。若尾文子が出ているのがうれしい。昭和30年代の日本の底辺はああだったのだ。格差があるとは言え、結核で死にかけていて、医療費が払えないから死ぬしかない、という人の数は多くなく、売りに出される少女もそれほどはいない今の時代は、かなり豊かなのかな、と思う。300年続いた吉原をなくす売春防止法に溝口は賛成していなかったようである。なんということのない室内の映像がとてもきれい。光と影を実に上手く撮っている。お祝いの料理を食べているところでおむつを替えているシーンに驚いた。昔はあんなものであったのであろう。
- 3月11日(日)
混む。閉架へ幾度もゆく。予約の帳票を沢山いただく。さすがに日曜である。
- 3月10日(土)
なかなか混んだ。大学生らしき若者がレポートにでも使うかのような本を探しているので、「レポートを書くのならば、雑誌の論文を集めたほうが楽だと思うよ」と言うと、「なんですか、雑誌の論文って」と尋ねられる。Webで雑誌記事索引を使える時代になっているのだが、雑誌の論文を使うという発想自体がないとなんともならないのだなあ、と思う。実際に引き方を見せて説明すると、「それで、その雑誌はどうやって見るのですか」と問われる。「そこから先は大学図書館を使って、所蔵を調べてもらい、自館になければ他館からコピーを取り寄せてもらえるよ」と、仕事を大学図書館に渡したのであった。と、こんなことを幾度も書いたような気がするなあ。
『文學界』4月号、小林信彦の『日本橋バビロン』を読む。随筆なのかな、と思ったのだが、目次に長篇小説とあった。読み終えたらぞっとした。これはホラー小説であるかもしれない。今までの作品群で断片的に語られていた箇所のいくつかが生な形で描かれていて、なかに激しい悪口がオブラートに包まれたように入っていたりするのだが、そうしたところが私にはとても興味深かった。「真逆(まぎゃく)」という言葉が使われていたのには真逆(まさか)と目を疑ってしまったが、東京では定着している言葉であったのであろうか。
- 3月9日(金)
昨日、近所の図書館からあった問い合わせについて回答の電話を朝にする。それはかなり自館にも関係のありそうな事柄なので、なぜ調べ始めたのか、ほかの館にも尋ねておられるのか、良い方法をとっているところがあるかどうかについて尋ねた。相手館のひとは明快で論理的。質問は大抵理由があって始まるわけで、他館の問題は自館においても問題である可能性がある。そして多分尋ねてきた館よりも早くそれについて対応をしたのであった。
研修等で職員が少なく、あれやこれやとあって、ばたばたとした一日であった。
- 3月8日(木)
真摯に過ごしている若い図書館員からのメールが昨日届いた。日頃考えなくなってしまったことを考える。脳が、かなりの刺激を受けたみたいだ。同じような日常、思考を繰り返していると頭のどこかが少しずつ錆びているのかもしれないと思う。
『イカとクジラ』を観る。ウディ・アレンに似ているとの評があったが、出来事の切り取り方や角度が随分と違う、と思う。ローティーンとハイティーンの兄弟のざらざらした感情の、ほんの少しの揺れを細かく描写している。お兄さん役のジェス・アイゼンバーグがとても良かった。
メールしても連絡がなく、年賀状もこなかったので、てっきり亡くなったと思っていた友達からメールが届いた。入院なさっていたとのこと。命があって良かった。メールのやりとりと年賀状のやりとりだけをしている電脳筒井線時代の友達が幾人かいるが、亡くなったとしてもわからないであろうな。私が死んでも、同じことである。
- 3月7日(水)
年度末は気分が焦っている割に仕事が進まず、それほど急がなくても良い仕事を思いついてしまったりするのが不思議。とりあえず急がぬ仕事は置いておいて、選書と視聴覚資料の発注をする。
CD屋さんが来て、CDの流通の世界の大変さを聞く。問屋さんが倒産したりしているとのこと。考えてみたら私も大きなCD屋さんにゆくか、Webで発注するかであり、町のCD屋さんになど長らく出かけたことがない。今は1曲ごとのダウンロードをしているひとも多いわけで、CD屋さんという業種自体の危機なのだ、と認識。中学、高校の頃、高くて買えないレコードを、いつか買いたい、と、見るためだけにレコード屋さんに行った時代を懐かしく思ったり。
- 3月6日(火)
利用者の来方に波のある日であった。
難しいレファレンスがあった。その分野に詳しい知人がいるので、帰宅後メール。忙しい人なので返事がくるかどうか。
- 3月5日(月)
朝、鰹節屋さんにゆく。店の名前を数年間勘違いしていたことに気づく。
『善き人のためのソナタ』を観る。何年に一度という傑作であった。今年一本だけ観るというひとにはこれを勧めます。
こないだの古本屋がどこであったかを確かめるため、回る。店はわかったが、その本があった位置に穴が開いていた。
夜、ムーンライダーズTHE MOVIE『マニアの受難』を名古屋シネマテークで観る。何の註もないので、ファン以外が観てもつらいかもしれない映画であったが、私は幾度か泣きそうになった。
- 3月4日(日)
さすがに日曜である。混む。閉架の資料が今日も沢山利用されていた。
長らく探していた本が昨日「日本の古本屋」に割と安い値段で近所の古本屋さんに出ていたので、Webで注文したのち電話をし、帰りに買いにゆく。「こんなに高い値段で買わなくてもきっとしばらくすると下がるよ」となじみのおじさん。1年くらいは探していたんですよ、と言うと、その間に2冊売って、1冊は今より千円安かったよ、とのこと。言ってくれたら買っていたのに、と思うが、私から言わないのであるからしかたがない。探していることを言うと、相場が上がってしまう可能性があるので、なるべく探求書について古本屋では語らないようにしている私である。
- 3月3日(土)
割と空いた土曜であった。視聴覚資料の発注業務。老眼が進んでいることをしかと感じる昨今である。
漢詩を持ってきて、「こうけいの詩だと思うのですが、色々さがしても出てきません」という利用者。はて、聞いたことがある詩人だが、と、思いつつ、「こうけいって、どんな字でしたっけ」と問うと、「高啓」とのこと。それでも思い出せないので『中国学芸事典』を引き、「高青邱」のことであるとわかる。ならば全詩集がある。どうも頭の接触が良くなくなっている感じである。
- 3月2日(金)
先日回った古本屋に、郷土人の資料があったのだが、所蔵していることを確信していたので、そのまま通りすぎたのだった。郷土担当と話をしていたら、良い状態のものがないし、元版であれば購入したいとのこと。はて、どこの古本屋であったか、と記憶を辿る。ここ以外ではない、と思われる店に連絡を取ったところ、「ありませんし、入荷していたこともないと思う」との返事がきたとのこと。記憶が弱ってきているようである。
暖かくなってきたので、ノラが早くから暴れる。
- 3月1日(木)
ふと、電脳筒井線の本を読み返してみた。自分が過去に書いた文を読み赤面。今ひとに読まれるとかなり恥ずかしい気がする。あの時期、朝配られる新聞を待ちかまえて読み、1日200もの膨大なログをすべて読み、そこに埋もれないような目立つ短い文(長いと読まれない可能性があった)を書いた半年。参加者全員が睡眠不足となりながら、パソコンの世界と小説の世界と日常生活を行き来していたわけで、みんながどこか狂っていたのかもしれない、と15年前のことを振り返る。
- 2月28日(水)
何かを知る、というのは実は大変なことで、知らない方が良かった、とか、わからずにいれば平穏であった、と思うことはしばしばある。本を読まずにいられない性分にならなかったほうが幸せであったのか、不幸せであったのか、と時折考える。「知」とか知識欲といったものは実に恐ろしいし、読書によってひとが患ってしまう可能性などを想像すると眩暈がすることがあるのだが、「本」についての仕事をしているひとすべてがそのような状態になるかどうかをふと知りたくなるときがある。
登録者が多かった日であった。CDの発注と図書の発注をする。
- 2月27日(火)
朝、ブックポストに返ってきていた本は600冊ほど。開館時間までになんとか棚に戻すことができた。利用者はそれほど多くなかったが、調べもの、閉架図書の利用はかなりあった。『としょかんだより』に載せる本を選ぶ。
- 2月26日(月)
名古屋シネマテークにチェコの監督ヤン・シュヴァンクマイエルの『ルナシー』を観にゆく。随分ヘンテコな作品で、ところどころ大笑いしそうになる。筒井康隆の短篇に似た題材のものがある。ひとによってはかなり不気味であり、生々しい?生肉がしばしば出てくるので、それに食傷する可能性があろう。
- 2月25日(日)
朝から古本屋をまわる。大須のノムラ書店、猫飛横丁が閉まっており、歩いて上前津へ。三松堂が閉まっていた。鶴舞まで歩く。いりなかの山中書店も休み。日曜定休ではなかった店がいくつかあったはずだが。時は流れているのであるな、としみじみ思う。ともあれ古本屋のなかをうろうろするのは楽しい時間である。本についての記憶、増補版が出る前には高額であった全集が、さらに再版され、恐ろしく値崩れしているのを見て少し淋しくなる。すべてのもの、ことが変転している。
- 2月24日(土)
名古屋市美術館に大エルミタージュ美術館展を観にゆく。「大」がつくほどの規模ではなかった気がする。シュルヴァージュの『風景』、ドランの『水辺の家』の絵葉書を買った。
- 2月23日(金)
昨日の利用者が資料を返却してくれた。ほっとする。
閉架図書の利用が近頃とみに増えている。利用者用件作端末機を使うひとが増えているのである。いままで死蔵に近い状態であった資料が借りられてゆくのはうれしいものである。
- 2月22日(木)
延滞した資料のある利用者が、なんとか家族の券で借りられないか、と幾度もほぼ同内容の質問。ともかく、遅れた資料を返して正常な状態で利用をしていただきたい、督促にもコストがかかるのである、とお願いをしたのだが、不満げに帰ってゆかれた。1ヶ月以上の延滞資料と20数日の延滞資料と2冊あるのである。明日返さねばならぬ資料を借りている状態で別の資料を借り、それから1ヶ月以上返していないという状況。また、予約をしては遅れ、ということをしばしばする人でもある。私の勤務する館では、家族であっても他人の貸出券の利用は不可、としている。督促をした際、「私は図書館に何年も行っていない」とか、「それは私の券ではないが、私が借りたのだからタイトルを教えて欲しい」などといったトラブルがあったり、本人の券では何ヶ月も延滞している資料があるのに、別の家族の券で堂々と借りている利用者が幾人かあったりもしたためである。家族券、という格好でまとめるのも良いのかもしれないが、その場合、1人が延滞をしたら家族全員が借りられなくなるわけで、それはそれで揉め事の種となろう。他の館では2週間延滞するまで貸出可、であったり、4週間延滞するまでは貸出可であったり、いくら延滞している本があっても貸出可であったりするようである。そしてそうしたルールを最大限利用する人物、というのが世の中にはいる。家族のふりをしてやってきて、同様の利用をしているというケースもあろう。下を見てゆけばきりがなく、そちらに合わせてゆけば、どこまでも方針は甘くなってゆく。社会教育機関としての図書館とはなんであろうか、と、あれこれ考えていたら暗澹とした気分になってきた。公共図書館活動が進んでゆけば、「個人」が増える、といった幻想を私はかなり長い間持ってきた。しかしそうはなってゆかない気がしてきている。
- 2月21日(水)
休み。出かける予定でいたのであったが、風邪のため、一日養生。
- 2月20日(火)
視聴覚資料の発注。かなり買い揃えたあとの選択なので、なかなか難しい仕事となっている。
- 2月19日(月)
『ドリーム・ガールズ』を観る。ジェイミー・フォックスがなんとも厭な役で良かった。エディ・マーフィはあんなに歌がうまかったのか。ミュージカル好きのひと、ソウルミュージック好きのひと必見、といった映画であった。『バベル』は未見だが、菊池凛子はジェニファー・ハドソンとオスカーを争うのだなあ。
風邪をひいた。
- 2月18日(日)
混む。
古い新聞の原紙を利用なさる方がある。酸性紙なので、かなり危険な状態となっている。触ると粉になるところまではきていないが、こうした資料を沢山持っている館はどうしているのであろうか。
- 2月17日(土)
勉強をしに来る中学生多し。ばたばたする。
利用者多し、レファレンスも沢山。気難しい利用者もいたりして、仕事を終えるとよれよれになっていた。
- 2月16日(金)
休み。朝、久しぶりに無言電話あり。
阪本順治監督の『魂萌え』を観る。風吹ジュンの同級生が、藤田弓子、由紀さおり、今陽子って無理がありはしないかと思われるようなキャスティングであったがそれほど違和感はなかった。藤田弓子は昭和20年、由紀さおりは23年、今陽子は25、6年であるが、風吹ジュンは岸辺のアルバムのときに20歳そこそこだったはずでいったいいつの生まれだっけ、ともあれ藤田弓子とは10歳くらい違う気がするぞ、などと思って観てしまっていたのだが、しばらくしたら慣れた。加藤治子と風吹ジュンの入浴シーンが圧巻。この二人、テレビ版『阿修羅のごとく』に出ていたが、一緒に映っているシーンはなかったような、などとぼんやり思う。それにしても加藤治子はおっかない。かれこれ85歳くらいになるのではあるまいか。加藤治子を観るだけでも価値のある作品。歌を歌うシーンで、風吹ジュンが歌ってなかったのが残念。浅田美代子の下手さが有名だが、風吹ジュンの歌もすさまじかった記憶がある。
晩に共著のひと2人と論文完成の打ち上げでフグを食べる。刺身、皮、茶碗蒸、鍋、雑炊、ひれ酒を堪能。食べるのに忙しくてあまり話をしなかったほど。雑炊の米一粒一粒まで食べ終えたのであった。
- 2月15日(木)
変則的な連休のあとなので混む。4500冊ほどの貸出。日曜日並である。
- 2月14日(水)
『ディパーテッド』を観る。ラスト30分くらいで話がぼろぼろになってしまったのではあるまいか、と感じた。
バレンタインデーであるが、私とは無縁であった。
- 2月13日(火)
『世界最速のインディアン』を観る。アンソニー・ホプキンスがとても良かった。映像がきれいで、ロードムーヴィーで、素敵な映画であった。
- 2月12日(月)
月曜に開館していると、開いているかどうかの問い合わせ電話がよくかかってくる。返却よりも貸出がかなり多く、登録も多い一日であった。
- 2月11日(日)
午前に空いていて厭な予感がしたのだが的中。午後から混む。
『先生とわたし』のおしまい近くに描かれた師弟三人についてのことが気になってくる。別の三人との対比をしてしまう私は穿ちすぎなのであろうか。あろうな。なんとなく丁寧に隠そうとしている、というように読める箇所があり、そこで引っかかってしまったのである。ともあれ一筋縄ではゆかない作品。
- 2月10日(土)
混む。レファレンスも多い。20年以上前から見知っている利用者からの質問に答えていると、「そこに戸田さんがいてくれるとほっとする」と言われた。生きていた良かったな、となんとなく感じた。
延滞督促の電話をする。
四方田犬彦の『先生とわたし』読了。どきどきしながら読み進んだ。傑作である。ラカンの『エクリ1』の訳への批判はつまりどういうことだったのかな、との疑問が湧いたが。
- 2月9日(金)
物忘れがひどい。朝覚えていたことを昼に忘れていたりする。
昨日、小学生高学年から中学生向けの雑誌の所蔵について小学生から尋ねられた。一誌は所蔵していたのだが、私はぱらぱらと開いたことがあるくらいで、実に不勉強な態度であった。彼女は二誌の存在を知っていて、それぞれ特徴があることを教えてくれた。また、一誌についてはタイトルを略して呼んでいるそうである。「おじさんはそのジャンルまるでわからないので、教えてください」と尋ねたのであった。知らない事柄を知るのはそれがどんなことであれ嬉しい。しかし対象年齢層が極端に狭い雑誌たちであるなあ。今までにここまで絞った雑誌はあったのだろうか。マニアしか読まない雑誌というのは沢山あるわけで、読者層を狭くしても広告も入れられるし、採算が取れるということなのかもしれない。
出版社が見計らい図書を持って来館。そこの本は古くから買っているので、欲しいものは大抵所蔵していた。良い出版社が良い本を出し続けられることを願う。
- 2月8日(木)
ばたばたであった。受付に4時間半出た。
昨日買った「新潮」に載った四方田犬彦の『先生とわたし』を読みはじめる。「波」で予告を見たときからわくわくしていたのであった。まだ途中までしか読んでいないが、大変興味深い評伝である。
- 2月7日(水)
ナベゾこと渡辺和博さんが亡くなった。私にとっての彼はガロ編集長であった。やまだ紫の『性悪猫』が載っていたからであったか、永島慎二の『その場しのぎの犯罪』が載っていたからであったか、それとも、おお、まだ出ているのか、と思ったのか、78年の冬、私はその雑誌を購入した。荒木経惟の名をはじめて知ったのはガロによってであった。赤瀬川原平、上野昂志の連載もあった。ナベゾというひとの不思議な絵も載っていて、このひとが編集人であった。何ともヘンテコなマンガ雑誌は月刊なのだが、出る日が一定ではなく、扱っている本屋さんもとても少なかった。定期購読を本屋さんに頼もうかとも思ったが、このひとは変なひとなのではないか、と思われる気がしてできず、隣町で月の半ばまでに入手できないときは名古屋の、バックナンバーまで揃っている店に出かけたりもし、青林堂が出している単行本もついでに買ったりしていた。『金魂巻』が有名だが、『週刊本』に彼の書いた文章に良いものがあった。小林信彦も評じていた記憶がある。56歳は少し早すぎる。ご冥福をお祈りします。
休み。朝、『マリー・アントワネット』を観る。豪華絢爛だが、淡々とした映画。物足りない感じもあるけれどきれいな良い映画だった。
晩になごやレファレンス探検隊。前回は腸炎で不調だったのだが、今日は快調。発表者が病気になるというジンクスがあるとかないとかで、今回は県図書館のKさんが風邪をひいておられた。名古屋のS氏の問題はインターネットでは決して回答できない、また、レファレンスツールをすんなり使えない実に良いものであった。こうした調べものには素人では決して対応できない。
懇親会場で同室だった大学生と思われる若者のなかに声の大きなのがいて、外国人差別発言や天皇礼賛を浅薄な知識で何の根拠もないまま、わめいていた。「世界で一番偉いのは天皇である」と、謎の説明に基づいて言っていて、まるで1940年代初めの小学生並だな、と呆れた。こういう輩が増えているのであろうか。狭いWebサイトだけを行き来して集めた情報を鵜呑みにしているのかもしれない。多くの論を知った上で信念を持って語るのであれば良いのだけれども。10年若かったら、何か言いにいったであろう私。若者達はどこにゆくのかな。
彼らの団体は早くに去り、平穏な懇親会となった。ドイツ旅行にいったひとがいて、皆で写真を見ていた。写真の裏にそれがどんな写真なのかの説明があり、食事の写真の裏にメニューもついていた。アップルジュース、と書かれたものもあった。6人坐ったテーブルのうち、ドイツに行ったことのないのは私だけであり、少し肩身が狭かった。初めて話すひともあり、楽しい時間を過ごすことができた。
- 2月6日(火)
朝、混む。書架案内も多い。図書館員は開架、閉架とよく歩くなあ、としみじみ思う。ばたばたとした一日であった。
- 2月5日(月)
『あるいは裏切りという名の犬』を観る。はじめはとてつもなく陰気で厭な映画なのであろうか、と不安になったが、良い作品であった。セリフはそれほど多くないのにド・パルデューのなんという存在感。
- 2月4日(日)
午前中、空いていたので厭な予感がしたのだが、午後から随分激しい混雑であった。督促電話もかける。閉館間際、長らくいらしていなかった、過去に大事件を起こした方の姿を目にする。何も起きないと良いが。
- 2月3日(土)
混む。ばたばたであった。延滞督促の当番。ひとりひとりはかなり気楽に延滞していて、ああ図書館から電話がかかってきたなあ、遅れちゃったな、と思うだけであろうが、かける側は100件ほどかけるのである。督促でかかった実費は徴収すべきではないか、と昔から考えているのだが、となると、確実に平等に督促電話、督促葉書を出す必要があるであろうし、それを払いたくないがためにさらに返さない、などという悪循環も生じるやもしれぬわけで、無理なのかな。このあたり、よその国ではどうしているのか以前から気になりつつも、調べていない私。
しかし、他国と比較しても、国民性が異なるのであまり意味がないようにも思われる。イギリスのシステムを真似て我が国の公共図書館の運動は進んできたのだけれど、国民性や、国の文化に対する施策や、出版状況などがあまりに異なっていたのではあるまいか、といった話をあまり聞かない。我が国における「本」は40年前と現在とでは大きく変化しているのだが、今でもすべてをひとからげに「本」として論じているところに図書館の問題がありはしないか。
- 2月2日(金)
老人力がついてきているのをひしひしと感じる昨今である。来週分のカウンターローテーションを作ったのだが、以前はほかの仕事の合間に一時間ほどでできていたのが、集中して二時間ほどかけて作って、誤りがあったりする。
BS2をぼんやりと点けたら、長谷川きよしが出ていて、ついつい見入ってしまう。生々しい演奏。椎名林檎がゲストで出て、『灰色の瞳』を歌う。そういえばカヴァーしていたのをラジオで聴いたな、と思い出す。加藤登紀子とのデュオよりも良い。サビの箇所の長谷川きよしのパートが難しいのだよなあ。あなたは何処にいるのだろか、ってところ。谷川俊太郎の詞、武満の曲『死んだ男の残したものは』も良かった。阿佐田哲也が長谷川きよしについて書いているエッセイで好きなのがあった、と思い出す。
- 2月1日(木)
利用者がやけに多い。なぜだろうか、と考えてはたと気づく。先々週の木曜日は、年末に借りたひとの返却日に設定してあった日で、3000冊以上の貸出をしたのだった。慌ただしく一日が過ぎる。
- 1月31日(水)
論文の校正と、部屋の片づけをしたくて休みをとったのだが、昼寝をしてしまったり。もうそろそろこの部屋をなんとかせなば、と考えはじめてから4年ほどになる。箪笥の抽斗が開かないのはかなり不便だ。
- 1月30日(火)
研修と休みのあとだったため、恐ろしい量の仕事がたまっていた。利用者も多かった。ばたばたと一日が過ぎた。
- 1月29日(月)
小池昌代の『井戸の底に落ちた星』(みすず書房)を読む。詩人はおっかないな、と思う。収められている書評のいくつかは初出時に読んでいるのだが、こうしてまとまると何とも言えぬ迫力がある。本を読むとはどういうことなのか、という根源に迫る本。書き下ろしの短篇小説『海の本』はとっても怖い。ひさびさに良い本を読んだ。
- 1月28日(日)
ベルイマンの『サラバンド』を観に名古屋シネマテークへ。早めにゆき、4番目に並んでいたのだが、前の3人が続いて上映される『ダーウィンの悪夢』も観る、と番号札をもらっている。映画館のひとが私に、「『サラバンド』だけでよろしかったでしょうか」と尋ねたので、「ええ。『サラバンド』だけです」と答えた。しばらくして気になり、やはり『ダーウィンの悪夢』も観ます、と言う。イングマール・ベルイマンの映像はとにかく美しい。お話なんてどうだっていい、と思えてしまうくらいに美しい。そして物語は重いに決まっているので、覚悟を決めて観たのであったが、それほど息苦しくはなかった。妻をうしなったあとを生きるヘンリックの「人生は空しい儀式だ」という言葉が印象に残った。
『ダーウィンの悪夢』はタンザニア、ヴィクトリア湖のナイルパーチをめぐるドキュメント。アフリカの貧困の上に、我が国も含め、裕福な国があるのだよな、としみじみ考えさせられた映画。あの干物はあまり食べたくないな。食物連鎖について、そろそろ真剣に対策を練らないと、なんともならなくなると思うけれど、すでに手遅れかもしれませんな。タンザニア、タンザニアという曲のメロディが耳についていたり、夜警のひとの目の光を時折思い出したり。すさまじい映画であった。
- 1月27日(土)
朝、『幸せのちから』を観る。予告で観た以上のところがなかった。ウィル・スミスを観るために行ったので、まあ満足ではあったが。
朝日陶芸展を観に高浜市のかわら美術館に行く。初めて出かけたのであるが、観終えて出てくるとピアノコンサートがはじまるところであった。展示室に音が入るのではあるまいか、観ているときに聞こえてこなくて良かった、と思った。大賞の『つちぶえ』はとてもダイナミックな作品で、なるほど大賞だなあ、という感じであった。
安城市の古本屋に出かける。犬と猫がいる店なのだが、犬はもうあまり先が長くないとのこと。
この頃無言電話がまるでない。なんとなくそれはそれで落ち着かない。
- 1月26日(金)
講師の生年が1968年と聞いて驚く。一昨年に書いた論文に彼の論文を引用しているのだが、私より10歳くらい上のひとだとばかり思っていた。かなり以前から様々な雑誌でお名前を見かける人。ほかの受講者の多くも、同じように考えていたみたいであった。しかしさすがに詳しい。館ごとで判断すべき、としながらも一定の見解を示し、明らかにそのようにしか解釈できない事柄については断言をし、と1問ずつに対し、しっかりと解説。グループの出した回答に矛盾する点や甘いところがあると鋭く質問を出してこられたりもした。思い込んでいたことが誤りであるかもしれない、と気づいたり、用心せねばならない箇所がわかったり、と実にためになる研修であった。かなりバテたけれども、これほど充実した研修を受けたのは職に就いてから初めてであった。
- 1月25日(木)
県図書館で著作権の研修会。事前に送られてきていた大量の問題をグループごとに討議。法律に詳しいひと、しっかりと下調べをしてきているひとがいて、順調に進む。他館の鋭いひととの共同作業は刺激的であった。書記をしたのだが、変換の際に何やらヘンテコで入力しづらかったりした。問題作成には担当のMさんがお正月休みを費やしたとのことで、一筋縄ではいかなかった。終わり次第帰っても良いとの話で、終了予定時刻は17時であったから15時くらいに終われるといいな、と考えていたのだが、全グループのなかで最も早く提出したものの終わったのは17時50分。20時までは開館していますので、とMさんが恐ろしいことを言っていた。
頭が著作権法だらけになっていたのを冷ますため、帰宅後、『それでもボクはやってない』を観にゆく。男にとって、とても恐ろしい映画であった。加瀬亮がとても良い。むっとした顔の鈴木蘭々も良い。小日向文世は厭なひとを演じると活き活きとしている。メッセージ性が生で出てくる映画はどうも苦手な私である。それにしても満員電車に乗るときには用心せねば。
- 1月24日(水)
明日、明後日と著作権の研修であり、その後二日は久々の土日休みなので、今日のうちに多くの仕事を片づけねばならなかった。図書の見計らい、視聴覚資料の整理をする。
個人情報の載っている一般に流通していない資料の扱いについて担当者が悩んでいたので、日本図書館協会の、「個人情報保護に関する主な検討課題」に関する意見を読んでいたら余計にわからなくなり、いくつかの図書館に尋ねるが、どうもすっきりしない。このところばたばたと様々な法律が作られているが、あらゆるところにおいて問題が起きないかどうか、といった点がないがしろにされている場合がしばしばあるのではあるまいか、という気がする。
- 1月23日(火)
文部科学省からの「地域の図書館サービスの充実に関する調査研究」というアンケートがしばらく前に送られてきた。司書有資格者全員が答えるものなのであるが、発送が5日、回答期限が25日。じっくり答えると一時間くらいかかる内容。これをとりまとめたりなんだりする。図書館行政に生かされると良いのだが。
レファレンス多し。
- 1月21日(日)
とても混む。閉架へ幾度も走る。休んでいる職員が幾人かいたこともあり、ばたばたであった。息が切れた状態で接客していたりもした。
- 1月20日(土)
利用者に尋ねられた江戸期に書かれた文書の本を書架に探すとない。この本、不明になったことが一度ではない。誰でもが読める本ではないのになぜであろうか。大学生の宿題で使われたりするのかなあ。公共図書館の触れられたくない問題に、不明図書と延滞図書がある。コストの点でこの問題を語ると大変なことになろう。指定管理者制度が導入された図書館においてはどのようにしているのであろうか。延滞督促電話をこまめにかけたり、葉書を出したり、盗難防止装置で盗まれたときブザーが鳴るようあれこれしたり、大きな館においてはガードマンをおいたり、といったようなことをしているのであろうか。
- 1月19日(金)
混む。今日が年末に貸し出した本の返却日に設定してあったのである。
『新世紀エヴァンゲリオン』26話分観終えた。19話が一番好き。しかし、動かないアニメーションであるな。私の好みとはかけ離れていたのであったが、読みはじめた本を最後まで読まないと気がすまないのと同様、観はじめるとおしまいまで観ないとおさまらない性格なのであった。困ったことである。
- 1月18日(木)
休み。ケン・ローチ監督の『麦の穂をゆらす風』を観る。名古屋シネマテークでの最終日であるせいか、とてもたくさんのひと。隣に坐ったおばさんが大鼾。独立戦争というのは大変であるな、とか、自由というのは闘って勝ちとるべきものなのだよな、といった当たり前なのだけれども忘れていたことを思い出す。きれいな映像。痛々しい映像多し。自由を勝ちとった国と、なんとなくみんなが自由になった気でいる国との差を思う。この頃、私は闘わなくなっているな、と気づく。闘い続けるのは簡単ではない。
植民地であった国がどのように独立国になったのか、とか、自国が戦争をしている時にその戦争を命がけで止めようとした国民がいた国のことなどを、小中学生の頃に教えるべきではないだろうか。そうした国々とこの国との違いは知っていたほうが良い。
- 1月17日(水)
県図書館に電話をしているとき、講習について受講生からのアンケートを集計したものを送ってもらうことになっていたのがまだ来ていなかったことを思い出し、ついでに尋ねると、入力が終わったばかりであったとのこと。メールで送っていただいた。それほど不評ではなかったようでほっとする。
混む。見計らいの出版社が来たのだが、すでにかなりその版元の本は買っているので、せっかくきてくれたのに意味があまりなかった。
- 1月15日(月)
かなり前に話題になっていて、友達が観ることを勧めたりもしたのだけれど、観たことのなかった『新世紀エヴァンゲリオン』をyoutubeで無料配信しているとのことなので、観る。マジンガーZやガンダムが苦手な私。人間が大きなものを操縦してなにやらする、というのだどうも駄目なようである。エヴァンゲリオンは科白が話題になったりしたようだが、ガンダムもそう。しかし、私はそれもまた体質的に合わないのであった。なにやらわけのわからぬストーリー展開であったりする。なかに「ヤマアラシのジレンマ」というのが出てきた。友人が数年前、これについて話をしたことがあったが、エヴァンゲリオンとは無関係であったはず。ヤマアラシの針は倒れるはずなので、仲良くくっつけるのになあ、と、この寓話だか童話だかについてはまるでよくわからなかったりする。私に向かないアニメーションであることを確認することができたのだが、観はじめた以上、最後まで観るべきなのかな、と悩む。
- 1月14日(日)
混む。遠方に住んでいる大学生の娘の宿題をしにお母さんが来館。著作権法上複写がみなはできない資料の複写を依頼されてきたとのこと。内容も量もほとんどなく、ほかの資料からの子引き、孫引きであるので、恐らくこれは論文の役に立たないと思われますよ、と説明。娘さんがこの資料を、と言った理由は、どこかに参考文献として載っていて、タイトルから類推して多くの事柄が載っているのでは、と考えたのだと思われます。とも説明。なんとなく卒業論文に使うらしい話。彼女が住んでいる地域にもこの資料を所蔵する館はあるのだし、出身地についてのテーマを設定したのであれば、自分で調べなくてはいけないと思う。真剣に調べようとしている姿勢はあるようなのだが、どこかが根本的に間違っている気がしてしまう。
することが多く、ばたばた。
利用者に、筒井康隆さんの著作の話をする際、「筒井さん」と言ってしまった。怪訝な顔をされた。
- 1月13日(土)
混む。レファレンスも多かった。
- 1月12日(金)
午前中、混み、昼からはやや穏やかになった一日であった。
ベストセラーとか、何かのベスト10といった本がよく借りられるのは昔からではあるが、この数年その傾向が顕著である。なかにはそうした本しか読まないひともある。それにしてもわけのわからぬベストセラーが増えている。なんにでも「力」をつけて、「りょく」と読ませる感覚の持ち主を私は好きになれないのであるが、世間はそうではないようである。
信じやすい国民、というか、疑うことを知らない国民が多いのであるなあ、と納豆がなくなったスーパーの売場を見て思う。納豆を二週間食べると痩せるらしいが、何年も毎日食べている私はいったい何キロになっていると良いのであろう。ブッシュがイラクへの兵員を二万人も増やす話への反応はあまりなさそうなのに、食べ物については過剰なほど情報を取りこんでいる。去年は寒天がすさまじい勢いで売場から姿を消し、相場がはねあがった。なんというか情けないニュースではある。そのニュースを見て納豆を買いに走るひともあるのだろうか。そういえば72年のオイルショックのとき、トイレットペーパーの買い占めが起きたっけなあ。走るときは一斉なのが恐ろしい。次はどこへ向かうのか。
沖縄ではこんなことが起きていたりもする。
- 1月11日(木)
ばたばたとした一日であった。自分史を書くために少年期をおくった土地について調べる方、遠方から明治期の雑誌をご覧になられた方など、レファレンス多し。満足して帰ってゆかれる利用者を見送るときは幸せである。
- 1月10日(水)
ロベルト・ベニーニの『人生は、奇跡の詩』を観る。同じ夢を毎日見る、というのが身につまされる。大人の童話のような映画。観終えて気持ちがなんとなくすっきりとした。
- 1月8日(月)
昨日、一昨日とそれほど混まなかったせいか、今日は混む。
昼休に『新潮』を買う。去年12月号の中原昌也『怪力の文芸編集者』と、この2月号筒井康隆『ダンシング・ヴァニティ』とが反復形式で書かれている点が非常に似ていると、1月号に書かれていたので興味深く読む。驚くべき共時性である。中原さんのは短篇で、読者を気にしない、というか、とてもとんがっていて、筒井さんの作品は長編の第一部で、ポップである、という差はあるが、使われている方法が同じなのであった。シンクロニシティというのはなぜ起きるのかがまるでわからぬ、実に興味深いものである。こんな実験的な手法による作品が同じ時に書かれている不思議。
川本三郎の『言葉のなかに風景が立ち上がる』も買う。「モクセイ地図」とか「カスピアン・ターン」について書いた作家にふれた章がある。こうした単語について語ることのできた友の不在を思う。
郷土資料を出している出版社の話で利用者のかたと盛り上がる。
- 1月7日(日)
西日本新聞のこの記事を発見。春にこの単語で件名検索にかかってきたため、標目表の変更があったはずなのに、MARCは変わっていなかったのだな、と気づいたのに直すことを失念していたのであった。歳というのは恐ろしいものである。
CDを発注するといくつかは廃盤である。私の勤める図書館は20年以上CDを購入していて、名盤と言われるものの多くをすでに持っている。選ぶのはなかなかの作業である。ウィキペディアで、ジャズミュージシャンを検索して、グラミー受賞作で買い落としているものがありはしないかと見てみたりもする。しかし、このジャンル、日本語のウィキペディアは充実していないようである。ブラッフォード・マルサリスはあるのに、ウィントン・マルサリスがなかったりするので、しかたなくアメリカのを見たりする。このところ老眼が進んでいるのと、元々英語が苦手なのとでへとへとになったりする。
『文芸誌「海」精選短篇集』のなかの阿部昭『人生の一日』を読む。はじめに読んだのはいつのことであろうか。どこを読んでいたのであろうか、という気分になる。この本に収められた作品のほとんどを単行本で持ってはいるが、雑誌「海」に載ったという視点で編まれていると実に興味深い。1960年前後生まれにとってのアイドル作家的存在であった筒井康隆、小林信彦が大江健三郎の同級生であった同誌編集長塙喜彦の依頼で先鋭的な作品を載せた雑誌。橋本治がなにかにアフォリズムのようなものを書いていてそこに、「『海』−SFも載っている」とあったのを目にし、店頭で手にとったら筒井さんの『虚人たち』が載っていたのだった。あれから28年もの時が過ぎたのか、と眩暈がする。中公文庫の、創業120周年記念企画のうち、文芸誌「海」関連の三冊をほとんどの本屋で目にしないが、これは良い本である、と思う。
- 1月6日(土)
暮れに貸出をした分の返却期限がまだ先だからなのか、貸出返却は土曜日にしては少なかったが、レファレンスがやたらとあった。大学生のレポートや卒業論文の季節らしい。卒業論文のテーマにしようとしているらしき人物について調べにきた学生が、その人物の名の読みを違えていたり、インターネットで検索をしたとのことであったのだが、調べ方がよくわからないらしきことに少し驚く。しかし、親が調べにくるのでないだけましである。
- 2007年1月5日(金)
午前は混むが、午後からは空いた。仕事が休みのひとは昼からどこか遠くへ出かけたり、家であれこれするのであろうか。閉架の児童向け古典小説を女子高生が出してくださいというで、「それは抄訳だけど、良いのですか」と問うと、「全訳はあるのですか」と返され、所蔵していたかどうかの自信が一瞬なくなる。十数年前、個人的に探したその作品の全訳は岩波文庫と、講談社の世界文学全集に入っているきりで、ほかからは出ていなかったのだった。その後、大正に出た個人全集があることを知ったのは、複刻されてからで、おお、その複刻の全集はあったぞ、と、記憶が蘇り、「旧字旧仮名のとても古いのならば、確か全訳であったはずです」と答えると、「それでも構いません」との返事。ところで旧字旧仮名を普通に読める高校生ってどれくらい我が国にいるのでしょうね。誰か調査してみませんか。念のために検索してみると、数年前に新訳が出ていて、所蔵していたので、それを提供。利用者用検索端末機ではうまくひっかからない入力になっていたのであった。大喜びの利用者。司書の醍醐味である。こんなやりとりは素人さんには無理であろう、と、ひとりほくそ笑んだ新春の私であるが、こうした専門性を評価する人の数がとても少ないのも厳然たる事実である。
書き忘れていたが、昨日の朝、天地の間に「一」の字を描いたかのような虹を見た。冬の虹自体珍しいが、こんなのは生まれてからはじめてであった。
正月休みに、これについて長い文を書こうと思っていて、時が流れてしまったのだが、昨年12月10日付の朝日新聞『知事権力−逮捕ドミノ2」のなかに気になる箇所があった。宮崎県の安藤前知事について、「初当選した直後、部長級ら36人を突然異動させた。知事選で相手方についたとされる総務部長を県立図書館長に」とあったのだ。この異動が栄転でないことは確かなようである。知事の人事権についての話なのではあるが、日本の国における県立図書館長の位置を新聞社がどのように見ているかについて考え込んでしまった。日本のジャーナリズムについても、また。
- 2007年1月4日(木)
暮れから正月にかけてのブックポストへの返却図書は数年前に比べると3分の1ほどに減っている。貸し出された数は多いくらいなのだが。こうして返ってくる本のなかには一年以上延滞していたものなどもある。
書架にたまった埃を払い、雑巾をかける。図書館は閉まっていても、館内ではひっそりと仕事が行われているのである。
気がつけば45歳である。
後輩からきた年賀状に家族の写真が載っており、二十年ぶりくらいでみる彼の姿のあまりの変わりように唖然とする。今まで来たなかで最も衝撃度の大きい年賀状であった。
- 2007年1月3日(水)
あけましておめでとうございます。
暮れは大掃除をしたり、黒豆や昆布巻を煮たり。猫のノラが寝ている間に昆布を巻いた私。しかし残り数枚になったとき、起き出した。なぜか生の干瓢を好きな猫なので大変なのである。
大晦日は早く寝て元日のとても早くに自転車に乗って初詣。時間が良かったので誰もいなかった。お伊勢さんはこの時間でも混んでいるのであろうな、と想像する。
1日が締切の句会があり、新年の句を元旦からつくるが、良いのができない。
名古屋市の図書館のF本さんがとあるウイルスにおかされた、とのメールを頂く。バイキンくん、というあだ名で呼ぶのはどうかな、と一瞬考えるが、大人はそういうことをしてはいけないのだよな、と思い直す。
日めくりタイムトラベルという番組が面白く、ついつい最後まで観てしまう。ミニスカートに飛びついたひとたちがその後、韓国スターに飛びついたのかな。右向け右の号令に何の疑いも持たない人がいっぱいいることを改めて感じる。当時5歳であった昭和42年という年は私にとってGSの年だった。祖母の家で共働きの母が帰ってくるのを待つ間、従姉からGSについての英才教育をほどこされていたのであった。訳の分からぬ固有名詞を詰め込まれたのだ。違う勉強をしていたらどうだったかな、と時折考えないでもない。当時若者であって、さまざまな破壊をしたひとたちはその後この国をどのようにしたのであろうな。
- 12月27日(水)
開館するのは今日まで。混む。レファレンスも多い。
生きていらっしゃるかどうかがはっきりしていないひとにメールを出してみたが、お返事がない。
- 12月26日(火)
学生は冬休であるが、それほど来ていない。
難しい調べものを受ける。もしかすると何かの資料に載っているかもしれない、と、しばらく探すが見つからず。宿題。年を越してしまうことであろう。
- 12月25日(月)
年賀状づくりで一日が終わった。数年分、どこに送ったのであったか、と調べていたら、亡くなった方や、あれこれあった方の名をみつける。諸行無常である。
- 12月24日(日)
クリスマス・イヴだからなのか、平穏な一日であった。知らない資料を教えていただいたりもした。普通に流通されていない郷土資料については、お客さんに教わることも多い。耳を傾けていないと通り過ぎてしまったりするので気をつけていなければならない。
- 12月23日(土)
先週から返却期限が来年に設定してあるためか、利用者がそれほど多くなかった。しばらく前から幾度かいらしている謎の利用者が怒っていらしたので、お話を伺う。歴史について調べていて、すでにかなりそのことについての知識を持っている方で、それ以上のことをどのように調べれば良いのかがわからなくなっている状態でいらっしゃることが判明。いらだちの主な原因はそこにあったらしいので、それ以上調べるためには古文書を読まねばならないけれども、そこに知りたいことが書かれている可能性は薄いことを説明した。また、ご自分が何をどのように調べ、その過程であれも調べ、これも知り、といった話を沢山してゆかれた。かなりスリリングで面白い内容だったが、脇に入り、迷路を彷徨うような感じにもなった。過去に多くの図書館で揉めてしまったとか。興奮なさりやすいひとのようではあるが、理知的な話し方をなさっていた。昔、「私は○○の子孫なのに系図に出てこないのはヘンだ」と喚いていらしたひとと対応をした経験があったので、すこし恐れながら出ていったのだったが、杞憂であった。レファレンスは難しく、時にはかなり時間をさかねばならないこともあるのであった。それが司書としての糧となってゆく場合もあり、徒労に終わる場合もある。そもそも人生とはそうしたものかもしれない。
- 12月21日(木)
朝から気が重くなるようなことがあった。年末はさすがに仕事が多い。
俳句の雑誌の原稿が完成。宿題が少しずつ減ってゆくのはうれしい。
- 12月20日(水)
『クリムト』を観る。私の好みではなかった。映像はきれいだし、クリムトを演じる役者はクリムトみたいだったし、エゴン・シーレを演じる役者はエゴン・シーレみたいだったのだけれども。
- 12月19日(火)
図書館についての本が多いとの指摘をするひとが来館。全部で1000冊もなく、年に30冊くらいしか購入していない分野であり、館の職員ではなく、大学で図書館学を学んでいるひとや、図書館に興味を持つひとが利用する旨を説明しても納得してもらえなかった。他館から電話でこうした質問があったとの話があったので多分同一のひと。なんとなく気持ちの悪い感じがぬぐえないので理由を考えると、「図書館がどのように本を選ぶかの本が図書館にあるのはなぜか」という問い自体が、パラドックスであることに気づく。本で答えを得ようとするひとであれば、「図書館についての本」を調べるわけで、その分野の本がなければならない理由ができてしまう。それを指摘していたら恐らくその人は逆上していたようにも思うが。
- 12月18日(月)
『犬神家の一族』を観る。リメイクした意味がよくわからなかった。奥菜恵が目的であった。
- 12月17日(日)
利用者多し。4時の時点で貸出冊数が4000を超えていた。
日本の古典を探す中学生を手伝う。年末年始に読むようである。10代の半ばあたりまでに古典に沢山触れておきたかった、と今しみじみ思う。英語よりも日本語が重要である。日本語で思考し、さまざまな表現ができないのにほかの国の言葉を喋ることができ、外国人とやりとりをしたって、日本人はバカだ、と思われるだけではなかろうか。母国語を大切にするフランス人が時折うらやましくなる。
- 12月16日(土)
混む。来週の受付ローテーション表を作り、予約が沢山かかっている図書のリストを作り、新刊の発注をしたり。
- 12月15日(金)
無言電話がこのごろない。我が家にはまるで電話がかかってきていないことに気づく。スパムメールは毎日100件以上来て賑やかだが、ふつうのひとからはほとんどこない。
多くの図書館でも同じであろうが二週間後から年末年始の休みに入るため、返却期限を長く設定してある。沢山借りてゆく利用者が多い。
中日新聞に坂口安吾の『白痴』が連載されているようで、それの複写申請依頼。「『白痴』ならばありますが」と言うと、「連載で少しずつ読むのが良いのだよ。戦後にこの作品をそのようにして読んだ」とのこと。小説にはいろいろな読み方、楽しみ方があるのだ。安吾に関連する話をあれこれする。
- 12月14日(木)
休み。ノラが、炬燵に入った私の足の上に乗るので、なにもできなくなり、テレビの国会中継を見ていると腹が立ってくるので、古い友達に電話。やがてノラはどこかへゆき、私は『エコール』を観に出かけた。幼女趣味のひとには良い映画なのであろうが、私にはまるでそのケがないので、なんだか厭なものを観せられている感じであった。細い臑が好きなフットフェティシズムのひとにも良いのかもしれない。映像が美しくはあった。しかしこの話、無理がずいぶんある。『タクシー』のマリオン・コティヤールがバレエの先生役で出ていたが、同僚の先生とのやりとりがよくわからなかったり。
11日に書いた文に書き足したが、まだ字数が足りないのであった。
- 12月13日(水)
利用者用検索端末がやや不調。昨日の影響である。
暮なので慌ただしい。珍しく、文学綜覧シリーズの複写依頼があり、見ると、とある作家の全集の内容。「このひとの全集は閉架にありますから、言ってくだされば出しますよ」と言うと、「え。検索したけれど、出てこなかったよ」とのこと。どうやら名前の読み方を間違っていらしたようである。その作家に関連するほかの作家の話などをする。思えば利用者と本の内容について話をするケースはあまりない。たいていは外側(タイトル、出版年など)の話ばかりである。
- 12月12日(火)
もともとは休みなのだが、電算のあれこれの立ち会いのために出勤。なかなか大変なことになった。
最近不便が段々なくなっているのだが、便利ってそんなに素晴らしいのかな、と時折考える。もしかしてそちらに戻ったほうが幸せになるかもしれない不便の側に動けなくなっているのであればそれは便利中毒ではなかろうか。ついこの間までなかったものがない状態に返ることができないのが人間のさがなのであろうな。どこへ行っちゃうのか。
- 12月11日(月)
『硫黄島からの手紙』を観る。二宮和也のうまさに驚く。加瀬亮もとても良い。日本の複雑な事情をしっかりと把握して作られている。二時間半があっという間であった。クリント・イーストウッド監督は偉い。この映画は観ないと損ではなかろうかと思う私。
俳句の雑誌に載る文章をノートに書く。我ながらなかなか良い出来だな、と原稿用紙に落としてみると字数が全然足りていなかった。書き直さねば。
- 12月10日(日)
朝、先日いらした不思議な利用者が後輩と謎のやりとりをしている。季節のせいであろうか。
混む。レファレンス多し。貸出は5000冊ほど。
- 12月9日(土)
帰る頃やたらと疲れていた。利用者が少なくはなかったが、なぜこんなに、と考えていてふと気づいた。利用者が作者の異なる和歌と俳句を十ほど書いて持ってきて、解釈の載った本はありませんか、と尋ねたのに対応したのだが、これはひとつのレファレンスではなく十件のレファレンスだったのだ。そういうことがすぐにわからなくなっているのは歳のせいかもしれない。
- 12月8日(金)
休み。109シネマズに『パプリカ』を観にゆく。今敏監督、音楽は平沢進。傑作であった。夢の中に出てくるものたちがかわいらしく、色がきれいで、実写では映像化不可能なところを見事にあらわしていた。筒井康隆原作のこの作品は「マリクレール」誌に連載されていたとき、『朝のガスパール』−『電脳筒井線』がはじまり、連載が中断されたので、電脳筒井線参加者にとって縁の深い物語である。単行本になって通して読んだときの衝撃はいまも残っているのだが、映画はまたそれとは違ったぞくぞくを与えてくれた
レファレンス探検隊の回答を県図書館のM氏に手渡したあと、調べものをする。名古屋市鶴舞中央図書館へ行ったほうが良さそうだったので地下鉄鶴舞線に乗る。「上前津」との放送が入ったら降りたくなり、古本屋を回りつつ、鶴舞へ向かう。なかなか良い本が200円均一の棚にある。真冬に古本屋めぐりをするのは楽しい。
- 12月5日(火)
久々の出勤。仕事が沢山たまっていた。
謎の利用者がきた。図書館までの道のでこぼこについて長々と不平を述べておられた。急に寒くなると様々なことが起きる。
- 12月4日(月)
『007カジノロワイヤル』を観る。長い映画であった。全体的に悪くはなかったのだが、プロットに甘いところがあり、観終えたあと、はて、という気分が残った。
- 12月3日(日)
南田辺駅というところで降り、古本屋へ。98年版の全国古本屋地図によると10時からあくはずなのに、あいていない。やってきたおばさんに訊くと、店売りはしていないとのこと。3匹の猫に紐をつけて散歩に出かけるこのおばさん。2匹は道に寝そべってしまった。しばらくあとをついていきたくなるが、止す。
日本橋にゆき、天牛書店を目指す。文楽劇場のそばであったはず。その番地はどうやらコンビニエンスストアになっていた。そいえば、大阪第一ビルの古本屋が減った話は岡崎武志の『気まぐれ古書店紀行』にあったような気がしてきた。根気がなくなり帰ることにする。黒門市場の近くで昼食。この店には入った記憶がある。ふぐを食べたのはここだった、と思い出す。家に帰って調べると2000年8月のこと。前日にはオフラインミーティングがあったのだった。インターネット予約をしたホテルに前払いをさせられた上に1万円を余分に置いてゆけ、と言われた厭な記憶も蘇る。大阪の古本屋をまわったのはその時以来。なくなっているのも無理はない。
帰りの電車では紀伊国屋書店で買った『文芸誌「海」精選対談集』(中公文庫)を読む。面白い対談とそうでないものとがある。
- 12月2日(土)
大阪へ行った。古本屋をまわろうと思いたったのであった。まずは梅田のかっぱ横丁。以前は確かかっぱ横丁のテーマソングが流れていたのではなかったか。うるさくてたまらなかった記憶があったが、静かになっていて安心。文庫本の100円均一棚に少し珍しい本があったので3冊買う。くろふねビルには古本屋が1軒しかなくなっていた。大阪第一ビルへゆく。4軒あるはず、と思っていたのだが、浪速書林が目録販売専門の店になっており、あとの3軒はなかった。愕然。前に来たのはいつだったろうか、と考える。
電車のなかでは幻冬舎新書の『インテリジェンス』を読んだ。かなり面白かったが、この本、なにかの狙いがあるのではあるまいか、と冒頭の佐藤優の言葉から連想してしまう。
Tさんから論文の件で割と大きな問題がありそうな話の連絡があった。
ホテルの夕ご飯で酷い目にあう。
- 12月1日(金)
休み。こないだ閉まっていた安城の古本屋へ行く。とある作家の本を買いにいったのだがその作家の本はない。しかし、良い本がいっぱいあって困る。店の小父さんと話すと、もう80歳になるとのこと。ご自身は文庫本が好きで、もう少し出したいのだけれど、幾人かの作家のを出すとすぐに売れてなくなってしまうので、悲しくなるから小出しにしているとのこと。先日閉まっていて看板もなくなっていた店について尋ねると、店主が入退院をくりかえしていてもう営業していないと言う。もう1軒、掘り出し物がよく出た店について訊いてみると、そこの店主はタクシーの運転手をしているという。一応古書店組合に入っているとのことなので、いつか再開するのであろうか。淋しい状況である。
2時頃電話が鳴って切れる。
- 11月30日(木)
昼休に幻冬舎新書を冊買う。新書はいったい何種類あるのであろう。清水良典氏は以前、図書館で文学講座をひきうけてくださったことがある。『2週間で小説を書く!』のあとがきを読むとおつれあいさまへの謝辞がある。朝日新書の『村上春樹はくせになる』にもあった。羨ましいような憎たらしいような微笑ましいような気分になる。
レファレンス多し。句碑にあった自由律の句の上五がどこにあたるのか、というのを受けていた職員がいた。一応、元の句が載っている本を探す。かなり以前、職員がその俳人の句集を見ていた記憶があるのだが、それが何であったのかを思い出せず、日外アソシエーツの文学綜覧シリーズを探す。ややぼけ気味である。それにしても図書館には日々様々な質問がやってくる。
- 11月29日(水)
交通安全研修があった。飲酒運転と轢き逃げについての怖い映画を観る。主演は金田賢一であった。ATGの『正午なり』が彼のデビューであったはず。原作は丸山健二である。丸山健二の近頃の作品の日本語にはどうもひっかかってしまう私。
古い友達が句会に行ってきた、とメールをくれた。私が最後に生の句会に出たのはいつだったろうか、としばらく考え、かれこれ5年ほど出ていないことに気づく。
またしても生牡蠣を食べる。腸は無事なようだ。お粥とうどんと雑炊の日々を一週間過ごしていたとき、生牡蠣を食べたくて仕方がなかった反動がやってきているらしい。フランスではバケツのような入れ物に生牡蠣が出てくるところがあるそうだ。一度そういう食べ方をしてみたいものである。
- 11月28日(火)
出勤途上でヌートリアが死んでいた。この頃増えているようである。あの大きな齧歯類が人を襲うと怖いだろうな。
CDを目録から選ぶ。いよいよ老眼である。
帰りにスーパーに寄ると宮城産の生牡蠣があったので買って帰りこじあけて食べる。
- 11月27日(月)
『プラダを着た悪魔』を観る。メリル・ストリープが強烈であった。予告がよくできている映画であったな、と観終えて思う。私の好むラストではなかった。
腹の調子が良いので生牡蠣を食べてみるがなんともない。
- 11月26日(日)
混む。リクエスト、予約多し。本らしい本へのリクエストはしかし激減している気がする。旅行ガイドのリクエストが多いのは図書館に旅行ガイドがあるからであり、オカルト関係のリクエストがくるのは、オカルト関係の本が多い図書館も結構あったりするからである。
出版傾向が変化してきていたときに、利用者の要望を全て受け入れる方向のまま多くの公共図書館が進んだのは良いことであったのだろうか、とこの頃しばしば考える。にちにちの仕事に流されているうち、知を守る場であることを失念してしまいはしないかと不安になる。読み物、はやり物ばかり読むひとが9割、純文学を読むひと、学術的な本を読むひとが1割、そのなかで調べ物をするひとは3分くらいという状態であって、自治体の財政状況が厳しくなればどういう方に図書館が向いてゆくであろうか、と想像する。読み物、はやり物だけをパターン配本してもらい、リクエストは判断せずに全部購入、調べものはどこかおおきな自治体の図書館に行ってもらうこととし、司書は不要、となりはしないか。利用者の読書水準の向上を目指した資料選択をしたとしても、より難解な図書に利用者が進むかどうかはわからないわけだが、少ない資料費で、娯楽だけのための図書を多く選択してゆけばどうなるか。利用者の喜びには繋がるが、どんどんと無料貸本屋に近づくだけではあるまいか。そうなった時、司書の居場所はあるのか。すでに手遅れの感もあるが。
- 11月25日(土)
歴史関係の調べものを継続的にしていらして、ついに古文書を読まねばならないところまできてしまったという利用者がご来館。調べものは楽しくも恐ろしい、としみじみ思う。その人とあれこれとやりとりをしているうち、歴史小説の話となり、私が、「歴史小説あまり好きではないのですよね。歴史学科出身なのですが」と口を滑らせてしまった。しかし、歴史は苦手であり、地図も苦手であり、系図もできれば見たくない、と説明をする。西洋史専攻であったのだけれど、語学もまるで駄目であったこともついでにつけ加えておいた。思えばいいとこなしである。
『プレイボーイの人生相談』をしばらく前、本屋でぱらぱらと読み、買うのを止したのであるが、今東光の『極道辻説法』が気になっていた。一昨日、なんとなくブックオフに行ってみたところ集英社文庫版が100円であったので買ったのだった。中学高校生の頃にプレイボーイを買うと真っ先に読んでいた連載。めちゃめちゃな坊さんがいるものだなあ、と驚いていたのであった。悩み相談なのだが、「女も口説けない」という相談の答えが、「簡単だ。マスかいとれ!」だったりする。壮絶である。「効果的な試験勉強は」との質問に、「新聞雑誌類は一切読まないようにする」とあった。「新聞を見るとダーッと見出し見て、事件を知っても、もう翌日になるときれいに忘れちゃって、「あれはいつの事件だっけ?」ということになる」と書かれていた。ヘッドラインばかりのインターネットの現在、今東光師が生きておられたらどう思うだろうか。
- 11月24日(金)
視聴覚資料のデータ入力作業が一段落。目が疲れた。
久々に鍼灸院にゆき、膝と腰にお灸を据えてもらう。ぢぢいみたいで良い感じである。
スパムブロックというのをかけている。こちらには多い日には150通くらいやってきている。それをすりぬけてくるのが150通くらいというときもあるので300通ほど来ていたりする。もしかすると、重要なメールを読み落としている可能性もあるが、多分ないことであろう。今日から一週間くらいはスパムブロックされている側もチェックしてみます。きっとオオアリクイに主人を殺された、とかそういうのしか来ていないと思いますが。
- 11月23日(木)
ホームページを開いてから丸十年である。思えば長く続いている。今朝、というか真夜中に電話が鳴って切れた。良い感じの夢を見ていたときだったのだが。起きてメールチェックをすると61通も来ている。内訳はスパムメール58通、ダイレクトメール3通。このところ個人のひとからメールがほとんど来ない。出さないこととも関係しているのかもしれない。
混む。わかりそうもないレファレンスを一件受ける。
- 11月22日(水)
県の図書館協会のレファレンス研修の日。休憩をはさんで2時間半の予定であったのに、質問があまり出てこないことなどもあって15分余ってしまったが、だいたい考えていたとおりの話ができた。書誌についての基本的な認識を持つべきであること、一人の作家の全作品を読もうとしてみると良いこと、など、など。笑いをとることもできたし、ぼちぼちの出来であったと思われる。
- 11月21日(火)
視聴覚資料のデータ入力作業。根を詰めてしていたら気持ち悪くなってくる。老眼のケが出てきていることも影響しているように思われる。
- 11月20日(月)
研修のレジュメと資料が完成。なんとか2時間半喋れそうである、との見込みができた。
安城の古本屋にゆく。この季節なのに店内に蚊がいて、刺される。以前、この店に友達が探していた作家の本が大量に並んでいたな、と思いつつ、書架を眺めていると、その時の本の並びが一瞬目の前に現出する。少し疲れているのかもしれない。最近しかし古本屋の夢を見なくなった。
- 11月19日(日)
レファレンス研修に自分で出した問題について気になる箇所ができたため、近所の図書館に行き、新聞の縮刷版を調べるが見つからない。大学のとき、確かに目にしたコラム。当時我が家では2つの新聞をとっていたのだから、どちらかにあるはずなのだが。そればかりに時間を使うわけにもゆかず、帰宅。ほかの問題の回答をチェック。ほかの人の調査過程はなかなか興味深い。
- 11月18日(土)
今日から3連休。午前は22日のレファレンス研修の準備。午後、豊田スタジアムへグランパス対浦和レッズの試合を観にゆく。厳しい試合だったが、なんとか勝利。うれしい。
サッカーを観たあと今池ボトムラインでムーンライダーズのライブ。結成30年である。相変わらずトンガっている。鈴木慶一は55歳。いつまでも新しい音楽を作っている。日本一のロックバンドであるな、としみじみ感じる。
- 11月14日(火)
『父親たちの星条旗』を観る。戦闘シーンがリアル。スピルバーグが撮ったとか。とても厭な話だが、戦争はそもそも厭なものであるし、アメリカは元々厭な国である。良い映画であった。続編を早く観たい。帰宅後うどんを食べ、横になって過ごす。
- 11月13日(月)
土日はばたばたであったが、なんとか過ごしたのだった。
今年も眼科へ黄斑部変性の検査にゆく。視神経にヘンなところがあるとも指摘されたが、昨年とさほど変化はなかった。
眼科が早く終わったので腸のお医者さんへもゆく。あと三四日で良くなるのではないか、と言われるが、まだしばらくはお粥。魚の煮たのも食べて良いとのことなので、ブリ大根を作る。
- 11月10日(金)
仕事へゆくが、なんだか体調が良くなくて夕方早引け。医者にゆくと、静脈注射の太いのを3本打たれる。今日は大先生であった。「食べるのはお粥。大根、人参、じゃがいもなどをやわらかくたいたの。冷たいものは飲んではだめ。薬をきちんと飲むこと」と言われたので、「そうしていれば大丈夫ですね」と気楽に訊くと、「大丈夫じゃないよ。そんな簡単な病気じゃないっ」と叱られた。お医者さんには子供の頃よく叱られたが、実に久しぶりだったのでなんだか懐かしかった。お粥は好きになれない私。そういえば昔、友達を見舞に行ったとき、「七分」と書かれた紙を見て「七分粥」のこととわかっていつつ、「ななふん?」と言ってウケたことを思い出したり。食べたいものを食べられないのは大変であるな、としみじみ思う。
- 11月9日(木)
休みをとっていて、朝床屋へゆき、映画へゆき、古本屋にゆき、それからレファレンス探検隊へ、という予定だったのだが、腹がヘンなので朝、医者へ行った。触診をされ、「押すときより離したときのほうが痛いようですね」と言われたあたりで怪しい、と思い、「もしかして胃腸風邪ではないのですか」と問うと、「これは胃腸風邪ではありませんね。もう少し下だと盲腸だけれど、ううむ」とお医者さん。腸がどうやらなにやらなっているとのことで、抗生物質の薬をもらう。
結局1日寝ていて、晩にレファレンス探検隊へ。コメンテイターだったのである。しゃべり場では、「医療、健康関連図書」についてだったので、私が、「どうして医療健康なのかな」と発言すると、県のひとが、「それだけじゃなく、起業支援とか法律関連とか、今まで図書館が目を向けていなかったサービスをしてゆこうということです」と言うので、「生き死に長寿関連と銭金関連なのだよなあ」と嘆息。さらに、「しかし、そうした分野については専門家が沢山いるわけで、もし流行ってしまって、そうしたサービスに重点がおかれるようになり、彼らが図書館に常駐するようになった場合、司書は何故必要なのかということになりはしないだろうか」と私。「ああ、暗い話ですね」と、場がなんだか明るくなくなってしまったのであった。病の影響であったかもしれない。私はしかし、司書は「本についての専門職」なのであるから、足を踏み入れていなかった分野ではなく、例えば019分類の読書ガイドについて、こんなひとにはこの読書ガイド、というような案内ができるように、するようにしていった方が良いように思う。また、医療健康とか闘病記に熱心になれないのは、物心つく前から10年ほど闘病していたこととも無関係ではないのかな、と気づいたりもした。これもまた病の影響かもしれない。体調はかなり良い感じにはなっていたが、大事をとって宴会は不参加。はじめての方もいらしたので行きたかったのだったが。
- 11月8日(水)
朝、腹の気持ちが悪いな、と感じる。昼に食欲がない。生まれてこのかた、食欲がなかった記憶がほとんどない私なので、胃腸風邪のたちのわるいのかもしれない、と思いつつも、パンを買ってきて1個食べる。午後、熱っぽかったが、仕事をする。県図書館に問い合わせの電話をすると、レファレンス探検隊の局長M氏が出られた。明日はレファレンス探検隊である。帰宅すると38度。風邪薬を飲んで早めに寝る。
- 11月5日(日)
混む。
しばらく前にいただいたメールで東京都知事が都立図書館の司書について語った事柄に触れられていた。呆れたが、図書館を使わない金持ちにとってはこんなものかもしれない、と感じる。司書って何してるの、と問われて、あらゆる人に必要である、とわかってもらえるような回答があるだろうか、としばらく前から私は考えている。
- 11月4日(土)
毎日のことだが、携帯電話の着信音がうるさい。館内で話し始める輩もかなりいる。以前にも書いたかもしれないが、あれは免許制にするのが本来ではないのか。図書館で着信の音がするのは日に10回やそこらではない。映画館や芝居の最中にもしばしば鳴る。免許制にし、音を鳴らすべきでない場所で電源を切っていない人間には罰金刑を処すなどすべきである。と、書いても、利権のなにやらがあったりしてはじまっているシステムなのであるから、なんともならないことであろうが。
江戸期の資料を遠くから閲覧にこられた方があった。将棋の本を所蔵しているところはあまりないとのこと。閉架の本の利用多し。ばたばたであった。
- 11月3日(金)
祝日である。混む。
昼休に単車で食べ物屋さんへ行った帰り、国旗をたてている家を発見。うちの近所は30年くらい前までどこでもたてていたなあ、と思い出す。血塗られていても国旗は国旗だし、日の丸はかわいいと思う私である。アラビアの国旗を描けるひとはあまりいないが、日本の旗は、子供でも描ける。
新刊書の見計らいをしていたら古い友人コモエスタ坂本氏の出した 『低度情報化社会』という本を発見。彼は早くから堀江貴文を批判していた慧眼の士であるが、変人としても知られている。
- 11月2日(木)
救命講習を受ける。以前にも一度受けたことがあったが、心臓マッサージはかなり体力がいるなあ、と改めて思った。
図書館で働いていると、本の値打が下がった、と感じることがしばしばある。以前にも幾度か書いたが、床の上で本を広げる子供を叱らぬ親、本を踏む子供を叱らぬ親、カウンターに投げるように本を出す大人を目にする回数が増えている。以前は活字の載った紙をまたぐと叱られたものであったが。パソコン、インターネットの出現で活字の価値が落ちたのは確かな気がする。それで書かれた事柄を真に受けない人が増えたのかと言えばそうでもなさそうなのが不思議である。原稿用紙に書いた文字が活字になった喜びを味わえなくなった世の中は淋しい。
学校ってなんだろうな、と考える。必須科目未履修問題である。世界史と日本史の片方しか学んでいない人が高校を卒業しているのである。高校を卒業しないと大学にはいけないのだけれど、すでに幾人もが進んでいるらしい。大学でまともに勉学に励む学生は稀である。バカを沢山作ってどうしようというのかな。と、まともに勉強をしたことがない私が書くのもどうかと思うが、しっかり履修をした生徒とそうでない生徒とで受験に対する有利不利ができてしまっているなかで、「受験勉強の時期に補修を受けたくない」などと言ってる高校生がいっぱいいるのは、自分さえ良ければフェアでなくとも構わないと言ってるのと同じなのだが、そのあたりについての考察を17、8にもなってできていないのはどうなのだろう。もちろん悪いのは高校であるが、履修すべき科目を履修していない、と知っていた学生は皆無だったのか。この高校では履修科目が少ないから受験に有利、とわかっていたとしたら、かなり悪い。そんな人間が立派な大学に入って社会に出て偉くなっちゃったりしたらろくなもんじゃない。根の深い厭な感じの話である。目先の損得だけを追う人間ばかりが蠢く気味の悪い国になったな、と、しみじみ思う。長い間続いてきた週5日半を週5日制にしたことが良かったのか、を本来は考え直すべきであろうが、一度はじまってしまった制度を元に戻しはしないのが我が国の伝統である。
- 10月30日(月)
『カポーティ』を観る。なるほどフィリップ・シーモア・ホフマンがアカデミー男優賞をとっただけのことはあったのであった。新潮社『夜の樹』のポートレイトをみると顔がみごとなまでにそっくり。以前、何かのテレビ番組でトルーマン・カポーティが話すのを見たことがあったが、あんな感じであった。実にきれいで静かな映像だった。『冷血』を書いたカポーティと、村上春樹が『アンダーグラウンド』を書いたのとは関係があるのかな、と、映画を観終えてふと思った。これについてはすでに誰かが書いているかもしれないが。清水良典さんの『村上春樹はくせになる』をこないだ読んだからこんなことを思いついたのであろう。
- 10月28日(土)
朝昼と割と空いていたのだが、私がカウンターに出た晩に混み始める。閉架から、良い本を沢山出した。若い人が、古い良い本を借りてゆくとき、なんとなく幸せな気分になる。
- 10月27日(金)
センチュリーシネマに『日本以外全部沈没』を観にゆく。いかにも低予算映画であった。面白い箇所もあったが、あのかっちりとした原作の世界を長い映画にするのは難しかったようである。
パルコの服屋さんを何軒か回る。館内に『燃えよドラゴンズ』がエンドレスで流れていて気が狂いそうになる。店員さんにそのことを言うと「なかなかたまりませんよ」と泣きそうな顔をしていた。私は30分もいたら気持ちが悪くなってきたのだが、彼らは一日いるのである。時期だけのこととは言え大変。音が暴力であることがわかっていないひとが世の中には多いとしみじみ思う。
- 10月26日(木)
大学図書館のYさんから朝、草稿が送られてきた。Yさんは大変緻密で間違いが少ないひとなので、熱心に気になる箇所を探した私であった。頭から何かを書くのは大変だが、書かれたものについて何かをするのは随分と楽な作業であるなあ、としみじみ思った。
小島信夫が亡くなった。最晩年に評価が高まった作家も珍しいのではなかろうか。
- 10月25日(水)
永井愛作演出、寺島しのぶ主演の『書く女』を名鉄ホールで観る。寺島しのぶは樋口一葉の役。着物がとてもよく似合い、立居振舞がきれいなのは子供の頃からの生活によるものであろう。なんとも良い芝居であった。
- 10月21日(土)
郷土の調べものをしている方が電話で問い合わせののちご来館。他の館にもあちこち出かけておられるそうで、中に貴重資料を乱暴にコピー機にかけていたところがあり、愛書家ではないそうだが、あまりのひどさに怒鳴ってしまった、と言っておられた。その館の名を聞いて、ああなるほど、と思った。世の中には様々な図書館があるのであった。
- 10月20日(金)
松岡正剛の『千夜千冊』(求龍堂)などを中央公論新社のひとが見計らいで持ってきてくれた。『千夜千冊』はサイトで幾度か読んだが、編集されて本の形になるとまるで別のものになる。松岡正剛の編集者としての力を改めて感じた。取り上げている本の多くは、スタンダードなのだが、切り口が面白く、読んでいると、その本を読みたくなる。
『きっこの日記』に載ったイーホームズの藤田社長の文章には少なからず驚いた。これを読むと耐震偽装を知りながら、そのままの図面で建った建物を売っていることになる。書かれている時系列が正しいとなると、藤田社長の話は真実であろうな、と思われる。この問題について何か書くと、命の危険が危ないわけで、思いつきでテキトーなことを書いているようには読めない。マスコミはとりあげないのかな。裏付けが難しいのであろうか。昔、マスコミで働く人達を、命知らずだなあ、と眺めていたのだが、そういう人は絶滅しちゃったのであろうか。と、書く私は臆病なのであり、命をかけているひとを、誰か力のあるひと、組織が援助し、何が本当なのかを白日の下にさらしてくれると良いなと願っているだけなのであった。
- 10月19日(木)
夜、大学図書館のYさん、名古屋の図書館のTさんと論文の打ち合わせ。公共図書館の現状についてあれこれと話す。スリリングで刺激的なひとときであった。
- 10月16日(月)
ブライアン・デ・パルマの『ブラック・ダリア』を観る。映像の美しさといったらありませんな。特に鳥瞰。デ・パルマの映画は失敗作でも嬉しかったりする私だが、この映画は傑作だった。『マッチ・ポイント』にも出ていたスカーレット・ヨハンソンがとても良い。
- 10月11日(水)
『大山倍達正伝』を読了。第一部の塚本佳子氏の冷静で科学的な書き方に好感を持った。もう少し読みやすいともっと良かったのだが。第二部の小島一志氏の文章はスリリングで、するすると読めた。80年代半ばまで格闘技を熱心に見ていた私にとってとても興味深い内容の本であった。
パトリオットミサイルがやってきましたが、大きなメディアがとりあげないのは沖縄が日本であることを忘れているからなのでありましょうか。良い悪いは各紙で考え方が異なるのだろうけれども、大きな出来事を記事にしないのはジャーナリズムとしてどうなのでしょうな。あったことを書かずにれば、それはないことになる、というわけですかな。第二次世界大戦の時、ひとびとを煽って、戦後非難されたのを教訓として、ある事柄に対してまずいコメントをするではなく、はじめから知らぬ顔をする、という方法をマスコミは思いついたのであろうか。
- 10月7日(土)
久々に瑞穂陸上競技場で観戦。FC東京平山相太のJリーグ初得点を見ることができた(T_T)。
- 10月4日(水)
することの多い一日。新着図書の分類、視聴覚資料の入力、受付、レファレンスなどなど。延滞督促の当番もまた回ってきている。100件ほどかける。
山の上ホテルからメールが来ていた。筒井さんをはじめ、作家のひとがよく泊まるとのことでミーハーな私は幾度か泊まったのであった。最後に行ってから何年になるであろう。天麩羅屋さんがおいしそうだな、と思いつつ、まだ入ったことがないのであった。
- 10月3日(火)
久々に大学生の親が子の調べものに来た。大変漠然としたレポートのテーマ。本人が自分である程度考えなければなんともならないはずである点が面白い。それもお母さんが考えるのであろうか。しかしそんなふうにして大学を卒業した人間がそれから先どのようになってゆくのであろうなあ。
郷土人作家の生涯と作品についてのレポートを書くために大学生が来る。二度目である。随分と先行論文がある作家なので、新たな視点を見つけるのは大変。しかし、先行論文には目を通す予定であるとのこと。論文を書く際には当然の作業ではあるが、親に宿題を手伝わせるのとは大違いである。学生も様々だ。概説書を数冊提供。
なごやレファレンス探検隊のコメント作業が終わる。
- 10月2日(月)
次回のなごやレファレンス探検隊で発表者をすることになっているので、コメントをつける作業をする。講習の講師よりもこちらのほうが大変かもしれない。
読みたい本がまたしても出てこない。本棚にないということは、本の山にあるのかもしれない。ついでに廃棄する雑誌を選んだりすると良いかも、と本の山をあれこれしようとすると、ノラが山の真ん中で寝はじめる。ノラを起こさぬよう注意しながら、山を積みかえていると、先日探していた丸山健二の『赤い眼』が出てくる。200円とあり、前の所有者が読んだ日付が鉛筆で書いてもある。ああ、これをあのときに三松堂で買ったのだった。『三角の山』ではなかったな、と思い出す。『三角の山』はどこかの本の山の下に埋もれているのであろうか、まだ出てこない。山の整理をしていると腰痛がしてきたので挫折。目的の本は見つからずじまいである。文庫本を古本屋で買おうか、と考えはじめている私。なにかがどこかで基本的に間違っている気がしないでもない。私の部屋は現在、巨大なゴミ箱と化しているのである。ノラはかなり危険な地帯で寝ていたりする。
- 10月1日(日)
昨日以上に混む。
昨日、別の後輩が受けたレファレンスは短歌の作者調べ。旧仮名になおしてYahooで検索するとすぐに見つかる。その後、歌の載った資料を見つける。どうやらインターネットで調べるのは最後の手段であるかのように考えている節があったので、補助的なツールとしてのインターネットの有用性について説明する。明治以降の短歌だな、とすぐにわかったのだけれど、後輩は国歌大観をまず引いたとのこと。もうじきレファレンス講習をするわけだけれど、調べ方がわかるのは何故か、どうしたらわかるようになるか、といったあたりが実のところ私にはわからない。かなり以前、インターネットに今ほどの情報がない時代、国文出身の臨時職員が受けた短歌の作者調べのレファレンスにヤマカンで対応して、私が先に若山牧水であることをつきとめたことがあった。そのときは確か、なんとなく歌が酒飲みっぽいから、との理由で見つけたような記憶。そんなのを理論化できるはずはない。
そいえば、インターネットで探せないレファレンス問題を作ろうと、つい先日まで四苦八苦していた私。大抵は探せるのである。しかし、それをそのまま利用者に提示せず、図書資料で同一の記述を見つけたり、複数サイトで一致していることを示したのち、知らせるといったあたりが重要。
- 9月30日(土)
随分と混んだ。
後輩職員が受けたレファレンスに、他館のとある分類でその本を見た、というのがあった。インターネットで蔵書検索ができる館なので、その分類すべてを拾い、見当をつければ良い、と私はすぐに思ったのだが、そうした発想はないようであった。1000冊や2000冊の書誌データを眺めて目的の本を探すくらいはなんということもないのに、と私は感じたのだが、子供の頃から古書目録を眺め、最近でも個人的な調べもので雑誌記事索引からあれこれ追ったり、作家から古本を検索したりしているから思うだけで、そんな生活を真っ当なひとはしていないのだよな、と気づく。
- 9月26日(火)
ばたばたの一日であった。朝、ブックポストに返ってきていた本が1000冊ほど。利用者が多く、レファレンスも多く、あれこれしているうちに一日が過ぎていったのであった。歳のせいかあちこちが痛かったり、いろんな事を忘れていたりする。ふう。
最近、戦争をしても構わないかのような風潮がなんとなくできてきそうな気配があり、若者のなかにもお国のために、のようなことを言い出している人達が結構いたりするのだけれど、死んでしまえばまだ良いのだろうけれど、戦争に行って手や足が無くなっちゃったりしても良いのか、といったあたりを本気で考えているのかな、とふと思ったりする私。イメージとしての戦争がなんとなく美しいから危険ですな。我が国民はある方向に動き出すと、善悪正邪を気にせず見事に走り出す傾向にあるのだから。ただ、色々言っている偉い人は決して傷つかないし簡単に死んだりもせず、真に受けた若者だけが死んじゃったり身体の一部を無くしたりするってことを、知ってるひとは教えてあげたほうが良いのではないかと考える私。いよいよきな臭くなってきたのではあるまいか。
ところで、沖縄では文化財調査をするのに機動隊が出てきたり牧師さんが逮捕されちゃったり、となかなかすさまじいことになっていますな。報道の自由は確かまだあるはずなのだけれど、これってある程度大きな事件じゃないのだろうか。
- 9月21日(木)
昨日の虫食い事件により、ほかに和紙でできた本はないかをチェック。
CDの入力。
インターネットの何かにより、不要となった、と多くのひとが思い込んでいる仕事はいくつかある。本当にそうなのであろうか、と疑うことは必要なのではなかろうか、と感じる事柄があった。
- 9月20日(水)
休み明けなので混む。エッセイはどこにありますか、との質問。職員にとって当たり前の事柄と思っていても利用者にはまるでわかってもらえていないことがある。著者の名前の五十音順で並んでいること、複数著者の著作は書名の五十音順で記号をとっていることからゆっくり説明するが、しばらく時間がかかった。こうした説明を億劫がるべきではなく、地道にしてゆかねば、やがて利用者が減ってゆくのだと思う。
利用者に提供した資料の一部分がひどい虫食いで開かなくなっていた。業者に出さないと到底剥がせない状態であったため、しばらく待っていただくことにする。
- 9月19日(火)
休み。『グエムル』を観る。韓国の怪獣映画。コミカルで少し悲しい。アメリカ人を茶化しているのが楽しい。前頭葉のあたりにウイルスがある、と言う目がヘンなアメリカ人の役者がとても面白かった。我が国ではアメリカ人をバカにした作品がこの頃あまりない気がする。春風亭昇太の『ジョージ・ワシントン伝』というのを十数年前に聴いた記憶があるくらい。
- 9月18日(月)
祝日の月曜日は比較的空いている。督促の電話をかけたり。
- 9月17日(日)
午前に平穏だったのだが、午後随分混む。登録者も多い。私は段々と何をしているのかわからなくなってくる。歳を感じる。
- 9月16日(土)
利用者多し。レファレンスも多い。夏休みよりもひとが沢山いた気がする。
- 9月15日(金)
休み。『スーパーマン・リターンズ』を観る。それほど期待せずに観たのだが、なかなか良かった。え、そんなことになっていたの、といったことがあったり。レックス・ルーサー役のケヴィン・スペイシーが最高。
夜、立川談春を聴きにゆく。生の落語は志ん朝さんが亡くなってから行っていなかったのだが、なんとなく談春には期待ができるかな、と思ったのであった。『桑名舟』のまくらに落合監督、常滑競艇、といったご当地関連の話題をちりばめ、なかなかうまい運びであったが、噺の途中で解説めいたものがはいり、なんだかなあ、と感じたのでした。『粗忽の使者』は勢いがあって面白かったのだけれど、いささか乱暴な箇所があった。そして『芝浜』。談春の『芝浜』の評判が前々から高かったので聴きたいとは思っていたのだが、暮れの噺なのでかけないだろうと考えていた私。先代三木助の『芝浜』を幾度レコードで聴いたことか。この噺は大好きだ。談春のは談志のともまた違い、一種独特の、怖ささえある『芝浜』。女を演じるとこのひとはとても良い。競艇の予想を新聞でしているくらいだから先代三木助ほどではないにしても博打打ち。そういうひとでないとこの噺を演じるのは難しいのかもしれない。しかし、師匠の談志の悪いところを継いでる箇所が気になった。聞き手が噺にのめりこんでいるのに、「ここまでならば美談ですよね」と解説を途中で入れるところ。聴いてる側はそれで現実世界に一辺に戻される。批評家の目は必要だが、噺の途中で自分の噺の解説をされたくない。良い方向にずっと進んでゆけば将来が楽しみな噺家だなと幸せな気分で帰宅したのであった。
- 9月12日(火)
黒木和雄の遺作『紙屋悦子の青春』を観る。静かな良い映画であった。永瀬正敏はもう少し髪の毛を短くすれば良いのに。あんな軍人さんはいないだろ。じじばばメイクはもう少しなんとかならなかったのであろうか、と、多少の不満が残った。九州の言葉は大変であろうな、と想像する。原田知世の抑制の利いた芝居が良い。そういえば彼女は長崎の出身であったな、と思い出す。小林薫の妻の役が本上まなみでは荷が重いのではなかろうか、と思って少しはらはらしていたが、なかなか良かった。しかし、戦争はしみじみ厭だな。もうじき首相になりそうなひとは、戦争に関わりたくてしかたがないみたいだが、自分で航空母艦に体当たりをする立場には決してならないわけで、若者達の死んでゆくさまを、暑苦しい顔で涼しいところで眺めたりするのであろうな。
- 9月10日(日)
やたらと混む。何をしているのかだんだんとわからなくなってくる。コピー機の文字が薄いな、とトナーのボトルを振ってやろう、と考え取り出して腕にこぼす。手とシャツが真っ黒になる。お客さんはさぞかしびっくりしたことであろう。今時振ってどうにかなるトナーはあまりないだろうに、私は何を思ったのか。
利用者が多いので、レファレンスも多かったのであった。難しいものもなかなかあった。面白い小説を書くひとを教えてほしい、などというのもあった。今までにどなたのを読んだのですか、と問うと、おびただしい人名があがる。幾人か別のひとの名を言ってみると、「それは読んだ」「読んだけれど、好みではなかった」と言われる。全集に案内し、選んで読んでいただいて、好きな作品があったひとの別の作品を読んではどうでしょうか、と言ってお茶を濁した私であった。
- 9月9日(土)
夏休みに借りた本を返す日であるためか、そこそこ混む。
おできはなかなか治らない。
- 9月8日(金)
CDの発注のため、CDカタログを見るのだが、曲目は天眼鏡がないと見えない。そろそろ遠近両用を買わねばならぬ年頃であろうか。
『群像』は60周年記念号。短篇や随筆が沢山入っていてうれしい。瀬戸内寂聴の『燐寸抄』は久世光彦についての随筆。懐かしくて怖くて暖かい文章。
- 9月7日(木)
レファレンス講習会の講師をすることとなった。4年前、この講習会でF本さんらと知り合ったのであったな、と思い出したりする。時の流れは早いものである。ともあれ問題を考えねばならないのであった。インターネットでは簡単に探せなくて、どの図書館にもありそうな資料で見つかるのだけれど、少し悩まなくてはならない、という問題が作れればベストなのだが、それはとても難しそうである。
- 9月6日(水)
頭にできたおできと耳のリンパ腺の腫れが気になりつつも出勤。受付でしゃべるたび、耳から頭にかけて痛みが走る。頭の中に鍛冶屋がいるような感じとなったため、早退。頭と目の奥がとても痛いのであった。皮膚科にゆくと、リンパ腺の腫れはおたふく風邪ではなく、おできのせいであるとのこと。化膿止め、痛み止めをもらう。
- 9月5日(火)
利用者の少ない火曜日であった。
- 9月4日(月)
休み。ウディ・アレンの『マッチポイント』を観る。とても力の入った作品。観ていて息苦しくなるほど。パトリシア・ハイスミスの小説みたい。しかし、男にしかわからない感覚を見事に描いている。映像が美しい。ベルイマン、トリュフォー、ヒッチコックなどの作品を思い出させるような箇所がところどころ。そしていかにもウディ・アレンだったのであった。傑作である。
- 9月3日(日)
貸出は4800冊ほど。なかなかばたばたの一日であった。いよいよ夏休が終わる感じである。
- 9月2日(土)
夏休みは終わったというのに子ども達はすぐに連休である。学校週休二日制は間違っているのではなかろうか、と混んだ図書館で働く司書は思ったりもする。中学生が宿題の調べもの。「もう夏休みは終わったのではないかな。七月のうちにその関係の本はみんな借りられてしまったよ。というのは嘘だが」と少しいじめたりしながら辞典の使い方を説明。
勘違いをなさっているひとが多いのだが中小公共図書館は急ぎの用事にはあまり役立たないのであった。郷土資料、参考資料などを除いてほとんどの資料を貸し出しているため、目的の図書が貸出中である確率がかなりあるのである。「いつ返ってきますか」と問われると図書館員は困る。返却期限はかなり先だけれど、もしかすると今日返してくれるかもしれないし、延滞するひともいるのである。延滞すれば督促するけれど、督促したからってすぐに返してくれるひとばかりでもない。返却後すぐに借りられてしまう場合もあるので、ともあれ予約をしていただくこととなる。「一週間後に必要なので今日借りに来たのだ」などとおっしゃる方もあるわけだけれど、貸し出されている可能性が常にあるので、そういう使われ方には向いていないのであった。
- 9月1日(金)
休み。終日読書。
- 8月31日(木)
昨日の朝日新聞夕刊、『東海の文芸』に清水良典さんが興味深いことを書いていた。「『中部ペン』13号で中村文則の講演会録と並んで、「日本の戦後文学再検討」と題した大がかりな座談会が、三島由紀夫の「金閣寺」と遠藤周作の「沈黙」をめぐって繰り広げられている。参加者が互いの読みを競っている熱心さは素晴らしいが、同じだけの情熱で彼らが中村文則を論じることはできるだろうか」。ここ何年かの小説について熱心に語ったことはないよなあ、と思う夏休みの終わりであった。
- 8月30日(水)
新聞の縮刷版を探しにきたお客さんがいた。うちには所蔵がないので、持っている館を探しはじめると、利用者が調べる内容を告げたのであった。それであればほかの参考資料で間に合いますよ。と、資料を提供。時折、膨大な量の新聞の提供を求める方がいるのだが、よくよく尋ねると、ある事柄の日付を調べたいだけであるケースがしばしば。そのあたりのやりとりができるかできないか、また、調べられるかどうか判断できるかどうかが司書の値打ちである。
- 8月29日(火)
中学生が宿題を調べにくる。「もう手遅れだよ。本はみんな貸し出されちゃってるよ」と意地悪を言ってやるのが楽しい。辞典類での調べ方を説明する。夏休みもいよいよおしまいが近づいている。
- 8月28日(月)
休み。午後、安城の古本屋を回る。ヒラ書店が閉めてしまったようだ。淋しいことである。月曜休みを失念していた店が開けてくれた。昔、ここで野呂邦暢の本を沢山買ったことがあった。名古屋周辺の店ではなぜか『草のつるぎ』以外見つからなくて探していた頃のこと。同時期に野呂の本を探していた友達がそれを知ったときの悔しそうな笑顔が頭のなかにふっと浮かんだ。本は不思議である。相変わらず良い本の多い店であった。最近はあまり力を入れていないかのようなことを店主が言っていたが、値づけもしっかりしていた。こういう古本屋に来るとうれしくなる。インターネット古書店では、知らない本を探すことはできないのである。文庫本を数冊買う。
- 8月27日(日)
休み。朝、『太陽』を観にゆく。開演30分前に着いたのだが、大行列。シネマスコーレはできた頃から行っているが、こんな行列は初めてではないだろうか。『ゆきゆきて神軍』のときもこんなではなかったし、『赤目四十八瀧心中未遂』でもこれほどではなかったが。イッセー尾形演じる昭和天皇は見事であった。皇居のなかで、天皇は「お上」と呼ばれているのだっけ。天皇が文字を書くシーンで新字新仮名なのはおかしい。ロシア人監督なのにロシア参戦について触れないのはなんとなく不満。そして大きなミスキャストがある気がする。話題作ではあるが、お金を出して観るほどのことはなかった、と思った私。晩にサッカーを観るので、ずっと名古屋をうろうろしよう、と考えていたのだが、映画をもう一本観るのも疲れそうだし、名古屋駅周辺の新刊書店をうろうろしたあと久々に上前津から鶴舞まで歩く。残念ながら三松堂は休み。古本屋まわりはとても楽しい時間であったのだが古本屋さんがかわったのか、私がかわったのか、なんとなく楽しくなかった。あまりみない本が100円であったので買う。宮原昭夫の『駆け落ち』。多分インターネット古書店で探せばなんということもなく見つかるのだろうが、目にしたから買うというのが良いのだろうな、などと思う。この作家の本を最後に古本屋で見たのは数年前、岡崎の、床が三和土であった店であった気がする。多分そんなことはなく、ほかでも見ているのであろうが、本にまつわる記憶は変梃なものなのである。鶴舞から千種へゆき、ちくさ正文館にも寄ってしまう。本は恐ろしいものである。
瑞穂はすさまじいひと。客の入れ方がおかしいのか指定席のチケットを持っているのに簡単にメインスタンドから入ることができない。スタッフの数も少なかったようである。グランパス、前半3対1であったのに、後半同点にされてしまう。主審も線審も怪しげであった。本田の入れた3点目は見事。
- 8月26日(土)
中学生の勤労体験は終わり、高校生は明日まで。本の修理をしてもらっていたところ、職員の説明が足らなくて失敗していたところがあった。折角なのでそれを直してもらったのであった。少し嫌な作業となったかもしれない。しかしこういうのは仕事につきものであるわけで、就業体験としては良かった気がする。謝らせてしまって申し訳なかったが。
夏休み最後の土曜日だけあってやたらと混んだ。
- 8月25日(金)
中学生の宿題がなかなか難しかったりする。提供した参考資料の中に俗字が使ってあり、どっちが正しいの、と問われ、自分で辞書を引け、と言えばよかったな、とあとで気づくのだが、辞書を引くのが好きなので、ついつい私が引いて教えてしまったり。
中学生と高校生は今日もまじめに勤労体験をしていた。
- 8月24日(木)
中学生と高校生が今日も勤労体験にきた。どちらの子たちもまじめで仕事が早い。書架のどこかにもぐり込んでいた本も彼らのおかげで発見できた。こういう生徒ばかりであれば毎日でも来てもらいたいものである。
- 8月23日(水)
中学生が勤労体験にくる。彼らもまた図書館を好きな子たちであった。書架をきれいにしてもらう。
つくつくぼうしが鳴いていた。夏休みのおしまいが近づいている。昔つくった法師蝉の句を思い出す。おしまいがくると厭だな、と思ってつくった句であった。油蝉の鳴きはじめは遅かったが、つくつくぼうしは例年通りである。
Tさんにお願いした調査結果を受けて現地を確認した利用者の方のさらなる調査結果を頂いたのでTさんの勤務する館にお知らせした。帰宅後Tさんよりメールが来ていた。やぶ蚊だらけの現地にゆかれたとのこと。と、何の話だかさっぱりわからなくなるので少し補足をすると、とある石碑の銘文がかすれて読みづらくなっているのの中身を知りたい、とのレファレンスだったのであるが、文献によって少しずつ異なっており、また後半部分が省略されているのかいないのかが判然とせず、直接現地にゆくほかないな、ということになったりした訳であった。
グランパス、負けたとのこと。
- 8月22日(火)
高校生が二人就業体験に来る。書架整理と、毀れた本に貼るラベルを切る作業をしてもらう。郷土資料を細かな分類順に並べるように頼むと予想していらよりもかなり早くにできたと言うので、あとから確かめにゆくと、綺麗に並んでいた。帰りに、「仕事はきつくなかったかな」と尋ねると、「楽しかったです」との返事。図書館の仕事に向いているひとたちである。ある仕事について楽しい、と思うひとと、苦しいと思うひとが世の中にはいるわけで、前者の数が増えれば良い世になってゆくであろう、と私は単純に考えるのだが、いかにすればそういう状況になるのかがよくわからない。
- 8月21日(月)
近所の古本屋にゆき、丸山健二の本の話をする。『赤い眼』がある、と言うので見せてもらい、買おうかな、と考えるが、ぱらぱらと読むと確かに読んだ記憶があり、これも二冊持っている気がしてきてやめる。本棚を真剣になんとかすべき時が来ている気がする。
太田幸司以来の決勝戦の延長翌日再試合をテレビで観る。久々の野球観戦。斎藤投手はすごい制球力である。連投につぐ連投。プロ野球のスカウトは選手がつぶれてしまわぬかと頭を抱えたことであろう。この日程をなんとかするか、中一日あけないと投げてはいけない、とのルールを作るべきだと思うが、もう30年くらい言われていることではある。アイシングやマッサージの進歩でなんとかなっているのであろうか。それにしても板東英二の6試合(延長戦あり)83奪三振がいかにすさまじい記録であるかを改めて思った。斉藤投手は7試合(含む延長)でもぬけなかったのである。
- 8月20日(日)
今朝もまた悪夢。どうしたことであろう。
混む。夏休みである。閉架の図書の利用多し。
閲覧席のすぐ前で話をしている中学生の男の子三人。おじさんに注意されても話をやめないので、「ロビーでゆっくり話をすれば良いよね」と言いにゆくと、「迷惑になるほど大きな声で話をしていない」と反論される。「小さな声でも話がずっと続くと、本を読むのに気になさる方もあるのだよ。場所を変えようね」と説明。「僕たちだけが話をしているわけではない。話をした全部のひとに注意すべきだ」と言い出す。「どこにそうしたひとがいるかな。そうしたひとがいれば良くないし注意すべきだが、君たちも話を止して欲しい」と言い、そこを去ったあと気になって「しかし、そうした考え方は良くないと思うよ。ほかのひとがいけないことをしているから自分もしても良いと考えるのは間違いだよ」と言いにゆく。子ども達は注意を受けたことがつまらなくて色々言い訳をしただけだとあとから思ったのだが、この考え方、なんとなく我が国に最近蔓延しているように感じる。お上や政治家が悪いことしてるんだから何をしたってかまやしない、とか、大人が悪いことしてるんだから、子供がしてもいいではないか、とか。そんなふうにどんどんと進んでゆくとどうなるのであろうな。
- 8月19日(土)
悪夢で目覚めたが、グランパスは4連勝。しかし、仕事のため観にゆけず。
さすがに夏休みの土曜日。ばたばたであった。何をしていたのかよくわからぬうちに一日が過ぎる。
丸山健二の『赤い眼』と『三角の山』の旧版を部屋で一昨日から探しているのだが、まだ発見できずにいる。空間が歪んでいるのかもしれない。って、ただ汚いだけなのであるが。『三角の山』は確か数年前、持っているにも関わらず「うちのには帯がないけれど、これには帯があるから」との理由で三松堂で安く買って、ひとに笑われたような記憶があるので2冊あるように思うのだが、出てこない。そういうことをしているから家が狭くなるのであるが、読みたいときにはどこにあるのやらである。ほかの丸山健二の本はあれこれ出てくる。新刊本屋で買った直後に古本屋で200円で売っていて悔しい思いをした『白と黒の十三話』とか、本一冊ずつについて変なことを覚えているのが不思議である。
- 8月18日(金)
図書館のヘビーユーザーで、働きながら通信課程で司書資格を取り、現在は関東の図書館で非常勤をしているひとが来館。しばらく話をしたのであった。延滞の扱いや、閉架の図書のことについて館によってかなり異なるのであるな、と改めて感じた私。公共図書館、という枠で、だいたい似たようなところである、と思っているひとが世の中のほとんどなのだけれども、実はまったくそうではないのが面白い。
中学生のボランティアがくる。返却図書が多く、児童書コーナーがすさまじいことになっているので助かる。
- 8月17日(木)
夏は涼むためだけに来たとしか思えないお客様たちがいらっしゃる。絵本のコーナーを幾組か一緒にいらした家族が占拠状態。書架のすぐ前に坐ってお話をなさっている。沢山注意をしたかったけれども、「本棚を見づらくなりますので、もう少し真ん中に寄っていただけますか」とお願いをする。しばらく後、レファレンスの案内をしたあと、絵本コーナーを見ると、小学生中学年の男の子達が書架の真ん前でうつぶせに寝そべって絵本を読んでいる。注意に行こうと、靴を脱ぐと、頁を破るような勢いでめくりはじめるので、「おいおい、本は大事にしないとだめだよ。それから、真ん中あたりで坐って読んでね。ほかの人が来られなくなるから」と、怒りをこらえて無理に笑顔をつくって言ったところ、その前にお願いをしたご一行様のご子息であったらしく、「さあ、もう帰ろうか」と十数名が一斉に立ち上がりお帰りになった。絵本は残されたままであった。
図書館はどうあるべきなのであろうな、とこのところしばしば考える。20年ほど前、図書館は無料貸本屋ではないのか、との論議があった。貸出を重視し、多くの人がやってくる図書館にすべきだ、との論で40年近く進んできたわけだが、私は間違っていたような気がしてならない。国民の民度の問題、経済状況の変化、出版業界の変質、といったことをまるで考えにいれず、利用者の要望に沿った本を購入する、という姿勢を続けてきたのは誤りであったとしか思えないのである。日本の公共図書館の方向性を示した前川恒雄氏は、読書水準の向上を図るべきではないかとの疑問に対し、「山手樹一郎の本ばかりを借り、一通り借り終えると、すでに読んだ山手樹一郎の本をまた借りるお爺さんがいる」といった例を示し、読書の幅はひとによって異なる、と書いていた。15年ほどまえのことである。私は、ほとんどの利用者がこのお爺さんみたいになっちゃったら図書館はどうなるのかな、とこの時感じたのだが、今まさにそんな状況である。図書館は「知」を扱う場所であるが、知的好奇心を持ち、読書水準を上げようと考えている利用者は一割もいるだろうか。レシピや旅行ガイド、猥本まがいの小説をリクエストする利用者が将来存在するであろうことまでを前川氏が予想していたとは思われないが、現状はそうなのである。それでもまだリクエスト重視、利用者に沿った図書館を目指してゆくのであれば、司書はレシピや旅行ガイドや猥本のスペシャリストとなってゆかねばならなくなるのであるが。
- 8月16日(水)
休み。暑い。
出たらすぐに切れる謎の電話がある。「もしもし」くらいは言ってくれても良い気がするが。まともな電話が最後にかかってきたのはいつのことであろうか。訃報と間違い電話と無言電話くらいしかかかってこない我が家である。
- 8月15日(火)
古くからの利用者がとあるところで無礼な出来事があったと怒っていらした。一度目で用事が片付かず、言われたようにして二度目に出かけたところ、それでも片付かなかったとのこと。一度目の際の担当のひとが、言い落としていた事柄があったとか。それはいけませんでしたね。しかし、言い落とすことは時折あるのですよ。あってはならないことですが、などといったやりとりをし、にこやかに去ってゆかれたあと、私はそのひとに話しておく用件があったのを思い出したのであった。慌てて電話で連絡。老眼ははじまったし、ぼけてきてもいるのであろうか。
利用者多し。延滞督促の電話を100件ほどかける。「ごめんなさい」を言うひとは三割くらい。謝るほどのひとであれば、遅れはしないか。
- 8月14日(月)
寝ていた時間に電話があったようである。夕べWOWOWで放送していた『着信アリ2』を少し観たので怖くて寝ていたのであった。
パトリス・ル・コント監督の『親密すぎるうちあけ話』を観る。冒頭、女の足が歩いてゆくシーンが良かった。パンフレットにロマンティック・コメディ、とあったのだが、割と重たい話であった。ところどころ笑える箇所もあったけれども。
日に100件ほどはスパムメールがある。スパムブロックで自動的に切っているものだけで80くらい。今朝は寝ぼけまなこでメールチェックしたところ来ていた20通すべてがスパムであった。こんなとき友達がいないな、と感じる。
- 8月13日(日)
お盆なのでそれほど利用者は多くなかったが、レファレンスはかなりあった。とある統計がないか、と問われ、しばらく探してから、はた、と気づいた。その統計は取れていないはずであるし、あったとしても信憑性に欠けるであろうと思われるのであった。それを説明。統計は正確な調査が行われぬとできないのであるが、案外そのことを忘れがちである。
督促電話を100件ほどかける。
- 8月12日(土)
休み。名古屋市美術館にニキ・ド・サンファル展を観にゆく。ナナがかわいい。蛇もかわいい。
名古屋対甲府戦。5対1。5点もとったのはいつ以来であろうか。直志が別人のようであった。代表に選ばれるとこんなに変わるのだな、と驚いた。
- 8月11日(金)
中村直志のJリーグ戦初ゴールを生で見ているはずだが、あれは暑い日。いつであったろう、と調べると2001年8月11日。実に見事なミドルシュートだった記憶。試合の後、瑞穂運動場近くの焼鳥屋さんでかなり飲んだのであった。ピクシーがいなくなったあとの司令塔としての期待に胸を躍らせたのであったなあ。遠い昔。
Tさんから資料が届いた。なるほど記述が異なっている。利用者によく説明せねばならない。
中学生たちに和本を見せると感心していた。
- 8月10日(木)
中学生の勤労体験。良い子たちである。きれいに書架整理をしてくれる。
昨日の貸出冊数を見ると5008冊。疲れるはずである。今日もなかなかの人出。早く夏休みが終わらないかな、と思えてくる。
昼休みに本屋へゆく。BGMが流れているのが厭であまり長居をせぬようにしている。先日中華料理屋でもかかっていたのだが、太田裕美の『九月の雨』のカヴァー。尾関美穂というひとが歌っているらしい。70年代の曲をややダンサブルにカヴァーする昨今の風潮を快く思っていない私であるが、そんなことよりも、この曲を大阪の友達が10年ほど前、えげつない大阪弁の替え歌にしたのが私の記憶に残っているのである。ことにサビのフレーズ「セプテンバー、レイン、レイン」を替えた箇所がケッ作であり、どうしてもその詞にしか聴こえてなくなってしまい、店を出ても頭のなかで渦を巻いてしまい、口に出してしまわぬか、と心配になってきたりして大変であった。歌謡曲をひところしばしば聴いていた時期があったな、と思い出したり。
Tさんから電話を頂戴する。調査をしてくださったのである。とても早い対応に感謝。三つ資料があったのだが、記述がどれも異なるとのこと。ううむ。
- 8月9日(水)
朝、ブックポストに1885冊の返却図書。処理に2時間ほどかかる。レファレンス多し。ここ1年ほど活動を休止しているフォークデュオ「あたたた」の相方Tさんの図書館に訊くとわかるかな、と思われるものについてTさんに調査依頼。かなりへろへろになった一日であった。
オシムジャパン初試合。実に面白いサッカー。アレックスが別人みたいだった。後半になってもしっかり守備をしていてびっくり。中村直志が出て来たときには、かなりはらはらどきどきしてしまったが、20分ほどの間にシュートを二本放った。偉かった。Jリーグデビュー戦から、何試合も生で彼を見てるので、良いところ、悪いところを知っているわけで、いろいろ怖いことを想像したのであった。
何年も前の一瞬がフラッシュバックのように頭のなかに幾度も現れた変梃な日であった。
- 8月8日(火)
『恋は足手まとい』を観る。エマニュエル・ベアールが目的である。コメディというよりもコントであった。今ひとつ物足りなさが残る映画。名演小劇場では今月末、黒木和雄の特集をするとのこと。楽しみ。
明日はいよいよオシムジャパンの初試合。
今日は立秋。早いものである。
- 8月7日(月)
粗大ごみを捨てる。
伊井直行の『青猫家族輾転録』を読む。おじさんという人がなんだかよかった。
- 8月6日(日)
さすがに日曜日である。何をしていたのかわからぬうちに一日が終わる。
- 8月5日(土)
さすがに土曜日である。ばたばた。20分ほどの間に登録者が5人。このままだと2時間で30人か、と思われたが12人で済んだ。課題図書や、夏休みに必要な本の予約が多い。予約をした本が夏休みに返ってくるかの問い合わせは今日もある。利用者がすべて延滞をしなければ、話はわかりやすいのだが、そんなはずはないわけで、遅れたら督促をするけれど、それで返ってくるとも限らないのでなんともいえません、と丁寧に説明をするうち、この問い合わせをしているひとはしばしば延滞をするひとではなかっただろうか、との妄想が起きてきたり。禁帯出の資料以外はすべて緊急性を要する場合に向いていないのである。すべて禁帯出、閲覧は館内のみ、閲覧室が沢山、館内閲覧以外の机使用厳禁という図書館が日本中、徒歩10分圏内くらいにあったら面白いだろうなあ、などと想像してみたり。
グランパスの中村直志が日本代表に追加招集されたとのこと。ファンとしてはうれしいのだが、なんとなく不安なのはなぜであろう。
- 8月4日(金)
中学生の勤労体験、今週の子たちは今日までであった。特別資料室の和本を見せると喜んでいた。延滞督促の話をした。「遅れていますよ」との電話を受けた方は、「ああ電話がかかってきちゃった」と思うだけだろうけれども、かける側は、日に数十件、その度に同じことを言うのだよ、と話すと、びっくりしていた。案外そうした当たり前のことにひとは気づいていないものである。
延滞督促の電話をする。視聴覚資料の延滞利用者リストを出すととんでもない人数。遅れるのであれば借りなければ良いだけなのに。夏休みの宿題で必要な図書を予約した子供の親からまだ本が返ってきませんか、との問い合わせも多い。貸出期間以上の日数が経っても返ってこないなんて想像したこともいないひとも中にはいる。何十年もの間、延滞を一度もしたことのないひとから見れば遅れていて督促を受けても返さない人間の存在を理解できないのは当然。同じ人間なのに、一人ずつ見事に違うのだなあ、と改めて思ったりしたのは暑かったからかもしれない。
『出版業界最底辺日記−エロ漫画編集者「嫌われ者の記」−』(塩山芳明著、ちくま文庫)を読了。乱暴な文体で装っているが、著者はとても細やかで優しいひとであるな、と感じる。すごい読書家。名著である。
サッカー日本代表発表。13人とはびっくり。9日の試合はもしかして13人でのぞむのであろうか。オシムは面白い。私の好きな我那覇、小林大悟、今野、田中隼磨が入っていてうれしいが、一人、あまり走らない選手がいるような気がするが、オシムのもとで練習するうち、変化してゆくのであろうか。
- 8月3日(木)
一月ほど前、ラジオから「君にも猫貸さない」という不思議な歌詞が流れてきた。鼠に悩まされているのでもなければ猫を借りる必要はあるまい、はて、としばらく考え込んだ私。去年、なごやレファレンス探検隊のキャンプで演奏を考えて挫折したBONNIE PINKの声であるな、と思ったのだが、この曲『A PERFECT SKY』は随分流行っているようである。さきに書いた歌詞、正しくは「君に胸焦がさない」らしいが、日本語がおかしい。「胸焦がす」はあっても「胸焦がさない」はない。頭の中で正しそうな言葉にかえるメカニズムが働くらしい。
今週の貸出返却は3500冊前後。仕事が終わるとよれよれになる。
中学生の勤労体験。書架がきれいになってありがたい。資料の収集方法の説明をするとき、たまたま尾崎豊の話をしたところ、彼らは5人とも尾崎豊を知らなかった。冷静になって考えると92年と93年生まれ。尾崎が死んだのは92年。そうか彼らは私と30歳違うのか、となんとなく驚いた。本についての話をしていると、ついつい中学生には難しいかもしれない内容になってゆく。でも、どこか意識に残る話であれば、5年、10年経ってから、あああれはこういうことだったのか、と思い出すだろうし、理解できても残らない話であれば、そこでおしまいになるのだから、多少わからないことを言っておくのも良い気がする。
- 8月2日(水)
勤労体験の中学2年生が2校5人来館。書架整理を一時間してもらったあとで感想を尋ねると、つらかった子と楽しかった子とがいる。特別整理期間に行う仕事の例を話すと、「絶対厭だ」と言う子と、うれしそうに聞いている子とがいる。本を触ったり並べたりという仕事を好きかどうかはすでにこれくらいの年齢で決まっているのかも知れないな、と感じる。私は図書館の基本的な仕事を厭だ、と感じたことがない。苦手なこともほとんどない。あまりしたくない、と思うこともない。最近は水準が低い出版物が多く、利用者からのリクエストの多くがレシピ、ガイドブック、オカルト関連、ハウ・トゥもの、軽い読み物であったりするので、そういう事実を厭だなと思ったりはするが。話が逸れた。本を好きなひとだけが本に関係する仕事に就いているのであれば、国の様々なあれこれは違ったことになるだろうな、と想像した。ただその本がレシピや旅行ガイドだとしたらそれはまた別の話となるわけであるが。書架整理をするのがうれしいひとと、つらいけれど仕事だからしなければならない、と考えるひととの隔たりの大きさを思うのであった。司書資格を取って図書館で働いているけれど、本に興味がない、というひとも世の中にはなぜか沢山いる。図書館でなんて働きたくないのだけれど、異動をしたため書架整理をしているというひとはもっと沢山いることであろう。多分そうしたひとたちよりも書架整理が楽しいと考える中学生が働いているほうが図書館にとって幸せであるように思う私。どんな仕事もそんな風なのだろうな。
7月19日のカレント・アウェアネスNo.87の記事に興味深いものがあったのを思い出した。2000年にライブラリー・オブ・ザ・イヤーを受賞したジョージア州のグイネット郡公共図書館で1991年から館長をつとめたピンダー氏が2006年6月12日に図書館委員会の議決により解雇されたというもの。少し引用する。「『ピンダー館長の方針はグィネット郡の家庭の伝統的な価値観とそぐわない』として,館長を解雇せよというキャンペーンを行ってきた。1回に貸し出す冊数が多く盗難を助長した,ベストセラーの複本を大量に購入してはすぐに除架して安値で売っている,管理職者の人数が多い,ALAの大会への参加費用が高額である,といった財務面からの批判や,館長個人の資質への批判もなされた」
ここに関連記事があります。ピンダー館長は2002年度の米国公共図書館協会(PLA)会長を勤めていたそうで、アメリカの公共図書館でよく知られていたひと。市民の意識と異なる図書館運営をすると解雇されるのか、と少しびっくり。また、我が国の公共図書館とは違う方向で運営されている館がいくつもあるらしいことにも驚いたのでした。民度とシステムの問題なのかな。日本に明治時代からこんな図書館があったとしたら歴史はどうなっていただろうか、などと想像すると面白かったりする。
- 8月1日(火)
朝、トイレで小用を足したくても足せない状況でいる夢で目覚める。久しぶりのこと。子供の頃はそのまま足してしまったりしたものである。夢の中ですっきりした頃には現実の世界では大変なことになっていた。
なんでこんなに大勢のひとが世の中にいるのであろうか、と思われるほどの利用者の波。登録者も多し。
私のファンとおっしゃるご老人が和歌を書いた紙をくださった。若い娘さんだともっとうれしかったであろうが、ありがたいことである。
- 7月31日(月)
朝、BS2で放送していた萩尾望都原作の『11人いる!』を観る。原作が良すぎると映画化はむずかしいものだとかんじる。
昼寝をしたり本を読んだりするうち一日が過ぎる。
- 7月30日(日)
休み。川を眺めた。
グランパス、今日も勝つ。一年ぶりくらいの連勝。めでたいめでたい。
- 7月29日(土)
休み。現代美術のアーティスト束芋の『ヨロヨロン』を観る。不気味なような懐かしいような。随分沢山お客さんがいた。古本屋と新刊本屋を回る。大荷物になる。
- 7月28日(金)
休みの職員が少し多かったり、健康診断があったりしてばたばた。朝、中学生のボランティア。夏休みはあっという間に書架が乱れるので、助かる。
- 7月27日(木)
今日も朝と昼に中学生のボランティア。昨日綺麗に揃っていた絵本コーナーが今日の午後にはすさまじいことになっていたので直してもらう。
- 7月26日(水)
朝と昼に中学生のボランティアがくる。書架整理をしてもらう。この作業、かなり個人差があって面白い。きれいに揃ってもじきにひどいことになる絵本の書架のはかなさ。
晩にサッカーを観にゆく。名古屋対大宮戦。名古屋が2対0で勝つ。うれしくて麦酒を二杯飲む。
- 7月25日(火)
朝、ブックポストに350冊。私が受付に入っていた2時間半の間に12人の新規登録者があった。
- 7月24日(月)
朝三時に起き、思い立って成瀬巳喜男監督の『流れる』を録画しておいたのを観る。山田五十鈴、田中絹枝、高峰秀子、岡田茉莉子、栗島すみ子と豪華絢爛なオールスターキャスト。昭和三十年代の柳橋の様子が見事に描き出されている。『浮雲』ではインチキ教団の教祖を山形勲が演じていて可笑しかったが、『流れる』にもちらと宗教団体の看板が映っていた。
『ゆれる』を観にゆく。オダギリジョーはなんとも良い。香川照之は怖いくらいうまい。真木よう子は好き。しかし、映画としてはどうなのだろうか。とてもきれいな映像だったが。『蛇イチゴ』のほうが私は好きである。
- 7月23日(日)
混む。私が受付にいた2時間で10人の新規登録者。
- 7月22日(土)
夏休二日目。朝、比較的空いていたので、天気も良いし、みんな遊びに行っちゃって図書館にはこないのかな、と思っていたら、午後から混む。難しいレファレンスがあったりもする。
グランパスは1対5で負けた。このままでは降格するなあ。
丸山健二が旧作三冊に手を入れて出版。読み比べるひとはいるのであろうか。ここ十年くらいの彼を私はあまり好きではないので買う予定はないのだが、旧作を持っているひとは捨ててほしいとまで言っているとのこと。三十年以上前の作品の改稿。作家として誠実な態度なのであろうなあ。大きな図書館はどちらも買うのかな。
- 7月21日(金)
ひさしぶりに来館された方と話をしていたら、脳梗塞で入院をしていたとのこと。我が国の様々なことが腹立たしくて脳梗塞になっちゃったよ、と笑っていらした。知的好奇心を持った人。
いよいよ夏休がはじまった。慌ただしく一日が過ぎる。
オシムが代表監督に正式に就任。喜ばしいことである。
- 7月20日(木)
混んだのであった。明日から小中校生は夏休。図書館にとってばたばたな季節となる。本は大切なものではなくなったな、としみじみ感じる。空中で絵本を広げ、真ん中から逆方向に向けて折ってしまおうとしている三歳くらいの子に注意しない親に、「本が痛みますので、置いて読んでもらうようにしてくださいね」と言うと、「あらそう」と淡々として、「いけないんだって」と子供から本を取り上げる。本を跨ぐと叱られた時代は遠く去ったのである。
天皇家は平和の象徴なのだな、と感じる。平成になってから18年。ご発言を集めた本が出されても良いのではなかろうか。政治的な意図をもって使いたいところだけを編集して小出しにする方法は健全ではないと思う。
- 7月19日(水)
休みをとった日。朝、腰が痛かったのでお灸をすえてもらう。
『時をかける少女』のアニメ映画を観る。女の子がボールを投げるフォームがぎこちないのはわかるが、男の子が投げるときもおかしいのが気になってしまった。学芸員が積んである資料の上にコーヒーカップをのせたソーサーを置いたりすることはあり得ない。監修者に学芸員がいたのに、この箇所は確認しなかったのであろうか、と、必然性もなさそうなこのシーンにはかなり憤りを覚えてしまった。親子連れにぶつかって自転車の籠からなくなっていたはずの桃をおばさんと食べていたが、いたんでいないのが積まれていたのはなぜか、とか、学校で、桃はどこに置かれていたのか、とか、細かい箇所が気になるのは私の性格ゆえか。NHKの少年ドラマシリーズ『タイムトラベラー』を観て筒井ファンになった私にとってこの作品はやはり特別な思い入れがあるのだな、などとぼんやり考える。思春期独特の感情が蘇ってきたりもするのであるが、気になる箇所がありすぎて、なんだかなあ、といった感じで映画館を出た私。
グランパス対サンフレッチェ。先制し、逆転され、前半に追いつき、後半に点を取られるというややスリリングな展開であったが、みごとに負けた。ディフェンスがしっかりしていないのではなかろうか。
- 7月18日(火)
『ミッション・インポッシブル3』を観る。私はあまり好きではなかった。誰が悪い奴であるか、が早い段階でわかってしまったりもした。
買ってあった『まほろ駅前多田便利軒』(三浦しをん)が直木賞を受賞したので読む。これは傑作だと思う。
北朝鮮はアメリカを怖がるあまり、ミサイルを撃っているのかもしれないな、などとふと思う。アメリカを怖がるのは健全かもしれない。9.11は映画になったりするわけだが、犠牲者の何倍のひとをあれから殺したのであろうか。
ジダン擁護派が多いようである。ひどいことを言われたら頭突をしてもよい、というルールに変わったら面白いかもしれない。言われそうだったら頭突可、とか、言うに違いないと感じたら頭突可、と変化していったりして。
忌野清志郎を大好きであった80年代初頭の私。横浜スタジアムまで、チャック・ベリー、サム&デイブレビューとの共演を観にいったりもした。あのでっかい声が手術でどうなるのか心配である。坂本龍一との共作『い・け・な・い・ルージュ・マジック』のプロモーション・ビデオでのコメントは「坂本が先に舌を入れてきそうだったので、俺が先に入れた」であった。先制攻撃や過剰防衛は気になるところである。
- 7月17日(月)
一昨日録画をしておいた中田英寿の特番を朝観る。4日に書いた私の記憶が出鱈目であることがよくわかる。初得点は代表3試合目のマカオ戦であり、インタビューでの答えもまるで違っている。「まぐれですよ」と言ったのはいつのことであったのだろうか。あるいは記憶がすりかわっているのかもしれない。ひとの頭というのはテキトーなものである、と、人類全般に敷衍してしまって平穏な顔をして過ごそうと思う私。クロアチア戦の分析が見事だった。アレックスが簡単にクロスをあげさせてしまったり、守備をしに出てゆかねばならないところでいかなかったり、といった点がずっと気になっていたのだが、中田も当然気づいていたのである。監督がどう考えていたのかがわからないところ。ジーコの人柄を気に入って代表にとどまっていた、という話はわかったようなわからぬような。右足首に水がたまるほどの状態でワールドカップを戦っていたのか、と驚いた。パスの精度が良くないな、とは思っていたが、それほどまでひどかったとは。制作スタッフは、特種をつかんでいながらも中田との信頼関係を崩さずにこの番組を作ったわけである。実に偉い。いまどきの日本人には珍しい態度である。中田はベルマーレにいた頃からプロフェッショナルであった。当時の日本代表選手にはすぐに転んでファールをもらおう、というひとが多かったが、中田は簡単には倒れず、前へ前へと進んでゆこうとしていた。また、審判にクレームをつけるのを見たことがない。熱が出た、とか、どこかが痛い、と言わずに試合に臨んでいたのだな、と改めて彼のプロ意識を思ったのであった。ほかの選手に色々言って、聞き入れてもらえなかったりもしたわけだが、言えるだけのことを常にしていたから言ったのである。それでも言ってはいけない、言われても聞きたくない、また、そういうひとからだから余計に言われたくない、というのが我が国のヒトには多くいるように思う。彼がイタリアやスペインで生まれていたら、いくつかの苦労はせずにすんだことであろう。また、監督がすべきことまで彼がしなくてはならなかったのは不幸であった。
仕事はばたばたであった。利用者はそれほどでもないのだが、閉架の資料の出納やレファレンス、予約、リクエストが多かった。
- 7月16日(日)
ばたばたの一日であった。書架のきついところがあったので、閉架へ異動する本を選びはじめたのであるが、その間に利用者からの問い合わせがしばしば。やはり開架に職員がいないといけないな、と痛感。二百冊ほどを選び、開いた隙間に本を動かす。少し腰痛になる。
- 7月15日(土)
利用者多し。ばてる。
録画をしておいたオールスター戦を観る。オシムが細かくチェックしていたようである。小林大悟が見事な活躍。古橋もしっかり得点。鈴木慎吾も良い動きであった。Jリーグで活躍している選手を代表に選ぶ、とオシムが言っていたので、誰が選ばれるかがとても楽しみである。
- 7月14日(金)
休み。
部屋を片づけようと決意していたのだが、どうしてよいのかわからないくらい汚いので厭になって止す。いつかはなんとかしないといけないのであるが、暑い。暑くないときにもしたくない仕事を暑いときにしようと考えたのが間違いである。
- 7月13日(木)
朝、小学三年生が見学にきた。とてつもなく暑い日であり、おしまいに外で質問を受けていたのだが、くらくらしてきそうであった。
視聴覚資料の入力、図書の分類、受付。ばたばたであった。
- 7月12日(水)
日曜に書架から出した本を朝早くから仕舞う。ブックポストへの返却本が1700冊。午前だけで一日が終わったような気分となる。
出版社が見計らいの本を持ってきた。ほとんど持っている本。持っていない本は高額でそれほど利用が見込まれないもの。結局何も買わなかった。最近、こういうことが多い。資料費はぎりぎりなのである。
夏休に勤労体験にやってくる中学生が二校から挨拶にきた。前もって聞いていたので準備ができていて安心。なかなか礼儀正しい少年少女たちであった。
突如として高校生二人が勤労体験をしたい、と来館。見計らいと中学生が終わったので、あとは受付業務とDVDの入力で今日が終わるな、と考えていたところだった私。話を聞くと、図書館を好きであり、図書館の仕事に肉体労働があることも知っていると言う。夏に五日間、朝から晩まで来たいとのこと。考えてみれば書架整理の即戦力である。上司と相談し、来てもらうことにする。
ガンバ大阪対ジュビロ磐田戦をテレビで観る。審判は西村さん。厳しいPKであった。ジュビロの監督アジウソンは現役時代と比べて太っている。
オシムが日本代表監督になるのは本決まりのようである。うれしくてしかたがない。ジェフの選手がインタビューで、「オシムがいなくなって弱くなったと言われたくない」と語っているのを数日前に見た。いなくなったら駄目になってしまう監督ではなく、しっかりと人間を育てている監督なのだということがよくわかる。『オシムの言葉』、大増刷である。著者の木村元彦さんは元疾走プロ。このプロダクションの作った有名な映画は『ゆきゆきて神軍』。木村さんは、何が真実なのかを深く掘り下げるライターである。オシムによって考える国民となる、なんてことはないだろうなあ。
- 7月11日(火)
耳に水が入ったらしく、変。耳鼻科へゆく。軽い外耳炎とのこと。年寄の冷や水という言葉をなぜか思いうかべる。
- 7月10日(月)
いよいよ決勝。リベリは百分走りっぱなしであった。惜しいシュートがあった。フランスを応援していた私。一体マテラッツィはジダンに何を言ったのであろう。イタリアの優勝。表彰式がいかにもイタリア人らしくて面白かった。次は南アフリカ大会である。四年後の世の中はどうなっているのであろうか。
海へゆき、泳ぐ。ビニール袋が浮いていたりする。地中海と三河湾はまるで違うな、と思う。海の家はまだ開いておらず、シャワーもないので、公衆トイレでテキトーに身体を流す。
- 7月9日(日)
ドイツ対ポルトガル戦。上川さんが笛を吹くことにどきどきする。Jリーグの試合でもどきどきするのに三位決定戦とは。なかなか良い試合であった。あと一試合でワールドカップが終わる。四年前のワールドカップのときに何をしていたのかを思い出す。友達の見舞に行ったとき、小さなテレビで試合を見たりしたな、とか。八年前のフランス大会のときは市民課にいたのであった。時は確実に動いているらしい。
さすがに日曜日である。ばたばたであった。閉館後、明日、明後日と照明をかえるため、書架を移動させる準備として本を二千冊ほど抜き、机に並べる作業。終わるとよれよれであった。
- 7月8日(土)
利用者から村上春樹の『アフターダーク』について書かれている雑誌記事を読みたい、との質問。私は『アンダーグラウンド』と勘違いして、サリン事件のあとだから書かれた時期は云々、と言い、利用者は若い人で、そんなに前ではありません、『海辺のカフカ』のあとです、と言う。変だな、と感じ、はた、と自分の間違いに気づく。5日の、書名を忘れてしまうミスと言い、どうやら明らかに年である。利用者多し。
- 7月7日(金)
観ようかどうしようかと悩んでいた『初恋』を観る。69年に部屋に電話を引いている下宿学生はあまりいないであろう、とか、おひょいさんと坊ちゃんである岸くんの接点はどこにあったのか、とか、みすずの門限は何時になったのか、とか、疑問点は色々あったりしたのだが、とにかく宮崎あおいが切なくて良かったのだった。予告編で大事なところを割ってしまっていたのが残念。
- 7月6日(木)
朝昼空いていたが、閉館間際に混む。
七夕について友達とやりとりをする。「一年に一度しか会えないのはやだな」「一生会えないよりはかなり良いと思う」。まるで子供みたいである。
- 7月5日(水)
朝はがらがらだったが、夕方混む。三冊の本の在処を訊かれ、一冊見つけて、「○○ともう一冊はなんでしたっけ」と尋ねた私。もう一冊を見つけたあと、「あと一冊はなんでしたっけ」と訊く。「閉架にいけばありますから持ってきます」と言うと利用者に、「紙に書きましょうか」と言われてしまった。四文字のタイトルの本を計三回尋ねたのであった。老化だな、と思う。
資料のあまりない郷土人についてのレファレンスがあった。『昭和人名辞典2』が役に立つ。日本図書センターが複刻した地域ごとの昭和初期の人名辞典。
- 7月4日(火)
朝、このホームページのデザインをしてくれたり、さまざまないたづらをしてくれているMさんことみつたさんにメールでフォームからのメール送信について質問。
ドイツ対イタリア戦の最中、北朝鮮からミサイル発射の報。めちゃめちゃな国であるなあ。日本とぐるになっていて、憲法改正のために動いた、なんてシナリオ、ではないよなあ。一番偉いひとが狂っているとすごいことになるのは歴史ではいくらでもあるのだが、もう少し遠い国だと良かったのにと思う。
中田英寿現役引退。私は彼が初めて日本代表に選ばれた韓国戦によってサッカーを熱心に見るようになったのだった。美しく力強いプレー。インタビューで本心を語らずはにかんでいる若者。「良いシュートでしたね」「いやあ、まぐれですよ」と言ったのではなかったか。解説の松木さんが、「あのシュート狙いすましていますよ。言ってみたいですね、まぐれだなんて」と言っていたような記憶。「ファンのみなさんに一言」「Jリーグを見てください」とも言っていたな。それで私はJリーグを見はじめたのだった。J1のベルマーレ平塚では森山に出したパスが合わず、怒っていたり。スタイリッシュな選手であった。彼がいなければ私はこんなにサッカーを見てはいなかっただろう。オシム監督のもとでの中田が見たかったが、あれだけしっかりとしたひとの意思である。長い間ありがとうと言いたい。
名古屋シネマテークにミヒャエル・ハネケ監督の『セブンス・コンチネント』を観にゆく。悲惨なシーンのはずなのだが、笑いがこみあげてしかたがない箇所があり、こらえるのに必死だった。私はどうもあまり好きではないな、と感じた。
- 7月3日(月)
近くの魚市場へ行き、舌平目を買う。安い。赤いのと黒いのがあり赤いのがうまい、とか、どのように調理するのかを教えてもらう。晩にムニエルにしたところとてもうまかった。
インデックスページのメール送付のフォームからはメールが送れなかったことが判明。どうしてよいのかわからない。
- 7月2日(日)
フランス対ブラジル。フランスの勝利。ジダンのFKをアンリが決めたのであった。リベリという選手を知らなかったのだったが、実に良い。よく走り、どこにでも顔を出す。そういえば日本代表の小笠原が1999年にはこんな感じであったな、などと思い出す。ナイジェリアで90分サッカーをした直後のインタビューで淡々と答えていた小笠原を見て、こいつは化け物か、と驚いたのだったが、7年経ってまるで走れない選手となってしまった。海外に移籍していればまた違っていたのかもしれない。
利用者多し。さすがに日曜日であった。
- 7月1日(土)
土曜日はばたばたである。
- 6月30日(金)
比較的利用者の少ない日であった。
昼休に焼魚定食を食べる。舌平目であった。この魚、高い割にまずい、と二十年くらい前に思ったのだったが、安い焼魚定食なのにとてつもなくうまくて驚いた。店のひとに尋ねると、近場で獲れたばかりのものだとのことであった。
- 6月29日(木)
みすず書房の『大人の本棚』のシリーズの造本はやや地味で、ラインナップも、これらは売れるのであろうか、と心配になったりする私。野呂邦暢の『愛についてのデッサン』は古本屋さんが主人公の小説。タイトルには感心しないが、この元版を入手するのに苦労していた頃を思い出す。古本屋さんの出てくる小説は梶山季之、紀田順一郎、出久根達郎ら、数えるほどしかない。リリカルな文章を書く野呂の書いた古本屋小説は是非読みたい、と考えたわけである。遠い昔のこと。みすず書房の版には佐藤正午が解説を書いているが、私はどうもこのひとに馴染めないのであった。しかし、『愛についてのデッサン』から野呂の文章が変化したとの話には肯いた。
仕事らしい仕事ができているのはうれしいことである。何が仕事らしい仕事であるかを考えないでいると、仕事の質は落ちてゆくであろうな、などと思う。
著名人の正妻ではないらしい女のひとについてのレファレンスがあった。大正、昭和初期のひとなので赤新聞や雑誌をこまめに見てゆけば何か出てくるかもしれないが、表に出にくい事柄を調べるのは一筋縄ではゆかないのであった。
- 6月28日(水)
小学3年生が見学に来た。またしても一番貴重な本はどれですか、との質問。当館には江戸初期から明治にかけての和本が1万冊ある。なぜあるかと言えば昭和初年に金持ちの読書クラブから寄贈されたからである。指定管理者制度が導入されるとどうなるのだろうな、とふと思う。どうやって本を集めたのですか、との質問。大正時代から図書館がある町なので、毎年少しずつ購入したり寄贈してもらった本が沢山になったのである。これらの資料を扱うのが民間会社の人達となった際、どんなことがおきるのであろうか、などと想像する。どうも頭が暗い方向に向きがちな昨今の私である。ともあれ小学生の見学は刺激になる。思いも寄らぬ質問があったり、気づいていなかったことを教えてもらえたりする。
- 6月27日(火)
火曜日の割に利用者の少ない日であった。身体に良いと信じてとある植物を食べ続けている利用者からその植物と効能についての本はないかと問われる。よくよく聞くとすでに何冊も借りており、効能について書かれているのは別の種類ばかりなのだが、家にあるのがどれかよくわからず、それにはどんな効き目があるのかを知りたいのだ、と言う。それが薬であるかどうかさえ怪しいわけであり、Webでその植物に関する項目をいくつか見せ、食べ過ぎると良くないと書かれている種類もあること、すべての種類が身体に良いのかどうかがわからないこと、植物の同定はなかなか難しいことなどを説明する。また、医学関連の本がすべて正しいとも限らないし、インターネットのページには嘘が書かれている場合もあるとも話す。植物の専門家とその植物の効能を調べる専門家は別であるとも説明。結局最後はご自分で責任を持って食べてください、と、念を押す。しかし、理解してくれたかどうかはさだかではない。命が危険なのかもしれないようなものを食べているひとなのだが、自覚がまるでないし、本人がいいのならばそれはそれで私は全然構わないのだけれど、一応危険性について話すべきであろうな、と職業柄考えたのであった。しかしみんな身体に良いものが好きだな。長生きをして何をしようというのか、という点についてはあまり語られないのが不思議であるが。ただただ長く生きているとうれしいのであろうなあ。
- 6月26日(月)
『アダン』を観る。会員価格の映画料金が1000円なのだが、先着何名か、ということで2000円の本『煌めく刻−映画『アダン』奄美大島ロケーション回想記−』をもらう。榎木孝明の田中一村を予告で観てこの映画を観ようと思った私。少し長い気もするが映像が美しく良い作品であった。
オシム監督をテレビで観ていて、色川武大に風貌が似ているな、と思う。『オシムの言葉』(木村元彦著、集英社インターナショナル)は良い本なので未読の方は是非ご一読を。しかし代表監督に就任してくれるのかなあ。
- 6月25日(日)
午前中は割と空いていたのだったが、午後から混む。中高生のマナーは良くない。飲食禁止場所での飲食をなんとも思っていない。この頃は大学の授業中でも給水をする学生がいるとか。昔は野球部の真夏の練習でも疲れるからと給水しなかったものだが。って、それはそれで身体に良くなかったわけであるが。そういえばショッピングモールにある鞄屋に、「店内でのご飲食はご遠慮ください」との貼り紙があったな。そういう客が多いわけだ。歩きながら食べたり飲んだりするのは昔は土方か不良学生くらいであったのだが世の中は変化しているのである。しかし、一時間や二時間給水しなくたって死にやしないし、そんなに飲みたければロビーに行けば良いだけなのに無精な子供たちである。彼らが日本の将来を背負ってゆくのだ。期待の持てる国になるなあ。
- 6月24日(土)
メキシコ対アルゼンチンは良い試合であった。
川淵三郎キャプテンはジーコを監督にしたことについての責任をどう感じているのであろうなあ。謎の人だ。オシムに会っていないし承諾も得ていないというのに次期代表監督はオシムであるとの失言をしたそうだが、ジェフの選手やファンの気持ちをどう考えているのであろう。オシムはレアル・マドリッドからオファーがあっても自分に向いていない、と、断る人である。誠意を重んじる人である。オシムが代表監督になってくれるのであれば私はとてもうれしいが、この川淵の失言(わざと?)で臍を曲げた可能性が大きいのではあるまいか。それにしても一次リーグ敗退直後に次期監督の話題を出すのは胡散臭すぎるな。今季のジェフがどうなるかも気になるところだ。
思ったより利用者の少ない土曜日であった。学習のためにやってくる中高生についての悩みが復活。利用不可とした期間が6年、認めてから6年。元の状態になってきた。
- 6月23日(金)
早起きをして日本対ブラジル戦を観る。実力差は戦う前から歴然。クロアチアでなく、オーストラリアが決勝進出をしたことに驚く。つぎは誰が日本代表監督になるのであろうか。
丁稚のような名前のミサイルで死ぬことは厭だなと思う。
『トリック劇場版2』を観る。乱暴なつくりである。しかし、山田と上田が出ていればそれでいいか、という気にもなる。
時折かかってくる無言電話はさみしいものであるな、と思う。
- 6月22日(木)
藤田嗣治展を見る。人が多い。今日明日と休みの私。
- 6月21日(水)
特別整理期間前の数日、返却期限をこの日に設定していた為、返却貸出が4000冊を超えた。慌ただしく一日が過ぎた。
- 6月20日(火)
休み明けなので少しばたばた。
小学三年生が見学に来たので対応。「一番価値のある本はなんですか」との問いの回答に悩む。
- 6月19日(月)
『雪に願うこと』を観る。伊勢谷友介は上手いんだか上手くないんだかよくわからない役者だが、存在感が強いことははっきりしている。佐藤浩市が良いのはわかりきっている。根岸吉太郎監督は田舎町の景色を見事に撮る。なんということのない話ではあるのだが、美しい映像と場面転換の上手さで実に見応えのある映画であった。
ちくさ正文館へゆく。ついつい沢山本を買ってしまう。昔の映画のDVDは500円で買えるのですな。知らずにいた私。エルンスト・ルビッチとかハワード・ホークスとか古めのヒッチコックがあったりする。ついつい買ってしまう。どうもこの本屋さんに来ると1万円くらいは使ってしまう私である。
- 6月18日(日)
貸出、返却とも5000冊を超えた。「芥川龍之介の『羅生門』はどこにありますか」との質問。簡単と言えば簡単な問いなのだが、「新仮名と旧仮名とどちらがよろしいでしょうか。字の大きさはどのくらいのが良いでしょうか」と確認し、どの全集を提供するか、といった思案をするかしないかが司書と素人の差かな、などと思う。もっと素人だと書名がデータになくて、「所蔵がありません」と答える場合もあるかもしれない。提供できてもできなくても、図書館は建っているわけであるが。
- 6月17日(土)
利用者、なかなか多し。
- 6月16日(金)
視聴覚資料の整理。一般書の見計らい。
- 6月15日(木)
出版社が二社、見計らいの本を持って来館。一社は歴史のあるところ。昔の出版傾向といまの同社の出版物と未来について少し話したり。採算の合わない本を沢山出していた出版社。大手なのに実験的な作品を載せる雑誌があったりして好きだったな、と高校生の頃のことを思い出す。
- 6月14日(水)
久々の出勤。ずっと休みだといいのにな、と思う。利用者多し。視聴覚資料の整理、本の見計らいをする。
- 6月13日(火)
岡崎美術博物館に「エコール・ド・パリ展」を観にゆく。私の好きな画家、彫刻家の作品がいくつかあったのであった。
- 6月12日(月)
10日から4連休である。あれこれしていた。今日は『僕の大事なコレクション』を観にいった。とても重いテーマを扱っている映画なのだが、良いギャグが入っていて淡々と観ていられる。映像が美しい。ユージーン・ハッツがとても良かった。どうもこのところ気がつくとユダヤ人の問題についての本や映画に接することが増えている気がする私。
- 6月9日(金)
久々に開館。さすがに利用者が多い。調べもののひとも沢山。特定外来種オオキンケイギクについての質問が興味深かった。しばらく前までは緑化のためと市町村などで積極的に植えられていた植物が他の植物に被害を及ぼすおそれがある、とされているのを多くの人が知らずにいるのは恐ろしいことである。世の中には知らないことがいっぱいあるな、と、この仕事に就いているとしみじみ感じる。
- 6月8日(木)
特別整理期間、最終日。閉架の移動作業は終わりきっていない。まだ7分類である。9分類への道のりは遠かった。
ワールドカップ一次予選を日本が勝ち抜くにはジーコの運にかけるくらいしかなさそうだな、と感じている私は同じように思っている友達と久しぶりに電話で話した。
沖縄在住の友達のブログに平良夏芽さんの文章が載っている。沖縄に住んでいない日本人のどれだけが、辺野古のことを知っているのか、関心があるのだろうか。沖縄が日本に還ってきてから34年になる。本当に還ってきたのだろうか、と時折考える。1945年に日本が見捨てた場所を今も見捨て続けているのではないのか。
- 6月7日(水)
6分類から7分類。7は美術である。本がでかい。一冊が5キログラムくらいあったりする。棚の高さがほかの分類と違っていたりする。やたらと時間がかかる。作業は進まない。あちこち痛くなる。埃も多い。そんな一日であった。図書館の仕事はばばっちくて重たいのだが、世間様からの目は、良い環境で楽そうに見えるのである。
パルコ・シティの出しているメールマガジン『 BOOK Door to Door 』を読むようになったのは、以前私のHPを紹介してくれたからであったのだが、今回紹介している白水社のページは実に面白かった。斎藤美奈子の連載を全部読んでしまったのだが、子供に本を読ませようとしている親や教師の読書週間や「感銘した本」というのがすごい。いやはや。アメリカでは読書会が流行っているのか。知らなかった。私は中学一年の時、一度だけ読書会に参加したことがある。担任が国語の先生で、「君は本が好きだから、ほかはみんな二年三年だけれど、出てはどうか」と勧められたのであった。壺井栄の『柿の木のある家』が課題図書。参加者は女のひとが多く、きれいなひともいて、弁が立って圧倒された記憶。体育会系の部活をしていたので、日が合わないこともあってそれ以降参加しなかったのだが、参加者が多様で鋭ければ面白い会であろうことは想像できる。三十年くらい前まではあちこちの図書館で企画されていたようでもある。今の私はあまり参加したいとは思わないけれども、読書会が日本のあちこちで開かれるのも悪くないかもな、などと思った。
- 6月6日(火)
一日閉架で作業。帰りにお灸を据えてもらいにゆく。背中にしっかりと痕がついているこの頃。すっかりおやぢである。
スパムメールが日に150通から200通ほど来る。8割方はアサヒネットのスパムブロックで切ってもらえているのだが、30通から40通ほどは届く。スパムメール以外のメールが全くこない日もあったりする。何もこないよりはましかもしれない、と自分を慰めたり。
- 6月5日(月)
休み。『嫌われ松子の一生』を観る。原作は出てすぐに本屋さんでぱらぱらと見、私に向かない文章だったので買うのを止したのだが、ベストセラーとなっていった。歳とともに読めない本が増えている。映画は『下妻物語』の監督中島哲也が撮ったのと、中谷美紀が主演であるということで観にいったのである。ううむ。中谷美紀、香川照之、伊勢谷友介がとても良かった。ところどころミュージカル仕立てになっているのも悪くない。でも、私の好みではなかったのだった。いくつか時代考証が気になったのだが、特に変だと感じたのが、松子の甥の子供の頃、父親とトヨタパブリカに乗っている点。時代が合わないと思う。2001年に25歳前後の男が5歳くらいであるとすれば1980年前後の話。二代目パブリカは70年代半ばにはほとんどなくなっていたはず。こういうのをついつい見てしまうのは良いことではないのだけれど、気がついてしまうのだからしかたがない。
衣替をする。ばてた。買ってすぐ、ペンキ塗り立てのベンチに坐ったため、尻に白くあとがついてしまったペンキをなんとか剥がして履いていた黒いコットンパンツの裾が擦れてきているのを捨てようかどうしようか、と迷った末、来シーズンも履くことにした。冬物よりも夏物のほうが多い私。タンスになんとかむりやりシャツを入れたのであった。ふう。
- 6月4日(日)
二人倒れたまま。4分類の本を運び終え、空いた4の棚に5を入れる。6、7、8、9と動かしてゆく予定でいるのだが、途中で空きがなくなりそうな気がしてくる。身体のあちこちが痛い。
- 6月3日(土)
新聞の移動が終わり、空いたスペースに4分類の本を移動。1階から2階へと運ぶのである。運ばれた本を適当な空きをつくりつつ本棚へ並べるという作業。本は埃だらけである。閉架はエアコンが入っていない。なかなか過酷だが、楽しい。本が好きでないひとにとってはただただ苦痛であるかもしれない仕事。嬉々として行う我々はすこし気が違っているように思えないでもない。体調不良で一人欠席、二人早引け。
- 6月2日(金)
午前にスキャンが終了。新聞の移動。歳のせいか身体がきしむ。書架を整理したのち、不明となった図書の一覧を見て本当に無くなったかを確認。よれよれとなる。
革のリュックサックが欲しい。今使っている革のリュックサックは1993年に購入したTOKIO KUMAGAIのものであるが、まさかこんな使われ方をされようとは思っていなかったことであろう。これでもか、というほど本を詰められたのである。丸っこい形なのに角が出てしまうほどに。週に一二度、どこかに運ばれてそんな目に遭っていた。一泊二泊三泊の旅行にも持ってゆかれた。おまけにノラ(現在11歳なのだが、早朝から大暴れをする猫。♀)が上に乗っかって引っ掻いたりもする。それでも内装は丈夫でしっかりしているのであるが、ベルトが切れてきたのであった。買う時には高いな、と感じたが、今にして思えばなんという安い買い物であっただろうか。もう一つ買っておけば良かった。数年前からかわりのものを探しているのである。こんな恐ろしい使われ方をすることはもうないので、多少軟弱でも構わないのだが、デザイン、大きさ、背負った感じの良いものが見つからない。どこかリュックサックを山のように置いてある店はないだろうか。革は傷だらけであるが、直してもらおうか、とも思うこの頃である。
- 6月1日(木)
特別整理期間。ひたすら本をスキャン。15万冊ほどなぞるのである。1時間スキャン、30分スキャン以外の仕事、というパターンなのであるが、この30分の間に新聞の移動という恐ろしい作業。一日が終わるとかなりぐったりするのであるが、本や紙を触っていることがなんとなくうれしいのが不思議。
- 5月31日(水)
休みの職員が多く、行事もあり、どたばたであった。
小学六年生が図書館見学に来た。彼らは三年前に見に来ているはずなので、案内をしつつ、ここは覚えているかな、と尋ねたのだが、二割ほどの児童しか覚えていないようであった。図書館から一番近所の小学校である。忙しい合間を縫って、子ども達に図書館を知ってもらおう、と説明をしたあれらの時間はなんであったのだろうか、と、やや淋しい気持ちになったが、きっと頭のどこかにすこしは図書館のことが残ってはいることであろう。
- 5月30日(火)
なかなか慌ただしい一日となった。明後日から特別整理期間である。
- 5月29日(月)
「お母ちゃん、パンツ破れちゃったよ」
「またかい」
などと古い小咄を思い出しつつ、パンツを捨てる。新しいパンツを買ったのであった。服をなかなか捨てられない性分。クレパスのキャラクターのパンツなどもあったが、これからはどこで脱いでもはずかしくない大人らしいものに変えてゆこうと思うのであった。ん。どこでも脱ぐ気か。それはいけないな。どこで見せても恥ずかしくない。これもまずいか。パンツというのはなかなか難しいものである。本格的な衣替をする予定であったが、根気がなかったので止した。
- 5月28日(日)
特別整理期間の前の日曜日なので混む。ふう。
- 5月27日(土)
さすがに土曜日であった。利用者が多く、ばたばたと一日が過ぎた。ベストセラーに予約をしたひとに、「三ヶ月ほどかかりますが」と言うと、「一冊しかないの。買わないの」とすごい剣幕で言われる。五件以上予約が入った時点で副本を検討するのであるが、そんなに早く読みたかったら買えばいいのに、と個人的には思う。数年経ったベストセラーは見向かれることが少ない。しかし、そういう本のほうが需要は多いわけで、多数に阿るだけで良い、という考え方に流れれば(そんな方向に多くの公共図書館は進んできた気がする)司書はいらない、指定管理者制度を導入したって問題はない。沢山のひとが喜んで使ってくれる、というふうに世間様が思ったとしてもなんの不思議もないのだよな、と、慌ただしい合間にそんなことが頭をよぎり、なんとなく憂鬱な気分に一瞬なった。
- 5月26日(金)
今日も利用者多し。リクエスト図書の発注、視聴覚資料の整理をする。
「カール・マルクスの伝記はありますか」との質問。簡単そうでかなり受け答えが難しい。生涯を網羅的に書いた伝記で良いのか、ある時期だけのもので良いのか、気質について書かれたものが良いのか、資本論の概略がついていたほうが良いのか、思想について踏み込んだものが良いのか、いくつかの質問をしながら提供をする。哲学、社会科学、そして、のちの時代への影響。あまりにすごいひとであると、「伝記ありますか」だけでも提供するのは楽ではないのである。しかし、司書でないひとが受けると簡単なレファレンスだったりするかもしれない。「はい」と言って件名で「マルクス」と出てきたうち、新しい本を何冊か渡すであろうし、案外それで事足りるのかもしれない。グルーチョ・マルクスの書いた『好色一代記』を提供するとまずいが。
朝、車の中で聴くカセットテープを探していたら、南沙織のが出てきたので、かけた。随分と古いテープなので、時折大きく「ぶわああ」、とノイズが入ったりするのが怖いが、『色づく街』、『ひとかけらの純情』、『哀しい妖精』などを聴くと、70年代はじめから30年の間のあれこれを思い浮かべ変梃な気分になった。アサヒネットで音楽の会議室のモデレーターをしていた日々を思い出したり。『17歳』をはじめて聴いたのは『おれは男だ』のなかでだった記憶。
- 5月25日(木)
来週から棚卸で、長い休みがあるせいか、利用者がとても多かった。
友達のホームページを見ていたら、『やわらか戦車』というのがあったので、それはいったいなんなのであろうか、と見てみたら、面白く、同じ作者の『くわがたツマミ』も全作見てしまった。
- 5月24日(水)
休み。『陽気なギャングが地球を回す』を観る。佐藤浩市が良いのは当然である。脇に濃いめのひとが沢山出ていた。大沢たかおの上司で出ている松尾スズキのあの役はどうなのであろう。オープニングまでの映像がとても面白く、期待したのだが、湿ったところがあったり、おしまいがやや乱暴であったり、と残念であった。
午後、ノラが暴れる。
- 5月23日(火)
宿題となっているレファレンス、やはり解決つかず。あれこれとばたばたした一日であった。
- 5月22日(月)
『ナイロビの蜂』を観る。良い映画であった。
夜、アサヒネットの古い友達とオフラインミーティング。狭い店で、若い娘さんの団体がいるところでシモがかった話をしたりすると、汚いものでも眺めるような目で睨まれたりする。それもまたアサヒネットの名古屋オフの醍醐味ではある。
- 5月21日(日)
日曜日である。混む。難しいレファレンスが一件、宿題となる。
- 5月20日(土)
休み。『グッドナイト&グッドラック』を観る。映画的に面白い、という映画ではないが、この頃のアメリカや日本の状況をあれこれ考えさせる内容であった。
- 5月19日(金)
訊かれたことのない郷土関連のレファレンス。五十年ほど前の、あまり資料がない分野とは言え、まるでないわけではなかったので一安心。思いも寄らぬ調べものが突然やってくるのは図書館員の一番の愉しみであるな、と感じた。
- 5月18日(木)
岡崎武志の『気まぐれ古書店紀行』を毎日少しずつ読んで、今日読み終えた。古本屋が大好きであった私であるが、部屋に本が入りきらなくなったことや、その他の理由でこの頃はあまり行かなくなってきている。以前であればこんな本を読んだら虫がわいたように古本屋回りに出かけたであろうな、と思った。
- 5月17日(水)
昨日書いた内容は、これならば場所、ひとを特定できないであろうな、と考えたのであったが、それはつまり日本のあちこちで空襲があって、ひとはとても沢山死んでいて、知り合いが死んでいるか生きているかはっきりしないひとがいっぱいいる、ということを私が知っているのだ、と気がついて、そのことに驚いた。
- 5月16日(火)
どこで尋ねればよいのかわからない事柄を図書館に訊く方がいる。それで判明する場合や、ある程度わかる場合もあるが、なんともならないこともしばしばある。今日私が受けた質問はかなりつらいものであった。ある町からある町へ複数人で就職をしたうち、質問者だけが母の実家のある町へと移ることになった。就職した町は空襲に遭い、働いていた事務所は壊滅的な被害を受けた。出身地は空襲と地震と火災で、さまざまな記録がなくなった。若いうちにはそれほど気にならなかったが、自分だけが生き残ったことに対する負い目のようなものを感じる。狭い部屋で一緒に暮らしていた人達は恐らく死んでしまった、いや、死んでしまったに違いない。それを確かめようと、空襲の記録も読んだ。ほかになんとかならないか。というお話であった。調べてみると空襲記録は幾度かに渡って編まれており、戦没者名簿のまとまったものもあるとのこと。利用者に確かめると、その名簿には目を通し、そこに、ともに働いた仲間の名はなかったそうである。彼らの消息をつかむには仲間たちの直系親族に連絡をとるか、出身地の寺の過去帳を調べるくらいしかないと思われる、と話すと、親類についてはわからず、寺も恐らくは震災と火災でどうにかなってしまったのではなかろうか、とのこと。図書館では調べようがない。60年以上経っても戦争が終わっていない人がいる。空から爆弾を降らせるってのは、絶対間違ってるよな、としみじみ思ったのであった。戦争でつけられた傷の大きさ、深さを、つけた側はどれくらい知っているのかな、と感じる。死んでしまったほうが良かった、と心のどこかで感じながら生きなければならなくなった人の一生に誰が責任を負えるのであろうか。今も爆弾を落としている人達がいる。私はそれに加担する国に住んでいる。
- 5月15日(月)
『ピンクパンサー』を観る。スティーブ・マーチンがクルーゾー警部を演じるのでなければ決して観ないであろうな、と思いつつ。見事に堂々としたバカを演じていた。ケヴィン・クラインのドレフュス主任警部も素晴らしい。
- 5月14日(日)
休み。ガス・ヴァン・サント監督の『ラスト・デイズ』を観る。映像が美しい。多分、こんな感じの映画であろうな、と予想していた以上に息苦しかった。ニルヴァーナのカート・コバーンが自殺の前の一週間ほどをモチーフとした作品。あれからもう十二年になるのか。背骨の歪みを気にして、などという理由もあったな、と思い出す。
本屋さんをまわる。このところやや買うのを控えていた反動か、やたらと買ってしまった。
グランパス対セレッソ大阪。久しぶりに勝てたかな、と思ったのだが89分に同点にされてしまった。
- 5月13日(土)
慌ただしい一日であった。帰り際、本棚がいっぱいなので、ずらそう、と軽く考えて作業に入ったところ、並びが乱れていたため、大がかりに直しながら動かしていたらかなり疲れた。歳なのだから、加減をしないといけない、と感じたのであった。
- 5月12日(金)
『富豪刑事デラックス』に友達が経営している旅館がロケに使われたという話を聞いていたのをほかの人達に知らせることをすっかり忘れていたので、慌てて朝にメールする。生死不明のひともいたりしたが、返事がきたり。
視聴覚資料の整理、図書の発注、カウンター業務。仕事の種類が多く、飽きないのが図書館の仕事のよいところである。
- 5月11日(木)
昨日とは違い、空いた日であった。三年ぶりの利用者の方がいらしていたので挨拶。様々な難しい質問をなさる人。お元気そう。
- 5月10日(水)
朝、ブックポストに返ってきていた本は約二千冊。棚に戻すのが大変であった。利用者多し。
夜、名古屋レファレンス探検隊のコメンテイターをした。出した問題は心理学関連のものであったのだが、昨年読んだ文に、精神分析学を講座としている大学はほとんどなくなった、と書かれていたことについて触れ、学問分野がなくなってしまうこともあるわけで、資料提供は慎重にせねばならないし、情報を得るような生活に努めねばならないのである、といったような話をした。過去に信用のおけるものだ、と考えられていた事柄が信用できなくなるのはしかし恐ろしいことである。晩の宴会ではATTTのTさんがつま恋にゆくことが判明。力が入っているようである。
- 5月9日(火)
『寝ずの番』を観る。予告で観せていた箇所が一番面白いところであった。オムニバス形式の映画をそもそもあまり好きではない私。木村佳乃と岸部一徳が出ていればそれで幸せなので、別に大した不満はない気もする。ラスト近く猥歌のシーンでの岸部一徳がとても良かった。タイガースのサリーなのだよな、と観終えてから変な感慨がわいた。
- 5月8日(月)
ミリオン座に『RENT』を観にゆく。歌のうまい役者が沢山出ている映画。ミミ役の女優が古い知り合いに少し似ているな、と思った。しかし誰に対しても感情移入がまるでできなかった。これは失敗作ではないのだろうか。アメリカではどうなのか知らないが、日本人には向いていない気がする。とある映画評論家が『ウエストサイドストーリー』以来、とまで褒めていたので、眉に唾をつけながら観に出かけたのだったが。その評論家の褒める作品を私が褒めたことがほとんどないのである。阿佐田哲也が全然当たらない予想屋が、どの目を捨てるのかに迷った際、役に立つ、とエッセイで書いていたが、どの映画を観ずにすまそうか、と考えるとき、その評論家の意見を常々とても参考にしているのであるから、観にゆくのが間違いであることは当然である。
- 5月7日(日)
詩の題名だけがわかっているのだが、誰の詩なのかもわからない、とのレファレンス。日外アソシエーツの文学綜覧シリーズから作者と掲載されている全集を確認し提供。知っている人は知っている明治期の新体詩であった。
ひどい雨の一日だったが、利用者はかなり多かった。
- 5月6日(土)
大学生が本の一覧表を出し、下線の引いてある本のうち二冊、どれでも良いから貸してください、とのこと。洋書があったり、特殊な出版社の本であったりするなかに岩波書店の本がまざっていて、それは確かあったはず、と検索すると、貸出中で延滞をしている。もう一冊も同じ返却期限で貸している。「きっと急ぐんですよね」と訊くと、「明後日までの宿題です。下線を引いてないのでも構いません」と言われるが、明らかに専門的な本ばかりである。「隣町の図書館でも調べてもらったのですが、なかったんです」と言う。町の図書館には、何かの間違いでもなければあるはずのない本のリストである。しかし、インターネットで探す、というようなことをそもそもしないのか。って、明後日の宿題用の資料を探そうとする学生に求めても無理かもしれない、と気をとりなおす。なんとか一冊閉架にあり、それを提供する。
古い資料のデータは引っ越す前に一括でアルバイトのひとにシートに記載してもらったものを、業者が入力したためもあって、誤りが多いのだが、書名、著者名あたりならばともかく、不可解な分類で、閉架に入った資料となると探すのに技が必要となる。十年以上図書館で働く司書二人が手こずっていたのだが、私がヒントを与えて解決。無事資料を出してくることができた。こんなときはうれしい気がするのだが、直しておいていないのがそもそもまずいのである。本が多いといろいろなことが起きる。
さすがに土曜日、ばたばたと過ぎていったのであった。
- 5月5日(金)
こんな感じの絵か写真がついている本はありますか、といった質問はなかなか難しい。それらしいものを提供するのだが、利用者のイメージと異なったり。しかし今日の場合は、割と良い感じでやりとりが進んだ。
高校生の課題用の図書一覧かな、と思っていたら大学生のだった。ふうむ。数年前からそういえばそんな風になりつつあるな、と思い出した。
- 5月4日(木)
5月の連休期間はほかの平日とあまり変わらないくらいの利用状況である。視聴覚資料の整理をする。
- 5月3日(水)
休みをとる。『美しき運命の傷痕』を観る。キェシロフスキ監督の遺稿を元にダニス・タノビッチ監督が撮った作品。エマニュエル・ベアールを目的にいったわけだが、ノーメイクで皺がいっぱいのベアールのアップにぞくぞく。好きなひとであれば皺も好きかもしれない、などと思ったり。きれいな映像、おっかない話。女のひとは実に恐ろしい、といまさらながらにしみじみ思ったのでありました。
夜、豊田スタジアムへ。横浜Fマリノス戦。DFの古賀正紘がFW。下がり目のMF山口慶が2列目という面白い布陣。点がなかなか取れず、後半の終わり近くに1点取られたときには終わってしまったかと思ったが、玉田に替わった鴨川がファールをもらい、本田のFKに古賀が合わせ同点。その後も攻めにゆく姿勢が良かった。引き分けではあったが、こういう試合をしてくれるのであれば期待が持てると思った私。
- 5月2日(火)
休み明けの朝はばたばた。近くの町の図書館から、「来館者が相互貸借の本です、と言ってお宅の本を返したのですが、そうではないようなのでお確かめください」との電話。間違いなくうちの館から個人へ貸している。その人に連絡をする。思い違いなのだろうけれども、ささいな事柄がなかなか煩雑な作業を生み出したりするのであった。世の中のすべてはこんな感じで成り立っているのかもしれない、などと思う。
利用者多し。
- 5月1日(月)
朝、鍼灸院にゆく。混んでいる。「膝が三日ほど前からとても痛い。多分ずれていると思います」と言うと、「ずれてないよ。はまっている」と言われる。昨晩立ち上がったときにはまったのだろうか。はて。そう言われてみると昨日や一昨日のような痛みはない。
ジム・ジャームッシュ監督の『ブロークン・フラワーズ』を観る。面白いし、映像もきれいだが、私の好みではなかった。
- 4月30日(日)
さすがに日曜であった。ばたばたしていた。膝の骨がこのところ時折ずれる。大腿部の筋肉が落ちたせいとのことなのだが、これがとてつもなく痛い。昨日からどうもずれている。書架案内、閉架の階段の上り下りがつらい。レファレンス多し。知らない本が世の中にはいっぱいあるな、と改めて実感した。
私にとっての夜中(10時には大抵寝ている)に電話が鳴り、切れる。誰からなのか、ナンバーディスプレイをつける気がないのでわからない。ひところ頻繁にポルトガル語の間違い電話がかかってきていたが、最近は電話自体がめったに鳴らない。たまに鳴ると訃報や親族の事故であったりする。電話が鳴るとうれしいような怖いような焦るような懐かしいような不思議な気持ちになる。立ち上がったとき、膝が変な感じになった。二三歩歩いたら切れた。
- 4月29日(土)
新着資料に分類を付す作業と、『としょかんだより』に載せる本を選ぶ作業。カウンター業務。レファレンス沢山、登録者多数。郷土資料についてのかなり専門的な質問があったりもした。体力が落ちていることを痛感する昨今である。
- 4月28日(金)
休みであった。第三書館の『ザ・俳句歳時記』に拙句が載っていると友人が教えてくれたのでインターネット書店へ注文したのが朝、届く。一般の人の現代俳句を沢山載せるという方針で編まれた歳時記。編者に小澤實先生のお名前があった。「澤」の会員のひとの句が載っている。探すと確かに一句見つかった。記憶にある、自分でも好きな句。いつ作ったのだったか、と調べてみると2002年6月。この時期の様々な事柄を思い出して午前中を過ごす。
伏見のミリオン座へ初めてゆく。現在ハートランドになった元のミリオン座へはよく行ったものだが。押井守の『立喰師列伝』を観る。ブローティガンの『バビロンを夢見て』を下敷きにした『・・・ランドを夢見て』のところは好きだったが、こんなに絵が動かなくて科白ばかりでは困るな、と思った。
電気文化会館の山下洋輔さんのソロライブにゆく。ラストのラヴェルのボレロがものすごく、アンコールの『枯葉』はもっとすごかった。背中がぞくぞくする演奏。トリオなどは観ているのだが、ソロライブを観るのは15年ぶり。電脳筒井線の最中に観たきりである。時の流れは早いなと感じる。
- 4月27日(木)
市民の意識を高める、といったような啓蒙的役割を図書館が担うべき、とされていた時期があったはずだが、そういう時期は過ぎたのであろうか。本来このようにあってほしい、とされる「市民モデル」があり、そうした市民を育成するための社会教育施設としての図書館は滅びたのかもしれない。そんなことをなぜかふと思った。
共謀罪法案というのはいくらでもギャグにできるような法案であるが、本当に通すつもりなのだな。治安維持法よりひどいことになる気がするけれど、みんなそれで良いのだろうか。例えば酔っぱらって海辺の堤防で立小便をしている友達に後ろから二人の友達が、「突き落としちゃおうか」などとふざけて言っている後ろをお巡りさんが通りかかったら、話した内容により二人は捕まるのですな。懲役か禁固ですぜ。ま、立小便も犯罪ですが。冗談で犯罪をおかすような事柄を口にすることは誰しもしばしばあり、私などはろくな冗談を言わないのですから、この法が通るとそのうち捕まりそうな予感にうちふるえてしまうのですが、誰もそんなに怖くないのでありましょうか。太った被告が容疑否認のまま痩せて保釈されたのがそんなに大事な話なのかな。今度ややこしい法案を通すときとか、自分たちに不都合なことが起きるときにはまた彼を捕まえるのではなかろうか、そんで次のときにはまた保釈したりするの。耐震偽装のひとたちも使えますな。などと穿った見方をしてしまうのは私だけかな。マスコミは何がそんなに恐ろしいのだろうか。こわいもの知らずの堅気じゃないような人達がマスコミで働いているとばかり思っていたのだけれどもどうやらそういう時代は過ぎたみたいです。
- 4月26日(水)
視聴覚資料の入力作業をする。あまりに久々でかなりいろいろなことを忘れてしまっていた私であった。利用者多し。レファレンスが沢山。郷土の歴史についての調べものを後輩が受けていた。よく訊かれる事柄なのであるで基本的な資料を提供していたあと、ほかに何かなかったかを私に尋ねる。ここ十年ほどで新しい資料がいくつか出ていることを指摘。また、利用者はかなり詳しく調べたかったようなので、そこに載っている参考文献もご覧になってはいかがか、他市の資料館、その近くの図書館にこれらの資料があります、と伝える。何をどう追うか、キーワードをどう捉えるか、といったあたりについて後ほど後輩に話をする。自分で雑誌論文を使った調べものをする、という習慣があると良いのだが、なかなかそうした生活をしている司書はいなかったりする。
- 4月25日(火)
朝、膝と腰が痛かったので鍼灸院に寄り、お灸を据えてもらう。遅番なので始業時間にはまだ余裕があった。
近隣の図書館に勤めるXさんが来館。彼はさらに遅い出勤シフトとのこと。開館時間が長くなっている館が多い。しかし職員は減っているとか。図書館七年目の彼はなぜか私を気に入っているらしい。私はしかし図書館で何をしてきたのかな、と時折考える。一つだけ言えるのは、起きているあいだの多くの時間、頭のなかのどこかで図書館について考えていた、ということだ。私がしているこれは正しいのであろうか、私がしようとしているそれは正しいことなのか、と、そんな問いを毎日繰り返していた。そんなふうに過ごしてきたのだけれど、方向が正しかったのか、してきたことが正しかったのかは実のところよくわからない。利用者が欲している本を探したり、調べようとしている事柄をつきとめるための手助けをしてきたことは確かではあるが。Xさんが、「図書館を利用しないひとが図書館に異動してくることがしばしばある」と言っていたのに対し、「実は私も図書館利用者ではないのです」と答えた。読む本は買う。新しい本は新刊本屋で、古い本は古本屋で買う。借りると返すのが面倒なのだ。買った本でないとなんとなく読んだ気がしない。また、選書の際、自分が読みたい本を選んでしまいそうな怖さもある。そんなわけでめったに図書館で本を借りることがない。雑誌を複写したり、参考資料で調べものはするが、積極的な貸借利用者であったことはない。良き利用者であるどころか、最初から利用者でなく、町の図書館がなくてもさして困らない。インターネットが普及してからは調べものが楽になり、さらに図書館を利用することが減った。図書館を離れた三年間に利用したのは雑誌を複写に出かけたのと、数ページだけ見たい高額な図書の相互貸借くらいであった。多くの一般利用者の気持ちは実のところよくわからない。貸出中心の、リクエスト予約、それ以外、それ以上の要求もできるだけ受け入れてゆく方向で三十年ほど公共図書館は進んできたわけだけれど、多くの人の目から見るとそこに専門職が必要であるとすぐにはわからない状態になっているようにも感じるのであるが、はて、これからどうなってゆくのが正しいのか、司書はよくよく考えながら動いてゆかねばならない時期なのではあるまいか、なんてことをふと思った。Xさんは元々司書資格を持った行政職のひとで、図書館で働くのが大好きなのだけれど、そろそろ異動がある頃であろう、と思っているとのことであった。
- 4月23日(日)
日曜日の割に空いていた。久々のお客さん、というか、三年ぶりにお目にかかる方が多く、「お、戻ってきたね。お久しぶり、またよろしく」とか、「どこ行ってたの。またいろいろ調べてね」などと言われる。うれしいことである。私がするべきは本と人を結びつけるための仕事だ、と再認識。三年の間に定年退職をなさり、読書三昧の日々を送っていらっしゃるひともいた。うらやましい限りである。
難解なレファレンスも、すぐに答えられるレファレンスもあった。閉架の図書の利用多し。
- 4月22日(土)
さすがに土曜日である。なかなかの混雑。著名人の有名な言葉の読みについて電話にて質問があった。朗読を録音する作業のためとのこと。Webでその言葉について調べると、仮名で載っているのは一件のみ、個人が作ったページであった。質問者ご本人もその読みで聞いたことがあるとのこと、音でいくと七、七であるし、私もそう耳にした記憶があるので、おそらくは良いはずですが、しっかり確認するためには二三冊の本でルビが振ってあるのを見つけるべきでしょう。簡単には探せないとは思いますが、と答える。読み方についての質問はかなり厄介なのである。
- 4月21日(金)
金曜日は比較的利用者が少ない。開架と閉架の整理を少しする。発注業務、カウンター業務。腰痛がひどい。
町田康の短篇集『浄土』に『自分の群像』という作品がある。似田という登場人物の造型が見事。『群像』に載ったとき読んで爆笑した記憶。単行本で読み返すと違う感覚。この作品集は傑作揃いなので未読のひとにはお勧めである。
- 4月20日(木)
休みの日。『かもめ食堂』を観る。『バーバー吉野』の荻上直子監督。いやはや面白い。映像がきれい。もたいまさこがすさまじい存在感。フィンランドに行ってみたくなった。
- 4月19日(水)
とある名作文学作品の、字が大きなのが良いのだけれど、との問い合わせ。以前幾度も読んだのだけれど、目が悪くなったので、できるだけ大きな字で印刷されたのが読みたい、というお話。総合的な文学全集は大抵字が小さい。昔の新潮文庫は字が小さい。最近の岩波文庫はかなり大きくなっているので、まずそれを見ていただくが、もう少し大きいのはないか、と問われ、個人全集が数年前に出ていたことを思い出す。出してみるとかなり大きい。新訳で読みやすくなってはいるが、以前の訳は高名な文学者のもの。その違いについて説明をしたのち、個人全集を貸し出す。個人全集に最初から行き当たれなくなっているのがブランク、というものである。不慣れなひとがこのレファレンスにあたったとき、どんな段取りで探しはじめ、どのような回答をするであろうか、とふと想像をした。
- 4月18日(火)
休み明けにはブックポストへの返却が多い。返却時のスキャンミスに気をつけないと、次にすぐ利用者が借りないので、貸出券をなぞらぬため、残冊数がわからず、本が棚に戻っているのに電算処理が終わっていない場合がありうる。確認をしっかりせねばならない。図書館の作業には神経をつかうものが多く、また、あまり神経質になりすぎると進まなくなる仕事もあり、様々で面白い。カウンター業務は楽しく、発注業務もうれしい。今日も慌ただしく一日が過ぎた。良いことである。
- 4月16日(日)
さすがに日曜日である。ひとだらけ。貸出冊数は4000冊を超えた。登録者も貸出券紛失届も多いし、リクエスト予約も多い。帰るころにはよれよれになった私。
- 4月15日(土)
カウンターに五時間半入った。古い新聞の複写申請が二件。マイクロフィルムリーダーではうまくとれず、原紙(我が館には縮刷版がない)から撮らねばならなかった。新聞は酸性紙なので、ぼろぼろになりかけており、なかなか大変であった。さすがに土曜日だけあって、ばたばたしていた。歳のせいで身体がついていけなくなっている。
- 4月14日(金)
ある詩が入っている本の所蔵調査が電話である。ほかの町のひと。近所の図書館へ行かれたそうだが、そこになかったとのこと。オリジナルの詩集はなくとも古い詩人であるので、日外アソエーツの文学綜覧シリーズがあれば、どの全集にはいっているかはわかるし、そうであれば所蔵館を調べて案内するか相互借り受けをすれば良いであろうに、と思う。このごろはレファレンスツールは充実しているし、インターネットもある。司書がいるはずの図書館での対応であるのにな、と残念に思ったのだが、私の勤務する館でもこんなケースがあったりするかもしれない。職員からすれば多くの利用者のひとりであるが、利用者からすれば、図書館員ならば助けてくれるであろう、と考えているのだ、という当然のことを忘れてはならない。
前の仕事場の歓送迎会。かなり特殊な仕事をした三年間であったな、と振り返ったりした私。図書館の仕事も特殊ではあるが。
- 4月13日(木)
慌ただしいのが図書館の仕事である、としみじみ思う。新刊を選んだり、閉架へ異動する図書を選んだり。耳のご不自由な方からの難しいレファレンス。筆談をする。私は筆談を好きだな、と思い出す。
- 4月12日(水)
貸出冊数が3900冊を超えた。土日並である。ばたばた。図書を分類したり、閉架の図書の除籍するのを選んだり、コンピューター屋さんが来たり、受付に入ったりしているうちに一日が過ぎた。図書館の仕事は慌ただしく、様々なことを考えなくても時が流れてゆく。
黒木和雄が死んだ。彼の映画をまだまだ観たかった。ご冥福をお祈りします。
- 4月10日(月)
図書館員日記には図書館でのこと、図書館についてのことのみにし、私生活のことをあまり書かずにおこうと思っていたのだが、今日観た映画が随分良かったので書く。『プロデューサーズ』はメル・ブルックスが脚本を書き、監督をした1968年の映画であり、2001年にブロードウェイで舞台化されトニー賞を沢山得た。今回は舞台での演出、振付をしたスーザン・ストローマンが監督をしたのであるが、いやはやとてつもなく面白い映画であった。ミュージカル映画が好きなひとは観ないと損である。コメディが好きなひとは観ないといけない。しかしユダヤ人というのはなんとも偉大であるな、としみじみ思った。あれだけのことをされた歴史があるのに、茶化して笑ってしまうのである。東洋人はその点真面目なのだなあ。笑ってもらえれば反省もし、関係を修復したりもできるであろうに、などと、そんなことを考えたのは観終えて数時間経ってから。最初の一時間くらいは涙が出そうなくらい笑い転げたのだが、ほかのお客さんがあまり笑っていないので声を出せずにいて大変苦しかったのだった。鳩につけた名前でこんなに笑えるとは思えなかった。エンド・ロールが出てきた途端に帰ってしまったひとが多かったが、おしまいまで帰ってはいけない。映画館は明るくなってから席を立たないと損をする場合がしばしばあるのである。
古い図書館員日記を少し読みかえしていたら、なんと過激なことを書いているのであろうな、と呆れた。落ち着いて眺めるとこいつはなんともヤな奴である。いわゆる世間の鼻つまみ者だな。いつか編集して「図書館員の穏やかな日々」とかそんなタイトルに変えようかな、とふと考えたりもした。
- 4月7日(金)
閉架がいっぱいである。三年前にもいっぱいであったのだから、もっといっぱいになっているのは当たり前であるが、かなり除籍作業も進めてくれていたようである。開架から閉架への異動も大変だが、除籍はもっとずっと難しいのは言うまでもない。図書館からその本がなくなるのだ。県が通函を回すようにしてくれたおかげで相互貸借が簡単になったとは言うものの、しばしば利用される図書や、古典と言われる資料は自館にあったほうが良い。ともあれぼちぼちと除籍図書選びなどもしてゆかねばならないのであった
- 4月6日(木)
予約の電話をかける。徐々に、というか、かなり以前から感じていることがある。予約リクエストの本の多くはベストセラー、読み物、レシピ、ガイドブックである。少し大きな本屋さんにいけばすぐにある本たち。図書館の存在意義、司書の存在意義をふと考える私。「市民の図書館」以前の図書館が良かったとは思わない。しかし、読書の水準、読書指導、といったようなことを念頭におかずに図書館運営をしていれば、図書館が無料貸本屋と化すのは必然ではあるまいか。我が国の出版状況、経済状態の変化と図書館は無縁ではなかったのにもかかわらず、多くのひとに利用される図書館、という側面だけを重視した活動を展開してきたがために、司書がいてもいなくてもそんなに違わないのではないの、と言われるような事態になってしまったことを反省すべきではなかろうか、と私は思うのである。多くの中小公共図書館の司書がしている八割くらいの仕事は無料貸本屋と言われてもしかたがなくはないだろうか。そしてインターネットの普及により、レファレンスの仕事は減り、図書の検索ができる利用者が増えている。司書のできること、すべきことを見直さねばいけない時期はとっくに過ぎてしまった、と自らへの反省をこめて思う。
- 4月5日(水)
図書館の仕事をしていて強く感じるのは老化である。書架整理をしていると膝が痛い腰が痛い。固有名詞が出てこない。以前数年間行っていた仕事なのに、はて、これはいったいどうするのであったか、とすっかり忘れている。しばらく経つとなんとかなってゆくのであろうか。
歓送迎会があった。挨拶をせねばならぬことをすっかり忘れていた。書架案内をしていたとき頭に浮かんだ『マルドロールの歌』の有名な一節、「解剖台の上のミシンと蝙蝠傘の偶然の出会いのように美しい」を使い、ランガナタンの第五法則「図書館は成長する有機体である」を引き、「成長する有機体である図書館での利用者と図書との出会いは解剖台の上のミシンとこうもり傘が偶然出会う確率とさして変わらない。その美しい出会いの手助けをする仕事をみなさんとともにすることができるのを幸せに思う」といったようなかっこいいような、わけのわからぬ話をしてお茶をにごした。
- 4月4日(火)
返却窓口に二時間半入る。春休なので利用者が多い。いろいろなことを忘れていてスリリングであったが、臨時職員さんに教えてもらいながら仕事をなんとかこなしたのであった。なんというか失語症的な感じになったりもして、変だった。やや難しいレファレンスが一件。楽しい。
- 4月3日(月)
西村賢太の『どうで死ぬ身のひと踊り』を読む。すさまじい私小説集。主人公はめちゃめちゃなひとであるが、逆上する瞬間の感覚が私によくわかる気がしてそれがなんだか怖かった。私小説というジャンルは車谷長吉が書かなくなったため終わってしまうのかな、と思っていたが、こういう人が出てくるとは。
- 4月2日(日)
貸出、返却、レファレンス業務を少しする。楽しい。書架整理。体力が落ちているので少し苦しい。
- 4月1日(土)
図書館に戻った。素直にうれしい。図書館をとりまく環境はかなり良くなくなってきているが、できうる仕事をしてゆこうと思う。
としょかんだより作成の手伝いをする。3月に購入した図書のリストを見ながらどれを載せるかを選ぶ。選書がしっかりと行われているなあ、とリストを眺めて感じる。楽しい作業である。
延滞利用者への督促電話をかける。楽しい。伝言の場合はプライヴァシーに留意せねばならず、多少の専門性が必要な作業。思えば個人情報保護は図書館においてかなり昔から意識的に行われてきている。時代が図書館のプライヴァシーについての感覚においついてきたようにも思える。ほかの意図がありそうな法律なのが難だが。
[ 目次に戻る ] [ 表紙に戻る ] [ いちばん上 ]