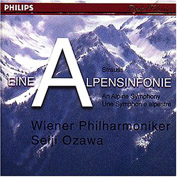R.シュトラウス:アルプス交響曲

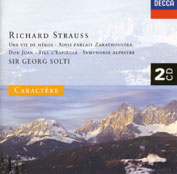

◆ コンヴィチュニー/バイエルン州立歌劇場管弦楽団 1952年
『サロメ』、『ばらの騎士』など傑作オペラを世に送り出した後に書かれたこの『アルプス交響曲』を演奏するのにもっとも相応しいのは、常日頃R.シュトラウスのオペラを演奏している歌劇場のオーケストラのはず・・・。
この演奏、冒頭の「日の出」ではやや雑然としたところがありますが(まるで出かける直前にバタバタする我が家の連中みたい・・)、徐々に落ち着きを見せ始め、その自信に満ちた弾き方で山登りの情景を描いていきます。とりわけ弦楽器の力強さ、弓を弦に密着させ密度の濃い音を聴かせる様は昨今の軽量で芯の細い演奏が蔓延している音楽界に辟易している方にはお薦めです。コンヴィチュニーはシュトラウスの細かい指示を横目で睨みつつ、適当に流しながら無理のないテンポで音符を紡いでいきます。譜面に忠実なあまり極端なピアニッシモを強調する演奏が多い今日この頃ですが、コンヴィチュニーはその辺もいちいち構わず自然体を維持します。
頂上周辺で金管が少々息切れ気味であったり、木管が不鮮明な箇所が随所にあったりしますが、決めるところは外さず一定の水準を保っています。録音の古さが大きなハンディになりがちな曲ですがそれを補うだけの充実したシュトラウスの音を聞かせてくれる演奏です。
◆ ショルティ/バイエルン放送交響楽団 1979年
何故シカゴ交響楽団ではなく、バイエルン放送響と録音したのか不思議な気がします。しかもショルティにとってスタジオ録音としては最初でかつ唯一の『アルプス交響曲』になってしまいました。しかし、初顔合わせの割には、ショルティの意図にかなりの精度で応えている印象を受けます。
ただ、それにしても速い・・・。いくら早足の人でも険しい山道をこんなスピードで駆け上がることはないでしょうし、はやる気持ちを抑えて、道すがら森や小川、滝、花咲く野原、牧場などの風景をわざわざ丹念に描き進めたシュトラウスの意図が台無しになってしまうと思うのですが・・。にも拘らずその速いテンポをものともせずに食い下がるバイエルンのオーケストラには脱帽です。無機的にならず、フレーズの節々や終わりにごく自然なテンポの緩みを加えることを決して忘れないところは流石と言えます。
残念なのは、シュトラウスがスコアに記した麓から頂上までの往復路における様々な風景や出来事と音楽がショルティの演奏と一致しないところがあるような気がします。大きなクライマックスであるはずの頂上での音楽が期待はずれのままあっさり通り過ぎてしまったり、下山中に遭遇する嵐のシーンでの畏怖・恐怖感が希薄で浮かれたお祭り騒ぎのように感じられるところが気になります。シュトラウス自身が自作を指揮した演奏では確かに速いテンポを取るケースが多いため、ショルティはそれに倣ったとも言えますし、或いは描写音楽というより、交響曲という純音楽という側面を強調したかったのかもしれません。
◆ カラヤン/ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1980年
私事で恐縮ですが、R.シュトラウスに入れ込んでいた筆者がLPでの購入を躊躇していたのがこの曲(と『英雄の生涯』)でして、初めてCDプレーヤーを買った後、しばらくしてようやくCD化されたのを満を持して購入したのがこの演奏の輸入盤CDでした。どうしても頂上の前後でLPをひっくり返す気になれなかったからで、曲の最初から最後まで席を立たずに途切れなく聴けるなんてなんと至福のひとときか、と思ったものでした。しかしこのCD、トラックはひとつしかありません(現在発売されているCDはトラックに切ってあるかもしれませんが)。
最初の ff となる「日の出」でややバランスを失って主旋律がかき消される箇所がありますが、気合十分で荒ぶるベルリンフィルをカラヤンが手綱を絞ってコントロールしようとしているみたいです。「登り道」に入ると、ベルリンフィルの低弦がパワー全開でズンズンと登り始めます。その推進力は、聴き手をもわくわくした気分にさせてくれます。「森の中へ」に入っても音楽の流れは途切れず、はやる気持ちを抑えられないといった趣で、ちょっと立ち止まって風景でも楽しもう、ということはさらさらありません。弦楽器は終始厚みのある、しかも引き締まった音でどんな難所でも動じることなく充実した演奏を展開します。
「林で道に迷う」あたりのベルリンフィルの迫力は満点で、その自信に満ちた演奏ぶりからは「迷い」のかけらも感じられません。頂上が近づいたあたり、オーボエのソロを支える弦楽器のトレモロの精緻さと響きは絶品です。いよいよ迎えた頂上では、金管の奥行きのあるサウンドと力のこもった弦楽器の一瞬たりとも弛緩しない推進力により、壮大な世界を眼前に展開させてくれます。何度か音の洪水に溺れそうになることがありますが、カラヤンは手綱を緩めることなく先へ歩みを進めていきます。続く「嵐」で、予想に反してベルリンフィルは暴れまわることをせず、クリアなサウンドを維持しつつ冷静に「嵐」を表現します。もちろん立派な「嵐」なのですが、どこか覚めたところがあるように思えます。
沈みゆく太陽に向かってヴァイオリンの何かに取り憑かれたような激情の吐露を「日没」で聴かせると、静寂な「終末」へと音楽は大きく舵を切られていきます。絶妙な音量で降ってくるオルガンから先は、カラヤンはひたすら音符だけに語らせようとしているのか、演奏される楽器が何であるかを聴き手に意識させないようなニュートラルな音色を出させ、それに微かに流れるオルガンの和音を絡めていきます。カラヤンはまさに、ここから最後の音までの約8分間を、この曲のクライマックスとして設計してしたのに違いありません。淡々としかもフレージングを長く維持させ、敬虔な世界を繰り広げていきます。ワーグナーの『さまよえるオランダ人』の引用で山場を迎える箇所でも、なだらか起伏だけでさらりと流していくあたり、この終曲の解釈として余人の真似できるものではありません。名演です。
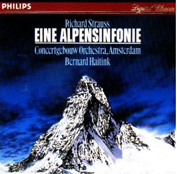
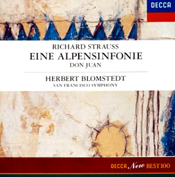

◆ ハイティンク/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 1985年
コンセルトヘボウ管弦楽団は、シュトラウスがこの曲をベルリンで世界初演した1915年の翌年に早くもメンゲルベルクの指揮でオランダ初演を果たしました。さらに一週間後にはシュトラウス自身の指揮で再演されています。その割に録音といえばこのハイティンクが初めてらしく、2回目の録音も2007年のヤンソンスまで待たないとありません。決してこの曲が向かないオケとは思わないのですが・・・。
曲の冒頭から相変わらずハイティンクらしい中庸のテンポで、肩の力が抜けた自然な音楽作りが光っています。精神性を追求した深刻な曲だとこういった姿勢ではたぶん物足らない演奏になるでしょう。この曲に限らずシュトラウスの作品は譜面そのものに演奏者の野心やあざとさを寄せ付けないところがあるだけに、ハイティンクの朴訥さがプラスになっていい効果を挙げているのかもしれません。
「森に入って」の後半はテンポを思いっきり落としてたっぷりヴァイオリンを歌わせるあたり、ハイティンクにしては随分大胆な印象を受けますが、聴き手には実に心地よい安堵感を与えてくれます。その後の混沌とした箇所では、録音の不鮮明さはやむを得ないとして、各楽器のバランスは見事で、しかも見通しのいい音楽を聴かせます。「頂上にて」の直前のオーボエのソロはその明るくのびのある音色と落ち着いたフレージングには思わず立ち止まって聴きほれてしまいます。これにつられてか、頂上での金管もまろやかで幸福感に満ちたサウンドを聴かせてくれます。ここには威圧感も征服感も、さらには絶叫もありません。
◆ ブロムシュテット/サンフランスコ交響楽団 1988年
全曲を通じて緩急の幅が多い演奏で、明るい音色で比較的楽観的な登山になっています。生み出されてくる音楽は常に生気に満ち溢れ、どんな難所も完璧に近い演奏をしているにもかかわらず、歌心を忘れないところが単なる描写音楽からこの演奏は救っています。
「森に入って」の後半でヴァイオリンが歌うところでは今にも止まりそうな遅いテンポになり、「花咲く草原」では一転して活き活きとした気分でクライマーをせきたてています。「頂上」に到達してからの一連の金管の強奏においても決して一線を越えない冷静さを維持し、「嵐」においては、クリアなサウンドの中を各パートの驚くほどの正確無比なアンサンブルを披露します。烈しい「嵐」におののくというよりは、シュトラウスの見事なオーケストレーションに唖然とさせられるシーンです。
「日没」では金管の均質で透明感のある響きに弦楽器が熱のある演奏を繰り広げます。「終末」における木管の一糸乱れぬ完璧さに感心している間もなく、奏者の息遣いをも伝わってくるヴァイオリンの高音部での素晴らしい演奏が繰り広げられ、聴き手に忘れがたい印象を残します。名演です。
◆ アシュケナージ/クリーヴランド管弦楽団 1988年
アシュケナージの、失礼な言い方ですが、くねくねした指揮姿から想像される音楽がそのままに聴こえてくる演奏です。どの音も鋭角的なところはなく、角が取れてツルンとしていながらちゃんと中身が詰まったサウンドを聴かせます。
テンポは総じて遅めでいて、登りでは音楽の流れや推進力に不足はありません。途中、技術的に困難な箇所など通常は混沌としがちなところも、クリアなサウンドで複数の楽器の絡み合う様などもくっきりと聴かせます。それでいて威圧的でないところに好感が持てます。細かい音符への配慮や細部の表現への拘りはあまりありませんが、結果としてはストーリー通りの音楽になっている、なんだか不思議な演奏です。鳥の囀りは実にリアルに再現している割には、起伏に富んだアルプス登山の様々な視覚的イメージが次々に目に浮かぶかというとそれ程ではありません。
「嵐」の後の「終末」、ヴァイオリンが高音部で綿々と旋律を紡ぐところでアシュケナージは極めて遅いテンポを採用しています。宗教的な恍惚感を出そうとしているでしょうが、あまりに遅すぎ、しかも起伏がなさ過ぎるために(シュトラスはスコアにほんの少しダイナミクスの変化を指示しています)、どこか居心地の悪さを憶えます。



◆ バレンボイム/シカゴ交響楽団 1992年
いよいよスーパーオーケストラの登場です。バレンボイムはこの時期集中してシュトラウスの交響詩をシカゴ響で録音しています。これらのCDを手にとって最初に驚いたのは、添付されているブックレットを開くと、トラック紹介の次のページにオーケストラの団員の名簿が掲載されていることです。しかも、その次にバレンボイム自身の文章で、どんなにこのオーケストラが素晴らしいかが書かれています。CDジャケットは聳え立つアルプスの威容ではなく、シンフォニーホールの客席でポーズを取る赤いジャケットを着込んだバレンボイムの写真です。まるで、シュトラウスの音楽より、俺達の演奏を聴いてくれと言わんばかりです。
さて演奏ですが、まさに『完璧』の一言です。スコアに書かれている音符や標記をこれほど忠実にかつ余すところなく読み取り、オーケストラが完璧に再現した演奏は他にはないでしょう。もちろん、譜面に書かれていない細かな味付けも忘れてはいません。しかも、管楽器のソロの技術的な完成度の高さだけでなく、聴き手を唸らせる旨さを存分に発揮しているところが凄いところです。
メリハリを効かせつつも決してパワーを全開させず余裕でクリアなサウンドを聴かせる金管、どんな込み入った箇所でもアンサンブルを崩さず常に明瞭に音を粒立たせる木管、やや硬質ながら力まずして管楽器群に引けを取らない弦楽器と、オーケストラのバランスの良さはさすがです。あまりにシンフォニックでメカニカルな面が鮮やかすぎるために、そちらに気を取られてしまって、シュトラウスの描こうとした風景を見落とす(聴き落とす)かもしれません。
「森に入って」の後半にあるヴァイオリンの聴かせどころでは、暖かさとは正反対の透明でひんやりとした音色に少々がっかりさせられますが、その代わりにバレンボイムはスコアにはないテンポの微妙な揺らぎを与えることで、音楽に息遣いと色彩感を与えています。聴き手の期待をはぐらかしながらも思いがけないところにもっといい物を用意するなんて、これを意図的にやったとなると、とてつもない職人技ということになるでしょう。
頂上の直前で吹かれるオーボエのソロ(たぶん奏者はレイ・スティルでしょう)は、周りをすべて沈黙させ、時が止まるとはこのことを言う位の素晴らしい演奏です。頂上では決して爆発させず、クールでスリムな咆哮を聴かせます。譜面どおり演奏すればそれなりの効果が上がるように書くのがシュトラウス音楽の本質ですから、リズム、音程、アタック、勢い、バランス、気構え、音色、方向性、見通し、等等あらゆる要素が100%完璧に揃えば、他に余計な策を弄する必要はない、そのお手本と言える演奏です。
驚いたことに、下山中の「嵐」のシーンで活躍するウィンドマシーン(これが回り出すとオーケストラの音をすべて掻き消すことがよくあります。)がこの演奏ではあまり聴こえません。つまり、バレンボイムはウィンドマシーンの存在を聴き手にアピールした直後に音を極端に落として、シュトラウスが各楽器に書いた半音階の上下進行だけで風を描写しきっているのです。「日没」では、全体の表現としてはやや物足らない感じはあります。弦楽器が力を控えめにしているからなのですが、金管にもう少し色彩感があるとよかったかもしれません。しかし、オルガンのコラールからの静謐さや、高貴とさえも感じさせる音楽の運び方はその完成度において他の追随を許しません。続くホルンを含む木管のアンサンブルの完璧さ、ヴァイオリンの息の長い歌いは音楽の流れを途切らすことなく最後まで静かな時を刻んでいきます。アルプス登山の後にこんな立派で精神性の高いエンディングはやや大げさな感じは否めませんが、シュトラウスがこの曲の副題として、ニーチェの言葉による『アンチ・キリスト』を当初考えていたことを思い起こすと、バレンボイムのアプローチはわからないでもありません。名演です。
◆ マゼール/バイエルン放送交響楽団 1998年
「日の出」の後、小気味のいいテンポでわくわくした気分を良く表わしていて、「森に入って」まで一気に聴かせます。森の中では男性的な恰幅のよさと同時に肩の力を抜いた音楽運びが光ります。続くヴァイオリンの難所でも音楽の流れを損なうことなく見事に弾ききっています。その後の混沌としたところでは、一点も揺るがせにしないクリアでバランスの取れた音の洪水を憎らしいほどの余裕をもってさばいていきます。
「頂上」の前に吹かれるオーボエがやや恣意的に聞こえますが、空気の薄い頂上付近で足元がふらつく様子を描こうという心憎い演出なのかもしれません(・・そんなわけはないですよね。)。しかしマゼールにしては、これまでのところ、これといった彼お得意の遊びがないということは言えると思います(まるで心のどこかで期待しているようですが・・・。)。
「頂上」に達するとたっぷり時間をかけ、見事な一大パノラマを繰り広げてくれます。ここでのバイエルン放送響のアンサンブルは素晴らしく、スタンドプレーよりはオケ全体としてまとまりを目指していると言えます。下山が始まって「嵐」までの描写は緻密を極め、しかも来るべき災難に先立つ山の空気の移ろいを楽器間の絶妙なバランスと息遣いで描いていきます。「嵐」ではついに持てるパワーを炸裂させ、畏怖と恐怖を広大な空間すべてを使って表現していきます。とりわけ「嵐」の最後は圧巻で視覚に訴えるほどの強烈な印象を聴き手に与えてくれます。続く「日の出」ではヴァイオリンがめいっぱいの音量で張り詰めた緊張を絶やさずに弾きこみます。ヴァイオリン弾きでもあるマゼールの本領発揮といったところです。マぜールはこの曲のクライマックスを山頂ではなく、嵐を乗り切った後のこの部分に置いているのは間違いありません。「終末」以降のフルートをはじめとする木管の細かいニュアンスや動きの変化、相変わらず濃厚な弦楽器の歌いを楽しみながら曲を閉じます。名演です。
終わって気づいたのですが、マゼールは譜面に指定されている弦楽器のポルタメントをほとんど実行していませんでした。これまでのマゼールでは嬉々としてヒューンとやっていたはずなのに・・・。シュトラウス独特の落差のある下降と上降、極端な跳躍を伴う旋律において、音と音の間を開けたくないという理由から作曲家がポルタメントを書いたとすれば、開けないで演奏できれば不要になるとも言えます。或いは、シュトラウスはこの曲を作曲し始めた頃に死んだマーラーへのオマージュとしてポルタメントを書き加えたと解釈して、そのマーラー臭さを排除しようとしたのか。策士マゼールはどんな理由でポルタメントの使用を回避したのかを想像するのも楽しいものです。
◆ コルト/ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団 1998年
コルトの指揮する演奏ですと、どうしてもショパンを中心としたピアノ協奏曲の伴奏者というイメージで聴いてしまいます。しかしここでのコルトは意外にも、難曲を見通しよくさばき、交響曲らしい構成感を意識させる演奏に仕上げています。細部の正確さに捉われて曲全体の姿を見失ったり、スケールの小さな演奏になったりすることが多い曲ですが、シュトラウスの音楽の持つパワフルな側面を勢いと熱気を振りまきながら体当たりで表現 しようとする意気込みは大いに買いたいところです。
基本的に速めのテンポを採用し、音符が詰まっている箇所は一層加速して一気に聞かせようとしています。しかしシュトラウスは、時として音符のひとつひとつにさまざまな音価を与えて、ニュアンスの移り変わりを克明に表現する手腕に長けていて、例えばオペラにおいて
登場人物の瞬間瞬間の心の動きを伴奏のオーケストラが微細に表わすことがあります。アルプス交響曲では歌がないだけに、オーケストラの技量と設定したテンポからするとこの演奏ではシュトラウスの期待に応えることはかなり難しいかもしれません。「嵐」の後の「終末」では、高音域での繊細なヴァイオリンの長いフレーズを比較的大きめの音で弾かせていますが、この解釈はどうもしっくりきません。やはりスコア通り
p (ピアノ=弱音)で演奏すべきでしょう。