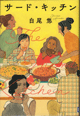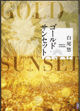| 「いまは、空しか見えない」 ★★☆ | |
|
2022年08月
|
生きること、それは闘いに他ならないということを改めて実感させられる連作ストーリィ。圧巻のデビュー作です。 山梨県の県立高校3年生の坂上智佳は、親に内緒で東京へ向かう長距離バスに乗り込みます。それなのに何と、自分とは正反対の位置にいる同級生=森本優亜が乗り込んできて智佳の隣席に座り込んでしまうとは。 智佳と優亜、各々ある決意を秘めた2人が、奇しくも東京へと同行することになったところから、この連作ストーリィは幕を開けます。 ・「夜を跳びこえて」:主人公は坂上智佳。その智佳の父親が、もう信じ難いほどの圧政者。たぶん、こうした人物の行動理由は、多分コンプレックスの裏返しなのでしょう。でもそうだとしても智佳には何の役立ちもせず。智佳にできる行動は何か。これがその第一歩なのでしょう。 ・「かなしい春を埋めに」:智佳の母親である雪子が主人公。何故、圧政的な夫の振る舞いに従うばかりなのか。彼女の切ないこれまでが語られます。そして少しの救いも。 ・「空のあの子」:大学卒業直前、3年間付き合った恋人から医学部の男に乗り換えられ立野翔馬はショックを引きずったまま。そんなとき、学内で“鉄仮面の処女”と噂される坂上智佳と出会い、思いも寄らぬその裏の顔を知ることになります。智佳との出会いは、翔馬にとってもひとつの成長に繋がっていく。 ・「さよなら苺畑」:名古屋にある伯母が営む美容院で美容師として働く優亜が主人公。高校時代に乱暴された過去から、今も男たちに対する恐怖感をぬぐえない。敬愛する先輩美容師は男性だが、ゲイだと判っているから安心していたのに・・・。 ・「黒い鳥飛んだ」:30歳間近になった智佳が主人公。実家を出て望んだ仕事に就いたといっても、現実は過酷な状況。高3時代と環境は違いながらも、いろいろな圧力に潰されそうになっている状況は変わらず。それでも・・・。 どの篇も閉塞感が拭えません。しかし、そこから抜け出すために必要なのは、結局自分が強くなるしかないのでしょう。 それでも少しずつ闘い続ける中で、同志と呼べる仲間との繋がりが生まれていることが何より貴重で、かつ嬉しいこと。 本書は、智佳たちの闘いの記であると同時に青春ストーリィと言って他なりません。お薦め。 夜を跳びこえて/かなしい春を埋めに/空のあの子/さよなら苺畑/黒い鳥飛んだ |