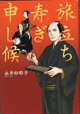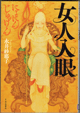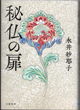| 「旅立ち寿ぎ(ことほぎ)申し候」 ★☆ (文庫改題・改稿:福を届けよ−日本橋紙問屋商い心得−) (新装版改題:旅立ち寿ぎ申し候) |
|
|
2016年03月 2025年02月
|
「大奥づとめ」が良かったのでとりあえずもう一冊読んでおこうと思い、読んだ次第です。 幕末という激動期が舞台。 日本橋の紙問屋・永岡屋の主人夫婦に気に入られた勘七は、夫婦の養子となり永岡屋を継ぐことに。 しかし、藩札という大きな商いを永岡屋に注文した小諸藩が、その藩内抗争から強引に注文をなかったことにしてしまう。 その結果、永岡屋は2千両もの負債を抱え込み、そのゴタゴタのために養父の善五郎は死去。永岡屋は一気に経営危機に瀕しますが、その重荷が店を引き継いで間もない勘七の双肩にかかってきます。 幕藩体制が揺るぎ、それまでの得意先だった武家を信用することができなくなるという難しい時期。そうした時代背景の中、故・善五郎の「人に福を届けるのが商人の道」という言葉を守り、商人の道を生き抜いた勘七の、苦闘の道のりを描いた物語。 背負わされた重荷を何度となく放り出したくなっても不思議ない苦境続き。それにもかかわらず、結局耐え抜いたのですから、当初は頼りない印象も受けましたが、勘七という人間は結局、かなりしぶとい人間だったのかもしれません。 本ストーリィは、決して勘七だけの物語ではなく、直次郎、紀之介、新三郎という4人の幼馴染による、時代物青春群像劇とも言えます。 また、主役の彼らに引けを取らず、脇役となる人物たちが魅力的であるところが、本作の良い処です。 勘七を叱咤し支える番頭の与七、気宇壮大な商人の浜口儀兵衛。そして何と言っても、最初弘前藩のご祐筆=松嶋さまとして出会い、その後墨筆硯問屋・松嶋屋の次女として再会したお京という女性の存在。 現代的なお京という女性の登場により俄然面白くなってきます。 時代の変化に応じて柔軟に行動を変えていくことも大事ですが、何のために生きるのかという柱を自分の中にしっかり持っていないとただ振り回されるだけ、と教えられた思いです。 序/1.門出/2.彷徨う/3.道しるべ/4.旅立ち/終 |