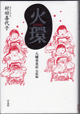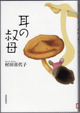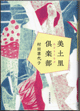| 「人の樹」 ★☆ | |
|
2022年12月
|
樹を擬人化して描く、樹、そして人との物語、という短篇集。 印象的なのは、樹を擬人化して主人公に仕立てたことから、悠久の時間を感じさせられること。 何しろ、人間に比べてはるかに長い時間を生きる樹木ですから、彼らが見る景色は、人間の見る景色とはかなり異なっています。 身体を動かさず、長い時間の視点から他のものを静かに眺めている、一生動き続ける人間の短い時間に比べて何やら魅せられるような気がします。 孤独に一本だけで立ち続ける樹、青年あるいは娘と樹との結婚、突然命を奪われたものの若い芽となって新しい人生を始める樹、人と樹の関わりを描いてユーモラスな篇、様々な樹の人生が描かれます。 前半は樹が主体。そして究極の樹と人間との関わりを描いた「生の森、死の森」を経て、後半は人間が主体となって樹との関わりを描くという構成。 本書を面白く読めるかどうかは好み次第と思いますが、私としては悠久の時間を少しなりとも味わえた本書、それなりに楽しめました。 ※好きな篇は、「孤独のレッスン」「四月の花婿」「リラの娘」「とむらいの木」「女たちのオークの木」といった辺り。 孤独のレッスン/花嫁の木/四月の花婿/大きな赤いトックリ/草原に並ぶもの/燃える木/リラの娘/さすらう松/逢いに来る男/みちのくの仏たち/生の森、死の森/とむらいの木/弔い花/女たちのオークの木/ナミブの奇想天外/青い蛍の木/ザワ、ザワ、ワサ、ワサ/深い夜の木 |