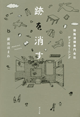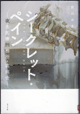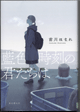| 1. | |
|
「跡を消す−特殊清掃専門会社 デッドモーニング−」 ★★ ポプラ社小説新人賞 |
|
|
2020年08月
|
孤独死や自殺、普通ではない死に方をしてしまった人間の遺した痕跡を、元通りになるよう清掃する、というのが副題にある“特殊清掃専門会社”というデッドモーニングの業務内容。 フリーターである主人公=浅井航(わたる)が小料理屋で知り合ったのは、笹川啓介という30代前半の人物。 その笹川の、一日で1万円のバイト代という言葉についひっかかり、航はそのバイトを引き受けるのですが、その仕事というのが何と特殊清掃だったとは・・・。 この特殊清掃、特別な思い、そして相当な覚悟がないと務まらない仕事だと思うのですが、同年代の廃棄物収集運搬業者である楓から「腑抜け」と罵倒されるような航が続けるに至ったのは、意地でしかなかった、と言ってよいでしょう。 本作は、極めて特殊な清掃業の苦労を描く“お仕事小説”であると同時に、その仕事や仲間たちとの関わりを通じて、航が<クラゲ>から<骨のあるクラゲ>へと成長していく青春成長ストーリィ。 そして、毎日喪服を着込み、会社内はいつも薄暗くしている笹川が抱えている闇の正体が明らかになり、航がそれに対峙せざるを得なくなっていく展開は、ちょっとサスペンス風のスリリングさを感じさせられます。 笹川や航を囲む、楓やデッドモーニングの事務職という望月、小料理屋「花瓶」の女将=悦子という周辺人物のキャラが立っているところも、本ストーリィに惹きつけられる理由。 さて、「跡を消す」という表題、その言葉が具体的に何を指すのか、そしてどういう意味を持つのか。読了後は、その言葉を噛み締めるように何度も繰り返してしまいます。 その言葉が表すもの、それは決して特殊な死に方をした人間だけに該当するものではなく、人間誰しもに共通することではないかと思うに至った次第です。 デビュー作でありながらこの出来の良さ、拍手喝采です。 1.青い月曜日/2.悲しみの回路/3.彼の欠片/4.私たちの合図/5.クラゲの骨/エピローグ |