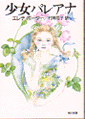|
|
|
|
|
2.パレアナの青春 3.スウ姉さん |
|
●「少女パレアナ」● ★★★ |
|
|
1962年07月 改版26刷
|
評判の高い少女小説だったのらしいですが、ここまで読まずに来ていました。角川文庫での復刊を機に読もうと思ったものです。 牧師だった父親が死に、独身で厳格な叔母パーレーにパレアナが引き取られるところから、この物語はスタートします。読み進むにつれ、“何にでも喜びをみつけるゲーム”を常に心がけているパレアナ・フィテアという、アンとはまた異なる少女像がはっきりとしてきます。表面だけみていると、単に楽観的、夢見がちな少女と思えますが、内心では寂しさに泣きながらも必死で喜びのゲームを続けようとする健気な少女、というのが真の姿です。そんな繊細さもちゃんと持ち合わせているところが、人の心を惹きつける魅力の理由でしょう。 パレアナには、アンの騒々しさ(比較して)と違い、ゆったりとした気分が感じられます。パレアナもまたおしゃべりということですが、読み限りではそんな風には感じられません。 |
|
●「パレアナの青春」● ★★ |
|
|
改版21刷
|
「パレアナを一服」、そんなところから続編は始まります。 さすがに、以前のような元気で屈託のないパレアナは見られません。それでも、カリウ夫人一家を交えてストーリィはにぎやかに進みます。 |
|
●「スウ姉さん」● ★★★ |
|
|
1965年12月 第39刷
|
「少女パレアナ」と比べると戸惑うくらいに印象が異なります。「パレアナ」には明るさや夢がありましたが、本作品には深刻なくらいの現実があります。 冒頭の作者の言葉に「全世界いたる所に、無数に散らばっている“スウ姉さんたち”に、この作品をささげます」「しんぼうづよく、不平をいわずに、わずらわしい毎日の雑用を果たしながら、はるか遠いかなたに自分たちをさしまねいている生きがいのある生活をながめているのが、それらのスウ姉さんたちです」とあります。 |