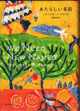|
「あたらしい名前」 ★★☆ PEN/ヘミングウェイ賞 |
|
|
2016年07月
|
新聞書評を見て読んでみようと思った一冊。 ジンバブエの少女ダーリンの故郷での暮らし、そして米国で働き暮らす叔母を頼って渡った米国での暮らしを描いた長編。 元々は「ブダペスト襲撃」という短編が高く評価され、そこから書き継がれて長編になったという経緯だそうです。 ジンバブエ出身の作家は未だ珍しいのではないかと思いますが、私としてはペティナ・ガッパ「イースタリーのエレジー」に続く2冊目。 前半、なにより印象的なことは、主人公や仲間たちの明るさ。 住んでいたホンモノの家をブルドーザーで破壊されたり(強制退去のため)、空腹を満たすため立派な家が建ち並ぶブダベスト地域でグァバの盗み食いをしたりと、生活は厳しいどころか悲惨とも感じられる状況であるだけになおのこと、主人公たちの明るさは眩しいくらいです。 しかし、葬儀に参加する傍らで、暴行を受けて半死半生にされた出来事まで子供たちが遊びにしてしまっている場面には、絶句する他ありません。 一方、米国に渡った後のダーリンの暮らしは、ジンバブエの頃からは一変。生活条件が向上したのは間違いありませんが、それがダーリンの幸せに繋がっているのか、という点は微妙。 故郷に帰ることもならず、結果的に故郷や両親を捨てた形となっている彼らの辛さが胸に迫ります。 本ストーリィの価値をきちんと掴もうとすれば、ジンバブエという国の歴史、国情を知ることが必要。大概のことは訳者のあとがきで知ることができますが、そうしたことを知るきっかけになるのも、海外作品を読む魅力です。 ジンバブエという国の内情、ジンバブエの人々を描くのに、少女の視点を以てしたところが本作の素晴らしいところです。 彼女たちの生き生きした姿が、いつまでも胸の中に残ります。 お薦め。 ブタペスト襲撃/山上のダーリン/国盗りゲーム/ほんとの変化/いかに彼らはあらわれたか/あたらしい名前/しーっ/ブラク・パワー/ほんとのこと/いかに彼らは出ていったか/デストロイド・ミシガン/結婚式/エンジェル/この動画には不快な表現が含まれています/クロスロード襲撃/いかに彼らは暮らしたか/あたしのアメリカ/壁に書く |