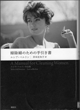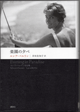| 「掃除婦のための手引き書−ルシア・ベルリン作品集−」 ★★★ 原題:"A Manual for Cleaning Women Selected Stories Lucia Berlin" 訳:岸本佐知子 |
|
|
2019年07月 2022年03月
|
2004年の逝去から10年後に出版されるいなやベストセラーになったという短編集“A Manual for Cleaning Women”(43篇収録)から、訳者の岸本さんが選りすぐった24篇を収録した一冊。 だいぶ前から読もうと思っていたものの、図書館の順番待ちにより今になったものですが、読めたことを幸運に思う作品の一つ。 ベルリンの作品は皆、本人の実体験に基づいて書かれたものばかりとのことですが、鉱山町に住んだ幼少時代、難物の祖父母と暮らしたテキサス時代、お嬢様として過ごした南米チリ時代、4人の息子を育てたシングルマザーの頃、アルコール中毒に苦しんだ頃等々と、その変遷ぶりは一人の人間として驚くばかり。 そして、それらがどの作品にも反映されているのですから、これはもう凄い、その身近なリアル感に圧倒されます。 ベルリン作品の魅力は、研ぎ澄まされたリアルな現実に、哀感と同時にユーモアが混じり合って存在している処。 現実の物語は、架空の物語を安々と凌駕する、そう感じさせられます。もっともフィクション部分も多々あるようですが。 「掃除婦のための手引き書」「わたしの騎手」「どうにもならない」の3篇が何と言っても圧巻! そして、癌のため余命僅かとなった妹サリーに寄り添う2篇も、胸に多くのものが伝わって来るようです。 なお、冒頭の「エンジェル・コインランドリー店」には、ふとヘミングウェイの短篇を連想させられ、「ドクターH.A.モイニハン」は凄絶なブラックジョークを聞くようで絶句。 この一冊の短篇集の中には絵空事でない、あらゆる世界、多種多様に生きる人々の姿、単純に割り切れない人間の複雑な心情が詰まっています。 是非お薦め! エンジェル・コインランドリー店/ドクターH.A.モイニハン/星と聖人/掃除婦のための手引き書/わたしの騎手/最初のデトックス/ファントム・ペイン/今を楽しめ/いいと悪い/どうにもならない/エルパソの電気自動車/セックス・アピール/ティーンエイジ・パンク/ステップ/バラ色の人生/マカダム/喪の仕事/苦しみの殿堂/ソー・ロング/ママ/沈黙/さあ土曜日だ/あとちょっとだけ/巣に帰る/ リディア・デイヴィス「物語こそがすべて」/訳者あとがき |