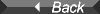俺の左目は、普通の人では持ち得ない色をしている。
金色。
それは、人としては、持ち得ない色。
だからなのか、その目には人には見えないモノまで映してくれるのだ。
そんな目だからこそ、俺は自分の目が嫌い。
だって、人には有り得ない色を持ち、人には見えないモノが見え目なんて普通なら、いらないって思うだろう。
だけど、俺が今でもこの目と共にあるのは、全部大切な人がこの目を好きだと言ってくれたからだ。
もしも、君が俺の目を否定していたら、俺はきっとこの目を潰していたかもしれない。
「お母さん、ボクの目おかしいの」
「あら?どうしたの?」
だから、俺は自分の目を捨てたかったのだ。
それを母親に相談すれば、ちょっと驚いたように聞き返してくる。
「変なモノが見えるの……」
「ゴミでも入っちゃったのかしら」
左目をゴシゴシと擦る俺に、母さんは慌ててしゃがみこみ俺の顔を覗き込んできた。
そして、擦っている手を優しく退けさせ俺の目を見る。
「ちがうの、ボクの目、おかしいの!こんな目いらいない!!」
必死で、自分の思いをぶつければ、母さんは困ったような顔を見せた。
「どうして、そんな事言うの?ちゃんのおメメはとっても綺麗なのに……」
「キレイじゃないもん!だって、みんなボクの目を見て、キモチ悪いって言うんだよ!!」
金色と琥珀のオッド・アイ。
琥珀の瞳の色は、双子の兄である綱吉とも同じ色なのに、片方の色は金色。
それは、明らかに右の瞳の色とは異なっているのだ。
「そんな事ないわよ、ちゃんの目はとっても綺麗で、お母さんは大好きよ」
「でも、でも、ボクの目は壊れてるんだよ」
自分が言いたい事が伝わらなくって、必死で伝えようと言葉を探すけど、小さな子供には難しい事で、母親には何も伝わらない。
だって、普通の人には見えないモノが、この目に映る事を、どう伝えればいいのか分からなかったから
「何が、壊れてるの?」
必死で訴える自分に、母親が困ったように質問してくる。
それに、俺は言葉に詰まった。
だって、ずっと見える訳ではないけど、見えるのだ。
時には手足を失った人や、頭から血を流している人。その人達は、存在が曖昧で、透き通っている。
でも、時々、本当に時々、それが何かを訴えるように自分に近付いてくるのが、怖かった。
彼らが、何を言ってるのかも分からない。
だから、ただ怖くって、ギュッと強く目を瞑る。
そうすれば、何も見えくなるから
「変なモノが見えるの……すっごく怖いモノが…」
「……ちゃんの目はね、ひいひいひいおばあちゃんと同じ色を片目だけ貰ってるのよ。その人はね、普通の人とはちょっと違う不思議な人だったみたいだから、もしかしたらちゃんにもその不思議な力があるのかもしれないわね」
何とか言葉を捜して伝えれば、母さんは少しだけ考えて、ある事を教えてくれた。
それは、俺の先祖に俺と同じような瞳の色を持った人が居たという事。
そして、その人は不思議な人で、その力を俺も持っているんじゃないかって事を……
「そんな不思議な力なんていらない!ボクは、普通の目が欲しいの!!」
駄々を捏ねて言う俺に、母親が困ったような表情を見せる。
分かてる、そんな事言っても、困らせるだけだって事を
だけど、小さな子供には分かっていても、どうする事も出来なかったから
「、どうしたの?」
母親を困らせていた俺に、兄弟である血を分け合った双子の兄が声を掛けてきた。
それに、振り返れば、優しい笑顔を見せてくれる。
「ボクも、ツナと同じ目がいい!!」
「どうして?の目は、とってもキレイで、オレは大好きだよ。だって、その瞳はだけが持っているモノだから……でも、どうしてもがイヤだって言うのなら、オレの目をにあげる。それで、が喜んでくれるなら」
迷いなく言われた言葉に、驚きを隠せない。
だって、何の迷いもなく言われたのは、俺に自分の目をくれると言うものだったから
それは、自分の大好きな優しい目がなくなってしまうという事
「やだ!ツナの目がなくなるのは、絶対にヤダ!!」
「有難う、オレも、の目がなくなるのはイヤだよ。だって、の目は本当に綺麗で、大好きなんだから」
母親から離れて、自分の兄に抱き付きながら必死に言えば、ギュッと抱き締め返してくれる優しい腕。
そして、慰めるように自分の目元にキスをくれる。
「ボクも、ツナの目スキ」
「じゃあ、ずっとオレ達で目を見詰め合って行こうね。そうすれば、それ以外のモノなんて見えないよ」
「うん!」
今考えると、そんな事をサラリと言う小学生低学年って思うけど、でもそう言ってくれたツナの言葉が嬉しかった。
それから、俺は自分の目を嫌いだけど、自分の一部だという事を認める事が出来たんだと思う。
「、何見てるの?」
昔の事を思い出しながらアルバムを懐かしむように笑いながら見ていた俺に、不思議そうに質問されてその顔を上げる。
「うん、部屋を掃除してたら、アルバムが出てきたから見てたんだ」
「へぇ、子供の頃のだね」
ツナの質問に答えて、見ていたアルバムを差し出す。
懐かしい子供のころの写真は、俺が事故に会う前のモノ。
活発に外に出て遊んでいた兄のツナと、部屋で大人しく本を読んでいた俺の二人が並んでいるモノが殆どの写真。
正反対な性格だけど、近所でも評判の仲良し兄弟で通っていた。
だから、どの写真を見ても自分達は嬉しそうにお互いを見て笑っているのが多い。
後は、仲良く二人で並んで寝てる写真とか、きっと母さんの趣味だろう。
「この頃の俺って、自分の目が嫌いだったんだよな。今でも、それは変わらないけど……でもね、ツナが俺に言ってくれた言葉で、認める事が出来たんだ」
「……オレ、に何て言ったのか覚えてないんだけど……」
懐かしくって、笑みを零しながら言ったその言葉に、ツナが珍しく不思議そうに首を傾げる。
記憶力は俺よりイイツナにしては、珍しい事。
でも、それはきっと他愛無い事だから、覚えている必要もなかったって事かもしれない。
「ツナはね、俺に自分の目がキレイで、大好きだって、この目は俺だけが持っているモノなんだって、そう言ってくれたんだよ。それにね、俺がこの目を持っていたくないって言ったら、自分の目をくれるって言ったんだ」
「ああ、それぐらい言うだろうね。だって、オレにとっては大切な存在なのは、今も昔も変わらないんだから」
昔を思い出しながら言った俺の言葉に、ツナは別段気にした風もなくサラリと頷いてくれる。
って、そんなにあっさり言われても……
「ねぇ、は今も自分の目がキライだって言ってたけど、それなら、何時だってオレの目をに上げるよ」
真剣に言われる言葉に、俺は少しだけ驚いて、だけど小さく首を振って返した。
「ううん、もう、俺は、自分の目をいらないなんて言わないよ。だって、この目があるから、ツナを守る事も出来るんだって、そう分かったから」
子供の頃よりも、瞳の色は一時期分からないぐらいに色が薄くなっていた。
多分、良く見ないと俺の瞳の色が左右で違う事は分からなかっただろう。それに、直ぐに分からないように、俺も眼鏡を掛けて誤魔化していたから
だけど、最近の事件の後、子供の頃の色に戻ってしまった。
昔と同じで、今は一目見ただけで分かるだろう、俺の瞳の色が左右で違う事が
でも、それを後悔なんてしていない。
確かに、この瞳には不思議な力があった。
俺と同じ瞳の色を持っていたおばあさんも、俺と同じだったのだろうか?
この力で、誰か大切な人を守っていたのかもしれない。
俺に力はない。
だけど、誰かを助ける為の力を手に入れる事が出来たのだから、これ以上望むモノなんてあっちゃいけない。
「!何度も言うけど、あの力は使っちゃだめだからね!!」
たとえ、それで自分が傷付いたとしても……
俺の考えている事が分かったかのように、ツナが真剣な瞳でクギをさしてくる。
でもね、俺はその約束だけは出来ないよ。
だって、この力は、大切な人達を守る為のモノだって、ちゃんと俺は知っているから
「、聞いてるの!!」
何も返事を返さない俺に、ツナが更に声を掛けてくる。
大切な自分の半身。
俺の事を心配してくれていると分かっているから、俺はただ笑顔を見せた。
俺が、この目を持って生まれた事に意味があるとすれば、それは大切な皆を守る為。
だから、約束は出来ないよ。
俺に出来る事は、それだけだから……