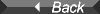「なんで、そんなにこいつが階段を上り下りするのを嫌がるんだ?」
何を考えているのか、突然のその言葉に、オレは一瞬意外過ぎてリボーンを見てしまった。
それと同時に、向けられるの視線を感じて小さくため息をつく。
確かに、の言うように、階段を人を抱えて歩くのは非常に危険な行為と言ってもいいだろう。
でも、だからと言って、一人で階段を上り下りさせるなんて、冗談じゃない。
「そんなの決まってるよ。が何度か階段から落ちそうになった事があるからに決まってる」
だから、キッパリとその質問に返事を返した。
それは決して嘘じゃない。
は、何度か階段から落ちそうになった事があるのは、本当の事。
だけどそれは、全部女子の誰かとすれ違った時だけに起こっていたって事も、オレは気付いている。
勿論、そんな事をした相手には、キツクお返しをしてあるから、同じ子が二度もその行動に出た事はないけど……
「おまえ、そんなにダメダメだったのか?」
オレの言葉に、リボーンが呆れたようにを見る。
もっとも、そんな事を言いながら、リボーンはとっくに気付いているんだろう。
がそんなにドジで、ダメダメじゃない事に……。
気付いているから、リボーンが時々優しく愛しい者を見詰める視線でを見ている事を……
「た、確かに、何度か落ちそうになったけど、落ちてないんだからいいじゃんか!!」
「その殆どが、オレが抱き止めたからだと思うんだけど」
リボーンから哀れんだように質問されたそれに、がすかさず弁解するけど、オレが更に事実を口にする。
オレが居ない時に落ちた時は、確かに自分で落ちないように頑張ったみたいだけど、その後確実に病院に行く嵌めになってしまうのだ。
の悲鳴を聞いたオレが、どれだけ心配したかなんて、きっと知らないだろう。
そして、突き落とした女子が、その悲痛な声でどれだけ自分が愚かな事をしたのだと、深く深く反省していた事さえきっとは、知らない。
酷い事をしてごめんなさいと謝った女子は、それこそ片手では足りない。
それでも、に直接謝罪する事を許さなかった。
だって、が許す事が分かっていたから、だからこそ、簡単に許されて、楽になろうだなんてオレが許せなかったのだ。
今でも、彼女達は、その時の罪を背負って生きていけばいい。
それだけの事を、したのだから……
「あう、でも……」
「でもは聞かないよ!何度も言ってるよね。は、一人で階段を上し下りしちゃ絶対にダメ!一人で上るとしても、オレが傍に居る時だけにして」
それでも、必死に言い訳しようとするに、キッパリと言葉を返す。
本当に、の悲鳴を聞いた時、どれだけオレが恐怖したかなんて、君は知らないんだろう。
また、君を失うかもしれないと言うあの恐怖を……
「あの、俺とツナさんは、クラス違うから、それは無理です」
キッパリと言ったオレに、が、恐る恐る言葉を返してくる。
の言う事は、確かに正論。でも、だからと言って、納得出来る訳がない。
本当に、なんでオレとは同じクラスじゃない訳!普通、障害がある生徒なんだから、学校側がきちんと配慮するべきだと思うんだけど!
そして、思い出したのは、並盛最強にして、オレにとっては、最低の風紀委員長様。
「………リボーン、お願いがあるんだけど」
「聞く気はねーぞ」
思い出した相手の事で、以外で唯一嫌われていないリボーンへと声を掛ければ、速攻で拒否られてしまった。
どうやら、オレの考えている事はバッチリと読まれているらしい。
「何?全然役に立ってないんだから、ちょっとぐらいは役に立ってくれてもいいんじゃない?」
「……おまえが、考えてる事が分かるから、嫌なんだぞ」
だけど、それぐらいで諦めるなんてするはずもなく、更に質問すれば、やっぱり拒否される。
まったく、人の考えてる事が分かるなら、素直に頷いてくれれば話が早くて助かるのに……
そんなリボーンに、オレは深々とため息をついて、ゆっくりと考える。
どうすれば、リボーンが納得するかを……
そして、オレはニッコリと笑顔をリボーンへと向けた。
「へぇ、分かるんだ。だったらお願いするよ、リボーン」
最近すっかりと定着しつつある自分でも十分黒いと思える笑顔を振り撒きながら、リボーンへと再度お願いする。
持つべき者は、腹黒の友達だろう。
山本のお陰で、脅しのテクニックが上がってきたと自分でも、良く分かる。
もっとも、には思いっきり引かれちゃうんだけどね。
「………一応手を回しといてやる。だが、あいつが聞き入れるかどうかは分かんねーからな」
オレの笑み付きのお願いに、リボーンが盛大なため息をついて、それで納得しろと言うように口を開く。
それだけ聞ければ、十分だ。
オレが満足気に笑った瞬間、が訳が分からないと言うように首を傾げて見詰めてくる。
「えっと、一体何の話をしてるんだ?」
全く分からないと言うように質問してくるに、オレがニッコリと笑顔を向けた。
「何でもないよ。もう直ぐ1年も終わりだなって思っただけだからね」
そして返事を返すのは、全く的外れな事ではなく、これからの計画にとっては重大な部分。
オレのその言葉に、またしてもリボーンが盛大にため息をつく声が聞こえてきたけど、それは完全に無視。
「えっと、俺の階段の話から、どうしてそんな話しに……」
「深く考えなくっても、大丈夫だよって話」
だけど、やっぱりそれでも意味が分からなかったのだろうが、不思議そうに首を傾げながら口を開くのに、もう一度笑顔を向けて、それ以上の質問を拒否する。
オレがそう返した瞬間、が複雑そうな表情を見せた。
がそんな顔を見せる時は、ろくな事を考えていない証拠だ。
思わずオレも眉間に皺を寄せて、を見た瞬間、ポツリと呟かれた言葉。
「……また、クラスの人に迷惑掛けちゃうな……」
深いため息と一緒に呟かれたその言葉に、思わず呆れたようにを見てしまう。
全く、どうして直ぐに周りの人間の事だけを考えてしまうんだろう、は!
「が気にする事なんて、何にもないんだからね!もう、どうしてそこでそんな事考えるの、は!」
見当違いな事を考えているに、そう言えば、何故怒られているのか分からないのだろうキョトンとした表情でオレを見上げてくる。
「ツナの言う通りだぞ。おまえは変な所で遠慮しすぎだ」
そして、オレと同じように、リボーンも呆れたようにに言葉を伝えた。
本当に、どうして、自分の事よりも、周り方を優先的に考えるんだろう。
「ちゃん、ちょっと手伝ってもらえるかしら!」
何故、リボーンとオレに怒られているのか分かってないのだろうが真剣に考えている中、階下から母さんの声が聞えてくる。
それにが、まるで助かったと言うように顔を上げた。
「分かった、直ぐ行く!」
母さんへと返事を返して、がゆっくりと立ち上がる。
一瞬だけ、申し訳なさそうな表情をしたけど、意を決したのかへにゃりと笑顔を見せた。
「って、訳だから、ちょっとごめんね」
「じゃなくって、先の今で、何さり気に一人で行こうとしてるの!」
そして、オレ達に謝りながら、さり気無く部屋を出て行こうとするに思わず突っ込んでしまう。
本気で、そのまま一人で行こうとしてるんだから、全然分かってないよね、の場合!
その後は、を抱えて階下まで移動。母さんは何時ものように、『ご苦労様、ツっくん』なんて返してくるから、それに笑顔を返した。
ランボに関しては、多分オレがを抱えていたのが許せなかったのだろう、裏返し状態でを馬鹿にしていたけど、オレに向けられた視線は、一丁前に嫉妬の色をしていたのだから。
もっとも、誰にだろうが、は渡さないけどね。
「ツナ、本当は知ってるんじゃねーのか?あいつが階段から落ちそうになった本当の理由……」
そして、部屋に戻ったオレに、リボーンが声を掛けてくる。
真剣な視線で言われたその言葉に、オレは惚けた声で返した。
「さぁ、何の事?」
言いたい事は、分かっているけど、あえて知らないフリをする。
「……仲がイイおまえ等に嫉妬した女共があいつを突き落としてたんだろうが!」
惚けたオレに、リボーンが呆れたような視線を向け、更に確信していたのだろうそれを口に出す。
やっぱり、気付いていたんだ。
だけど、だからってどうでもいい事だけどね。
「それは推測でしかないけどね、でもが何も言わないから、オレには分からないよ……それにね、これはオレにとっては一番の役得なんだから、誰にも邪魔されたくないんだけど」
「分かってるのに、あんな事言ってやがるのか!」
本当は、それが真実だと知っているけど、オレはあくまでも知らないフリをする。
だって、オレにとって、に触れられると言うのなら、どんな理由でも行動に移す事は厭わない。
「さぁね……それじゃ、ここまで話したんだから、例の件宜しく頼むね」
あんな事と言うのが、何を指しているのを十分理解しているからこそ、オレはただ笑みを浮かべて返事を誤魔化す。
そして、肯定するように、言葉を続けた。
それぐらいの理由がなければ、オレがリボーンにここまで話をする訳がないと言うように……。
「……やっぱり、喰えないヤツだな……」
オレのその言葉に、ポツリと聞えて来たリボーンの言葉を完全に無視して、微笑んだ。
だって、オレには、が全てだから……。
だからこそ、実行あるのみ、てね。