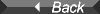休日の朝、何時ものように目を覚ましたのはお昼を回ってからの事。
「ねぇ、何時も休みの日はこんな時間に起きてるの?」
ぼんやりとした頭で時間を確認していた俺の耳に、誰かの声が聞こえてくる。
聞こえてきたその声は、綱吉の声じゃない。
不機嫌なその声は聞き慣れたと言うほどには聞き慣れてはいないけど、間違いなく良く知っている人の声。
聞こえてきたその声に、俺は恐る恐る視線を向けた。
「えっと、おはようございます、恭弥さん」
予想通り視線を向けた先に居たのは、椅子に座ってこちらを見ている恭弥さん。
どうしてそこに居るのだろうと疑問に思ったのだが、寝ぼけた頭が弾き出した言葉は、朝の挨拶だった。
「おはようって、言う時間じゃないけどね。他に言うことはないの?」
「えっと、それじゃ、こんにちは?」
挨拶の言葉を口にした俺に、恭弥さんがため息をつきながら質問してくるのに、首を傾げながら問い返す。
寝ぼけた頭では、まだ状況を把握できていないのだから、仕方ない。
「……まぁ、いいよ。起きるのを待っていてあげたんだから、お礼を言ってよね」
「あっ、はい、有難うございます?」
そんな俺にまたもや恭弥さんがため息をついて、お礼を言えと言われたので素直にお礼を言ったんだけど、言いながら何でお礼を言っているのかが分からなくなって、思わず疑問系で返してしまった。
「何で、疑問系なの?」
「えっと、まだ頭が働いていないので……それで、恭弥さんは、どうしてここに?」
すかさずそれに突っ込みをする恭弥さんに、素直に理由を話して漸く一番に質問すべきだったであろう内容を質問した。
だって、なんでここに恭弥さんが居るのか、本気で俺には分からないから
「君、今日が何日か分かってる?」
「今日、ですか?えっと、日曜日ですよね??日にちは……」
質問した俺に対して、またしても恭弥さんが質問で返してくる。
質問された内容に、俺は必死で今日の事を考えた。
勿論、曜日はちゃんと理解している。
だけど、日にちとなると、寝ぼけた頭では直ぐに出てこなかった。
だってね、そんなに重要だと思ってないんだもん。
「3月14日」
「はい?」
考えても日付が出てこなかった俺に、恭弥さんがため息を付いて呟かれたのは、多分今日の日付、だよね?
一瞬言われた事が理解できなくて、聞き返すように首を傾げた俺に、再度恭弥さんがため息をつく。
「3月14日って言ったんだよ。聞こえたの?」
「あっ、はい、ちゃんと聞こえました!そっか、今日は、14日なんだぁ……でも、それと恭弥さんがここに居る理由が結びつかないんですけど?」
呆れた様子の恭弥さんに、慌てて返事を返してから、またしても首を傾げる。
俺、起きてからずっと首を傾げているような気がするのは、気の所為じゃないよね。
「君、今日が何の日か知らないの?」
しかも、質問した内容が全部質問で返されているように思うのも、きっと気の所為じゃないと思うんだけど……
今日が、何の日って……3月14日だよね?
なんの日かって言われたら、まず一番に出てくるのが日曜日。
うん、日曜日じゃないと、俺がこんなにもゆっくりと寝ていられないもんね。
そうじゃなきゃ、ツナに起こされて学校に行っている時間だから
でも、それだけだと恭弥さんがそんな質問してくる訳ないよね?他に、何か特別な日だったっけ?
「ホワイトデー」
漸くまともに動き始めた頭で、恭弥さんの質問に答えようと頑張っている俺に、ポツリと呟かれた言葉が聞こえてきた。
ホワイトデー?
ああ、そうか、今日はホワイトデーなんだ……
あれ?そう言えばツナが今日のお昼から一緒に出掛けようって誘ってくれたような気がするんだけど、それって、もしかして……
「えっと、もしかして、バレンタインのお返し、ですか?」
そこまで考えてから、漸く恭弥さんがここに居る理由が結びついて、恐る恐る質問。
「そうだよ。君から貰ったからね、それに言ったはずだよ、ホワイトデーを楽しみにしてってね」
俺の質問に、返されたのは不敵な笑み。
言われて思い出した。
確かに、バレンタインにプティングをプレゼントした時に、そう言われていたっけ
すっかり忘れていました、俺。
「あ、有難うございます、恭弥さん」
すっかり忘れていたのに、こうやって態々お返しを届けに来てくれた事が嬉しい。
「別に、大したものじゃないよ」
嬉しいと言うのが顔に出て、ニコニコと笑みを浮かべた俺に、恭弥さんがボソリと口を開く。
「いいんです!だって、俺のために準備してくれた事が嬉しいんですから!」
それに対して俺は、力を込めて返事を返した。
そうすれば、恭弥さんが呆れたようにため息をつくのが分かるけど、何時もの事なので気にしちゃいけない。
「はい」
そして、その後ベッドに座ったままの俺に投げられたのはラッピングされている小箱。
「有難うございます。開けてもいいですか?」
「君に上げたものなんだから、好きにしなよ」
それを手にとって質問すれば、素っ気無く返される返事。
許可を貰ったので、俺はその包装を綺麗に外していく。
出てきたのは、どう見てもジュエリーボックスに見えるんだけど……
「あ、あの恭弥さん、ホワイトデーのお返しって、お菓子じゃないんですか?」
「知らないよ。ただ、貰ったものの3倍返しだって聞いたからね」
出てきたジュエリーボックスを手に恐る恐る質問した俺に、恭弥さんが誰から聞いたのかとんでもない内容を返してきた。
それは確かに本命にはそうかもしれないんですが、一般的じゃありません!
しかも、これはどう見ても10倍返しだと思うんですが?!
「こ、こんな高級なもの貰えませんよ!」
「何?受け取れないって言うの?君が受け取らないなら、捨てるだけだよ」
そっと開いたジュエリーボックスの中に入っていたのは、どう見ても高そうなネックレス。
いや、男の俺に渡すようなものじゃないと思うんですけど……
四葉のクローバーのペンダントヘッドに使われているのは、もしかしなくても宝石ですか?!
こんな高価なものは受け取れないと言うと、恭弥さんが不機嫌そうに返してきたのはとんでもない言葉だった。
いや、それは脅しです。
だって、捨てるなんて、そんなもったいない事……
「ダメです!モノは大切にしないとダメなんですよ!しかも、宝石を捨てるなんて……」
ギュッと箱を握り締めて言った俺のその言葉に、恭弥さんが満足そうな表情で笑みを浮かべる。
「なら、ちゃんと大事にしなよ」
は、嵌められた。
満足そうなその笑みを見た瞬間、見事に恭弥さんの術中にはまってしまった事を悟ってしまう。
「お返しを渡したんなら、さっさと帰ってもらえますかねぇ」
それに気付いた俺が複雑な表情をした瞬間、不機嫌な声が聞こえて来た。
声の主は、何時の間にドアを開い入ってきたのか、腕を組んだ状態で壁に凭れているツナの姿。
「ツ、ツナ、おはよう」
「うん、おはよう、。で、ヒバリさんはさっさと帰ってください」
「何で僕が君の言う事を聞かなきゃいけないの?」
突然のツナの登場に驚いたんだけど、それでも何とか挨拶をすればニッコリと笑顔で返事を返してから、早速恭弥さんとの間に険悪なムードが流れてしまう。
な、何でこんなにも険悪なんだろう、この二人……。
恭弥さんも恭弥さんで、ツナに笑顔で言われたそれに対して、不機嫌な表情で聞き返している。
「そんなの、今からはオレと一緒に出掛けるんで、ヒバリさんが邪魔なだけですよ」
えっ、ツナ、それ笑顔で言う事じゃないと思うんだけど……
それに、出掛けるのは確かに昨日聞いたけど、どこに行くとかそんな話は全然聞いていない。
「そんなの君の勝手でしょ、僕には関係ないよ」
「関係ありますよ。ヒバリさんが居たら、が着替えられないじゃないですか」
恭弥さんが言葉を返せば、当然だと言うように綱吉が口を開く。
あれ?もう俺の意思関係なく、出掛けるのは確定?
出掛けるのは別にいいんだけど、どんどん二人の空気が険悪になっていくのが分かって、怖い。
「えっと、それじゃ、恭弥さんも一緒に出掛けるって言うのは?」
その空気を何とかしようと、俺は恐る恐る口を開いた。
そうすれば、同時に二人から視線を向けられてしまう。
「何で、オレがヒバリさんなんかと出掛けなきゃいけないの!」
「僕に群れろって言うの?冗談じゃないね」
しかも、同時に文句を言われる。
えっ、俺としては、あの空気をどうにかしたかっただけなんだけど、なんでこんなにも攻めれているんだろう?
「いいよ、僕は暇じゃないからね、帰らせてもらうよ」
二人同時に返されたそれにオロオロしていた俺は、完全無視で盛大なため息をついて恭弥さんがそう言うと窓から出て行ってしまった。
って、何で窓から?!
もしかして、入ってきたのも、窓からなんだろうか??
俺、窓の鍵閉めてなかったっけ?
「、何で窓の鍵閉めてないの!!」
窓から出て行ってしまった恭弥さんを見送っていた俺に、すかさずツナが突っ込んでくる。
えっと、俺は閉めたつもりだったんだけど……
「窓を開けたのはオレだぞ」
ツナに叱られたので、本気で昨日の夜の事を思い出していた俺の耳に、また新たな声が聞こえてきた。
「リボーン、おはよう。えっと、開けたのがリボーンって……」
「ヒバリに頼まれたから、窓の鍵を開けといてやったんだぞ」
視線を向ければ、これまた何時来たのか俺のベッドに座っているリボーンの姿があって、一応朝の挨拶をしてから、恐る恐る質問すれば、すんなりとリボーンが窓の鍵を開いた理由を話してくれる。
あれ?それって、俺は怒られ損ですか?!
「何勝手なことしてるんだよ、リボーン!!」
「オレは、ヒバリに貸しを作っただけだぞ。あいつに貸しを作っておけば後々楽しめそうだからな」
何だか複雑な気持ちになった俺には気付かない様子で、綱吉がリボーンを怒鳴るけど、全く気にした様子も見せないでリボーンが返事を返す。
でもね、リボーンが貸しを作るその為に俺が売られてるんですが……
起きた時、恭弥さんが居て、本気で驚いたんだけど、俺。
「ダメ」
「んっ?」
多分、何を言っても無駄だろうと思ってため息をついた瞬間、リボーンに呼ばれて顔を上げれば、俺の手元に袋が置かれていた。
「オレからもバレンタインのお返しだぞ」
「有難う……って、コーヒー豆って事は、これで俺にコーヒー入れろって事なんだね」
言われた言葉にお礼を言って袋の中身を確認したら、俺が飲めないコーヒー。
リボーンの意図が理解できて、ため息をついてしまった。
うん、別にねいいんだけど、俺コーヒー分からないから、豆を買ってきてくれるのは、正直助かる。
「そっちじゃねぇぞ」
だけど、ため息をついた俺に、リボーンが呆れたように否定した。
「えっ?」
「その下だぞ」
どうやらコーヒー豆がお返しじゃないらしく、リボーンに言われるままに豆の下にあるものを見れば、それは俺が好きな紅茶の葉。
「有難う、リボーン」
それを見付けて素直にお礼を言えば、フンと視線を逸らされてしまった。
「リボーンからもお返し貰ったみたいだから、今度はオレから渡したいんだけど、いい?」
そんな俺に、続けて綱吉が声を掛けてくる。
「ツナも?皆、律儀だね。俺、お返しが貰えるなんて考えてなかったんだけど……」
「それは、からもらえて嬉しかったからだよ。だから、オレ達もに感謝の気持ちを伝える為にお返しを準備してるんだからね」
まさか本当に綱吉もお返しを準備してくれているとは思ってなかったので、思わず苦笑を零した俺にツナが笑いながらすごく嬉しい事を言ってくれた。
だって、いつも迷惑を掛けているから、感謝の気持ちでバレンタインにお菓子を作ったのだ。
少しでも、自分のこの気持ちが伝わりますようにと願いを込めて
それが伝わっているだけでも嬉しいのに、同じように俺にその気持ちを返したいと思ってくれた事が本当に嬉しい。
「有難う、ツナ」
言われた言葉が本当に嬉しくて、気が付いたら笑顔でお礼の言葉を返していた。
「まだお礼は早いよ。ほら、これに着替えて、出掛けよう」
お礼を言った俺に、ツナが手に持っていた服を差し出してくる。
それを受け取って、俺は首を傾げた。
そう言えば、ずっと出掛けるって言ってるんだけど、どこに行くんだろう?
「行き先は、お楽しみだからね」
首を傾げてツナを見た俺に、そう言ってツナが笑う。
どうやら、俺が考えていた事は筒抜けだったらしい。
そう言ってから、ツナはリボーンを連れて部屋から出て行ってしまった。
後に残されたのは、俺一人。
呆然と考えていても仕方ないと、俺はツナから受け取った服に着替える事にする。
でも、着替えていて気付いたんだけど、やっぱり服は女物だった。
絶対に、母さんのコーディネートだ。
真っ白なホワホワした服は、肩から少しだけ切れ目があってリボンで結ばれている。
それに合わせたズボンは、白と黒のチェックで膝下までの長さしかなく、ソックスは黒でズボンの丈より長めなので足は全く出ない。
おまけと言うように、ホワホワ素材の黒のベレー帽が用意されていた。
でもこれだと胸元がちょっと寂しいかも、あんまり付けないんだけどアクセサリーを着けた方がいいかなぁ?
そこで目に入ったのが、先程恭弥さんに貰ったもの。
そこそこの長さがあるので、首元が隠れるようになっているこの服でもその上から着けられそうだ。
一応可笑しくないかどうかを鏡で確認してから、大丈夫なのを確認して部屋から出る。
「準備できた?」
部屋から出た瞬間、ツナが声を掛けてきたのでちょっと驚いてしまう。
「ここで待ってたの?」
「まぁ、と直ぐに出掛けたかったからね」
驚いて質問した俺に、ツナが少しだけ照れたように返してくる。
そんなツナに思わず笑ってしまったのは、仕方ないだろう。
「有難う、それじゃ早く出掛けよう、母さんには言ってるんだよね?」
笑ってお礼を言って、確認する。
この服を用意したのは間違いなく母さんだろうから、話はしているだろうと予想は付いたから
「うん、その服も母さんのコーディネートだからね」
「だろうと思った……これ、どう見ても女物だから……」
「それじゃこれ、外は春と言ってもまだ寒いからね」
俺が確認した内容に、当然と言うようにツナが頷く。
それから差し出されたのは、真っ黒なスプリングコート。
「珍しいね、白と黒で統一なんて」
差し出されたそれを受け取って、思わず素直な感想を口にする。
母さんの好みは、女の子らしいふんわりした色使いなんだよね。
だから、春の服と言うとピンクとかグリーンとかイエローが多いのに、今日の服は白と黒のみ。
「そうだね、母さんにしては珍しいけど、は白も黒も似合ってるよ」
ニッコリと笑顔でそう言ったツナの服は、水色のカッターシャツに、折り目の後がしっかりと分かる黒のズボン。
ネクタイを着けたら、間違いなくスーツになりそうだ。
それにスプリングコートは、真っ黒なトレンチコート。
うん、何でそんなに似合ってるんだろう……ネクタイを着けたくなるんですが……
「ツナは、何かスーツ着てるみたい……ネクタイ着けたら、似合いそうだね」
「そう?変かなぁ?」
「変じゃない!すごくカッコいい!!」
「有難う、も似合ってる」
呆然とツナを見ていた俺は、素直な感想を口に出していたみたいで、ツナが心配そうに質問してきた内容に力一杯返事を返してしまった。
そんな俺にツナが嬉しそうに笑って言われたのは、先程も聞かされた言葉。
うーん、俺としては、女物が似合っていると言われるのは複雑な気分なんだけど……
「あらあら、まだ出掛けてなかったの?早くしないと、時間がなくなっちゃうわよ」
どう返答するか迷っている中、聞きなれた声が掛けられる。
振り返ると、母さんが少し呆れたような表情をしてそこに立っていた。
「もう出掛けるよ。言ってたように、夕飯はいらないから」
「はいはい、気を付けて行ってくるのよ」
「分かってる。それじゃ、行こうか?」
「うん、母さん行ってきます」
「いってらっしゃい」
母さんに送り出されて、俺と綱吉は一緒に家を出る。
勿論、靴もしっかりと準備されていました。
汚れが目立ちそうな、真っ白なショートブーツを……
「それじゃ、本当はお昼ご飯を食べる時間なんだけど、お昼食べちゃうと多分食べられなくなるだろうからナシにして、今日は特別にが一番喜んでくれる場所に連れて行ってあげるからね」
何処か楽しそうに言われるツナのその言葉に、思わず首を傾げてしまう。
確かに、今の時間だとお昼ご飯の時間と言ってもいいだろう。
もっとも、それよりちょっと時間が経ってるけど
何時もは、ご飯を食べてない俺に、ツナは怒るんだけど、そのツナが咎める事をせずに、しかもお昼ご飯よりも俺が喜ぶ様な場所に連れて行ってくれるとの事。
訳が分かりません。
多分、これがツナのお返しなのだと分かるんだけど、どんなお返しになるのか想像もつかない。
「今日は、特別だからね」
そう言って連れて来られたのは、どう見ても高級ホテル。
並盛の中では一番高級とされているリゾートホテルに、一体どんな用事が?!
と思ったら、もしかしてケーキバイキング……なんだろうか?
目の前では、沢山のケーキがトレーに並べられている。
それを嬉しそうに取り分けている女の人が……
「ここね、イベントのみに限られるんだけど、ケーキバイキングをしてるんだよ」
驚いている俺に、ツナがこっそりと教えてくれる。
なるほど、知らなかった。
ここで、そんな素敵なイベントが開催されていたなんて……
「1時間の時間制限だけど、値段も手頃で、結構好評みたいだね」
そう言うツナはもう既に支払いを済ませたのか、手に専用のトレーを持ってきていた。
「これに取り分けて、テーブルにあるお皿を使うんだって、飲み物もお替り自由」
説明してくれるツナのその言葉を聞いて、目がキラキラしてしまう。
だって、ここの紅茶ってすごく恭弥さん好みで美味しいんだって草壁さんが教えてくれたから!
「有難う、ツナ」
きっと、俺の為に探してくれたのだと分かるから、素直にツナにお礼を言う。
ケーキは好き。
でも、そんなに食べられないから、バイキングで大丈夫かなぁと心配してたんだけど、ここのケーキはちょっと小さ目で思っていたよりも食べられた。
ツナも、甘さ控えめと言う事で、3個食べていたのに、ちょっと吃驚。
俺が作ったケーキは良く食べてくれるけど、基本ツナは甘いものが好きじゃないないから、ケーキを3個も食べたって言うのは、本当に凄いと思う。
そう言う俺も、自己最高の6個を完食しました。
とっても、美味しかったです。
紅茶も、恭弥さんが気に入るのが分かるぐらい美味しかった。
茶葉の単体販売もしていたから、今度買いに来よう。
「お腹一杯!すっごく美味しかった」
「そうだね、にしては珍しく一杯食べてたよね」
満足してホテルを出てからそう言った俺に、ツナが楽しそうに笑いながら返してくる。
うん、だって本当に美味しかったから、俺にしては珍しく一杯食べちゃいました。
「そんなに食べたら、夕飯食べれないよね……」
素直に頷いた俺に、ツナがボソリと口を開く。
その声が聞こえて来て、思わず首を傾げてしまった。
だって、ツナは母さんに夕飯はいらないって、言ってのだから、心配する事ないと思うんだけど
「まだ時間は大丈夫だから、ちょっと歩いてから行こうか」
疑問に思って質問しようとしたら、ツナは腕時計で時間を確認してからそう声を掛けてくる。
全く意味は分からなかったけど、ツナがそう言うからとりあえず頷いて返す。
「足、大丈夫?」
「うん、大丈夫……ツナ、さっきのあれ、どう言う意味?」
ゆっくりとホテルの近くにある公園へと歩き出したツナに並んで歩きながら、心配そうに質問して来たツナに返事を返して、疑問に思った事を質問する。
「この後、山本の家に行く事になってるんだよ」
「山本の家?」
「うん、夕飯をご馳走してくれるって言うからね」
質問した俺に、ツナがあっさりとその意味を教えてくれた。
言われた内容に、ちょっと驚いた。
何時の間に、そんな話が……
でも、何で行き成りそんな話が出てきたんだろう?
「京子ちゃんとハルも招待されてるって言ったら、理由分かるよね?」
疑問に思って首を傾げた俺に、ツナが笑いながら問い掛けてきた。
京子ちゃんにハルちゃんが招待されてるって事は、山本のお返しって事だろう。
「獄寺も便乗してくるらしいから、多分お返し準備してるんじゃないかな」
そう言って、またツナが笑った。
確かに、口は悪いけど、何だかんだで獄寺くんは律儀な性格なので、間違いなくお返しを準備してくるだろう事は、想像できる。
「だから、お腹一杯で行くと、まずいかなぁって……」
「うん、確かにそうだね。それじゃ、どっかで買い物して行こうよ!ツナも京子ちゃん達にお返し準備するんだよね?」
「もう準備してる。ちゃんと山本の家で預かって貰ってるから心配しないでいいよ」
ああ、ツナはちゃんと準備してるんだ。
俺は、何も準備してないから、流石にまずいよね……。
「それじゃ、俺が二人に準備するから、付き合って!」
「は、バレンタインに渡してるから、必要ないんじゃないの」
「えっ、でも、俺も二人から貰ってるから……」
「それで返してたら、キリがないと思うんだけど」
た、確かにそうかもしれない。
すっかり忘れてたけど、本当は何か作って渡そうと思ってたんだよね、バレンタインの時には
だから、何かを買ってお返ししようと思ったんだけど、それをツナに止められてしまった。
でもね、やっぱりちゃんとお返ししたい。
「うん、でもあれは感謝の気持ちを形にしたものだから、今日贈るのは、バレンタインのお返し。だから、間違ってないよね?」
必要ないと言われたけど、それでもこれは俺の気持ちだから、と恐る恐る問い掛けてみたら、ため息をつかれてしまった。
「本当、らしい考え方だよね」
そして言われたのは、明らかに諦めたと言うようなツナの言葉。
それって、ため息つきながら言うような事じゃないよね?!
「褒め言葉になってない」
「褒めてないよ。だって、オレは呆れてるんだから」
ため息をつきながら言われたそれは、褒め言葉ともとれるような言葉なのに、全然そんな風に聞こえてこなかったので文句を言えば呆れたように返されてしまう。
褒め言葉じゃなかったんだ。
「それはそれで酷いと思う……」
褒め言葉じゃないといったツナにボソリと文句を言えば、笑って返されてしまった。
それでも、俺が言ったように、しっかりとお返しを買う為に付き合ってくれるんだから、優しいよね、ツナは。
結構な時間を散歩と称した買い物に費やして、何とかお腹も空いたような気がする時間になってから、山本の家に向かう。
そこでは、山本がお返しにと俺達に自分が作ったお寿司をご馳走してくれた。
勿論、獄寺くんも文句を言いながらもお返しにと、クッキーを準備していた。
本当に何だかんだと言いながらも、律儀な性格をしている。
ツナも、二人にケーキのマスコットが付いたストラップをプレゼントしていた。
それとセットで、ビンに詰められたキャンディをプレゼントしているのがニクイ演出です。
俺が準備したのも、獄寺くんとかぶっちゃってるんだけど、クッキー。
ローズマリーのクッキーなので、リラックス出来るかなぁと思ったんだけど
勿論、黒川さんの分もちゃんと準備しているので、明日渡さなきゃだよね。
今日はホワイトデー。
バレンタインに貰った気持ちにお返しをする日。
俺も、皆から沢山のお返しを貰った。
来年も、同じように感謝の気持ちを贈りたいと、そう強く思ったのは、俺だけの秘密。
でも、来年も再来年も、皆と一緒にこんな時間が持てればいいなぁと思った事は素直に言えば、皆が笑って頷いてくれたのが、何よりも嬉しかった。
だから、お願いします。
来年も再来年も、こんなに沢山の幸せがありますように