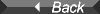「、起きて、」
今日は、日曜日。
だから、何時もの様にのんびりと眠りについていたのに、何故かツツナに起こされた。
何度も揺り起こされて、眠りの世界から無理やり覚醒へと導かれてしまう。
「ん〜っ、今日は、日曜、だよ……もうちょっと、寝かせて……」
「寝かせて上げたいんだけど、オレ達の命の危機なんだよ。だから、起きて!」
まだ寝ていたい俺は、布団に潜り込みながら、ツナに文句を言えば切羽詰ったツナの声が更に俺を起こしてくる。
珍しいツナの切羽詰った声と、命の危機と言うその言葉に、まだまだ夢の中を彷徨っていた俺の意識が完全に呼び覚まされた。
「命の危機って?!な、何があったの?!!」
ガバリと勢い良く起き上がって、ツナへと質問する。
だって、命の危機なんて、そんな大変な時にゆっくりと寝てなんていられない。
「おはよう、」
「暢気に挨拶なんてしてる場合じゃないよ!何があったの、ツナ??!」
まさに飛び起きると言う表現が一番ぴったりな位勢い良く起き上がって、暢気に朝の挨拶をしてきたツナに問い掛けた。
だって、命の危機だって言うのに、暢気に挨拶してくる場合じゃないと思うんだよね。
「安心して、まだ大丈夫だから」
だけど俺の質問に、ツナが苦笑を零しながら返事を返してきた。
えっと、まだ大丈夫って……一体、どう言う事?
訳が分からない俺は、首を傾げながら思わずツナを見てしまう。
「が起きなかったら、オレ達の命が危なくなるって言うのは本当」
俺の顔を見て、何を言いたいのかを察したのだろうツナがもう一度口を開いて同じ事を言う。
「えっと、どう言う事なのか聞いても大丈夫?」
だけど、その意味が分からなくて恐る恐る質問する。
だって、俺が起きたからと言ってみんなが無事でいられるなんて、そんな力があるとは思えない。
「ああ、まだ説明してなかったね。命の危機って言うのは、ビアンキのポイズンクッキングの事だよ」
「ポイズンクッキング?ビアンキさんが料理してるの?」
心配に思いながら質問すれば、ツナが理由を教えてくれる。
確かにそれは、命の危機だ。
だけど、俺がビアンキさんを止められるとは思えない。
「いや、まだ料理してる訳じゃないよ。今、京子ちゃんとハルが来ているんだけど、が起きてこないなら、ビアンキに料理を習うって言うから……」
恐る恐る質問した俺にツナが更に説明してくれた内容で、漸く理解できた。
ビアンキさんが京ちゃん達に料理を教えてしまったら、それがポイズンクッキングになってしまう、だから、ツナは俺を起こしに来たんだ。
確かに、俺が教えれば間違いなく安全なものが出来上がる。
「そう言う事なんだ……」
説明された事で納得して頷き、俺はベッドから起き上がった。
「なら、早く行かないと、京ちゃん達待たせてるんだよね?」
「あっ、うん。いいの?」
「勿論。二人が俺を頼って来てくれたんだから、とっても嬉しい」
クローゼットから洋服を取り出しながら言った俺に、ツナが心配そうに質問してくる。
それに俺は、笑顔で返事を返した。
二人が俺を頼ってくれた事は、本当に嬉しい。
「それじゃ、二人にはオレから話しとくよ」
「うん、着替えたらすぐに行くって言っといて」
俺の返事にツナがホッとしたような表情をして部屋から出て行くのを、頷いて返してから急いで服を着替える。
と言っても、出掛ける訳じゃないから、ラフな格好だけどね。
トレナーにGパンと言う簡単な格好に着替えてから、部屋を出てキッチンへと向かう。
「おはよう、待たせちゃってごめんね」
「おはようございます!起こしてしまって、すみません」
「おはよう、くん。無理言ってごめんね」
キッチンに顔を出せば、俺が来るのを待っていてくれたのだろうハルちゃんと京ちゃんが申し訳なさそうに謝罪してくる。
確かに、俺は寝るのが好きだけど、二人が俺を頼ってくれたのが嬉しいから、迷惑だとは思わない。
「気にしなくて大丈夫だよ。それで、今年はどんなチョコを作るの?」
申し訳なさそうな表情を見せている二人に笑顔を返して、話題を俺が起こされた理由のモノへと向けさせる。
明日はバレンタインデー。
二人が俺を頼ってきたのは、そのバレンタインのチョコレートを作る為。
だからこそ、まずは二人がどうしたいのかを聞く事から始めないとだよね。
「えっと、それが、まだこれと言うのが決まってないんです……」
「うん、どれを見ても美味しそうで……」
俺の問い掛けに、二人が本を手に苦笑を零しながら返事を返してくる。
あれ?去年もその台詞聞いたように思うのは、俺の気の所為だろうか?
「えっと、今年もみんなにチョコ渡すんだよね?それは、学校で渡すの?」
「うん、風紀委員もバレンタインだけは大目に見てくれるから、学校で渡そうかなぁと思ってるんだけど……」
「私は、学校が違うので、お家にお届けしようと思ってます」
なら、二人が誰にチョコを渡すのかを聞き出す必要がる。
そう思って問い掛ければ、二人がそれに答えてくれた。
確かに、ハルちゃんは学校が違うから、みんなに配るのは放課後になるだろう。
それから、京ちゃんはやっぱり学校で渡すみたいだ。
なら、ラッピングとか出来るのがいいよね?
ハルちゃんは、ツナとリボーンに渡すんだろうから……
「そうか、なら……ハルちゃんは、これなんてどうかなぁ?」
「チョコラスクですか?」
「うん、甘い物がダメなツナでも結構こう言うのは食べるんだ」
「そうなんですか?!なら、それにします!!」
本を開いてハルちゃんに差し出して言えば、不思議そうな顔をして見上げてくるので、頷いてツナ情報を教えてあげる。
カリカリになるラスクの歯応えは、ツナも好んで食べるんだよね。
俺が前に作ったモカラスクは、結構好評だった。
作るものが決まったハルちゃんが、嬉しそうに材料を選んでいるのを横目に、今度は京ちゃんの分を考える。
京ちゃんは、結構料理をする方なので、少し難しくても大丈夫かな?
ケーキでも小分けにしてラッピングすれば、可愛く渡せるしね。
「京ちゃんは、ちょっと冒険して、コーヒーのガトーショコラ作ってみる?」
「ガトーショコラかぁ……うん、頑張ってみようかな」
俺の質問に頷いた京ちゃんは、早速ハルちゃんに続いて材料を集め始めた。
それを見ながら、俺もその横でみんなにプレゼントするチョコレートを作ろうかなぁと、本を眺める。
去年は、みんなにプリンを上げたので、今年は何にしよう。
ペラペラと本を捲っていれば、一つのページで手が止まる。
これ、リボーンとか好きそうだなぁ……うん、俺はこれにしよう。
俺が選んだのは、エスプレッソチョコケーキ。
後は、ちょっと変わったところで抹茶のガトーショコラかな?
京ちゃんと被るけど、味がまた違うから大丈夫。
こっちは、京ちゃん達が帰った後で作ればいいだろう。
みんなにプレゼントするんだから、秘密にした方がいいよね?
「さんも、作るんですか?」
「うん、一緒に作らせてね」
「楽しみだね」
俺も一緒に作ると言ったら、何故か二人が嬉しそうな表情で返してきた。
あれ?何で楽しみなんだろう??
それから、二人にアドバイスをしながらチョコレートのお菓子を作った。
二人とも一生懸命作っていたから、とっても上手に出来たので、後はそれをラッピングする。
ハルちゃんは見えるラッピングで、透明フィルムを使って可愛くアレンジ。
サクサクのラスクは、チョコだけじゃ物足りないと言うので、前に俺が作ったモカラスクも一緒に作ったので2色のカラーが見えるように包装する。
京ちゃんはケーキだから、切り分けて一つ一つに下紙を準備してその上に乗せ、紙袋に入れてレースのコースターをアクセントに細めの紐で結んで出来上がり。
「さんは、ラッピングしないんですか?」
「うん、これは家用だから、みんなに配るのはこれから作るよ。だから、楽しみにしててね」
「えっ?!まだ作るんだ!すごいね、くん」
俺は出来上がったケーキをそのまま片付けていれば、それを不思議に思ったハルちゃんが質問してくるのに、笑顔で返せば京ちゃんが感心したように返してくる。
凄いのかなぁ?
良く分からないけど、別段苦に思わないんだけど……
みんなが喜んで食べてくれるのは、作った者にとっては、本当に嬉しい。
だから、作るのは好きなんだよね。
みんなが食べてくれた時の顔を思いながら作るのは、とっても楽しいから
「作るのは楽しいし、みんなが喜んでくれるのが嬉しいんだ」
「さんは、本当にお優しいですね」
素直に俺の思っている事を口に出したら、何故かハルちゃんに感動されてしまった。
俺、優しいのかなぁ?
自分が好きでしていることだから、優しいとは思わないんだけど
どちらかと言えば、自己満足と言うかなんと言うか……
あれ、そう考えると俺って酷いヤツのような気がする。
ごめんね、みんな、何か色々押し付けて……
「終わったみたいね」
「あっ!お母様です、すみません、キッチンお借りしちゃって」
「いいのよ、女の子が居るのってとっても華やかですもの。それで、みんなちゃんと作れたのかしら?」
「はい、くんのお陰でちゃんと出来ました」
何だか自分で考えた事に落ち込んでいれば、母さんがキッチンへと入って来る。
それにハルちゃんと京ちゃんが返事を返してる声が聞こえてきたけど、俺は何も返す事が出来なかった。
俺、みんなに喜んで貰えるとか、そんな事を思ってお菓子作ってたんだけど、本当は自分の気持ちを勝手に押し付けていただけなのかもしれないなぁ。
「ちゃん?」
考えれば考えるほど、落ち込んでいた俺は、心配そうな声で名前を呼ばれて現実へと引き戻される。
「あれ?」
「もしかして、疲れてしまわれたんですか?」
「くん、大丈夫?」
顔を上げれば、母さんやハルちゃん達が心配そうに俺を見ていた。
どうやら、ちょっと前から名前を呼んでいたみたいだ。
「ご、ごめん、ちょっと考え事してて……疲れたとかじゃないから、心配しないでね」
心配そうな3人の視線を受けて、俺は慌てて笑顔を作ってみんなを安心させようと思ったんだけど、それでもみんなの視線は心配の色を移していた。
俺、そんなに心配掛けるような顔してたんだろうか?
「ほ、本当に大丈夫だよ。ほら、明日みんなに渡すのはどんなのにしようかを考えていただけだから!!」
だから、慌てて言い訳の言葉を口に出せば、みんなが少しだけ安心してくれた。
「疲れてるなら、無理して作らなくていいよ」
「そうですよ!さんが作ってくださるお菓子は楽しみですが、さんの体調が一番なんですから!!」
それから、心配そうに京ちゃんとハルちゃんがしっかりと言ってくれる。
でも、ハルちゃんが言ってくれたその言葉が、俺の心の不安を少しだけ浮上させてくれた。
「うん、有難う、二人とも」
俺の作るお菓子を楽しみにしてくれているって言われたのは、俺が自分の作った物をみんなに押し付けていた訳じゃないんだと、そう思わせてくれたから
「でも、本当に疲れてる訳じゃないから大丈夫だよ。俺がみんなに食べて貰いたいから、作るんだ。有難うって気持ちを込めて……」
だから、みんなに作りたいってそう思う。
そう言った俺に、京ちゃんとハルちゃんは、嬉しそうに笑ってくれた。
うん、その笑顔が俺は好きだから、みんなのその笑顔を見るために作ってもいいかなぁ?
「ふふ、ちゃんの作るお菓子、私も大好きよ。だから、何時も作ってくれて有難う」
ちょっとだけ不安に思った俺は、そう言って後ろから抱き締めてくれた母さんの言葉に、また救われる。
俺の作るお菓子を好きって言って貰えるのは、本当に嬉しい。
「明日のお菓子も楽しみにしててね」
だからこそ、笑顔で言う事が出来た。
俺の作る物が好きだと、楽しみだと言ってくれる人達が居てくれるから
ハルちゃん達が帰ってから、俺はみんなに渡すケーキを作った。
本当はホールで作ろうと思ったんだけど、プレゼントするんだからってカップケーキで作ることにした。
みんなに、俺と一緒に居てくれる事を、心から感謝の気持ちを込めて
でも、それを作ってから、ツナに怒られた。
何でって、全然足の事を気にしないで作業に没頭していたから……
足のマッサージして貰いながら、俺が今日こんな風に思った事を話したら『馬鹿だね』って笑われてしまう。
「押し付けてなんてないよ。みんな、が作ってくれるお菓子が好きで、本当に美味しいって思ってるんだからね。そんな事考えるなんて、本当に馬鹿だよ」
うっ、確かに、そうかもしれないけど、何度も『馬鹿』って、酷いです。
だって、そう考えちゃったんだもん。
俺、馬鹿だから……
「でも、お菓子を作ってくれるのは嬉しいんだけど、今度こんな無茶な事したら、お菓子作りを禁止するからね」
「……ごめんなさい……ツナ」
「んっ?」
何度も馬鹿って言われて落ち込んでいる俺に、ツナがしっかりと釘を刺してくる。
俺はそれに素直に謝罪の言葉を返してから、俺の足をマッサージしてくれているツナの名前を呼んだ。
そうすれば、ツナが聞き返してくる。
「……有難う……」
「………どういたしまして」
それから、小さな声で感謝の気持ちを伝えれば、ツナから返ってきたのは少しだけ呆れたような返事だった。
バレンタインデーに、みんなに感謝の気持ちを伝える事が出来たのは、きっとツナやみんなが居てくれたから
だから、俺はこれからも、みんなにその気持ちを伝えていければいいなぁとそう思う。