|
「ヤマトが、熱を出したんですか?」
ヤマトの父親からの突然の電話。
それは、自分の親友でもあり、そして一番大切な人が熱を出して倒れてしまったと言う知らせ。
『そうなんだ。私も、そばに居てやりたいんだが、急ぎの仕事があって、今から局の方に行かなきゃいけない。こんな事を太一くんに頼むのは申し訳ないんだが、ヤマトのこと、お願いできないかな?』
「俺なんかで、いいんでしたら……」
申し訳なさそうに言われるその言葉に、太一は躊躇いながらも返事を返す。
自分とヤマトの関係は知らないはずなのに、こんなお願いをされると言うのは、信頼されているという事。
少なくとも、悪い印象は与えていないと言う事だろう。
だから、頼られて嬉しいと思ってしまうのは止められない。
『引き受けてくれるかい?それじゃ、親御さんには、私の方から話をした方が……』
「大丈夫ですよ。説明すれば、分かってくれますから…。それに、そちらには何度もお邪魔してますし」
『そうかい…それじゃ、頼むよ』
ほっとしたような口調の相手に、太一は頷いて返す。
そして、電話を切ってから、両親にその事を伝えてた。
そうすれば、逆に母親の方が心配してお見舞いと称した果物や、多分何も食べていないだろうとお弁当まで準備してくれる。
忙しそうに動いている母親を見詰めていた太一は、ソファに座って不機嫌そうにTVを見てい妹に気が付いて、その顔を覗き込んだ。
「どうかしたのか、ヒカリ?」
「なんでもない……おじさんが待ってるんでしょう?早く、行かなきゃ……」
母親の準備してくれたお弁当を受け取って、無理やり自分に押し付けると、ヒカリはまたソファに座ってその視線をTVへと向けた。
「えっ?ああ……それじゃ、行って来るな」
無理やり渡されたお弁当と、不機嫌なのが直ぐに分かるような送り出しの言葉に、疑問を感じながら、その言葉が的を得ているだけに、太一は慌てて自分が用意したカバンを持つと慌てて家を後にする。
「…折角、一緒に居られたのに、お兄ちゃんを取られちゃったから、怒ってるのよね、ヒカリは」
玄関のドアが閉まる音を聞いてから、楽しそうに言われた母の言葉に、ヒカリは言い当てられて、ますます不機嫌になる。
「本当、お兄ちゃん子ねぇ……そんなんじゃ、太一に彼女が出来た時は、大変よ」
自分の言葉に何も言わないヒカリを前に、母親は苦笑を零す。
だが、その言われた言葉に、ヒカリは盛大なため息をついた。
「……お兄ちゃんに、恋人が居る事くらい知ってる……だから、行かせたくないの……」
「ヒカリ?」
ポツリと呟かれたその言葉を聞き逃して、母親がヒカリを見る。
それに、ヒカリは苦笑を零して、再度ため息をつくのだった。
「遅くなって、すみません」
開いた玄関の先に居る人物に、頭を下げる。
「いや、こちらが無理なお願いをしたんだからね……ヤマトの奴は、今寝てるよ。食欲が無いみたいでね、まだ夕食も食べてないんだ」
ばたばたと準備をしながら言われたその事に、太一が小さく頷く。
「分かりました。何か作って食べさせます」
「すまないねぇ…」
「いえ、気にしないで下さい。おじさんも、夕食まだなんですよね?」
「ああ、私は何か弁当でも買って食べるから大丈夫だよ」
「あっ、母から、おじさんに、お弁当預かって来ましたので……持っていってください」
慌てて、無理やり持たされたお弁当をヤマト父に差し出す。
その差し出されたものに、父は一瞬驚いたように太一を見た。
「果物もありますから、皆さんで召し上がってください」
「…すまないねぇ……こっちが無理なお願いをしたのに……」
差し出されたそれを素直に受け取って、ヤマト父が申し訳なさそうに謝罪する事に、太一は笑顔を向ける。
「気にしないで下さい。ヤマト…あっ、ヤマト、くんとは、友達ですから」
ニコニコと笑顔を見せれば、父親が小さく苦笑を零す気配を感じて、太一は不思議そうに首を貸しげた。
「無理はしないでいいよ。それじゃ、ヤマトの事、お願いするね」
「はい、気を付けて、行ってくださいね」
にっこりと笑顔で自分の事を送り出してくれる太一の姿に、父親は再度ため息をつく。
「……まるで、嫁を貰った気分だな……」
渡されたお弁当を見詰めて、苦笑を零す。
だが、それが嫌な気がしない。
「……あの子なら、認めてやるしかないんだろうな……」
そして、実の息子がずっと自分に隠し事をしている事に、満足そうに頷くのだった。
「えっと、ヤマトの奴、飯食ってないんだったよなぁ……」
勝手したる状態で、太一は靴を脱ぐと、まずはキッチンへと足を運ぶ。
「って、何だ?」
そして、リビングに入った瞬間、その場のありさまに思わず声を上げて、慌てて自分の口を抑えた。
まるで強盗にでも入られたかのような状態に、ただ呆然としてしまう。
そして、自分がきた時に、ヤマトの父親がばたばたと走り回っていたのを思い出して、盛大なため息をついた。
「……そう言えば、おじさんウチの片付けしてないって言ってたよなぁ……」
目の前の悲惨な状態に、思わず盛大なため息をついてしまうのは、止められない。
「……と、とりあえず、先にヤマトが食べられそうなモノ作るか……」
現実逃避したくなる現状に終止符を打って、太一はキッチンへと足を運んだ。
そして、ヤマトが食べられそうなモノという事で、定番のおかゆを作ることにする。
「…確か、30分はかかるよな……その間に、この部屋片付けるか……」
土鍋に蓋をしてから、太一は再度ため息をついて、出来れば振り向きたくない気持ちを堪えながら、後ろの状態に疲れたように肩を落とした。
物音に、意識が浮上してくる。
父親の事を知っているからこそ、その音にヤマトは重い体をゆっくりと起こした。
「……親父の奴、また部屋を散らかして……」
「あれ?起きたのか?」
呆れながら呟いて、注意しに行こうと立ち上がりかけたヤマトは、突然開いた扉と、その掛けられた声に驚いて相手を凝視する。
「まだ寝てろよ。熱、大分高いんだろう?それにしても、こんな時期にどうして風邪ひくなんだよ」
少しだけ呆れたような口調で、そのまま部屋の中に入って来る人物を見詰めながら、ヤマトはまだ状況が分からずに、ただ呆然と相手を見詰めてしまう。
「ヤマト?」
信じられないと言うように自分の事を見詰めてくる相手に気が付いて、太一は不思議そうにその顔を覗き込んだ。
「……何で、お前が……親父は?」
「ああ、おじさんは、急な仕事とかで局の方。だから、風邪引いてるお前の看病の為に、俺が呼び出されたんだよ。分かったか?」
自分の質問に笑みを零しながら、太一は簡単に説明をする。
それに、ヤマトは納得したように小さく頷いた。
こんな時だけ、父親に感謝したくなってしまうのが、今の正直な気持ちである。
「……悪かったな…迷惑掛けて……」
内心の嬉しさを隠しながらも、ヤマトは謝罪の言葉を口にした。
その言われた事に、太一は苦笑を零して、持っていたモノを机に置くと小さくため息をついた。
「…なぁ、俺が迷惑だと、思うなんて、お前は本気で思うのか?」
そして、少しだけ怒ったように自分を見詰めながら言われたそれに、ヤマトは慌てて大きく首を振って返す。
「なら、そんな事言うなよ……そんな事よりも、飯食えるか?」
「えっ?いや、食欲は無いから……」
「無理にでも食えよ。薬も飲めないだろう?それに、風邪の時は栄養のあるもんを取った方がいいんだぜ」
にっこりと嬉しそうな笑顔で言われた事に、思わず苦笑を零してしまう。
気分は最悪なのに、幸せを感じてしまうのは止められない。
「ちょっと待ってろよvv」
言うが早いか、太一は先ほど自分が持ってきたモノに手を伸ばして、蓋を開けると小さな器に盛り付ける。
「ヤマト、ほら口あけろよ」
そして、蓮華で救ったそれを何度か息を吹きかけて冷ましてから、すっと差し出す。
「……自分で食べられる……」
嬉しそうに差し出されるそれとその差し出している相手とを交互に見詰めてから、ヤマトは小さく息を吐き出して苦笑を零した。
「いいんだよ、やってみたかったんだから、やらせろよ!」
「……『やらせろよ』って、何かエロい……」
「……本当のエロオヤジなヤマトにだけは言われたくないよなぁ……」
ため息と同時に言われたその言葉に、太一も同じようにため息をつくと呆れたような視線をヤマトに向ける。
「エロオヤジって何だよ!」
「…言葉のまんま……自覚してなかったのか?」
「するわけ無いだろう!!」
呆れたような太一の言葉に怒鳴り声を上げた瞬間、ヤマトはそのまま眩暈を起こして倒れこんでしまう。
そんなヤマトの姿に、太一は苦笑を零した。
「…お前、熱出してるの忘れてんじゃねぇか?」
ベッドに倒れこんでいるヤマトを気の毒そうに見詰めて、太一は状態を確認するようにそっと手を額に当てる。
「…かなり高いな…お前平熱低いから、辛いだろう?だから、無理にでも飯食って、薬飲んで大人しくしとくんだな」
「……だ、誰の所為でこんな状態になってるんだよ……」
「えっ?風邪ひいた自分の所為だろう?」
自分の言葉にサラリと返されたそれに、ヤマトは疲れたようにため息をつく。
「…この風邪は親父の所為なんだよ!自分の所為で風邪ひいた息子ほっといて、仕事に行くか普通?」
不機嫌そのままに文句を言うヤマトを前に、太一は思わず苦笑を零した。
「…そう言えば、この間、おじさんが風邪で寝込んでるって言ってたな……うつされたのか?」
気の毒そうな問い掛けに、頷く事で返事を返す。
「と、兎に角、飯食って寝ちまえよ。ずっと傍に居るからさぁ」
苦笑混じりに言われたその言葉に、ヤマトの機嫌が浮上してくる。
そして、今は居ない父親に素直に感謝するのだった。
「それじゃ、ヤマトは寝てろよ」
食欲が無いと言っていた割に綺麗に無くなったその土鍋を持って太一はドアへと歩いていく。
「置いとけば、後で俺が片付けるぞ」
「病人は余計な心配するなよ。部屋の方もばっちり片付けてやったからな」
ウインク付きで言われたそれに、ヤマトは物音で目を覚ましたのを思い出してすまなさそうな表情を見せる。
「親父の奴が散らかしていったんだろう……それじゃ、さっきの物音は、お前だったのか?」
「もしかして、俺が起こしちまったのか?……流石に、掃除機掛けるのはやめたんだけど、意味無かったな……」
ばつ悪そうな表情を見せる太一に、ヤマトは思わず困ったような微笑を見せた。
「まぁ、取りあえず、お前は寝てろって。家の事は俺に任せても大丈夫だからな」
笑顔のまま言われる言葉は、自分を気遣っているもの。
一番大切な人が、何よりも自分の事を気にしてくれるというのは、くすぐったくもあるが、幸せだと思えること。
扉の閉まる音と太一の姿が完全に視界から消えてしまったのは殆ど同時で、ヤマトはそれを残念に思いながらも疲れた体を休めるように瞳を閉じた。
キッチンに感じる人の気配。
その存在が嬉しくって、そして何よりも幸せなど思えるから、何も心配せずに休む事が出来る。
心地よい睡魔に誘われるように、ヤマトはそのまま夢の世界へと誘われていった。
「ヤマト」
完全にヤマトが夢の世界の住人となった頃、全ての片づけを終わらせて、太一がその部屋に入った瞬間慌てて口に手を当てる。
眠っていると分かるその相手に、太一は思わず笑みを零す。
「……全く、風邪引いてる時くらい、俺に甘えてくれてもいいと思うんだけどなぁ……」
自分ばかりが相手に頼っているように思えるからこそ、そう思う。
大切だからこそ、頼ってもらいたいと思うのは、贅沢な望みなのだろうか?
汗で張り付いた前髪にそっと手伸ばして、太一は小さくため息をつく。
「……お休み、ヤマト……早く、風邪治せよ」
幸せそうな表情で眠っている相手の唇に、そっと触れるだけのキスを送る。
相手が、起きている時には絶対に出来ない、自分からのキス。
「……ずっと、一緒に居るからな……」
うっすらと汗をかいているのをタオルで拭きながら、太一は眠るその姿を嬉しそうに見詰めるのだった。
− お ま け −
それから直ぐにヤマトの風邪は全快。
その代わりとばかりに、今度は太一が熱を出してしまった。
「……なんで、お前が風邪引くんだ?」
「…一緒に居たからだろう…」
見舞いに来てくれた相手の顔が見れずに、太一はヤマトから顔を逸らして返事を返す。
「…何で、俺の顔見ないんだよ?」
太一の態度に不機嫌そうな声が質問をしてくるのに、太一は慌てて大きく首を振る。
「な、何でもないに決まってるだろう!だから、風邪は空気感染で……」
「……そうか、あくまでもそんな態度をとるんなら、考えがあるぞ」
「な、なんだよ、俺は病人だぞ!」
「勿論直ってからだ。覚悟しとけよ」
嬉しそうな笑顔と共に言われた言葉に、太一は複雑な表情を見せた。
本当の事など絶対に言えない。
『お前にキスした所為だなんて、絶対に言える訳無いだろうが!!』
心の中で文句を言っても、誰にも聞こえるはずは無し。
その事実は、太一の心の中にだけにある真実である。
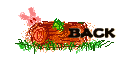
はい、44000HITリクエストでございます。
リクエスト内容は、風邪を引いたヤマトさんを太一さんが看病する。
なのですが、これで大丈夫でしょうか??
またしても、リクエストに失敗しているような気がしてなりません。
と、言うより失敗ですね……xx
メカロ皇月様、折角のリクエストが、駄文となってしまいまして、本当にすみません(><)
そして、キリ番&リクエスト本当に有難うございました。
|