 |
 |
| バスフィッシング用語 |
| 2011. 5.21のボキャブラリー数 76 2011. 5.28のボキャブラリー数 194 2011. 6.17のボキャブラリー数 375 2011. 6.23のボキャブラリー数 600 2011. 7. 8 のボキャブラリー数 672 |
| アーキーヘッド(arky head) |
ジグヘッドの形状の一種。 |
| アーム(arm) |
| スピナーベイトのワイヤ(針金)の部分。 |
| アイ |
| (1)プラグやフックなどラインを結ぶためのリング部分 (2)ルアーの目のこと |
| IGFA(アイジーエフエー) |
| 国際ゲームフィッシュ協会の略称(International Game Fish Association)。釣りを良識と秩序ある健全なスポーツとして発展させるために、国際ルールに則った釣魚記録の認定を行っている。1939年設立。設立にはあのアーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Miller Hemingway)も関わっている。 |
| アウトサイド(outside) |
| 外側のこと。川が曲がる部分は外側をアウトサイド、内側をインサイドという。ウィードラインの場合は岸側をインサイド、沖側をアウトサイドという。 |
| アウトサイドエッジ(outside edge) |
| ウイードなどショアと並行に存在するカバーやストラクチャーの沖側の切れ目のこと。 |
| アウトサイドベンド(outside bend) |
| 河川がカーブしている部分の外側のこと。水が良く当たる部分なので深く掘れている。 |
| アウトバーブ(out barb) |
カエシが外側にあるフックのこと。 |
| アウトレット |
| 流れ出し。湖や沼などの止水域から水が流れ出す場所のこと |
| アオコ |
富栄養化が進んだ湖沼において異常繁殖した微細藻類のこと。また、異常繁殖した微細藻類により水が抹茶のような色になること。アオコが発生すると水中の溶存酸素が低下し、水も悪くなるため魚の活性が落ちる。 |
| 赤星鉄馬(あかぼしてつま) |
| 1925年、アメリカから神奈川県芦ノ湖にブラックバスを日本で初めて移植した人物。1883年生まれ。父、赤星弥之助は貿易商として巨万の富を築き、鉄馬は18歳で当時としては珍しいアメリカ留学をする。アメリカの生活でブラックバスを始めとするスポーツフィッシングに出会い、27歳で結婚、日本に帰国し実業家になった後、日本のスポーツフィッシングの普及を夢見てブラックバスをアメリカから移植した。 |
| アキュラシー(accuracy) |
| 正確さのこと。キャスト精度(思ったところにキャストできる正確さ)のことを指す。 |
| アクション(action) |
| ルアーの動きのこと |
| 朝マズメ |
| 日の出前後の薄暗い状態のこと。一般的に魚の活性が高い時間帯と言われる。 |
| 浅溝スプール |
スプールの溝が浅く糸巻量が少ないもの。スプール径が大きいので糸クセが付きにくい、ラインを巻いた時のスプール重量が軽くなりベイトリールの場合よくルアーが飛ばせる、無駄なラインを巻く必要がない、といったメリットがある。 |
| 葦(アシ) |
平地の湖沼の岸よくみられるイネ科の水生植物。ヨシともいう。 |
| アシストフック(assist hook) |
スピナーベイトなどに付ける補助のフックのこと。フッキング率を上げるために装着する。トレーラーフックともいう。 |
| 葦原(アシハラ) |
| 葦(アシ)が群生しているエリアのこと。 |
| アタック(attack) |
| 魚がルアーに攻撃してくること。ルアーに食いついてくること。 |
| アタリ |
| 魚がエサやルアーに食いついた時に、ウキやロッドに感じる魚の反応のこと。 |
| アップクロス(up cross) |
| 川の流れに対して、下流から上流に向かってキャストすること。アップストリームともいう。 |
| アップストリーム(up stream) |
| 川の流れに対して、下流から上流に向かってキャストすること。アップクロスともいう。 |
| アトラクター(attractor) |
| 魚を引付ける匂いの薬品。集魚剤のこと。ルアーに吹き付けて食い込みを良くしたりルアーをくわえる時間を長引かせる効果がある。フィッシュアトラクターともいう。 |
| 穴釣り(あなづり) |
| テトラの隙間にルアーを落とし込む釣りのこと。 |
| 穴場(あなば) |
| 人にはあまり知られていない魚が良く釣れる場所のこと。 |
| アピール(appeal) |
| ルアーが魚を引き付ける力のこと。派手な動き、色のことをいう。 |
| ABU(アブ) |
| 元々はスウェーデンのリールメーカーであったが、現在はアブ・ガルシア社という名前でアメリカのピュアフィッシング社の傘下にある。1980年代前半以前にバスフィッシングを始めたバサーにとってはABU社のリールは憧れの存在で、まさにベイトリールの代名詞的な存在であった。1982年にアメリカでABU社のリールの代理店を務めていたガルシア社が倒産。アメリカ市場を失うのを恐れABU社はガルシア社を買収し、アブ・ガルシア社と社名を変更したが、その後、日本製リールの台頭や様々な買収劇に翻弄され、かつての輝きを失ってしまった。しかし、1982年までのABU社としてのリールは未だにオールドリールとしての価値が高く、往年のファンの憧れの存在であり続けている。 |
| アフタースポーン(after-spawn) |
| バスの産卵が終了したあとのしばらくの間のこと。産卵を終えたメスや卵を守って孵化させたオスがスポーニングエリアから若干深い場所で産卵の疲れを癒している期間を指す。 |
| アブレ |
| 魚が釣れないこと。ボウズ、オデコと同意語。 |
| アプロ−チ(approach) |
| バスがいる場所までの工程、道筋のこと。「岸からアプローチする」、「静かにアプローチする」など |
| アベレージサイズ(average size) |
| その湖で釣れる平均的なバスの大きさのこと。 |
| アルミボート(alminum boat) |
アルミニウム製のボートのこと。底がV字状のVハルと四角いジョンボートがある。 |
| 合わせ(アワセ) |
| 魚をかける動作。アタリがあった時に竿をぐいっと引付けてフックを魚の口に貫通させる動作のことをいう。 |
| アワセ切れ |
| アワセた瞬間にラインブレイク(ラインが切れる)してしまうこと。 |
| アンカー(anchor) |
| 船を動かないように固定するための錨(いかり)のこと。 |
| アングラー(angler) |
| 釣り人のこと。 |
| アンダーウォーター(under water) |
| 水中。一方、水面はトップウォーター(top water)。 |
| アンダーショットリグ(under shot rig) |
| ダウンショットリグの項参照。常吉リグ、ドロップショットリグとも言う。 |
| EVA(イーブイエー) |
ロッドのグリップの素材として使われている材質の名前。EVA樹脂はエチレン・酢酸ビニル共重合樹脂で、水、紫外線に優れた安定性があると同時に、ゴム弾性、柔軟性、強靭性、低温特性、耐候性など多くの優れた特性を備えている。黒く固いスポンジのような素材はEVAである。 |
| 居食い |
| 魚がルアーを食ってそのまま動かないこと。アタリが伝わりにくい。 |
| 一文字(いちもんじ) |
| 岸と並行に消波を目的に設置された構造物。一文字テトラなど。 |
| 居着き |
| 魚が特定の場所に居続けること。一方、動き回ることは回遊という。 |
| 糸フケ |
| 糸がたるんでいる状態のこと。ラインスラックともいう。 |
| 糸巻量 |
| リールのスプールにラインを巻く適正の量、目安の量のこと。リールにとってラインの強度(または太さ)により糸巻量は変わってくる。糸巻量を無視してラインを少なく巻くとキャストの飛距離が伸びなかったり、巻きすぎたりするとラインがからんだりといった不具合がおこる。ラインキャパシティー(line capacity)ともいう。 |
| イミテーション(imitation) |
| 似せること。形や動きをエサになるものに似せることをいう。 |
| イモグラブ |
テールをちぎったグラブのこと。イモのような形をしていることから命名された。 |
| 入れ食い |
| ルアーをキャストすれば魚がヒットする状況。ワンキャストワンフィッシュともいう。 |
| インサイド(inside) |
| 内側のこと。川が曲がる部分は外側をアウトサイド、内側をインサイドという。ウィードラインの場合は岸側をインサイド、沖側をアウトサイドという。 |
| インジェクション(injection) |
| プラスチック製品を作る製法の名前で射出成型のこと。ドロドロに溶かした樹脂を金型に注入して冷やす方法のことである。ソフトルアーもインジェクションで作られる。 |
| インターセクション(intersection) |
| 交差点という意味。複数の川が合流する場所をいう。 |
| インチワッキー |
| ラウンドタイプのジグヘッドを使用したワッキーリグのこと。 |
| インディアナブレード(indiana blade) |
スピナーベイトのブレードの形状の一種。コロラドブレードより細長い形状をしたブレード。 |
| インビジブル(invisible) |
| 目に見えない、という意味。水の中に沈んでいて目に見えないものを指す。「インビジブルストラクチャー」など。一方、目に見えるものはビジブル(visible)。 |
| インレット |
| 流れ込み。湖や沼などの止水域に水が流れ込んでいる場所のこと。バックウォーターとも言う。 |
| ウィード(weed) |
藻のこと。キンギョ藻、フサモ、エビモなど水中に沈んでいる藻をウィードという。一方、ヒシモやハスなど水面に葉を出す水草はリリーパッド(lily pad)、葦(アシ)やガマなど岸に生えている水生植物をリーズ(reeds)という。 |
| ウィードエリア(weed area) |
| ウィードが生えている場所のこと。 |
| ウィードガード(weed guard) |
| ウィードが引っかからないようにフックついているガードのこと。 |
| ウィードベッド(weed bed) |
| ウィードが密生して生えている場所のこと。 |
| ウィードポケット(weed pocket) |
| ウィードが密生して生えている場所にぽっかり空いた空間。隙間のこと。 |
| ウィードレス(weedless) |
| ウィードにひっかからないこと。その構造のこと。フックにガードがついていたり、針先を隠したりする工夫のことをいう。 |
| ウィグリング(wiggling) |
| クランクベイトやミノーを正面から見た時にボディーを左右に倒すように傾く動きのこと。ローリング(rolling)ともいう。 |
| ウイローブレード(willow blade) |
スピナーベイトのブレードの形状の一種で流線型のものを指す。 |
| ウイローリーフ(willow leaf) |
| スピナーベイトのブレードの形状の一種で流線型のものを指す。ウイローブレードのこと。 |
| ウィンディー・サイド(windy side) |
| 風が当たる場所のこと。風が当たることにより、エサが吹き寄せられたり、溶存酸素が増えたり、水が動いたりすることによってバスの活性が上がったり、バスが集まったりするため、絶好のポイントになることがある。 |
| ウエーダー(wader) |
釣り用の腰や胸まである長靴。膝や腰まで水の中に入って釣りをするための長靴。 |
| ウエイイン(weight in) |
| バストーナメントで魚を検量のために持ち込むこと。 |
| ウエイト(weight) |
| (1)オモリのこと。 (2)バスフィッシングトーナメントで釣り上げたバスの重量のこと。 |
| ウェッピング(wepping) |
| ルアーを上方にキャストし、葦(アシ)やガマなどの水生植物の真上からルアーを水の中に放り込むキャスト方法。 |
| ウォーキング・ザ・ドック(walking the dog) |
| ペンシルベイトのアクションの一種で頭を上下に動かしつつ左右にスライドするアクションのこと。犬が歩くのに似ているためこの名がついた。 |
| ウォーターメロン(watermelon) |
| ソフトルアーのカラーの一種で深緑のこと。 |
| ウォブリング(wobbling) |
| クランクベイトやミノーを真上から見たときにヘッドやテールを左右に振る動きのこと。 |
| 浮き草 |
| 土の中に根を張らず、水面に浮いている水草のこと。ウキクサやホテイアオイなど。 |
| 浮き桟橋 |
水の上に浮く構造の桟橋のこと。水の増減があっても使うことができる。 |
| ウキ止めゴム |
本来は中通しのウキを固定するためのゴムだがバスフィッシングではシンカーを固定するために使用する。 |
| 馬の背(うまのせ) |
| 岬が水中にそのまま伸びた地形のこと。馬の背のように水中で盛り上がった部分。 |
| エア抜き |
| ディープエリアからバスを釣り上げると、水圧の高い場所から抜きあげられたバスの浮き袋が膨張してしまう。その浮き袋のガスを体の外側から注射針を刺して抜くことをエア抜きという。 |
| SiC(エスアイシー) |
シリコンカーバイド(silicon carbide)の略でファインセラミックのこと。ロッドのガイドの材質として使われる。割れにくい、熱に強い、滑りやすいといった特徴がある。 |
| エッジ(edge) |
| 端部のこと。ウィードやアシの切れ目の部分。 |
| FRP(エフアールピー:Fiber Reinforced Plastics ) |
| FRPはFiber Reinforced Plasticsの略でボートの素材である。FRPはFiber(繊維)の違いによりいくつか種類があるが、ボートに使われているものはガラス繊維(glass fiber)に樹脂を溶かしこんで固めたものである。 FRPは軽量、対候性・耐熱性・耐熱性に優れている、いろいろな形状のものが作れる、といった利点があり、航空宇宙、自動車、建築など様々な分野で使われている素材である。。 |
| FLW tour(エフエルダブリューツアー) |
| アメリカのバスフィッシングトーナメントツアーのこと。オペレーションバスが前身組織であるが、1996年にオーナー変更と共にFLW Outdoorsに名称変更した。B.A.S.S.と人気を二分するトーナメントである。FLWはレンジャーボートの創設者であるフォレスト・L・ウッド(Forrest L. Wood)を略したもの。 |
| エラ洗い |
バスやスズキ(シーバス)などが水面で頭を左右に振って暴れること。フックが外れやすいので注意をする。 |
| エリ |
魚を獲るために水中に仕掛けた罠(ワナ)のこと。春に魚が浅場に上がってくる性質を利用し、魚を「つぼ」と呼ばれる狭い空間に誘導する漁のこと。魚を誘導するために打った杭がバスの絶好のポイントになるが、根掛かりしたルアーなどが漁の邪魔になるので漁をしているエリは釣り禁止である。 |
| エレキ |
| エレクトリックモーターのこと。エレクトリックモーターの項参照。 |
| エレクトリックモーター(electric moter) |
ディープサイクルバッテリーの電気で動き、ボートをゆっくりと静かに移動させるためのモーター。 |
| エントリー(entry) |
| ウエーダーを履いて水の中に入ること。また、フローターで入水すること。 |
| オーバーハング(over hung) |
木が覆いかぶさっている場所のこと。 |
| オーバーヘッドキャスト(over head cast) |
| ロッドを頭の真上を振りぬいてキャストするフォームのこと。 |
| オープンウォーター(openwater) |
| 開けた水域。障害物がなにもない場所のこと。 |
| オールドタックル(old tackle) |
| 昔の釣り道具のこと。それらを収集したり、使ったりする愛好家がいる。特に60年代以前のタックルは希少価値もあり人気がある。 |
| オイカワ |
コイ科の淡水魚。バスのベイトフィッシュである。オスは緑と赤の綺麗な婚姻色を発する。 |
| 追い食い |
| ルアーを食い損ねたバスが、そのままルアーを追って食いつくこと。 |
| オエオエ棒 |
魚の喉の奥に刺さったフックを外すための道具のこと。フックディスゴージャーともいう。 |
| オオクチバス |
| ブラックバスの呼び名の一つ。ブラックバスの正式な名称はノーザンラージマウスバス。ブラックバスの呼び名としてはその他に、大口黒鱒(おおくちくろます)、ラージマウスバス、ラージなど。 |
| 大潮(おおしお) |
| 月は地球の周りを回りながら、地球に対して引力の影響を及ぼしている。この影響により海水面が盛り上がる、つまり、海水が月に引っ張られ潮の満ち引きが発生する。また、地球は太陽の周りを回っており、太陽は地球に対して引力及び遠心力の影響を及ぼしている。月、太陽、地球の位置関係により地球への月、太陽の引力や太陽の周りを回る遠心力の影響を強めあったり打ち消しあったりしており、潮の満ち引きにも干満の差が大きい時、小さい時がある。潮の干満が一番大きい潮回りを大潮という。潮回りによって大潮、中潮、小潮、長潮、若潮がある。また、ブラックバスは春の産卵を大潮の時に行うと言われている。 |
| オカッパリ |
| 岸からバスを釣ること。同じ読みで陸っぱりとも書く。 |
| オクラホマブレード(oklahoma blade) |
スピナーベイトのブレードの形状の一種でウイローリーフを短くした形状のブレードのこと。 |
| オダ |
| 魚を集めるために枝を沈めたもの。ブラックバスの絶好のポイントとなる。アメリカではブッシュパイル(bush pile)と言う。 |
| 落ち込み |
| 浅いところから急激に深くなる地形のこと。同じ意味の言葉としてブレイクライン(break Line)、ドロップオフ(drop off)、カケアガリがある。 |
| オデコ |
| 魚が一匹も釣れないこと。ボウズともいう。一匹も釣れないことをデコるという。 |
| オフショア(off shore) |
| 沖のこと。岸から離れた場所。一方、岸はショア(shore)。 |
| オフセットグリップ(off set grip) |
ロッドのグリップがブランクと分離するタイプのもの。一方、グリップとブランクが一体になっているものをブランクスルーという。 |
| オフセットフック(off set hook) |
フックのシャフトがクランクしている針先がソフトベイトに隠れるようにセットできるフックのこと。フックのシャフトがまっすぐのストレートフックに比べると根掛かりしにくくソフトベイトの姿勢もまっすぐになる。 |
| オフリミット(off limit) |
| バスフィッシングのトーナメントで釣りをしてはいけない期間や釣りをしてはいけない場所のこと。 |
| オンス(ounce、oz) |
| ルアーの重さの単位で1オンスは28.349523125グラムである。 |
| ガーグリング(gurging) |
| スピナーベイトの速引きのこと。ブレードが水面を飛び出すくらいに高速で引いてくること。バジング(buzzing)ともいう。 |
| カーブフォール(curve fall) |
| ラインを張った状態で手前にカーブさせながらルアーを沈めること。一方、ラインを緩めた状態でバーチカル(垂直)にルアーを沈めることをカーブフォールという。 |
| カーボン(carbon) |
| ロッドの素材の一種で炭素繊維のこと。軽くて反発力が強い。ロッドで一番、一般的な素材である。カーボングラファイトともいう。 |
| カーボングラファイト(carbon graphite) |
| ロッドの素材の一種で炭素繊維のこと。軽くて反発力が強い。ロッドで一番、一般的な素材である。単にカーボンともいう。 |
| カーボンロッド(carbon rod) |
| カーボン素材のロッドのこと |
| カーリーテール(curly tail) |
ソフトルアーのテールの形状でカールしているものを指す。 |
| ガイド(guide) |
| (1)湖で釣れるポイントに案内し、釣れるルアーやメソッドを教えてお客さん(ゲスト)にバスを釣らせる案内人のこと。フィッシングガイドとも言う。 (2)ロッドに取り付けられているラインを通すための輪のようなパーツのこと。ガイドの材質としてはSiC(エスアイシー))、ゴールドサーメット、ハードガイドなどがある。 |
| 回遊 |
| 魚が泳ぎまわること。一定場所に留まらず動き回る性質の魚を回遊魚という。 |
| カウントダウン(count down) |
| シンキングルアーが着水したあとに沈んだ時間を数えること。ルアーが1秒で何メートル沈むかを知っていればカウントダウンすることにより何メートルの深さを探れるか計算することができる。 |
| カエシ |
フックの部位でフックポイント(フックの先端部分)にあり、かかった魚が逃げないようにするための棘(トゲ)のような突起部分のこと。バーブ(barb)ともいう。 |
| カケアガリ |
| 浅いところから急激に深くなる地形のこと。同じ意味の言葉としてブレイクライン(Break Line)、ドロップオフ(Drop off)、落ち込みがある。 |
| 型(かた) |
| 魚の大きさのこと。大きい魚のことを良型(りょうがた)という。 |
| 活性 |
| バスがルアーに反応する能力のこと。「今日はバスの活性が高い」など |
| カバー(cover) |
水中や水上の構造物のこと。 |
| カベラス(Cabelas) |
アメリカの釣り具通販大手。ハンティング用品やキャンピング用品も扱っている。日本からの個人通販での輸入も可能である。 |
| かみつぶしオモリ |
ラインを挟む割れ目の入ったオモリ。スプリットショット、ガン玉ともいう。 |
| カレント(current) |
| 流れのこと。「ダムが放水されてカレントが発生した」など |
| 冠水植物 |
水の中に浸かっているように生えている植物。葦(アシ)やガマなど。陸上に生えている植物が増水などによって一時的に水に浸かっているものも冠水植物という時もある。 |
| ガン玉 |
ラインを挟む割れ目の入ったオモリ。かみつぶしオモリ、スプリットショットともいう。 |
| キーパー(keeper) |
| トーナメントで検量に持ち込むことができる魚のこと。トーナメントルールがキーパーサイズ30センチの場合、30センチ以上の魚をキーパーと言い、30センチ未満の魚をノンキーパーという。 |
| キーパーサイズ(keeper size) |
| トーナメントの検量に持ち込める魚の大きさ。 |
| 聞く |
| ブラックバスがルアーに食いついたかどうかラインを張って確認すること。 |
| 聞きアワセ |
| ブラックバスがルアーに食いついたかどうか確認するようにラインを張りながらゆっくり合わせること。スイープフッキング(sweep hooking)ともいう。 |
| 疑似餌 |
| エサに似せて魚に食いつかせるもの。ルアーやフライなど。 |
| 汽水域 |
| 川の河口部など海水と淡水が混ざった水域のこと。 |
| キャスタビリティー(castability) |
| 遠投能力のこと。遠投に優れたロッドやルアーの性能のことを指す。 |
| キャスティング(casting) |
| ルアーを投げること。 |
| キャスト(cast) |
| ルアーを投げること。 |
| キャッチ(catch) |
| 魚を捕えること。釣りあげること。 |
| キャッチ・アンド・リリース(catch & release) |
| 魚を釣り上げた後に逃がしてあげること。 |
| ギャップ(gap) |
| フックにおいてフックポイント(針先)とシャンクの隙間を指す。 |
| キャナル(canal) |
運河のこと。川と川や湖と川などをつなぐ水路のことを指す。 |
| ギヤ比 |
| ギヤ比はリールのハンドルのギヤと、ベイトリールの場合はスプール、スピニングリールの場合はローターの回転するギヤとの比率である。つまり、ハンドルを1回転させるとスプールまたはローターが何回転するかという比率である。 ベイトリールでギヤ比が4.9のリールはハンドル1回転でスプールが4.9回転し、ギヤ比7.1のリールはハンドル1回転でスプールが7.1回転する。ギヤ比が高いほど、巻き上げトルクは弱いが、ルアーを早く巻くことができる。使うルアーやシチュエーションによって使い分ける。 |
| 橋脚(きょうきゃく) |
橋の脚(あし)の部分のこと。大きなシェードを作り出し多くの魚が集まる。また水中の構造も複雑のものも多い。 |
| 魚影(ぎょえい) |
| 魚の数のこと。「魚影が濃い」は魚がたくさんいること。「魚影が薄い」は魚があまりいないこと。 |
| 魚群探知機 |
超音波を発信して湖底から反射する反射波から湖の地形や魚の有無を判別する機械のこと。液晶ディスプレーに湖や魚の有無が表示される。デプスファインダーとも言う。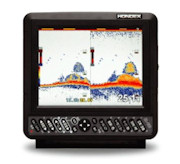 |
| 漁礁(ぎょしょう) |
| 魚を集めるために沈めたもの。或いは魚がたくさん集まっている複雑な地形や構造物のこと。 |
| 魚探(ぎょたん) |
| 魚群探知機の略称。 |
| ギル |
| ギル(gill)とは一般的には魚のエラという意味だが、バス釣りではブルーギルという魚を指すことが多い。 |
| キンク(kink) |
| ライン(釣り糸)がねじれたり折れ曲がったりする状態。ベイトキャスティング・リールでバックラッシュが発生した時やスピニング・リールで糸撚れ(いとよれ)が発生した時に、キンクが起きやすい。キンクするとライントラブルが多発し、ラインの強度も一気に落ちてしまう。 |
| 食い上げ |
| 魚がエサに食いついて上(浅い方)に動くこと。魚が食いあげると、ウキ釣りではウキが倒れ、ルアー釣りではラインがたるむ。 |
| 食い渋り |
| 魚がエサをなかなか食べない状態のこと。 |
| クオリファイ(qualify) |
| トーナメントに参加すること。参加資格を持っていること。 |
| クオリファイアー(qualifier) |
| トーナメントの参加資格を持っている人、参加者。 |
| 口を使う |
| 魚がエサを食べること。 |
| グライダーシンカー(glider sinker) |
チューブワームの中に入れる専用のシンカーのこと。 |
| グラス(glass) |
| 意味としてはガラスだがバスフィッシングではガラス繊維のロッドの素材のことを指す。グラスファイバーともいう。 |
| グラス(grass) |
| 植物のこと。水中あるいは水際に生えている植物のこと。 |
| グラスファイバー(glass fiber) |
| ロッドの素材の一種でガラス繊維のこと。カーボンに比べ粘りがあり価格が安いが、重いという欠点もある。 |
| グラスロッド(glass rod) |
| グラスファイバーを素材にしたロッドのこと。 |
| グラビングバス(grubbing buzz) |
| ノーシンカーのグラブを水面で引き波を立てて引くメソッドのこと。グラビングバスはバスプロの河辺裕和プロが名づけた造語。 |
| グラブ(grub) |
ソフトルアーの一種でずんぐりとしたボディーにカーリーテールをつけたルアーのこと。ゲーリーグラブが有名。 |
| グラファイト(graphite) |
| ロッドの素材の一つでカーボン繊維のこと。カーボングラファイトのこと。 |
| クランクベイト(crank bait) |
ルアーの種類でフグのような丸いボディーにリップがついたプラグ。左右にボディーを振りながら泳ぐ。 |
| クリーク(creek) |
小川のこと。 |
| クリーチャー系(creature lure) |
ブラッシュホグに代表される特殊な形のワームの総称。ホグ系ともいう。 |
| クリアウォーター(clear water) |
澄んだ透明の水のこと。 |
| グリッター(glitter) |
ラメのこと。ワームの中に入っているキラキラ光る金属箔のこと。フレーク(flake)ともいう。 |
| グリップ(grip) |
| ロッドの握りの部分。 |
| クリンチノット(clinch knot) |
| ラインの結び方の一種。 |
| クレイフィッシュ(crayfish) |
ザリガニのこと。またはザリガニを模したソフルアーのこと。ザリガニの呼び名は他にクローフィッシュ(crawfish)、クローダッド(crawdad)がある。一方、エビはシュリンプ(shrimp)という。 |
| クローズドフェイスリール(closed face reel) |
スプールがカバーに覆われており、ボタンを押してルアーをキャストするリール。初心者が扱いやすく、軽いルアーも投げやすいが、糸撚れが起きやすく、巻き上げ力も弱い。スピンキャストリールともいう。 |
| クローダッド(crawdad) |
| ザリガニのこと。またはザリガニを模したソフルアーのこと。ザリガニの呼び名は他にクレイフィッシュ(crayfish)、クローフィッシュ(crawfish)がある。一方、エビはシュリンプ(shrimp)という。 |
| クローフィッシュ(crawfish) |
| ザリガニのこと。またはザリガニを模したソフルアーのこと。ザリガニの呼び名は他にクレイフィッシュ(crayfish)、クローダッド(crawdad)がある。一方、エビはシュリンプ(shrimp)という。 |
| 食わせ |
| 魚の食欲をあおって誘うこと。口を使わせること。 |
| ケミホタル |
| 黄色に光る発光体のこと。夜釣りでウキが見えやすいように使ったり、ルアーに装着したりして目立つようにして使う。 |
| ゲリラ放流 |
| 外来魚を誰にも知られずに違う水域に放流すること。密放流(みつほうりゅう)ともいう。 |
| コーヴ(cove) |
ワンド。入り江のこと。意味はワンドの項参照。 |
| ゴーストカラー(ghost color) |
半透明のルアーカラーのこと。 |
| ゴールドサーメット |
ロッドのガイドの材質の一種でチタンナイトライドという金属材料のこと。SiCガイドに比べると、耐衝撃性に強い、ラインのすべりが良い、金色のため高級感がある、といった特徴がある。ただし価格は高い。 |
| コールドフロント(cold front) |
| 寒冷前線のこと。寒冷前線が通過すると天気が良くなり、気温が急激に下がり、突風が吹きやすくなる。 |
| ゴアテックス |
| ゴアテックス(Gore-Tex)はアメリカのWLゴア&アソシエイツ社が開発した防水透湿素材である。ポリテトラフルオロエチレン、ポリウレタンポリマー、ナイロンなどを組み合わせて生地を作る。防水透湿素材とは、雨のような大きい水滴は通さないが、水蒸気のように小さい水滴は通すという意味である。 防水性能しかないレインウエアだと雨は凌げるが、汗を外に出すことができずアッという間に汗びっしょりになってしまうが、防水透湿素材だと雨を凌ぎ、体から蒸発する汗(水蒸気)を外に出すことができる。ゴアテックスは防水透湿素材の代名詞的な商品である。 |
| 高気圧 |
| 周りに比べて気圧が高い部分のこと。気圧とは大気の重さによって生じる圧力で、高気圧は空気の層が厚いために気圧が高い。高気圧は一般的に雲が少なく天気が良い。高気圧が近づくと一般的に魚の活性が下がると言われている。その理由は諸説あり、太陽光が差し込み水中が明るくなるので魚の警戒心が高まる、浮き袋が縮まり動きが重くなるといったことが挙げられているが本当の理由はわかっていない。 |
| 護岸(ごがん) |
岸の泥や土が崩れないようにコンクリート化された岸のこと。 |
| コクチバス(small mouth bass) |
スモールマウスバスの日本名。ブラックバス(ラージマウスバス)に比べると口が小さいのでこの名がついた。桧原湖や野尻湖などに生息している。 |
| 5段変速 |
| エレクトリックモータのスピード調整には5段変速と無段変速の2種類が存在する。5段変速は5段階の電気抵抗を切り替えることによりスピードを変え、無段階変速は5段階のスピードに応じて電気の量を調節することによりスピードを変える。5段階変速は常に最大電流が流れているために無段階変速よりもバッテリーの消耗は激しい。無段階変速はバッテリーの消耗は少ないが、電気回路が複雑で故障が多い、価格が高いというデメリットがある。 |
| ゴボウ抜き |
| かかった魚をランディングネットなどを使わずにそのまま抜きあげること。 |
| コルク(cork) |
| ロッドのグリップの素材でコルクガシという木の樹皮を加工した素材。コルクは断熱、防音、電気的絶縁性、弾力性、耐薬品性に優れ、軽く、さまざまなプラスチック製品が開発された現在でも多方面に利用されており、ロッドのグリップの素材としても良く使われている。 |
| コルクグリップ(cork grip) |
ロッドのグリップがコルク製のもの。 |
| ゴロタ石 |
水の中に転がっているコブシ大の石のこと。その石が沈んだ場所。 |
| コロラドブレード(colorado blade) |
スピナーベイトのブレードの形状の一種で、幅の広い丸いブレードのこと。バイブレーションが強いのが特徴。 |
| コンタクトポイント(contact point) |
| バスがディープからシャローに移動する際に立ち寄る場所のこと。 |
| コンディション(condition) |
| 状態のこと。魚や釣り場の状態のことを指す。 |
| コンポジット(composite) |
| 複合や合成という意味だが、二つの素材を合わせたロッドのこと。例えばカーボンとグラスを混ぜ合わせた素材をコンポジットという。 |
| サーチベイト(serch bait) |
| 最初に投げるルアーのこと。バスの活性を探ったり、まず1匹目を釣るために最初に投げるルアーのことをいう。パイロットルアーともいう。 |
| サーフェス(surface) |
| 水面のこと。 |
| サーフェスプラグ(surface plug) |
| 水面に浮くタイプのプラグのこと。トップウォータープラグも同義語。 |
| サーモクライン(thermocline) |
| 水温躍層。急激に水温が変化する水の層のこと。例えば真夏は湖の表水温が太陽に温められて30℃近くに達するが水深が深くなるほと水温が下がっていくがある水深を境目に急激に水温が変化する。この急激に温度が変化する水の層をサーモクライン(水温躍層)という。 |
| サイト(sight) |
| 水中のバスを見ながら釣ること。サイト・フィッシングとも言う。 |
| サイドキャスト(side cast) |
| ロッドを横に振りぬいてルアーをキャストするフォームのこと。 |
| サイトフィッシング(sight fishing) |
| 水中のバスを見ながら釣ること。単にサイトとも言う。 |
| サイドプレート(side plate) |
| ベイトリールのスプールの両側にあるプレートのこと。ハンドル側のプレートの内部にはギアやメカニカルブレーキが、ハンドルと逆側のプレートの内部にはブレーキ機構が収められている。 |
| サイレント(silent) |
| ラトル(rattle)が入っていないルアーのこと。ノンラトル(non rattle)ともいう。 |
| サウスキャロライナリグ(south carolina rig) |
| シンカー(オモリ)にヨリモドシをつけその先に50〜1メートルのリーダー(ライン)とワームを取り付けた仕掛け(リグ)のこと。 |
| 先調子 |
| 穂先が曲がるタイプのロッドのアクション(曲がり具合)のこと。ファーストテーパーのロッドは先調子である。 |
| 雑魚(ざこ) |
| 雑多な小魚のこと。どうでもよい小魚のこと。 |
| サスペンド(suspend) |
| ルアーが水中で浮きも沈みもせず静止すること。その状態。水の重さは水温で変わるので、20℃の水温でサスペンドするルアーは10℃の水では浮き、30℃の水では沈んでしまう。 |
| サスペンドルアー(suspend lure) |
| 水中で浮きも沈みもせず静止するルアー。水に浮くルアーはフローティングルアー、沈むルアーはシンキングルアーという。 |
| 誘う |
| ルアーにアクションをつけて魚を誘惑すること。 |
| サブサーフェス(subsurface) |
| 水面直下のこと。 |
| サミング(thumbing) |
| ベイトタックルでキャストした時にルアーが着水する直前にスプールを親指で押さえる動作のこと。一方、スピニングタックルでキャストした時に人差し指でスプールを押さえる動作はフェザーリング(feathering)という。 |
| サルカン |
糸撚れ(いとよれ)やエサの回転を防ぐ金属製のパーツのこと。ヨリモドシとも言う。 |
| サンドバー(sandbar) |
中州。流れによって砂が堆積して浅く島のようになった場所のこと。 |
| 桟橋(さんばし) |
船に乗るために沖に向かって設置されている構造物のこと。 |
| 産卵床(さんらんしょう) |
バスが卵を産むためにオスが掘った窪地のこと。スポーニング・ベッドの項参照。 |
| シーズナル・パターン(seasonal pattern) |
| バスの季節(シーズン)的な行動パターンのこと。例えば、春はスポーニングのためにシャローに動く、夏は水温も上がり溶存酸素量も低くなるので水通しのよい岬周りに動くといったバスの季節的な動きのことをいう。このようなバスの行動パターンを元に進める釣りをパターン・フィッシングという。 |
| 時合い(じあい) |
| 魚の活性が一番高い時間帯のこと。プライムタイム(prime time)ともいう。 |
| JGFA(ジェージーエフエー) |
| 日本ゲームフィッシュ協会(japan Game Fish Association)のこと。IGFAの日本支部である。日本のゲームフィッシング振興のために1979年に設立された。日本の釣魚記録の認定などを行っている。 |
| シェード(Shade) |
| 日よけのこと。樹木や構造物など、太陽光を遮るもの。バス釣りでは影という意味で使われる場合もある。 |
| JB(ジェービー) |
| 日本バスプロ協会(Japan Bass Pro Association)の略称。1985年にJBTAとして発足したバスフィッシングのプロトーナメント団体である。 |
| JBCC(ジェービーシーシー) |
| Japan Bass Culture Clubの略称。釣り具の量販店である上州屋が設立したバスフィッシングトーナメント団体。1994年に設立され、バスバブルにのりボートでのプロトーナメントと共にアマチュアのオカッパリトーナメントが人気を博した。一時は会員数を増やしたが、バスバブルがはじけると同時に衰退。2009年に解散した。 |
| JBTA(ジェービーティーエー) |
| 1985年に発足した現JB(日本バスプロ協会)の前身団体。日本にもアメリカのような本格的なバスプロを育てるべく設立された。 |
| シェイク(shake) |
| ロッドを細かく揺さぶってワームやルアーに細かい振動を与えること。シェイキングともいう。 |
| シェイキング(shaking) |
| ロッドを細かく揺さぶってワームやルアーに細かい振動を与えること。シェイキングともいう。 |
| 仕掛け(しかけ) |
| ロッド(釣り竿)から先のライン、シンカー(おもり)、スナップ、フックの構成のことをいう。リグ(rig)ともいう。 |
| ジギング(jigging) |
| メタルジグというルアーを上下にシャクって魚を誘う釣り方のこと。 |
| ジギングスプーン(jigging spoon) |
上下にシャクってキラキラとフラッシングする動きで誘う金属製のルアーのこと。メタルジグともいう。 |
| ジグスピナー(jig spinner) |
「く」の字型のステンレスワイヤとブレードがついたルアー。ブレードの反対側にジグヘッドを装着し、スピナーベイトのように使う。 |
| ジグヘッド(jig head) |
ワームフックに鉛のオモリが頭の部分についたもの。 |
| シシィベイト(sissy bait) |
| 小さなルアーのこと。 |
| システムクランク(system crank bait) |
| いくつかの潜行深度を備えたシリーズ化されたクランクベイトのこと。日本ではスミスのハスティーがその先駆けだった。 |
| ジャーキング(jerking) |
| ルアーの操作方法の一種でジャークベイトを左右にダートさせること。 |
| ジャークベイト(jerk bait) |
ミノーの一種でロッドをあおると急激にダートするミノープラグのこと。ラトリンログやロングAなどが有名。 |
| シャーピン |
エレクトリックモータやボートエンジンのプロップを外すとシャフトと垂直に差し込まれている金属製のピンがある。これがシャーピンである。ボートを走行中にプロップが何かにヒットするとプロップとシャフトが強い力で締結されているとプロップはシャフトの破損につながるが、シャーピンが折れるとプロップがシャフトと空回りし、プロップやシャフトの破損を防いでくれるのである。 |
| シャイナー(shiner) |
アメリカにおけるコイ科の小魚の総称。 |
| シャッド(shad) |
シャッドはニシン科の魚の一種。 |
| シャッドテール(shad tail) |
ソフトルアーの一種で細長いボデーに直角のフィン(ヒレ)がついておりフィンを左右に激しく振りながら泳ぐルアー。 |
| シャッドプラグ(shad plug) |
シャッドに形を似せたプラグのこと。細長いミノーに対して体高があり平べったい形状の小魚に似せたルアー。 |
| シャロー(shallow) |
| 水深が浅い部分のこと。 |
| シャローウォーター(shallow water) |
| 浅い場所のこと。 |
| シャローレンジ(shallow range) |
| 湖の浅い部分のこと。シャロー(shallow)は浅場。レンジ(range)は水深の幅のこと。 |
| シャンク(shank) |
| フックの部位のことでアイ(ラインを結ぶ場所)からまっすぐ伸びた柄の部分。 |
| ジューンバグ(june bug) |
ジューンバグはアメリカの緑色のコガネムシの一種で、この色からきているルアーカラー。紫色に緑のラメが入ったカラーである。 |
| 集魚剤 |
| 魚を引付ける匂いの薬品。集魚剤のこと。ルアーに吹き付けて食い込みを良くしたりルアーをくわえる時間を長引かせる効果がある。アトラクター、フィッシュアトラクターともいう。 |
| 重心移動システム |
| ルアーに入っているウエイト(オモリ)が可動式になっており、キャストをした時には後方に移動することで飛距離がアップし、ルアーを泳がせた時に前方に移動する方式のこと |
| 浚渫(しゅんせつ・dredge) |
| 湖の底を砂利の採掘やヘドロの除去のために掘り起こすこと。浚渫跡は起伏があり、また湖底が固いのでバスが集まりやすい。 |
| ショートバイト(short bite) |
| 魚がルアーくわえてする放したり、ルアー全体を食わずにワームのテールだけ食いつくといった、合わせても針掛かりしない浅い食い方のこと。 |
| ショア(shore) |
| 岸のこと。一方、沖はオフ・ショア(off shore)。 |
| ショアフィッシング(shore fishing) |
| 岸釣り、オカッパリのこと。バンクフィッシングともいう。 |
| ショアライン(shore line) |
| 湖岸線のこと。 |
| ジョイントルアー(jointed lure) |
ボディが連結しているルアーのこと。 |
| 消波ブロック |
| 波がぶつかる場所に設置され波を弱めるためのブロック。テトラポットなどを積む場合が多い。岸と並行にブロックを並べるものを一文字(いちもんじ)という。 |
| ショルダー(shoulder) |
| ショルダーは肩という意味。カケアガリの上がりきった部分のこと。肩のような形をしている部分のためこう呼ぶ。 |
| ジョンボート(jon boat) |
底が四角い形状のアルミボートのこと。 |
| シリコンラバー(silicon rubber) |
シリコン材質のラバーのこと。ラバージグやスピナーベイトのスカートに使われる。 |
| シンカー(sinker) |
| 仕掛けやルアーを沈めるためのおもりのこと。鉛やタングステン、真鍮(しんちゅう)などの金属でできている。 |
| シンキング(sinking) |
| ルアーやラインが水に沈むこと。一方、水に浮くことはフローティング(floating)という。 |
| シンキングルアー(sinking lure) |
| 沈むルアーのこと。浮くルアーはフローティングルアー、水中で浮きも沈みもしないルアーはサスペンドルアーという。 |
| シングルスイッシャー(single swisher) |
プロペラが1枚ついているスイッシャーのこと。トップウォータープラグの一種。 |
| シングルフック(single hook) |
1本の釣り針のこと。2つに枝分かれした針をダブルフック、3つに枝分かれしたフックをトリプルフックまたはトレブルフックという。 |
| 新月(しんげつ) |
| 月は太陽の光を反射して光っているように見えるが、太陽の位置関係により月の満ち欠けがある。太陽の反射がなく、真っ黒な状態を新月という。新月は月と太陽の地球への引力を強め合う位置関係にあるため潮回りは大潮になる。 |
| スイープフッキング(sweep hooking) |
| バイトがあった時にホウキで掃くような動作(sweep)でロッドをゆっくり大きな動作で合わせること。聞きアワセともいう。 |
| 水中島(すいちゅうじま) |
| 水の中にある山のように盛り上がった地形のこと。ハンプともいう。 |
| スイッシャー(swisher) |
トップウォータープラグの一種でプロペラが回転して発生する音や波紋でバスを誘うルアー。プロップベイト(prop bait)ともいう。プロペラが1つついているものをシングルスイッシャー、2つついているものをダブルスイッシャーという。 |
| スイベル(swivel) |
ラインやエサが回転しないようにする金属製の小物。ヨリモドシともいう。 |
| スイムベイト(swim bait) |
ルアーの種類でビッグベイトとも言われる1オンスかそれ以上の大きさのあるルアーのこと。 |
| スカート(skirt) |
ラバーやシリコン製のルアーに装着するスカート。ラバージグやスピナーベイトなどに装着する。 |
| スキーイング(skiing) |
| ペンシルベイトのアクションの一種で、頭は上下に振らず左右にスライドするアクションのこと。スライディング、スキーイングともいう。 |
| スキッピング(skipping) |
| 平らな小石を水面で跳ねさせるようにオーバーハングの奥などにルアーを放り込むキャストのこと。 |
| スキニーウォーター(skinny water) |
| スキニーとは「皮のような」の意味であるが、スキニーウォーターで「浅い場所」という意味で使う。シャローウォーターと同意語。 |
| スクール(school) |
| 魚の群れ。 |
| スケーティング(skating) |
| ペンシルベイトのアクションの一種で頭は上下に振らず左右にスライドするアクションのこと。スライディング、スキーイングともいう。 |
| スタードラグ(star drag) |
ベイトリールのドラグのつまみは星のような形をしているのでスタードラグという。一方、スピニングリールのドラグのつまみはドラグノブという。 |
| スタンプ(stump) |
木の切り株のこと。ダム湖などに多く見られる。絶好のバスの付き場になる。 |
| ステイ(stay) |
| ルアーの動きを止めること。 |
| 捨て石 |
| 石が捨ててある場所。消波を目的に捨ててある場合もある。 |
| スティックベイト(stick bait) |
棒状のソフトルアーのこと。ランカーシティー社のスラッゴーなどトゥイッチすると左右にダートするソフトルアー。 |
| ステインウォーター(stain water) |
| 木の色素がしみ込んだ褐色の水のこと。 |
| ステディーリトリーブ(steady retrieve) |
| ルアーを止めずに一定の速度で巻き続けること。 |
| ストック(stock) |
| 在庫や蓄えるという意味で、バスフィッシングではバスがいること。「この場所はたくさんのバスをストックしている」など |
| ストップ&ゴー(stop & go) |
| ルアーを動かしては止めること。 |
| ストライク(strike) |
| 魚がルアーにアタックして針掛かりすること。 |
| ストラクチャー(structure) |
| 日本では水中の杭、橋、テトラなどの構造物を指すこともあるが、アメリカでは水中の地形の変化のことを指す。アメリカでは水中の構造物をカバー(cover)と表現する。 |
| ストリンガー(stringer) |
釣った魚を活かしたまま湖や川の中でキープしておくための道具。金属製のもの樹脂製のものがある。 |
| ストレートフック(straight hook) |
シャフトがまっすぐなフックのこと。ソフトベイトをセットした時にソフトベイトをまっすぐな姿勢に保ちにくいが、フッキングをした時に魚をかけやすいとされる。一方、シャフトがクランクしているタイプをオフセットフックという。 |
| ストレートワーム(straight worm) |
まっすぐ棒状の形をしたワームのこと。 |
| ストレッチ(stretch) |
| 直線コースのこと。バス釣りでは、湖のある一定区間のことを指す。「このストレッチはバスの反応が良い」など。 |
| スナッグレス(snagless) |
| 根掛かりしにくい構造のルアーのこと。 |
| スナップ(snap) |
ルアー交換を容易にする金属製の小物類。 |
| スナップスイベル(snap swivel) |
ルアー交換を容易にするための金属パーツであるスナップと、糸撚れを防ぐスイベルが連結した小物類。 |
| スパイダージグ(spider jig) |
フラグラブにジグヘッドを装着したルアーのこと。 |
| スパイラルガイド(spiral guide) |
ベイトロッドのガイドは普通、ロッドの上部に一直線に並んでいるが、スパイラル(螺旋)状に並べたガイドのこと。ブランクとラインが干渉しないのが特徴。 |
| スパイラルフォール(spiral fall) |
| ルアーがらせん状に沈んでいくこと。チューブワームの中にジグヘッドを装着した時などに、スパイラルフォールする。 |
| スピナー(spinner) |
ルアーの種類で金属製の回転羽(ブレード)がついたルアー。金属羽が回転して魚を誘う。バス釣りではあまり使われないがトラウト(マス)フィッシングでは良く使われるルアー。 |
| スピナーベイト(spinnerbait) |
ルアーの種類で金属製の回転羽(ブレード)とラバースカートが装着された金属製のヘッドが組み合わされたルアー。ブレードとヘッドがワイヤ(針金)でつながれているのでワイヤベイトとも言う。 |
| スピニングタックル(spinning tackle) |
| スピニングリールとスピニングロッドの道具一式のこと。 |
| スピニングリール(spinning reel) |
ハンドルでローターを回転させスプールにラインを巻きつけるリール。軽いルアーをキャストできる長所があるが、巻き取り力は弱い。 |
| スピニングロッド(spinning rod) |
| スピニングリールを装着するためのロッド。 |
| スピンキャストリール(spin cast reel) |
スプールがカバーに覆われており、ボタンを押してルアーをキャストするリール。初心者が扱いやすく、軽いルアーも投げやすいが、糸撚れが起きやすく、巻き上げ力も弱い。クローズドフェイストリールともいう。 |
| スプーキー(spooky) |
| 魚が臆病になっている状態のこと。 |
| スプール(spool) |
スピニングリールのパーツの名称。ラインが巻いてある場所のこと。 |
| スプーン(spoon) |
匙(さじ)のような形状をした金属製のルアー。 |
| スプラッシュ(splash) |
| ポッパーが飛ばす水しぶきのこと。 |
| スプリットショット(split shot) |
ラインを挟む割れ目の入ったオモリ。かみつぶしオモリ、ガン玉ともいう。 |
| スプリットショットリグ(split shot rig) |
| フックの手前にかみつぶしオモリをつけた仕掛けのこと。 |
| スプリットリング(split ring) |
フックとプラグのヒートンを接続するための二重のらせん状のリングのこと。フックが自由に動くためについている。またラインアイについている場合もあり、ラインアイにラインを直結するよりもプラグの動きが自由になる。 |
| スポーニング(spawning) |
| 産卵のこと。バスのスポーニング期間について、産卵の準備期間をプリスポーン、産卵中をミッドスポーン、産卵後のしばらくをアフタースポーンまたはポストスポーンと呼ぶ。 |
| スポーニングエリア(spawning area) |
| 産卵に適した場所のこと。バスのスポーニングに適した場所は、(1)湖底は泥底よりも細かい砂利や岩盤などの固い場所、(2)南向きの日光が良くあたる場所、(3)日光が届く深さ、といった場所である |
| スポーニングベッド(spawning bed) |
バスの産卵床(さんらんしょう)のこと。オスのバスはメスが卵を産むために尾びれで湖底の砂を掘り円形状の窪地を作る。ネストともいう。 |
| スポッツ(spots) |
| スポッテッドバスの略称。 |
| スポッテッドバス(spotted bass) |
ラージマウスバスの近似種で外見はラージマウスバスに良く似ているが斑点がはっきりしており、ディープウォーターを好む。遊泳力が高く良く引く。ラージマウスバスよりも小型である、などの特徴がある。日本には存在しない。スポッツと呼ぶ場合もある。 |
| スポット(spot) |
| 釣りをする場所のこと。エリアは広域の場所に対して、スポットやポイントはある特定の狭い領域や箇所として使う。 |
| スモールマウスバス(small mouth bass) |
日本名でコクチバスと呼ばれるブラックバス(ラージマウスバス)の近似種。ブラックバスよりも口が小さいのでこの名がついた。桧原湖や野尻湖などに生息している。 |
| スライディング(sliding) |
| ペンシルベイトのアクションの一種で、頭は上下に振らず左右にスライドするアクションのこと。スケーティング、スキーイングともいう。 |
| スラック(slack) |
| 弛(たる)むという意味。ラインスラックはラインの弛み。 |
| スプラッシュ(splash) |
| ポッパー(ルアーの一種)が水しぶきを上げること。 |
| スライダーヘッド(slider head) |
スライダーワームに装着するための専用ジグヘッド。小魚がスーッと泳ぐように真っ直ぐ引いてくる。 |
| ズル引き |
| ソフトベイトをボトムまで沈め、ボトムをゆっくりとズルズル引いてくること。 |
| スレ |
| フックが口にかからず体にかかること。 |
| スレッド(thread) |
| 糸のこと。通常、釣り糸はライン(line)を使うのが一般的だが、スレッドを使う場合もある。フライタイイング(フライを巻くこと)の糸やラバージグのラバーを固定する糸はスレッドと呼ぶ。 |
| スレる |
| 魚がルアーに飽きて見向きもしないこと。 |
| スローテーパー(slow taper) |
| テーパー(taper)とは先に向かって細くなる度合いのことで、スローテーパーは先に向かってゆっくりと細くなるという意味。そのためロッドとしては全体が曲がるアクション(曲がり具合)になる。全体に曲がるアクションを胴調子と言う。 |
| スローリトリーブ(slow retrieve) |
| リールをゆっくり巻くこと。 |
| スローローリング(slow rolling) |
| スピナーベイトをボトムや中層など一定の層を一定のスピードで引いてくること。スローロールともいう。 |
| セカンダリーポイント(secondary point) |
| バスがスポーニングのために向かう場所の手前で待機する場所のこと。 |
| セパレートグリップ(separate grip) |
ロッドのグリップが2つに分離しているタイプのもの。ピッチングの際にグリップの中央に腕が当たらない、ダブルハンドキャストの時にしっかり握れる、ロッドが軽くなるといった利点がある。 |
| セルフウイードレス(self-weedless) |
ソフトベイトにオフセットフックを装着した時に針先をソフトベイトの中に埋め込み根掛かりしにくくすること。 |
| 側線(そくせん) |
魚類が水中で水圧や水流の変化を感じとるための器官のことで、ブラックバスの場合はエラから尾びれの付け根まで続いている線である。 |
| 底荒れ |
| 強い風や波で底の泥や砂が巻き上がって濁ってしまうさま。一般的に底荒れすると魚の活性が落ちてしまう。 |
| 底ベタ |
| 魚やルアーが底にべったりとついている状態。 |
| 底を切る |
| ルアーを底から少し上を泳がせること。 |
| 底を取る |
| ルアーやオモリが浮き上がらないようにきっちりと底を感じること。 |
| ソフトベイト(soft bait) |
| やわらかい樹脂でできたルアーのこと。ソフトルアーやワームも類義語。 |
| ソフトルアー(soft lure) |
| やわらかい樹脂でできたルアーのこと。ソフトベイトやワームも類義語。 |
| ソリッド(solid) |
| 中が詰まっているという意味。普通、ロッドは中が中空(チューブラー)になっているが、中が詰まっているものをソリッドブランクなどという。 |
| ソリッドティップ(solid tip) |
| 普通、ロッドは中が中空(チューブラー)になっているが、中が詰まっているティップ(ロッドの先端部)のこと。ソリッドティップはチューブラーに比べて良く曲がり食い込みが良い。 |
| ソルティー(salty) |
| しょっぱい、塩辛いという意味。ソフトルアーの中には塩を入れてあったり、周りにまぶしてあったりするが、動物の体の中には塩分があり、魚がソフトルアーをくわえた時に食いつきを良くする効果がある。 |
| ソルト(salt) |
| 塩のこと。海水の中の塩分や、ソフトルアーの中や外にまぶしてある塩のこと。 |
| ソルトウォーター(salt water) |
| 海水のこと。一方、淡水はフレッシュウォーター(flesh water)という。 |
| ダーター(darter) |
トップウォータープラグの一種で強く引くと左右にダートするプラグ。ポッパーに似ているが、口がカップ状になっておらず「つ」のような形になっている。へドンのラッキー13などが有名。 |
| ダートアクション(dirt action) |
| ジャークベイトなど強く引くと軌道を大きくそらす動きのこと。 |
| ターンオーバー(turn over) |
| 気温が下がることで表水温が冷やされ、冷たい水は重いため下層の水と循環し、湖の中が大きく撹拌(かくはん)されること。秋や春に発生する自然現象で下層の貧酸素部分が巻き上がるため、水が悪くなり魚の活性が下がると言われている。 |
| タイト(tight) |
| 障害物ギリギリにルアーを通す状態。「障害物をタイトに攻める」 |
| ダイビング(diving) |
| ペンシルベイトのアクションの一種で、アクションをつけると水中に沈む動きのこと。 |
| ダウンクロス(down cross) |
| 川の流れに対して、上流から下流に向かって斜めにキャストすること。ダウンストリームともいう。 |
| ダウンショットリグ(down shot rig) |
| シンカー(オモリ)の手前にワームがとりつけられているリグ(仕掛け)のこと。ボトム(湖底)から少し上の層を狙う時に使われる。アンダーショットリグ、常吉リグ、ドロップショットリグとも言う。 |
| ダウンストリーム(down stream) |
| 川の流れに対して、上流から下流に向かって斜めにキャストすること。ダウンクロスともいう。 |
| タダ巻き |
| リールを一定のスピードで巻くこと。ステディーリトリーブと同意語。 |
| 立ち木(たちき) |
水に没した乱立した木々のこと。ダム湖など、昔、山だった場所を水域にした場所に多い。 |
| タックル(tackle) |
| リール、ロッド、ライン、ルアーの釣り道具一式のこと。 |
| タックルボックス(tackle box) |
ルアーを入れるケースのこと。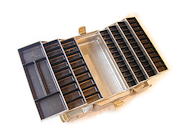 |
| タナ |
| 水のある一定の層のこと。レンジと同意語。魚がいる水深のことをいう場合もある。 |
| タフコンディション(tough condition) |
| 魚の活性が極端に悪い状態のこと。 |
| ダブルスイッシャー(double swisher) |
プロペラが2枚ついているスイッシャーのこと。トップウォータープラグの一種。 |
| W.B.S.(World Bass Society) |
| 1987年から1989年までアメリカのプロトーナメントに参戦していた吉田幸二氏が中心となり、1989年に発足したバスフィッシングのプロトーナメント団体。霞ヶ浦を中心に活動している。 |
| ダブルフック(double hook) |
2つに枝分かれしたタイプの釣り針のこと。1本のタイプはシングルフック、3本のタイプをトリプルフックまたはトレブルフックという。 |
| ダム湖 |
水利目的(水力発電や飲料水)で川を堰き止めて作った人造湖のこと。 |
| ダムサイト(damsite) |
| 本来はダムの建設用地のことをダムサイトという。バスフィッシングではダム(堰)のことをダムサイトといっているが本来は間違いである。 |
| タラシ |
| ルアーをキャストする時に穂先から垂らしたルアーまでの距離のこと。 |
| タンデム(tandem) |
2つに並んだという意味で、スピナーベイトのブレードが2つあることをタンデムブレードという。 |
| チャンネル(Channel) |
| 湖の底にある深い溝のこと。湖の底が流れによって削られてできる。また、ダム湖などは谷を堰き止めて作られるので底(谷)の溝のこと。チャネルとも言う。 |
| チェイス(chase) |
| 魚がルアーを追いかけること。 |
| チャートリュース(chartreuse) |
蛍光黄色のカラーこと。ルアーカラーの呼び名の一種。 |
| チューブヘッド(tube head) |
チューブワームを装着するためのジグヘッド。チューブワームの中(中空部)にヘッドを入れてアイをワームのボディーの外に出して使う。 |
| チューブラー(tubelar) |
| 中が中空である素材のことである。ロッドのは一般的に中が中空である。一方、中が中空であり詰まっているものをソリッド(solid)という。 |
| チューブワーム(tube worm) |
中が中空でイカのような形状をしたソフトルアーのこと。 |
| チューンナップ(tune up) |
| 市販のルアーやリールを改造すること。 |
| 中層 |
| 水中において底でも水面近くでもないある一定の層のこと。 |
| 超音波 |
| 人間には聞こえない高い振動数を持つ音波のこと。明確な定義はないが16KHz(キロヘルツ)以上ともいわれる。魚群探知機では振動子から超音波を湖底に発信し、湖底や魚に反射した反射波の反射時間をとらえ、画像として表している。 |
| 釣果(ちょうか) |
| 魚釣りの結果のこと。 |
| 釣行(ちょうこう) |
| 魚釣りに行くこと。 |
| 釣行記(ちょうこうき) |
| 魚釣りに行った結果や状況を記した記録のこと。 |
| 沈船(ちんせん) |
湖に沈んでしまい放置された船のこと。バスフィッシングでのポイントのひとつ。 |
| 2サイクルエンジン |
| 2ストロークエンジンともいわれ、吸気、圧縮、膨張、排気をエンジンの1往復(2工程=2ストローク)、つまりピストン上昇(吸気、圧縮)、下降(膨張、排気)で行うエンジンのことである。ボートのエンジンでは2サイクルエンジンが主流であったが、燃費が悪い、環境に悪い、音がうるさいといったことから4サイクルエンジンへの切り替えが進んでいる。 |
| ツーピースロッド(two piece rod) |
| 2本のブランクを継ぐロッドのこと。ただし、ブランクに継ぎ目がなく1本でグリップが脱着できるものは、ワンピースロッドである。ツーピースロッドはあくまでブランクに継ぎ目があるかどうかである。 |
| ツインテールグラブ(twin tail grub) |
カーリーテールが2つあるグラブのこと。 |
| 常吉リグ |
| 村上晴彦氏が世に広めたリグ。現在はアンダーショットリグやダウンショットリグが一般的な呼び名となっている。シンカー(オモリ)の手前にワームがとりつけられているリグ(仕掛け)のこと。ボトム(湖底)から少し上の層を狙う時に使われる。名前の由来は常に結果が吉と出るからだとか。 |
| テーパー(taper) |
| 先に向かって段々細くなる形状、その度合いをテーパーという。ロッドの形状のことをいう。ファーストテーパー(fast taper)は急激に先細っていくという意味で先の部分が曲がるロッドのこと。スローテーパー(slow taper)は先に向かってゆっくりと細くなっていくという意味でロッド全体が曲がるロッドのこと。その中間がレギュラーテーパー(regular taper)である。。 |
| テールスピンジグ(tail spin jig) |
金属のボディーのテールにスピナーが装着されたルアー。マンズ社のリトルジョージが有名。 |
| DQ(ディーキュー) |
| デスクオリファイ(disqualify)の略で失格という意味。トーナメントルールに反した行為をして失格になること。 |
| 低気圧 |
| 周りに比べて気圧が低い部分のこと。気圧とは大気の重さによって生じる圧力で、低気圧は空気の層が薄いために気圧が低い。低気圧は一般的に雲や雨を伴い、風が吹く。低気圧が近づくと一般的に魚の活性が上がると言われている。その理由は諸説あり、曇ったり風が吹いたりするので魚の警戒心が薄れる、風や雨で水中の溶存酸素が増える、天気が荒れエサにありつけないので本能的に獲物をとらえようとする、浮き袋が膨らみ動きが軽くなるので活発に泳ぎ回ることができるといったことが挙げられているが本当の理由はわかっていない。 |
| ディープ(deep) |
| 水深の深い場所。 |
| ディープウォーター(deep water) |
| 深い場所のこと。 |
| ディープサイクルバッテリー(deep cycle battery) |
車のバッテリー(スターターバッテリー)はエンジン始動後はオルタネータから常時充電されているが、充電してから空になるまで(放電しきってしまうまで)使うタイプのバッテリーのことをディープサイクルバッテリーという。通常、バッテリーは放電しきってしまうと電極などが劣化してしまうが、ディープサイクルバッテリーはそれぞれのパーツが劣化に強くできている。エレクトリックモーターを動かしたり、魚群探知機の電源として使う。 |
| ディープダイバー(deep diver) |
| 引くと深く潜るタイプのルアーのこと。深く潜るクランクベイトの別の呼び名。 |
| ディープレンジ(deep range) |
| 湖の深い部分のこと。ディープ(deep)は「深い」、レンジ(range)は水深の幅のこと。 |
| ディッチ(ditch) |
| 溝のこと。バスフィッシングでは水中にある溝のことを指す。特にシャローウォーターでは周りより深くなった溝にバスが集まったりすることがある。 |
| ティップ(tip) |
| ロッドの先端部分のこと。ロッドティップとも言う。 |
| ティンバー(timber) |
水に没した集合的な立ち木のこと。 |
| 手返し |
| ルアーをキャストして引いてくるまでの一連の動作のこと。「手返しが早い」はテンポよくルアーをキャストしていくこと。 |
| テキサスリグ(texas rig) |
| ワームの手前にバレットシンカーという弾丸のようなオモリを使ったリグのこと。リグの構造がシンプルなので根掛かりがしにくく、シンカーとルアーの位置が近いのでボトムを感じながらルアーの動きのイメージがしやすい。 |
| テクトロ |
| テクはテクテク歩くのテク、トロはトローリング。護岸などの岸際を歩きながらルアーを泳がせること。 |
| デコる |
| 魚が一匹も釣れないこと。 |
| デッドスティックング(dead sticking) |
| ルアーをほとんど動かさない、或いはまったく動かさずにバスを誘うテクニック。 |
| デッドスロー(dead slow) |
| (1)ルアーを超低速で動かすこと。 (2)エンジン船をアイドリング状態で進めること。湖により騒音防止などでデッドスローで航行する区域や時間帯がある。 |
| デッドフィッシュ(dead fish) |
| 死魚のこと。バスフィッシングトーナメントで死魚をウエイインするとペナルティーが課されるといったルールがある。 |
| テトラ(tetrapod) |
円錐状の4本の足がある消波ブロックのこと。川の流れが良く当たる部分や波が強く打ちつける湖岸、海岸などに置かれる。水通しが良く魚の隠れ家となりバスの絶好のポイントでもある。テトラポッドとも言う。 |
| テネシーグリップ(tennessee grip) |
ロッドには通常、リールシートというリールをセットするパーツがついているがリールシートがなく、金属の輪やテープでリールを止めるグリップのこと。 |
| デプスファインダー(depth finder) |
| 魚群探知機のこと。魚群探知機の項参照のこと。 |
| テリトリー(territory) |
| なわばりのこと。産卵期のバスはテリトリー意識が特に強く、食欲だけでなくテリトリーに侵入してきたものにアタックする。 |
| テレスコピック(telescopic) |
収納時には元竿(一番太い竿の部分)の1本が収まり、引き出して使う釣り竿のこと。振り出し竿ともいう。 |
| テンション(tension) |
| 張り、張力のこと。ラインの張りのこと。「魚がバレてラインがテンションを失った」など。 |
| 天ぷらキャスト |
| 野球のフライのように高い軌道でルアーが飛んでしまうキャストのこと。天ぷらが「揚げる」、軌道が高く「上がる」をひっかけて名づけられた。一般的に高い軌道のキャストは着水音が大きくなり、風の影響も受けるため良くない。しかし、ウエッピングのようにポイントの真上から直撃したい場合や、高い着水音に魚の反応が良い場合などは意図的に行うこともある。 |
| トーナメントプロ(tornament professional fisherman) |
| バスフィッシングのプロトーナメントに参戦する競技者のこと。バスフィッシングのプロトーナメント団体にはJBやWBSなどがある。 |
| 胴調子 |
| 穂先から手元まで全体的に曲がるタイプのロッドのアクション(曲がり具合)のこと。スローテーパーとも言う。 |
| ドゥードゥリング(doodling) |
| ドン・アイビーノ(Don Iovino)というバスプロが普及させたルアーテクニック。シンカーとワームの間にビーズを挟み、ルアーを細かくシェイクしてカチカチと音を立てるテクニックのこと。 |
| ドゥーナッシング(do nothing) |
| バスプロのジャック・チャンセラー(Jack Chancellor)が普及させたテクニック。ドゥーナッシングワームという専用のストレートワームを用いて、キャストしたらそのまま放置するというテクニック。 |
| トゥイッチング(twitching) |
| ミノーのアクションの一種で、ロッドをツンツンと連続的にあおり、ミノーを不規則に動かすこと。ジャーキングに似ているがジャーキングの方がミノーの動きが激しい。 |
| トゥルーチューン(true tune) |
| クランクベイトやシャッドプラグがまっすぐ泳ぐようにラインアイの位置を調整すること。傾いて泳ぐ方向と逆側に少し曲げるとまっすぐ泳ぐようになる。 |
| ドック(dock) |
船溜まり。漁港。霞ヶ浦や琵琶湖などに多く見られる。コンクリートの護岸やミオ筋、係留船の影などバスの好ポイントになる。 |
| ドッグウォーク(dog walk) |
| 左右に首を振るルアーの動きのこと。ペンシルベイトのアクションを指す。 |
| トップウォーター(top water) |
| 水面。一方、水中はアンダーウォーター。 |
| トップウォータープラグ(top water plug) |
| 水面に浮くタイプのプラグのこと。サーフェスプラグも同義語。 |
| トップガイド(top guide) |
ロッドの先端についているガイドのこと。 |
| ドラグ(drag) |
| 強い魚の引きでラインにある負荷がかかるとリールのスプールが逆転してラインを送り出す機構のこと。ラインブレイクを防止する。 |
| ドラグノブ(drag knob) |
スピニングリールの上部にあるドラグのつまみのこと。 |
| ドラッギング(dragging) |
| リールを巻かずにボートをエレクトリックモータや風の力で流すトローリングのこと。 |
| トランスデューサー(transducer) |
| 魚群探知機の超音波を発信装置のこと。船底やエレクトリックモータに取り付けて湖底に向かって超音波を発信する。 |
| トリガー(trigger) |
ベイトロッドのグリップにある親指をかけるための突起部のこと。 |
| 取り込み |
| 針にかかった魚を引き上げること。ランディングとも言う。 |
| トリム(trim) |
| 船首と船尾の吃水(きっすい)の差のこと。水に浸かった時の船の前後の傾きのことをいう。また、バスボートでのトランサムボードと船外機の傾きもトリムといい、トリムによって船外機の角度を調節する必要がある。 |
| トリプルフック(triple hook) |
ハードルアーについている、3本針のこと。トレプルフックともいう。 |
| トレース(trace) |
| 通った跡、通った跡をたどる、という意味。ルアーを引きたいラインに沿って引いてくることを言う。 |
| トレーラー(trailer) |
(1)ボートを自動車で牽引(けんいん)するための台車のこと。 (2)スピナーベイトやラバージグのフックにつけるワームやポークのこと。ルアーのボリュームやアピールをアップさせたりするためにつける。  |
| トレーラーフック(trailer hook) |
スピナーベイトなどに付ける補助のフックのこと。フッキング率を上げるために装着する。アシストフックともいう。 |
| トレブルフック(treble hook) |
ハードルアーについている、3本針のこと。トリプルフックともいう。 |
| ドレッジ(dredge) |
| 浚渫(しゅんせつ)のこと。意味は浚渫の項を参照。 |
| トローリング(trawling) |
| 船を走らせてルアーやエサを引き魚を釣ること。 |
| ドロップオフ(drop off) |
| 浅いところから急激に深くなる地形のこと。同じ意味の言葉としてブレイクライン(break Line)、カケアガリ、落ち込みがある。 |
| ドロップショットリグ(drop shot rig) |
| シンカー(オモリ)の手前にワームがとりつけられているリグ(仕掛け)のこと。ボトム(湖底)から少し上の層を狙う時に使われる。アンダーショットリグ、常吉リグ、ダウンショットリグとも言う。 |
| ナイトフィッシング(night fishing) |
| 夜釣りのこと。 |
| ナイロンライン(nylon line) |
| ナイロン素材のモノフィラメント(単繊維)の釣り糸のこと。しなやかで適度な伸びがあり安価である。釣り糸の一般的な素材である。 |
| 中州 |
流れによって砂が堆積して浅く島のようになった場所のこと。サンドバー(sand bar)ともいう。 |
| 中通しオモリ |
| オモリの中でもラインを通す穴があいているオモリの総称。 |
| ナチュラル(natural) |
| ルアーの自然な動き。 |
| ナツメオモリ |
フットボールの形をした中通しオモリのこと。 |
| ニーブーツ(knee boots) |
膝までの高さの長靴のこと。 |
| ニーリング(kneeling) |
| ニール(kneel)とは膝(ひざ)の意味。ボートに膝をついてロッドを水中に突っ込み、ディープクランクを引く釣り方のこと。ロッドを水中に突っ込んだ分、深い層を引くことができる。 |
| 日本バスプロ協会 |
| 1985年にJBTAとして発足したバスフィッシングのプロトーナメント団体のこと。JB(ジェービー)とも言う。 |
| 入漁料 |
| 入漁者(釣り人)が漁業権者に対して払う費用のこと。遊漁料ともいう。 |
| ネイルシンカー(nail sinker) |
ネコリグなど、ワームのボディーの中にねじ込むシンカー。爪(nail)のようなシンカーのような形をしている。 |
| 根掛かり(ねがかり) |
| ルアーや仕掛け(リグ)が湖底の障害物にひっかかってしまうこと。 |
| 根掛かり回収機 |
ルアーが根掛かり(ねがかり)した時に回収するための道具で、ラインをたどってルアーに到達しルアーのフックに金属パーツをひっかけて回収するタイプや、棒の先についている金属パーツで直接ルアーをひっかけるタイプなどがある。 |
| ネコリグ |
| ワームの頭部にシンカーをねじ込んで、ワームのボディー中央に針を刺したリグのこと。頭をボトムにして逆立ちしたような姿勢になり、小魚が湖底をついばんでいるような姿勢をイメージしてバスを誘う。 |
| ネスト(nest) |
バスの産卵床(さんらんしょう)のこと。オスのバスはメスが卵を産むために尾びれで湖底の砂を掘り円形状の窪地を作る。スポーニングベッドともいう。 |
| 根ズレ |
| 水中に沈んだ障害物にラインが擦れてしまうこと。ラインブレイクが多発するので注意する。 |
| ネムリバリ |
フックポイント(針先)が内側に曲がっているフックのこと。魚の喉ではなく口にかかりやすい、刺さったらバレにくいといった利点がある。 |
| ノーシンカー(no sinker) |
| ソフトベイトにシンカーをつけない状態。水面近くを泳がせたり、沈めるスピードをゆっくりさせたい時にノーシンカーにする。 |
| ノーシンカーリグ(no sinker rig) |
| ワームフックにワームを装着しただけのオモリをつけないリグのこと。水面近くを泳がせたり、沈めるスピードをゆっくりさせたい時にノーシンカーにする。 |
| ノイジー(noizy) |
水面を騒がしく泳ぎ回るルアーの総称。ノイジープラグ(noizy plug)ともいう。へドン社のクレイジークロウラーやフレッドアーボガスト社のジッターバグなどがこのカテゴリーのルアーである。 |
| ノイジープラグ(noizy plug) |
| 水面を騒がしく泳ぎ回るルアーの総称。ノイジー(noizy)ともいう。 |
| 納竿(のうかん) |
| 釣りを終えること。竿をしまうこと。 |
| 乗っ込み(のっこみ) |
| 春になると多くの魚がシャローを目指すが、フナやコイなどのコイ科の魚が春にシャローを目指すことを乗っ込みという。コイ科の魚以外でも春にシャローを目指す時に使うこともある。 |
| ノット(knot) |
| 糸を結ぶこと。ユニノット、クリンチノットなど結び方にも色々ある。 |
| 乗る |
| 魚が針にかかること。ロッドに魚の重みな乗ること。 |
| ノンキーパー(non keeper) |
| トーナメントで検量に持ち込むことのできない魚。基準に満たない小さな魚のこと。 |
| ノンラトル(non rattle) |
| ラトル(rattle)が入っていないルアーのこと。サイレント(silent)ともいう。 |
| バーチカル(vertical) |
| 垂直方向という意味。ポイントの上にボートをステイし垂直方向にワームやメタルジグで攻める時に「バーチカル」に攻める。 |
| バーチカルジギング(vertical jigging) |
| ロッドを連続的にしゃくって垂直方向にメタルジグを動かす釣り方。 |
| パーティングライン(parting line) |
| 成形部品にできる金型の合わせ目の線のこと。ソフトルアーはインジェクション(射出成型)という製法で作られるが二つの金型を合わせて、その中に溶かした樹脂を流し込んで冷やして作る。金型を割って製品を取り出した時にパーティングラインという金型の合わせ目の線ができる。 |
| ハードガイド |
ロッドのガイドの材質の一種でアルミナオキサイドという材質を使ったもの。ガイドの中では最も安価な素材である。 |
| ハードボトム(hard bottom) |
| 湖底が岩盤、コンクリートなど固いマテリアルでできている場所のこと。 |
| ハードルアー(hard lure) |
| 樹脂や木材でできたルアーの総称。プラグも同義語。 |
| バーブ(barb) |
フックの部位でフックポイント(フックの先端部分)にあり、かかった魚が逃げないようにするための棘(トゲ)のような突起部分のこと。カエシともいう。 |
| バーブレスフック(barbless hook) |
カエシのないフックのこと。魚のダメージを減らす効果があるがバレやすいので注意が必要である。 |
| パーミング(palming) |
| ベイトキャスティングリールを手のひらで包み込むように持つこと。右巻きリールの場合は左手、左巻きリールは右手の手のひらでロッドと一緒にリールとホールドする。 |
| パーミングカップ(palming cup) |
ABU社のリールの丸みを帯びたサイドプレートのこと。従来のABU社のベイトリールは平べったい形状であったがホールド性を高めるために丸みを帯びたサイドプレートをデザインした。従来のABU社のベイトリールのファンからは賛否両論が巻き起こった。 |
| バイト(bite) |
| バスがルアーに食いつくこと。 |
| バイブレーションプラグ(vibration plug) |
ルアーの種類で水中で激しく振動するルアーのこと。水に沈み、扁平な形をしており、ヘッドの部分にあたる水の抵抗でボディーを細かく振動させるルアー。 |
| ハイランドレイク(high land lake) |
| 標高が高い場所にある湖のこと。一方、平地の湖はフラットランドレイクと言う。 |
| パイロットルアー(pilot lure) |
| 最初に投げるルアーのこと。バスの活性を探ったり、まず1匹目を釣るために最初に投げるルアーのことをいう。サーチベイトともいう。 |
| 爆釣(ばくちょう) |
| 物凄く釣れること。 |
| バジング(buzzing) |
| スピナーベイトの速引きのこと。ブレードが水面を飛び出すくらいに高速で引いてくること。ガーグリング(gurging)ともいう。 |
| バス(bass) |
| (1)ブラックバスの略称。 (2)B.A.S.S.(ビーエーエスエス)のもう一つの呼び名。B.A.S.S.の項参照。 |
| B.A.S.S. of Japan(バスオブジャパン) |
| B.A.S.S.はアメリカだけでなく世界に下部組織を有しているが、その日本支局がB.A.S.S. of Japanである。1979年にB.A.S.S.に認定され、日本においてバスフィッシングの普及活動やバスフィッシングトーナメントの開催を行っている。 |
| バスプロ |
| バスフィッシングのみで生計を立てている人。またはJBやW.B.Sなどプロトーナメント団体に選手登録しているアングラーのこと。 |
| バスプロショップス(Bass Pro Shops) |
アメリカの釣り具大手チェーン店のこと。釣り具だけでなくハンティング用品なども取り扱っている。通販にも力を入れており、日本から通販で購入することも可能。 |
| バスベイト(buzz bait) |
ルアーの種類で形はスピナーベイトに似ているがブレードの部分がプロップ(回転翼)になっていて水面をプロップで水しぶきをあげながら魚を誘うタイプのルアー。 |
| バスボート(bass boat) |
バスフィッシングのために設計されたボートのこと。船の形は扁平(へんぺい)で、大馬力のエンジン、バスを活かすためのいけす、エレクトリックモータ、魚群探知機などを装備している。 |
| パターンフィッシング(pattern fishing) |
| 魚の居場所、ルアーへの反応などを、あらゆる情報から法則性(パターン)を導き出してバスを釣ること。 |
| ハタキ |
| コイやヘラブナなどが葦際で産卵するさま。尾びれでバシャバシャと水しぶきを上げてはたいているのでハタキという。ハタキが始まるとバスが警戒してシャローに近づかすシャローがまったく釣れなくなってしまう。 |
| バックウォーター(back water) |
流れ込み。湖や沼などの止水域に水が流れ込んでいる場所のこと。インレットとも言う。 |
| バックラッシュ(backlash) |
| ベイトリールでラインが放出されるスピードに比べてスプールが回転するスピードが速すぎるためにラインがグシャグシャになってしまうこと。スプールのスピードを親指で調整(サミング)することによりバックラッシュを防ぐことができる。 |
| バッグリミット(bag limit) |
| 釣り上げてキープできる魚の制限匹数のこと。バスフィッシングのトーナメントでウエイインできるバスの数や、魚を資源管理している釣り場で釣ってキープできる魚の数のことを指す。 |
| ハッチ(hatch) |
| カワゲラやトビゲラの幼虫が羽化すること。 |
| バット(butt) |
| ロッドの部位の名称で、グリップに近い一番手元の太い部分のこと。 |
| パッド(pad) |
ヒシやハスなど水面に葉が浮いている水生植物の総称。 |
| パドルテール(paddle tail) |
ソフトルアーの一種で、パドル(櫓)のような形のテールをしたルアーのこと。 |
| 早合わせ |
| 魚がルアーに食いついたら即、合わせること。ショートバイトの時には早合わせが必要だが、魚が十分にルアーに食いついておらず、魚がかからない場合もある。 |
| パラアシ |
| パラパラとまばらに生えている葦(アシ)のこと。 |
| バラシ |
| 釣り針にかかった魚が外れて逃げられること。 |
| バラす |
| 釣り針にかかった魚が外れて逃げられること。 |
| 張り出し |
| 水中で沖まで岬状に盛り上がって突き出している地形のこと。 |
| バルキー(bulky) |
| ルアーのボリューム、サイズが大きいこと。 |
| バレットシンカー(bullet sinker) |
テキサスリグに使う弾丸型のオモリのこと。バレットは英語で弾丸という意味。 |
| バレットヘッド(bullet head) |
ジグヘッドの一種でシンカーの部分がバレット(弾丸)形状のもの。 |
| バンク(bank) |
| バンクとは土手のこと。岸の意味でも使う。 |
| バンクフィッシング(bank fishing) |
| 岸釣り、オカッパリのこと。ショアフィッシングともいう。 |
| ハンドコン |
エレクトリックモータの中で手で舵を切るタイプのもの。ハンドコントロールの略。 |
| ハンドポワード(hand poured) |
| 通常、ソフトベイトはインジェクションという方法で作るが、金型にドロドロに溶かした樹脂を手流しで作る方法をハンドポワードという。 |
| ハンドル(handle) |
リールについているスプールを回転させるための手で回転させる部品のこと。 |
| ハンドルノブ(handle knob) |
| リールのハンドルの先についているつまみ部分のこと。 |
| ハンプ(hump) |
| 水の中にある山のように盛り上がった地形のこと。水中島。 |
| ハンマードブレード(hammered blade) |
スピナーベイトのブレードの表面形状のことで、小さなくぼみがたくさんついたブレードのこと。 |
| B.A.S.S.(ビーエーエスエス) |
| アメリカで最も古く、最も権威のあるバスフィッシングトーナメント団体。バスアングラーズスポーツマンソサイエティー(Bass Anglers Sportsman Society)の略称である。1967年にレイ・スコット(Ray Scott)が アーカンソー州のビーバー・レイクで主催したトーナメント、オールアメリカン(All American)が発足のきっかけとなった。バスフィッシングトーナメントだけでなく、多くの会員を有し、バスマスターマガジン(Bassmaster magazine)という会員誌の発行などバスフィッシングの普及活動も行う。 |
| PEライン |
| PE(ポリエチレン)素材のより糸で、細いが引っ張り強度が高い、浮力が高いという特徴がある。トップウォーターやカバーでの釣りに使われる。欠点としては価格が高い、瞬間的な負荷をかけると切れる、ロッドティップにまとわりつくといったものがある。 |
| ビーズ(beads) |
シンカーとソフトベイトの間やシンカーとスイベルの間に装着し、シンカーと接触してカチカチと音を発生させてバスの注意を惹く。 |
| ヒートン |
先端が輪のように丸められた金属製のネジのこと。プラグのラインアイやフックを装着するために使われる。 |
| ビジブル(visible) |
| 目に見える、という意味。水の上に出ている、或いは沈んでいるが目で確認できるものを指す。「ビジブルストラクチャー」など。一方、目に見えないものはインビジブル(invisible)。 |
| 比重 |
| ある物質の密度(単位体積当たりの質量)と、基準物質の密度(単位体積当たりの質量)との比を比重という。ルアーには浮くルアー、沈むルアー、サスペンドするルアーがあるが、比重が1より大きいものは沈み、1より小さいものは浮き、1と等しいものはサスペンドする。 |
| ビッグベイト(big bait) |
ルアーの種類でスイムベイトとも呼ばれる1オンスかそれ以上ある大きさのルアーのこと。 |
| ピッチング(pitching) |
| 野球の下手投げのようなフォームでルアーをキャストする方法のこと。近距離をアップテンポで探るときに多用する。 |
| ピット(pit) |
| アメリカで燐(リン)の採掘所にできた穴のこと。ここに水が溜まり沼地になった場所にバスを放し、釣り場になることがある。燐は植物を成長させる養分にもなり水生植物が繁茂し、生物が生きる環境としても良いので大きなバスが育つ。ただし、私有地であることが多く、一般の人は釣りができない場合が多い。 |
| ヒラ打ち |
| ルアーが障害物にぶつかった直後にルアーのボディーをひるがえして障害物を乗り越える動作のこと。 |
| ビルジ(bilge) |
| 船の底にたまった水のこと。 |
| ビルジポンプ(bilge pump) |
| 船の底にたまった水を船の外に排出するためのポンプ。 |
| ピンテールワーム(pin tail worm) |
ストレートワームの中でもテールが尖って(とがって)いるワームのこと。 |
| ファーストテーパー(fast taper) |
| テーパー(taper)とは先に向かって細くなる度合いのことで、ファーストテーパーは急激に細くなるという意味。ファーストテーパーのロッドはロッドのアクション(曲がり具合)は先が曲がる。先が曲がることを先調子と言う。 |
| ファーストムービングルアー(fast moving lure) |
| 早い動きで手返し良く効率的に探れるルアーのこと。クランクベイトやスピナーベイト、バイブレーションプラグなどを指す。 |
| ファーストリトリーブ(fast retrieve) |
| リールを早く巻くこと。 |
| ファームポンド(farm pond) |
| 農業用のため池のこと。 |
| ファイト(fight) |
| 針掛かりした魚とのやりとりのこと。 |
| フィーディング(feeding) |
| 魚がエサを食べること。食べている状態。 |
| フィーディングモード(feeding mode) |
| 魚の食いがたっている状態。エサを積極的に食べている状態。 |
| フィッシュアトラクター(fish attractor) |
魚を引付ける匂いの薬品。集魚剤のこと。ルアーに吹き付けて食い込みを良くしたりルアーをくわえる時間を長引かせる効果がある。アトラクター(attractor)、フィッシュフォーミュラー(fish formula)ともいう。 |
| フィッシャーマン(fisherman) |
| 釣り人または漁師のこと。 |
| フィッシュフォーミュラー(fish formula) |
| 魚を引付ける匂いの薬品。集魚剤のこと。ルアーに吹き付けて食い込みを良くしたりルアーをくわえる時間を長引かせる効果がある。アトラクター(attractor)、フィッシュアトラクター(fish attractor)ともいう。 |
| フィッシングガイド(fishing guide) |
| 湖で釣れるポイントに案内し、釣れるルアーやメソッドを教えてお客さん(ゲスト)にバスを釣らせる案内人のこと。 |
| フィッシングプレッシャー(fishing pressure) |
| 人の影、音、振動やルアーなどが魚に与える圧迫感のこと。フィッシングプレッシャーがかかると魚が警戒心を持ってしい釣りにくくなる。 |
| フィネス(finesse) |
| 繊細な釣りのこと。小さなルアーを細いラインでスローに繊細に攻める釣り方のこと。 |
| Vハル(V hull) |
| アルミボートの底がV字状の形状のこと。 |
| フィンガーリング(fingerling) |
| 幼魚のこと。 |
| フェザージグ(feather jig) |
ジグヘッドに羽毛(feather)を巻いたルアーのこと。羽毛ではなく動物の毛を使ったもののフェザージグと呼ぶことがある。 |
| フェザーリング(feathering) |
| スピニングタックルでキャストした時にルアーが着水する直前に人差し指でスプールを押さえる動作のこと。ベイトタックルでキャストする時にに親指でスプールを押さえる動作はサミング(thumbing)という。 |
| 4サイクルエンジン |
| 4ストロークエンジンともいわれ、吸気、圧縮、膨張、排気をエンジンの2往復(4工程=4ストローク)、つまりピストン上昇(吸気)、ピストン下降(圧縮)、ピストン上昇(膨張)、ピストン下降(排気)で行うエンジンのことである。ボートのエンジンでは2サイクルエンジンが主流であったが、燃費が悪い、環境に悪い、音がうるさいといったことから4サイクルエンジンへの切り替えが進んでいる。 |
| フォーリング(falling) |
| キャスト後、ルアーを沈めること魚を誘うこと。沈んでいくものにバスが反応する時に用いるテクニック。ルアーの沈み方によって、ラインスラックを作って真下に沈めるフリーフォール、ラインにテンションをかけて手前に弧を描いて沈めることをカーブフォール、フリーフォールではあるがらせん状にルアーを沈めるスパイラルフォールなどがある。。 |
| フォール(fall) |
| ルアーが沈んでいくこと。 |
| フォールターンオーバー(fall turn over) |
| 秋に発生するターンオーバーのこと。ターンオーバーの項参照。 |
| フォローベイト(follow bait) |
| 今、投げているルアーの次に投げるルアーのこと。またはミスバイトがあった時に間髪入れずに投げ入れるルアーのこと。 |
| フッキング(hooking) |
| アタリがあった時に、魚の口に釣り針をひっかけるためにロッドをグイッとあおる動作のこと。 |
| フック(hook) |
| 釣り針のこと。 |
| フックアップ(hook up) |
| 魚がフック(釣り針)にかかること。 |
| フックカバー(hook cover) |
フックにかぶせるプラスチック製のカバーのこと。 |
| フックシャープナー(hook sharpener) |
フックの先端を研ぐためのヤスリのこと。 |
| フックディスゴージャー(hook disgorger) |
魚の喉の奥に刺さったフックを外すための道具のこと。通称「オエオエ棒」。 |
| フックポイント(hook point) |
| フックの先端部分のこと。尖った部分。 |
| ブッシュ(bush) |
低い灌木(かんぼく)、小枝のことを指す。ブッシュが水に浸かっている場所はバスの絶好の隠れ家になる。 |
| フットコン |
| エレクトリックモータの中で足でペダルを踏んで舵を切るタイプのもの。ふっとコントロールの略。 |
| フットボールヘッド(football head) |
ジグヘッドの一種でヘッドの部分がフットボールの形をしたもの。 |
| プラ |
| プラクティスの略称。プラクティスとはバストーナメントの本戦前の下見、試し釣り、練習のこと。 |
| フライ(fly) |
毛バリのこと。 |
| プライムタイム(prime time) |
| 魚の活性が一番高い時間帯のこと。時合ともいう。 |
| プライヤー(plier) |
バスの口からフックを外したり、プラグのアイの位置を修正したり、曲がったフックを修正したりするための道具。先端が「へ」の字形状になっていてスプリットリングを外したりするものもある。 |
| ブラインド(blind) |
| 見えなくすること。魚の姿を確認できなくすること。魚から釣り人が見えない場所に移動すること。 |
| プラグ(plug) |
| 樹脂や木材でできたルアーの総称。ハードルアーも同義語。 |
| プラクティス(practice) |
| バストーナメントの本戦前の下見、試し釣り、練習のこと。略してプラとも言う。 |
| ブラシガード(brush guard) |
ラバージグなどに装着されているブラシ状のガードのこと。 |
| ブラスシンカー(brass sinker) |
| 真鍮(しんちゅう、brass)製のシンカーのこと。真鍮とは黄銅のことだが、一般的なシンカーの材質の鉛よりも硬度が高く、ビーズと組み合わせてカチカチと音をたてたりして使う。ただし、鉛よりは比重は低い(軽い)。 |
| プラスチックワーム(plastic worm) |
| やわらかい樹脂でできたルアー。ワームやソフトベイトも類義語。 |
| フラッシャー(flasher) |
魚探と同様、湖底に超音波を発信し、水深を測定する装置。魚探のように固定の形状の画像ではなく、深さを瞬時に測定する。ボートを高速で飛ばしていても水深を測定することができる。 |
| ブラッシュパイル(brush pile) |
| 魚を集めるために小枝を束ねて沈めたもの。日本ではオダという。 |
| フラッシング(flashing) |
| スピナーベイトのブレードやミノーのボディーのシルバーカラーがギラギラと反射すること。 |
| フラット(flat) |
| ボトム(水の底)が平らな場所のこと。 |
| フラットサイドクランクベイト(flat side crankbait) |
クランクベイトの中でもサイドボディーが平らなクランクベイトのこと。丸みを帯びたボディーに比べて水を押す力が強い。 |
| フラットランドレイク(flat land lake) |
| 平地の湖のこと。一方、標高が高い場所にある湖はハイランドレイクと言う。 |
| ブランク(blank) |
| ロッドがブランクやガイドなどを装着していない状態のこと。 |
| ブランクスルー(blank through) |
| グリップの中をブランクが貫通して一体になったもの。一方、取り外しできるグリップをオフセットグリップという。 |
| フリーフォール(free fall) |
| ラインを緩めた状態でルアーを沈めること。ルアーはバーチカル(垂直)に沈んでいく。一方、ラインを張ってルアーを手前にカーブさせながら沈めることをカーブフォールという。 |
| 振出竿(ふりだしざお) |
収納時は元竿(一番太い竿の部分)の中に収められていて、引き出して使う釣り竿のこと。テレスコピック(telescopic)ともいう。 |
| フリッピンスティック(flipping stick) |
| フリッピング専用のロッドで長さが8フィート近いロングロッドのこと。フリッピングとはルアーを振り子のように静かにプレゼンテーションするキャスト方法である。 |
| フリッピング(flipping) |
| ルアーを振り子のように静かにプレゼンテーションするキャスト方法の一種。 |
| プリスポーン(pre-spawn) |
| バスの産卵準備期間のこと。バスが産卵をするために越冬期間の深場から浅場に移動している期間のことを指す。 |
| ブルーギル(blue gill) |
1960年に当時の皇太子明仁親王(平成時代の今上天皇)がシカゴ市長から寄贈された魚で伊豆の一碧湖に移植された。その後、漁業関係者によって全国的に拡散した。バス釣りでもワームを食いちぎり、引き(ファイト)も良くないので厄介者として扱われている。 |
| フレーク(flake) |
ラメのこと。ワームの中に入っているキラキラ光る金属箔のこと。グリッター(glitter)ともいう。 |
| ブレード(blade) |
| スピナーベイトやスピナーの回転する金属の羽のこと。 |
| プレーニング(planing) |
| ボートは走り始めてスピードが加速すると船が水に沈んている状態から水の上に浮かびあがって滑走するような状態になる。この水に浮かび上がって滑走する状態をプレーニングという。 |
| ブレイク(break) |
| ブレイクラインの項参照。 |
| ブレイクライン(break Line) |
| 浅いところ、深いところの境界線のことで浅いところから急激に深くなる場所を指す。同じ意味の言葉としてドロップオフ(Drop off)、カケアガリ、落ち込みがある。 |
| ブレイデッドライン(braided line) |
| ナイロンラインのように1本のラインをモノフィラメント(単繊維)というが、ブレイデッドラインはモノフィラメントラインを何本か編んだラインである。PEラインがこれにあたる。 |
| プレゼンテーション(presentation) |
| ルアーを魚のいる場所に送り届けること。 |
| フレッシュウォーター(flesh water) |
| 淡水のこと。一方、海水はソルトウォーター(salt water)という。 |
| フローター(floater) |
釣り用の浮き輪。足ひれをつけて移動する。フロートチューブ(float tube)ともいう。 |
| フローティング(floating) |
| ルアーやラインが水に浮くこと。一方、水に沈むことはシンキング(sinking)という。 |
| フローティングルアー(floating lure) |
| 水に浮くルアーのこと。沈むルアーはシンキングルアー、水中で浮きも沈みもしないルアーはサスペンドルアーという。 |
| フロートチューブ(float tube) |
| 釣り用の浮き輪。足ひれをつけて移動する。フローター(floater)ともいう。 |
| フロッグ(frog) |
| (1)カエルのこと。 (2)カエルを模したルアーのこと。  |
| プロップベイト(prop bait) |
| トップウォータープラグの一種でプロペラが回転して発生する音や波紋でバスを誘うルアー。スイッシャー(swisher)ともいう。プロペラが1つついているものをシングルスイッシャー、2つついているものをダブルスイッシャーという。 |
| フロリダシンカー(florida sinker) |
バレットシンカーの一種で、ワームを固定するためのバネがついているシンカー。シンカーとワームが一体になることで、カバーのすり抜け性が良くなる。 |
| フロリダバス(florida bass) |
| アメリカのフロリダ州などに生息するラージマウスバスの亜種。ラージマウスバスに比べて、浅い場所を好む、警戒心が強い、大型になるといった特徴がある。日本には奈良県の池原ダムに放流され、近年は琵琶湖にも繁殖している。 |
| フロロカーボンライン(florocarbon line) |
| ポリフッ化ビニリデンを原料にしたライン。かつてはナイロンラインがバスフィッシングでは主流だったが、現在は、ナイロンラインと並んで使われるフィッシングラインである。ナイロンラインと比べて、比重が高い(重い)ためボトムの釣りに適している、吸水性が低い、紫外線に強いといった特徴がある。一方、巻きグセや糸撚れがおきやすいというデメリットもある。 |
| フロロライン(florocarbon line) |
| フロロカーボンラインの略称。フロロカーボンラインの項参照。 |
| ベイト(bait) |
| エサ。バス・フィッシングではルアーまたは、バスが食べている生き物のことを指す。 |
| ベイトキャスティングリール(bait casting reel) |
両軸受けリールのこと。比較的重たいルアーを投げる時に使う。略してベイトリールとも言う。 |
| ベイトキャスティングロッド(bait casting rod) |
| ベイトキャスティングリールを装着するためのロッドのこと。略してベイトロッドとも言う。 |
| ベイトタックル(bait tackle) |
| ベイトキャスティングリールとベイトキャスティングの道具一式のこと。 |
| ベイトリール(bait casting reel) |
| 両軸受けリールのこと。比較的重たいルアーを投げる時に使う。ベイトキャスティングリールを略した呼び名。 |
| ベイトロッド(bait casting rod) |
| ベイトキャスティングリールを装着するためのロッドのこと。ベイトキャスティングロッドを略した呼び名。 |
| ベイトフィッシュ(bait fish) |
| バスが普段食べている小魚のこと。魚以外にザリガニやエビといったエサをなるものすべてを指す場合もある。 |
| ベイマウス(bay mouth) |
| ワンド(入り江)の入り口部分のこと。 |
| ベイル(veil) |
スピニングリールのスプールの外周にあるラインローラーにラインを導く金属製のアームのこと。ベイルアーム(veil arm)ともいう。 |
| ベイルアーム(veil arm) |
| ベイル(veil)の項参照。 |
| ペギング(pegging) |
| シンカーが移動しないように爪楊枝のような棒をシンカーの穴にねじ込んでウエイトを固定すること。ペグ止めともいう。 |
| ペグ止め |
| シンカーが移動しないように爪楊枝のような棒をシンカーの穴にねじ込んでウエイトを固定すること。ペギング(pegging)ともいう。 |
| ベジテーション(vegetation) |
| 水の中や岸に生える植物の総称。 |
| ベタ凪(なぎ) |
| 無風で鏡のような水面の状態。英語ではデッドカーム(dead calm)という。 |
| へドン(Heddon) |
| 1894年、友人を待っている時に暇だったので落ちていた木片をナイフで削って湖に放り込むと、そこにブラックバスが食いついてきた・・・そんな体験からルアーメーカーを立ち上げたのがジェームス・ヘドン(James Heddon)です。ヘドンの歴史はアメリカのバスルアーの歴史そのものでもあります。クレイジークローラー、トーピードゥ、ザラスプーク等々、ヘドンが世に送り出したルアーは未だに世界の多くのバサーに愛され続け、また釣れ続けています。現在は、プラドコ社の参加でプラドコの一ブランドとしてルアーを作り続けています。 |
| ヘビーカバー(heavy cover) |
| 密集したカバー(障害物)がある場所。 |
| ヘビーキャロライナリグ(heavy carolina rig) |
| サウスキャロライナリグのシンカーを重くしたリグのこと。サウスキャロライナリグの項参照。 |
| ヘビーダウンショットリグ(heavy down shot rig) |
| 重いウエイトを装着したダウンショットリグのこと。 |
| ヘビキャロ |
| ヘビーキャロライナリグの短縮名称。ヘビーキャロライナリグの項参照。 |
| ヘビダン |
| ヘビーダウンショットリグ(heavy down shot rig)の略称。ヘビーダウンショットリグの項参照。 |
| 偏光グラス |
水面の乱反射を防ぎ、水の中が良く見えるメガネのこと。魚を確認するだけでなく水中の様子が確認できるバス釣りの必需品。 |
| ペンシルベイト(pencil bait) |
トップウォータープラグの一種で、水面を左右に首を振りながら進む棒状のルアーのこと。 |
| ベンド(bend) |
| 「曲がった」という意味で、ダム湖や川などのカーブした部分のこと。 |
| ポークラインド(pork rind) |
ブタの皮と脂身の部分でできているソフトベイトの一種。単品で使うのではなく、ラバージグと組み合わせて使う。 |
| ポーズ(pause) |
| 動いているルアーを止めること。その状態のこと。 |
| ボイル(boil) |
| 肉食魚が小魚を水面に追い上げて捕食している状態。お湯が沸騰しているように泡がたつような状態になるためボイル(=沸騰)という。 |
| ポイント(point) |
| (1)よく釣れる場所のこと。 (2)岬のこと。 |
| ボウズ |
| 魚が一匹も釣れないこと。オデコともいう。一匹も釣れないことをデコるという。 |
| 防水透湿素材 |
| レインウエアに使われる素材で大きな水滴は通さないが水蒸気のような小さい水の粒子は通す生地のこと。釣り用のレインウエアなどに使われる。雨粒は中に侵入させないが発汗した汗は外に放出するので蒸れない。ゴアテックス、エントラント、ドライテックなどが有名。 |
| 膨張色 |
| 水の中で大きく見える色のこと。白、黄色、ピンクなどが膨張色の代表である。 |
| ホグ系(hog worm) |
ブラッシュホグに代表される特殊な形のワームの総称。クリーチャー系ともいう。 |
| ポケット(pocket) |
| ウィードなどがびっしり生えた場所でぽっかり空いた空間のこと。 |
| ポットベリー(pot belly) |
| 直訳すると「ポットのようなおなか」で、おなかの大きいランカーサイズのバスをいう。 |
| ポッパー(popper) |
トップウォータープラグの一種で、へこんだ口で水を受け、水しぶきを上げたり、ポップ音でバスを誘うルアー。 |
| ボディーウォーター(body water) |
| 本流筋のこと。メインレイク(main lake)ともいう。 |
| ボトム(bottom) |
| 湖や川の底のこと。 |
| ボトムバンピング(bottom bumping) |
| ボトムを叩くようにピョンピョン跳ね上げながらラバージグやテキサスリグを引いてくること。 |
| ボトムマテリアル(bottom material) |
| 湖や川の底質のこと。 |
| ボロン(boron) |
| ボロンという金属の繊維を素材の一部に使ったロッドのこと。反発力や強度が高いが重いというデメリットもある。 |
| ポンドテスト(pound test) |
| IGFA(国際ゲームフィッシング協会)が定めたラインの強度規格。ポンド(lbs、LBS)という単位で表記される。例えば、10ポンドラインでは10ポンド(1ポンドは453.592グラム)の負荷をかけると必ず切れる強度でなければならない。日本ではラインは太さ(号という単位)で表記されるが、欧米では強度で表記される。 |
| ポンピング(pumping) |
| 大きな魚がかかった時に、ロッドを胸元に引きつけて魚を寄せてはロッドを倒しながらラインを巻き取ることを繰り返して魚を寄せること。 |
| ポンプリトリーブ(pump retrieve) |
| ロングビルミノーのリトリーブテクニックでロッドを顔に引き寄せるように、或いは横方向にゆっくり移動させ、ルアーを一定の層を引いては止めるテクニック。特に早春のバスに効くとされるテクニック。1989年3月にラリー・ニクソン(Larry Nixon)が琵琶湖で披露して日本のバサーに衝撃を与えたのは有名。 |
| マーカーブイ(marker buoy) |
ウィードのエッジやハンプのトップなどポイントと思われる場所に目印と投入するブイのこと。 |
| マイグレーション(migration) |
| バスが回遊すること。 |
| マス針リグ |
| 環付きマス針と極小のスプリットショット、小さなソフトベイトを使ったリグ。超タフコンディションの時の切り札として80年代に流行った。 |
| マズメ時 |
| 日の出や日の入り前後の薄暗い状態のこと。一般的に魚の活性が高い時間帯と言われる。ローライト(low light)も同義語。 |
| マッチ・ザ・ベイト(match the bait) |
| ルアーを魚が捕食しているベイトのカラー、サイズに合わせて釣りをすること。 |
| マッディーウォーター(muddy water) |
| 泥の粒子で茶色く濁った水のこと。 |
| マテリアル(material) |
| 材質のこと。ロッドの材質、ルアーの材質、湖や川の底質など材質全般に使われる。 |
| 満月 |
| 月は太陽の光を反射して光っているように見えるが、太陽の位置関係により月の満ち欠けがある。太陽の反射を前面に受け、真ん丸な状態を満月という。満月は月の引力、太陽の遠心力が強め合う位置関係にあるため潮回りは大潮になる。 |
| マンメイドストラクチャー(man made structure) |
| 人工の構造物のこと。桟橋、橋脚、ドックなどをさす。 |
| ミオ筋 |
| ドック(漁港)から船がでるために深く掘られた通り道のこと。 |
| 三日月湖(みかずきこ) |
| 蛇行していた川がとり残されてできた河跡湖のこと。 |
| 水通し |
| 水が良く通ること。「ここは水通しが良い場所だ」など |
| ミスバイト(miss bite) |
| 魚がルアーにアタックしたが食い損ねること。 |
| ミッドストローリング(mid-strolling) |
| ジグヘッドを中層でシェイクしながら一定層を引いてくるテクニックのこと。略してミドストともいう。 |
| ミッドスポーン(mid-spawn) |
| バスが産卵している最中の時期のこと。オスのバスがネストを作り、メスバスを呼び込んで産卵し、オスが卵を守っている期間のことを指す。 |
| ミッドレンジ(mid range) |
| ミドルレンジの項参照。 |
| 密放流(みつほうりゅう) |
| 外来魚を誰にも知られずに違う水域に放流すること。ゲリラ放流ともいう。 |
| ミドスト |
| ミッドストローリングの略称。ミッドストローリングの項参照。 |
| ミドルレンジ(middle range) |
| 湖の深くもなく浅くもない中間的な深さの部分のこと。ミドル(middle)は「中間」、レンジ(range)は水深の幅のこと。ミッドレンジ(mid range)ともいう。 |
| ミノー(minnow) |
| (1)小魚のこと (2)細長い小魚のような形をしたルアーのこと。  |
| ミノープラグ(minnow plug) |
| 細長い小魚のような形をしたルアーのこと。 |
| 虫パターン |
| バスが水面に落ちる虫に反応する時に水面に浮く虫に似せたルアーでバスを釣る方法のこと。 |
| 無段階変速 |
| エレクトリックモータのスピード調整には5段変速と無段変速の2種類が存在する。5段変速は5段階の電気抵抗を切り替えることによりスピードを変え、無段階変速は5段階のスピードに応じて電気の量を調節することによりスピードを変える。5段階変速は常に最大電流が流れているために無段階変速よりもバッテリーの消耗は激しい。無段階変速はバッテリーの消耗は少ないが、電気回路が複雑で故障が多い、価格が高いというデメリットがある。 |
| メインレイク(main lake) |
| 本流筋のこと。ボディーウォーター(body water)ともいう。 |
| メソッド(method) |
| 釣法のこと。 |
| メタルジグ(metal jig) |
上下にシャクってキラキラとフラッシングする動きで誘う金属製のルアーのこと。ジギングスプーン(jigging spoon)ともいう。 |
| メタルバイブレーション(metal vibration) |
バイブレーションプラグの中でも金属製のものをさす。 |
| モーニングバイト(morning bite) |
| 朝マズメはバスの活性が高いが、この朝マズメのチャンスにルアーをキャストして得るバイトのこと。 |
| モモる |
| バックラッシュすること。 |
| 矢板 |
岸の泥や土が崩れないように、岸沿いに一列に立てた板の壁こと。 |
| やり取り |
| 魚とのファイトのこと。かかった魚をあしらうこと。 |
| 遊漁料 |
| 遊漁者(釣り人)が漁業権者に対して払う費用のこと。入漁料ともいう。 |
| 夕マズメ |
| 日の入り前後の薄暗い状態のこと。一般的に魚の活性が高い時間帯と言われる。 |
| ユニノット(uni-knot) |
| ラインの結び方の一種。 |
| 溶岩帯 |
ショアやボトムが溶岩で構成される場所のこと。 |
| ヨリモドシ |
糸撚れ(いとよれ)やエサの回転を防ぐ金属製のパーツのこと。サルカンとも言う。 |
| ラージマウスバス(large mouth bass) |
サンフィッシュ科の北米原産の魚。日本ではブラックバスと呼ばれる。アメリカではゲームフィッシュとして最もポピュラーな魚である。日本へは1925年、実業家の赤星鉄馬氏の尽力により芦ノ湖に移植された。その後、国内において研究のための移植、自然繁殖、他の淡水魚に混入しての移植、釣り人の移植などにより全国的に分布している。 |
| ライズ(rise) |
| マス類が水生昆虫が水面で羽化する時や、水面に落ちた昆虫を捕食すること。 |
| ライトキャロ(light carolina rig) |
| サウスキャロライナリグで軽いオモリを使ったもの。 |
| ライトリグ(light rig) |
| 細いライン、軽いシンカーを使ったソフトベイトのリグ(仕掛け)のこと。 |
| ライブウェル(live well) |
バスフィッシングトーナメントで釣ったバスをウエイインするために生かしておくためにボートに設置するいけすのこと。 |
| ライン |
| (1)釣り糸のこと。 (2)線のこと。ルアーを通す経路をさす。 |
| ラインスラック(line slack) |
| 糸がたるんでいる状態のこと。糸フケともいう。 |
| ラインローラー(line roller) |
スピニングリールでベイルとローターの間についている溝がついた金属パーツのこと。 |
| ラインキャパシティー(line capacity) |
| リールのスプールにラインを巻く適正の量、目安の量のこと。リールにとってラインの強度(または太さ)により糸巻量は変わってくる。糸巻量を無視してラインを少なく巻くとキャストの飛距離が伸びなかったり、巻きすぎたりするとラインがからんだりといった不具合がおこる。ラインキャパシティー(line capacity)ともいう。 |
| ラインスラック(line slack) |
| ラインが弛(たる)んでいること。 |
| ラインブレイク(line break) |
| ラインが切れること。 |
| ラウンドヘッド(round head) |
ジグヘッドの形状の一種でヘッドが丸い形をしたもの。 |
| ラバージグ(rubber jig) |
鉛のヘッドにゴム製のラバースカート(rubber skirt)がついているルアー。 |
| ラバースカート(rubber skirt) |
ラバージグやスピナーベイトについているゴム製のスカートのこと。 |
| ラパラ(RAPALA) |
| 1905年、フィンランドに生まれたラウリ・ラパラ(Lauri Rapala)は貧しい漁師であった。ラウリはコルクに銀紙を巻いたルアーを作ったが、これが驚くべき釣果をもたらし、彼のルアーは口コミで噂になった。第二次世界大戦での食糧難と相まって彼のルアーの驚くべき釣果が噂を呼び、注文が殺到。ルアーメーカーとして生きていくこととなった。その後、バルサ素材のミノーを中心に、ミノーと言えばラパラとして今日に至っている。 |
| ラフウォーター(rough water) |
| 湖が荒れている状態のこと。 |
| ラメ |
| ワームの中に入っているキラキラ光る金属箔のこと。フレーク(flake)、グリッター(glitter)ともいう。 |
| ランカー(lunker) |
| 大物の魚。 |
| ランカーバス(lunker bass) |
| 大物のバスのこと。 |
| ランガン(run & gun) |
| ルアーをキャストしては移動を繰り返すこと。一か所でじっくり攻めるのとは対照的なやり方で、次から次へと釣れそうな場所を移動する釣り方。 |
| ランディング(landing) |
| 針にかかった魚を取り込むこと。引き上げること。 |
| ランディングネット(landing net) |
かかった魚を取り込むための網のこと。 |
| リーズ(reeds) |
| 葦(アシ)やガマなど岸に生えている水生植物のこと。一方、キンギョ藻、フサモ、エビモなど水中に沈んでいる藻をウィード(weed)、ヒシモやハスなど水面に葉を出す水草をリリーパッド(lily pad)という。 |
| リーチ(leech) |
ソフトベイトの一種でテールが幅広いストレートワームのこと。リーチは本来、環形動物のヒルのこと。ロボワームのリーチなどが有名。 |
| リーリング(reeling) |
| リールを巻いてルアーを泳がせること。リトリーブともいう。 |
| リール(reel) |
| ラインを巻き取るための道具。スピニングリールやベイトキャスティングリールなどがある。 |
| リールフット(reel foot) |
リールをロッドにセットするための台座の部分。 |
| リグ(rig) |
| (1)仕掛けのこと。仕掛けとはロッドから先のライン、シンカー、スイベル、フックの構造のことである。 (2)船の装備のこと。エンジン、魚探、エレキ、ライブウェルを装備した船をフルリグ(full rig)という。 |
| リザード(lizard) |
ソフトルアーの一種で、いもりの形をしたもの。アメリカではスポーニングの時期によく効くルアーだと言われている。イモリがバスの卵を狙うため、リザードを卵を狙いにきたイモリと勘違いし、威嚇でバイトするためである。 |
| リザーバー(reservoir) |
貯水池やダム湖など人工的に作られた湖沼のこと。バス釣りでは普通、山間の谷間に作られたダム湖のことを指す場合が多い。 |
| リップラップ(rip rap) |
人工的に作られた石積みの護岸のこと。 |
| リトリーブ(ritreave) |
| リールを巻いてルアーを泳がせること。リーリングともいう。 |
| リフト&フォール(lift & fall) |
| 沈んだルアーを持ち上げて落とすルアーの動かし方のこと。縦方向の動きに反応が良い場合に使うルアーの動かし方。 |
| リミット(limit) |
| バスフィッシングのトーナメントで魚を持ち込める数の上限値のこと。 |
| リミットメイク(limit make) |
| リミットが揃うこと。 |
| 良型(りょうがた) |
| 魚の大きさのことを型(かた)という。大きな魚のことを良型(りょうがた)という。 |
| リリーパッド(lily pad) |
ヒシモやハスなど水面に葉を出す水草のこと。一方、葦(アシ)やガマなど岸に生えている水生植物をリーズ(reeds)、キンギョ藻、エビモ、フサモなと水中に生える藻をウィード(weed)という。 |
| レイダウン(laydown) |
岸に生えていた木が水の中に倒れこんだ場所のこと。 |
| レインウエア(rain wear) |
雨の中で釣りをするための防水服のこと。 |
| レギュラーテーパー(regular taper) |
| テーパー(taper)とは先に向かって細くなる度合いのことで、レギュラーテーパーはスローテーパーとファーストテーパーの中間的な先細り度合いである。ロッドのアクション(曲がり具合)も中間的なものとなる。 |
| レベルワインダー(level wind) |
ベイトリールでラインをスプールの水平方向に均等に巻き取るための部品。ハンドルを回すとレベルワインダーが左右に移動しラインを均等にスプールに導く。 |
| レンジ(range) |
| 範囲、距離、幅を意味するが、バス釣りではある特定の水深の幅のことを言う。シャロー・レンジ、ディープ・レンジなど。 |
| ローター(rotor) |
スプールの周りを回転する部品。ベイルアームと一体となっており、ベイルアームを回転させラインをスプールに巻きつける役割をしている。 |
| ローテーション(rotation) |
| ルアーを次から次へと変えること。ルアー・ローテーションとも言う。 |
| ローライト(low light) |
| 日の出や日の入り前後の薄暗い状態のこと。一般的に魚の活性が高い時間帯と言われる。マズメ時も同義語。 |
| ローリング(rolling) |
| クランクベイトやミノーを正面から見た時にボディーを左右に倒すように傾く動きのこと。ウィグリング(wiggling)ともいう。 |
| ロッド(rod) |
| 釣り竿のこと。 |
| ロッドティップ(rod tip) |
| ロッドの先端部分のこと。単にティップとも言う。 |
| ロングビルミノー(long bill minnow) |
リップの長いミノーのこと。 |
| ワーム(worm) |
| やわらかい樹脂でできたミミズのような形のルアー。ソフトベイトとも言う。 |
| ワームオイル(worm oil) |
| ワームに匂いをつけたり、柔らかくしたりするためのオイルのこと。 |
| ワームキーパー(worm keeper) |
ワームがずれないようにフックに施された突起やパーツのこと。 |
| ワームプルーフ(worm proof) |
| ワームに溶けないこと。ワームは素材によってはタックルボックス(特に塩化ビニール製のプラスチック)を溶かしてしまものがある。ワームに溶けない性能をワームプルーフという。 |
| Yガード(Y guard) |
Y字(或いはV字)の形をした根掛かり防止のフックガードのこと。 |
| ワイヤーガード(wire guard) |
針金製の根掛かり防止のフックガードのこと。 |
| ワイヤーベイト(wire bait) |
| スピナーベイトの別名。スピナーベイトの意味はスピナーベイトの項参照。 |
| ワカサギ |
キュウリウオ科の淡水魚。ワカサギの生息している湖ではバスのベイトフィッシュとなっている。 |
| ワッキー(wacky) |
| ワームの中央にフックを刺すスタイル、フックの刺し方のこと。ワッキー(wachy)とは英語で「風変わりな」という意味で、普通、ワームの先端からフックを通すが、変則的な刺し方なのでこの名前がついた。ワッキーリグやワッキースタイルも同義語。 |
| ワッキースタイル(wacky style) |
| ワームの中央にフックを刺すスタイル、フックの刺し方のこと。ワッキー(wachy)とは英語で「風変わりな」という意味で、普通、ワームの先端からフックを通すが、変則的な刺し方なのでこの名前がついた。ワッキーリグも同義語。 |
| ワッキーリグ(wacky rig) |
| ワームの中央にフックを刺すリグのこと。ワッキー(wachy)とは英語で「風変わりな」という意味で、普通、ワームの先端からフックを通すが、変則的な刺し方なのでこの名前がついた。ワッキースタイルも同義語。 |
| ワンキャスト・ワンフィッシュ(one cast one fish) |
| ルアーをキャストすれば魚が釣れる状況。入れ食いともいう。 |
| ワンド |
入り江。コーヴ(cove)。湖岸線が凹状に奥まった地形。水が動かず水温が暖まりやすいので春の絶好のポイントになる。逆に夏は水が悪くなりバスが集まらない。 |
| ワンピースロッド(one piece rod) |
| トップガイドからバットの部分までブランクに継ぎ目のないロッドのこと。グリップが脱着できるものも、ブランクに継ぎ目がなければワンピースロッドである。 |