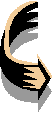|
塾日記 11月1日〜15日 11月1日 10月から社会を中3に加えた(基本英数国の3日)。日本史のできない事。 縄文時代から平成までの時代区分を言える子は実に少ない。 戦後史に関しては皆無。昨日今日の日本の出来事に関しても危うすぎる。 日ごろから新聞、ニュースを見るようにと言ってはいるし、できるだけ今の状況を折に触れ話してはいるが、ダメだ。 人間衣食住が確保できていれば、関心は自分の周囲に終始する。人間は本質的に楽を好むからだ。何かに不足を感じている時に関心は外に向かう。 彼らは今衣食住は足り、さらに一人遊びの道具は充実している。 であれば周囲へ関心は向かわない。自分の手の届く範囲で1日は過ぎていく。 よく言われるように、熱湯の中へカエルを入れればすぐに外へ飛び出すが、水の中に入れそれを少しずつ温めていけば、熱湯の中でカエルは死んでいく。気付けないのだ。 彼らにも優れた点はある。もちろんだ。 しかし今がまずい状態であることは、たとえその状況を作ったのがそれを注意するこちらにあるとしても、言わねばならない。その責任がこちらにあることを認めながらだ。 11月3日 そろそろ低めの子に関しては、推薦を考えなくてはならない。 ここからの伸びが期待できなければ、推薦で決めなくてはならないのだ。 ここで期末を一気に上げる。できるだけ上げる。それで内申をワンランク上げる。 担任に他の生徒よりも早めに推薦についての相談を持ちかける。やる気があることを伝えるのだ。でないと推薦は早い者勝ちの所がある。部活での活躍があればいいが、無ければ先生を味方につけるしかない。そしてそれは塾側からは難しい。嫌がる先生もいるからだ。まずは生徒を早めに担任の先生へ動くように仕向けること。 これから期末。 いよいよ本番。 11月6日 11日は成田夢牧場と航空科学博物館に遠足。 小2、2名、小3,3名、小6、1名を連れて行く。 遠足ではいつもと違う子供達の面が見られてうれしい。 いつも静かにしている子が電車の中や通りを歩いていると、中吊りの広告や看板をいちいち批評し始め、だったら国語の読解もそうすればいいんだよと思わず言ったり、 お土産で少しお金が足りない時、援助してやるといつもはえらく馴れ馴れしい子がえらく恐縮して、最後に今日はありがとうございました、と丁寧に御礼を言ってホ〜〜と思ったり、いつもけんかしてる子がおやつの交換をえらく真剣にしていたり、いつもバタバタしてる子がお弁当の時になるときちんと正座していかにも美味しそうに卵焼きをにこにこ頬張っていたり、計算の苦手な子がお土産の計算は速かったりする。顔つきが違うのだ。元々苦手な勉強の面でいつも付き合ってるわけだから、そうでない遊びの面を知らないとそのこの子の全体はわからない。今度はどんな面が見られるか、楽しみ。 11月12日 9人を連れて成田ゆめ牧場と航空科学博物館。全部で90名、バス2台。 3名は初対面だったので、緊張した。事前に電話はしたが、会うのは初めて。楽しい遠足にしなければならない。楽しい思い出を持って帰ってもらわなければならない。 まず3人の話を聞く。うなずく。まずうなずく。コンピュ−タ、ゲーム、野球。タレント、テレビ、だんだんと緊張が解けてくる。次は他の生徒達との関係。うまく溶け込んでくれるか。間に入り互いを紹介。何とかなりそう。 友達作りのうまい子好きな子、また嫌いな子、一人が好きな子もいる。むしろ一人でゆっくりという遠足もあって良い。 リラックスしているかどうかをじっと見る。 とはいっても9人いるとたいへん。小1、小2、小3が中心となると、やはり人の話を聞けない、動作が遅い、じっとしていられない、自分のペースでしか動けない、自分の気分で動いてしまう。 しかし小学生ではしょうがない。だから怪我と他人への迷惑だけを考える。飛び回る子とは一緒に飛び回りゆっくりの子にはゆっくり合わせる。だからたいへんだ。点呼のたびにいなくなる子がいる。走り回る。 飛行機作り、フライト大会。クイズと宝捜し、みんな楽しめたようだった。 帰ってメールで今日の一日を全員に送る。はっきりいって無茶苦茶疲れる。 しかしその疲れが心地よい。 勉強へ弾みをつける。 11月15日。 今月は期末。中3はここで内申が決まる。 しかし殆どが他人事。のんきともいえるが、自分のことと言う意識がない。別にどうでもいい。流れのまま。流されるまま。 とはいえ自分はどうだったか。 確か17歳になるまでは脳天気一筋。何も考えてはいなかった。今の子には社会のこと、世界のこと、環境のこと、地球の未来のことに付いて考えろと言ってしまうのだが、昔は世界も地球も問題なしと思っていたから、何も考えなかった。今は宇宙船地球号の乗員ということで、もっとしっかり考えろとなる。 大人たちが(我々だが)地球を壊しておいて、子供の世代に地球を治せと言っている。 しかも現在環境一つをとってもさまざまに連鎖し、勉強し考えなくてはならないことは山積みで、なかなか子供たちにも手をつけようという気が起きないのだ。 今教科書には必ず環境に関する説明文、論説文がある。最後は必ずこれからは一人一人が自分の生活をしっかりと見つめ、今すぐできるところから始めなくては地球の未来はないと締めくくる。 ソンダヨナ〜〜とみんな言う。 貧乏くじ引いたよな〜〜と言う。 そうだよな。 |