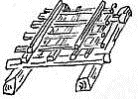 |
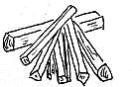 |
| いげた型 | さんかくすい型 |
薪を燃やす事が 苦手な人のために、燃焼について科学的に考えて見ましょう
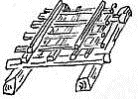 |
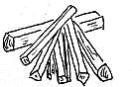 |
| いげた型 | さんかくすい型 |
上の図にあるのは 良く使われる薪の組み方です 物が燃えるということはいったいどんなことでしょう
| 燃焼の3要素 | |||
| 1,可燃性物質 | (燃えるもの) | ||
| 2,酸素 | (O2、酸化性物質など) | ||
| 3,温度 | (点火に必要な熱エネルギー) | ||
まず火をつけるためには燃えやすいものが必要です
| 燃えやすいもの | |
| 1,可燃性物質が燃えやすい性質を持っている 酸化されやすい性質を持つ 可燃性蒸気が発生しやすい |
代表は油脂(ガソリン・灯油)など 野外では使わないようにしましょう (邪道です) |
| 2,酸素が供給されやすい 表面積が大きい(酸素との接触面積大) |
紙、新聞紙など |
| 3,供給される熱エネルギーが大きい 可燃体が燃えるときの発熱量が大きい(その熱でさらに反応が起こる) 熱伝導率が小さい(外部に熱が逃げず、熱がこもる) よく乾燥している(水分があると、蒸発や温度上昇時に熱が奪われる) |
良く乾燥した薪など |
燃やす為には酸素が必要です酸素は空気中から供給します
| 空気の流れを考えて薪を組んでください 火吹き竹やうちわ で強制的に空気を送り込むのも良いかもしれません ただし うちわ などで扇ぐと回りじゅう 灰だらけ になる可能性 大 です (^^♪ 風向きや薪の組み方をうまくやれば 火吹き竹やうちわ は不要です |
| 燃焼の3T | |
| 1,燃焼温度 | (Temperature) |
| 2,滞留時間 | (Time) |
| 3,空気との混合状態 | (Turbulance) |
| 発火点 |
| 継続的に燃焼し始める最低温度 |
| 引火点 |
| 炎が存在した場合に、大気中に置かれた物体に着火する最低温度(結果として燃焼が継続しなくとも良い) |
| 火を大きくする為には小さなのもから少しずつ大きな薪へ燃え移らせなければいけません |
| 火起こしの手順 |
| 新聞紙をやわらかく丸めて置きます (固めると燃えにくい) 着火材 |
| 上に枯葉や小さい枝 などを乗せます(下の新聞が少し見えるように) 着火材 |
| さらに上に 径1Cm程度の薪を数本載せておきます |
| 一番下の新聞紙(着火材)に下から火をつけます (火は下のほうから 上に登る) |
| ここであわててはいけません、じっと炎が上がるのを待ちましょう |
| たきつけの山がしっかりできていると、放っておいても薪に燃え移ります |
| 上の薪が発火点に達するまで 熱と時間が必要です |
| 一番上の小さな薪に火がついたら少しづつ 小さい薪を足していってください |
| 枯れ葉から小枝に、小枝から細い薪に、細い薪から太い薪に、徐々に燃え移らせていきます |
| 薪に燃え移り炎が安定するまで静かに(そっと)薪を足してください |
| 薪の種類 |
| 着火性が良く燃焼速度が速い薪」とは、火が付きやすく燃えるのも早い |
| 燃焼速度が遅く火持ちのいい薪」とは、燃えにくいけど一度火がつくと長時間燃えてる |
| 針葉樹は全般に柔らかくて燃えやすく、広葉樹は全般に硬くて燃えにくい |
| 着火性が良く燃焼速度が速い薪 |
| 檜(ヒノキ)、杉(スギ)、赤松(アカマツ) |
| 燃焼速度が遅く火持ちのいい薪 |
| 楢(ナラ)、椚(クヌギ)、桜(サクラ)、樫(カシ)、欅(ケヤキ)、楠(クスノキ) |