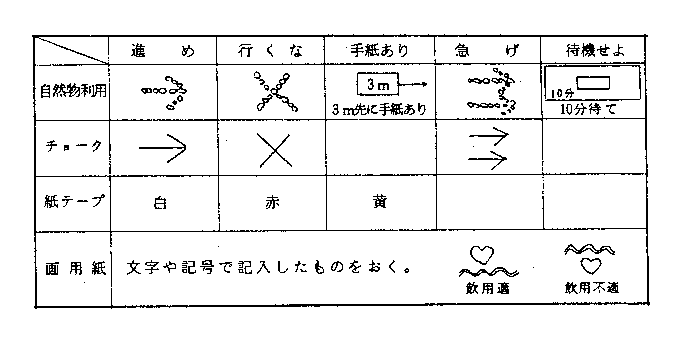
テーマ・・・1.参加者にゲーム感覚で自然に興味を抱かせ、植物の特徴や
働きを通して、自然の大切さを知ってもらう。
2.参加者の協力関係を促し、団体活動を施してみんなで達成する
喜びをお手伝いする。
流 れ・・・1.暗号文を元にハイキング開始
2.コンパスを使い地図と指令書を探す
3.自然観察をしながら植物(くっつき種 オナモミ等)の秘密
を探る
4.おなもみの種を使った、的当てゲーム
5.休憩をかねて、替え歌を作詞
6.かずらを採取、クラフトに使用
まとめ・・・ハイキングのプログラムは、まず自分が楽しむことです.創意
工夫により自分なりに勉強
し、それを人に伝えようとする事から姶まります。それと自然に
感謝する気持ちも忘れないで下さいね。
注意点・・・1.服装をきちんとしておく(長袖、長ズボン、軍手、タオル、
帽子等)
2.無理なプログラムをたてない.(スタッフの人数等考えて)
3.コースの下見を行なっておく.(危険な所を確認しておく)
(自然は変わりやすく、植物の移り変わりもある)
出会い一ふれあい→分かち合い
(l)未知の山野を、あらかじめとり決めておいたサインを目印に(目印は、先
行した指導者がコースを設定し,サインをつけておく)進み、各種の課題や
関所を突破し、終着点まで楽しく安全に導くもので、サインゲーム 関所ゲ
ームなどを併用させたものです。
各グループは全員の協力のもと、注意力、観察力、推理判断を働かせ、チ
ームワークの実際を感覚全体の総合訓練として養い、グループ意識の高揚や
冒険心の満足を充すロマンのある野外ハイキングです。
(2)疲労感を少なく、楽しく安全に、そして自然観察など教室では学べない‘も
のを実地に遊びの中で学ぶことができるものです。
参加者の人数、グループ数、性別、年令、経験、体力等を考慮するととも
に、行動時間、距離に配慮し、課題、槻所の敷や問題を準備します。
あまり長距離であったり、単純な1本道や、車道をなるべく避け、コース
の中に地形的な変化、観察にふさわしいポイントを織り込みます。
距離は4〜8Km程度とし、時間も正味1〜2時間程度にします。特に夏季
は午前中に行動を終るようにしたがよいでしょう。(気象、疲労度安全との
関係)もし、行方不明のグループなどがあった場合、その発見誘導等に時間
を要するので、日没までには十分な時間的余裕を持っておくことは大切です。
ア ハイキングの単調さを補い、疲労度を感じさせないで、安全に日的地に
導くための一方法であるので、目的に応じた内容を組み込むことが必要で
す。
イ 通信文やサインの指示などを組み合せ、生徒が全行程に興味を持つよう
に計画するが、迷い易いポイントには指導者を配置して関所を設け、グル
ープに課題を与えながら人員の把握や時間の調整などを行うようにすると
よいでしょう。
トランシーバー等により、スタート、各ポイントの指導者間に連賂がと
れると効果的で、バイクの通れる道があれはパトロール員により、適宜、
指導、看視を行うこともよいでしょう。
ウ 形式
追跡サインに次のような指示や関所における課頻を加味して、コースに
変化をつけましょう。
◎ 研修的なもの(指導者講習会などの内容を組み込む.救急法、歩行法、
結乗法等)
◎ レクリ的なもの(うた、クイズ、創作おどり等)
◎ 野外ゲーム的なもの(ロープわたり、宝さがし、宇宙遊泳等)
◎ 点検的なもの(服簸、携行品などの確認)
◎ 文化的なもの(スケッチ、作詞、句作、等)
◎ 観察的なもの(動植物観察、川、橋、碑など探せば分かるる固有名詞等)
◎ OL的なもの(シルバーコンパス、地図の使い方、歩測、目測等)
エ サインの例 ・
年令、経験度に応じ難易度に変化を持たせ、色や形も、きまった形はな
いので、とり決めて実施するとよいでし上う。(極度の不安感は抱かせな
い。)
サインの種類としては、
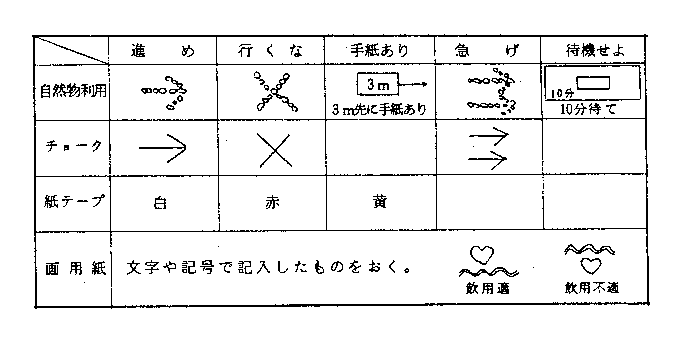
画用紙に必要事項を記入したもの、チョ−ク、石灰、紙テープ、モミガ
ラ、・毛糸、糸、こおい、足跡、地図、シルバーコンパス、自然物(石や技)
などを目的に応じて一種類およびづ複合して使います。
(1)必要時間、距離、交通量、記号、救急、看視、気象、先行者(サイン設置
者)、下見、人員掌握など十分に配慮することが大切です。
(2)グループとグループの間は3〜5分間かくで出発させ、出発待ち組、帰着
組も放置しないで、ミーティングや課題の整理などしながら待機させます。
指導者が本部に一人おれば、全体掌握にも待機者の指導もできるので好都合
です。
(3) サインのつけ方
ァ 1本道では、サインの聞かくは、少し離し、サインのつしいた場所から、
次のサインが見えないように工夫する.曲がった道ではもう少し近くする。
ィ 山野には大小の分岐点があるので、サイン設置者は、慎重に設置し、つ
け残しがないようにします。
分岐点の技道では、そこからサインが見えない位置につけます。心配な
場所には、関所を作り、指導者を配置し、危険防止に努めることが大切で
す。分岐点等における班員の協力の仕方、偵察の要領も教えておくとよい
でしょう。
ゥ サインは大きすぎたり、必要以上に間かくが短かすぎると興味が半減し
注意力が散漫となるので、紙テープなら10〜15Cm位、チョークなら5
Cm位のものを道の上下左右につけ、手紙も手紙をかくす場所のあるほうが
面白いと思われる.上級になるに従いサインは小さく、自然色に近いもの
を使うとよいでしょう。
エ 最後尾の班は、サインを撤去(チョ一クなら消去)しながら進みます.
紙テープの場合、通し番号をつけておき、設置した場所を地図上に記入
しておくと、回収が確認でき、未回収がわかります。
サイン設置者は、確認のため再度最後に回ります.未回収があると、次
の使用団体がサインを混同し、目的地外に進み、思わぬ事故を招くことに
なります。
オ 服装は、なるべく皮ふの露出部分を少なくするため、長そで、長ズボン
手袋、ばうし等を着用し、防虫、切り傷防止に努めさせ、雨具は天気がよ
くても携行するのが野外活動の鉄則です。
携行品は、雨具の他、タオル、必要に応じて水筒などを持たせます。各
グループには、ホイッスル、かい中電灯、腕時計など1個ずつ持たせてお
くと、緊急の時に有効です。
(1)サインにいたずらをしない。設置してあった位置を変えない。
(2)サインの意味を全員が十分理解しておく。
(3)サインは全員協力のもと分担して探し、手紙文はリーダーが大声で全員に
読み聞かせ、その指示を確実に実行する。
(4)サインを見失ったら一つ手前のサインまで引返し、改めて考える。
(5)道幅にあった隊列を組み、むやみに走ったりせず、沈着に行動する.歩行
は急いだり、止まったりすると疲れるので、なるへく一定のスピードを保つ。
また、隊列の前部に足の弱い人を配置する。
(6) 自然を大切にし、傷つけたり、散らしたり、採集したりしない。
(7) 自分の進路が全く分らなくなった時には、なるペく大きな道の上に待機し
救助を待つ.あわてて動き回ったり、分裂したりしない。なるべく見通しの
いい尾根道などが待機場所にはよい。決して谷ぞいに下に降りない。
待機中は、全員で大声を出したり、ホイッスルでSOS(・・・−−−・・・)を
鳴 らしたりして発見を助け、日没後は、かい中電灯などが効果的です。
(8)緊急の場合は、あらかじめ持たせた封筒入りの緊急指令書(迷った時の注
意、処置の仕方について記載したもの)を開封させ、事態に冷静に対処させ
ます。
もどる |