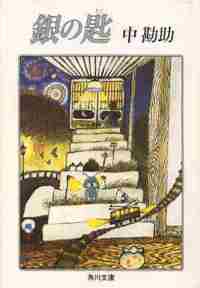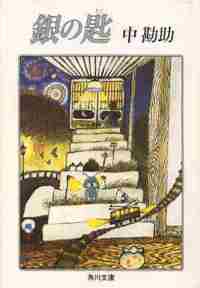
『銀の匙』
(中勘助,角川文庫)
この本は、前編が大正元年、後編は大正四年に書かれた。古い小説です。しかし、そのイメージは永遠に輝いている…。そんなキラキラとした小説です。あるいは、まさに子供の時のくだらない、しかしその時は宝物(ビー玉やおはじきなど)であった。そうしたものをうまくつなぎ合わせたファンタジーです。
銀の匙とは、この小説では、そんなに大きな意味を持ちません。主人公がすでに大人になり、書斎の机の引き出しから、古い銀の匙が出てくる。それは、小さいときに薬を飲むために買った匙である。そして、子供の時の回想へ、時間の張りが逆回転していく…。一つのきっかけとしての銀の匙なのです。
そして、物語が始まる。そこは、主人公が子供の時に見た祭りの光景〜あくまでも子供の視点での回想となっているが。子供の時に見た階段の大きさや祭りの幻想的な雰囲気、思春期の甘い、切ない恋や仲間との遊び、子供だからこそ深刻な悩みや葛藤が、まさに等身大で書かれている。(厳密には大人が読んでも共感できるという視点であるが)
現代では、もうすでに忘れ去られ、語り伝えられている程度の街の風物詩や祭りの雰囲気や遊びも、読み進めて行くほどに、その世界にすっと入り込んでいて、タイムトリップをしてしまいます。
例えば、
やはりこのへんに住んで百姓と商いを半々にしている水飴屋のおやじがあった。彼は天気でさえあれば必ずちゃるめるをふきふき車をひいてくる。あの全てのものの調和をうちこわしてしまうような響きが妙に子供の胸をときめかせて家にいるものは家をとびだし、遊んでいるものは遊びをやめてとんできて、棒ちぎれを刀にさしたやつや、泥だらけの独楽をふところへおしこんだやつが車をとりまいてわいわいと騒ぐ。水飴の他にあてものや駄菓子などをもってくるのでみんなが我れがちに赤や青の紙をめくってあてものをする。
…よかよか飴屋もきた。真鍮の箍をたくさんはめた盥みたいなもののまわりに日の丸や小旗がぐるりとたって、旗竿のさきに鴛鴦の形をした紅白の飴がついている。鯉の滝のぼりの浴衣を着た飴屋の男が、うどどんどん、と太鼓をたたきながら肩と腰とでゆらりと調子をとってくるあとからきたあねさんかぶりをした女がじゃんじゃかじゃんじゃか三味線をひいてくる。
といった調子で、絶妙な文章のひびきや面白い表現が随所に光っています。子供同士の無邪気なやりとりや素朴な音の表現。漢字の使い分けがまた絶妙で、それがまた幻想的な雰囲気を醸し出しています。
子供の時の小説では、「次郎物語」「路傍の石」なんかが代表ですし、宮沢賢治なんかは子供の時の童話なんかを書いています。「風の又三郎」とか「銀河鉄道の夜」とか。しかし、この本のように、本当に純粋に、子供の視点でキラキラとその時を描いたものは、ないと思います。文体も表現も無邪気で細部の描写も全体も損なわずにセンチメンタルに陥らずに輝きを放っています。