清泉女子大学受講生のページへ
日本古典文学演習07受講生のページ
『宇津保物語』の婚姻の成立儀礼
《かうぶり》と《裳着》 平安貴族社会の男子成人式は加冠たる《かうぶり》の儀をもって行われた。といって、髪を、頭の中央から左右に分け、耳の辺りでわがね、中央部を緒で結んで垂れる子供の髪型を解き、一部分を切って大人の髪型、冠をかぶるための髪型に改め、冠をつけ大人の服をつける式である。元服する人、冠をかぶる人をという。冠者に冠をかぶらせる役をのといい、皇子のときは大臣がつとめる。鬟を切り、大人の髪型にする理髪のことはがつとめる。加冠は、を(冠の髻を入れる高くなったところ)に入れ、をさしてとめる。服は別室で大人の服に改める。 昔、藤原の君ときこゆる一世の源氏おはしましけり。童より名高くて、・心・魂・身の、人に勝れ、学問に心いれて、遊びの道〔管絃〕にも入り立ち給へり。・・・・時に、よろずの上達部・皇子たち、婿に取らんと思ほす中に、時の太政大臣のひとり娘に、御かうぶりし給ふ夜、婿どりて、限りなくいたはりて住ませ奉り給ふ。 (「藤原の君」一二一) 『宇津保物語』の二人の主人公の一方である源正頼の場合について、『藤原の君』の巻の冒頭でこう述べられている。 《かうぶり》の儀式があげられる年齢は一定していなかった。おおよそ、天皇にあっにあってはだいたい十一歳から十五歳位まで、皇太子は十一歳から十七歳位までの間におこなわれ、親王もこれに準ずると考えてよい。また、一般の者は五、六歳から二十歳位までの間に行われた。『宇津保物語』でも正頼の場合、十五歳と推定されており、清原俊蔭の場合は本文に明記されているところでは、十二歳であった。またその外孫たる藤原仲忠の場合には、次の文が示すように十六歳であった。 十六といふ年に、かうぶりせさせ給ひて、名をば仲忠といふ。 上達部の御子なれば、やがてかうぶり賜ひて、殿上せさせ・・・。 (「俊蔭」九九) また、三位以上の官人たる上達部の子は成人式後に更に「かうぶり賜ふ」~五位の冠を授けられる~のであり、この叙爵で昇殿が許され「殿上人」となる。 成人式は人類学的にみれば一人前の共同体成員としての資格が賦与される通過儀礼であり、多くの民族では婚姻の能力も、それ故、求婚の機能をもった婚前の性交渉~わが国の<よばひ>~もまた、この儀礼を機に初めて認められたのだ。 では、『源氏物語』の主人公光源氏の《かうぶり》どのようなものであったか?? さき程から言っている、この成人式を機とする性享受を象徴的に示しているのが平安時代の皇男子のもとで行われた《添臥》の風習であろう。《かうぶり》した夜、その皇子に、親王や公卿の娘を添寝させる風習である。その添臥した女子がそのまま皇子の妃妻となることが多かったらしい。また、その多くは年長の少女であった。東宮であれば元服のときに妃がきまる。 光源氏のときはというと、添臥の相手をつとめたのは周知のとおり左大臣の娘の葵の上である。そのまま彼女が光源氏の正妻となったのはいうまでもないことであり、光源氏は左大臣家に婿どりされた。 しかしながら、《宇津保物語》では、このような《添臥》の習俗は明確に記述されていない。 ではあるが、ナンバー3のプリントの上にあるように、正頼が「御かうぶりし夜、婿どりて」と書かれている。したがって、成人式の夜に婿どりが行われたと読み取れるのである。 男子の成人式が《かうぶり》ならば、女子の成人式たるものは《裳着》の儀である。 裳着にはといって、裳を着せる役の人がいて、立派な人に頼む。また、結婚は裳着をすませてのちで、腰結役は婚約者に頼むことも多い。裳というのはひだのついたスカートのうしろだけのようなもので、裳を腰に結ぶには、細い紐が付いていてそれを前にして結ぶのである。裳にはというのが付いていて、はじめはそれで結んだようだが、平安時代になるとそれは装飾になって、うしろにひいた裳の上に引腰が垂れるかっこうになる。 『宇津保物語』では、あて宮の裳着がこのように描かれている。 あて宮は御年十二と申しける二月に、御裳たてまつるほどもなく、大人になりいで給ふ。 『源氏物語』にみられる裳着は・・・ 朱雀院の娘の女三の宮の裳着は盛大であった。腰結役は太政大臣がつとめ、その他、親王八人、左右大臣、上達部、殿上人が残らず参列したという。 父朱雀院の力の入れようが見られるし、作者紫式部の光源氏への降嫁予定の新たなヒロインとしての女三の宮へのクローズアップが、盛大な裳着の式に感じられる程の描かれかたである。 裳着の儀とは、あて宮の「大人になりいで給ふ」という叙述からもうかがえるように、この祝は〔成女式〕に他ならなかった。そしてこれを機に一人前の女として扱われたのであるり、結婚させるべき親の意思表明である。
裳着をすませるといよいよ結婚で、当時、女の結婚適齢期は十四、五歳であった。結婚の相手は近親が多く、それがふつうだった。身分を結婚の第一の条件に考えるから結婚範囲は狭くなり、近親結婚が多くなるのである。
さて、二人の間に契りが成った翌朝、男は女のもとに文を送る。これを後朝の文という。できるだけ早いのが誠意・情熱があるとされた。二人が結ばれれば新婚三日間は、どんなことがあっても男は女のもとに通い、誠意・情熱を示すのだ。例えば、匂の宮は、新婚第三夜、嵐の中を宇治に来た。この三日間は、夜暗いうちに行って、まだ東の空が明るくならないうちに帰ってくるのだが、三日がすむとといって、明るい所での、御披露となる。三日がすむと、男は暗いうちに帰るのではなく、朝までいる。そこで女の親の方から御披露の宴の催しがある。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
源正頼の将来を見込まれた嵯峨院は、正頼にすでに妻があるのを承知の上で、女一の宮のために婿どりされたが、この婿どりの三日目の夜に院はこの婿君と盃を交わされたのである。
三日目の夜、御かはらけ取りて、「ここにかくものするとて、かのおほいまうちぎみ〔太政大臣〕のむすめを忘れず、ひとしく通ひ給はんなん、よかるべき」なんどの給ひて・・・・。
(「藤原の君」一二二)
すなわち嵯峨院は、三日夜の盃事の際に、女一の宮の婿になっても、大い殿の方を忘れず、均しく通ってやるがよかろうと訓戒され、そのお言葉のあと、源正頼に、「御かはらけ腸はる」のであった。
平安時代には、周知のごとく、婿どりの三日目の夜に婚姻が正式に成立し、それを祝い、かつ公表する宴たる「露顕~ところあらはし」が催され、その際に親子の盃が交わされたが、右のように嵯峨院が「御かはらけ取りて」、源正頼に「御かはらけ腸はる」とは、たとえそこに「露顕」の語が用いられておらずとも、この三日夜の儀礼を叙述したものといえる。
かような三日夜の祝宴は、正頼の娘や外孫女一の宮の婿取りの場合にも行われた。正頼一四女のさまこそとの婚姻、長女仁寿殿腹の女一の宮と藤原仲忠との婚姻の場合がしかりである。
八月になりて、大将殿〔源正頼〕の御婿とりのこと近くなりて、仲忠の宰相の中将に女一の宮、源氏の中将〔涼〕にさまこそ君、これは宣旨にて腸ふ。
(「沖つ白波」八七四)
この二組の婚姻は、正頼が婿取りする形式で行われた。さまこその場合は正頼の娘の結婚であるから当然であるが、朱雀帝の皇女の結婚も正頼の婿取りの形式で行われたのは、その皇女が正頼邸に居住していたことによるのであろう。天皇や東宮の妃妻であれ、お産は妃妻の里方で行われており、産後に妃妻が内裏に戻るのは当然であるが、この女一の宮の場合、母たる仁壽殿が内裏に帰った後も正頼の許で育てられていたのである。
こうして正頼は涼と仲忠を「八月十三日に婿取り給ふ」のであるが、三日の夜に意外な展開をみる。すなわち―――――、十五の夜、三日にあたるに、その夜、より大将殿〔正頼〕に「その婿たち率て参れ」とあり、驚き給ひて、宰相中将たち・・・・ひきて参り給ふ。
(「沖つ白波」八七五―六)
この二人の婿取りの三日夜の儀礼を、朱雀帝が自ら催すと申し出されたのである。正頼が「驚き給ふ」のも尤もだが、このことは婚姻の成立にとって三日夜の儀礼がもつ意義の重要性を示唆するものである。
ちなみに、右の二人の婿取りに引きつづいて、正頼は、八月二十八日に他の四人を婿取りしたが、この四組の婚姻の場合には正頼が三日夜の儀礼を主催した。
三日の夜、四ところながら対面し給ひて、御ごとにかづけ物、例おとらず豊かにいきほひたり。
(「沖つ白波」八九八)
舅正頼と婿たちとの「対面」という通常の儀礼が行われ、舅の贈物(「かづけ物」)も人並以上の贅がこされたというのである。総じて、正頼によって婿取られたこれらの婚姻では、婿側からの求婚という過程は経られていないが、三日夜の儀礼のみは当時の婚姻成立の慣習に準拠して行われたのであり、ここでもその儀礼の重要性が示唆されてると言えよう。
源涼・藤原仲忠両名の縁組
藤原仲忠
朱雀帝
女一の宮
源 正頼 長女仁壽
大宮 一四女さまこそ
源 涼
(考察)
以上のように男女の成人式たるものをみてきたが、現代の成人式とは大きく異なることは言うまでもないことではある。ひとことに、《かうぶり》・《裳着》といっても『宇津保物語』・『源氏物語』の両作品に描かれるだけでも様々である。
この時代の成人式とは、最初の方でも述べたとおり婚姻の能力・資格を一人の大人として初めて認められる儀礼なのであり、色恋を自由に楽しむことが出来るようになるのだ。
最後に私たちの発表をまとめると、井川さんの発表の部分で紹介したとおり、『宇津保物語』・『源氏物語』の描かれた時代では未成年者同士の恋愛は現代より厳しく規制されており、また、この発表にあるとおり、現代で言うところの成人式たる元服・裳着は、婚姻と密接に関わっているのである。その婚姻も高橋さんの発表でわかるように、ひとつの儀式として当時は大切に扱われていたのだ。婚姻に関する一連の流れをみていくだけでも、現代の形式化した成人式、軽くなりがちな結婚式の意味など男女関係のみならず今の世に生きる私たちも見習うべき事があるような気がしてならない。
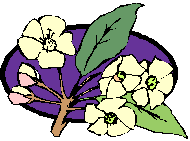 (訳) 99001066 高橋 由佳
(訳) 99001066 高橋 由佳
現在は退位後で気楽な生活ゆえどうであろうと人知れぬ気持ちを持っていた。それに中々聞かして貰えず、軽く取り扱われたのこそ、世に口惜しく妬ましい事はない。よしや、私の思う心の中は届かなくても、簡単に弾ける琴の音さえ聞かして貰えないのは辛い。私にとっては、そなたのこういう態度が辛い」と仰せられるので、内侍督「大変恐れ多い仰せ言を承りまして恐れ入ります。かねての仰せ言を朝夕粗略にはいたしておりませんが、近年は、宮や若君たちの事をいろいろお世話いたしておりまして、時々も参内いたしませんで・・・・。琴は大層お喜び下さる由ございますが・・・・。私も年をとりまして、しっかりとも弾けますまい。どんなものでございましょう。」と申し上げると、朱雀院「大層上手に物を言われる」と、仰せられた後、「〝犬宮に、かように教えました〟と琴を引き寄せて聞かせて下さい。あのほそを秘曲のもの、〝いま三つ、四つは〟と云われたが、それ以外にも決して忘れておられないと、源中納言涼が『七月七日の夜、まだ聞いた事のない曲を弾かれた』と云っていたから、りうかく風の琴の調子のして、七日の夜の事を今宵聞かせて下さい。今夜のような夜がいつ又あろうか。嵯峨院も、年頃聞きたいと思し召していらせられる。残り少ないお年であるのに・・・・。今日はこうして御幸になった事ゆえ、院の方では別になんとも思し召してはいらせられなくとも、そなたが有難いと思う心を述べるには今日こそ絶好の機会である。かねてお聞きになりたく思し召した琴をお聞かせする、今夜のそなたの心がけによって一層ご嘉納あらせられよう。仲忠の将来についても言いたい事がある。いろいろ心配になることもある。今、私が云った事は、そなたも同感であろか。いかが」と仰せられるので、仲忠母「誠にご尤もだと存じます。何とか筋の通るような事を申し上げたいと存じます。実は琴より外のお話かと思っておりました。琴は、数多もございません。りうかく、ほそおだけでございます。それは、仲忠も折々禁中で弾きましたので、お聞き遊ばされたと存じます。」と申し上げた。朱雀院と内侍督の会話を、右大臣兼雅が不安そうに見ている。左大臣正頼の心、今でも普通でないと思うと、仲忠も不安になる。りうかく、ほそおの琴や、又かの冶部卿俊蔭の集の中に、今は紙に書いたのを消してあるが、〝西国に思ひ屈すべし〟と書いてあった。それらを見たいと仰せられる。琴は、非常に立派な高麗の錦の袋に入ってる。とり出して渡すと、何ともいえないよい匂いがするのを奉った。「もう一つある筈」と仰せられたがはっきりしたお返事はしなかった。
内侍督「どうしたらよいかしら」と思案している時、嵯峨院が、傍においでなって、院「仲忠に云っておいた事を聞かれたか。俊蔭が私えお怨んでいる事は、本当に罪に当たる事ではあるが、私も余命いくらもない身ゆえ、許してくれるならば嬉しい」など仰せられる様子が、巧者らしく愛敬がおありになる。内侍督院「恐れ多い事・・・」と申し上げると、院「では、あのりうかく風よりは、なん風、はし風などいう琴が聞きたい。あの琴は、先年、雷鳴壺で、仲忠と涼が弾いて、まだ残りがあると思ったが、空の雲が騒がしく、乱れ来る気はいがすると云って、中途でやめて、残りをその後聞かない。それが是非聞きたい。又はし風もほのかに聞いただけで、本気に弾かれるのを聞いた事がない。もしかしたら、はし風であろうかと当て推量に伝えきくだけである。それを今宵聞かせてくれたならば、生々世々嬉しく思おう。もしこれを聞かせてくれないで、後で人に聞かせるならば、世の中の恨みと思おう。
いまはのみかぎりと思ふすゑの世にもとのうらみをとくともきかなん内侍督の返歌、
「二葉にておもほえぬかなむすび松うちとけてこそ人はひくらめなん風の曲は余り多くは存じませぬ」
と申し上げた。
朱雀院は親しみ易いなつかしい態度で、いろいろの事を筋道立てておっしゃる。嵯峨院は、ご高齢でもあり、畏敬の念のおこるような方で、古の事おっしゃってお断り出来ないような事をおっしゃる。内侍督はどうしたらよかろうかと思案にくれる。昔、故治部卿は、はし風、なん風二面の琴について、世の中で今が一番栄花を極めたと思う時と、見るかげもなく零落した時に弾けおっしゃった。北山の空洞生活の獣の中にいた時、南風を一生懸命に弾いたが、人々に聞きつけられたので中途でやめたのである。今は、仲忠も年齢的にも、功績の上からも早いのに、大将になっている、自分自身も内侍督にして頂いている恩寵などから、昔、俊蔭が云った事から考えると、今日の有様こそ、たとえ、ご退位後とは云え、二方のみかどの行幸があり、式部宮始め多くの栄誉ある宮達がおられ、春宮の上達部も参集されている。后と申す方には嵯峨院の大后がおられ、皇女には左大臣夫人を始め五人もおられる。女御には、式部卿の宮の御女を始め三人もある。只人としては、私共に信望のある太政大臣、上達部は全部で十五人、三位、左右大弁、頭、蔵人、すべて殿上人のある限りは来ておられる。聞いてわかる人もわからない人も、なん風の曲の物の手を弾く事は易い。只、これを弾けば悲しかった昔が思い出されて辛い。
はし風は、七日の夜、棚機に奉るためと、犬宮に教えるために、それもそっとかき鳴らしただけである。たとえみかどの御前であっても、格別愛していらっしゃる女一宮を仲忠の妻とし、犬宮の祖母となり、右大臣兼雅の妻である事を思えば幸福ではあるが、これが、幸せの極致とは思えない。二院の御前でも南風を弾く事はいかがと、思案にくれるのである。
十五夜の月が、明るく照らさぬ所もなく、空は静かに澄み渡って美しい。仲忠の母は、「うまく弾けそうにない・・・・」と何度も何度も嘆声をもらしてはいるが、先ず自分が習い始めに弾いたりうかく風の琴を、秋の調子にして声高く、仁寿殿で弾いた時より勝れて、世に二つとない程に立派に弾いた。この琴の音によって、他のいろいろの楽器、笛の音を引き立て、いろいろの音楽の音を調えた。二院、宮達、その他の方々も、「りうかく風の音を、かすかにきいた事があるが、これ程ではなかった」と驚いておられる。耳に入り心にしみ、興深く、世の中にこれ程勝れた音楽があろうかと思われる程に立派である。次に、ほそお風を曲の調べで一つ弾くと、霰が度々降り出し、雲が急に襲来し、星が騒ぎ、空の気色が怖ろしい様子ではなく、珍しい雲が立ち渡った。廂にいた人々は、狭い程人が入っているので、熱気にあてられていたが、急に涼しくなり、心地も快い、命も延び、世の中のめでたい繁栄を集めて見聞くようである。今度は同じ調べながら、遥かに高く澄み上がる声で、心細く哀れ深く、上は空を響かし、下は地の底を震わすようである。四方の山や林がそれぞれ音を変え、悲しく深刻な事、世の無常が、忽ち胸に迫って、涙が落ちて止める事が出来ない。院を始め、大勢の人々が聞いて涙を落とさない人はいない。
清泉女子大学受講生のページへ
日本古典文学演習07受講生のページ