【紫式部の衣装哲学】 Text By 鳥屋原 華
「梅枝」の巻で作者は光源氏に、「錦、綾なども、なほ古きものこそなつかしくこまやかにはありけり」と言わせています。
光源氏のひとり娘で11才となった明石の姫君が裳着を行うことになり、六城院ではその準備に大騒ぎでした。裳着というのは、初めて裳をつける儀式で、現代の成人式のようなものです。しかも明石の姫君は裳着の後、すぐに東宮妃になって入内することが予定されていました。 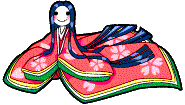
この裳着の支度にと集められた裂地なのに今どきのものはもう一つ気に入らず、光源氏は倉を開けさせ、30年以前に高麗人が献上したものを使うことにしまし
た。その時の源氏の述懐の言葉が冒頭の言葉です。
「古いものが良い」という思想は、文学者に多くみられます。紫式部にも同じように文人風の片意地の気持ちもあったのでしょうが、現実に、紫式部の生きていた時代には、織物の技術が落ちて、かつて遣唐船時代に輸入していたものと品質に差が開きました。
当然ながら衣装の地質に、紫式部の目がまず光っていたことが「梅枝」の巻の記述でわかります。「いいもの好き」というのは紫式部ほどの大作家にとっては当然の傾向に違いありません。
六条院の衣配りの場面で、紫式部は「源氏物語」のヒロインである紫の上の口を通して、卓抜な衣装論を吐かせています。紫の上はたくさんの衣装を前にして、「どれもみな優り劣りのない品ばかりでございます。お召しになる方のお姿やご器量に合わせて差し上げて下さいまし。着たものがその方の人柄に似合わないのはみにくいものでございますもの」と言いました。
その人に似合わないものをプレゼントするという紫の上の考えのどこが卓抜なのだ、当たり前の話ではないかと思う人がいるでしょう。たしかに紫の上のセリフは現代の私達には当たり前のことですが、今から一千年前の日本では、当たり前のことではなく、異端の言葉だったのです。
では、当時はどういう基準で衣装を選んだのかというと、第一に身分でした。二陪織物といって、上文と下文のある豪華な裂地は、帝からゆるされないと着ることができませんでした。二陪織物が着られるのは、後宮でいえば女御以上ではなかったかと思われます。
綾織物でさえも、やはり許されないと着られず、一般には平絹です。身分の低い女房達は晴れの儀式に行く時などは、何とかして華やかに見せようとして平絹に刺繍をしたり、泥で絵を書いたり、たくさん を重ねたりして、苦労するのでした。
また、青と赤は禁色で、女房達も許されないと着ることができませんでした。また、帝は青、太上天皇は赤、皇太子は黄丹が正式の場での袍の色だったので、これらの色も袍 に使うことを遠慮しなければなりませんでした。
つまり、この時代の衣装は、身分によって制約を受けたのです。
次に、季節によって色目にもきまりがありました。年令による制約はないのですが、現代とは全く違う感覚でした。
女房(侍女)や既婚者は緋の袴をはきます。未婚者はこきといって、現代感覚からは緋よりはるかに地味な海老茶の袴をはきます。「源氏物語」の紫の上は北山で祖母のもとにいた時代から光に引き取られ結婚するまではこきを着ていました。光が須磨に流れていくころには緋にかわっていたのでしょう。
弘徽殿女御は悪后などと書かれる時もありますが、個性の強い面白い人物です。彼女は夫の桐壷帝が亡くなっても、尼にもならず、息子が帝位についたのちは、大いに時めいて、光に圧迫しました。彼女くらいのわき役になると、その服装は全く記述されていませんが、簡単に想像できます。緋の袴、禁色の赤をこれみよがしにたっぷり使って何枚も袿を重ね、一番上にはやはり赤を基調にした二陪織物をはおっていたに違いないと思います。
こういった感じで、赤が弘徽殿女御に似合うかどうかは考える必要ないと思いますが、当時の対応の仕方なのです。だから、そういった時代に、「似合うきものを着るべきだ」と言った紫式部はユニークなのです。
では紫式部は、どんな着物を<似合うもの>として「源氏物語」の女性達に着せたのでしょうか。
「白き袷、薄色のなよらかなるを重ねて、はなやかならぬ姿、いとらうたげにあはれなるここちして、そこと取りたててすぐれたることもなけれど、ほそやかにたをたをとして、ものうち言ひたるけはひ、あな心苦しと、ただいとらうたく見ゆ」
白い袷、薄色のなよやかなるを重ねていたのは夕顔の君です。彼女は光の永遠の恋人となった女性で、当時18才でしたが、すでに女の子を持ち、大人の味もありました。性格はおっとりしていて、素直でした。もちろん美人で「顔こそいとよくはべりしか」「かたちなむ、ほのかなれど、いとらうたげにはべる」などと言われています。そういう人柄の女性には、白と薄紫のとり合わせこそ、うってつけと作者は考えたのです。夕顔に着せた衣装を紫式部は「はなやかならぬ姿」と言っていますが、では、華やかな姿とはどういう色使いをいうのかというと、この時代では、赤、黄と赤、赤と青(緑)などが頭に浮かんできます。赤はもちろん最高の色です。黄と赤は玉かずらの君がよく着る配色で、作者は彼女を現代風の華やかな美人という感じで描写しているのです。赤と緑の配色はかさねの色目でいうと松がさねで、この時代に最も流行したものです。この赤と緑も、黄と赤も中国風の色使いであることがわかります。
それに対し、白とうす紫は日本風です。紫でも濃いものは高貴をあらわす色となりますが、薄いものは染めとしてももう一つ値は安く、はかなげな女性の性格にもぴったり合います。さらに自然好きの日本人が、自然の草や花色をうつしたかさね色は、華やかではなく、しっとりした味を期待していると考えるできです。 また、紫式部が喜ぶのは<をりにあひたる>衣装ということです。その場の情趣、人の感情にぴったりの衣装ということです。ある夜、光源氏が恋人の一人、六条御息所のもとに泊まります。その翌朝早く、 から去る光を、侍女の中将が見送りにたちます。昨夜の情事のなごりを心にとどめながら、光が秋草の乱れている庭を歩んでいきます。その目に、お供の中将が紫苑がさねの表着にうすものの裳をすっきりと着ている姿が、まるで秋の精のように新鮮な美しさにうつるのです。従って<をりにあひたる>を、単に、その季節にふさわしい衣装と解釈するなは、少し考えが足りないように思います。
習俗である服装のきまりよりも、その人の人柄に合うきもので、しかも<をりにあった>きものが良いのです。
もう一つ紫式部が要求している条件がきものにあります。それは「蜻蛉」の巻を読むとわかります。
「宇治十帖」の主役である薫が、妻の女二の宮に、「ずいぶん暑い日ですね。薄ものをお召しになったらいかがですか」と声をかけ、「女は変わったものを着るのがその折々につけて風情があるのです」と教えるところがあります。こうしたやりとりを読むと、「源氏物語」が千年も昔に書かれたものとは思えなくなります。
衣装は当時はたしかに貴重なものでした。しかし、それ以上に心あるもの、もの以上のものとして扱っているように思えます。それは互いに想思う男女が閨できものを互いに取り替えて着るということでもうなずけるように思います。光源氏はだからおもうようになびかない空蝉の君の代わりに彼女の小袿を持って帰るし、明石の上と別れて都に帰る時は、着なれて肌の香りのしみたきものを光は女のもとへ残したりしたのです。
さて、こうした素晴らしい意見を衣装についてもっていた紫式部自身は、どのような衣装を着ていたかを知るために、例として、一条天皇と彰子中宮との間に生まれた二の宮敦良親王の五十日の祝いに式部が出席した時の晴れ装束をあげます。唐衣は柳、裳は現代風の摺り模様のあるもの、表着は紅梅、かさねは萌黄です。この時すでに37才ぐらいだったと思われる式部の年令に対し、現代の視点から言えば若づくりといえます。
この日の同輩達の衣装をあげると、小少将は赤の唐衣・地摺りの裳・桜がさねの織りの袿、中務の乳母は桜の唐衣・青の表着・葡萄染めの袿 、小侍従は桜の唐衣・紅梅の匂いのかさね・紅の単、源式部は紅梅がさねに紅梅の綾の表着です。この時点では、紫式部はまだ色ゆるされるというわけではなかったらしいようです。年に似合わない若づくりだと式部は言っていますが、色ゆるされぬ女房が少々目立つには、それも仕方なかったのではないかと思います。
どちらかと言うと陰気なタイプの紫式部が二の宮の五十日の祝いにあった服装をと考え、カラフルな衣装を選んだのです。萌黄のかさねの上に紅梅色の表着を着て、その上に表が白、裏が緑の唐衣を着たのです。しかし、彼女は似合わないとは思いませんでした。現代風の摺り模様の裳をつけたのも彼女の意志だったのでしょう。なぜならば、作家であった紫式部は人にすすめられて、身につける衣装を決めるような自主性のない女性ではなかったからです。
<感想>
自分の着たいきものや好きな色のきものを着ることが出来ないなんて、今の時代では考えられないことなので想像できません。服装というのは、その人の個性を最も表すものだと思うので、身分によって着て良いものを制限してしまうと、個性というものがなくなってしまいます。しかし、こんな制限がありながらも、登場人物を生き生きと、そして個性的に描いている紫式部は、さすがすごい作家だと思いました。また式部自身も、制限を守りながらも、自分の個性を最大限にアピールしているところは、とても素晴らしいことなので、私も見習わなくてはいけないと思いました。
参考文献・近藤富枝『服装から見た源氏物語』文化出版社・1982